【論文】「着物趣味」の成立 [論文・講演アーカイブ]
一般社団法人現代風俗研究会・東京の会の研究誌『現代風俗学研究』15号「趣味の風俗」(2014年3月 ISSN2188-482X)に掲載した論文「『着物趣味』の成立」のカラー画像入り全文。

日常衣料だった「着物」が非日常化し、さらに「趣味化」していく過程を、和装文化の展開を踏まえて、まとめてみた。
欲張った内容なので不十分な点は多々あるが、自分が考える和装文化の衰退と「着物趣味」の成立の流れを、まとめることができたと思っている。
------------------------------------------
「着物趣味」の成立 三橋 順子
【概要】
本来、日本人の日常の衣料であり、洋装化が進んだ戦後においても時と場を限定しながら衣料として機能していた着物(和装)の世界に、2000年頃からひとつの変化が現れる。それは着物の趣味化である。「着物趣味」は戦後の和装世界で形成されたさまざまな規範を超越しながら、ある種のコスチューム・プレイとして新たな展開をみせていく。本稿では、近代における和装文化の流れを踏まえながら、着物趣味の成立過程をたどってみたい。
キーワード 着物 趣味化 コスチューム・プレイ
はじめに
まず「趣味」とは何か、ということを考えておこう。「趣味」を辞書で引くと、「①仕事・職業としてでなく、個人が楽しみとしてしている事柄。②どういうものに美しさやおもしろさを感じるかという、その人の感覚のあり方。好みの傾向」(『大辞泉』)というように、だいたい2つの意味が出てくる。ここで論じる「着物趣味」の「趣味」は①である。さらに、人間だれしもが持っている時間に注目すれば、趣味とは、食事や睡眠などの生活必要時間、仕事や職業、家事などの労働時間以外の自由時間(余暇)に営まれるものと言うことができる。たとえば、私のように、ほぼ毎日、自分と家族のために食事を作っている人は「料理好き」かもしれないが、それは家事労働であって「料理趣味」ではない。料理趣味とは、日頃、家庭で料理をしない人が、休日などの余暇を利用して日常の食べ物とはちょっと違うレベルのものを料理することを言うのだと思う。
次に「着物趣味」の成立の要件を考えてみたい。着物が生活衣料である間は、着物を着ることは日常に必要な営みであって、趣味にはならない。私の明治生まれの祖母は2人とも、生涯、ほとんど和装しかしなかった人で、毎日、着物を着ていたが、それは「趣味」とはまったく遠い。そうした着物が日常衣料だった時代にも、裕福で高価な着物をたくさん誂える人はいたが、それは「着道楽」であって、「着物趣味」とは言わなかった。つまり、着物が趣味化して「着物趣味」が成立する前提、第1の要件として、着物が日常衣料としてのポジションを失うことが必要になる。
最初の辞書的定義のように「趣味」は本来、個人のものだ。しかし、個人が孤立している間は、ほとんど社会性を持たない。「趣味」がある程度の社会性をもつためには、同じ「趣味」をもつ「同好の士」が集まることが必要になる。つまり、「着物趣味」の同好の士が横のつながりをもって集うことが「着物趣味」の成立の第2の要件になると考える。
そして、その仲間たちの間で、「着物趣味とはこういうものだ」という意識、ある種の規範が共有される。その共有された規範が仲間としての意識を強化していく。こうした特有の規範の成立を第3の要件と考えたい。
Ⅰ 日常衣料としての和装の衰退 ―趣味化の前提として―
1 洋装化と和装の衰退
明治の文明開化とともに日本人の洋装化が始まる。西欧近代文化の輸入と模倣に懸命な新政府は鹿鳴館(1883)に象徴される洋風文化を演出するが根付かなかった。洋装化は軍人の軍服、巡査の制服、官公吏の上層部や洋行帰りの学者など、男性のごく一部に止まり、女性の洋装化はほとんど進展しなかった。
大正後期から昭和初期(1920~36)になると、洋服を着たモダンボーイ(モボ)とモダンガール(モガ)が最新の流行ファッションとして注目されるようになる。とりわけ、女性の洋装化の端緒となったモガへの社会的注目度は高かった。しかし、それは都市における尖端文化ではあったが、全国的・全階層的な広がりを持つものではなかった。
一方、この時代は和装にも大きな変化があった。化学染料と力織機の普及により銘仙やお召などの絹織物の大量生産が可能になり、それまで木綿の着物しか着られなかった階層にまで絹織物が普及していく。
昭和初期に大都市に出現するデパートは、絹織物としては安価な銘仙を衣料品売り場の目玉商品に据える。そして、産地と提携した展示会などを開催して積極的に「流行」を演出していった。
主要な産地(伊勢崎、秩父、足利、八王子など)は、デパートが演出する「流行」に応じるために熾烈な競争をしながら、デザインと技術のレベルを高めていった。その結果、アール・ヌーボーやアール・デコなどヨーロッパの新感覚デザインが取り入れられ、「解し織り」(経糸をざっくりと仮織りしてから型染め捺染した上で織機にかけて、仮糸を解しながら、緯糸を入れていく技法)など技術の進歩によって多彩な色柄を細かく織り出すことが可能になった。こうして、従来の着物とは感覚的に大きく異なる、華やかで斬新な色柄の銘仙が大量に市場に供給され、銘仙は都市大衆消費文化を代表する女性衣料としての地位を確立する(三橋2010)。


【写真1】銀座4丁目交差点(昭和7年=1932年)
出典:石川光陽『昭和の東京 ―あのころの街と風俗―』(朝日新聞社 1987年)

【写真1拡大】

【写真1拡大】
写真1は、1932年(昭和7)の銀座4丁目交差点である(石川1987)。男女とも和装・洋装さまざまな服装の人が行き交い、この時代の服飾文化の豊かさを思わせる。右側、仲良く連れ立った2人の女性の1人は、典型的なモガ・ファッションだが、もう1人は大きな麻の葉柄の振袖で、おそらく銘仙と思われる。また左側の袴姿の女子学生の着物は直線を交差させたアール・デコ風の銘仙だと思う。そしてその右の男の子を連れた母親は縞お召、もしくは縞銘仙を着ていると思われる。
この時代における銘仙・お召の流行が見て取れるが、日本近代の服飾史を洋装化の歴史としか見ない従来のファッション史のほとんどは、モガの出現に注目するあまり、この時代が大衆絹織物の普及による女性の和装文化の全盛期であったことを見落としている(註1)。
日中戦争から太平洋戦争の時代(1937~45)になると、軍服や国民服の着用によって男性の洋装化が進行する。また戦時体制への移行にともない繊維・衣服の統制が行われ、「贅沢は敵だ!」のスローガンのもと、女性の和装文化が抑圧されていった。また、戦地に赴く男性に代わる労働力として、「非常時」への対処として、女性の衣服にも活動性が求められ、そうした社会的要請から着物の上に履くズボン型衣料としての「もんぺ」が普及する。そして、戦争末期には、アメリカ軍の空襲によって繊維製品生産と流通機構が破壊されてしまう。
戦後混乱期(1945~51)は、戦災による物資の欠乏に始まり、繊維素材・製品の統制が衣料品の不足に輪をかけた。そうした中、日本を占領した進駐軍がもたらしたアメリカ文化への崇拝、日本の伝統文化否定の風潮が強まり、和装は旧態の象徴になっていく。その結果、戦時中に進行した男性の洋装化に加えて、女性の家庭外での洋装化が大きく進行する。
そして高度経済成長期(1960~75)になると、経済効率を優先した社会システムの画一化が進む。衣服における画一化はすなわち洋装化であり、企業にでも学校でも洋装が一般化・標準化する。同時に、家庭生活の洋風化も進行し、それまでは外では洋装、家では和装が主流だったのが、家庭内においても男女ともに洋装化が進んだ。
こうして、和装は生活衣料としてのポジションを失っていった。その時期は、地域によって差はあるが、東京などの大都市では1960年代後半から70年代前半の時期に押さえることができると思う。
2 女性着物の多層性の崩壊
1960年代後半から70年代前半に起こった注目すべき現象のひとつは、女性着物の多層性の崩壊である。
(表1)着物の階層性

着物を着る場が大きく狭まった結果、礼装・社交着としての着物は残ったものの、街着・家内着・労働着としての着物(お召・銘仙・木綿・麻)は洋装に取って代わられ衰退した。新たに茶道などの「お稽古着」が登場し、色無地や江戸小紋が好んで用いられるようになる。また、本来は家内着だった紬は高級化して社交着化する。階層性の崩壊と同時に、着物の材質も多様性が失われ、木綿・麻・ウールなどは、ごく一部が高級化して残った以外は姿を消し、着物と言えばほとんどが絹という状態になっていく。
3 「着付け教室」の登場と規範化
この時期に起こったもうひとつの注目すべき現象は「着付け教室」の登場である。1964年(昭和39)に「装道礼法きもの学院」が、1967年に「長沼静きもの学院」(当時は「長沼学園きもの着付け教室」)が、そして1969年には「ハクビ京都きもの学院」が創立され、「着付け教室」として全国的に展開していく。現在に続く大手の「着付け教室」が1960年代後半に創立されたことは偶然ではなく、それなりの社会的理由が有ったからだと思われる。
男性の着付けに比べて女性の着付けは帯結びが複雑・多様であるが、それにしても、着物の着付け、帯の結び方は、母や祖母から娘が生活の中で教わり習い覚えるもので、月謝を払って習うようなものではなかった。しかし、戦中・戦後混乱期に着物を思うように着られなかった女性が母親になった時、成長した娘に着物の着付けを伝授できない事態が発生したと思われる。
たとえば、1925年(大正14)生まれの女性は、戦間・戦後混乱期(1941~50)には16~25歳だった。23歳で娘を産めば、1967年には母親42歳、娘19歳である。成人式が間近になった娘に着付けを教えようと思っても、自分の和装経験が乏しく自信がないというようなケースである。祖母がいれば助けてもらえるだろうが、都会で核家族となると、そうもいかない。どこか教えてくれる所はないだろうか?
この時期に「着付け教室」が次々に創立された背景には、そうした戦争による母から娘へという和装文化の継承断絶が生んだ需要があったのではないだろうか。
着物の着付けは、いたって不器用な私の経験からして、単に着るだけなら、3日も習えば、なんとか着られるようになり、後は反復練習である。器用な人なら1日で覚えられるだろう。しかし、それでは月謝を取って教える「着付け教室」の経営は成り立たない。したがって、「着付け教室」では手っ取り早い簡便な着付けを教えず、いろいろと複雑な手順で教える。さらにごく日常的・庶民的な着付け法ではなく、戦前の上流階級の着付け法をベースにして伝授する。その方が付加価値が高いからである。
実際、この時期の著名な着付け指導者には、戦前の上流階級の女性が多かった。1970年にベストセラーになった『冠婚葬祭入門(正)』(カッパ・ホームス)で「着付け」法を広めた塩月弥栄子(1918~)は裏千家14世家元碩叟宗室の娘であり、1973年から「ハクビ総合学院」の学長を務めた酒井美意子(1926~99)は旧加賀藩主で侯爵の前田利為の娘で、旧姫路藩主で伯爵の酒井忠元の妻だった。
こうした戦前の上流階級の女性たちによって、自分で働かなくてよい上流階級の「奥様」「お嬢様」の非活動的な着付けがマニュアル化され、「着付け教室」で教えられ規範化していった。その結果、着物の着方がすっかり様式化し「こう着なければいけない」という形ができ上がる。
本来、生活衣料であった着物には、その状況に応じた着付け方があった。働く時には身体を動かしやすいように楽に緩めに着付けし、たくさん歩く時には裾がさばき易いように合わせを浅めにしてやや裾短かに着付けるなどといった着付けの融通性が失われてしまった。こうして、働けない、身動き不自由な、皺ひとつ許されないきっちりした、着ていて苦しい着物の着付けが成立する。
習わなければ自分で着られない衣服は、もう日常の生活衣料とは言えない。こうした過程をたどって、着物は日常の衣服としての機能を喪失していき、特別な場合、たとえば、お正月、冠婚葬祭(成人式、結婚式、葬儀、法事)などの非日常の衣服となり、あるいは特殊な職業の人(仲居、ホステスなど)の衣服になってしまった。
Ⅱ 「美しい着物世界」の成立
1 高級化と「美しい」の規範化
着物が生活衣料の地位を失い、特別な衣服になったことで、着物の生産・流通業界は、安価な大量生産中心から高価な少量生産へと転換していく。かっての主役だった銘仙やお召はまったく見捨てられ、手作業のため少量生産しかできなかった各地に残る紬が見出され、そのいくつかが付加価値がある織物として高級品化していった。
たとえば、1933年(昭和8)に秩父産の模様銘仙は5円80銭~6円50銭だった。当時の6円は現代の21000~24000円ほどと考えられ、中産階層なら1シーズン1着の購入が可能な値段だった(三橋2010)。ところが、1999年(平成11)に八丈島特産の黄八丈の反物は48万円もした。平均的な収入の人だったらローンでも組まない限り購入は難しい。
こうした着物の高級品化時代に主な情報媒体となったのが婦人画報社(現:ハースト婦人画報社)の『美しいキモノ』(1953年創刊・季刊)に代表される着物雑誌である。この種の着物雑誌の中身は、高価な着物のオン・パレードであり、安価な着物やまして古着などはけっして登場しない。高価な着物を売りたい着物業者と、そうした高価な着物を購入できる富裕な奥様・お嬢様の「美しい」「上品な」着物世界である。私はこれを「美しい着物世界」と呼んでいる。
「美しい着物世界」の特徴は、誌名通り「美しさ」と「着物」とが過度に結合したことである。『美しいキモノ』は、創刊以来毎号、高価な着物を着た女優さんが表紙を飾るのが通例で、中の誌面もほとんどがプロのモデルの着物姿である。その姿はたしかに美しく、なるほど誌名にふさわしい、と思ってしまう。しかし、着姿が美しいのはもともと美しい女優やモデルが着ているからであって、同じ着物を一般の女性が着ても必ずしも美しくなるとは限らない。
着物が日常の衣料であった時代、そんなことは考えるまでもなく誰もが解っていることだった。ところが、着物が非日常の衣服になるにつれて、わざわざ着物を着て特別の装いをするのだから、きっと美しくなるに違いない、というある種の期待が生まれてくる。実際にはそうなる場合もそうならない場合もあるわけだが、着物業界は、そうした期待感を利用して、着物雑誌の誌面を通じて「着物を着ている人は美しい」というイメージを流布し、「着物を着れば美しくなれる」さらに「高価な着物を着ればより美しくなれる」という幻想(錯覚)を喚起し、売り上げの向上につなげるという戦略をとった。
「着物を着ている人は美しい」というイメージは、やがて「着物を着ている人は美しくなければならない」という非現実的な意識に転化していき、必ずしもそうならない女性たちを着物世界から遠ざけることになった。
2 色・柄の衰退
日本の女性の和装文化は、江戸時代には遊廓の高級遊女(花魁)がファッションリーダーであり、明治以降も芸者をはじめとする玄人筋が大きな比重を保っていた。着物が生活衣料としての地位を失っていく時代になっても着物を着続け、着物業界の売り上げのかなりの部分を担ったのは銀座や北新地に代表されるクラブ・ホステスたちだった。にもかかわらず、「美しい着物世界」では、こうした玄人の着物は徹底的に無視・排除される。間違っても「銀座クラブママの着こなしに学ぶ」などという特集は組まれない。
「美しい着物世界」の着物のコンセプトは、あくまでも「上品」である。これを意訳すれば「玄人っぽくない」ということになる。具体的には、色味の弱い色、小さ目の柄、つまり自己主張の弱い「控えめ」が上品とされる。色については、原色や強い色は忌避され、薄い色、さらには無彩色(白・黒・グレーの濃淡、銀)が好まれる、柄は巨大柄・大柄が避けられ、比較的小さめの柄を反復する小紋や、細かな点で小さな意匠を全面に置く江戸小紋、さらには柄が消失した色無地が好まれるようになる。また、日本の伝統的な意匠である縞も、太縞や棒縞のようなシンプルで大胆なものは忌避され、細縞やよろけ縞のような控えめなものが好まれる。太縞や棒縞がもつ粋なイメージが玄人(粋筋)を連想させるためと思われる。
こうした傾向は着物の階層性が崩壊し、「お稽古着」の比重が増した結果、万事派手を嫌い、地味を上品とする茶道の世界の「趣味」が着物全体に影響を及ぼすようになったことが作用していると思われる。その結果、戦前の着物に比べて、現代の着物は、色は淡く、柄は小さく、色柄のバリエーションが少なくなり、創造性が失われ類型的となり、個性的でなく画一化が進んでしまった。服飾デザインという見地からすれば、明らかな退化であるが、商業的にはそうした無個性な無難な着物でないと売れなくなってしまったのである。
3 高級化の帰着と「趣味の着物」
こうした着物の高級化は、着物の世界をますます狭めていった。何10万円という衣料を次々に購入できるような富裕層がそんなに多いはずはない。「和装が好き、着物を着たいけど高くて手が出ない」という階層の方がずっと多かった。それでもバブル経済期(1980年代後半)はまだよかった。驚くほど高い着物が売れた。たとえば、染色家の久保田一竹(1917~2003)の一竹辻が花の訪問着が1200万円とか。しかし、購入された高価な着物が実際に着られたかというと必ずしもそうでもなく、多くは「箪笥の肥やし」と化し、着物世界が再び拡大することにはつながらなかった。そして、バブル崩壊後、着物業界は大量の在庫を抱えたことに加えて、バブル期の「箪笥の肥やし」がリサイクル市場に放出されることで、新規需要の落ち込みに苦しむことになる。
ところで、1980年代には「趣味の着物」を看板にする店が現れる。目の肥えた顧客を相手に、普及品ではなく高級紬や作家物など厳選された商品を扱う店である。しかし、この「趣味」は、「はじめに」で紹介した辞書の②の意味「どういうものに美しさやおもしろさを感じるかという、その人の感覚のあり方。好みの傾向」と解釈すべきだろう。「良いお着物の趣味でいらっしゃいますわね」の「趣味」である。この時点では、「仕事・職業としてでなく、個人が楽しみとしてしている事柄」という①の意味での「着物趣味」はまだ成立していなかった。
4 男性の和装の(ほぼ)絶滅
写真2は、1959(昭和34)正月のある一族(東京在住)の集合写真である(小泉2000)。
.jpg)
【写真2】ある一族のお正月(昭和34年=1959年)
出典:小泉和子『昭和のくらし博物館』(河出書房新社 2000年)
成年女性8人はすべて和装である。これに対して成年男性4人は家長と思われる1人が和装なだけで他の3人は洋装である。また子供たちも女児6人が和装4、洋装2であるのに対し男児2人はいずれも洋装だ。つまり、男性の和装はおじいちゃんだけという状態で、男性の洋装化=和装の衰退が女性のそれよりもかなり早く進行したことがはっきり見てとれる。
お正月ですらこの状態なのだから、平常時において男性が和装する機会はいよいよ乏しくなっていった。歌舞伎役者、茶道家、落語家、棋士など一部の限られた職業の男性の需要に応じた生産は続けられていたが、1970年代後半から80年代になると、男性の着物は高級品を除き店頭から姿を消していく。和装趣味の青年が着物を着たいと思っても、(彼の手が届く範囲では)「どこにも売っていない」状況になり、着付けのマニュアル本からも男性向けの記述はほとんどなくなってしまう(早坂2002)。こうして、1980年代後半から90年代前半には、男性着物はほぼ絶滅状態になり、着物は女性の物という社会認識が定着し、着物世界におけるジェンダー的な乖離は極限に達した。
こうして、着物趣味の成立の第1の要件である日常衣料としての地位の喪失は、少なくとも1980年代末には完全に達成されていた。しかし、まだこの時期には、着物世界の人間関係は、着物を売る着物屋と着物が好きで買う客の商業的関係であり、着物好きの客同士の横のつながりは、ほとんどなかった。第2の要件である着物好き同士の横のつながりができるまでには、もう一段階が必要だった。
Ⅲ 情報革命と着物世界 ―趣味化への胎動―
1 「着ていく場所がない」
着物を着て家を出ると、顔見知りの近所の奥さんに「あら、お着物でお出かけ? 今日は何かありますの?」と興味津々に尋ねられる。多くの着物好きの女性が経験したことだ(男性の場合はさらに不審がられて声も掛けられない)。1990年代になると、日常性を完全に喪失し衣服として特殊化してしまった着物には「着る理由」が必要とされるようになってしまった。「ただ着物を着たい」、「着て出かけたい」ができない状況が生じたのである。
「近所でジロジロ見られるので、着物で出掛けられない」、「変わり者扱いされるので(着物のことは)周囲の人に黙っている」、そんな話を聞いて「なんだ、女装と同じではないか?」と思ったことがある。冗談ではなく、1990年代には、着物のファッション・マイノリティ化はそこまで進行していた(三橋2006)。
実際、堂々と着物を「着られる場所」「着る機会」は少なかった。お正月は年に1度だし、結婚式に呼ばれる機会もそうはない。そうした状況の中で、「鈴乃屋」や「三松」のような大手の着物チェーンが「着物を着る場」としてイベントを企画・開催するようになる。しかし、お商売だから当然なのだが、そうしたイベントは着物展示会と併設されていたり、そうでなくても「お出かけ」の度に着物を作ることを勧められ、結局、多大の出費をすることになる。そうした制約なしに、「気楽に着物を着る場・機会があればいいのに」と、着物好きの多くが思うようになっていた。
2 パソコン通信からインターネットへ
1997年8月、パソコン通信「NIFTY-Serve」の中に「きものフォーラム」が開設される。「NIFTY-Serve」のサービス開始(1987年4月)から10年も後のことだった。そして11月25日には東京赤坂の「全日空ホテル」で「きものフォーラム」の「オフ会」(オフライン・ミーティング)が20名の参加者で開催された(早坂2002)。
これはパソコン通信と趣味の世界の結合としてはかなり遅い。たとえば女装趣味のパソコン通信「EON」(主宰:神名龍子)は1990年に創立され、その活動を通じて1995年頃にはすでに「電脳女装世界」ともいうべき女装仲間の横のつながりが形成されていた。1996年4月に開催された「EON」ボード上に設置された「クラブ・フェイクレディ(CFL)」(主宰:三橋順子)の「オフ会(FL3)」には77名が参加している。そんなものと比較するなと言われるかもしれないが、パソコン通信を通じての仲間の結合という点で、この時期の「着物仲間」は「女装仲間」よりもずっとマイナーな存在だったことがわかる。
1996~97年頃から日本でもようやくインターネットが盛んになると、1997年に秋田県在住の「澤井夫妻」がインターネット上に「きものくらぶ」を開設する。これが日本最初のインターネット着物サイトと思われ、私が最初にアクセスした着物サイトも「きものくらぶ」だった。同年12月には早坂伊織氏が「男のきもの大全」を立ち上げ、これが最初の「男着物」専門サイトになった。
こうして、パソコン通信、次いでインターネットを媒介にして、日本各地に孤立、散在していた「着物好き」が結びつき、仲間化していくことになる。
3 「男着物」の復活と男性主導の「オフ会」
パソコン通信時代から代表的な「着物好き」として活躍する早坂氏の本業が「富士通」のシステムエンジニアだったように、また「きものフォーラム」の中に「男のきもの」会議室が設置されたように、パソコンの普及度、パソコン通信やインターネットへのアクセス率は、その初期においては男性の方が圧倒的に高かった。したがって、インターネットによる仲間化や「オフ会」の開催は男性が先行する。
早坂氏が主催する男着物の「オフ会」である「男のきもの大全会」が開催されたのは1998年10月だった(参加者50名)。1999年12月には、毎週土曜日に着物男性が銀座に集まる「きものde銀座」の第1回が開催される(参加者14名)。この集まりは1999年11月に開催された第2回「男のきもの大全会」から派生したものだった(早坂2002)。
こうした経緯をたどって、1990年代末に、ほぼ絶滅状態だった男着物が復活し仲間同士の横のつながりが形成されていった。1990年代末から2000年代初頭にかけて、着物趣味成立の第2の要件が整ったことになる。
4 「ふだん着きもの」への志向
「インターネットきもの」の初期に多くのアクセスを集めたサイトに「あみさんのきもの」(主宰・鳥羽亜弓)があった。このサイトの特徴は、地方在住の子育て中の主婦が毎日着物を着て生活しているという「特異性」にあった(鳥羽2001)。着物で日常を過ごし、家事を行い、子供を育てるという戦前期の日本の多くの主婦がしていたことが、すっかり特異なことになってしまったのである。
2002年に『天使突抜一丁目―着物と自転車と―』を出版したマリンバ奏者の通崎睦美も、着物で自転車に乗るという「特異性」で注目された(通崎2002)。明治~大正期のハイカラ女学生がごく普通にしていたことなのに。
また、現代風俗研究会の古参会員である磯映美は、「華宵」の名義で、2001年から2003年にかけて、散歩きもの普及員会ニュースレターとして「着物で、ぶらぶら」を刊行した。
こうした「ふだん着着物」、あるいは日常的な「着物暮らし」への志向は、日常性を喪失した和装文化に反発・逆行するものであり、その方向性はその後の「趣味化」の中に受け継がれていくことになる。
Ⅳ アンティーク着物ブームと「着物趣味」の成立
1 女性主導の「オフ会」の盛行
当初、男性主導だった着物「オフ会」も、女性のインターネットアクセス率が上がるにつれて、女性の参加が増加していった。男性主導の「オフ会」には、男性だけで語り合いたいホモ・ソーシャルなタイプと、主催者が「女好き」で積極的に女性の参加を勧誘するタイプとがあった。2000年頃に何度か開催された村上酔魚堂の「オフ会」は後者のタイプだった。
.jpg)
【写真3】「村上酔魚堂・浅草オフ会」(2000年9月)。
ここで後の「うきうききもの」の初期中核メンバーが出会う
そうした場で着物好きの女性たちが知り合い、その横のつながりをベースに、2001年頃から女性主導の「オフ会」が盛んに開催されるようになる。その代表は、東京を中心とした首都圏では「うきうききもの」(主宰:古川阿津子、2001~10)、京都を中心とした関西圏では「夏海の遊び着」(主宰:夏海、2001~ )であり、最盛期には月に数回ペースで「オフ会」を開催した。
-5d3a9.jpg)
【写真4】「うきうききもの」秩父銘仙オフ会(2002年4月)。
中央が主宰の「あつこ女将」
こうした「オフ会」は心置きなく好きな着物を着られる場であり、着物に関する様々な情報や工夫が交換され、またお互いの着こなしが参照され相互に影響を与えあった。そして、「オフ会」の様子がインターネットサイトにレポートされることで、新しい参加者を引きつけていった。2000年代前半は、インターネットと「オフ会」を通じて、女性の着物仲間が横のつながりを形成していった時代だった。
私も参加した「うきうききもの」では、初期のメンバーの間には、既存の着物世界への飽き足らなさ、不満が共通意識としてあった。地味=上品に固定化され、「着付け教室」が作り上げた厳格な着用規範に反発し、「もっとどんどん、自由に、楽しく着物を着たい!」「(ミセスだって)派手な着物を着てもいいじゃない!」という思いである。「美しい着物世界」とまったく異なる着物への志向・嗜好がそこにはあった。
2 アンティーク着物ブーム
女性主導の「オフ会」の盛行とほぼ時を同じくして、アンティーク着物ブームが起こる。その火付け役は「別冊太陽」(平凡社)の「昔きもの」シリーズだった。2000年3月の『昔きものを楽しむ(1)』に始まり、『昔きものを楽しむ(2)』(2000年11月)、『昔きものと遊ぶ』(2001年8月)、『昔きものを買いに行く』(2002年12月)、『昔きものの着こなし』(2003年4月)、『昔きもの 私の着こなし』(2004年5月)とほぼ1年1冊ペースで計6冊が刊行された。
このシリーズ、最初は「骨董を楽しむ」シリーズの1冊として刊行されたように、骨董的な価値のあるアンティーク着物を「収集して楽しむ」というスタンスだった。ところが途中から、アンティーク着物を「着て楽しむ」という方向に変化していった。表紙も最初は着物の意匠だったのが、3冊目の『昔きものと遊ぶ』は着姿になっている。
「別冊太陽」の「昔きもの」シリーズによってアンティーク着物への関心が急速に高まり、骨董屋や骨董市の露店で、古い着物を漁る人々が出現するようになる。とくに現代の着物に比べてデザイン性に富み、派手な色柄の銘仙やお召が注目され、それまで二束三文(500円以下)だった銘仙の古着がたちまち値上がりしていった。
そうして探し出し手に入れた古着を洗い繕って、場合によっては仕立て直す。手間暇を惜しまない。そして、その着物を「オフ会」で仲間たちにお披露目する。すると、「わ~ぁ、すてき、どこで手に入れたの?」「いくらだった?」と仲間から質問が飛ぶ。「○○の露天市でね、500円だったの。けっこう汚れていたから(着られるようにするのが)大変だったけど…」。こう答えるとき、それまでの労苦が報われ、ある種の達成感がある。
探す→洗う・直す→着る→仲間に見せる、このサイクルが毎月のように繰り返される。傍目から見れば、いい大人の女性が古着を漁り集め、着ることに夢中になっているわけで、いったいウチの娘(もしくは妻)は何をしているのだ、と呆れられることになるが、まさにそれが「趣味」なのである。
2002年6月には、アンティーク着物に特化した着物雑誌『Kimono道』(祥伝社、後に『Kimono姫』と改題)が創刊される。そのコンセプトは「アンティーク&チープ」であり、表紙に記されたリードは「キモノのはじめてはアンティークから」だった。
アンティーク着物の場合、値上がりしたと言っても、せいぜい1000円から5000円程度で千の桁で納まり、万の桁になることは少なかった。稀に数万円という高級アンティーク着物もあったが、当時、市販の現代着物の多くは20~50万円の価格帯だったから、それでも10分の1である。30万円の現代着物1枚を買う値段で、露天商から3000円のアンティーク着物が約100枚買える計算になり、すさまじい価格破壊ということになる。
安価なアンティーク着物がブームになったことは、それまで経済的な理由で着物を思うように着られなかった「着物好き」にとっては大きな福音であり、とくに20代、30代の比較的若い人たちが着物世界に参入できるようになった。20世紀後半の50年間一貫して長期低落傾向にあった着物人口は、21世紀に入って一時的にせよ増加に転じたのである。これは「趣味化」というある種の「突然変異」かもしれないが、長い和装の歴史の中で、やはり画期的なことだと思う。
2000年代のアンティーク着物ブームによって、東京白金の「池田」、原宿の「壱の蔵」などのアンティーク着物専門店はおおいに賑わい、コレクターとしても知られた店主の池田重子(1925~)や弓岡勝美の名も高まった。とりわけ池田は、新宿伊勢丹や銀座松屋などで「池田重子コレクション―日本のおしゃれ展―」(1993~2011)を何度も開催し、アンティーク着物の社会的認知を高めた。池田のコレクションとコーディネートは、アンティーク着物ファンの垂涎の的になった。
また、リサイクル着物の「ながもち屋」や「たんす屋」がチェーン展開するのもこの時期である。しかし、アンティーク着物ブームは既存の着物業界にはほとんど影響しなかった。
3 銘仙への注目
アンティーク着物ブームの中で、とりわけ人気度が高かったのが銘仙だった。銘仙とは、先染(糸の段階で染める)、平織(経糸と緯糸の直交組織)の絹織物である。その詳細については別稿に譲るが(三橋2002,2010)、大正~昭和戦前期においては、安い価格と豊富な色柄が、中産階層のお嬢さんの普段着、女中さんの晴れ着、もしくは、女教師の銘仙+女袴(行燈袴)、牛鍋屋の仲居の赤銘仙、カフェの女給の銘仙+白エプロンといったような職業婦人の仕事着として好まれ大流行した。戦後も生産は続いたが、主な着用層だった「お嬢さん」や職業婦人が真っ先に洋装化したこと、粗悪品の流通によりイメージが低下したことで徐々に衰退した。それでも、大柄で色鮮やかな模様銘仙は、自分を「広告塔」にする女性、具体的には「赤線」(黙認買売春地区)の「女給」(実態は娼婦)たちに愛用された。
着尺としての銘仙の生産は、1960年代末までにほぼ途絶え、工場生産品ゆえに伝統工芸・美術品になることもなく、技術もほとんど断絶してしまった。つまり、銘仙はいったん滅んだ織物だった。
ところが、アンティーク着物ブームにより、女性の和装文化の最盛期だった大正・昭和初期の着物文化が再評価された結果、その最盛期を担った銘仙がにわかに注目されるようになる。2002年1月に主要産地だった埼玉県秩父市に初めての銘仙資料館「ちちぶ銘仙館」がオープンし、それを受けて2003年5月に三橋順子が「艶やかなる銘仙」を『Kimono姫』2号に執筆した(三橋2002)。2003年6月には銘仙コレクターの木村理恵と通崎睦美の「銘仙コレクション2人展」が東京中野の「シルクラブ」で開催される。そして2004年12月には秩父市在住の木村理恵のコレクションを紹介した『銘仙―大正・昭和のおしゃれ着―』が「別冊太陽」(平凡社)の1冊として刊行され、銘仙ブームはひとつの頂点を迎える。
その後も銘仙ブームは続き、銘仙をメインにした企画展が各地で立て続けに開催された(註2)。そして、2009年5月には銘仙を主な展示品とする「日本きもの文化美術館」が福島県郡山市にオープンし、2010年4月には同美術館から『ハイカラさんのおしゃれじょうず-銘仙きもの 多彩な世界』が刊行された。
こうした銘仙ブームは、現代の着物にはまったく失われてしまった大胆で前衛的な大柄と、原色を多用し多色を巧みに配した強烈な色彩感覚が作り出す華やかで艶やかなイメージに多くの着物好きが魅せられたからであり、銘仙そのものが現代着物へのアンチテーゼとなっている。銘仙のそうした性格は、2000年代に成立する「着物趣味」の方向性と合致し、それゆえに重要なアイテムとなったのである。
4 「規範」を越えて ―「着物趣味」の成立―
2000年代前半のアンティーク着物ブームの中で成立する「着物趣味」の基本コンセプトは、大正・昭和戦前期の着物文化の再評価とそれへの回帰である。それは、1970年代以降に形成された地味=上品に固定化された「美しい着物世界」や、「着付け教室」が流布する厳格な着用規範への反発と表裏一体だった。それはまた、すっかり特別な場の衣服になってしまった着物から、本来の日常性を取り戻す方向性だった。和装文化の伝統を意識しつつも、戦後の着物世界が作り上げた規範から自由に、好きな着物を着たいように着る、というスタンスだ。
日本の女性着物は、既婚か未婚かの区分が明瞭で、それが身分標識にもなっていたが、アンティーク系の場合、そうした境界も越えてしまう。ミセスであっても、派手な着物、目立つ帯を厭わない。振袖だって着てしまう。白半襟、白足袋という「美しい着物世界」の「常識」に対し、色半襟・刺繍半襟、色足袋・柄足袋が好まれる。着物と帯、そして小物類(半襟、帯揚、帯締、足袋)の色合わせ・柄合わせや帯結びに凝る。髪も、お正月やイベントには、すでに見かけることも稀になった日本髪を結う。
「美しい着物世界」の人に比べて行動性が高いので、着付けも前合わせは浅く、したがって襟のy字は深く半襟をたくさん露出し、襟もかなり抜く。「着付け教室」で「下品なのでやってはいけません」と教えられることばかりである。そして、いつでも(仕事以外)どこにでも着物で出掛ける。休日、近所に買い物に行くのも着物だし、国内旅行はもちろん、海外旅行も着物で行く。履物は、たくさん歩くので、草履より下駄が好まれる。なにより、着物も帯も「値段の高きをもって貴しとせず」で、その人の個性に合ったコーディネートや創意工夫が評価される。
こうした方向性・嗜好は、ほとんどすべて「美しい着物世界」への明確なアンチテーゼである。したがって、当然のことながら、従来の規範を順守する「美しい着物世界」の人たちからの反発も大きかった。ネット上で「ぼろ着て何が楽しいの?」「お女郎さんの集まり」「座敷牢から抜け出してきたみたい」と批判されるのは常のことで、銀座で集まっていた時、見知らぬ中年女性(洋装)にいきなり「ここは銀座なんだから、日本の恥になるようなみっともない着方はしないで!」と面と向かって言われたこともあった。単なる好奇の視線には慣れっこだが、さすがに「日本の恥」とまで言われるとは思っていなかった。
しかし、そこまで強く反発されるということは、従来の着物世界の規範を越えた、新しい、そして特有の方向性が成立したということである。既存の着物世界から批判されたことで逆に「私たちの着物趣味とはこうなんだ、これでいいんだ」という意識が仲間たちの間で共有化されていった。こうして、第3の要件が満たされ2000年代前半に新しい「着物趣味」の世界が成立した。
-9cd66.jpg)
【写真5】アンティーク銘仙のコーディネート。
モデル:(左)小紋、(右)YUKO
2人とも「アラフォー」のミセス(2005年3月)
Ⅳ 新しい着物世界
1 着物趣味イベントの開催
2000年代中頃になると、「着物趣味」の成立を背景に、従来の「オフ会」からさらに発展した着物趣味イベントが開催されるようになる。ここでは東京で開催され、私も参加したことがある代表的な2つの着物趣味イベントを紹介してみたい。
① 「きものde銀座」
「きものde銀座」は毎月1度銀座で開催される「着物好き」の集会イベントで、「男のきもの大全会」の派生イベントとして1999年12月に第1回が開催された。最初は毎週土曜日開催、着物男性だけの集いだったが、2000年2月からは月1回(毎月第2土曜)となり、着物女性も参加するようになった。主催者はなく、当初は「旦那さん」(牧田氏)が事務局を担当していたが、2006年以降は有志の当番制で運営している。着物で集まる人も会員制ではなく、まったくの任意参加である。
15時に銀座4丁目交差点「和光」前で待ち合わせ、「歩行者天国」の中央通りを1丁目方向に歩き「ティファニー」前で集合写真を撮影、その後は自由行動で、なにかイベントがあれば行きたい人はまとまって行く。17時半頃から「土風炉・銀座1丁目店」で懇親会(会費3000円)となり、20時前後にお開き、希望者は二次会へという毎回同じスケジュールで、途中参加・離脱も自由である。
コンセプトは文字通り「銀座で着物を着る」ということだけ。参加者の着物のスタイルもアンティーク系、「ふだん着着物」系から「美しい着物」系まで様々であり、どんな着方であっても批判しないことになっている。
2008年4月8日に第100回を迎え、2013年12月には168回となる。台風でも大雪でも中止せず(連絡方法がないため)、東日本太平洋沖大地震の翌日(2011年3月12日)にも20数名の参加者で開催された。最初期には参加者1名ということもあったが、近年は集合写真を見る限り40~60名くらいだろうか(註3)。
主催者がいない有志持ち回りの運営と、参加も着方も自由度が高い「緩い」形態が「着物趣味」のイベントとして最も長続きしている秘訣だと思う。
-944a6.jpg)
【写真6】第100回「きものde銀座」(2008年4月8日)
.jpg)
【写真7】2009年1月の「きものde銀座」。
日本髪を結い大振袖を着て築地・波除神社に初詣
② 「日本全国きもの日和」
「日本全国きもの日和」は、「きものであそぼう」をスローガンにした着物ファンの手作りイベントで、「玉龍」こと西脇龍二氏を中心とした「実行委員会」が運営している。メンバーの多くは「きものde銀座」で出会っている。11月3日を「きもの日和」として全国各地で着物イベントの開催を呼びかけ、第1回は7都市、第2回は20都市、第4回は25都市で「きもの日和」が開催され、「着物趣味」の地方への波及に大きな役割を果たした(註4)。
メイン会場である「きもの日和TOKYO」は、恵比寿のイベントホール「EBIS303」で2004年から2008年まで5回開催され、入場者は第1回が1500人、第3回(2日開催)は3000人だった。モデルもスタッフもすべて着物仲間で構成する本格的な「きものファッションショー」は観衆の注目の的だった。さらに、着物写真集『Kimono人』(2005、2006、2007の3冊)を自費出版した。
また、中心メンバーは、毎年5月に開催される静岡県下田市「黒船祭」に出張し、「賑わいパレード」に参加し、野外ファッションショーを開催している。
しかし、2007年の第4回から入場者、出店、広告が減少し赤字となり、経済不況(リーマン・ショック)もあって2009年11月に計画された「きもの日和TOKYO」は延期になってしまう。2010年3月に「きもの日和with目黒雅叙園」として開催されたが、2011年4月の開催予定が東日本大震災の影響で中止になった後は復活していない。
-5318c.jpg)
【写真8】「きもの日和TOKYO 2004」の冊子(2004年11月
-c5c3c.jpg)
【写真9】「きもの日和TOKYO」の「きものファッションショー」(2006年11月)
-c92c7.jpg)
【写真10】「下田黒船祭」の野外ファッションショー。
「ペリー・ロード」の橋の上が舞台(2007年5月)
-ddbca.jpg)
【写真11】「下田黒船祭」の賑わいパレード(2008年5月)
日本髪は美容院ではなく自分で結う
2 着物イベントの問題点
着物イベントに参加して、気付いた問題点を整理しておこう。第一はお金の問題である。「きもの日和TOKYO」のように、意欲的に活動を展開した結果、イベントの規模があまりに拡大してしまうと、集客や採算のような「趣味」とは性格が異なる要請が発生してしまう。また必要な経費が大きくなれば、経済・社会情勢の影響を大きく受けるようになる。「趣味」とは本来、浪費だが、あまり補填しなければならない金額が大きくなると、「趣味」の仲間では耐えられなくなる。といって、企業の協賛・支援を受ければ、商業資本の論理が入ってきて、ますます「趣味」の領域から外れてしまうジレンマがある。「趣味」としては拡大路線一筋ではなく適正規模を保つことも必要だと思う。
第2は、着物イベントのジェンダー的な構造問題である。端的に言えば、リーダーシップをとる男性、イベントの「華」としての女性という基本構造がそこにある。たとえば、ファッションショーやパレードで、男性リーダーの指示で若手の女性や美しい女性が目立つ場所に配される傾向は明らかにあった。それもまた社会的要請なのかもしれないが、必ずしもそうでない女性たちからは不満が出ることになる。
第3は、セクシュアリティの問題で、大人の男女が集まり、懇親会などでお酒が入ると、男性による女性へのセクシュアル・ハラスメントが発生する。その場合、運営側の男性のセクハラ認識が甘いと、結局は被害を受けた女性が泣くことになってしまう。
第4は、和装女装趣味の男性の問題で、近年は「女装」を禁止する着物イベントが増加している。和装文化に女形が貢献してきた度合いを考えれば、まったく理不尽と言いたくなる。そして、「女装禁止」の結果、日常的に女性として生活しているMtF(Male to Female)のトランスジェンダーまでが排除されることになってしまう。これは性的マイノリティに対する不当な社会的排除である。
第5は、高齢化の問題で、他の趣味の世界と同様に若い人がなかなか入ってこない。2000年代初頭のアンティークブームを担った30~40歳代は、10年たった現在40~50歳代であり、さらに10年たてば…である。今のままでは先細り傾向は免れないだろう。
これらの問題、とりわけ第2~5の問題は、着物趣味の世界だけの問題ではなく、日本社会が抱える問題の投影である。しかし、比較的柔構造な「趣味」の世界の特性を生かし、しっかりした認識をもって対応すれば、ある程度は改善可能な問題であると思う。
おわりに ―着物趣味の将来―
1 着たい着物がなくなる
現代の「着物趣味」、とりわけアンティーク派にとっての最大の不安は、近い将来、着たい着物がなくなってしまうのではないか、ということである。なんら特徴のない「つまらない」現代着物は巨大なデッドストックがあるのに、着たいと思うようなアンティーク系の着物はどんどん消えていく。和装文化の全盛期(1926~1936)に作られた銘仙・お召は、すでに80年前後が経過し耐用年数が過ぎつつあり、衣類としての寿命が尽きるのはもう遠いことではない。せめて、あと10年もってほしいと思うのだが。
また、現代女性の体格向上により、女性が小柄・低身長だった時代に作られたアンティーク着物を着られる人が減っている。こうした状況で頼りになったのは、2000年代の銘仙ブーム期に足利・伊勢崎などの旧産地で生産された復刻銘仙だった。復刻銘仙は、問屋価格で5~6万円、小売価格では8~10万円になってしまうので、かってのような普及は無理だったが、それでも、私のように身長が高い銘仙好きにはとてもありがたかった。しかし、わずかに残っていた職人さんの高齢化や逝去によって、2010年代初めに生産が途絶えてしまった(註4)。
先染め(糸を染めて柄を織り出す)の織物は技術的に難易度が高く、現状ではいったん絶えた技術の復活は望めそうにない。それが無理なら、せめて「全盛期(昭和戦前期)」のデザインを、後染め(糸を布に織った後で染める)の染物で再現してほしい。幸い現在ではアンティーク着物の色柄をコンピューターに取り込み、補修を加えた後に、インクジェット・プリンターで布地にプリントすることが容易になった。銘仙写しの浴衣や小紋が増えてくれればと思うのだが、現在の着物業界の沈滞した状況では、それも難しそうだ。
2 コスチューム・プレイとして
生産面では大きな不安があるが、着物をファッション・アイテムと考えた場合、その将来に希望はなくもない。
着物が日常の衣服としての機能を失い、着物を着る人がファッション・マイノリティになったことで、社会の服飾規範を超越する、ある種の自由を獲得できた。そもそも着物を着ていることが「変わり者」「外れ者」なのだから、細かな社会規範に縛られることはない。
そう思いきってしまえば、着物は自己主張、自己表現の手段として、そして変身のアイテムとして絶好である。コーディネートに工夫を凝らせば、立派な会社勤めの男性が任侠系の「あぶなそうな兄さん」に、まともな会社のOLさんや良家の奥様が芸者やお女郎上がりの「あやしい姐さん」に変身できる。背景や小道具に気を使えば、あっという間に昭和初期や昭和30年代にタイムワープした写真を撮ることも可能だ(三橋2006)。
-c2fb9.jpg)
【写真12】石仏に祈る村娘(昭和初期風)
モデル:YUKO
撮影:2008年2月、埼玉県秩父市金昌寺

【写真13】「赤線」の女(昭和28年設定)
モデル:YUKO
撮影:20010年10月、東京「鳩の街」旧「赤線」建物(娼館)をバックに
今や着物は、社会的立場を変え、年齢を化けて、時空すら超える力を持つようになった。それを活用しない手はない。21世紀の着物趣味は、こうした「着物で遊ぶ」、コスチューム・プレイとしての方向性をより強めていくことになると思う。
日本人の伝統衣装という路線では、美術工芸品としてはともかく、衣類としての着物はもう生き残れない段階になっている。「着物趣味」の仲間たちが目指してきた創造性のある自己表現のファッション・アイテムという方向こそが、着物という日本人の民族衣装を次の世代に伝える道だと私は思う。
(註1)村上信彦『服装の歴史2(キモノの時代)』(理論社、1974年)だけが、この時代の和装文化の発展に正当な評価を与えている。
(註2)主なものを掲げると、京都古布保存会「京都に残る100枚の銘仙展」(東京世田谷「キャロットタワー」、2005年3月)、須坂クラッシック美術館「大正浪漫のおしゃれ―銘仙着物―」(長野県、2007年8月)、京都府城陽市歴史民俗資料館「銘仙―レトロでモダンでおしゃれな着物―」(京都府、2008年8月)、神戸ファッション美術館「華やぐこころ―大正昭和のおでかけ着物―」(兵庫県、2008年11月)など。
(註3)の公式サイト「着物de銀座」(管理人:京屋悟雀氏)を参照
http://www.kimono-de-ginza.net/sub2.htm
(註4)2013年段階で継続しているものとして「着物日和in信州須坂」「奈良きもの日和」「きもの日和 in TOMO」(広島県福山市鞆の浦)などがある。また「群馬きもの復興委員会」「NPO法人川越きもの散歩」のように、それぞれの地域で積極的な着物普及活動をするグループも増えた。
(註5)京都の着物問屋「きものACT」が現地の職人さんに依頼して生産していた足利銘仙は2010年頃に、NHKの朝の連続ドラマ「カーネーション」(2011年度後期)で話題になった「木島織物」の伊勢崎銘仙は2012年末に生産が止まった。
文献
石川光陽1987『昭和の東京 ―あのころの街と風俗―』(朝日新聞社)
小泉和子2000『昭和のくらし博物館』(河出書房新社)
通崎睦美2002『天使突抜一丁目 ―着物と自転車と―』(淡交社)
鳥羽亜弓2001『浴衣の次に着るきもの(アミサンノキモノ)』(インデックス出版)
日本きもの文化美術館2010『ハイカラさんのおしゃれじょうず -銘仙きもの 多彩な世界-』(日本きもの文化美術館)
早坂伊織2002『男、はじめて和服を着る』(光文社新書)
別冊太陽2000a『昔きものを楽しむ(1)』(平凡社)
別冊太陽2000b『昔きものを楽しむ(2)』(平凡社)
別冊太陽2001『昔きものと遊ぶ』(平凡社)
別冊太陽2002『昔きものを買いに行く』(平凡社)
別冊太陽2003『昔きものの着こなし』(平凡社)
別冊太陽2004a『昔きもの 私の着こなし』(平凡社)
別冊太陽2004b『銘仙 ―大正・昭和のおしゃれ着物―』(平凡社)
村上信彦1974『服装の歴史2(キモノの時代)』(理論社)
三橋順子2002「艶やかなる銘仙」(『KIMONO道』2号、祥伝社。後に『KIMONO姫』2号、2003年、祥伝社、に拡大再掲)
三橋順子2006「着物マイノリティ論」(『Kimono人 2006』きもの日和実行委員会)
三橋順子2010「銘仙とその時代」(『ハイカラさんのおしゃれじょうず -銘仙きもの 多彩な世界-』日本きもの文化美術館)

日常衣料だった「着物」が非日常化し、さらに「趣味化」していく過程を、和装文化の展開を踏まえて、まとめてみた。
欲張った内容なので不十分な点は多々あるが、自分が考える和装文化の衰退と「着物趣味」の成立の流れを、まとめることができたと思っている。
------------------------------------------
「着物趣味」の成立 三橋 順子
【概要】
本来、日本人の日常の衣料であり、洋装化が進んだ戦後においても時と場を限定しながら衣料として機能していた着物(和装)の世界に、2000年頃からひとつの変化が現れる。それは着物の趣味化である。「着物趣味」は戦後の和装世界で形成されたさまざまな規範を超越しながら、ある種のコスチューム・プレイとして新たな展開をみせていく。本稿では、近代における和装文化の流れを踏まえながら、着物趣味の成立過程をたどってみたい。
キーワード 着物 趣味化 コスチューム・プレイ
はじめに
まず「趣味」とは何か、ということを考えておこう。「趣味」を辞書で引くと、「①仕事・職業としてでなく、個人が楽しみとしてしている事柄。②どういうものに美しさやおもしろさを感じるかという、その人の感覚のあり方。好みの傾向」(『大辞泉』)というように、だいたい2つの意味が出てくる。ここで論じる「着物趣味」の「趣味」は①である。さらに、人間だれしもが持っている時間に注目すれば、趣味とは、食事や睡眠などの生活必要時間、仕事や職業、家事などの労働時間以外の自由時間(余暇)に営まれるものと言うことができる。たとえば、私のように、ほぼ毎日、自分と家族のために食事を作っている人は「料理好き」かもしれないが、それは家事労働であって「料理趣味」ではない。料理趣味とは、日頃、家庭で料理をしない人が、休日などの余暇を利用して日常の食べ物とはちょっと違うレベルのものを料理することを言うのだと思う。
次に「着物趣味」の成立の要件を考えてみたい。着物が生活衣料である間は、着物を着ることは日常に必要な営みであって、趣味にはならない。私の明治生まれの祖母は2人とも、生涯、ほとんど和装しかしなかった人で、毎日、着物を着ていたが、それは「趣味」とはまったく遠い。そうした着物が日常衣料だった時代にも、裕福で高価な着物をたくさん誂える人はいたが、それは「着道楽」であって、「着物趣味」とは言わなかった。つまり、着物が趣味化して「着物趣味」が成立する前提、第1の要件として、着物が日常衣料としてのポジションを失うことが必要になる。
最初の辞書的定義のように「趣味」は本来、個人のものだ。しかし、個人が孤立している間は、ほとんど社会性を持たない。「趣味」がある程度の社会性をもつためには、同じ「趣味」をもつ「同好の士」が集まることが必要になる。つまり、「着物趣味」の同好の士が横のつながりをもって集うことが「着物趣味」の成立の第2の要件になると考える。
そして、その仲間たちの間で、「着物趣味とはこういうものだ」という意識、ある種の規範が共有される。その共有された規範が仲間としての意識を強化していく。こうした特有の規範の成立を第3の要件と考えたい。
Ⅰ 日常衣料としての和装の衰退 ―趣味化の前提として―
1 洋装化と和装の衰退
明治の文明開化とともに日本人の洋装化が始まる。西欧近代文化の輸入と模倣に懸命な新政府は鹿鳴館(1883)に象徴される洋風文化を演出するが根付かなかった。洋装化は軍人の軍服、巡査の制服、官公吏の上層部や洋行帰りの学者など、男性のごく一部に止まり、女性の洋装化はほとんど進展しなかった。
大正後期から昭和初期(1920~36)になると、洋服を着たモダンボーイ(モボ)とモダンガール(モガ)が最新の流行ファッションとして注目されるようになる。とりわけ、女性の洋装化の端緒となったモガへの社会的注目度は高かった。しかし、それは都市における尖端文化ではあったが、全国的・全階層的な広がりを持つものではなかった。
一方、この時代は和装にも大きな変化があった。化学染料と力織機の普及により銘仙やお召などの絹織物の大量生産が可能になり、それまで木綿の着物しか着られなかった階層にまで絹織物が普及していく。
昭和初期に大都市に出現するデパートは、絹織物としては安価な銘仙を衣料品売り場の目玉商品に据える。そして、産地と提携した展示会などを開催して積極的に「流行」を演出していった。
主要な産地(伊勢崎、秩父、足利、八王子など)は、デパートが演出する「流行」に応じるために熾烈な競争をしながら、デザインと技術のレベルを高めていった。その結果、アール・ヌーボーやアール・デコなどヨーロッパの新感覚デザインが取り入れられ、「解し織り」(経糸をざっくりと仮織りしてから型染め捺染した上で織機にかけて、仮糸を解しながら、緯糸を入れていく技法)など技術の進歩によって多彩な色柄を細かく織り出すことが可能になった。こうして、従来の着物とは感覚的に大きく異なる、華やかで斬新な色柄の銘仙が大量に市場に供給され、銘仙は都市大衆消費文化を代表する女性衣料としての地位を確立する(三橋2010)。


【写真1】銀座4丁目交差点(昭和7年=1932年)
出典:石川光陽『昭和の東京 ―あのころの街と風俗―』(朝日新聞社 1987年)

【写真1拡大】

【写真1拡大】
写真1は、1932年(昭和7)の銀座4丁目交差点である(石川1987)。男女とも和装・洋装さまざまな服装の人が行き交い、この時代の服飾文化の豊かさを思わせる。右側、仲良く連れ立った2人の女性の1人は、典型的なモガ・ファッションだが、もう1人は大きな麻の葉柄の振袖で、おそらく銘仙と思われる。また左側の袴姿の女子学生の着物は直線を交差させたアール・デコ風の銘仙だと思う。そしてその右の男の子を連れた母親は縞お召、もしくは縞銘仙を着ていると思われる。
この時代における銘仙・お召の流行が見て取れるが、日本近代の服飾史を洋装化の歴史としか見ない従来のファッション史のほとんどは、モガの出現に注目するあまり、この時代が大衆絹織物の普及による女性の和装文化の全盛期であったことを見落としている(註1)。
日中戦争から太平洋戦争の時代(1937~45)になると、軍服や国民服の着用によって男性の洋装化が進行する。また戦時体制への移行にともない繊維・衣服の統制が行われ、「贅沢は敵だ!」のスローガンのもと、女性の和装文化が抑圧されていった。また、戦地に赴く男性に代わる労働力として、「非常時」への対処として、女性の衣服にも活動性が求められ、そうした社会的要請から着物の上に履くズボン型衣料としての「もんぺ」が普及する。そして、戦争末期には、アメリカ軍の空襲によって繊維製品生産と流通機構が破壊されてしまう。
戦後混乱期(1945~51)は、戦災による物資の欠乏に始まり、繊維素材・製品の統制が衣料品の不足に輪をかけた。そうした中、日本を占領した進駐軍がもたらしたアメリカ文化への崇拝、日本の伝統文化否定の風潮が強まり、和装は旧態の象徴になっていく。その結果、戦時中に進行した男性の洋装化に加えて、女性の家庭外での洋装化が大きく進行する。
そして高度経済成長期(1960~75)になると、経済効率を優先した社会システムの画一化が進む。衣服における画一化はすなわち洋装化であり、企業にでも学校でも洋装が一般化・標準化する。同時に、家庭生活の洋風化も進行し、それまでは外では洋装、家では和装が主流だったのが、家庭内においても男女ともに洋装化が進んだ。
こうして、和装は生活衣料としてのポジションを失っていった。その時期は、地域によって差はあるが、東京などの大都市では1960年代後半から70年代前半の時期に押さえることができると思う。
2 女性着物の多層性の崩壊
1960年代後半から70年代前半に起こった注目すべき現象のひとつは、女性着物の多層性の崩壊である。
(表1)着物の階層性

着物を着る場が大きく狭まった結果、礼装・社交着としての着物は残ったものの、街着・家内着・労働着としての着物(お召・銘仙・木綿・麻)は洋装に取って代わられ衰退した。新たに茶道などの「お稽古着」が登場し、色無地や江戸小紋が好んで用いられるようになる。また、本来は家内着だった紬は高級化して社交着化する。階層性の崩壊と同時に、着物の材質も多様性が失われ、木綿・麻・ウールなどは、ごく一部が高級化して残った以外は姿を消し、着物と言えばほとんどが絹という状態になっていく。
3 「着付け教室」の登場と規範化
この時期に起こったもうひとつの注目すべき現象は「着付け教室」の登場である。1964年(昭和39)に「装道礼法きもの学院」が、1967年に「長沼静きもの学院」(当時は「長沼学園きもの着付け教室」)が、そして1969年には「ハクビ京都きもの学院」が創立され、「着付け教室」として全国的に展開していく。現在に続く大手の「着付け教室」が1960年代後半に創立されたことは偶然ではなく、それなりの社会的理由が有ったからだと思われる。
男性の着付けに比べて女性の着付けは帯結びが複雑・多様であるが、それにしても、着物の着付け、帯の結び方は、母や祖母から娘が生活の中で教わり習い覚えるもので、月謝を払って習うようなものではなかった。しかし、戦中・戦後混乱期に着物を思うように着られなかった女性が母親になった時、成長した娘に着物の着付けを伝授できない事態が発生したと思われる。
たとえば、1925年(大正14)生まれの女性は、戦間・戦後混乱期(1941~50)には16~25歳だった。23歳で娘を産めば、1967年には母親42歳、娘19歳である。成人式が間近になった娘に着付けを教えようと思っても、自分の和装経験が乏しく自信がないというようなケースである。祖母がいれば助けてもらえるだろうが、都会で核家族となると、そうもいかない。どこか教えてくれる所はないだろうか?
この時期に「着付け教室」が次々に創立された背景には、そうした戦争による母から娘へという和装文化の継承断絶が生んだ需要があったのではないだろうか。
着物の着付けは、いたって不器用な私の経験からして、単に着るだけなら、3日も習えば、なんとか着られるようになり、後は反復練習である。器用な人なら1日で覚えられるだろう。しかし、それでは月謝を取って教える「着付け教室」の経営は成り立たない。したがって、「着付け教室」では手っ取り早い簡便な着付けを教えず、いろいろと複雑な手順で教える。さらにごく日常的・庶民的な着付け法ではなく、戦前の上流階級の着付け法をベースにして伝授する。その方が付加価値が高いからである。
実際、この時期の著名な着付け指導者には、戦前の上流階級の女性が多かった。1970年にベストセラーになった『冠婚葬祭入門(正)』(カッパ・ホームス)で「着付け」法を広めた塩月弥栄子(1918~)は裏千家14世家元碩叟宗室の娘であり、1973年から「ハクビ総合学院」の学長を務めた酒井美意子(1926~99)は旧加賀藩主で侯爵の前田利為の娘で、旧姫路藩主で伯爵の酒井忠元の妻だった。
こうした戦前の上流階級の女性たちによって、自分で働かなくてよい上流階級の「奥様」「お嬢様」の非活動的な着付けがマニュアル化され、「着付け教室」で教えられ規範化していった。その結果、着物の着方がすっかり様式化し「こう着なければいけない」という形ができ上がる。
本来、生活衣料であった着物には、その状況に応じた着付け方があった。働く時には身体を動かしやすいように楽に緩めに着付けし、たくさん歩く時には裾がさばき易いように合わせを浅めにしてやや裾短かに着付けるなどといった着付けの融通性が失われてしまった。こうして、働けない、身動き不自由な、皺ひとつ許されないきっちりした、着ていて苦しい着物の着付けが成立する。
習わなければ自分で着られない衣服は、もう日常の生活衣料とは言えない。こうした過程をたどって、着物は日常の衣服としての機能を喪失していき、特別な場合、たとえば、お正月、冠婚葬祭(成人式、結婚式、葬儀、法事)などの非日常の衣服となり、あるいは特殊な職業の人(仲居、ホステスなど)の衣服になってしまった。
Ⅱ 「美しい着物世界」の成立
1 高級化と「美しい」の規範化
着物が生活衣料の地位を失い、特別な衣服になったことで、着物の生産・流通業界は、安価な大量生産中心から高価な少量生産へと転換していく。かっての主役だった銘仙やお召はまったく見捨てられ、手作業のため少量生産しかできなかった各地に残る紬が見出され、そのいくつかが付加価値がある織物として高級品化していった。
たとえば、1933年(昭和8)に秩父産の模様銘仙は5円80銭~6円50銭だった。当時の6円は現代の21000~24000円ほどと考えられ、中産階層なら1シーズン1着の購入が可能な値段だった(三橋2010)。ところが、1999年(平成11)に八丈島特産の黄八丈の反物は48万円もした。平均的な収入の人だったらローンでも組まない限り購入は難しい。
こうした着物の高級品化時代に主な情報媒体となったのが婦人画報社(現:ハースト婦人画報社)の『美しいキモノ』(1953年創刊・季刊)に代表される着物雑誌である。この種の着物雑誌の中身は、高価な着物のオン・パレードであり、安価な着物やまして古着などはけっして登場しない。高価な着物を売りたい着物業者と、そうした高価な着物を購入できる富裕な奥様・お嬢様の「美しい」「上品な」着物世界である。私はこれを「美しい着物世界」と呼んでいる。
「美しい着物世界」の特徴は、誌名通り「美しさ」と「着物」とが過度に結合したことである。『美しいキモノ』は、創刊以来毎号、高価な着物を着た女優さんが表紙を飾るのが通例で、中の誌面もほとんどがプロのモデルの着物姿である。その姿はたしかに美しく、なるほど誌名にふさわしい、と思ってしまう。しかし、着姿が美しいのはもともと美しい女優やモデルが着ているからであって、同じ着物を一般の女性が着ても必ずしも美しくなるとは限らない。
着物が日常の衣料であった時代、そんなことは考えるまでもなく誰もが解っていることだった。ところが、着物が非日常の衣服になるにつれて、わざわざ着物を着て特別の装いをするのだから、きっと美しくなるに違いない、というある種の期待が生まれてくる。実際にはそうなる場合もそうならない場合もあるわけだが、着物業界は、そうした期待感を利用して、着物雑誌の誌面を通じて「着物を着ている人は美しい」というイメージを流布し、「着物を着れば美しくなれる」さらに「高価な着物を着ればより美しくなれる」という幻想(錯覚)を喚起し、売り上げの向上につなげるという戦略をとった。
「着物を着ている人は美しい」というイメージは、やがて「着物を着ている人は美しくなければならない」という非現実的な意識に転化していき、必ずしもそうならない女性たちを着物世界から遠ざけることになった。
2 色・柄の衰退
日本の女性の和装文化は、江戸時代には遊廓の高級遊女(花魁)がファッションリーダーであり、明治以降も芸者をはじめとする玄人筋が大きな比重を保っていた。着物が生活衣料としての地位を失っていく時代になっても着物を着続け、着物業界の売り上げのかなりの部分を担ったのは銀座や北新地に代表されるクラブ・ホステスたちだった。にもかかわらず、「美しい着物世界」では、こうした玄人の着物は徹底的に無視・排除される。間違っても「銀座クラブママの着こなしに学ぶ」などという特集は組まれない。
「美しい着物世界」の着物のコンセプトは、あくまでも「上品」である。これを意訳すれば「玄人っぽくない」ということになる。具体的には、色味の弱い色、小さ目の柄、つまり自己主張の弱い「控えめ」が上品とされる。色については、原色や強い色は忌避され、薄い色、さらには無彩色(白・黒・グレーの濃淡、銀)が好まれる、柄は巨大柄・大柄が避けられ、比較的小さめの柄を反復する小紋や、細かな点で小さな意匠を全面に置く江戸小紋、さらには柄が消失した色無地が好まれるようになる。また、日本の伝統的な意匠である縞も、太縞や棒縞のようなシンプルで大胆なものは忌避され、細縞やよろけ縞のような控えめなものが好まれる。太縞や棒縞がもつ粋なイメージが玄人(粋筋)を連想させるためと思われる。
こうした傾向は着物の階層性が崩壊し、「お稽古着」の比重が増した結果、万事派手を嫌い、地味を上品とする茶道の世界の「趣味」が着物全体に影響を及ぼすようになったことが作用していると思われる。その結果、戦前の着物に比べて、現代の着物は、色は淡く、柄は小さく、色柄のバリエーションが少なくなり、創造性が失われ類型的となり、個性的でなく画一化が進んでしまった。服飾デザインという見地からすれば、明らかな退化であるが、商業的にはそうした無個性な無難な着物でないと売れなくなってしまったのである。
3 高級化の帰着と「趣味の着物」
こうした着物の高級化は、着物の世界をますます狭めていった。何10万円という衣料を次々に購入できるような富裕層がそんなに多いはずはない。「和装が好き、着物を着たいけど高くて手が出ない」という階層の方がずっと多かった。それでもバブル経済期(1980年代後半)はまだよかった。驚くほど高い着物が売れた。たとえば、染色家の久保田一竹(1917~2003)の一竹辻が花の訪問着が1200万円とか。しかし、購入された高価な着物が実際に着られたかというと必ずしもそうでもなく、多くは「箪笥の肥やし」と化し、着物世界が再び拡大することにはつながらなかった。そして、バブル崩壊後、着物業界は大量の在庫を抱えたことに加えて、バブル期の「箪笥の肥やし」がリサイクル市場に放出されることで、新規需要の落ち込みに苦しむことになる。
ところで、1980年代には「趣味の着物」を看板にする店が現れる。目の肥えた顧客を相手に、普及品ではなく高級紬や作家物など厳選された商品を扱う店である。しかし、この「趣味」は、「はじめに」で紹介した辞書の②の意味「どういうものに美しさやおもしろさを感じるかという、その人の感覚のあり方。好みの傾向」と解釈すべきだろう。「良いお着物の趣味でいらっしゃいますわね」の「趣味」である。この時点では、「仕事・職業としてでなく、個人が楽しみとしてしている事柄」という①の意味での「着物趣味」はまだ成立していなかった。
4 男性の和装の(ほぼ)絶滅
写真2は、1959(昭和34)正月のある一族(東京在住)の集合写真である(小泉2000)。
.jpg)
【写真2】ある一族のお正月(昭和34年=1959年)
出典:小泉和子『昭和のくらし博物館』(河出書房新社 2000年)
成年女性8人はすべて和装である。これに対して成年男性4人は家長と思われる1人が和装なだけで他の3人は洋装である。また子供たちも女児6人が和装4、洋装2であるのに対し男児2人はいずれも洋装だ。つまり、男性の和装はおじいちゃんだけという状態で、男性の洋装化=和装の衰退が女性のそれよりもかなり早く進行したことがはっきり見てとれる。
お正月ですらこの状態なのだから、平常時において男性が和装する機会はいよいよ乏しくなっていった。歌舞伎役者、茶道家、落語家、棋士など一部の限られた職業の男性の需要に応じた生産は続けられていたが、1970年代後半から80年代になると、男性の着物は高級品を除き店頭から姿を消していく。和装趣味の青年が着物を着たいと思っても、(彼の手が届く範囲では)「どこにも売っていない」状況になり、着付けのマニュアル本からも男性向けの記述はほとんどなくなってしまう(早坂2002)。こうして、1980年代後半から90年代前半には、男性着物はほぼ絶滅状態になり、着物は女性の物という社会認識が定着し、着物世界におけるジェンダー的な乖離は極限に達した。
こうして、着物趣味の成立の第1の要件である日常衣料としての地位の喪失は、少なくとも1980年代末には完全に達成されていた。しかし、まだこの時期には、着物世界の人間関係は、着物を売る着物屋と着物が好きで買う客の商業的関係であり、着物好きの客同士の横のつながりは、ほとんどなかった。第2の要件である着物好き同士の横のつながりができるまでには、もう一段階が必要だった。
Ⅲ 情報革命と着物世界 ―趣味化への胎動―
1 「着ていく場所がない」
着物を着て家を出ると、顔見知りの近所の奥さんに「あら、お着物でお出かけ? 今日は何かありますの?」と興味津々に尋ねられる。多くの着物好きの女性が経験したことだ(男性の場合はさらに不審がられて声も掛けられない)。1990年代になると、日常性を完全に喪失し衣服として特殊化してしまった着物には「着る理由」が必要とされるようになってしまった。「ただ着物を着たい」、「着て出かけたい」ができない状況が生じたのである。
「近所でジロジロ見られるので、着物で出掛けられない」、「変わり者扱いされるので(着物のことは)周囲の人に黙っている」、そんな話を聞いて「なんだ、女装と同じではないか?」と思ったことがある。冗談ではなく、1990年代には、着物のファッション・マイノリティ化はそこまで進行していた(三橋2006)。
実際、堂々と着物を「着られる場所」「着る機会」は少なかった。お正月は年に1度だし、結婚式に呼ばれる機会もそうはない。そうした状況の中で、「鈴乃屋」や「三松」のような大手の着物チェーンが「着物を着る場」としてイベントを企画・開催するようになる。しかし、お商売だから当然なのだが、そうしたイベントは着物展示会と併設されていたり、そうでなくても「お出かけ」の度に着物を作ることを勧められ、結局、多大の出費をすることになる。そうした制約なしに、「気楽に着物を着る場・機会があればいいのに」と、着物好きの多くが思うようになっていた。
2 パソコン通信からインターネットへ
1997年8月、パソコン通信「NIFTY-Serve」の中に「きものフォーラム」が開設される。「NIFTY-Serve」のサービス開始(1987年4月)から10年も後のことだった。そして11月25日には東京赤坂の「全日空ホテル」で「きものフォーラム」の「オフ会」(オフライン・ミーティング)が20名の参加者で開催された(早坂2002)。
これはパソコン通信と趣味の世界の結合としてはかなり遅い。たとえば女装趣味のパソコン通信「EON」(主宰:神名龍子)は1990年に創立され、その活動を通じて1995年頃にはすでに「電脳女装世界」ともいうべき女装仲間の横のつながりが形成されていた。1996年4月に開催された「EON」ボード上に設置された「クラブ・フェイクレディ(CFL)」(主宰:三橋順子)の「オフ会(FL3)」には77名が参加している。そんなものと比較するなと言われるかもしれないが、パソコン通信を通じての仲間の結合という点で、この時期の「着物仲間」は「女装仲間」よりもずっとマイナーな存在だったことがわかる。
1996~97年頃から日本でもようやくインターネットが盛んになると、1997年に秋田県在住の「澤井夫妻」がインターネット上に「きものくらぶ」を開設する。これが日本最初のインターネット着物サイトと思われ、私が最初にアクセスした着物サイトも「きものくらぶ」だった。同年12月には早坂伊織氏が「男のきもの大全」を立ち上げ、これが最初の「男着物」専門サイトになった。
こうして、パソコン通信、次いでインターネットを媒介にして、日本各地に孤立、散在していた「着物好き」が結びつき、仲間化していくことになる。
3 「男着物」の復活と男性主導の「オフ会」
パソコン通信時代から代表的な「着物好き」として活躍する早坂氏の本業が「富士通」のシステムエンジニアだったように、また「きものフォーラム」の中に「男のきもの」会議室が設置されたように、パソコンの普及度、パソコン通信やインターネットへのアクセス率は、その初期においては男性の方が圧倒的に高かった。したがって、インターネットによる仲間化や「オフ会」の開催は男性が先行する。
早坂氏が主催する男着物の「オフ会」である「男のきもの大全会」が開催されたのは1998年10月だった(参加者50名)。1999年12月には、毎週土曜日に着物男性が銀座に集まる「きものde銀座」の第1回が開催される(参加者14名)。この集まりは1999年11月に開催された第2回「男のきもの大全会」から派生したものだった(早坂2002)。
こうした経緯をたどって、1990年代末に、ほぼ絶滅状態だった男着物が復活し仲間同士の横のつながりが形成されていった。1990年代末から2000年代初頭にかけて、着物趣味成立の第2の要件が整ったことになる。
4 「ふだん着きもの」への志向
「インターネットきもの」の初期に多くのアクセスを集めたサイトに「あみさんのきもの」(主宰・鳥羽亜弓)があった。このサイトの特徴は、地方在住の子育て中の主婦が毎日着物を着て生活しているという「特異性」にあった(鳥羽2001)。着物で日常を過ごし、家事を行い、子供を育てるという戦前期の日本の多くの主婦がしていたことが、すっかり特異なことになってしまったのである。
2002年に『天使突抜一丁目―着物と自転車と―』を出版したマリンバ奏者の通崎睦美も、着物で自転車に乗るという「特異性」で注目された(通崎2002)。明治~大正期のハイカラ女学生がごく普通にしていたことなのに。
また、現代風俗研究会の古参会員である磯映美は、「華宵」の名義で、2001年から2003年にかけて、散歩きもの普及員会ニュースレターとして「着物で、ぶらぶら」を刊行した。
こうした「ふだん着着物」、あるいは日常的な「着物暮らし」への志向は、日常性を喪失した和装文化に反発・逆行するものであり、その方向性はその後の「趣味化」の中に受け継がれていくことになる。
Ⅳ アンティーク着物ブームと「着物趣味」の成立
1 女性主導の「オフ会」の盛行
当初、男性主導だった着物「オフ会」も、女性のインターネットアクセス率が上がるにつれて、女性の参加が増加していった。男性主導の「オフ会」には、男性だけで語り合いたいホモ・ソーシャルなタイプと、主催者が「女好き」で積極的に女性の参加を勧誘するタイプとがあった。2000年頃に何度か開催された村上酔魚堂の「オフ会」は後者のタイプだった。
.jpg)
【写真3】「村上酔魚堂・浅草オフ会」(2000年9月)。
ここで後の「うきうききもの」の初期中核メンバーが出会う
そうした場で着物好きの女性たちが知り合い、その横のつながりをベースに、2001年頃から女性主導の「オフ会」が盛んに開催されるようになる。その代表は、東京を中心とした首都圏では「うきうききもの」(主宰:古川阿津子、2001~10)、京都を中心とした関西圏では「夏海の遊び着」(主宰:夏海、2001~ )であり、最盛期には月に数回ペースで「オフ会」を開催した。
-5d3a9.jpg)
【写真4】「うきうききもの」秩父銘仙オフ会(2002年4月)。
中央が主宰の「あつこ女将」
こうした「オフ会」は心置きなく好きな着物を着られる場であり、着物に関する様々な情報や工夫が交換され、またお互いの着こなしが参照され相互に影響を与えあった。そして、「オフ会」の様子がインターネットサイトにレポートされることで、新しい参加者を引きつけていった。2000年代前半は、インターネットと「オフ会」を通じて、女性の着物仲間が横のつながりを形成していった時代だった。
私も参加した「うきうききもの」では、初期のメンバーの間には、既存の着物世界への飽き足らなさ、不満が共通意識としてあった。地味=上品に固定化され、「着付け教室」が作り上げた厳格な着用規範に反発し、「もっとどんどん、自由に、楽しく着物を着たい!」「(ミセスだって)派手な着物を着てもいいじゃない!」という思いである。「美しい着物世界」とまったく異なる着物への志向・嗜好がそこにはあった。
2 アンティーク着物ブーム
女性主導の「オフ会」の盛行とほぼ時を同じくして、アンティーク着物ブームが起こる。その火付け役は「別冊太陽」(平凡社)の「昔きもの」シリーズだった。2000年3月の『昔きものを楽しむ(1)』に始まり、『昔きものを楽しむ(2)』(2000年11月)、『昔きものと遊ぶ』(2001年8月)、『昔きものを買いに行く』(2002年12月)、『昔きものの着こなし』(2003年4月)、『昔きもの 私の着こなし』(2004年5月)とほぼ1年1冊ペースで計6冊が刊行された。
このシリーズ、最初は「骨董を楽しむ」シリーズの1冊として刊行されたように、骨董的な価値のあるアンティーク着物を「収集して楽しむ」というスタンスだった。ところが途中から、アンティーク着物を「着て楽しむ」という方向に変化していった。表紙も最初は着物の意匠だったのが、3冊目の『昔きものと遊ぶ』は着姿になっている。
「別冊太陽」の「昔きもの」シリーズによってアンティーク着物への関心が急速に高まり、骨董屋や骨董市の露店で、古い着物を漁る人々が出現するようになる。とくに現代の着物に比べてデザイン性に富み、派手な色柄の銘仙やお召が注目され、それまで二束三文(500円以下)だった銘仙の古着がたちまち値上がりしていった。
そうして探し出し手に入れた古着を洗い繕って、場合によっては仕立て直す。手間暇を惜しまない。そして、その着物を「オフ会」で仲間たちにお披露目する。すると、「わ~ぁ、すてき、どこで手に入れたの?」「いくらだった?」と仲間から質問が飛ぶ。「○○の露天市でね、500円だったの。けっこう汚れていたから(着られるようにするのが)大変だったけど…」。こう答えるとき、それまでの労苦が報われ、ある種の達成感がある。
探す→洗う・直す→着る→仲間に見せる、このサイクルが毎月のように繰り返される。傍目から見れば、いい大人の女性が古着を漁り集め、着ることに夢中になっているわけで、いったいウチの娘(もしくは妻)は何をしているのだ、と呆れられることになるが、まさにそれが「趣味」なのである。
2002年6月には、アンティーク着物に特化した着物雑誌『Kimono道』(祥伝社、後に『Kimono姫』と改題)が創刊される。そのコンセプトは「アンティーク&チープ」であり、表紙に記されたリードは「キモノのはじめてはアンティークから」だった。
アンティーク着物の場合、値上がりしたと言っても、せいぜい1000円から5000円程度で千の桁で納まり、万の桁になることは少なかった。稀に数万円という高級アンティーク着物もあったが、当時、市販の現代着物の多くは20~50万円の価格帯だったから、それでも10分の1である。30万円の現代着物1枚を買う値段で、露天商から3000円のアンティーク着物が約100枚買える計算になり、すさまじい価格破壊ということになる。
安価なアンティーク着物がブームになったことは、それまで経済的な理由で着物を思うように着られなかった「着物好き」にとっては大きな福音であり、とくに20代、30代の比較的若い人たちが着物世界に参入できるようになった。20世紀後半の50年間一貫して長期低落傾向にあった着物人口は、21世紀に入って一時的にせよ増加に転じたのである。これは「趣味化」というある種の「突然変異」かもしれないが、長い和装の歴史の中で、やはり画期的なことだと思う。
2000年代のアンティーク着物ブームによって、東京白金の「池田」、原宿の「壱の蔵」などのアンティーク着物専門店はおおいに賑わい、コレクターとしても知られた店主の池田重子(1925~)や弓岡勝美の名も高まった。とりわけ池田は、新宿伊勢丹や銀座松屋などで「池田重子コレクション―日本のおしゃれ展―」(1993~2011)を何度も開催し、アンティーク着物の社会的認知を高めた。池田のコレクションとコーディネートは、アンティーク着物ファンの垂涎の的になった。
また、リサイクル着物の「ながもち屋」や「たんす屋」がチェーン展開するのもこの時期である。しかし、アンティーク着物ブームは既存の着物業界にはほとんど影響しなかった。
3 銘仙への注目
アンティーク着物ブームの中で、とりわけ人気度が高かったのが銘仙だった。銘仙とは、先染(糸の段階で染める)、平織(経糸と緯糸の直交組織)の絹織物である。その詳細については別稿に譲るが(三橋2002,2010)、大正~昭和戦前期においては、安い価格と豊富な色柄が、中産階層のお嬢さんの普段着、女中さんの晴れ着、もしくは、女教師の銘仙+女袴(行燈袴)、牛鍋屋の仲居の赤銘仙、カフェの女給の銘仙+白エプロンといったような職業婦人の仕事着として好まれ大流行した。戦後も生産は続いたが、主な着用層だった「お嬢さん」や職業婦人が真っ先に洋装化したこと、粗悪品の流通によりイメージが低下したことで徐々に衰退した。それでも、大柄で色鮮やかな模様銘仙は、自分を「広告塔」にする女性、具体的には「赤線」(黙認買売春地区)の「女給」(実態は娼婦)たちに愛用された。
着尺としての銘仙の生産は、1960年代末までにほぼ途絶え、工場生産品ゆえに伝統工芸・美術品になることもなく、技術もほとんど断絶してしまった。つまり、銘仙はいったん滅んだ織物だった。
ところが、アンティーク着物ブームにより、女性の和装文化の最盛期だった大正・昭和初期の着物文化が再評価された結果、その最盛期を担った銘仙がにわかに注目されるようになる。2002年1月に主要産地だった埼玉県秩父市に初めての銘仙資料館「ちちぶ銘仙館」がオープンし、それを受けて2003年5月に三橋順子が「艶やかなる銘仙」を『Kimono姫』2号に執筆した(三橋2002)。2003年6月には銘仙コレクターの木村理恵と通崎睦美の「銘仙コレクション2人展」が東京中野の「シルクラブ」で開催される。そして2004年12月には秩父市在住の木村理恵のコレクションを紹介した『銘仙―大正・昭和のおしゃれ着―』が「別冊太陽」(平凡社)の1冊として刊行され、銘仙ブームはひとつの頂点を迎える。
その後も銘仙ブームは続き、銘仙をメインにした企画展が各地で立て続けに開催された(註2)。そして、2009年5月には銘仙を主な展示品とする「日本きもの文化美術館」が福島県郡山市にオープンし、2010年4月には同美術館から『ハイカラさんのおしゃれじょうず-銘仙きもの 多彩な世界』が刊行された。
こうした銘仙ブームは、現代の着物にはまったく失われてしまった大胆で前衛的な大柄と、原色を多用し多色を巧みに配した強烈な色彩感覚が作り出す華やかで艶やかなイメージに多くの着物好きが魅せられたからであり、銘仙そのものが現代着物へのアンチテーゼとなっている。銘仙のそうした性格は、2000年代に成立する「着物趣味」の方向性と合致し、それゆえに重要なアイテムとなったのである。
4 「規範」を越えて ―「着物趣味」の成立―
2000年代前半のアンティーク着物ブームの中で成立する「着物趣味」の基本コンセプトは、大正・昭和戦前期の着物文化の再評価とそれへの回帰である。それは、1970年代以降に形成された地味=上品に固定化された「美しい着物世界」や、「着付け教室」が流布する厳格な着用規範への反発と表裏一体だった。それはまた、すっかり特別な場の衣服になってしまった着物から、本来の日常性を取り戻す方向性だった。和装文化の伝統を意識しつつも、戦後の着物世界が作り上げた規範から自由に、好きな着物を着たいように着る、というスタンスだ。
日本の女性着物は、既婚か未婚かの区分が明瞭で、それが身分標識にもなっていたが、アンティーク系の場合、そうした境界も越えてしまう。ミセスであっても、派手な着物、目立つ帯を厭わない。振袖だって着てしまう。白半襟、白足袋という「美しい着物世界」の「常識」に対し、色半襟・刺繍半襟、色足袋・柄足袋が好まれる。着物と帯、そして小物類(半襟、帯揚、帯締、足袋)の色合わせ・柄合わせや帯結びに凝る。髪も、お正月やイベントには、すでに見かけることも稀になった日本髪を結う。
「美しい着物世界」の人に比べて行動性が高いので、着付けも前合わせは浅く、したがって襟のy字は深く半襟をたくさん露出し、襟もかなり抜く。「着付け教室」で「下品なのでやってはいけません」と教えられることばかりである。そして、いつでも(仕事以外)どこにでも着物で出掛ける。休日、近所に買い物に行くのも着物だし、国内旅行はもちろん、海外旅行も着物で行く。履物は、たくさん歩くので、草履より下駄が好まれる。なにより、着物も帯も「値段の高きをもって貴しとせず」で、その人の個性に合ったコーディネートや創意工夫が評価される。
こうした方向性・嗜好は、ほとんどすべて「美しい着物世界」への明確なアンチテーゼである。したがって、当然のことながら、従来の規範を順守する「美しい着物世界」の人たちからの反発も大きかった。ネット上で「ぼろ着て何が楽しいの?」「お女郎さんの集まり」「座敷牢から抜け出してきたみたい」と批判されるのは常のことで、銀座で集まっていた時、見知らぬ中年女性(洋装)にいきなり「ここは銀座なんだから、日本の恥になるようなみっともない着方はしないで!」と面と向かって言われたこともあった。単なる好奇の視線には慣れっこだが、さすがに「日本の恥」とまで言われるとは思っていなかった。
しかし、そこまで強く反発されるということは、従来の着物世界の規範を越えた、新しい、そして特有の方向性が成立したということである。既存の着物世界から批判されたことで逆に「私たちの着物趣味とはこうなんだ、これでいいんだ」という意識が仲間たちの間で共有化されていった。こうして、第3の要件が満たされ2000年代前半に新しい「着物趣味」の世界が成立した。
-9cd66.jpg)
【写真5】アンティーク銘仙のコーディネート。
モデル:(左)小紋、(右)YUKO
2人とも「アラフォー」のミセス(2005年3月)
Ⅳ 新しい着物世界
1 着物趣味イベントの開催
2000年代中頃になると、「着物趣味」の成立を背景に、従来の「オフ会」からさらに発展した着物趣味イベントが開催されるようになる。ここでは東京で開催され、私も参加したことがある代表的な2つの着物趣味イベントを紹介してみたい。
① 「きものde銀座」
「きものde銀座」は毎月1度銀座で開催される「着物好き」の集会イベントで、「男のきもの大全会」の派生イベントとして1999年12月に第1回が開催された。最初は毎週土曜日開催、着物男性だけの集いだったが、2000年2月からは月1回(毎月第2土曜)となり、着物女性も参加するようになった。主催者はなく、当初は「旦那さん」(牧田氏)が事務局を担当していたが、2006年以降は有志の当番制で運営している。着物で集まる人も会員制ではなく、まったくの任意参加である。
15時に銀座4丁目交差点「和光」前で待ち合わせ、「歩行者天国」の中央通りを1丁目方向に歩き「ティファニー」前で集合写真を撮影、その後は自由行動で、なにかイベントがあれば行きたい人はまとまって行く。17時半頃から「土風炉・銀座1丁目店」で懇親会(会費3000円)となり、20時前後にお開き、希望者は二次会へという毎回同じスケジュールで、途中参加・離脱も自由である。
コンセプトは文字通り「銀座で着物を着る」ということだけ。参加者の着物のスタイルもアンティーク系、「ふだん着着物」系から「美しい着物」系まで様々であり、どんな着方であっても批判しないことになっている。
2008年4月8日に第100回を迎え、2013年12月には168回となる。台風でも大雪でも中止せず(連絡方法がないため)、東日本太平洋沖大地震の翌日(2011年3月12日)にも20数名の参加者で開催された。最初期には参加者1名ということもあったが、近年は集合写真を見る限り40~60名くらいだろうか(註3)。
主催者がいない有志持ち回りの運営と、参加も着方も自由度が高い「緩い」形態が「着物趣味」のイベントとして最も長続きしている秘訣だと思う。
-944a6.jpg)
【写真6】第100回「きものde銀座」(2008年4月8日)
.jpg)
【写真7】2009年1月の「きものde銀座」。
日本髪を結い大振袖を着て築地・波除神社に初詣
② 「日本全国きもの日和」
「日本全国きもの日和」は、「きものであそぼう」をスローガンにした着物ファンの手作りイベントで、「玉龍」こと西脇龍二氏を中心とした「実行委員会」が運営している。メンバーの多くは「きものde銀座」で出会っている。11月3日を「きもの日和」として全国各地で着物イベントの開催を呼びかけ、第1回は7都市、第2回は20都市、第4回は25都市で「きもの日和」が開催され、「着物趣味」の地方への波及に大きな役割を果たした(註4)。
メイン会場である「きもの日和TOKYO」は、恵比寿のイベントホール「EBIS303」で2004年から2008年まで5回開催され、入場者は第1回が1500人、第3回(2日開催)は3000人だった。モデルもスタッフもすべて着物仲間で構成する本格的な「きものファッションショー」は観衆の注目の的だった。さらに、着物写真集『Kimono人』(2005、2006、2007の3冊)を自費出版した。
また、中心メンバーは、毎年5月に開催される静岡県下田市「黒船祭」に出張し、「賑わいパレード」に参加し、野外ファッションショーを開催している。
しかし、2007年の第4回から入場者、出店、広告が減少し赤字となり、経済不況(リーマン・ショック)もあって2009年11月に計画された「きもの日和TOKYO」は延期になってしまう。2010年3月に「きもの日和with目黒雅叙園」として開催されたが、2011年4月の開催予定が東日本大震災の影響で中止になった後は復活していない。
-5318c.jpg)
【写真8】「きもの日和TOKYO 2004」の冊子(2004年11月
-c5c3c.jpg)
【写真9】「きもの日和TOKYO」の「きものファッションショー」(2006年11月)
-c92c7.jpg)
【写真10】「下田黒船祭」の野外ファッションショー。
「ペリー・ロード」の橋の上が舞台(2007年5月)
-ddbca.jpg)
【写真11】「下田黒船祭」の賑わいパレード(2008年5月)
日本髪は美容院ではなく自分で結う
2 着物イベントの問題点
着物イベントに参加して、気付いた問題点を整理しておこう。第一はお金の問題である。「きもの日和TOKYO」のように、意欲的に活動を展開した結果、イベントの規模があまりに拡大してしまうと、集客や採算のような「趣味」とは性格が異なる要請が発生してしまう。また必要な経費が大きくなれば、経済・社会情勢の影響を大きく受けるようになる。「趣味」とは本来、浪費だが、あまり補填しなければならない金額が大きくなると、「趣味」の仲間では耐えられなくなる。といって、企業の協賛・支援を受ければ、商業資本の論理が入ってきて、ますます「趣味」の領域から外れてしまうジレンマがある。「趣味」としては拡大路線一筋ではなく適正規模を保つことも必要だと思う。
第2は、着物イベントのジェンダー的な構造問題である。端的に言えば、リーダーシップをとる男性、イベントの「華」としての女性という基本構造がそこにある。たとえば、ファッションショーやパレードで、男性リーダーの指示で若手の女性や美しい女性が目立つ場所に配される傾向は明らかにあった。それもまた社会的要請なのかもしれないが、必ずしもそうでない女性たちからは不満が出ることになる。
第3は、セクシュアリティの問題で、大人の男女が集まり、懇親会などでお酒が入ると、男性による女性へのセクシュアル・ハラスメントが発生する。その場合、運営側の男性のセクハラ認識が甘いと、結局は被害を受けた女性が泣くことになってしまう。
第4は、和装女装趣味の男性の問題で、近年は「女装」を禁止する着物イベントが増加している。和装文化に女形が貢献してきた度合いを考えれば、まったく理不尽と言いたくなる。そして、「女装禁止」の結果、日常的に女性として生活しているMtF(Male to Female)のトランスジェンダーまでが排除されることになってしまう。これは性的マイノリティに対する不当な社会的排除である。
第5は、高齢化の問題で、他の趣味の世界と同様に若い人がなかなか入ってこない。2000年代初頭のアンティークブームを担った30~40歳代は、10年たった現在40~50歳代であり、さらに10年たてば…である。今のままでは先細り傾向は免れないだろう。
これらの問題、とりわけ第2~5の問題は、着物趣味の世界だけの問題ではなく、日本社会が抱える問題の投影である。しかし、比較的柔構造な「趣味」の世界の特性を生かし、しっかりした認識をもって対応すれば、ある程度は改善可能な問題であると思う。
おわりに ―着物趣味の将来―
1 着たい着物がなくなる
現代の「着物趣味」、とりわけアンティーク派にとっての最大の不安は、近い将来、着たい着物がなくなってしまうのではないか、ということである。なんら特徴のない「つまらない」現代着物は巨大なデッドストックがあるのに、着たいと思うようなアンティーク系の着物はどんどん消えていく。和装文化の全盛期(1926~1936)に作られた銘仙・お召は、すでに80年前後が経過し耐用年数が過ぎつつあり、衣類としての寿命が尽きるのはもう遠いことではない。せめて、あと10年もってほしいと思うのだが。
また、現代女性の体格向上により、女性が小柄・低身長だった時代に作られたアンティーク着物を着られる人が減っている。こうした状況で頼りになったのは、2000年代の銘仙ブーム期に足利・伊勢崎などの旧産地で生産された復刻銘仙だった。復刻銘仙は、問屋価格で5~6万円、小売価格では8~10万円になってしまうので、かってのような普及は無理だったが、それでも、私のように身長が高い銘仙好きにはとてもありがたかった。しかし、わずかに残っていた職人さんの高齢化や逝去によって、2010年代初めに生産が途絶えてしまった(註4)。
先染め(糸を染めて柄を織り出す)の織物は技術的に難易度が高く、現状ではいったん絶えた技術の復活は望めそうにない。それが無理なら、せめて「全盛期(昭和戦前期)」のデザインを、後染め(糸を布に織った後で染める)の染物で再現してほしい。幸い現在ではアンティーク着物の色柄をコンピューターに取り込み、補修を加えた後に、インクジェット・プリンターで布地にプリントすることが容易になった。銘仙写しの浴衣や小紋が増えてくれればと思うのだが、現在の着物業界の沈滞した状況では、それも難しそうだ。
2 コスチューム・プレイとして
生産面では大きな不安があるが、着物をファッション・アイテムと考えた場合、その将来に希望はなくもない。
着物が日常の衣服としての機能を失い、着物を着る人がファッション・マイノリティになったことで、社会の服飾規範を超越する、ある種の自由を獲得できた。そもそも着物を着ていることが「変わり者」「外れ者」なのだから、細かな社会規範に縛られることはない。
そう思いきってしまえば、着物は自己主張、自己表現の手段として、そして変身のアイテムとして絶好である。コーディネートに工夫を凝らせば、立派な会社勤めの男性が任侠系の「あぶなそうな兄さん」に、まともな会社のOLさんや良家の奥様が芸者やお女郎上がりの「あやしい姐さん」に変身できる。背景や小道具に気を使えば、あっという間に昭和初期や昭和30年代にタイムワープした写真を撮ることも可能だ(三橋2006)。
-c2fb9.jpg)
【写真12】石仏に祈る村娘(昭和初期風)
モデル:YUKO
撮影:2008年2月、埼玉県秩父市金昌寺

【写真13】「赤線」の女(昭和28年設定)
モデル:YUKO
撮影:20010年10月、東京「鳩の街」旧「赤線」建物(娼館)をバックに
今や着物は、社会的立場を変え、年齢を化けて、時空すら超える力を持つようになった。それを活用しない手はない。21世紀の着物趣味は、こうした「着物で遊ぶ」、コスチューム・プレイとしての方向性をより強めていくことになると思う。
日本人の伝統衣装という路線では、美術工芸品としてはともかく、衣類としての着物はもう生き残れない段階になっている。「着物趣味」の仲間たちが目指してきた創造性のある自己表現のファッション・アイテムという方向こそが、着物という日本人の民族衣装を次の世代に伝える道だと私は思う。
(註1)村上信彦『服装の歴史2(キモノの時代)』(理論社、1974年)だけが、この時代の和装文化の発展に正当な評価を与えている。
(註2)主なものを掲げると、京都古布保存会「京都に残る100枚の銘仙展」(東京世田谷「キャロットタワー」、2005年3月)、須坂クラッシック美術館「大正浪漫のおしゃれ―銘仙着物―」(長野県、2007年8月)、京都府城陽市歴史民俗資料館「銘仙―レトロでモダンでおしゃれな着物―」(京都府、2008年8月)、神戸ファッション美術館「華やぐこころ―大正昭和のおでかけ着物―」(兵庫県、2008年11月)など。
(註3)の公式サイト「着物de銀座」(管理人:京屋悟雀氏)を参照
http://www.kimono-de-ginza.net/sub2.htm
(註4)2013年段階で継続しているものとして「着物日和in信州須坂」「奈良きもの日和」「きもの日和 in TOMO」(広島県福山市鞆の浦)などがある。また「群馬きもの復興委員会」「NPO法人川越きもの散歩」のように、それぞれの地域で積極的な着物普及活動をするグループも増えた。
(註5)京都の着物問屋「きものACT」が現地の職人さんに依頼して生産していた足利銘仙は2010年頃に、NHKの朝の連続ドラマ「カーネーション」(2011年度後期)で話題になった「木島織物」の伊勢崎銘仙は2012年末に生産が止まった。
文献
石川光陽1987『昭和の東京 ―あのころの街と風俗―』(朝日新聞社)
小泉和子2000『昭和のくらし博物館』(河出書房新社)
通崎睦美2002『天使突抜一丁目 ―着物と自転車と―』(淡交社)
鳥羽亜弓2001『浴衣の次に着るきもの(アミサンノキモノ)』(インデックス出版)
日本きもの文化美術館2010『ハイカラさんのおしゃれじょうず -銘仙きもの 多彩な世界-』(日本きもの文化美術館)
早坂伊織2002『男、はじめて和服を着る』(光文社新書)
別冊太陽2000a『昔きものを楽しむ(1)』(平凡社)
別冊太陽2000b『昔きものを楽しむ(2)』(平凡社)
別冊太陽2001『昔きものと遊ぶ』(平凡社)
別冊太陽2002『昔きものを買いに行く』(平凡社)
別冊太陽2003『昔きものの着こなし』(平凡社)
別冊太陽2004a『昔きもの 私の着こなし』(平凡社)
別冊太陽2004b『銘仙 ―大正・昭和のおしゃれ着物―』(平凡社)
村上信彦1974『服装の歴史2(キモノの時代)』(理論社)
三橋順子2002「艶やかなる銘仙」(『KIMONO道』2号、祥伝社。後に『KIMONO姫』2号、2003年、祥伝社、に拡大再掲)
三橋順子2006「着物マイノリティ論」(『Kimono人 2006』きもの日和実行委員会)
三橋順子2010「銘仙とその時代」(『ハイカラさんのおしゃれじょうず -銘仙きもの 多彩な世界-』日本きもの文化美術館)
【講演録】「男の娘(おとこのこ)」なるもの ―その今と昔・性別認識を考える― [論文・講演アーカイブ]
駒沢女子大学日本文化研究所『日本文化研究』第10号(2013年3月)掲載
.jpg)
---------------------------------------
平成24年(2012)度(駒沢女子大学)日本文化研究所主催講演会 2012年6月15日
「男の娘(おとこのこ)」なるもの
―その今と昔・性別認識を考える―
三橋 順子(性社会・文化史研究者 都留文科大学・明治大学非常勤講師)
皆さん、こんにちは。三橋でございます。このたびは私のような者をお招きいただき、大変うれしく思っております。自己紹介するとそれだけで持ち時間が終わってしまうようなややこしい人間なので、今、所長先生からお話がありましたように、適当に中に折り込んでいこうと思います。
最初にこちらにご縁をいただきましたことを少しお話ししておきます。以前、駒沢女子大学にいらした日本古代史の倉本一宏さんが京都の国際日本文化研究センターに着任をされました。私はもう10年ほど前から井上章一さんという建築史・風俗史の先生が主宰する「性欲の文化史」「性欲の社会史」の共同研究のメンバー(共同研究員)として年に5~6回、京都へ通っていました。
日文研は共同研究を重視する組織で専任の先生は他の先生の共同研究会にもいくつか出ないといけないというルールがあります。それで井上さんが倉本さんの研究会に出ることになりました。倉本さんが主宰されているのは主に平安、鎌倉の貴族の日記、そこから広げた日記の総合的研究という研究会です。井上さんが「僕、貴族の日記なんて読めないし、わからない。少しサポートしてもらえませんか」ということで、井上さんのお伴で私も倉本さんの研究会の共同研究員になりました。
その懇親会のときに、研究会の中核のメンバーの方たちは、日記のことばかりマニアックに話しています。その話についていけないメンバーは、端のほうに座っています。私も昔は平安時代の日記をやっていたのですが、もういいやと思っているので、隅っこのほうに座ります。そうすると、だいたい同じテーブルに池田先生、蘭先生、富田先生がいらっしゃる。そこでいろいろお話するようになったわけです。
そんな感じで、日文研の倉本さんの研究会つながりなのですが、お互い中核ではなく周辺、少し外れたところにいる者同士というつながりで、そう考えると、大変おもしろいご縁です。
ところで、私は都留文科大学で「ジェンダー研究」の講義を担当しているのですが、先ほど、佐々木先生とお話していて、先生が都留の方で、さらになんと都留市の谷村という町に嫁いだ私の叔母の菩提寺のご住職であることがわかり、本当にびっくりいたしました。人の縁(えにし)というものは実に不思議なものだと改めて感じております。
そんなご縁があって講演会に呼んでいただき、さて何をお話ししたらいいのだろうと悩みました。私は性社会・文化史という専門を名乗っております。日本におけるジェンダー&セクシャリティの歴史研究ということですが、もっぱら日本における性別越境、トランスジェンダーの研究をしております。お話をいただいたころに調べていたのは、昭和戦前期の大阪の女装男娼、つまり女装のセックスワーカーのことでした。それはいくら何でもあまりにもマニアックだろう、もう少し現代的なポピュラーな話題の方が興味をもっていただけるだろうと考えました。
そこで、こちらの研究所の総合テーマが「女性なるものと男性なるもの」とお聞きしていましたので、それでは、その間で行こう、女性なるものと男性なるものの境界領域をお話しようと、「『男の娘(おとこのこ)』なるもの」というテーマを思いつきました。ということで、今日は「男の娘」という最近の事象について、社会における性別認識という視点を絡めてお話することにいたします。
「男の娘(おとこのこ)」とは?
「男の娘」と書いて「おとこのこ」と読ませます。誰が考えたのかよくわからないのですが、なかなかしゃれたネーミングです。ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、なんのことやらわからないという方もいらっしゃると思います。その程度の社会的浸透度の新しい言葉です。
「男の娘」はまだ定義が固まっている言葉ではありません。いくつかご紹介しましょう。「まるで女の子のような男の子、女装している男性のこと」(『オトコの娘(こ)のための変身ガイド』)。「女の子のようにカワイイ女装少年のこと」(『わが輩は『男の娘』である!』)。あるいは、「二・五次元に生息する、(中略)女の子よりカワイイ男の子」(ニコニコ動画「男の娘ちゃんねる」)。二次元というのはいわゆる紙媒体、アニメの世界、そして三次元が現実世界ですから、二・五次元はその中間ということです。ウィキペディアは、「男性でありながら女性にしか見えない容姿と内面を持つ者」という定義です。これだと、それ以前の「女装」している人たちとの差違化が全くできていないので、あまりよろしくありません。
今、定義を四つ申しましたが、そのうちの二つに「カワイイ」という言葉が入っています。これが一つのキーワードだと思います。そこで、私なりの定義を示しますと「まるで女の子のようにカワイイ、女装した男の子」ということになります。
「男の娘」の出現
次に、「男の娘」というネーミングがいつ出てきたのかということをお話します。書籍でまず注目しておきたいのは、2007年9月に出た『オンナノコになりたい!』です。書名には「男の娘」とは入っていないのですが、帯の記述の中に「もっとかわいい男の娘になろう」と入っています。ただ帯は後からつけ替えられるので、少し不安があります。私の持っているのが第二刷で、初刷りではないので、余計に不安です。
書名に「男の娘」が入っているものとしては、2008年10月に女装普及委員会というところが出した『オトコの娘(こ)のための変身ガイド―カワイイは女の子だけのものじゃない―』(画像1)が最初だと思います。
E382AAE38388E382B3E381AEE5A898E381AEE3819FE38281E381AEEFBC882008E5B9B410E69C88EFBC89.jpg)
【画像1】
私は、2008年9月に『女装と日本人』という講談社現代新書を出しました。執筆は2007年です。その段階では、私の頭にはまだ「男の娘」という文字は入っていませんでした。ということは、「男の娘」というネーミングが社会の表面に浮上したのは、やはり2008年ではないか?と思います。
ところで、この『オトコの娘(こ)のための変身ガイド』という本は、男の子が女の子の格好をするためのテクニックやいろいろなアイテムに関して事細かに記している女装指南本です。こんな本が普通の書店で売られることすらびっくりしたのに、これ一冊だけで1万5000部以上、全4冊シリーズで6万部というかなりの売れ行きになったことも衝撃的でした。同時期に出た私の『女装と日本人』が1万部ぐらいしか売れないのに…、すごく悔しいです。
その後、2009年5月に『オトコノコ倶楽部』という女装美少年総合専門雑誌が三和出版から刊行されます。三和出版はもっぱら成人雑誌を出している出版社ですが、少し前まで『ニューハーフ倶楽部』(1995年3月~2007年8月)というニューハーフ(身体を女性化した男性、女装した男性であることをセールスポイントにした商業的なトランスジェンダー)をメインにした雑誌を出していました。私も連載コラムを2本持っていたのですが、コロッと宗旨替えして新しい流れに乗ったということです。このあたりまでくると、どうも様子がおかしいぞということに、私も気づいておりました。
その少し前、2008年の4月、私が銀座四丁目の「和光」の前におりましたら、背が高くてスタイルがいい振り袖のお嬢さんが、お母様らしき着物の女性と二人で、目の前を通過していったのです(画像2)。「あれ?」と思って、少し後をつけました。あれ?と思ったのは、スタイルが良すぎるというか、写真を見ればわかるように、少し袖で隠れていますが、お尻が小さいのです。つまり、女性ではないのではないか?ということを、直観的に感じたわけです。そこらへんの「目利き」は私のように女装業界に長くおりますと、自然と身についてきます。
E98A80E5BAA7E381AEE68CAFE3828AE8A296E3808CE5A898E3808DEFBC882008E5B9B44E69C88EFBC89.jpg)
【画像2】
後で、お話をうかがうと、やはり男性でした。左側の40歳ぐらいの女性が、右側の25歳ぐらいの男性に自分のお振り袖一式を着付けて、お化粧もしてあげて、銀座に連れ出したということでした。
そう言えば、少し前に新宿や渋谷で、「あれ、今の女の子の二人連れ、片一方は男の子じゃないかな?」と気づいたことが数回あったことを思い出しました。一見、女性の二人連れに見えるのですが、実は片方が女装した男の子というカップルです。そういう現象がひそかに増えていることに、私が気付いたのが、だいたい2008年の春ぐらいだったということです。たった4年前ぐらいのことです。
ちょうどその頃、今、京都造形芸術大学の成実弘至先生から、『コスプレする社会―サブカルチャーの身体文化』という本を一緒にやらないかというお話をいただきました。それで、『女装と日本人』に書いた後の女装世界の変化をフォローした「変容する女装文化」という論考を執筆しました。「男の娘」というネーミングは使いませんでしたが、後に「男の娘」とネーミングされるような若い女装者の意識の変化や、新しい現象として女性と女装した男性のカップルの話を取り上げたわけです。自画自賛になりますが、こうした女装文化の変化に真っ先に気づいて考察した論考が「変容する女装文化」ということになります。
マス・メディアへの登場
「変容する女装文化」を掲載した『コスプレする社会』は2009年6月に刊行されましたが、大手のメディアが「男の娘」現象に気づき始めたのは、その半年ほど後でした。12月に共同通信の記者から電話インタビューの依頼がありました。「おっ、やっと気付いたか」という感じでした。そのコメントが載ったのが、「きれいならOK?『女装男子』急増」という記事で(2009年12月22日配信)、こんな写真を載せていました(画像3)。秋葉原のメイドカフェで、メイドの格好をした女装の男の子が、本物の女性のお客さんに飲み物を運んでいる写真で、新しい現象のポイントをよく捉えています。つまり、後で詳しく申しますが、女装した男の子と女性との関係性です。
E794B7E381AEE5A8981-e63a3.jpg)
【画像3】
年末にはなんとNHKワールドからコメント出演の依頼がありました。NHKワールドは英語で世界百何十何カ国に放送している国際放送局ですが、NEWS LINEというニュース番組の中で現代日本の若者の女装文化を取り上げたいという話でした。私は驚いて「そんなことを取り上げて、世界に放送していいんですか」と問い返しました。そうしたら「実は、日本国内よりも外国で注目されているので、十分ニュース価値があるんです」というディレクターのお話でした。
年が明けた2010年の2月に「Boys Will Be Boys?」(少年は果たして男の子になるのでしょうか? もしかすると男の娘になっちゃうかもしれませんよ)という5分間ほどの特集で、現代日本の若者の一つのカルチャーとして「女装」する男の子現象が世界に紹介されました。DVDを持ってきましたので時間があったら、後でお見せします。
2010年8月には、共同通信がもっと本格的な「ニッポン解析:女装楽しむ『男の娘(こ)』」という記事を出しました(2010年8月25日配信)。銀座の街を歩いているのは二人とも「男の娘」です(画像4)。このような流れで、「男の娘」現象がマス・メディアで認知されたのは2010年ということになります。
E794B7E381AEE5A898EFBC93-168e0.jpg)
【画像4】
2011年11月には朝日新聞に、「『男の娘』(オトコノコ)になりたくて」という記事が出ました(2011年11月12日夕刊)。とうとう朝日新聞にまでと感慨深かったです。ついこの間、2012年5月には「男装大好き!」という題で、今度は女の子が男の子の格好をしているのが徐々にブーム化しているという記事が朝日新聞に載りました(2012年5月26日)。比べてみたら違う記者が書いているので、一人だけマニアックな記者がいるわけでもなさそうです。
男装のお話をする場がないので、ここでちょっとだけ触れておきますと、女性のファッションの範囲はとても広いので、極端に言えば、女性がどんな格好をしても、女性の幅広いファッション・カテゴリーの一部だと見なされてしまって、なかなか男装になりません。それこそ髭でもつけない限りは男装が成立しない、そういう意味で、男装の困難さがあるのです。朝日新聞の「男装大好き!」という記事の写真を見ますと、私からするとやはり女の子がボーイッシュなファッションをしているように見えてしまいます。ただし、本人たちは男装のつもりでやっている、そしてそこに「女子ファン増殖中」とあるように女の子が寄ってくる。男装女子がある種のアイドルとして、女の子にもてるという現象が社会の表面に出てきたというのは、なかなか興味深いことだと思います。
合わせて考えれば、コスチューム・プレイという感覚で、性別表現の転換が容易になっている。男女両方からの行き来がかなり自由になってきている。そして、そうした行為に対する評価が、以前のような「そんなことをするのは変態」というマイナスではなく、ある種のアイドル性を持った肯定的なプラス評価になってきている。そこが大きな変化、いちばん大事なポイントでだと思っています。
まとめますと、「男の娘」現象は、2008年ぐらいから社会の表面に浮上して、2010年にメディアに認知され、若者たちの間の異性装ブームは、現在進行中と言うことです。
「男の娘」の起源
もう少し掘り下げてみましょう。「男の娘」の定義のところで「二・五次元」云々という話が出てきましたが、「男の娘」の淵源は、二次元媒体、漫画、コミック、あるいはもっとローカルな、コミケ(コミック・マーケット。年二回開催される大規模な同人誌即売会)などで売られているコミック同人誌にあります。
確実なところでは、2006年9月に「男の娘 COS☆H」という名前の同人誌即売会が行われています。さらに、2000年の春頃、巨大インターネット掲示板で有名な「2ちゃんねる」の中で、「男の娘(おとこのこ)」という表現があったという話があります。ただこれは確認できていません。2000年代の前半、しかも早い時期に、マニアックな二次元媒体の中で「男の娘」というネーミングが生まれていたことは間違いなさそうです。
さらに、「男の娘」の元祖は、1980年代半ばにベストセラーになった江口寿史『ストップ ひばりくん!』の主人公大空ひばり(画像5)であるという説があります。『ストップ!! ひばりくん!』は、1981年~1983年の連載で、もう20年前の漫画です。私はリアルタイムで読んでいましたし、その世代の女装者には、やたらと「ひばり」という名前(女装名)の人が多くて、影響力があったことは間違いありません。しかし、これは「始祖伝説」のような話で、そういうふうに仮託されているということでして、日本最初の天皇は神武天皇というのと同様に歴史的事実として語れる話ではありません。
E382B9E38388E38383E38397E381B2E381B0E3828AE3818FE38293201-194cb.jpg)
【画像5】
「男の娘」の起源としていえることは、少なくとも2000年代の前半にコミック世界で女装した美しい男の子が「女装美少年」とか「化粧男子」とか、いろいろな名称で語られていて、それらのうちの一つが「男の娘」だったということです。
ところで、「娘」と書いて「こ」と読ませることですが、女装者を「女装娘」と書いて「じょそこ」と読ませることが、すでに1990年代前半の東京新宿の女装コミュニティで広く行われていました。その起源は1950年代に始まる男性同性愛者のコミュニティにおける女装する男性への侮蔑的な呼称である「女装子」にあります。男性同性愛者の世界は基本的に「男らしさ」を価値基準にする女性性嫌悪の強い世界ですから、「女らしい」人や女性の格好をする人は下位に位置づけられます。
ちなみに、なぜかゲイ業界では「〇〇子」という表現が好まれます。店で働いているゲイの人を「店子」と書いて「みせこ」と言います。「『店子』と書いたら普通は『たなこ』と読むのよ」などと言うと、「このばあさんは何を言っているんだ」と怪訝な顔をされるわけです。言葉としての「男の娘」、「娘」と書いて「こ」と読ませることには、そんな文化伝統があるわけです。
これまで述べたことをまとめますと、「男の娘」という言葉は、2000年代の前半、しかも早い時期に、マニアックなコミック世界で生まれ、最初はあくまでも二次元媒体の存在だったのが「コスプレ」などを通じて徐々に肉体を持った三次元キャラクターとして実体化していき、2008年ごろから社会の表面に現れてきて、2010年に「男の娘」現象としてマス・メディアの認知を得た、最初はある種のファッション・カテゴリーであったものが、ミニ流行化の中で次第にジェンダー・カテゴリーという感じになっていった、そんなところだと思います。
「男の娘」の実際
さて、二次元キャラクターの「男の娘」はいくらでも理想化が利きます。どんどん可愛く描けばいいわけです。ところが、三次元の「男の娘」はそうはいきません。皆さん、それなりに苦労しています。ここで、どんな「娘」がいるかちょっと見てみましょう。
この「娘」は、私の友人の吉野さやかさんです(画像6)。「彼女」に最初会った時、私ですらわかりませんでした。これはお友達の結婚パーティのときの写真を借りてきたのですが、本当に普通に女の子という感じで、こういう「娘」が現に存在しているのです。
E59089E9878EE38195E38284E3818B(2011E5B9B48E69C88)-2bd3c.jpg)
【画像6】
こちらの「娘」は、毎月、新宿歌舞伎町で「女装 ニューハーフプロパガンダ」というイベントを主催しているモカちゃんです(画像7)。彼女はイベントの主催者であると同時に、イベント最大のスターという存在です、この「娘」も、わかりませんでした。カワイイ女の子がいるなと思ったら「男の娘」で、びっくりでした。
E383A2E382AB20(2012E5B9B41E69C88)-19fc7.jpg)
【画像7】
これはテレビなどでときどき見かけるモデル兼タレントの佐藤かよさんです(画像8)。彼女は自分で「男の娘」とは名乗っていないと思いますが、世代的、容姿的、カワイイ系のファッションという点で、まさに最先端の「男の娘」だと思います。
E4BD90E897A4E3818BE38288(2011E5B9B4EFBC89-ca9d2.jpg)
【画像8】
こちらは、私の「娘分」的な存在の井上魅夜さんです(画像9)。以前は仲の良い後輩の女装者を「妹分」と言っていたのですが、もう無理です。どう考えても姉妹というより母と娘の年齢差ですから。この「娘」、身体的にまったく女の子サイズなので「男の娘」だとはまず気付かれません。黙っていればですが・・・。
E4BA95E4B88AE9AD85E5A49C.jpg)
【画像9】
2009年11月に、この井上魅夜さん主宰の「東京化粧男子宣言!」というイベントが行われました。早い話、化粧男子のミスコンです。これがそのポスターですが(画像10)、描いているのはいがらしゆみこさんという漫画家です。1970年代に「キャンディ・キャンディ」という大ヒット作がある方です。若い方はあまりなじみがないかもしれませんが……。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-2-d72ac.jpg)
【画像10】
では、なぜ、いがらし先生のような大家がポスターを描いてくださったのかといいますと、これは2010年12月に出た『わが輩は「男の娘」である!」という本です(画像11)。帯のところに、「こんな立派な『男の娘』になってくれて…… 母は嬉しいです!(実母・いがらしゆみこ)」と書いてあります。つまり、この本の著者いがらし奈波さんがいがらしゆみこ先生の息子さんなのです。
E794B7E381AEE5A898E381A7E38182E3828B(2010E5B9B412E69C88)-58968.jpg)
【画像11】
これは「東京化粧男子宣言!」のオープニングの写真です(画像12)。左側が主催者の井上魅夜さん、真ん中が審査員で「ニューハーフ女優」の月野姫さん、そして右側が司会のいがらし奈波さんです。つまり、司会の奈波さんの縁でいがらし先生にポスターを描いてくださったわけです。さらに、いがらし先生には審査委員長をお願いしました。審査員席で、私の隣がいがらし先生だったのですが、カワイイ「男の娘」になった息子さんの活躍を、本当にうれしそうに見ていました。まさに母親公認で、世の中つくづく変わったと実感したわけです。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-3-464b3.jpg)
【画像12】
さて、「東京化粧男子宣言!」の審査結果です。決勝進出の8人から審査員一致で(会場投票もトップ)グランプリに選ばれたのが、るるさんでした(画像13)。シャボン玉をふーっと吹くパフォーマンスで「男の娘」の最大のポイントである「カワイイ」を巧みに表現していました。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-5E584AAE58B9DE88085E3828BE3828B-8be4b.jpg)
【画像13】
これは優勝者を囲んだ審査員一同の写真です(画像14)。左からいがらし先生、グランプリのるるさん、月野姫さん、私です。全員女性のように見えますが、戸籍上の女性はいがらし先生だけという写真です。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-6E5AFA9E69FBBE593A1E381A8E584AAE58B9DE88085-9ca68.jpg)
【画像14】
るるさんにそっと「あなた、学生さんらしいけど、大学はどこ?」と聞いたら、「少し硬派なイメージがある、渋谷の……」という返事で、なんと私の後輩(笑)。またびっくりでした。要は、こんなかわいい「娘」がごく普通の男子大学生ということです。
「男の娘」を遡る
これが現代の状況です。しかし、こういうカワイイ女の子に見える男の子、「男の娘」的な存在が過去にいなかったかというと、そうでもありません。「男の娘」というネーミングは現代的なものですが、実態的に似たような「娘」が過去にも存在していました。そこで、次に「男の娘」的存在を過去に遡ってみましょう。
まず、1994年の浅草寺のほおずき市での写真です(画像15)。右側(私)は大貫録の姐さん風ですが、左側の岡野香菜さんは20代後半、当時江東区の亀戸にあったアマチュア女装クラブ「エリザベス会館」の若手スターです。
E9A086E5AD90EFBC881994E5B9B47E69C88EFBC89-1e0c5.jpg)
【画像15】
次は、20年ほど遡って1973年の中野のあるマンションのベランダで焼肉パーティをしている写真です(画像16)。写っているのは夢野すみれさんという女装秘密結社「富貴倶楽部」で若手ナンバーワンと呼ばれた方。大学を卒業して間もない20代前半だと思います。現在の「男の娘」と年齢的にはほとんど変わりありません。こういうカワイイ「娘」が1970年代にもいたのです。
E5A4A2E9878EE38199E381BFE3828CEFBC881973E5B9B4EFBC89-e03c4.jpg)
【画像16】
こちらは1969年、東京日比谷です(画像17)。お堀の石垣を背に大振袖で立つのは、佐々木涼子さんという方。実年齢は30代だと思いますが、やはり「富貴倶楽部」の有力メンバーで、振袖女装で有名だった方です。
E4BD90E38085E69CA8E6B6BCE5AD90EFBC881969E5B9B4EFBC89-10767.jpg)
【画像17】
次は、東京オリンピック直前の1964年6月の新宿駅東口駅前でのスナップです(画像18)。右側のお二人は少し年配、30代だと思います。左の横を向いている松葉ゆかりさんは、当時25歳で、今の「男の娘」と年齢的に変わりません。60年代の「富貴倶楽部」の若手花形で、私はこの方のロングインタビューを採ったことがあります。
E696B0E5AEBFE9A785E5898DE381AEE5A5B3E8A385E88085EFBC881964E5B9B46E69C88EFBC8920(2).jpg)
【画像18】
戦前に飛びます。横書きの文字が今と逆ですが、「これが男に見えますか」というキャッチコピーが入ったタブロイド判(夕刊フジの大きさ)の新聞号外です(『東京日日新聞』1937年3月31日特報)。写っているのは福島ゆみ子という24歳の人です(画像19)。風紀係の私服刑事が、銀座七丁目の資生堂の前で声をかけてきた女性を「密淫売」(無届売春)の容疑で逮捕して築地署に連行し取り調べたら、なんと女性ではなく女装の男性だったという事件を報じたものです。
E7A68FE5B3B6E38286E381BFEFBC881937E5B9B4EFBC8920(2)-0f5c0.jpg)
【画像19】
ちなみに、現在の売春防止法もそうですが、戦前の売春関係の法律も売春の行為主体を女性に限定していますので、男性だとわかった途端に罪状が消えてしまい、仕方なく(厳重説諭の上)釈放になります。ゆみ子さん、釈放になるので余裕でポーズを作っています。違う新聞の写真には「男なんて甘いわ」というセリフがついています。昭和戦前期には、非合法売春の容疑で捕まった女装男娼が何人か新聞報道されていますが、私が見る限り彼女がいちばんの美形です。
さらに時を遡りましょう。これは江戸時代中期、18世紀後半に活躍した鈴木春信(1725?~70)の作品です(画像20)。春信は錦絵の大成者として知られる浮世絵師で教科書にも出てくるとても有名な人です。前を歩いているのはもちろん男性で、後ろを歩いている華麗な大振袖、島田髷の人は、今の私たちの目には娘に見えますが、当時「陰間」と呼ばれた、芸能・飲食接客・セックスワークを職業にした女装の少年です。これから贔屓筋の座敷に出勤するところです。
E6B19FE688B8E69982E4BBA3E999B0E996931-fd07f.jpg)
【画像20】
こちらは、少し後の浮世絵師、北尾重政(1739~1820)の「東西南北美人」シリーズの「西方の美人 堺町」です(画像21)。江戸の東西南北の美人を2人ずつ描いた4枚のセットですが、残念ながら全部残っていないようです。確認できる「東方」は深川の芸者を描いていて、たぶん「北方」は吉原の遊女、「南方」は品川の飯盛女(実態は遊女)でしょう。どれもまちがいなく女性ですが問題はこの「西方」です。立ち姿が橘屋の三喜蔵、座っているのが天王寺屋の松之丞という子で、松之丞は江戸の町娘のあこがれだった黄八丈の振袖姿です。もうあらためて言うまでもないと思いますが、「西方の美人」は女性ではなく、女装の少年なのです。
E6B19FE688B8E69982E4BBA3E999B0E9969324-cdde8.jpg)
【画像21】
このようにさかのぼっていくと、「男の娘」的存在がぞろぞろと出てくるわけです。なぜ前近代の日本にそういう「娘」がたくさん出てくるのか、そこら辺のことは私の『女装と日本人』に詳しく書いてありますので、ご参照いただければ幸いです。
もう一息です。これは鎌倉時代末期に描かれた『石山寺縁起絵巻』です(画像22)。この子が着ている橙色の衣服、肩が割れていないので少年が着る水干ではなく、女性が着る袿(うちき)です。履物もけばけばしています。藺げげ(いげげ)という当時の若い女性の履き物です。後にお坊さんがいます。首が切れていますが…。この時代、僧侶は戒律で女性と行動を共にしてはいけません。お坊さんの連れが少女ではまずいのです。つまり、この子は女装の稚児です。きっと後ろにいる師匠のお坊さんが(性的にも)可愛がっている「娘」なのでしょう。
E98E8CE58089E69982E4BBA3E7A89AE585901-42089.jpg)
【画像22】
これで最後です(画像23)。私の話を何度も聞いてくださっている方は「またか」と思われるかもしれませんが、やはり行き着くところは女装の建国英雄・ヤマトタケルになってしまいます。これは三重県鈴鹿市の加佐登神社に奉納されている大きな絵馬です。ヤマトタケルは少女の姿になって九州の豪族クマソタケル兄弟の館に入り込み、その美少女ぶりで兄弟を魅了します。絵馬は長い垂れ髪に緋色の裳の女姿のヤマトタケルがクマソタケル兄弟をやっつける場面を描いています。ヤマトタケルの右手に握られた剣はすでに血にまみれていて。すでにクマソタケル兄の方を殺し、これから青い衣の髭面のクマソタケル弟を刺そうとするところです。ヤマトタケルはこのとき16歳。まさに元祖「男の娘」です。
E383A4E3839EE38388E382BFE382B1E383AB-5fd8c.jpg)
【画像23】
こうして歴史を遡ってみますと、「男の娘」的存在は日本の長い歴史の中に常に存在していたことがわかります。言葉を変えるならば、現在、ミニブームになっている「男の娘」も、男でもあり女でもある双性、ダブルジェンダー的な存在への強い嗜好に支えられた日本の性別越境文化の末裔であり、決して現代の特異現象ではないということです。メディアは新しいものが大好きなので、最新の社会現象だと騒ぎますが、実は根っこはずっと続いているのです。「男の娘」は、2000年の長い歴史を持つ日本の女装文化の21世紀リニューアルバージョンだと、私は理解をしています。
「男の娘」出現の背景
さて、再び現代の「男の娘」に戻って、もう少し深く考えてみましょう。まず「男の娘」がクローズアップされてきた背景です。1990年代後半から2000年代前半は、性別を越えて生きたいと考えることを「病」、精神疾患だと考える性同一性障害という概念が大流行した時代です。メディアの報道も性同一性障害一色でした。こうした性同一性障害の概念の大流行で、従来の女装世界、例えば女装スナックやバーを拠点に形成されている新宿の女装コミュニティは、長年培ってきた人的資源をごっそり奪われて大打撃を受けました。わかりやすく言えば、「女になりたい」と思う人は、それまではお店に来ていたのが、病院に行くようになってしまったわけです。
私は1995年から2001年まで6年間、新宿歌舞伎町の老舗の女装スナック「ジュネ」やニューハーフ・パブ「MISTY」でお手伝いホステス(ゲスト・スタッフ)をしていていました。ちょうど性同一性障害の概念が流行していった時期です。『女装と日本人』を書いた理由の一つは、性別を越えて生きることが精神疾患であるという病理化の思想が社会に蔓延してしまうと、ヤマトタケル以来連綿と続いてきた日本の女装文化は終わりになってしまう、ならば、こういう世界があったんだということをちゃんと調べて書き残そう、そう思って、1998年頃から歴史学や社会学の勉強をし直して学術的な女装文化の研究を始めたわけです。つまり、日本の女装文化の遺言を書くようなすごく悲観的な気持ちで書き始めたのですが、先ほど述べましたように、執筆しているうちにあれ、何か様子が変だぞ、流れが微妙に変わりつつあるぞ、という感じになったのです。
性同一性障害の概念には、医療によって身体の女性化を進めていくことを重視して、性別表現、ファッションや化粧というものを軽視する傾向があります。そのアンチテーゼとして、性別表現を重視した自己表現的な性別越境の形が復活してきた。「男の娘」現象の背景には、そうした性別越境をめぐる大きな流れの転換があると考えています。
メディアも、性同一性障害を10年間も報道すると、もう番組の作り方がなくなってきます。さらに言えば、重苦しさがつきまとう性同一性障害の報道にそろそろ嫌気が差していた。「また性同一性障害かよ、もうちょっと飽きてきたな」と思い始めていたところに、もっと楽しく気軽に性別を越えようという「男の娘」が浮上してきたわけです。メディアは、何度も言うように新しいものが大好きですから、そちらに飛びついた。そういうメディアの視点の転換も、「男の娘」がクローズアップされた背景にあったと思います。
ただし、性同一性障害概念の流布以前に戻ったわけではなく、「男の娘」たちの多くは1990年代まで主流だった新宿の女装コミュニティとは一線を画しています。そもそもエリアが違います。新宿ではなく秋葉原、中心が東京の東側へ動きました。「東京化粧男子宣言」の井上魅夜さんは、2011年12月に「若衆バー 化粧男子」という店を出したのですが、場所は新宿ではなく秋葉原の北の湯島でした。
もっとも、女装世界の中心は、新宿に移る前は上野や浅草でした。戦後最初の女装した女将さんがいるバーは「湯島」という名で、その名の通り湯島天神の男坂の下にありました。さらに言えば、江戸時代、女装の少年が接客する陰間茶屋の江戸における三大密集地の一つが湯島天神界隈でした。徳川将軍家の菩提寺である上野寛永寺のお坊さんが最大の客筋でした。そういう意味では、「男の娘」の拠点が秋葉原や湯島になったのは、先祖返りとも言えます。
「男の娘」の内実
次に「男の娘」の内実です。これはけっこう複雑で、趣味のコスチューム・プレイ(コスプレ)としてやっている女装者から、将来的には女性への性別越境を考えている、つまり戸籍まで女性に変えたいという子までかなり幅広いです。性同一性障害の診断書を持っている子も少なくありません。ですから、身体の女性化の程度も様々で、ほとんど何もしていない人もいれば、女性ホルモン継続の投与だけという人もいれば、外性器の手術(睾丸摘出手術や造膣手術)までしてしまっている人もいます。「男の娘」と言っても中身はいろいろなのです。
性的指向(セクシュアル・オリエンテーション)も一定ではありません。「女好き」、つまり、女の子の格好で女の子が好きという見かけ上レズビアンも多いですが、「男好き」(見かけヘテロセクシャル)もいます。バイセクシャルもいます。
1990年代後半から2000年代にかけては、女装あるいはトランスジェンダーというカテゴリーと、性同一性障害というカテゴリーの間に、かなり強烈な対立がありました。「あなたはどっちなの?」という感じ。ところが「男の娘」は、そうした対立、境界にこだわらない傾向があります。「そんなのどっちだっていいじゃないですか」という感じ。そうした概念へのこだわりのなさも新しいところです。つまり、「男の娘」の内実はかなり多様であり、良く言えばそうした幅広さ、悪く言えばとらえどころのなさ、無思想性が特色になっていると言えます。
「男の娘」出現の条件
次に、「男の娘」出現の条件です。なぜ「男の娘」が出てきたのですか?という質問はメディアの取材で必ず聞かれます。
第一に大きいのは情報流通の変化、具体的に言うとインターネットの普及です。インターネットの普及以前、女装やニューハーフの世界は、まさに閉ざされた世界でした。
先ほどお話した歌舞伎町の女装スナック「ジュネ」)の先輩で、200軒以上の飲み屋が集まっている新宿のゴールデン街を端から飲みまくって、10万円ぐらい飲んだところでやっと女装の店の情報に行き着いたという人がいます。1980年代後半、もう25年くらい前の話ですが、世の中にほとんど情報が回ってなく、伝手をたどってその種のお店を探すしかなかったわけです。どうやったら化粧ができるか、そういう情報もありません。女装やニューハーフの世界になんとかしてたどり着かないと、いくら女の子になりたくても始まりませんでした。
今は、インターネットでいくらでもお店の情報や女装テクニックが簡単に得られるようになりました。初めの方で紹介したように女装指南本が一般の本屋で売られている時代です。昔は女装の専門雑誌を買うのもけっこう大変で、どこに行けば売っているのか、なかなかわかりません。売っている場所に行っても、買うのにすごいドキドキでした。どうしても勇気が出なくて店の前を何度も往復してとうとう買えなかった、なんて話もあります。ともかく、ものすごく敷居が高い世界でした。それが今はもうまったく違います。
第二は男の子たちの顔や体形の変化です。私、今はすっかり太って丸顔ですが、若いころは1000人に1人の女顎、つまり三角顎だと言われたことがあったのですが、悔しいことに今、私レベルの三角顎の男の子はごろごろいます。そのくらい日本人の男性の顔立ちは変わってきています。フーテンの寅さん、渥美清さんのようなエラが張っているホームベース型の顔で、髭の剃り跡が青く見えるような男の子は本当に少なくなっています。顎のラインがすっきりした、髭もあまり濃くないような子が増えています。体形も手足が長く、骨格がずいぶん華奢になり、女物の9号の服が着られるような男の子が増加しています。つまり、男の子の顔立ちや体型が女装向きに変化してきています。昔に比べて「女の子になる」ベースに恵まれている男の子が多くなっているわけです。
第三に社会環境の変化があります。男の子が髪を長くのばしたり、眉を細く手入れしたり、髭や手足の体毛を脱毛していることが、それほど奇異に見られなくなっています。別に女の子になりたいわけでなくても、身体のメンテナンスに気を遣うおしゃれな男の子が増えていますから、そういう女装のための身体条件を整えることをしても、あまり目立ちません。
社会全体として性別の越境に対する許容度・自由度が以前に比べればだいぶ緩くなっています。コスチューム・プレイという感覚で、男性と女性の間を行って戻ってみたいなことがかなり自由になっている。社会環境として性別の越境、性別表現の転換が容易になっているということです。昔はそこに乗り越えなければならない高い壁のようなもの厳としてありましたったのが、私の世代だと、女装すること自体がものすごく大変で、そこに至るのに何年かかるという世界だったわけです。たとえば、私は振袖を着たいと思ってから実際に振袖姿で外へ出るまで20年近くかかっています。ところが最初に紹介した銀座の振袖「男の娘」は、2回目の女装でした。それほど違うのです。心理的な、もしくは社会的な、越えなければいけない障壁がとても低くなっています。
第四は、女性が男の子の女装を受け入れるようになったことです。女装した男性と一緒に遊ぶ、さらには積極的に女装に協力するような女性が確実に増えてきています。化粧にしてもファッション・コーディネートにしても、男の子が一から独力で覚えるのと、女性が協力してくれるのとでは、進度も到達レベルもまったく違います。こうした関係性の変化については、また後で詳しく述べます。
第五は、これがいちばん重要なことですが、価値観の変化です。昔は男が女の格好をする、女装することは、男性上位社会において明らかな社会的下降でした。よりによって「女『なんか』になる」という感じです。ですから、女装にはしばしばマゾヒズムが伴っていました。マゾヒズムについては、富田先生がここでお話になったと思うのですが、わざわざ女という低い身分になる、「あたし、とうとう女に墜ちちゃったわ」というような被虐的な陶酔にひたる女装者は少なくありませんでした。
ところが、今の「男の娘」たちはまったく違います。現代の男の子は同世代の女の子のライフスタイルに、かなり強いあこがれを持っています。男の子のライフスタイルは冴えないけれども、女の子たちはとても輝いている」。あくまでも見えるだけで、必ずしも実際はそうでないのですが、ともかく女の子ライフが素敵に見える。自分もああなりたいと思うわけです。つまり、「女になる」ということ下降ではなく、明らかに上昇志向なのです。より輝いているあこがれの女の子ライフに近づいていくという意識です。そこが、昔とまったく違います。
性別表現の転換に対する評価が、以前のような「そんなことをするのは変態」というマイナスではなく、ある種のアイドル性を持った肯定的なプラス評価になってきています。そこが大きな変化、大事なポイントだと思います。
今の若い女性の最大の価値観はカワイイです。カワイイものがいちばん価値がある。それに近づいていくための自己表現が「男の娘」になることなのです。だから、「男の娘」の世界では、カワイイことが基準化され重視されます。残念ながら誰でもカワイクなれるわけではないですから、そこに淘汰が生じます。カワイクない「男の娘」は女性に受け入れられません。
それと、年齢を重ねると、どうしてもカワイイが似合わなくなってきます。ですから、「男の娘」は年齢的な制約がとてもにきつい。当人たちに言わせると「10代から20代で20代が中心。アラサー(30歳前後)はもう辛いですね」ということになります。
従来の女装コミュニティでは、30代、40代が中核でした。これは、ある程度の経済的余力がないと、化粧品や服、さらにそれらの隠し場所である変身部屋(仕度部屋)にお金がかかる女装という遊びができなかったからです。20代だと独力では経済的に難しい、男性のお世話(援助)がないとそれなりのレベルの女装は無理でした。
男性主導から女性主導へ
男性のお世話になると言いましたが、伝統的な女装世界では、自分は女装しないけれど女装者が大好きな男性、私は「女装者愛好男性」名付けているのですが、そういう人たちが大きな役割を果たしていました。女装者愛好男性が若い女装者を「育てる」、経済的に援助することはしばしば行われていました。前に出てきた女装秘密結社「富貴倶楽部」はそうした援助がシステム化されたものと言えます。
援助の見返りとして女装者は、女装者愛好男性に性的に従属することが当然視されました。つまり、女装して女になることは男に抱かれるということと全く同義で、女装とセクシャリティが表裏一体でした。
それが徐々に変わっていきます。1979年創業のアマチュア女装クラブ「エリザベス会館」では女装者愛好男性を出入禁止にします。女性スタッフと女装者だけの空間で、セクシャリティを基本的に排除したのです。
私は1990年から4年半「エリザベス会館」に通って、本格的な女装の技術を習得し、その後、1995年から新宿歌舞伎町の女装ホステスになりました。今述べた歴史的な流れとは逆のコースだったので、女装者が女装者愛好男性に抱かれることが当然視されていることに驚きました。店で男性客に「ホテルに行こう」と誘われても、私は「嫌」と言うので、「あいつは生意気だ」とずいぶん言われたものです。
そうした女性と女装者の空間という形は、2000年代に登場してくる女性が経営するハイスペック、ハイレベルな、ただし費用も高い女装スタジオにも受け継がれます。これはそうした高級女装スタジオのひとつ、早乙女麗子さん主宰の「R’s(アールズ)」(曙橋から新宿御苑前に移転)の作品です(画像24)。モデルは前に出てきた吉野さやかさんですが、まったく男性らしさの欠片も感じられません。
E59089E9878EE38195E38284E3818BEFBC882009E5B9B4EFBC89-94b07.jpg)
【画像24】
先ほど本物の女の子と「男の娘」とが一緒に遊ぶと言いましたが、この写真がそれです(画像25)。やはり早乙女さんの作品ですが、一見、どっちがどっちだかわかりません。右側がSakiさんという「男の娘」で、左側が生まれつき本物の女の子です。こういう形で「男の娘」と女の子が仲よく一緒に遊んでいる世界になると、もう女装者愛好男性が入り込む余地はありません。
Saki26E7B494E5A5B3-c34db.jpg)
【画像25】
これは「東京化粧男子宣言」ポスターですが、このシルエット画像がなかなか象徴的です。左のお化粧されているのが男の子で、右のメーキャップしているのが女性です(画像26)。先ほど言い忘れましたが、「東京化粧男子宣言」は、モデルの男の子と、ファッション・コーディネート&メイク担当の女の子が男女ペアで競うコンセプトのコンテストです。このシルエット画像は、現在の女装が、かっての男性主導から女性主導へと変わってきていることをよく示しています。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A8802009-1-2714c.jpg)
【画像26】
そうなると評価の基準も変わってきます。以前の男性目線の評価だと、きれい、色っぽい、おとなしい(従順)が評価基準でした。どれだけ男性の性欲をそそるかが価値基準だったわけです。それが同世代の女性目線の評価になるとカワイイが絶対的な価値基準です。女の子にカワイイと承認されるかどうかが、「男の娘」の最大のポイントになる、そういう世界です。
こうした変化の背景には、2000年代においてさまざまな分野で女性の社会的進出が進み、社会の中で女性の嗜好が重視されるようになり、相対的に男性の影響力が減少したことがあるのだろうと思います。
性別認識をめぐって
さて、そろそろ与えられた時間が尽きそうです。最後に「男の娘」をめぐる性別認識についてお話します。
湯島の「若衆バー 化粧男子」でこんなことがありました。ある「男の娘」、なかなかカワイイ子なのですが、店に入ってくるなり「今日ここに来る前に、男の人に声かけられて、ナンパだったんですよぉ。ああ、キモ!(気持ち悪い)」と言っています。そこで私が「それはあなた、どう見ても女の子なんだから、男の人が寄ってくるのは当然でしょう」と言ったら、「でも、自分、男ですよ」と(笑)。
どう見ても女の子に見える「娘」が、「えー、でも自分、男ですよ」と言っている。この「男の娘」の性自認(ジェンダー・アイデンティティ)は、女性ではなく男性で、しかも性的指向(セクシュアル・オリエンテーション)は男性には向いていないということです。私は他者から与えられる性別認識を、性自認に対して「性他認」と言っています。たぶん私の造語だと思うのですが…。この「男の娘」の場合、性自認は男性だけど性他認は女性で両者が一致していません。それで男性にナンパされるという性的指向に沿わない不快な経験をしてしまったということです。
ところで、性同一性障害の世界では、これと逆の現象がしばしば見られます。MtF(Male to Female 男から女へ)の方で、性自認が女性で「私は女なんです」と主張しているのに、周囲から「あなた、女に見えないよ」と言われてしまうケースが問題になっています。性自認は女性なのに、性他認は男性という不一致です。
つまり、「男の娘」の世界と性同一性障害の世界でパターンは逆ですが、同じような性自認と性他認の不一致による混乱が起こっているということです。「男の娘」の方は遊びの要素が強いですから笑って済ませられますが、性同一性障害の方のパターンは、社会生活にいろいろ支障をきたし、よほど深刻です。性自認が女性であるにもかかわらず女性の性他認が得られないのは、女性としての性別表現が不十分なことに原因があることが多いので、私は機会があるとそういう方たちのために、女性的なしぐさや歩き方のレッスンをしていますが、男性としての生活が長かった中高年の性同一性障害の方の場合、なかなか大変なのが実際です。
それはともかく、現代の日本では、男に見えるから男、女に見えるから女というふうに、もう単純に言えなくなってきているということです。「男なるもの」と「女なるもの」の境界がかなりぼやけてきて、境界領域が幅広くなっている。社会の中で自明と思われていた性別認識が、実はかなり揺らいできているということ、それが大事なポイントではないかと思うわけです。
「男の娘」の可能性
最後に「男の娘」の可能性です。「男の娘」というネーミングがいつまで続くかわからないので、「男の娘」を含むトランスジェンダーの可能性ということになると思いますが、21世紀の日本におけるの「男なるもの」と「女なるもの」の境界に位置するサード・ジェンダー的存在として、世の中には男と女しかいないのだという性別二元制、あるいは体が男なら男、体が女なら女というような身体構造を絶対視する性別決定論、さらには。男なら女が好き、女なら男が好き、そうでなければいけないというような異性愛絶対主義などを揺るがしていく存在になる、そんな可能性、期待感を持っています。
話し始めて1時間たちましたので時間切れですが、せっかくなので最後にNHKワールドの「(NEWS LINE)Boys Will Be Boys?」をご覧いただきましょう。
(5分間ほど番組視聴)
なにやら怪しい着物の先生が今日お話したようなことをコメントしていましたが、番組の後半は、早稲田大学の男子学生さんが卒業記念に横浜の「アルテミス」という高級女装スタジオに行ってドレスアップした卒業記念写真を撮るという話です。私、この番組の収録の時に、その早稲田の学生さんに「あなた、素顔を出しちゃって大丈夫なの?」と尋ねました。彼はある地方の公務員に採用が決まっていると聞いていましたので、昔ならこんな形で番組に出てしまったら採用取り消しになりかねません。それで、心配して「(素顔に)モザイクかけなくていいの?」と言ったわけです。そうしたら「私、面接のときに『趣味は女装です』と言って合格していますから、問題ありません」という返事でした。ここでも、世の中つくづく変わったなと思ったわけです。
今日は、日本の長いトランスジェンダーの歴史の中の、いちばん新しい現象である「男の娘」についてお話しました。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
【追記・「男の娘」をめぐるその後の動向】
2012年11月20日、男の娘を主人公にした映画『僕の中のオトコの娘』(窪田將治監督、12月1日公開)公開記念イベント「オトコの娘サミット2012」が開催された(東京新宿歌舞伎町「ロフトプラスワン」)。
.jpg)
年が明けた2013年2月17日には『毎日新聞』が「S ストーリー」という企画記事で「月一度『封印』を解くー女子化する男たちー」(鈴木敦子記者)と題して社会的視点から「男の娘」問題を1面の一部と4面の全部を使って大きく取り上げた(http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2013-02-18)。
【参考文献】
三橋順子「現代日本のトランスジェンダー世界 -東京新宿の女装コミュニティを中心に-」
三橋順子「『女装者』概念の成立」
三橋順子「女装者愛好男性という存在」
(以上、矢島正見編著『戦後日本女装・同性愛研究』中央大学出版部 2006年)
三橋順子「往還するジェンダーと身体-トランスジェンダーを生きる-」
(鷲田清一編『身体をめぐるレッスン 1 夢みる身体 Fantasy』 岩波書店 2006年)
三橋順子『女装と日本人』(講談社現代新書 2008年)
三橋順子「変容する女装文化 -異性装と自己表現-」
(成実弘至編著『コスプレする社会 -サブカルチャーの身体文化-』せりか書房 2009年)
三橋順子「異性装と身体意識 -女装と女体化の間-」
(武田佐知子編『着衣する身体と女性の周縁化』思文閣出版 2012年)
.jpg)
---------------------------------------
平成24年(2012)度(駒沢女子大学)日本文化研究所主催講演会 2012年6月15日
「男の娘(おとこのこ)」なるもの
―その今と昔・性別認識を考える―
三橋 順子(性社会・文化史研究者 都留文科大学・明治大学非常勤講師)
皆さん、こんにちは。三橋でございます。このたびは私のような者をお招きいただき、大変うれしく思っております。自己紹介するとそれだけで持ち時間が終わってしまうようなややこしい人間なので、今、所長先生からお話がありましたように、適当に中に折り込んでいこうと思います。
最初にこちらにご縁をいただきましたことを少しお話ししておきます。以前、駒沢女子大学にいらした日本古代史の倉本一宏さんが京都の国際日本文化研究センターに着任をされました。私はもう10年ほど前から井上章一さんという建築史・風俗史の先生が主宰する「性欲の文化史」「性欲の社会史」の共同研究のメンバー(共同研究員)として年に5~6回、京都へ通っていました。
日文研は共同研究を重視する組織で専任の先生は他の先生の共同研究会にもいくつか出ないといけないというルールがあります。それで井上さんが倉本さんの研究会に出ることになりました。倉本さんが主宰されているのは主に平安、鎌倉の貴族の日記、そこから広げた日記の総合的研究という研究会です。井上さんが「僕、貴族の日記なんて読めないし、わからない。少しサポートしてもらえませんか」ということで、井上さんのお伴で私も倉本さんの研究会の共同研究員になりました。
その懇親会のときに、研究会の中核のメンバーの方たちは、日記のことばかりマニアックに話しています。その話についていけないメンバーは、端のほうに座っています。私も昔は平安時代の日記をやっていたのですが、もういいやと思っているので、隅っこのほうに座ります。そうすると、だいたい同じテーブルに池田先生、蘭先生、富田先生がいらっしゃる。そこでいろいろお話するようになったわけです。
そんな感じで、日文研の倉本さんの研究会つながりなのですが、お互い中核ではなく周辺、少し外れたところにいる者同士というつながりで、そう考えると、大変おもしろいご縁です。
ところで、私は都留文科大学で「ジェンダー研究」の講義を担当しているのですが、先ほど、佐々木先生とお話していて、先生が都留の方で、さらになんと都留市の谷村という町に嫁いだ私の叔母の菩提寺のご住職であることがわかり、本当にびっくりいたしました。人の縁(えにし)というものは実に不思議なものだと改めて感じております。
そんなご縁があって講演会に呼んでいただき、さて何をお話ししたらいいのだろうと悩みました。私は性社会・文化史という専門を名乗っております。日本におけるジェンダー&セクシャリティの歴史研究ということですが、もっぱら日本における性別越境、トランスジェンダーの研究をしております。お話をいただいたころに調べていたのは、昭和戦前期の大阪の女装男娼、つまり女装のセックスワーカーのことでした。それはいくら何でもあまりにもマニアックだろう、もう少し現代的なポピュラーな話題の方が興味をもっていただけるだろうと考えました。
そこで、こちらの研究所の総合テーマが「女性なるものと男性なるもの」とお聞きしていましたので、それでは、その間で行こう、女性なるものと男性なるものの境界領域をお話しようと、「『男の娘(おとこのこ)』なるもの」というテーマを思いつきました。ということで、今日は「男の娘」という最近の事象について、社会における性別認識という視点を絡めてお話することにいたします。
「男の娘(おとこのこ)」とは?
「男の娘」と書いて「おとこのこ」と読ませます。誰が考えたのかよくわからないのですが、なかなかしゃれたネーミングです。ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、なんのことやらわからないという方もいらっしゃると思います。その程度の社会的浸透度の新しい言葉です。
「男の娘」はまだ定義が固まっている言葉ではありません。いくつかご紹介しましょう。「まるで女の子のような男の子、女装している男性のこと」(『オトコの娘(こ)のための変身ガイド』)。「女の子のようにカワイイ女装少年のこと」(『わが輩は『男の娘』である!』)。あるいは、「二・五次元に生息する、(中略)女の子よりカワイイ男の子」(ニコニコ動画「男の娘ちゃんねる」)。二次元というのはいわゆる紙媒体、アニメの世界、そして三次元が現実世界ですから、二・五次元はその中間ということです。ウィキペディアは、「男性でありながら女性にしか見えない容姿と内面を持つ者」という定義です。これだと、それ以前の「女装」している人たちとの差違化が全くできていないので、あまりよろしくありません。
今、定義を四つ申しましたが、そのうちの二つに「カワイイ」という言葉が入っています。これが一つのキーワードだと思います。そこで、私なりの定義を示しますと「まるで女の子のようにカワイイ、女装した男の子」ということになります。
「男の娘」の出現
次に、「男の娘」というネーミングがいつ出てきたのかということをお話します。書籍でまず注目しておきたいのは、2007年9月に出た『オンナノコになりたい!』です。書名には「男の娘」とは入っていないのですが、帯の記述の中に「もっとかわいい男の娘になろう」と入っています。ただ帯は後からつけ替えられるので、少し不安があります。私の持っているのが第二刷で、初刷りではないので、余計に不安です。
書名に「男の娘」が入っているものとしては、2008年10月に女装普及委員会というところが出した『オトコの娘(こ)のための変身ガイド―カワイイは女の子だけのものじゃない―』(画像1)が最初だと思います。
E382AAE38388E382B3E381AEE5A898E381AEE3819FE38281E381AEEFBC882008E5B9B410E69C88EFBC89.jpg)
【画像1】
私は、2008年9月に『女装と日本人』という講談社現代新書を出しました。執筆は2007年です。その段階では、私の頭にはまだ「男の娘」という文字は入っていませんでした。ということは、「男の娘」というネーミングが社会の表面に浮上したのは、やはり2008年ではないか?と思います。
ところで、この『オトコの娘(こ)のための変身ガイド』という本は、男の子が女の子の格好をするためのテクニックやいろいろなアイテムに関して事細かに記している女装指南本です。こんな本が普通の書店で売られることすらびっくりしたのに、これ一冊だけで1万5000部以上、全4冊シリーズで6万部というかなりの売れ行きになったことも衝撃的でした。同時期に出た私の『女装と日本人』が1万部ぐらいしか売れないのに…、すごく悔しいです。
その後、2009年5月に『オトコノコ倶楽部』という女装美少年総合専門雑誌が三和出版から刊行されます。三和出版はもっぱら成人雑誌を出している出版社ですが、少し前まで『ニューハーフ倶楽部』(1995年3月~2007年8月)というニューハーフ(身体を女性化した男性、女装した男性であることをセールスポイントにした商業的なトランスジェンダー)をメインにした雑誌を出していました。私も連載コラムを2本持っていたのですが、コロッと宗旨替えして新しい流れに乗ったということです。このあたりまでくると、どうも様子がおかしいぞということに、私も気づいておりました。
その少し前、2008年の4月、私が銀座四丁目の「和光」の前におりましたら、背が高くてスタイルがいい振り袖のお嬢さんが、お母様らしき着物の女性と二人で、目の前を通過していったのです(画像2)。「あれ?」と思って、少し後をつけました。あれ?と思ったのは、スタイルが良すぎるというか、写真を見ればわかるように、少し袖で隠れていますが、お尻が小さいのです。つまり、女性ではないのではないか?ということを、直観的に感じたわけです。そこらへんの「目利き」は私のように女装業界に長くおりますと、自然と身についてきます。
E98A80E5BAA7E381AEE68CAFE3828AE8A296E3808CE5A898E3808DEFBC882008E5B9B44E69C88EFBC89.jpg)
【画像2】
後で、お話をうかがうと、やはり男性でした。左側の40歳ぐらいの女性が、右側の25歳ぐらいの男性に自分のお振り袖一式を着付けて、お化粧もしてあげて、銀座に連れ出したということでした。
そう言えば、少し前に新宿や渋谷で、「あれ、今の女の子の二人連れ、片一方は男の子じゃないかな?」と気づいたことが数回あったことを思い出しました。一見、女性の二人連れに見えるのですが、実は片方が女装した男の子というカップルです。そういう現象がひそかに増えていることに、私が気付いたのが、だいたい2008年の春ぐらいだったということです。たった4年前ぐらいのことです。
ちょうどその頃、今、京都造形芸術大学の成実弘至先生から、『コスプレする社会―サブカルチャーの身体文化』という本を一緒にやらないかというお話をいただきました。それで、『女装と日本人』に書いた後の女装世界の変化をフォローした「変容する女装文化」という論考を執筆しました。「男の娘」というネーミングは使いませんでしたが、後に「男の娘」とネーミングされるような若い女装者の意識の変化や、新しい現象として女性と女装した男性のカップルの話を取り上げたわけです。自画自賛になりますが、こうした女装文化の変化に真っ先に気づいて考察した論考が「変容する女装文化」ということになります。
マス・メディアへの登場
「変容する女装文化」を掲載した『コスプレする社会』は2009年6月に刊行されましたが、大手のメディアが「男の娘」現象に気づき始めたのは、その半年ほど後でした。12月に共同通信の記者から電話インタビューの依頼がありました。「おっ、やっと気付いたか」という感じでした。そのコメントが載ったのが、「きれいならOK?『女装男子』急増」という記事で(2009年12月22日配信)、こんな写真を載せていました(画像3)。秋葉原のメイドカフェで、メイドの格好をした女装の男の子が、本物の女性のお客さんに飲み物を運んでいる写真で、新しい現象のポイントをよく捉えています。つまり、後で詳しく申しますが、女装した男の子と女性との関係性です。
E794B7E381AEE5A8981-e63a3.jpg)
【画像3】
年末にはなんとNHKワールドからコメント出演の依頼がありました。NHKワールドは英語で世界百何十何カ国に放送している国際放送局ですが、NEWS LINEというニュース番組の中で現代日本の若者の女装文化を取り上げたいという話でした。私は驚いて「そんなことを取り上げて、世界に放送していいんですか」と問い返しました。そうしたら「実は、日本国内よりも外国で注目されているので、十分ニュース価値があるんです」というディレクターのお話でした。
年が明けた2010年の2月に「Boys Will Be Boys?」(少年は果たして男の子になるのでしょうか? もしかすると男の娘になっちゃうかもしれませんよ)という5分間ほどの特集で、現代日本の若者の一つのカルチャーとして「女装」する男の子現象が世界に紹介されました。DVDを持ってきましたので時間があったら、後でお見せします。
2010年8月には、共同通信がもっと本格的な「ニッポン解析:女装楽しむ『男の娘(こ)』」という記事を出しました(2010年8月25日配信)。銀座の街を歩いているのは二人とも「男の娘」です(画像4)。このような流れで、「男の娘」現象がマス・メディアで認知されたのは2010年ということになります。
E794B7E381AEE5A898EFBC93-168e0.jpg)
【画像4】
2011年11月には朝日新聞に、「『男の娘』(オトコノコ)になりたくて」という記事が出ました(2011年11月12日夕刊)。とうとう朝日新聞にまでと感慨深かったです。ついこの間、2012年5月には「男装大好き!」という題で、今度は女の子が男の子の格好をしているのが徐々にブーム化しているという記事が朝日新聞に載りました(2012年5月26日)。比べてみたら違う記者が書いているので、一人だけマニアックな記者がいるわけでもなさそうです。
男装のお話をする場がないので、ここでちょっとだけ触れておきますと、女性のファッションの範囲はとても広いので、極端に言えば、女性がどんな格好をしても、女性の幅広いファッション・カテゴリーの一部だと見なされてしまって、なかなか男装になりません。それこそ髭でもつけない限りは男装が成立しない、そういう意味で、男装の困難さがあるのです。朝日新聞の「男装大好き!」という記事の写真を見ますと、私からするとやはり女の子がボーイッシュなファッションをしているように見えてしまいます。ただし、本人たちは男装のつもりでやっている、そしてそこに「女子ファン増殖中」とあるように女の子が寄ってくる。男装女子がある種のアイドルとして、女の子にもてるという現象が社会の表面に出てきたというのは、なかなか興味深いことだと思います。
合わせて考えれば、コスチューム・プレイという感覚で、性別表現の転換が容易になっている。男女両方からの行き来がかなり自由になってきている。そして、そうした行為に対する評価が、以前のような「そんなことをするのは変態」というマイナスではなく、ある種のアイドル性を持った肯定的なプラス評価になってきている。そこが大きな変化、いちばん大事なポイントでだと思っています。
まとめますと、「男の娘」現象は、2008年ぐらいから社会の表面に浮上して、2010年にメディアに認知され、若者たちの間の異性装ブームは、現在進行中と言うことです。
「男の娘」の起源
もう少し掘り下げてみましょう。「男の娘」の定義のところで「二・五次元」云々という話が出てきましたが、「男の娘」の淵源は、二次元媒体、漫画、コミック、あるいはもっとローカルな、コミケ(コミック・マーケット。年二回開催される大規模な同人誌即売会)などで売られているコミック同人誌にあります。
確実なところでは、2006年9月に「男の娘 COS☆H」という名前の同人誌即売会が行われています。さらに、2000年の春頃、巨大インターネット掲示板で有名な「2ちゃんねる」の中で、「男の娘(おとこのこ)」という表現があったという話があります。ただこれは確認できていません。2000年代の前半、しかも早い時期に、マニアックな二次元媒体の中で「男の娘」というネーミングが生まれていたことは間違いなさそうです。
さらに、「男の娘」の元祖は、1980年代半ばにベストセラーになった江口寿史『ストップ ひばりくん!』の主人公大空ひばり(画像5)であるという説があります。『ストップ!! ひばりくん!』は、1981年~1983年の連載で、もう20年前の漫画です。私はリアルタイムで読んでいましたし、その世代の女装者には、やたらと「ひばり」という名前(女装名)の人が多くて、影響力があったことは間違いありません。しかし、これは「始祖伝説」のような話で、そういうふうに仮託されているということでして、日本最初の天皇は神武天皇というのと同様に歴史的事実として語れる話ではありません。
E382B9E38388E38383E38397E381B2E381B0E3828AE3818FE38293201-194cb.jpg)
【画像5】
「男の娘」の起源としていえることは、少なくとも2000年代の前半にコミック世界で女装した美しい男の子が「女装美少年」とか「化粧男子」とか、いろいろな名称で語られていて、それらのうちの一つが「男の娘」だったということです。
ところで、「娘」と書いて「こ」と読ませることですが、女装者を「女装娘」と書いて「じょそこ」と読ませることが、すでに1990年代前半の東京新宿の女装コミュニティで広く行われていました。その起源は1950年代に始まる男性同性愛者のコミュニティにおける女装する男性への侮蔑的な呼称である「女装子」にあります。男性同性愛者の世界は基本的に「男らしさ」を価値基準にする女性性嫌悪の強い世界ですから、「女らしい」人や女性の格好をする人は下位に位置づけられます。
ちなみに、なぜかゲイ業界では「〇〇子」という表現が好まれます。店で働いているゲイの人を「店子」と書いて「みせこ」と言います。「『店子』と書いたら普通は『たなこ』と読むのよ」などと言うと、「このばあさんは何を言っているんだ」と怪訝な顔をされるわけです。言葉としての「男の娘」、「娘」と書いて「こ」と読ませることには、そんな文化伝統があるわけです。
これまで述べたことをまとめますと、「男の娘」という言葉は、2000年代の前半、しかも早い時期に、マニアックなコミック世界で生まれ、最初はあくまでも二次元媒体の存在だったのが「コスプレ」などを通じて徐々に肉体を持った三次元キャラクターとして実体化していき、2008年ごろから社会の表面に現れてきて、2010年に「男の娘」現象としてマス・メディアの認知を得た、最初はある種のファッション・カテゴリーであったものが、ミニ流行化の中で次第にジェンダー・カテゴリーという感じになっていった、そんなところだと思います。
「男の娘」の実際
さて、二次元キャラクターの「男の娘」はいくらでも理想化が利きます。どんどん可愛く描けばいいわけです。ところが、三次元の「男の娘」はそうはいきません。皆さん、それなりに苦労しています。ここで、どんな「娘」がいるかちょっと見てみましょう。
この「娘」は、私の友人の吉野さやかさんです(画像6)。「彼女」に最初会った時、私ですらわかりませんでした。これはお友達の結婚パーティのときの写真を借りてきたのですが、本当に普通に女の子という感じで、こういう「娘」が現に存在しているのです。
E59089E9878EE38195E38284E3818B(2011E5B9B48E69C88)-2bd3c.jpg)
【画像6】
こちらの「娘」は、毎月、新宿歌舞伎町で「女装 ニューハーフプロパガンダ」というイベントを主催しているモカちゃんです(画像7)。彼女はイベントの主催者であると同時に、イベント最大のスターという存在です、この「娘」も、わかりませんでした。カワイイ女の子がいるなと思ったら「男の娘」で、びっくりでした。
E383A2E382AB20(2012E5B9B41E69C88)-19fc7.jpg)
【画像7】
これはテレビなどでときどき見かけるモデル兼タレントの佐藤かよさんです(画像8)。彼女は自分で「男の娘」とは名乗っていないと思いますが、世代的、容姿的、カワイイ系のファッションという点で、まさに最先端の「男の娘」だと思います。
E4BD90E897A4E3818BE38288(2011E5B9B4EFBC89-ca9d2.jpg)
【画像8】
こちらは、私の「娘分」的な存在の井上魅夜さんです(画像9)。以前は仲の良い後輩の女装者を「妹分」と言っていたのですが、もう無理です。どう考えても姉妹というより母と娘の年齢差ですから。この「娘」、身体的にまったく女の子サイズなので「男の娘」だとはまず気付かれません。黙っていればですが・・・。
E4BA95E4B88AE9AD85E5A49C.jpg)
【画像9】
2009年11月に、この井上魅夜さん主宰の「東京化粧男子宣言!」というイベントが行われました。早い話、化粧男子のミスコンです。これがそのポスターですが(画像10)、描いているのはいがらしゆみこさんという漫画家です。1970年代に「キャンディ・キャンディ」という大ヒット作がある方です。若い方はあまりなじみがないかもしれませんが……。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-2-d72ac.jpg)
【画像10】
では、なぜ、いがらし先生のような大家がポスターを描いてくださったのかといいますと、これは2010年12月に出た『わが輩は「男の娘」である!」という本です(画像11)。帯のところに、「こんな立派な『男の娘』になってくれて…… 母は嬉しいです!(実母・いがらしゆみこ)」と書いてあります。つまり、この本の著者いがらし奈波さんがいがらしゆみこ先生の息子さんなのです。
E794B7E381AEE5A898E381A7E38182E3828B(2010E5B9B412E69C88)-58968.jpg)
【画像11】
これは「東京化粧男子宣言!」のオープニングの写真です(画像12)。左側が主催者の井上魅夜さん、真ん中が審査員で「ニューハーフ女優」の月野姫さん、そして右側が司会のいがらし奈波さんです。つまり、司会の奈波さんの縁でいがらし先生にポスターを描いてくださったわけです。さらに、いがらし先生には審査委員長をお願いしました。審査員席で、私の隣がいがらし先生だったのですが、カワイイ「男の娘」になった息子さんの活躍を、本当にうれしそうに見ていました。まさに母親公認で、世の中つくづく変わったと実感したわけです。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-3-464b3.jpg)
【画像12】
さて、「東京化粧男子宣言!」の審査結果です。決勝進出の8人から審査員一致で(会場投票もトップ)グランプリに選ばれたのが、るるさんでした(画像13)。シャボン玉をふーっと吹くパフォーマンスで「男の娘」の最大のポイントである「カワイイ」を巧みに表現していました。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-5E584AAE58B9DE88085E3828BE3828B-8be4b.jpg)
【画像13】
これは優勝者を囲んだ審査員一同の写真です(画像14)。左からいがらし先生、グランプリのるるさん、月野姫さん、私です。全員女性のように見えますが、戸籍上の女性はいがらし先生だけという写真です。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A880200920-6E5AFA9E69FBBE593A1E381A8E584AAE58B9DE88085-9ca68.jpg)
【画像14】
るるさんにそっと「あなた、学生さんらしいけど、大学はどこ?」と聞いたら、「少し硬派なイメージがある、渋谷の……」という返事で、なんと私の後輩(笑)。またびっくりでした。要は、こんなかわいい「娘」がごく普通の男子大学生ということです。
「男の娘」を遡る
これが現代の状況です。しかし、こういうカワイイ女の子に見える男の子、「男の娘」的な存在が過去にいなかったかというと、そうでもありません。「男の娘」というネーミングは現代的なものですが、実態的に似たような「娘」が過去にも存在していました。そこで、次に「男の娘」的存在を過去に遡ってみましょう。
まず、1994年の浅草寺のほおずき市での写真です(画像15)。右側(私)は大貫録の姐さん風ですが、左側の岡野香菜さんは20代後半、当時江東区の亀戸にあったアマチュア女装クラブ「エリザベス会館」の若手スターです。
E9A086E5AD90EFBC881994E5B9B47E69C88EFBC89-1e0c5.jpg)
【画像15】
次は、20年ほど遡って1973年の中野のあるマンションのベランダで焼肉パーティをしている写真です(画像16)。写っているのは夢野すみれさんという女装秘密結社「富貴倶楽部」で若手ナンバーワンと呼ばれた方。大学を卒業して間もない20代前半だと思います。現在の「男の娘」と年齢的にはほとんど変わりありません。こういうカワイイ「娘」が1970年代にもいたのです。
E5A4A2E9878EE38199E381BFE3828CEFBC881973E5B9B4EFBC89-e03c4.jpg)
【画像16】
こちらは1969年、東京日比谷です(画像17)。お堀の石垣を背に大振袖で立つのは、佐々木涼子さんという方。実年齢は30代だと思いますが、やはり「富貴倶楽部」の有力メンバーで、振袖女装で有名だった方です。
E4BD90E38085E69CA8E6B6BCE5AD90EFBC881969E5B9B4EFBC89-10767.jpg)
【画像17】
次は、東京オリンピック直前の1964年6月の新宿駅東口駅前でのスナップです(画像18)。右側のお二人は少し年配、30代だと思います。左の横を向いている松葉ゆかりさんは、当時25歳で、今の「男の娘」と年齢的に変わりません。60年代の「富貴倶楽部」の若手花形で、私はこの方のロングインタビューを採ったことがあります。
E696B0E5AEBFE9A785E5898DE381AEE5A5B3E8A385E88085EFBC881964E5B9B46E69C88EFBC8920(2).jpg)
【画像18】
戦前に飛びます。横書きの文字が今と逆ですが、「これが男に見えますか」というキャッチコピーが入ったタブロイド判(夕刊フジの大きさ)の新聞号外です(『東京日日新聞』1937年3月31日特報)。写っているのは福島ゆみ子という24歳の人です(画像19)。風紀係の私服刑事が、銀座七丁目の資生堂の前で声をかけてきた女性を「密淫売」(無届売春)の容疑で逮捕して築地署に連行し取り調べたら、なんと女性ではなく女装の男性だったという事件を報じたものです。
E7A68FE5B3B6E38286E381BFEFBC881937E5B9B4EFBC8920(2)-0f5c0.jpg)
【画像19】
ちなみに、現在の売春防止法もそうですが、戦前の売春関係の法律も売春の行為主体を女性に限定していますので、男性だとわかった途端に罪状が消えてしまい、仕方なく(厳重説諭の上)釈放になります。ゆみ子さん、釈放になるので余裕でポーズを作っています。違う新聞の写真には「男なんて甘いわ」というセリフがついています。昭和戦前期には、非合法売春の容疑で捕まった女装男娼が何人か新聞報道されていますが、私が見る限り彼女がいちばんの美形です。
さらに時を遡りましょう。これは江戸時代中期、18世紀後半に活躍した鈴木春信(1725?~70)の作品です(画像20)。春信は錦絵の大成者として知られる浮世絵師で教科書にも出てくるとても有名な人です。前を歩いているのはもちろん男性で、後ろを歩いている華麗な大振袖、島田髷の人は、今の私たちの目には娘に見えますが、当時「陰間」と呼ばれた、芸能・飲食接客・セックスワークを職業にした女装の少年です。これから贔屓筋の座敷に出勤するところです。
E6B19FE688B8E69982E4BBA3E999B0E996931-fd07f.jpg)
【画像20】
こちらは、少し後の浮世絵師、北尾重政(1739~1820)の「東西南北美人」シリーズの「西方の美人 堺町」です(画像21)。江戸の東西南北の美人を2人ずつ描いた4枚のセットですが、残念ながら全部残っていないようです。確認できる「東方」は深川の芸者を描いていて、たぶん「北方」は吉原の遊女、「南方」は品川の飯盛女(実態は遊女)でしょう。どれもまちがいなく女性ですが問題はこの「西方」です。立ち姿が橘屋の三喜蔵、座っているのが天王寺屋の松之丞という子で、松之丞は江戸の町娘のあこがれだった黄八丈の振袖姿です。もうあらためて言うまでもないと思いますが、「西方の美人」は女性ではなく、女装の少年なのです。
E6B19FE688B8E69982E4BBA3E999B0E9969324-cdde8.jpg)
【画像21】
このようにさかのぼっていくと、「男の娘」的存在がぞろぞろと出てくるわけです。なぜ前近代の日本にそういう「娘」がたくさん出てくるのか、そこら辺のことは私の『女装と日本人』に詳しく書いてありますので、ご参照いただければ幸いです。
もう一息です。これは鎌倉時代末期に描かれた『石山寺縁起絵巻』です(画像22)。この子が着ている橙色の衣服、肩が割れていないので少年が着る水干ではなく、女性が着る袿(うちき)です。履物もけばけばしています。藺げげ(いげげ)という当時の若い女性の履き物です。後にお坊さんがいます。首が切れていますが…。この時代、僧侶は戒律で女性と行動を共にしてはいけません。お坊さんの連れが少女ではまずいのです。つまり、この子は女装の稚児です。きっと後ろにいる師匠のお坊さんが(性的にも)可愛がっている「娘」なのでしょう。
E98E8CE58089E69982E4BBA3E7A89AE585901-42089.jpg)
【画像22】
これで最後です(画像23)。私の話を何度も聞いてくださっている方は「またか」と思われるかもしれませんが、やはり行き着くところは女装の建国英雄・ヤマトタケルになってしまいます。これは三重県鈴鹿市の加佐登神社に奉納されている大きな絵馬です。ヤマトタケルは少女の姿になって九州の豪族クマソタケル兄弟の館に入り込み、その美少女ぶりで兄弟を魅了します。絵馬は長い垂れ髪に緋色の裳の女姿のヤマトタケルがクマソタケル兄弟をやっつける場面を描いています。ヤマトタケルの右手に握られた剣はすでに血にまみれていて。すでにクマソタケル兄の方を殺し、これから青い衣の髭面のクマソタケル弟を刺そうとするところです。ヤマトタケルはこのとき16歳。まさに元祖「男の娘」です。
E383A4E3839EE38388E382BFE382B1E383AB-5fd8c.jpg)
【画像23】
こうして歴史を遡ってみますと、「男の娘」的存在は日本の長い歴史の中に常に存在していたことがわかります。言葉を変えるならば、現在、ミニブームになっている「男の娘」も、男でもあり女でもある双性、ダブルジェンダー的な存在への強い嗜好に支えられた日本の性別越境文化の末裔であり、決して現代の特異現象ではないということです。メディアは新しいものが大好きなので、最新の社会現象だと騒ぎますが、実は根っこはずっと続いているのです。「男の娘」は、2000年の長い歴史を持つ日本の女装文化の21世紀リニューアルバージョンだと、私は理解をしています。
「男の娘」出現の背景
さて、再び現代の「男の娘」に戻って、もう少し深く考えてみましょう。まず「男の娘」がクローズアップされてきた背景です。1990年代後半から2000年代前半は、性別を越えて生きたいと考えることを「病」、精神疾患だと考える性同一性障害という概念が大流行した時代です。メディアの報道も性同一性障害一色でした。こうした性同一性障害の概念の大流行で、従来の女装世界、例えば女装スナックやバーを拠点に形成されている新宿の女装コミュニティは、長年培ってきた人的資源をごっそり奪われて大打撃を受けました。わかりやすく言えば、「女になりたい」と思う人は、それまではお店に来ていたのが、病院に行くようになってしまったわけです。
私は1995年から2001年まで6年間、新宿歌舞伎町の老舗の女装スナック「ジュネ」やニューハーフ・パブ「MISTY」でお手伝いホステス(ゲスト・スタッフ)をしていていました。ちょうど性同一性障害の概念が流行していった時期です。『女装と日本人』を書いた理由の一つは、性別を越えて生きることが精神疾患であるという病理化の思想が社会に蔓延してしまうと、ヤマトタケル以来連綿と続いてきた日本の女装文化は終わりになってしまう、ならば、こういう世界があったんだということをちゃんと調べて書き残そう、そう思って、1998年頃から歴史学や社会学の勉強をし直して学術的な女装文化の研究を始めたわけです。つまり、日本の女装文化の遺言を書くようなすごく悲観的な気持ちで書き始めたのですが、先ほど述べましたように、執筆しているうちにあれ、何か様子が変だぞ、流れが微妙に変わりつつあるぞ、という感じになったのです。
性同一性障害の概念には、医療によって身体の女性化を進めていくことを重視して、性別表現、ファッションや化粧というものを軽視する傾向があります。そのアンチテーゼとして、性別表現を重視した自己表現的な性別越境の形が復活してきた。「男の娘」現象の背景には、そうした性別越境をめぐる大きな流れの転換があると考えています。
メディアも、性同一性障害を10年間も報道すると、もう番組の作り方がなくなってきます。さらに言えば、重苦しさがつきまとう性同一性障害の報道にそろそろ嫌気が差していた。「また性同一性障害かよ、もうちょっと飽きてきたな」と思い始めていたところに、もっと楽しく気軽に性別を越えようという「男の娘」が浮上してきたわけです。メディアは、何度も言うように新しいものが大好きですから、そちらに飛びついた。そういうメディアの視点の転換も、「男の娘」がクローズアップされた背景にあったと思います。
ただし、性同一性障害概念の流布以前に戻ったわけではなく、「男の娘」たちの多くは1990年代まで主流だった新宿の女装コミュニティとは一線を画しています。そもそもエリアが違います。新宿ではなく秋葉原、中心が東京の東側へ動きました。「東京化粧男子宣言」の井上魅夜さんは、2011年12月に「若衆バー 化粧男子」という店を出したのですが、場所は新宿ではなく秋葉原の北の湯島でした。
もっとも、女装世界の中心は、新宿に移る前は上野や浅草でした。戦後最初の女装した女将さんがいるバーは「湯島」という名で、その名の通り湯島天神の男坂の下にありました。さらに言えば、江戸時代、女装の少年が接客する陰間茶屋の江戸における三大密集地の一つが湯島天神界隈でした。徳川将軍家の菩提寺である上野寛永寺のお坊さんが最大の客筋でした。そういう意味では、「男の娘」の拠点が秋葉原や湯島になったのは、先祖返りとも言えます。
「男の娘」の内実
次に「男の娘」の内実です。これはけっこう複雑で、趣味のコスチューム・プレイ(コスプレ)としてやっている女装者から、将来的には女性への性別越境を考えている、つまり戸籍まで女性に変えたいという子までかなり幅広いです。性同一性障害の診断書を持っている子も少なくありません。ですから、身体の女性化の程度も様々で、ほとんど何もしていない人もいれば、女性ホルモン継続の投与だけという人もいれば、外性器の手術(睾丸摘出手術や造膣手術)までしてしまっている人もいます。「男の娘」と言っても中身はいろいろなのです。
性的指向(セクシュアル・オリエンテーション)も一定ではありません。「女好き」、つまり、女の子の格好で女の子が好きという見かけ上レズビアンも多いですが、「男好き」(見かけヘテロセクシャル)もいます。バイセクシャルもいます。
1990年代後半から2000年代にかけては、女装あるいはトランスジェンダーというカテゴリーと、性同一性障害というカテゴリーの間に、かなり強烈な対立がありました。「あなたはどっちなの?」という感じ。ところが「男の娘」は、そうした対立、境界にこだわらない傾向があります。「そんなのどっちだっていいじゃないですか」という感じ。そうした概念へのこだわりのなさも新しいところです。つまり、「男の娘」の内実はかなり多様であり、良く言えばそうした幅広さ、悪く言えばとらえどころのなさ、無思想性が特色になっていると言えます。
「男の娘」出現の条件
次に、「男の娘」出現の条件です。なぜ「男の娘」が出てきたのですか?という質問はメディアの取材で必ず聞かれます。
第一に大きいのは情報流通の変化、具体的に言うとインターネットの普及です。インターネットの普及以前、女装やニューハーフの世界は、まさに閉ざされた世界でした。
先ほどお話した歌舞伎町の女装スナック「ジュネ」)の先輩で、200軒以上の飲み屋が集まっている新宿のゴールデン街を端から飲みまくって、10万円ぐらい飲んだところでやっと女装の店の情報に行き着いたという人がいます。1980年代後半、もう25年くらい前の話ですが、世の中にほとんど情報が回ってなく、伝手をたどってその種のお店を探すしかなかったわけです。どうやったら化粧ができるか、そういう情報もありません。女装やニューハーフの世界になんとかしてたどり着かないと、いくら女の子になりたくても始まりませんでした。
今は、インターネットでいくらでもお店の情報や女装テクニックが簡単に得られるようになりました。初めの方で紹介したように女装指南本が一般の本屋で売られている時代です。昔は女装の専門雑誌を買うのもけっこう大変で、どこに行けば売っているのか、なかなかわかりません。売っている場所に行っても、買うのにすごいドキドキでした。どうしても勇気が出なくて店の前を何度も往復してとうとう買えなかった、なんて話もあります。ともかく、ものすごく敷居が高い世界でした。それが今はもうまったく違います。
第二は男の子たちの顔や体形の変化です。私、今はすっかり太って丸顔ですが、若いころは1000人に1人の女顎、つまり三角顎だと言われたことがあったのですが、悔しいことに今、私レベルの三角顎の男の子はごろごろいます。そのくらい日本人の男性の顔立ちは変わってきています。フーテンの寅さん、渥美清さんのようなエラが張っているホームベース型の顔で、髭の剃り跡が青く見えるような男の子は本当に少なくなっています。顎のラインがすっきりした、髭もあまり濃くないような子が増えています。体形も手足が長く、骨格がずいぶん華奢になり、女物の9号の服が着られるような男の子が増加しています。つまり、男の子の顔立ちや体型が女装向きに変化してきています。昔に比べて「女の子になる」ベースに恵まれている男の子が多くなっているわけです。
第三に社会環境の変化があります。男の子が髪を長くのばしたり、眉を細く手入れしたり、髭や手足の体毛を脱毛していることが、それほど奇異に見られなくなっています。別に女の子になりたいわけでなくても、身体のメンテナンスに気を遣うおしゃれな男の子が増えていますから、そういう女装のための身体条件を整えることをしても、あまり目立ちません。
社会全体として性別の越境に対する許容度・自由度が以前に比べればだいぶ緩くなっています。コスチューム・プレイという感覚で、男性と女性の間を行って戻ってみたいなことがかなり自由になっている。社会環境として性別の越境、性別表現の転換が容易になっているということです。昔はそこに乗り越えなければならない高い壁のようなもの厳としてありましたったのが、私の世代だと、女装すること自体がものすごく大変で、そこに至るのに何年かかるという世界だったわけです。たとえば、私は振袖を着たいと思ってから実際に振袖姿で外へ出るまで20年近くかかっています。ところが最初に紹介した銀座の振袖「男の娘」は、2回目の女装でした。それほど違うのです。心理的な、もしくは社会的な、越えなければいけない障壁がとても低くなっています。
第四は、女性が男の子の女装を受け入れるようになったことです。女装した男性と一緒に遊ぶ、さらには積極的に女装に協力するような女性が確実に増えてきています。化粧にしてもファッション・コーディネートにしても、男の子が一から独力で覚えるのと、女性が協力してくれるのとでは、進度も到達レベルもまったく違います。こうした関係性の変化については、また後で詳しく述べます。
第五は、これがいちばん重要なことですが、価値観の変化です。昔は男が女の格好をする、女装することは、男性上位社会において明らかな社会的下降でした。よりによって「女『なんか』になる」という感じです。ですから、女装にはしばしばマゾヒズムが伴っていました。マゾヒズムについては、富田先生がここでお話になったと思うのですが、わざわざ女という低い身分になる、「あたし、とうとう女に墜ちちゃったわ」というような被虐的な陶酔にひたる女装者は少なくありませんでした。
ところが、今の「男の娘」たちはまったく違います。現代の男の子は同世代の女の子のライフスタイルに、かなり強いあこがれを持っています。男の子のライフスタイルは冴えないけれども、女の子たちはとても輝いている」。あくまでも見えるだけで、必ずしも実際はそうでないのですが、ともかく女の子ライフが素敵に見える。自分もああなりたいと思うわけです。つまり、「女になる」ということ下降ではなく、明らかに上昇志向なのです。より輝いているあこがれの女の子ライフに近づいていくという意識です。そこが、昔とまったく違います。
性別表現の転換に対する評価が、以前のような「そんなことをするのは変態」というマイナスではなく、ある種のアイドル性を持った肯定的なプラス評価になってきています。そこが大きな変化、大事なポイントだと思います。
今の若い女性の最大の価値観はカワイイです。カワイイものがいちばん価値がある。それに近づいていくための自己表現が「男の娘」になることなのです。だから、「男の娘」の世界では、カワイイことが基準化され重視されます。残念ながら誰でもカワイクなれるわけではないですから、そこに淘汰が生じます。カワイクない「男の娘」は女性に受け入れられません。
それと、年齢を重ねると、どうしてもカワイイが似合わなくなってきます。ですから、「男の娘」は年齢的な制約がとてもにきつい。当人たちに言わせると「10代から20代で20代が中心。アラサー(30歳前後)はもう辛いですね」ということになります。
従来の女装コミュニティでは、30代、40代が中核でした。これは、ある程度の経済的余力がないと、化粧品や服、さらにそれらの隠し場所である変身部屋(仕度部屋)にお金がかかる女装という遊びができなかったからです。20代だと独力では経済的に難しい、男性のお世話(援助)がないとそれなりのレベルの女装は無理でした。
男性主導から女性主導へ
男性のお世話になると言いましたが、伝統的な女装世界では、自分は女装しないけれど女装者が大好きな男性、私は「女装者愛好男性」名付けているのですが、そういう人たちが大きな役割を果たしていました。女装者愛好男性が若い女装者を「育てる」、経済的に援助することはしばしば行われていました。前に出てきた女装秘密結社「富貴倶楽部」はそうした援助がシステム化されたものと言えます。
援助の見返りとして女装者は、女装者愛好男性に性的に従属することが当然視されました。つまり、女装して女になることは男に抱かれるということと全く同義で、女装とセクシャリティが表裏一体でした。
それが徐々に変わっていきます。1979年創業のアマチュア女装クラブ「エリザベス会館」では女装者愛好男性を出入禁止にします。女性スタッフと女装者だけの空間で、セクシャリティを基本的に排除したのです。
私は1990年から4年半「エリザベス会館」に通って、本格的な女装の技術を習得し、その後、1995年から新宿歌舞伎町の女装ホステスになりました。今述べた歴史的な流れとは逆のコースだったので、女装者が女装者愛好男性に抱かれることが当然視されていることに驚きました。店で男性客に「ホテルに行こう」と誘われても、私は「嫌」と言うので、「あいつは生意気だ」とずいぶん言われたものです。
そうした女性と女装者の空間という形は、2000年代に登場してくる女性が経営するハイスペック、ハイレベルな、ただし費用も高い女装スタジオにも受け継がれます。これはそうした高級女装スタジオのひとつ、早乙女麗子さん主宰の「R’s(アールズ)」(曙橋から新宿御苑前に移転)の作品です(画像24)。モデルは前に出てきた吉野さやかさんですが、まったく男性らしさの欠片も感じられません。
E59089E9878EE38195E38284E3818BEFBC882009E5B9B4EFBC89-94b07.jpg)
【画像24】
先ほど本物の女の子と「男の娘」とが一緒に遊ぶと言いましたが、この写真がそれです(画像25)。やはり早乙女さんの作品ですが、一見、どっちがどっちだかわかりません。右側がSakiさんという「男の娘」で、左側が生まれつき本物の女の子です。こういう形で「男の娘」と女の子が仲よく一緒に遊んでいる世界になると、もう女装者愛好男性が入り込む余地はありません。
Saki26E7B494E5A5B3-c34db.jpg)
【画像25】
これは「東京化粧男子宣言」ポスターですが、このシルエット画像がなかなか象徴的です。左のお化粧されているのが男の子で、右のメーキャップしているのが女性です(画像26)。先ほど言い忘れましたが、「東京化粧男子宣言」は、モデルの男の子と、ファッション・コーディネート&メイク担当の女の子が男女ペアで競うコンセプトのコンテストです。このシルエット画像は、現在の女装が、かっての男性主導から女性主導へと変わってきていることをよく示しています。
E69DB1E4BAACE58C96E7B2A7E794B7E5AD90E5AEA3E8A8802009-1-2714c.jpg)
【画像26】
そうなると評価の基準も変わってきます。以前の男性目線の評価だと、きれい、色っぽい、おとなしい(従順)が評価基準でした。どれだけ男性の性欲をそそるかが価値基準だったわけです。それが同世代の女性目線の評価になるとカワイイが絶対的な価値基準です。女の子にカワイイと承認されるかどうかが、「男の娘」の最大のポイントになる、そういう世界です。
こうした変化の背景には、2000年代においてさまざまな分野で女性の社会的進出が進み、社会の中で女性の嗜好が重視されるようになり、相対的に男性の影響力が減少したことがあるのだろうと思います。
性別認識をめぐって
さて、そろそろ与えられた時間が尽きそうです。最後に「男の娘」をめぐる性別認識についてお話します。
湯島の「若衆バー 化粧男子」でこんなことがありました。ある「男の娘」、なかなかカワイイ子なのですが、店に入ってくるなり「今日ここに来る前に、男の人に声かけられて、ナンパだったんですよぉ。ああ、キモ!(気持ち悪い)」と言っています。そこで私が「それはあなた、どう見ても女の子なんだから、男の人が寄ってくるのは当然でしょう」と言ったら、「でも、自分、男ですよ」と(笑)。
どう見ても女の子に見える「娘」が、「えー、でも自分、男ですよ」と言っている。この「男の娘」の性自認(ジェンダー・アイデンティティ)は、女性ではなく男性で、しかも性的指向(セクシュアル・オリエンテーション)は男性には向いていないということです。私は他者から与えられる性別認識を、性自認に対して「性他認」と言っています。たぶん私の造語だと思うのですが…。この「男の娘」の場合、性自認は男性だけど性他認は女性で両者が一致していません。それで男性にナンパされるという性的指向に沿わない不快な経験をしてしまったということです。
ところで、性同一性障害の世界では、これと逆の現象がしばしば見られます。MtF(Male to Female 男から女へ)の方で、性自認が女性で「私は女なんです」と主張しているのに、周囲から「あなた、女に見えないよ」と言われてしまうケースが問題になっています。性自認は女性なのに、性他認は男性という不一致です。
つまり、「男の娘」の世界と性同一性障害の世界でパターンは逆ですが、同じような性自認と性他認の不一致による混乱が起こっているということです。「男の娘」の方は遊びの要素が強いですから笑って済ませられますが、性同一性障害の方のパターンは、社会生活にいろいろ支障をきたし、よほど深刻です。性自認が女性であるにもかかわらず女性の性他認が得られないのは、女性としての性別表現が不十分なことに原因があることが多いので、私は機会があるとそういう方たちのために、女性的なしぐさや歩き方のレッスンをしていますが、男性としての生活が長かった中高年の性同一性障害の方の場合、なかなか大変なのが実際です。
それはともかく、現代の日本では、男に見えるから男、女に見えるから女というふうに、もう単純に言えなくなってきているということです。「男なるもの」と「女なるもの」の境界がかなりぼやけてきて、境界領域が幅広くなっている。社会の中で自明と思われていた性別認識が、実はかなり揺らいできているということ、それが大事なポイントではないかと思うわけです。
「男の娘」の可能性
最後に「男の娘」の可能性です。「男の娘」というネーミングがいつまで続くかわからないので、「男の娘」を含むトランスジェンダーの可能性ということになると思いますが、21世紀の日本におけるの「男なるもの」と「女なるもの」の境界に位置するサード・ジェンダー的存在として、世の中には男と女しかいないのだという性別二元制、あるいは体が男なら男、体が女なら女というような身体構造を絶対視する性別決定論、さらには。男なら女が好き、女なら男が好き、そうでなければいけないというような異性愛絶対主義などを揺るがしていく存在になる、そんな可能性、期待感を持っています。
話し始めて1時間たちましたので時間切れですが、せっかくなので最後にNHKワールドの「(NEWS LINE)Boys Will Be Boys?」をご覧いただきましょう。
(5分間ほど番組視聴)
なにやら怪しい着物の先生が今日お話したようなことをコメントしていましたが、番組の後半は、早稲田大学の男子学生さんが卒業記念に横浜の「アルテミス」という高級女装スタジオに行ってドレスアップした卒業記念写真を撮るという話です。私、この番組の収録の時に、その早稲田の学生さんに「あなた、素顔を出しちゃって大丈夫なの?」と尋ねました。彼はある地方の公務員に採用が決まっていると聞いていましたので、昔ならこんな形で番組に出てしまったら採用取り消しになりかねません。それで、心配して「(素顔に)モザイクかけなくていいの?」と言ったわけです。そうしたら「私、面接のときに『趣味は女装です』と言って合格していますから、問題ありません」という返事でした。ここでも、世の中つくづく変わったなと思ったわけです。
今日は、日本の長いトランスジェンダーの歴史の中の、いちばん新しい現象である「男の娘」についてお話しました。ご清聴ありがとうございました。(拍手)
【追記・「男の娘」をめぐるその後の動向】
2012年11月20日、男の娘を主人公にした映画『僕の中のオトコの娘』(窪田將治監督、12月1日公開)公開記念イベント「オトコの娘サミット2012」が開催された(東京新宿歌舞伎町「ロフトプラスワン」)。
.jpg)
年が明けた2013年2月17日には『毎日新聞』が「S ストーリー」という企画記事で「月一度『封印』を解くー女子化する男たちー」(鈴木敦子記者)と題して社会的視点から「男の娘」問題を1面の一部と4面の全部を使って大きく取り上げた(http://junko-mitsuhashi.blog.so-net.ne.jp/2013-02-18)。
【参考文献】
三橋順子「現代日本のトランスジェンダー世界 -東京新宿の女装コミュニティを中心に-」
三橋順子「『女装者』概念の成立」
三橋順子「女装者愛好男性という存在」
(以上、矢島正見編著『戦後日本女装・同性愛研究』中央大学出版部 2006年)
三橋順子「往還するジェンダーと身体-トランスジェンダーを生きる-」
(鷲田清一編『身体をめぐるレッスン 1 夢みる身体 Fantasy』 岩波書店 2006年)
三橋順子『女装と日本人』(講談社現代新書 2008年)
三橋順子「変容する女装文化 -異性装と自己表現-」
(成実弘至編著『コスプレする社会 -サブカルチャーの身体文化-』せりか書房 2009年)
三橋順子「異性装と身体意識 -女装と女体化の間-」
(武田佐知子編『着衣する身体と女性の周縁化』思文閣出版 2012年)
【講演録】性別違和感を抱く学生に教職員はどう対応していくか [論文・講演アーカイブ]
2014年7月27日、明治大学(駿河台)で開催された「第53回学生相談室夏期セミナー」に呼んでいただき、「性別違和感を抱く学生に教職員はどう対応していくか」というテーマでお話しました。
その記録が『学生相談 2014年度 学生相談室報告』(明治大学学生支援部 2015年6月)に掲載されました。
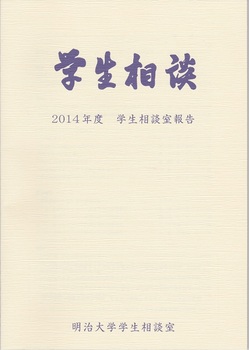
学外者には入手が難しい学内誌なので、全文をここに掲載します。
--------------------------------------
明治大学 第53回学生相談室夏期セミナー 講演
「性別違和感を抱く学生に教職員はどう対応していくか」
2014年7月27日(日)
文学部 兼任講師 三橋 順子
はじめに
皆さん、こんにちは。三橋順子です。明治大学に非常勤講師で呼んでいただいて3年目になります。簡単に自己紹介しますと、私は、男性から女性へのトランスジェンダーですが、戸籍は生まれたときの性別、名前で変えておりません。1995年くらいから社会的には女性として、講演、著述、あるいは教育活動をしてきました。女性としてそれなりに実績はあったわけですが、実は、明治大学から講師のオファーがあったとき、すんなりとはいきませんでした。「お引き受けします」とお返事した後、履歴書段階で1~2カ月ほど手続きが止まってしまったのです。理由は履歴書の性別欄の記載です。私は履歴書の性別欄を空欄で提出しました。私の性自認からして「男」とは書けませんし、男女雇用機会均等法の趣旨からして性別の記載は強要されるべきではないと考えますので。それに対して人事課は「性別欄が空欄なのは前例が無い。戸籍通りちゃんと男性と記載してください」ということでした。私から明大で講義をさせてくれとお願いしたわけではなく、明大から依頼してきたことですので、「それなら結構です」と申しましたら、やっと人事が動いたということがありました。性別記載で引っ掛かってしまうということが、まだまだ日本の現実としてあるということです。明治大学だけが理解がないわけではなくて、日本社会のシステムが男女二元で、しかも硬直的で融通が利かない。それが性別を越えて生きるトランスジェンダーの人たちをどれだけ生きにくくしているかという事例としてお話しました。今日はそうした問題をどのようにクリアしていけばよいかというお話をいたします。
1 基礎知識として
今日のテーマは「性別違和感を抱く学生に」ということですが、最初に基礎知識的なことを、三つお話をしておきましょう。
(1) 同性愛とトランスジェンダー
一つ目は、同性愛とトランスジェンダーの違いです。学生も一番ここが分からないと言うので、こんな説明をします。同性愛は、男が好きか女が好きかという性的指向sexual orientation問題であって、自分が男であるか女であるかというgender identity性自認(性同一性)の問題ではありません。誰を好きになるかという相手の性別がマジョリティーの人と違っているのが同性愛です。トランスジェンダーは自分が男であるか女であるかという性自認gender identityの問題で、男が好きか女が好きかというsexual orientationの問題ではありません。男として生きるか女として生きるかという自分の性別の在り方の問題です。
(2) 性別違和感(Gender Dysphoria=GD)とは?
基礎知識の二つ目は、性別違和感gender dysphoriaとは何かということです。一般的には、自分の性別に対する心理的な違和感が性別違和感です。性別違和感を考える場合、基本になるのは自分の性自認、自分を男と思うか、女と思うかということです。自分は男だと思っているのに、身体が女である、生理が来る。あるいは、自分が女だと思っているのに、男性の身体である、声変わりをしてしまう、髭が生えてくるというような性自認と身体の性のズレが身体違和です。
ズレ(違和感)はそれだけでなく、性自認と社会的性(ジェンダー)の間にも生じます。自分が女だと思っているのに、世の中からは男として扱われる。「あなたは、戸籍は男でしょう。だから男として扱いますよ」ということです。自分は男だと思っているのに、「あなた、戸籍上は女でしょう。女性のほうに入りなさい」と言われてしまう。性別違和感は性自認と身体の間、性自認と社会的な扱いの2カ所で生じます。ここがポイントです。身体のほうの違和感は大学でどうこうできる話ではありませんので、医学的な対処が必要になりますが、社会的な扱いに関しては、世の中の一部である大学でも対応できる問題ということになります。
心が女なのに身体が男であるというのはやはり辛いわけで、何とかズレを直そう、整合性を回復しようとします。自分は女だと思っているのに世の中から男として扱われるというのはとてもきついことです。さっきの私の履歴書の話ですが、あの時は精神的に相当きつかった、かなり落ち込みました。そのあたりは、性別違和感がない方にはなかなか理解をしていただけないと思いますが。性別違和感というのは、ギザギザ、トゲトゲした、やっかいな嫌なものなので、何とかそれを解消しようと努力します。つまり、性別違和感は、性別を移行していく原動力になるわけです。
(3) 性同一性障害(Gender Identity Disorder=GID)とは?
基礎知識の三つ目は、性同一性障害とは何かということです。性同一性障害は、Gender Identity Disorderという英語の疾患名の日本語訳です。先ほど、性別違和感は性自認(性同一性)gender identityと身体的性sex、性自認と社会的役割gender roleの2カ所で生じると申しましたが、その2カ所の不一致に起因する性別違和感がどんどんひどくなっていった結果、著しい精神的苦痛や、社会生活・職場における機能障害、つまり、社会生活がうまくいかない、あるいは学校や職場でそこにうまく身をおけないという形になって、医療のサポートが必要になった状態をいう精神疾患概念です。「性同一性障害は病気ではないと思います」という学生がときどきいますが、「性同一性障害というのは精神疾患の名称なので、それを病気でないというのは概念矛盾で、成り立ちませんよ」と説明します。ただし、性同一性障害というのは性別違和感を原因とする社会的不適応の病であって、性別違和感を持っていること自体は病気ではないということです。ここはマスメディアが心の性と身体の性がズレていることが病気だというような説明をすることが多いのですが、それは間違いです。実は、自分の性の在り様が何かズレている、違和感があるという人は、けっこう多いのです。それは違和感の程度の問題でして、違和感があること自体を病にしてしまうのは、問題があると思います。そのような状態をとても苦痛を感じていて、社会生活上、不適応を起こしていることが病であると捉えないといけないと思います。
2 「性別違和」の現在
(1) この15年間の流れと最新の動向
次に、日本で性別移行の問題が社会的に浮上したこの15年ぐらいの流れをざっとおさらいしておきます。もちろんそれ以前から、性別を変えようと努力したいろいろな人がいたわけですが、やはり起点は1996年です。私立の埼玉医科大学の倫理委員会が、形成外科の教授から申請があったSex Reassignment Surgery、「性転換手術」、現在で言う「性別適合手術」を正当な医療行為として承認したことがニュースになりました。これはあくまでも一大学の倫理委員会の判断で、本来はそんなに大げさに報道することではないと思うのですが。それを受けて97年の5月に、日本精神神経学会が「性同一性障害に関する答申と提言」という、私たちが「ガイドライン」と呼んでいるものを出しました。これもかなり大きなニュースになって、このあたりから性同一性障害という病名が『現代用語の基礎知識』などにも載るようになってきました。98年10月に埼玉医科大学が「ガイドライン」に基づいたものとして初めての性別適合手術を実施しました。あくまでもガイドラインに基づいたものとしては初めての手術であって、性別適合手術自体は日本では1951年、世界でも指折りに早い時期からやっています。これは私が調べたことですが。
そんな流れの中で2002年の8月に六大学「学生相談」連絡会議で「性別違和を抱える学生をどう受け入れるか」という講演をさせていただきました。会場は中央大学で、私は中央大学の社会科学研究所の研究員という立場でした。その、きっかけは明治大学だったように覚えています。明大で、自分は男ですという女子学生、つまりFtM(Female to Male)の学生さんが出てきて、教授会で問題になったというお話でした。「問題になったというのは、対策が問題になったのですか」とうかがったら、そうではなく、「『明治大学の学生ともあろうものがけしからん』とある教授が言い出した」というお話でした。今からすると、とんでもない無理解ですが、この頃は、明大だけがそうだったわけではありません。
早稲田の学生部の方が「うちはいないと思います」と言ってきたので、「早稲田大学の学生数って6万人でしたよね。6万人いていなかったら、それはそういう人たちを選別して落としているという意味ですか」と尋ねたら「いや、そんなことしていません」と言う。「だったら、いるに決まっているんです。プライバシーの問題があるから誰ということは言えませんが、早稲田大はニューハーフ業界でもかなり名門ですよ」とお返事しました。法政大はカルーセル麻紀さんのお師匠さんの「青江のママ」さんが法政大の学徒出陣ですからもっと名門ですね。後でまた申しますが、性別の悩みを持った学生さんというのは、東京の私立の大きな大学だったら確率的に必ずいるのです。ただ、それがきちんと認識されていない、あるいは本人が隠しているというだけの話なのです、ということをそのときの講演で、お話しました。
あの講演、少しは効果があったかなと思います。例えば慶應義塾大学で、MtF(Male to Female)の学生さんの就職がなかなかきついということで、大学の職員として雇用してくださった例がありました。もちろん、本人にそれだけの能力があったからでしょうが。
大きく流れが変わったのは、2003年です。7月に「性同一性障害者の性別取り扱いの特例法」(GID特例法)が成立し、翌年の7月に実施されました。この7月でちょうど実施10周年になります。これを大学に関係させて言うと、大学の学部あるいは大学院在学中に学生・院生が性別の変更を行うことが合法的に現実のものになったということです。あるいは、教職員の方で性別を変更する方が出てくるかもしれないということです。
少し飛びますが、2013年、文部科学省が全国の小中高校と支援学級を対象に、いわゆる性別違和に悩む児童、生徒の一斉調査というものをやりました。本当に一斉調査なのかという疑問もあるのですけれども、私は良い面と問題な面と両方を感じています。結果的に性別違和を持つ児童、生徒は606人。うち性同一性障害の診断をすでに受けている児童、生徒が165人という結果が出ました。実際はもっといるはずです。ただこれも、どの範囲を性別違和と捉えるかによってだいぶ人数が違ってきます。何度も言いますが、この問題がとてもややこしいのは、どの程度の性別違和感までを病理として把握するかということです。
例えば、私は明大で260人ぐらい受講生がいます。後期、山梨の都留文科大学でも240人ぐらいを持っています。だいたいその200人越えぐらいの人数で、コメントシートやレポートなどで、自分の性別違和を書いてくる学生がだいたい毎年2~3人はいます。不思議なことになぜか女子学生が多いのですが。周囲が女の子扱いするのが嫌で学校に行きたくなかったというような、かなり辛い性別違和を経験している例もあります。その時点で診断を受けたら、多分、性同一性障害の診断が出るだろうと思います。ところが、その学生とたまたま面談すると、一応女子学生で適応していたりします。本人は「まだ今でも違和感があります、すっきりしない部分はあります。だから先生の授業を取りました。でも何とか女子大生でやっています」という感じですね。そういう学生たちは、今後、病院へはたぶん行かないでしょう。だからそこまでを病理の範囲に入れるか入れないかで、かなり話は違ってくるのです。
最新の状況についてもお話ししておきましょう。実は今、国際的な動きがいろいろあります。2013年5月にアメリカ精神医学会のマニュアル「精神疾患の分類と診断の手引き」の改定が行われ、「DSM-5」と言われる第5版が施行されました。そこで、gender identity disorder、日本語でいう性同一性障害をgender dysphoria性別違和という病名に置き換えました。ただ病名を変更しただけではなく、診断基準も手直ししているので、置き換えたという言い方をしています。その結果、アメリカでは、すでにgender identity disorder、性同一性障害という病名はなくなりました。やはり「disorder」という部分に抵抗感を強く持つ当事者が多いのです。これはアメリカの診断基準ですから、どう変えようが、本来なら日本は関係ないはずなのですが、実際には日本の精神科医もかなり影響を受けています。日本のメンタルクリニックや心療内科へ行くと、「どうされました?」と尋ねる先生の後ろの書棚に分厚いDSMのマニュアルが飾ってあることが多いのです。ちゃんと読んでいるかどうかは知りませんが、影響力はすごくあるのです。
さらに、日本は国際連合に加盟していて、国連の専門機関である世界保健機関WHOのメンバーです。WHOにはICDと言う疾患リストがありまして、本来はこちらが日本で診断マニュアル化されるべきものです。そのICDの改訂作業が現在進行中で、新しい第11版、ICD-11の施行が2017年に予定されています。性別違和に関して、かなり大きな改訂になりそうで、まず確定的なのは、gender identity disorder性同一性障害はなくなります。何という病名に置き換えるかまだ決定ではないのですが、どうもgender incongruence、性別不一致という病名に置き換えられそうです。さらに重要な変更は、今までの精神疾患のカテゴリーから「その他の疾患」のカテゴリーに移す案が有力視されています。そこらへんの情報は2014年2月にバンコクの国際学会で仕入れてきた最新のもので、日本で知っている人はまだそんなに多くありません。
このまま実現すれば、gender identity disorder性同一性障害という病名は、国際的な疾患リストから完全に消えます。ですから、日本でも病名を変えなければなりませんし、「性同一性障害者の性別取り扱いの特例法」という法律名も変えなければいけなくなります。そして性別移行の脱精神疾患化が達成されることになりますが、この点はまだ少し不確定な要素があります。
ということで、現在は過渡期でありまして、2000年代に入って高まってきた性別移行の脱精神疾患化という世界的な流れが結実するかどうか、微妙なところに来ています。日本はそういう世界的な潮流にはまったく鈍感ですが、いずれそういう方向に行かざるを得ない、行くべきだということです。
(2) 性別移行システムの問題点
問題点を整理しておきましょう。2000年代、「GID特例法」制定の前後からにメディアが活発に性同一性障害について報道をしました。しかし、その報道は医療側の言説をそのまま流すという形で、病気だから仕方ないから戸籍を変えるのだという流れになってしまい、本来、考えなければいけない性的マイノリティの人権という視点が希薄化してしまいました。病気ということなら認めましょうという流れ、性別移行の病理化が一気に進行してしまったのです。それでうまくいった人もいるわけで、それはそれで結構なのですが、世界の流れは、2000年代に入って、むしろ病理化ではなく脱病理化、具体的には、性別移行を精神疾患概念からどうやって外していくかという脱精神疾患化の方向に向かっていました。ところが、日本は世界的な潮流とまったく逆行して、この10年間に病理化を推進してきたわけで、大学も「対応しますから、診断書を出しなさい」、さらに高校や中・小学校まで「診断書を出しなさい、診断書を出したら対応しますよ」という、形になってしまいました。性同一性障害概念の流布によって、性別移行の病理化が極端に進みすぎてしまい、病理を前提にしないと社会的対応ができないような仕組みができてしまいました。これは大きな問題です。今後、こうした病理を前提にしたやり方を人権を前提にした考え方に変えていかなければなりません。
先ほど申しましたように、弱い性別違和を持つ人は、けっこうたくさんいます。おそらく100人に数人レベルでいると思います。弱い性別違和をもつ人たちの多くは自然に解消する、あるいは自分で折り合いがつく可能性があるわけで、病理化する必要はないのです。ところが、医者の中には、性別違和感を持つ人すべてを病理化しようとする、性同一性障害の診断基準から外れるような弱い違和の人までを性別違和症候群として把握するような形が理想とする医師もいます。病理化の徹底ですね。そこには、自分にふさわしい性の在り様を自分で選んで決定するのは人権の一つであるという発想がないわけで、まったく困ったものです。
性別移行の当事者の方も、戸籍の性別変更が目的化してしまって、「GID特例法」の要件をクリアするため、ともかく性別適合手術をするという状況が生じています。必ずしもしなくてもいい手術まで受けてしまう過剰な医療化です。今、世界的にはIDカードなどの性別の書き換えに手術を要件とするのは人権侵害だという方向になっています。つい1カ月ほど前に、WHOが性別の移行に関して性別適合手術を要件化するのは人権侵害という勧告を出しました。日本の「GID特例法」は手術して生殖機能を喪失しないと性別の変更は認めない形ですから、WHOの勧告に完全に抵触します。日本の現状は、世界の性転換法の中で人権意識の低い、遅れた形になってしまっています。
病理化の徹底、過剰な医療化を進めながら、実は国内の医療施設がまったく足りません。患者は激増したのに、医療施設が増えないのです。だから手術をするのにみんな海外、主にタイへ行かざるを得ない。日本の医療というのは、面倒くさいことは全部外注してしまう傾向がありますが、まさにその典型です。
過剰な医療化、あるいはアンバランスな医療化の弊害が実際に出てきています。性同一性障害の診断を受けたのにジェンダーの移行がなかなか進まない。これは何か違う精神的な原因で引っ掛かっていると思われます。さらには、性別適合手術を受けて戸籍変更までしながら、新しい性別で社会適応ができない。たとえば、身体の外形も戸籍も女になりました。だけれど女性として社会適応ができませんというケースが増えているように思います。大学でこういう形が出てくると、なかなか対応が難しいことになります。
(3) 性別違和の人口比
性別違和を抱える人はだいたいどのぐらいの比率なのか、皆さんけっこう気になるのではないかと思いますので、その話をしましょう。
もともと欧米では、私のような男性から女性への移行を望むMtFが3万人に1人、逆に女性から男性への移行を望むFTMが10万人、つまり、MtFとFtMの比率は3対1と言われていました。このデータ、実はあまり信用度が高くないのですが、日本で90年代末に性同一性障害の問題が浮上したとき、どうも日本はFTMが少し多いのではないか、MtFが1~2万人に1人、FtMが3万人に1人、MtF対FtMの比率は2対1くらいに考える人が多かったと思います。ところが、どんどんどんどん差が詰まっていきまして、2000年代の初めぐらいには、MtF、FtMを通じてだいたい1~2万人に1人、MtF対FtMは1対1に近い。もうこの時点で、世界の研究者から「日本のデータが変じゃないか?」と言われ始めていました。さらに2008年ぐらいから、中高大学生ぐらいの若いFtMが急増して、MtFとFtMの比率が1対1.5~2と完全に逆転してしまいます。
私の授業では、2008年に放送された「ラストフレンズ」というテレビドラマの中で、ボーイッシュなレズビアンっぽい女性が性同一性障害だと思ってメンタルクリニックに行くシーンを学生に見せて、メディアのミスリードが現実世界に影響しているのではないかという話をするのですが、2008年ぐらいから様子ががらっと変わってきました。その後も女性から男性になりたい若い人の増加傾向がずっと続いていて、現状MtFとFtMの比率は1対3、90年代とは完全に裏返しになっています。人口比で言うと、MtFが1万人に1人か2人。MtFはあまり変わっていません。FtMが1万人に3人くらいという状況です。現状、日本は世界で最も顕著にFtMの比率が高い国になっています。
性別違和が重く性別適合手術をして戸籍の性別変更をした人が、2013年12月末現在で、全国で4353人というデータが出ています。このペースだと2014年末には5000人を超えるのは確実ですので、だいたい2万人に1人が戸籍の性別を変更しているということになります。
10年前に法律ができたときには、こんなに多いとは思いませんでした。年間50人ぐらいだろうと予想していました。年間50人だと10年で500人ですから、10倍ぐらい予想より多いというのが今の状況です。
なぜ、こんなに多いのか、そしてFtMの比率がこんなに高いのか。とても重要な問題なのですが、誰もきちんとした説を出していません。私が頑張って考えているのですが…。要は、全体に増加傾向にあるということと、特にFtMが増えているということを頭に置いておいてください。
それから、2010年代に入ると、あるお医者さんの言い方で「確信的でない受診者」が増えています。以前、メンタルクリニックに来る人は、かなり確信的に「私は、心は女なのに、男性なのです」とか、逆に「俺は絶対男だと思うんだけど、女なんで何とかしてください」というタイプが圧倒的でした。ところが最近は、「自分の性別がよく分からない」とい言う人が増えてきています。これをXジェンダーといいます。数学で不明数をXとするのと同じです。そういう人たちは「自分はXです」と言います。男ではないと思うけれども女でもないMtX。女ではないけれども男でもないFtXというタイプです。これが現実にかなり増えていて、理由を考えなければと思うのですが、まだ調査が進んでいません。私は弱い性別違和までを病理化してしまった結果、本来だったら男女どちらかに折り合いをつけるべきところを折り合いがつけられない人が増えてきているのだろうと思っています。それから女性に多いと思うのですが、いわゆる成熟拒否、大人の女性になりたくない。できるだけ猶予期間を長引かせたいという人も含んでいると思います。
こういう現状で、数値モデルを整理しておきますと、弱い性別違和を持つ人が100人に2~3人、医療が必要な強い性別違和を持つ人がそのうちの100人に1人ぐらい、つまり1万人に2~3人という話になります。さらに戸籍変更に至るまでの人は、そのうちの8~9人で、10万人に5人、2万人に1人。ここはかなり確定的なデータが出ていますので、こんなモデルが作られるわけです。私はどちらかと言うと少なめに見積もっていますが、そんなに違ってはいないと思います。
明治大学の学生数は2万9千人だそうです。このモデルに合わせると、強い性別違和を持つ学生は1万人に2~3人ですから、6~9人ぐらいいて当たり前ということです。1万人に2~3人というのは全人口比ですから、大学在学年齢だともっと多いと思います。何10人ということではありませんが10数人いてもおかしくないということです。何度も申しますが、いて当たり前だという認識がとても大事です。
さらに言うと、まさに10代後半ぐらいの年齢層では、自分の性別がよく分かりませんというXジェンダー的な学生がだいぶ増えているはずです。おそらく「性同一性障害」のカテゴリーに入る学生と同じくらいいるかもしれません、かなり強い性別違和を持つ学生が仮に10人いたとしたら、曖昧な形で何か性別に悩んでいるような学生も、もう10人ぐらいはいるという勘定です。これだけいたらもう珍しい話ではありませんので、そういう学生が相談に来た時の対応マニュアルをきちんと作っておくべきです。ただし、マニュアルは、個々のケースに応じて弾力的に運用することが大事です。
3 大学はどう対応すべきか
では、大学は具体的にどういう対応をしていけばいいのかについてお話しします。ここからは私の主観的な意見になっていくわけですが、実を言うと12年前にお話ししたことと基本は変わっていません。自分でも頑固だなとは思いますが、12年前から言ってきたことが今、現実になっている感じがありますので、少し自信を持っています。
① いて当たり前という基本認識
先ほども申しましたように、ある程度の規模の大学なら強い性別違和感を持つ学生が在籍しているのは確率的に当然で、まったく特異なことではありません。いて当たり前だという基本認識を持ち、いると思って対応すべきなのです。不思議なことでも特異なことでもないということです。
② 基本的には本人の自主性に任せる(放っておく)
異性装、身体の性別とは違う服装をするとか、性別を越えて生きるということ自体は、病でも性的逸脱でもありません。客観的には「変わり者」かもしれませんが、現在の日本では法律で禁止されているわけでもありません。日本で異性装が違法だったのは、明治5~6年から14年(1881)までの約10年間、文明開花期だけです。基本的に、服装表現、性別表現、ジェンダーの選択は個人の自由で、人権として認められるべきものです。つまり、本人の自主性にまかせるべき問題で、そうした学生がいたからといって、大学のほうから積極的に介入する必要はありません。基本的には放っておくべきことなのです。性同一性障害なんていう話が出てくる以前にも、書類上は男子学生だけどずっと女の格好で大学に通っていましたという人は実際にいます。もちろん大学側は気付いていたはずですけど、処分するようなことはできませんし、結局そのまま「あいつは変わっているな」で卒業してしまったという話です。基本的には放っておく、でも、なにか困って相談に来たら、ちゃんと対応するということが大事なところです。
③ 環境整備に努める
性別を移行したい学生にとって一番困るのは、学生名簿の男女欄など、学内における性別記載です。日本の大学、例えば文学部だったら文学士という学位を出します。文学士男とか、文学士女という学位ではないわけで、男だろうが女だろうが……女子大は別ですが、明大は共学なので、いちいち学生名簿に男女欄とか男女の識別記号はいらないはずです。学生証の性別記載欄も同様です。性別で引っ掛かってしまう学生にとっては、引っ掛かる場所がたくさんあるのは辛いものなのです。
これは何も大学だけではなく、世の中がそういう方向に向かわないといけません。たとえば住民票の申請をするのに何でいちいち男女欄に丸を付けなければいけないのか。あるいは選挙で投票するのに、なぜいちいち投票場の入場券に男女と書いてあるのか。そういう問題を私たちトランスジェンダーは、10年以上、いろいろ問題化して社会に働きかけてきました。実際、ずいぶん減っているのです。私が住んでいる川崎市では、投票場の入場券に以前は男・女とはっきり書いてあったのが、記号化されてあまり目立たなくなっています。大学も同じように、環境整備としてそうした必ずしも必要でない性別記載欄を減らしていく方向で行くべきだと思います。
今ちょうどレポートの採点時期で、昨日も履修者名簿を見ていたのですが、明大の名簿には、名前の欄の尻尾のところに、女子学生だけ「F」という記号が付いています。これは必要でしょうか。前もそんなお話をしたら、名前を呼ぶ先生が、男なら何とか君、女なら何とかさんと、敬称を変える必要があるからというお話でした。でも、1回目の授業のときに先生が「この学生は女子」と個人的にチェックしていけばいいわけで、公的な名簿で性別表記をする必要があるのかということです。そもそもなぜ男子と女子で敬称を変えなければいけないのでしょうか。全員「さん」で問題ないでしょう。私が関わっている大学では、都留文科大学と東京経済大学の名簿には、性別を示す記号はありません。こういうことは慣例でずっとやってきたことなので、それに慣れているとなかなか変えにくいのかもしれませんが、本質的によく考えていただきたいと思います。実際に男女の別が必要なのはごくごく限られた、例えば体育実技などだけだと思います。体育実技だって男女一緒のスポーツでやっている場合は、そんなに必要もありませんね。
④ 何が障害になっているのかを聞く
先ほど申しましたように、基本的には放っておくべきなのですが、性別に悩みがある学生が相談に訪れた場合は、何が問題なのかをきちんと聞くことが大切です。この場合、悩みが性自認の問題なのか、あるいは性的指向の問題なのか、分別すること必要です。ただし、相談に来ている学生自身がよく分かっていないことがけっこうありますから、相談を受ける側がそこらへんを整理しながら聞いていくことが必要になります。その学生にとって何が一番の問題なのか。たとえば、自分は男なのに男が好きということで悩んでいるのか、自分は男なのだけど、どうもそれに馴染めない、自分の中身が女のほうにズレているという悩みなのか、ということです。
実は、前に触れた文科省の全国一斉調査は、この部分の指示がないのです。つまり、性に違和感がある、友達と性のあり方が違うという子供が、それは性的指向が違っているのか、それとも自分の性別に対する違和感なのか、小学校段階できちんと分別がつくはずがないのです。中学生だってあやしいです。それを一緒にして、あたかも性同一性障害の予備軍的に見るのは大きな間違いです。人数的には性同一性障害よりも同性愛のほうが圧倒的に多いはずですから。
先日、朝日新聞の教育欄に、大学におけるLGBT――レズビアン、ゲイ、バイ・セクシャル、トランスジェンダーの学生のサークルがすいぶん増えてきたというニュースが載っていました。明大の私の受講生にも、そういうサークルを立ち上げて熱心に活動しているレズビアンの女子学生がいます。各大学を結ぶインターカレッジ的なつながりもできてきているようです。
ゲイ、レズビアンの学生たちは、自分たちで何とかやっていける人も多いのです。それに対して、性別違和を抱える学生は、身体の問題もありますので、悩みを内に抱えてしまう傾向があり、そういう学生が相談に来る可能性が高いと思います。その場合、最初から性同一性障害という病気と決め付けるのではなくて、何に困っているのかから入るべきです。例えばトイレ。性別の問題が引っ掛かる人には、いわゆる「誰でもトイレ」(多目的トイレ)を使うようにアドバイスするのが一般的ですが、私の講師控室があるリバティタワーの3階は、少し進みすぎていて、車椅子でも入れるトイレが男女別に…女子トイレの中にあるのです。そうなると、またややこしい状況が出てくるわけです。トイレの問題は、性別に悩みがある学生には切実な問題なので、大学のどこかに誰でも使えるユニバーサルなトイレが確保されていることが必要です。
⑤ 知識を提供する
性の問題というのは多様ですので、適当な参考書を紹介して知識を提供して、その多様な性の形態の中からもっとも自分にふさわしいジェンダー&セクシュアリティのあり方を自分で選択させることが大事です。具体的には野宮亜紀、針間克己ほか著『性同一性障害って何? ―一人一人の性のありようを大切にするために (プロブレムQ&A)』(緑風書房、2011年増補改訂版)などがよいでしょう。私もジェンダー論の授業の最初と最後に、「この授業が皆さんにとって一番心地よいジェンダー・セクシュアリティのあり方を見つけるための手がかりになればうれしいです」という話をします。これは性的なマイノリティの人たちも全く同じで、自分が何なのだということをきちんと自分なりに理解をしていかないと、自己肯定感が生まれないのです。セクシュアル・マイノリティはゲイ、レズビアンでもトランスジェンダーでもそうなのですが、最終的にはマジョリティーとは違う自分の性のあり方を、私はこうなのだ、私はこれでいいのだと自己肯定できないと、悩みはいつまでも続いてします。私などもある程度の自己肯定はできても、なかなか100パーセントの自己肯定には至りません。その難しい自己肯定の材料をどう与えていくか、サジェスチョンをしていくか、とても大事だと思うのです。
⑥ 必要な場合は専門医を紹介する
自分の体が嫌で嫌で仕方がないというような強い身体違和、FtMだったら生理が来るたびに死にたくなるとか、MtFだったらシャワーを浴びるたびに自分のペニスを切断したくなるようなケース。あるいは、ジェンダー違和が強くて、家から出られない、学校にも行けないような性別違和感に由来する社会的不適応を訴える学生は、放置できません。放置をすると本当に自殺を企ててしまうか、修学が継続できなくなってしまいます。そういうケースでは、性同一性障害の専門医を紹介して、専門的なカウンセリングを受けるように方向付けることが必要です。
この点については、明治大学駿河台校舎は日本一恵まれています。日本における精神科領域の性別違和、性同一性障害問題の第一人者である針間克己先生が2008年に神田小川町3‐24‐1に「はりまメンタルクリニック」を開院したからです。私はリバティホールで授業をやっていますが、リバティホールからだと信号に引っ掛からなければ3分で行ける距離で、本当にすぐそこです。私が明大で初めて講義を持った2012年前期、「あれ?何か社会人学生にしてもばかにひねた大人が後ろのほうで聞いているな」と思ったら針間先生でした。たまたま先生のクリニックは火曜日の午後が休診で、私の講義が火曜日の午後の1コマ目だったので聴講していたのです。東京大学医学部を出た先生が、私なんかの講義を聞いて少しでも勉強しよういう謙虚な姿勢、すばらしいです。ただ、明大の授業をただ聞きしていたわけですから、何かあったときに少し無理を頼んでも嫌とは言えない立場です。専門的なカウンセリングが必要な学生がいたら、ぜひ紹介してください。残念ながら、性同一性障害の診察で、私が自信を持ってご紹介ができるメンタルクリニックは、東京近辺に3つしかありません。他に千葉県浦安市の阿部輝夫先生の「あべメンタルクリニック」、埼玉県さいたま市の塚田攻先生の「彩の国みなみのクリニック」ですが、針間先生のところが一番近いです。
⑦ 学内で可能な限り対応措置をとる
MtFが学内での女性扱い、FtMが男性扱いを希望する場合は、通称名の学内使用をはじめ可能な限り対応措置をとっていただきたいと思います。ただ、なかなかやっかいなのは、希望する性別への適合度です。一目見て、「あなた、どう見たってそれで男子学生は無理でしょう、女子学生の方が自然でしょう」というようなMtF、あるいは「それで女子学生は無理でしょう」というようなFtMの学生だったら大きな問題はないと思います。しかし「う~ん、微妙と」というケースもしばしばあります。そうしたケースは、ある程度、1年くらいの観察期間が必要だと思います。中には精神的に不安定な学生もいて、ガーッとどちらかの性別に偏って、少しすると熱が冷めるというようなケースもあります。あまり性別をコロコロ変えられるのは、大学の事務としては困るでしょうから、基本的には、4年間、卒業までの継続性を前提に、学生が求める措置を取って欲しいと思います。
⑧ 性別移行プロセスへの協力
在学中に戸籍名を望みの性別にふさわしいものに改名したり、戸籍の性別を変更したりする学生、院生が出てくることは、現在の性別移行システムで十分にありうることです。現在のガイドラインでは、クロスホルモン―男性だった人に女性ホルモンを投与、女性だった人に男性ホルモンを投与すること―は、場合によっては16歳から可能です。戸籍の変更要件は20歳以上になっていますが、外国で性別適合手術を受けるだけならその前でも可能です。つまり、入学以前からクロスホルモン投与を受け、在学中に性別適合手術をして、戸籍の性別を変更して、卒業証書は新しい名前と性別でもらって、望みの性別で社会に巣立つという人生計画を立てる学生が出てくるということです。それは現在、認められている性別移行システムに沿ったものなので、そうした性別移行のプロセスに、大学はできるだけ協力をしてあげてください。
⑨ いっそうの就労支援
問題は、戸籍の性別変更がまだ済んでいない学生、あるいは、性別は移行するけども戸籍の性別まで変えるつもりはない学生の場合です。そうした学生の場合、最大の難関は望みの性別での就労です。私もそれでさんざんそれで引っ掛かってきたわけです。日本の大学は非常勤でトランスジェンダーの教員を任用するところまでは来ていますが、常勤ではまず採らないでしょう。それが日本の現実です。ただ、この点に関しては、日本が遅れているわけではなく、外国だと非常勤でもトランスジェンダーは採用しない国はけっこうあります。日本は非常勤ではあるけれど、トランスジェンダーを大学教員に採用していますという話をしたら、外国の研究者に「great、素晴らしい」言われたことがあります。私の場合、年齢的にもう仕方がないなと諦めていますが、若いトランスジェンダーの学生にとっては、やはり就職が最大の難関です。前から言っていることですが、就職課が格別の配慮、一般学生に不平等にならない程度にできるだけのバックアップをしていただきたい。能力が十分にあるトランスジェンダー学生が性別の問題だけで就職ができないということは、その学生だけでなく、社会全体にとっても損失ですし、それは何とか避けたいと思うわけです。
性同一性障害の場合、会社に入ってから性別移行をしたとして、それを理由にした解雇は違法という判例が固まっていますので、入社してからは首を切れません。性同一性障害を理由に解雇して裁判になったらほぼ確実に会社側が負けます。さすがだなと思ったのは、判例が出た頃に企業の総務課や人事課の人たちが読む専門雑誌に、さっそくその判例が紹介されていました。きちんと勉強している企業の労務管理担当者は知っているはずです。ですが、採用段階での就労差別はかなりあります。「戸籍を変更されてからもう一度当社をご受験ください」という形で門前払いするケースです。ですから、学生にしてみると、とりあえ生得的な性別で入社して、入ってから性別を移行するという手もなくはないです。でも、「就職のときは、そのことを隠していたのか」という信義の問題になりかねませんので、なかなか難しいところです。何度も言いますが、就労問題が最大のネックですので、何とかバックアップしていただきたいと思います。
⑩ 望みの性別で生きて行くための社会訓練の場としての大学
実は今、小・中学校では、性別違和を抱える児童、生徒がいると、隔離的、特別に扱って「どこどこの病院へ行って診断書を取って来てください」というように、問題を性同一性障害医療に委ねてしまう形がけっこう多くなっています。大学レベル、ましてや明治大学みたいなトップクラスの大学だったら、そんな安易な方法は採らないと思います。医療の手に委ねてしまうのではなく、大学という一つの社会で性別違和を抱える学生を受け入れていくという姿勢が望まれるわけです。トランスジェンダーの学生が望みの性別での生活を円滑にできるようになるためには、トレーニング期間が必要です。いずれ望みの性別で社会に出て行かなければならない学生にとって、大学の4年間プラスアルファが、トレーニング、社会訓練の場になるわけです。大学はそれをサポートする方向で対応してほしい、そうした姿勢を持って欲しいということです。
私は2002年に「トランスジェンダーと学校教育」という論文を書いているのですが、私が書いた論文の中で一番読まれません。どうしてなのだろうと思うのですが、どうも、現実の学校現場の先生とだいぶ意識が違うようなのです。たとえば、先生方は「男女別に並べるときにどうしたらいいのですか?」と質問してきます。私が「男女別に並べること自体を考え直した方がよろしいのではないですか」と返事をすると、ものすごく不満な顔をされてしまいます。前例が無いケースが出て来た時には、前例に合わせようとするのではなく、従来のシステムを再検討して新例を開くという姿勢が大事だと思います。
おわりに
2014年2月にタイのバンコクでWPATH2014という国際会議が開催されました。WPATHというのはWorld Professional Association for Transgender Health、トランスジェンダーの健康のための世界専門家会議という団体です。今回が第23回でしたが、今までずっと欧米で開催されていて、今回が初めてのアジア開催でした。そこでアジア・太平洋地域のトランスジェンダーをできるだけ集めて「Trans People in Asia and Pacific」というシンポジウムをやろうということになりました。とはいえ、これがなかなか大変で、トランスジェンダーは、お金持ちではない人がほとんどなので、飛行機代、滞在費を世界開発機構、世界エイズ会議など国際連合の4機関が資金提供して、アジア・パシフィック10カ国、最終的は日本も入って11カ国のトランスジェンダーがバンコクに集まりました。私も招待状をもらったのですが、日本はOECD加盟国で、世界開発機構ではお金を出す立場でお金をもらう立場ではない、だから日本の研究者には資金提供はできないから旅費と滞在費は自分持ちで来てくれ、というという話で、「それはあんまりな・・・」と思いました。お金のことはともかく、世界のどの国にも、トランスジェンダーはいるということです。いろいろ困難な状況はあるけれども、それぞれの国でそれぞれの社会の中で頑張って生きているわけです。
そうしたシンポジウムで、とても考えさせられたことがありました。全部で12人が各国の事情を報告したのですが、12人のうち11人がMtFなのです。私以外のMtFは、フィリピン、インドネシア、タイ、ネパール、インド、そしてトンガ、みんな英語がペラペラで、パワーポイントできちんと資料を作ってきて、しっかりプレゼンテーションをできる能力があります。ところが、FtMの人はそうしたプレゼンテーションができないのです。12人中1人だけ、しかもニュージーランドの活動家でしたから、少し事情が違います。
どういうことかと言いますと、アジアの国で、女性として生まれて女性としての教育を受けてきた人は、開発途上国における男女の教育格差を被ってしまうのです。女で育てられると、なかなか十分な教育が受けられない。それで男になっても、一定の知的レベルが求められる社会的活動がなかなか難しいのです。
この例のように、性別を変えて生きる人たちにとって、大事なのは教育なのです。社会に出て一般の人よりももっと厳しい状況の中で生き抜いていくための力になるのは教育です。教育をきちんと受けられるかどうかが鍵なのです。実は、日本もそういう傾向があって、日本で今FtMがこんなに多くなっているのに、日本から参加して報告したメンバーは2人ともMtFでした。残念ながら、国際学会で通用するレベルのプレゼンテーションができるFtMは、日本ではほとんどいません。なぜかというと、FtMの最終学歴は、MtFに比べて明らかに低く、高校中退レベルの人がかなりいます。そうした状況は徐々に改善されてきていますが、制服とかいろいろなことで引っ掛かってしまって修学が継続できず、その結果、低学歴で終わってしまって、学力やスキルが伴わないFtMがまだかなりいるのです。
社会の中でより良く生きていくための力を大学教育の中で身に着ける必要性は、一般学生でもトランスジェンダーの学生でもまったく変わりません。むしろトランスジェンダーであるがゆえにその必要性は高いのです。そのためには、何度も言うように修学が継続できる……きちんと卒業ができて、できることなら望む方面に就職ができるようなバックアップを、明治大学だけではなく全国の大学でぜひとっていただきたいと思います。
だいたい予定の時間になりました。3年前、明大に非常勤で呼んでいただいた時から、いつか講義以外でもお役に立てる機会があればと思っていましたので、今日はこういう機会をいただいて、とてもうれしかったです。どうもありがとうございました。
(紙幅の都合により、講師紹介及び質疑応答は割愛させていただきました。)
【参考文献】
三橋順子「『性』を考える-トランスジェンダーの視点から-」
(シリーズ 女性と心理 第2巻『セクシュアリティをめぐって』 新水社 1998年)
三橋順子「トランスジェンダーと学校教育」
(『アソシエ』8号 御茶の水書房 2002年)
三橋順子「トランスジェンダーをめぐる疎外・差異化・差別」
(シリーズ「現代の差別と排除」第6巻『セクシュアリティ』明石書店 2010年)
その記録が『学生相談 2014年度 学生相談室報告』(明治大学学生支援部 2015年6月)に掲載されました。
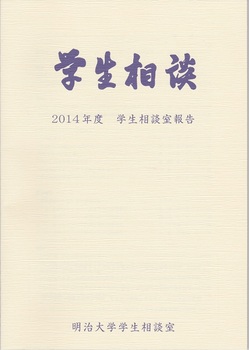
学外者には入手が難しい学内誌なので、全文をここに掲載します。
--------------------------------------
明治大学 第53回学生相談室夏期セミナー 講演
「性別違和感を抱く学生に教職員はどう対応していくか」
2014年7月27日(日)
文学部 兼任講師 三橋 順子
はじめに
皆さん、こんにちは。三橋順子です。明治大学に非常勤講師で呼んでいただいて3年目になります。簡単に自己紹介しますと、私は、男性から女性へのトランスジェンダーですが、戸籍は生まれたときの性別、名前で変えておりません。1995年くらいから社会的には女性として、講演、著述、あるいは教育活動をしてきました。女性としてそれなりに実績はあったわけですが、実は、明治大学から講師のオファーがあったとき、すんなりとはいきませんでした。「お引き受けします」とお返事した後、履歴書段階で1~2カ月ほど手続きが止まってしまったのです。理由は履歴書の性別欄の記載です。私は履歴書の性別欄を空欄で提出しました。私の性自認からして「男」とは書けませんし、男女雇用機会均等法の趣旨からして性別の記載は強要されるべきではないと考えますので。それに対して人事課は「性別欄が空欄なのは前例が無い。戸籍通りちゃんと男性と記載してください」ということでした。私から明大で講義をさせてくれとお願いしたわけではなく、明大から依頼してきたことですので、「それなら結構です」と申しましたら、やっと人事が動いたということがありました。性別記載で引っ掛かってしまうということが、まだまだ日本の現実としてあるということです。明治大学だけが理解がないわけではなくて、日本社会のシステムが男女二元で、しかも硬直的で融通が利かない。それが性別を越えて生きるトランスジェンダーの人たちをどれだけ生きにくくしているかという事例としてお話しました。今日はそうした問題をどのようにクリアしていけばよいかというお話をいたします。
1 基礎知識として
今日のテーマは「性別違和感を抱く学生に」ということですが、最初に基礎知識的なことを、三つお話をしておきましょう。
(1) 同性愛とトランスジェンダー
一つ目は、同性愛とトランスジェンダーの違いです。学生も一番ここが分からないと言うので、こんな説明をします。同性愛は、男が好きか女が好きかという性的指向sexual orientation問題であって、自分が男であるか女であるかというgender identity性自認(性同一性)の問題ではありません。誰を好きになるかという相手の性別がマジョリティーの人と違っているのが同性愛です。トランスジェンダーは自分が男であるか女であるかという性自認gender identityの問題で、男が好きか女が好きかというsexual orientationの問題ではありません。男として生きるか女として生きるかという自分の性別の在り方の問題です。
(2) 性別違和感(Gender Dysphoria=GD)とは?
基礎知識の二つ目は、性別違和感gender dysphoriaとは何かということです。一般的には、自分の性別に対する心理的な違和感が性別違和感です。性別違和感を考える場合、基本になるのは自分の性自認、自分を男と思うか、女と思うかということです。自分は男だと思っているのに、身体が女である、生理が来る。あるいは、自分が女だと思っているのに、男性の身体である、声変わりをしてしまう、髭が生えてくるというような性自認と身体の性のズレが身体違和です。
ズレ(違和感)はそれだけでなく、性自認と社会的性(ジェンダー)の間にも生じます。自分が女だと思っているのに、世の中からは男として扱われる。「あなたは、戸籍は男でしょう。だから男として扱いますよ」ということです。自分は男だと思っているのに、「あなた、戸籍上は女でしょう。女性のほうに入りなさい」と言われてしまう。性別違和感は性自認と身体の間、性自認と社会的な扱いの2カ所で生じます。ここがポイントです。身体のほうの違和感は大学でどうこうできる話ではありませんので、医学的な対処が必要になりますが、社会的な扱いに関しては、世の中の一部である大学でも対応できる問題ということになります。
心が女なのに身体が男であるというのはやはり辛いわけで、何とかズレを直そう、整合性を回復しようとします。自分は女だと思っているのに世の中から男として扱われるというのはとてもきついことです。さっきの私の履歴書の話ですが、あの時は精神的に相当きつかった、かなり落ち込みました。そのあたりは、性別違和感がない方にはなかなか理解をしていただけないと思いますが。性別違和感というのは、ギザギザ、トゲトゲした、やっかいな嫌なものなので、何とかそれを解消しようと努力します。つまり、性別違和感は、性別を移行していく原動力になるわけです。
(3) 性同一性障害(Gender Identity Disorder=GID)とは?
基礎知識の三つ目は、性同一性障害とは何かということです。性同一性障害は、Gender Identity Disorderという英語の疾患名の日本語訳です。先ほど、性別違和感は性自認(性同一性)gender identityと身体的性sex、性自認と社会的役割gender roleの2カ所で生じると申しましたが、その2カ所の不一致に起因する性別違和感がどんどんひどくなっていった結果、著しい精神的苦痛や、社会生活・職場における機能障害、つまり、社会生活がうまくいかない、あるいは学校や職場でそこにうまく身をおけないという形になって、医療のサポートが必要になった状態をいう精神疾患概念です。「性同一性障害は病気ではないと思います」という学生がときどきいますが、「性同一性障害というのは精神疾患の名称なので、それを病気でないというのは概念矛盾で、成り立ちませんよ」と説明します。ただし、性同一性障害というのは性別違和感を原因とする社会的不適応の病であって、性別違和感を持っていること自体は病気ではないということです。ここはマスメディアが心の性と身体の性がズレていることが病気だというような説明をすることが多いのですが、それは間違いです。実は、自分の性の在り様が何かズレている、違和感があるという人は、けっこう多いのです。それは違和感の程度の問題でして、違和感があること自体を病にしてしまうのは、問題があると思います。そのような状態をとても苦痛を感じていて、社会生活上、不適応を起こしていることが病であると捉えないといけないと思います。
2 「性別違和」の現在
(1) この15年間の流れと最新の動向
次に、日本で性別移行の問題が社会的に浮上したこの15年ぐらいの流れをざっとおさらいしておきます。もちろんそれ以前から、性別を変えようと努力したいろいろな人がいたわけですが、やはり起点は1996年です。私立の埼玉医科大学の倫理委員会が、形成外科の教授から申請があったSex Reassignment Surgery、「性転換手術」、現在で言う「性別適合手術」を正当な医療行為として承認したことがニュースになりました。これはあくまでも一大学の倫理委員会の判断で、本来はそんなに大げさに報道することではないと思うのですが。それを受けて97年の5月に、日本精神神経学会が「性同一性障害に関する答申と提言」という、私たちが「ガイドライン」と呼んでいるものを出しました。これもかなり大きなニュースになって、このあたりから性同一性障害という病名が『現代用語の基礎知識』などにも載るようになってきました。98年10月に埼玉医科大学が「ガイドライン」に基づいたものとして初めての性別適合手術を実施しました。あくまでもガイドラインに基づいたものとしては初めての手術であって、性別適合手術自体は日本では1951年、世界でも指折りに早い時期からやっています。これは私が調べたことですが。
そんな流れの中で2002年の8月に六大学「学生相談」連絡会議で「性別違和を抱える学生をどう受け入れるか」という講演をさせていただきました。会場は中央大学で、私は中央大学の社会科学研究所の研究員という立場でした。その、きっかけは明治大学だったように覚えています。明大で、自分は男ですという女子学生、つまりFtM(Female to Male)の学生さんが出てきて、教授会で問題になったというお話でした。「問題になったというのは、対策が問題になったのですか」とうかがったら、そうではなく、「『明治大学の学生ともあろうものがけしからん』とある教授が言い出した」というお話でした。今からすると、とんでもない無理解ですが、この頃は、明大だけがそうだったわけではありません。
早稲田の学生部の方が「うちはいないと思います」と言ってきたので、「早稲田大学の学生数って6万人でしたよね。6万人いていなかったら、それはそういう人たちを選別して落としているという意味ですか」と尋ねたら「いや、そんなことしていません」と言う。「だったら、いるに決まっているんです。プライバシーの問題があるから誰ということは言えませんが、早稲田大はニューハーフ業界でもかなり名門ですよ」とお返事しました。法政大はカルーセル麻紀さんのお師匠さんの「青江のママ」さんが法政大の学徒出陣ですからもっと名門ですね。後でまた申しますが、性別の悩みを持った学生さんというのは、東京の私立の大きな大学だったら確率的に必ずいるのです。ただ、それがきちんと認識されていない、あるいは本人が隠しているというだけの話なのです、ということをそのときの講演で、お話しました。
あの講演、少しは効果があったかなと思います。例えば慶應義塾大学で、MtF(Male to Female)の学生さんの就職がなかなかきついということで、大学の職員として雇用してくださった例がありました。もちろん、本人にそれだけの能力があったからでしょうが。
大きく流れが変わったのは、2003年です。7月に「性同一性障害者の性別取り扱いの特例法」(GID特例法)が成立し、翌年の7月に実施されました。この7月でちょうど実施10周年になります。これを大学に関係させて言うと、大学の学部あるいは大学院在学中に学生・院生が性別の変更を行うことが合法的に現実のものになったということです。あるいは、教職員の方で性別を変更する方が出てくるかもしれないということです。
少し飛びますが、2013年、文部科学省が全国の小中高校と支援学級を対象に、いわゆる性別違和に悩む児童、生徒の一斉調査というものをやりました。本当に一斉調査なのかという疑問もあるのですけれども、私は良い面と問題な面と両方を感じています。結果的に性別違和を持つ児童、生徒は606人。うち性同一性障害の診断をすでに受けている児童、生徒が165人という結果が出ました。実際はもっといるはずです。ただこれも、どの範囲を性別違和と捉えるかによってだいぶ人数が違ってきます。何度も言いますが、この問題がとてもややこしいのは、どの程度の性別違和感までを病理として把握するかということです。
例えば、私は明大で260人ぐらい受講生がいます。後期、山梨の都留文科大学でも240人ぐらいを持っています。だいたいその200人越えぐらいの人数で、コメントシートやレポートなどで、自分の性別違和を書いてくる学生がだいたい毎年2~3人はいます。不思議なことになぜか女子学生が多いのですが。周囲が女の子扱いするのが嫌で学校に行きたくなかったというような、かなり辛い性別違和を経験している例もあります。その時点で診断を受けたら、多分、性同一性障害の診断が出るだろうと思います。ところが、その学生とたまたま面談すると、一応女子学生で適応していたりします。本人は「まだ今でも違和感があります、すっきりしない部分はあります。だから先生の授業を取りました。でも何とか女子大生でやっています」という感じですね。そういう学生たちは、今後、病院へはたぶん行かないでしょう。だからそこまでを病理の範囲に入れるか入れないかで、かなり話は違ってくるのです。
最新の状況についてもお話ししておきましょう。実は今、国際的な動きがいろいろあります。2013年5月にアメリカ精神医学会のマニュアル「精神疾患の分類と診断の手引き」の改定が行われ、「DSM-5」と言われる第5版が施行されました。そこで、gender identity disorder、日本語でいう性同一性障害をgender dysphoria性別違和という病名に置き換えました。ただ病名を変更しただけではなく、診断基準も手直ししているので、置き換えたという言い方をしています。その結果、アメリカでは、すでにgender identity disorder、性同一性障害という病名はなくなりました。やはり「disorder」という部分に抵抗感を強く持つ当事者が多いのです。これはアメリカの診断基準ですから、どう変えようが、本来なら日本は関係ないはずなのですが、実際には日本の精神科医もかなり影響を受けています。日本のメンタルクリニックや心療内科へ行くと、「どうされました?」と尋ねる先生の後ろの書棚に分厚いDSMのマニュアルが飾ってあることが多いのです。ちゃんと読んでいるかどうかは知りませんが、影響力はすごくあるのです。
さらに、日本は国際連合に加盟していて、国連の専門機関である世界保健機関WHOのメンバーです。WHOにはICDと言う疾患リストがありまして、本来はこちらが日本で診断マニュアル化されるべきものです。そのICDの改訂作業が現在進行中で、新しい第11版、ICD-11の施行が2017年に予定されています。性別違和に関して、かなり大きな改訂になりそうで、まず確定的なのは、gender identity disorder性同一性障害はなくなります。何という病名に置き換えるかまだ決定ではないのですが、どうもgender incongruence、性別不一致という病名に置き換えられそうです。さらに重要な変更は、今までの精神疾患のカテゴリーから「その他の疾患」のカテゴリーに移す案が有力視されています。そこらへんの情報は2014年2月にバンコクの国際学会で仕入れてきた最新のもので、日本で知っている人はまだそんなに多くありません。
このまま実現すれば、gender identity disorder性同一性障害という病名は、国際的な疾患リストから完全に消えます。ですから、日本でも病名を変えなければなりませんし、「性同一性障害者の性別取り扱いの特例法」という法律名も変えなければいけなくなります。そして性別移行の脱精神疾患化が達成されることになりますが、この点はまだ少し不確定な要素があります。
ということで、現在は過渡期でありまして、2000年代に入って高まってきた性別移行の脱精神疾患化という世界的な流れが結実するかどうか、微妙なところに来ています。日本はそういう世界的な潮流にはまったく鈍感ですが、いずれそういう方向に行かざるを得ない、行くべきだということです。
(2) 性別移行システムの問題点
問題点を整理しておきましょう。2000年代、「GID特例法」制定の前後からにメディアが活発に性同一性障害について報道をしました。しかし、その報道は医療側の言説をそのまま流すという形で、病気だから仕方ないから戸籍を変えるのだという流れになってしまい、本来、考えなければいけない性的マイノリティの人権という視点が希薄化してしまいました。病気ということなら認めましょうという流れ、性別移行の病理化が一気に進行してしまったのです。それでうまくいった人もいるわけで、それはそれで結構なのですが、世界の流れは、2000年代に入って、むしろ病理化ではなく脱病理化、具体的には、性別移行を精神疾患概念からどうやって外していくかという脱精神疾患化の方向に向かっていました。ところが、日本は世界的な潮流とまったく逆行して、この10年間に病理化を推進してきたわけで、大学も「対応しますから、診断書を出しなさい」、さらに高校や中・小学校まで「診断書を出しなさい、診断書を出したら対応しますよ」という、形になってしまいました。性同一性障害概念の流布によって、性別移行の病理化が極端に進みすぎてしまい、病理を前提にしないと社会的対応ができないような仕組みができてしまいました。これは大きな問題です。今後、こうした病理を前提にしたやり方を人権を前提にした考え方に変えていかなければなりません。
先ほど申しましたように、弱い性別違和を持つ人は、けっこうたくさんいます。おそらく100人に数人レベルでいると思います。弱い性別違和をもつ人たちの多くは自然に解消する、あるいは自分で折り合いがつく可能性があるわけで、病理化する必要はないのです。ところが、医者の中には、性別違和感を持つ人すべてを病理化しようとする、性同一性障害の診断基準から外れるような弱い違和の人までを性別違和症候群として把握するような形が理想とする医師もいます。病理化の徹底ですね。そこには、自分にふさわしい性の在り様を自分で選んで決定するのは人権の一つであるという発想がないわけで、まったく困ったものです。
性別移行の当事者の方も、戸籍の性別変更が目的化してしまって、「GID特例法」の要件をクリアするため、ともかく性別適合手術をするという状況が生じています。必ずしもしなくてもいい手術まで受けてしまう過剰な医療化です。今、世界的にはIDカードなどの性別の書き換えに手術を要件とするのは人権侵害だという方向になっています。つい1カ月ほど前に、WHOが性別の移行に関して性別適合手術を要件化するのは人権侵害という勧告を出しました。日本の「GID特例法」は手術して生殖機能を喪失しないと性別の変更は認めない形ですから、WHOの勧告に完全に抵触します。日本の現状は、世界の性転換法の中で人権意識の低い、遅れた形になってしまっています。
病理化の徹底、過剰な医療化を進めながら、実は国内の医療施設がまったく足りません。患者は激増したのに、医療施設が増えないのです。だから手術をするのにみんな海外、主にタイへ行かざるを得ない。日本の医療というのは、面倒くさいことは全部外注してしまう傾向がありますが、まさにその典型です。
過剰な医療化、あるいはアンバランスな医療化の弊害が実際に出てきています。性同一性障害の診断を受けたのにジェンダーの移行がなかなか進まない。これは何か違う精神的な原因で引っ掛かっていると思われます。さらには、性別適合手術を受けて戸籍変更までしながら、新しい性別で社会適応ができない。たとえば、身体の外形も戸籍も女になりました。だけれど女性として社会適応ができませんというケースが増えているように思います。大学でこういう形が出てくると、なかなか対応が難しいことになります。
(3) 性別違和の人口比
性別違和を抱える人はだいたいどのぐらいの比率なのか、皆さんけっこう気になるのではないかと思いますので、その話をしましょう。
もともと欧米では、私のような男性から女性への移行を望むMtFが3万人に1人、逆に女性から男性への移行を望むFTMが10万人、つまり、MtFとFtMの比率は3対1と言われていました。このデータ、実はあまり信用度が高くないのですが、日本で90年代末に性同一性障害の問題が浮上したとき、どうも日本はFTMが少し多いのではないか、MtFが1~2万人に1人、FtMが3万人に1人、MtF対FtMの比率は2対1くらいに考える人が多かったと思います。ところが、どんどんどんどん差が詰まっていきまして、2000年代の初めぐらいには、MtF、FtMを通じてだいたい1~2万人に1人、MtF対FtMは1対1に近い。もうこの時点で、世界の研究者から「日本のデータが変じゃないか?」と言われ始めていました。さらに2008年ぐらいから、中高大学生ぐらいの若いFtMが急増して、MtFとFtMの比率が1対1.5~2と完全に逆転してしまいます。
私の授業では、2008年に放送された「ラストフレンズ」というテレビドラマの中で、ボーイッシュなレズビアンっぽい女性が性同一性障害だと思ってメンタルクリニックに行くシーンを学生に見せて、メディアのミスリードが現実世界に影響しているのではないかという話をするのですが、2008年ぐらいから様子ががらっと変わってきました。その後も女性から男性になりたい若い人の増加傾向がずっと続いていて、現状MtFとFtMの比率は1対3、90年代とは完全に裏返しになっています。人口比で言うと、MtFが1万人に1人か2人。MtFはあまり変わっていません。FtMが1万人に3人くらいという状況です。現状、日本は世界で最も顕著にFtMの比率が高い国になっています。
性別違和が重く性別適合手術をして戸籍の性別変更をした人が、2013年12月末現在で、全国で4353人というデータが出ています。このペースだと2014年末には5000人を超えるのは確実ですので、だいたい2万人に1人が戸籍の性別を変更しているということになります。
10年前に法律ができたときには、こんなに多いとは思いませんでした。年間50人ぐらいだろうと予想していました。年間50人だと10年で500人ですから、10倍ぐらい予想より多いというのが今の状況です。
なぜ、こんなに多いのか、そしてFtMの比率がこんなに高いのか。とても重要な問題なのですが、誰もきちんとした説を出していません。私が頑張って考えているのですが…。要は、全体に増加傾向にあるということと、特にFtMが増えているということを頭に置いておいてください。
それから、2010年代に入ると、あるお医者さんの言い方で「確信的でない受診者」が増えています。以前、メンタルクリニックに来る人は、かなり確信的に「私は、心は女なのに、男性なのです」とか、逆に「俺は絶対男だと思うんだけど、女なんで何とかしてください」というタイプが圧倒的でした。ところが最近は、「自分の性別がよく分からない」とい言う人が増えてきています。これをXジェンダーといいます。数学で不明数をXとするのと同じです。そういう人たちは「自分はXです」と言います。男ではないと思うけれども女でもないMtX。女ではないけれども男でもないFtXというタイプです。これが現実にかなり増えていて、理由を考えなければと思うのですが、まだ調査が進んでいません。私は弱い性別違和までを病理化してしまった結果、本来だったら男女どちらかに折り合いをつけるべきところを折り合いがつけられない人が増えてきているのだろうと思っています。それから女性に多いと思うのですが、いわゆる成熟拒否、大人の女性になりたくない。できるだけ猶予期間を長引かせたいという人も含んでいると思います。
こういう現状で、数値モデルを整理しておきますと、弱い性別違和を持つ人が100人に2~3人、医療が必要な強い性別違和を持つ人がそのうちの100人に1人ぐらい、つまり1万人に2~3人という話になります。さらに戸籍変更に至るまでの人は、そのうちの8~9人で、10万人に5人、2万人に1人。ここはかなり確定的なデータが出ていますので、こんなモデルが作られるわけです。私はどちらかと言うと少なめに見積もっていますが、そんなに違ってはいないと思います。
明治大学の学生数は2万9千人だそうです。このモデルに合わせると、強い性別違和を持つ学生は1万人に2~3人ですから、6~9人ぐらいいて当たり前ということです。1万人に2~3人というのは全人口比ですから、大学在学年齢だともっと多いと思います。何10人ということではありませんが10数人いてもおかしくないということです。何度も申しますが、いて当たり前だという認識がとても大事です。
さらに言うと、まさに10代後半ぐらいの年齢層では、自分の性別がよく分かりませんというXジェンダー的な学生がだいぶ増えているはずです。おそらく「性同一性障害」のカテゴリーに入る学生と同じくらいいるかもしれません、かなり強い性別違和を持つ学生が仮に10人いたとしたら、曖昧な形で何か性別に悩んでいるような学生も、もう10人ぐらいはいるという勘定です。これだけいたらもう珍しい話ではありませんので、そういう学生が相談に来た時の対応マニュアルをきちんと作っておくべきです。ただし、マニュアルは、個々のケースに応じて弾力的に運用することが大事です。
3 大学はどう対応すべきか
では、大学は具体的にどういう対応をしていけばいいのかについてお話しします。ここからは私の主観的な意見になっていくわけですが、実を言うと12年前にお話ししたことと基本は変わっていません。自分でも頑固だなとは思いますが、12年前から言ってきたことが今、現実になっている感じがありますので、少し自信を持っています。
① いて当たり前という基本認識
先ほども申しましたように、ある程度の規模の大学なら強い性別違和感を持つ学生が在籍しているのは確率的に当然で、まったく特異なことではありません。いて当たり前だという基本認識を持ち、いると思って対応すべきなのです。不思議なことでも特異なことでもないということです。
② 基本的には本人の自主性に任せる(放っておく)
異性装、身体の性別とは違う服装をするとか、性別を越えて生きるということ自体は、病でも性的逸脱でもありません。客観的には「変わり者」かもしれませんが、現在の日本では法律で禁止されているわけでもありません。日本で異性装が違法だったのは、明治5~6年から14年(1881)までの約10年間、文明開花期だけです。基本的に、服装表現、性別表現、ジェンダーの選択は個人の自由で、人権として認められるべきものです。つまり、本人の自主性にまかせるべき問題で、そうした学生がいたからといって、大学のほうから積極的に介入する必要はありません。基本的には放っておくべきことなのです。性同一性障害なんていう話が出てくる以前にも、書類上は男子学生だけどずっと女の格好で大学に通っていましたという人は実際にいます。もちろん大学側は気付いていたはずですけど、処分するようなことはできませんし、結局そのまま「あいつは変わっているな」で卒業してしまったという話です。基本的には放っておく、でも、なにか困って相談に来たら、ちゃんと対応するということが大事なところです。
③ 環境整備に努める
性別を移行したい学生にとって一番困るのは、学生名簿の男女欄など、学内における性別記載です。日本の大学、例えば文学部だったら文学士という学位を出します。文学士男とか、文学士女という学位ではないわけで、男だろうが女だろうが……女子大は別ですが、明大は共学なので、いちいち学生名簿に男女欄とか男女の識別記号はいらないはずです。学生証の性別記載欄も同様です。性別で引っ掛かってしまう学生にとっては、引っ掛かる場所がたくさんあるのは辛いものなのです。
これは何も大学だけではなく、世の中がそういう方向に向かわないといけません。たとえば住民票の申請をするのに何でいちいち男女欄に丸を付けなければいけないのか。あるいは選挙で投票するのに、なぜいちいち投票場の入場券に男女と書いてあるのか。そういう問題を私たちトランスジェンダーは、10年以上、いろいろ問題化して社会に働きかけてきました。実際、ずいぶん減っているのです。私が住んでいる川崎市では、投票場の入場券に以前は男・女とはっきり書いてあったのが、記号化されてあまり目立たなくなっています。大学も同じように、環境整備としてそうした必ずしも必要でない性別記載欄を減らしていく方向で行くべきだと思います。
今ちょうどレポートの採点時期で、昨日も履修者名簿を見ていたのですが、明大の名簿には、名前の欄の尻尾のところに、女子学生だけ「F」という記号が付いています。これは必要でしょうか。前もそんなお話をしたら、名前を呼ぶ先生が、男なら何とか君、女なら何とかさんと、敬称を変える必要があるからというお話でした。でも、1回目の授業のときに先生が「この学生は女子」と個人的にチェックしていけばいいわけで、公的な名簿で性別表記をする必要があるのかということです。そもそもなぜ男子と女子で敬称を変えなければいけないのでしょうか。全員「さん」で問題ないでしょう。私が関わっている大学では、都留文科大学と東京経済大学の名簿には、性別を示す記号はありません。こういうことは慣例でずっとやってきたことなので、それに慣れているとなかなか変えにくいのかもしれませんが、本質的によく考えていただきたいと思います。実際に男女の別が必要なのはごくごく限られた、例えば体育実技などだけだと思います。体育実技だって男女一緒のスポーツでやっている場合は、そんなに必要もありませんね。
④ 何が障害になっているのかを聞く
先ほど申しましたように、基本的には放っておくべきなのですが、性別に悩みがある学生が相談に訪れた場合は、何が問題なのかをきちんと聞くことが大切です。この場合、悩みが性自認の問題なのか、あるいは性的指向の問題なのか、分別すること必要です。ただし、相談に来ている学生自身がよく分かっていないことがけっこうありますから、相談を受ける側がそこらへんを整理しながら聞いていくことが必要になります。その学生にとって何が一番の問題なのか。たとえば、自分は男なのに男が好きということで悩んでいるのか、自分は男なのだけど、どうもそれに馴染めない、自分の中身が女のほうにズレているという悩みなのか、ということです。
実は、前に触れた文科省の全国一斉調査は、この部分の指示がないのです。つまり、性に違和感がある、友達と性のあり方が違うという子供が、それは性的指向が違っているのか、それとも自分の性別に対する違和感なのか、小学校段階できちんと分別がつくはずがないのです。中学生だってあやしいです。それを一緒にして、あたかも性同一性障害の予備軍的に見るのは大きな間違いです。人数的には性同一性障害よりも同性愛のほうが圧倒的に多いはずですから。
先日、朝日新聞の教育欄に、大学におけるLGBT――レズビアン、ゲイ、バイ・セクシャル、トランスジェンダーの学生のサークルがすいぶん増えてきたというニュースが載っていました。明大の私の受講生にも、そういうサークルを立ち上げて熱心に活動しているレズビアンの女子学生がいます。各大学を結ぶインターカレッジ的なつながりもできてきているようです。
ゲイ、レズビアンの学生たちは、自分たちで何とかやっていける人も多いのです。それに対して、性別違和を抱える学生は、身体の問題もありますので、悩みを内に抱えてしまう傾向があり、そういう学生が相談に来る可能性が高いと思います。その場合、最初から性同一性障害という病気と決め付けるのではなくて、何に困っているのかから入るべきです。例えばトイレ。性別の問題が引っ掛かる人には、いわゆる「誰でもトイレ」(多目的トイレ)を使うようにアドバイスするのが一般的ですが、私の講師控室があるリバティタワーの3階は、少し進みすぎていて、車椅子でも入れるトイレが男女別に…女子トイレの中にあるのです。そうなると、またややこしい状況が出てくるわけです。トイレの問題は、性別に悩みがある学生には切実な問題なので、大学のどこかに誰でも使えるユニバーサルなトイレが確保されていることが必要です。
⑤ 知識を提供する
性の問題というのは多様ですので、適当な参考書を紹介して知識を提供して、その多様な性の形態の中からもっとも自分にふさわしいジェンダー&セクシュアリティのあり方を自分で選択させることが大事です。具体的には野宮亜紀、針間克己ほか著『性同一性障害って何? ―一人一人の性のありようを大切にするために (プロブレムQ&A)』(緑風書房、2011年増補改訂版)などがよいでしょう。私もジェンダー論の授業の最初と最後に、「この授業が皆さんにとって一番心地よいジェンダー・セクシュアリティのあり方を見つけるための手がかりになればうれしいです」という話をします。これは性的なマイノリティの人たちも全く同じで、自分が何なのだということをきちんと自分なりに理解をしていかないと、自己肯定感が生まれないのです。セクシュアル・マイノリティはゲイ、レズビアンでもトランスジェンダーでもそうなのですが、最終的にはマジョリティーとは違う自分の性のあり方を、私はこうなのだ、私はこれでいいのだと自己肯定できないと、悩みはいつまでも続いてします。私などもある程度の自己肯定はできても、なかなか100パーセントの自己肯定には至りません。その難しい自己肯定の材料をどう与えていくか、サジェスチョンをしていくか、とても大事だと思うのです。
⑥ 必要な場合は専門医を紹介する
自分の体が嫌で嫌で仕方がないというような強い身体違和、FtMだったら生理が来るたびに死にたくなるとか、MtFだったらシャワーを浴びるたびに自分のペニスを切断したくなるようなケース。あるいは、ジェンダー違和が強くて、家から出られない、学校にも行けないような性別違和感に由来する社会的不適応を訴える学生は、放置できません。放置をすると本当に自殺を企ててしまうか、修学が継続できなくなってしまいます。そういうケースでは、性同一性障害の専門医を紹介して、専門的なカウンセリングを受けるように方向付けることが必要です。
この点については、明治大学駿河台校舎は日本一恵まれています。日本における精神科領域の性別違和、性同一性障害問題の第一人者である針間克己先生が2008年に神田小川町3‐24‐1に「はりまメンタルクリニック」を開院したからです。私はリバティホールで授業をやっていますが、リバティホールからだと信号に引っ掛からなければ3分で行ける距離で、本当にすぐそこです。私が明大で初めて講義を持った2012年前期、「あれ?何か社会人学生にしてもばかにひねた大人が後ろのほうで聞いているな」と思ったら針間先生でした。たまたま先生のクリニックは火曜日の午後が休診で、私の講義が火曜日の午後の1コマ目だったので聴講していたのです。東京大学医学部を出た先生が、私なんかの講義を聞いて少しでも勉強しよういう謙虚な姿勢、すばらしいです。ただ、明大の授業をただ聞きしていたわけですから、何かあったときに少し無理を頼んでも嫌とは言えない立場です。専門的なカウンセリングが必要な学生がいたら、ぜひ紹介してください。残念ながら、性同一性障害の診察で、私が自信を持ってご紹介ができるメンタルクリニックは、東京近辺に3つしかありません。他に千葉県浦安市の阿部輝夫先生の「あべメンタルクリニック」、埼玉県さいたま市の塚田攻先生の「彩の国みなみのクリニック」ですが、針間先生のところが一番近いです。
⑦ 学内で可能な限り対応措置をとる
MtFが学内での女性扱い、FtMが男性扱いを希望する場合は、通称名の学内使用をはじめ可能な限り対応措置をとっていただきたいと思います。ただ、なかなかやっかいなのは、希望する性別への適合度です。一目見て、「あなた、どう見たってそれで男子学生は無理でしょう、女子学生の方が自然でしょう」というようなMtF、あるいは「それで女子学生は無理でしょう」というようなFtMの学生だったら大きな問題はないと思います。しかし「う~ん、微妙と」というケースもしばしばあります。そうしたケースは、ある程度、1年くらいの観察期間が必要だと思います。中には精神的に不安定な学生もいて、ガーッとどちらかの性別に偏って、少しすると熱が冷めるというようなケースもあります。あまり性別をコロコロ変えられるのは、大学の事務としては困るでしょうから、基本的には、4年間、卒業までの継続性を前提に、学生が求める措置を取って欲しいと思います。
⑧ 性別移行プロセスへの協力
在学中に戸籍名を望みの性別にふさわしいものに改名したり、戸籍の性別を変更したりする学生、院生が出てくることは、現在の性別移行システムで十分にありうることです。現在のガイドラインでは、クロスホルモン―男性だった人に女性ホルモンを投与、女性だった人に男性ホルモンを投与すること―は、場合によっては16歳から可能です。戸籍の変更要件は20歳以上になっていますが、外国で性別適合手術を受けるだけならその前でも可能です。つまり、入学以前からクロスホルモン投与を受け、在学中に性別適合手術をして、戸籍の性別を変更して、卒業証書は新しい名前と性別でもらって、望みの性別で社会に巣立つという人生計画を立てる学生が出てくるということです。それは現在、認められている性別移行システムに沿ったものなので、そうした性別移行のプロセスに、大学はできるだけ協力をしてあげてください。
⑨ いっそうの就労支援
問題は、戸籍の性別変更がまだ済んでいない学生、あるいは、性別は移行するけども戸籍の性別まで変えるつもりはない学生の場合です。そうした学生の場合、最大の難関は望みの性別での就労です。私もそれでさんざんそれで引っ掛かってきたわけです。日本の大学は非常勤でトランスジェンダーの教員を任用するところまでは来ていますが、常勤ではまず採らないでしょう。それが日本の現実です。ただ、この点に関しては、日本が遅れているわけではなく、外国だと非常勤でもトランスジェンダーは採用しない国はけっこうあります。日本は非常勤ではあるけれど、トランスジェンダーを大学教員に採用していますという話をしたら、外国の研究者に「great、素晴らしい」言われたことがあります。私の場合、年齢的にもう仕方がないなと諦めていますが、若いトランスジェンダーの学生にとっては、やはり就職が最大の難関です。前から言っていることですが、就職課が格別の配慮、一般学生に不平等にならない程度にできるだけのバックアップをしていただきたい。能力が十分にあるトランスジェンダー学生が性別の問題だけで就職ができないということは、その学生だけでなく、社会全体にとっても損失ですし、それは何とか避けたいと思うわけです。
性同一性障害の場合、会社に入ってから性別移行をしたとして、それを理由にした解雇は違法という判例が固まっていますので、入社してからは首を切れません。性同一性障害を理由に解雇して裁判になったらほぼ確実に会社側が負けます。さすがだなと思ったのは、判例が出た頃に企業の総務課や人事課の人たちが読む専門雑誌に、さっそくその判例が紹介されていました。きちんと勉強している企業の労務管理担当者は知っているはずです。ですが、採用段階での就労差別はかなりあります。「戸籍を変更されてからもう一度当社をご受験ください」という形で門前払いするケースです。ですから、学生にしてみると、とりあえ生得的な性別で入社して、入ってから性別を移行するという手もなくはないです。でも、「就職のときは、そのことを隠していたのか」という信義の問題になりかねませんので、なかなか難しいところです。何度も言いますが、就労問題が最大のネックですので、何とかバックアップしていただきたいと思います。
⑩ 望みの性別で生きて行くための社会訓練の場としての大学
実は今、小・中学校では、性別違和を抱える児童、生徒がいると、隔離的、特別に扱って「どこどこの病院へ行って診断書を取って来てください」というように、問題を性同一性障害医療に委ねてしまう形がけっこう多くなっています。大学レベル、ましてや明治大学みたいなトップクラスの大学だったら、そんな安易な方法は採らないと思います。医療の手に委ねてしまうのではなく、大学という一つの社会で性別違和を抱える学生を受け入れていくという姿勢が望まれるわけです。トランスジェンダーの学生が望みの性別での生活を円滑にできるようになるためには、トレーニング期間が必要です。いずれ望みの性別で社会に出て行かなければならない学生にとって、大学の4年間プラスアルファが、トレーニング、社会訓練の場になるわけです。大学はそれをサポートする方向で対応してほしい、そうした姿勢を持って欲しいということです。
私は2002年に「トランスジェンダーと学校教育」という論文を書いているのですが、私が書いた論文の中で一番読まれません。どうしてなのだろうと思うのですが、どうも、現実の学校現場の先生とだいぶ意識が違うようなのです。たとえば、先生方は「男女別に並べるときにどうしたらいいのですか?」と質問してきます。私が「男女別に並べること自体を考え直した方がよろしいのではないですか」と返事をすると、ものすごく不満な顔をされてしまいます。前例が無いケースが出て来た時には、前例に合わせようとするのではなく、従来のシステムを再検討して新例を開くという姿勢が大事だと思います。
おわりに
2014年2月にタイのバンコクでWPATH2014という国際会議が開催されました。WPATHというのはWorld Professional Association for Transgender Health、トランスジェンダーの健康のための世界専門家会議という団体です。今回が第23回でしたが、今までずっと欧米で開催されていて、今回が初めてのアジア開催でした。そこでアジア・太平洋地域のトランスジェンダーをできるだけ集めて「Trans People in Asia and Pacific」というシンポジウムをやろうということになりました。とはいえ、これがなかなか大変で、トランスジェンダーは、お金持ちではない人がほとんどなので、飛行機代、滞在費を世界開発機構、世界エイズ会議など国際連合の4機関が資金提供して、アジア・パシフィック10カ国、最終的は日本も入って11カ国のトランスジェンダーがバンコクに集まりました。私も招待状をもらったのですが、日本はOECD加盟国で、世界開発機構ではお金を出す立場でお金をもらう立場ではない、だから日本の研究者には資金提供はできないから旅費と滞在費は自分持ちで来てくれ、というという話で、「それはあんまりな・・・」と思いました。お金のことはともかく、世界のどの国にも、トランスジェンダーはいるということです。いろいろ困難な状況はあるけれども、それぞれの国でそれぞれの社会の中で頑張って生きているわけです。
そうしたシンポジウムで、とても考えさせられたことがありました。全部で12人が各国の事情を報告したのですが、12人のうち11人がMtFなのです。私以外のMtFは、フィリピン、インドネシア、タイ、ネパール、インド、そしてトンガ、みんな英語がペラペラで、パワーポイントできちんと資料を作ってきて、しっかりプレゼンテーションをできる能力があります。ところが、FtMの人はそうしたプレゼンテーションができないのです。12人中1人だけ、しかもニュージーランドの活動家でしたから、少し事情が違います。
どういうことかと言いますと、アジアの国で、女性として生まれて女性としての教育を受けてきた人は、開発途上国における男女の教育格差を被ってしまうのです。女で育てられると、なかなか十分な教育が受けられない。それで男になっても、一定の知的レベルが求められる社会的活動がなかなか難しいのです。
この例のように、性別を変えて生きる人たちにとって、大事なのは教育なのです。社会に出て一般の人よりももっと厳しい状況の中で生き抜いていくための力になるのは教育です。教育をきちんと受けられるかどうかが鍵なのです。実は、日本もそういう傾向があって、日本で今FtMがこんなに多くなっているのに、日本から参加して報告したメンバーは2人ともMtFでした。残念ながら、国際学会で通用するレベルのプレゼンテーションができるFtMは、日本ではほとんどいません。なぜかというと、FtMの最終学歴は、MtFに比べて明らかに低く、高校中退レベルの人がかなりいます。そうした状況は徐々に改善されてきていますが、制服とかいろいろなことで引っ掛かってしまって修学が継続できず、その結果、低学歴で終わってしまって、学力やスキルが伴わないFtMがまだかなりいるのです。
社会の中でより良く生きていくための力を大学教育の中で身に着ける必要性は、一般学生でもトランスジェンダーの学生でもまったく変わりません。むしろトランスジェンダーであるがゆえにその必要性は高いのです。そのためには、何度も言うように修学が継続できる……きちんと卒業ができて、できることなら望む方面に就職ができるようなバックアップを、明治大学だけではなく全国の大学でぜひとっていただきたいと思います。
だいたい予定の時間になりました。3年前、明大に非常勤で呼んでいただいた時から、いつか講義以外でもお役に立てる機会があればと思っていましたので、今日はこういう機会をいただいて、とてもうれしかったです。どうもありがとうございました。
(紙幅の都合により、講師紹介及び質疑応答は割愛させていただきました。)
【参考文献】
三橋順子「『性』を考える-トランスジェンダーの視点から-」
(シリーズ 女性と心理 第2巻『セクシュアリティをめぐって』 新水社 1998年)
三橋順子「トランスジェンダーと学校教育」
(『アソシエ』8号 御茶の水書房 2002年)
三橋順子「トランスジェンダーをめぐる疎外・差異化・差別」
(シリーズ「現代の差別と排除」第6巻『セクシュアリティ』明石書店 2010年)



