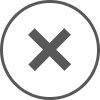て‐ざわり〔‐ざはり〕【手触り】
手ざわり
『古事談』巻4-13 源斉頼は鷹の飼育を業としていたが、晩年失明した。ある人が、信濃の鷹を「西国の鷹です」と、いつわって示したところ、斉頼は鷹の体を手で探り、「これは西国の鷹でなく、信濃の腹白の栖の鷹だ」と言い当てた。
『盲獣』(江戸川乱歩) 富豪の1人息子でありながら盲目に生まれた男が、あんまとなって美女の肉体に触れ、目明きにはわからぬ奥深い触覚世界を探求する。男は7人の美女のそれぞれ個性的な触感を味わってから殺し、彼女らの乳房や尻など身体各部の手ざわりを再現した像を造って、展覧会に出す。それは目で見るのでなく、手で触れて鑑賞する芸術作品だった。
『盲目物語』(谷崎潤一郎) 盲目の法師である「わたくし」は、浅井長政公の奥方(=お市の方)から「弥市」という名をいただき、お側近く仕えた。日ごと夜ごと、奥方のあんまを仰せつかったので、お身体の様子がわかるのみか、お心の中のことまで自然と「わたくし」の手先へ伝わった。このようなお方の御身に手を触れ、御腰を揉ませていただけるのは、盲目なればこその幸せだった→〔背中〕2b。
『菊池寛』(小林秀雄) 昭和14年(1939)11月。菊池さん(=菊池寛)が、四国の今治市の旅館に泊まった夜。胸苦しくなって目を覚ますと、24~25歳の痩せた男が馬乗りになっていた。首を絞めようとするので、菊池さんは両手で男の顎を下から押し上げた。男の口から流れる血が見え、男の無精髯のチクチクする感触が掌に感じられた。菊池さんが「君はいつから出てるんだ?」と問うと、男は「3年前からだ」と答えた。それは、3年前に肺病で死んだ、旅館の若主人の幽霊だった。
『生死半半』(淀川長治)「友人の亡霊たち」 フランス映画社の社長・川喜多和子さんが亡くなった時、「私(淀川長治)」はベッドの横にその姿が現れるのを、はっきり見た。彼女は「やんなきゃならない仕事がいっぱいあるのに、もう行かなくちゃいけないの」と言った。「私」は「あんた、死んじゃったの。可哀相に」と言いながら、手をさすってあげようとしたが、「私」との間がガラスで仕切られているような感じで、どうしても身体に触れることができなかった。
★4.一般に幽霊は、さわろうとして手をのばしても、手ごたえがなく、突き抜けてしまうことが多い。
『遠野物語』(柳田国男)82 田尻丸吉という人の実体験。少年の頃、ある夜、便所へ行こうとして茶の間を通ったら、座敷との境に人が立っていた。幽(かす)かに茫(ぼう)としていたが、衣類の縞も眼鼻もよく見え、髪を垂れていた。手をのばして探ると、板戸にガタと突き当たり、戸の桟にもさわった。自分の手は見えず、その上に、影のように重なって人の形がある。顔の所へ手をやれば、手の上に顔が見えた。
*亡母の霊を抱こうとするが、影か夢のごとく手をすり抜けた→〔冥界行〕2の『オデュッセイア』第11巻。
「手ざわり」の例文・使い方・用例・文例
- 手ざわりのページへのリンク