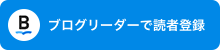日本史の中では奈良時代が一番おもしろいかもと私は思います
昨年、豊橋市美術博物館へ馬越長火塚古墳の出土品を見に行き、文化財センターで貴重なお話もうかがうことができまして、
もっと豊橋の歴史について詳しくなりたい!という気持ちが沸き起こってきました。
そこで!豊橋の遺跡と言えば真っ先に思い浮かぶ、(歴史好きな人の間では)超有名な「瓜郷遺跡」を取材することにしました。
※写真が冬景色なのにはツッコミ入れないでください・・・笑
瓜郷遺跡は、「豊川下流の沖積地に立地する弥生時代中期から後期にかけての集落」で、竪穴住居、石包丁、木製の鋤・鍬などが出土し、貝塚も確認されています。
それだけでなく、「『瓜郷式』と呼ばれる櫛描文を多用した特徴的な土器」も出土しており、唐古遺跡や登呂遺跡と並んで弥生時代を知るための重要な遺跡と位置付けられます。
(出典:豊橋市美術博物館 瓜郷遺跡のページ)
歴史の教科書に必ずと言っていいほど載ってる登呂遺跡に匹敵する、すごい遺跡なんですね
当時の人々は、湿地を利用して水田を開き、湿地を望む小高いところに集落を形成していたようです。
自然環境としては、周辺はクリやシイなどの広葉樹の林があったほか、海岸線が今より内陸側にあったため、川を少し下ればすぐに海に出られたようです。
こちらが現在の瓜郷遺跡の様子。当時の住居が復元されています。
小学生の頃、校外学習か何かで瓜郷遺跡の見学に来たことがあるのですが、
当時はこの住居が遺跡のすべてだと思っていたので、「なんかしょぼい遺跡だな」と感じた記憶があります(失礼)
でも、大学のゼミ(実は考古学を専攻していました)で自宅が豊橋だと言ったら、
「瓜郷遺跡あるよね!すごい遺跡だよね!」と先輩に言われ、国の史跡に指定されている遺跡だということをその時知りました
瓜郷遺跡では、昭和22年から27年にかけて5回の発掘調査が行われており、
前述の通り様々なものが出土しています(出土遺物は美術博物館にて見ることができます)。←令和4年10月17日から改修のため休館となりますので、ご注意ください。
水田の遺構こそ見つかっていないものの、木製の農機具や炭化したコメが発見されたことから、稲作が行われていたことが推測されます。
また、貝塚(いわば古代人のゴミステーションですね)があり、そこから動物・魚の骨や木の実が出ていることから、狩猟・採集・漁撈も行われていたことがわかります。
では、せっかくなのでおうちにぐぐっと近寄ってみましょう
通常の竪穴住居が四本柱なのに対し、瓜郷の住居は二本柱。屋根がまるで合掌造りのようで、なかなかスタイリッシュじゃないですか。
おうちの中は・・・なかなか広いですね。中央に炉の跡があるそうです。
こちらで食べ物を煮炊きすると同時に、暖をとっていたのでしょう。まさに家族「暖」らんです。
稲作が始まったとはいえ、当時の生産技術はまだまだ高くはなかったようですので、
田植えから稲刈り(当時は稲穂の部分だけを切り取っていました)まで相当大変だったでしょう。
その分、秋の収穫の時季にはコメなどを神に捧げ、盛大なお祭りを催したようです。
ちょっと赤みがかった古代米や、クリなどの木の実、ハマグリやアサリのスープなど、
実に様々なものが食卓に並んでいたのかな。想像するとなんだか楽しいですね
古代人の暮らしに思いをはせていたらお腹がすいてきたので、カピバラもおうちへ帰ることにしました
※公共交通に詳しいオコジョさん からひとこと
からひとこと
瓜郷遺跡へお出かけの際は、ぜひコミュニティバス「かわきたバス スマイル号」をご利用ください!
運行日、運賃、時刻表等、詳しい情報はこちらからご確認いただけます。
〔遺跡data〕
遺跡名:瓜郷遺跡(うりごういせき)
所在地:豊橋市瓜郷町寄道地内
アクセス:JR飯田線「下地」駅から徒歩約10分
かわきたバススマイル号「瓜郷遺跡」下車すぐ
昨年、豊橋市美術博物館へ馬越長火塚古墳の出土品を見に行き、文化財センターで貴重なお話もうかがうことができまして、
もっと豊橋の歴史について詳しくなりたい!という気持ちが沸き起こってきました。
そこで!豊橋の遺跡と言えば真っ先に思い浮かぶ、(歴史好きな人の間では)超有名な「瓜郷遺跡」を取材することにしました。
※写真が冬景色なのにはツッコミ入れないでください・・・笑
国の史跡に指定されているんですよ!
瓜郷遺跡は、「豊川下流の沖積地に立地する弥生時代中期から後期にかけての集落」で、竪穴住居、石包丁、木製の鋤・鍬などが出土し、貝塚も確認されています。
それだけでなく、「『瓜郷式』と呼ばれる櫛描文を多用した特徴的な土器」も出土しており、唐古遺跡や登呂遺跡と並んで弥生時代を知るための重要な遺跡と位置付けられます。
(出典:豊橋市美術博物館 瓜郷遺跡のページ)
歴史の教科書に必ずと言っていいほど載ってる登呂遺跡に匹敵する、すごい遺跡なんですね
当時の人々は、湿地を利用して水田を開き、湿地を望む小高いところに集落を形成していたようです。
自然環境としては、周辺はクリやシイなどの広葉樹の林があったほか、海岸線が今より内陸側にあったため、川を少し下ればすぐに海に出られたようです。
こちらが現在の瓜郷遺跡の様子。当時の住居が復元されています。
小学生の頃、校外学習か何かで瓜郷遺跡の見学に来たことがあるのですが、
当時はこの住居が遺跡のすべてだと思っていたので、「なんかしょぼい遺跡だな」と感じた記憶があります(失礼)
でも、大学のゼミ(実は考古学を専攻していました)で自宅が豊橋だと言ったら、
「瓜郷遺跡あるよね!すごい遺跡だよね!」と先輩に言われ、国の史跡に指定されている遺跡だということをその時知りました
瓜郷遺跡では、昭和22年から27年にかけて5回の発掘調査が行われており、
前述の通り様々なものが出土しています(出土遺物は美術博物館にて見ることができます)。←令和4年10月17日から改修のため休館となりますので、ご注意ください。
水田の遺構こそ見つかっていないものの、木製の農機具や炭化したコメが発見されたことから、稲作が行われていたことが推測されます。
また、貝塚(いわば古代人のゴミステーションですね)があり、そこから動物・魚の骨や木の実が出ていることから、狩猟・採集・漁撈も行われていたことがわかります。
では、せっかくなのでおうちにぐぐっと近寄ってみましょう
通常の竪穴住居が四本柱なのに対し、瓜郷の住居は二本柱。屋根がまるで合掌造りのようで、なかなかスタイリッシュじゃないですか。
おうちの中は・・・なかなか広いですね。中央に炉の跡があるそうです。
こちらで食べ物を煮炊きすると同時に、暖をとっていたのでしょう。まさに家族「暖」らんです。
稲作が始まったとはいえ、当時の生産技術はまだまだ高くはなかったようですので、
田植えから稲刈り(当時は稲穂の部分だけを切り取っていました)まで相当大変だったでしょう。
その分、秋の収穫の時季にはコメなどを神に捧げ、盛大なお祭りを催したようです。
ちょっと赤みがかった古代米や、クリなどの木の実、ハマグリやアサリのスープなど、
実に様々なものが食卓に並んでいたのかな。想像するとなんだか楽しいですね
古代人の暮らしに思いをはせていたらお腹がすいてきたので、カピバラもおうちへ帰ることにしました
※公共交通に詳しいオコジョさん
瓜郷遺跡へお出かけの際は、ぜひコミュニティバス「かわきたバス スマイル号」をご利用ください!
運行日、運賃、時刻表等、詳しい情報はこちらからご確認いただけます。
〔遺跡data〕
遺跡名:瓜郷遺跡(うりごういせき)
所在地:豊橋市瓜郷町寄道地内
アクセス:JR飯田線「下地」駅から徒歩約10分
かわきたバススマイル号「瓜郷遺跡」下車すぐ