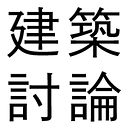出版社を立ち上げ、持続させること
インタビュー:富井雄太郎(株式会社ミルグラフ)|063|202201 特集:建築メディアはたのしい
アナログとデジタル
──今回の特集のなかで、富井さんは唯一の出版・編集の実務者です。その立場から、リアルな話をお聞かせください。活動を振り返ってお話いただくのは初めてとのことですが、まずは、出版社を創業するまでの経緯を教えてください。
富井雄太郎:出版社をつくる前は、2005年から5年間、新建築社の編集部に勤めていました。ちょうど建築写真がアナログからデジタルに切り替わっていった期間で、2005年は100%フィルムでしたが、2007年あたりから徐々にデジタルカメラが導入され、2010年に会社を辞めた時には100%デジタルになっていました。僕は撮影現場が好きで、カメラマンと意見を交わしたり、ファインダーを覗かせてもらうこともよくしていましたが、アナログの場合、機材が重く、フィルムやレンズの交換、露出計で光を測ったり、シャッターなどあらゆることに時間がかかり、フィルム代や現像代のこともあるので、なるべくカット数を抑えなくてはいけない。1カット1カットが貴重で、撮影者、編集者、立ち会っている人みんなで状況を整えて、シャッターを切る瞬間には息を止めるほどの緊張感が漲っていました。まるですべてがフィルムという神に仕える祭事のようでした。しかも、フィルムには現像されてくる数日後までなにがどう写っているかは完璧にはわからず、良くも悪くも想像が裏切られる。
デジタルの場合はそのフィルムがない。機材は軽く、スピーディで、その場でざっと確認して失敗なら撮り直せばいいし、あれもこれも色々なパターンが撮れるので当然現場はカジュアルになります。現像は内製化され、Photoshopでかなりのことが操作できる。そうしたアナログからデジタルへの移行を経験しました。撮影現場はとても大事で、デジタルでもいかに写真家と一緒にハードルを設定するかが肝心だと思います。
他方、2009年6月に発売されて手にしたiPhone 3GSの圧倒的な衝撃がありました。それ以前は自宅にパソコンもないという状態でしたが、情報技術に強く関心を持つようになりました。とりわけ(今では当たり前ですが)インターネットにどこでもつながること、本当に誰もが使うようになることのインパクトです。情報の流れ、コミュニケーションだけではなく、仕事や生活も大きく変わっていくだろうという予感を肌で感じました。
アナログのものづくりとデジタルによる革新、その両方に触れ、30歳手前で会社を辞めようと決めました。自分で出版社をやろうとは思っていませんでしたが、様々な本を読んだり、電子書籍について調べたりもしていました。当時はまだマーケットが未熟で、結局物理的に本をつくることにしたのです。情報技術、特に常時接続されたインターネットがもたらす建築・都市の変化というテーマを、原広司さんや吉村靖孝さん、柄沢祐輔さん、藤村龍至さんらに投げかけ、他領域の専門家も交えた対談・インタビュー・リサーチを収録した『アーキテクチャとクラウド──情報による空間の変容』を2010年10月に出版しました。会社は社会的信用や取引のため、株式会社として同年5月に立ち上げていました。
──新建築社などの会社を退職後に、フリーランスのエディターやライターになる、というキャリアは建築系では割合多くおられるかと思います。雑誌・書籍の企画を立てて出版社に売り込むかたちではなく、自分で版元をつくった富井さんの選択は異質に見えるのですが、そう考えたのはなぜでしょうか。
富井:若さゆえの勢いですね。キャリア形成みたいなことは考えていませんでしたし、フリーランスの働き方もよく知らなかったです。Amazonが浸透していて、そうしたプラットフォーム上では小さな出版社でも普通に流通させられるはずだという確信がありました。『アーキテクチャとクラウド』は3,000部発行して割とすぐに完売しました。インターネット、SNSがなければできなかったと思います。書店へは直接卸していましたが、理解のある書店員さんは積極的に販売してくれました。そうした情熱を持った方々の存在も大きかったです。
『磯崎新的訪談@中韓日』の経験
富井:自分で本をつくってしまおうと思ったのは、『磯崎新的訪談@中韓日』(新建築社、2008年)を手掛けた経験も影響しています。2008年の中国・深圳への出張は、サラリーマン時代の最も印象深い出来事です。当初は『新建築』で磯崎新さんによる「深圳文化中心」を掲載するための取材・撮影でしたが、深圳は1980年代からの改革開放政策で漁村が急変貌したところで、圧倒的な経済と政治によってつくられた超特殊な都市でした。中国珠江デルタ地域はレム・コールハースらもハーバード大学でリサーチしていましたよね。
──『大躍進』(OMA+Harvard Graduate School of Design, “Project on the City I Great Leap Forward”, Taschen, 2002)ですね。
富井:そうですね。これは建築単体を見せるだけではしょうがないと、現地から編集長に電話をして、急遽企画を立ち上げました。そのレム・コールハースらのリサーチも踏まえ、磯崎さんの相手としてOMAのシンクタンクAMOの太田佳代子さんたちにも加わってもらいました。磯崎さんは、ある日の夕方から翌朝まで、ノンストップで様々な話をしてくださいました。夜中に料理をつくり始め、ワインを振る舞いながら12時間、レコーダーの電池が切れて記録に残らずともお構いなしです(笑)。それらは月刊誌の2号連続で掲載することになりました。
さらに磯崎さんから連絡があり、ちょうど同じ頃中国と韓国の建築雑誌で受けたインタビューも翻訳し、合わせて単行本にしようという流れになりました。企画から始まり、編集、DTPなどすべてをやって、刊行後には磯崎さんがレクチャーをする韓国・釜山へ本を詰めたダンボール箱を持ってひとりで出張し、現地で様々な国の人たちに販売まで行ったのです。深圳出張からわずか9カ月でした。
──現在の出版・編集プロダクションとしての仕事の原形がここで作られた。
富井:意外とひとりでもできるし、行商みたいに売るのもありなんだなと思いました。
豊島美術館から瀬戸内の世界へ
──出版社を立ち上げることや本をつくることそのものは容易であるとしても、それを10年以上、基本的にはひとりで維持・持続してきたことは、やはりすごいことであると思います。小規模でも「続けること」に価値を見出していると想像します。
富井:今12期目になりますが、最初から持続を意識していたわけではなく、思い返してみると、会社創業から10カ月で起きた東日本大震災は大きかったです。当時2冊目の書籍として、2010年10月に開館した「豊島美術館」(建築:西沢立衛、アート:内藤礼)の写真集の企画が動いていました。
──『豊島美術館 写真集』 は富井さんの企画なのですか。
富井:はい。きっかけはSANAAによる建築などを撮影していた写真家の鈴木研一さんから、がらんどうな豊島美術館の写真を見せてもらったことです。とてもすごいものだと思い、開館前でしたが、企画をつくって西沢立衛さんに打診をしました。
『GA JAPAN』や『新建築』などの建築雑誌では、オープン後すぐの様子が掲載されていましたが、秋冬で太陽高度が低く、植栽も乏しい状態でした。僕たちは光などの条件を考えて春の撮影を待っていたところで大震災が起こったのです。会社は1年目でしたし、個人的にも様々な感情がありましたが、やはりこのプロジェクトはやりたいと思い至りました。うまく言えないのですが、本をつくって出すことがなにか救いになるだろうというような気持ちでした。震災後の5月末、撮影のため現地へ赴き、3日間ずっと美術館内外で過ごしました(フィルムでの撮影でした)。豊島は瀬戸内の島々のなかでも水が豊かなところで、棚田には水が張られ、植物が芽吹き、明るく、生命感がありました。内藤礼さんの作品《母型》にも驚き、大変な感銘を受けました。出張から戻り、写真プリントを仕上げてもらい、試作していた束見本も持って内藤さんと初めて会うと、「ひとりで制作をしている時、こういう光を見て感激していた」と、出版を歓迎してくださいました。西沢さんや直島福武美術館財団(現・福武財団)さんも寛大で、未知の企画を信頼してくださり感謝しています。開館1周年に合わせ、2011年10月に刊行することができました。
──最初の『アーキテクチャとクラウド』は新しい技術と建築の思考を捉える、いわば同時代的な性格の強い書籍です。その1年後の『豊島美術館 写真集』は、製本などにしても、そういう時代に捉われない、タイムレスな書籍が目指されている印象を受けます。
富井:本は人間の寿命よりも長生きする可能性があります。自分の本棚を見ても、既に亡くなっている人の本が大半です。もしかしたら写真集は、豊島美術館が誕生したばかりのピュアな姿を、美術館そのものがなくなった後の時代にまで伝えるものになるかもしれません。豊島美術館は自然と人間、生命といった大きなことに思い至らせる力があります。
その後2015年には作品集『内藤礼|1985–2015 祝福』を出版することになりますが、出版社は著者や作家の一生、あるいは死後まで、必然的に関わることになります。簡単に事業をやめることはできませんし、会社(法人)は二代目、三代目と社長が変わりながら、一個人の生を超えて続いていくこともあるというのはおもしろいと思います。
豊島美術館の仕事以降、妹島和世さんの依頼から『犬島「家プロジェクト」』(2014年)、岡山の基盤づくりに関わった津田永忠が手掛けた閑谷学校の『国宝・閑谷学校|Timeless Landscapes 1』(写真:小川重雄、解説:西本真一、2017年)、倉敷を拠点としたクリエイティブリユースの活動を紹介する『クリエイティブリユース──廃材と循環するモノ・コト・ヒト』(著:大月ヒロ子、中台澄之、田中浩也、山崎亮、伏見唯、2013年)、瀬戸内海を周遊する客船の『ガンツウ|guntû』(著:堀部安嗣、2019年)、春に刊行予定の尾道「LOG」(設計:ビジョイ・ジェイン/スタジオ・ムンバイ・アーキテクツ)の本など、瀬戸内との縁が続いています。
倉敷の大原美術館の創設者・大原孫三郎や「経済は文化のしもべである」という福武財団の福武總一郎さんらが関わった建築、美術コレクションは独自かつ厚みがありますが、社会事業としての尊さも感じます。文化を育み、将来へ継承していこうという理念の影響が瀬戸内一帯に存在しています。自らの出版も、長期的にそうしたものの一環として位置づけていけたらと願うようになりました。
メディウムの多面的展開
──millegraphは非常にハイクオリティな写真集・作品集を出版する一方で、近年はWebプラットフォーム「note」を使って若手建築家の立石遼太郎さんよる連載「建築におけるフィクションについての12章」を展開したり、連勇太朗さんの自主ゼミ「社会変革としての建築に向けて」では、執筆途中の文章を題材に議論する取り組みなど、メディウムを書籍に限ることなく横断的に用いられています。このあたりの意図を教えてください。
富井:最初は、建築史家・中川武さんが自発的に書いてくださった『国宝・閑谷学校|Timeless Landscapes 1』の書評の受け皿がなかったというところからnoteを始めました。合わせて、藤原徹平さんが雑誌『住宅建築』に寄稿された書評の加筆版も再録させてもらいました。書評の域を超えて津田永忠論としても読み応えのあるものです。
以降、少し関わっていた「10+1 website」が2019年に縮小(2020年に終了)されたことに伴い、特に若い人が書ける場所をつくろうという意識もあって企画を続けています。立石遼太郎さんの連載は、打合せ段階ではもっと軽やかなものを想定していたのですが、毎回のボリュームが大きくて、さらに番外編のレクチャーなども収録することになり、終わってみれば膨大になっていました。実験的な側面もありますね。
2020年に出版した『建築情報学へ』(監修:建築情報学会)については、全国の有志学生によるオンライン勉強会が立ち上がっていたので、その企画メンバーに会の経緯や活動を書いてもらいました。
連勇太朗さんの自主ゼミは、ゲスト講師を招いて執筆中の新著について様々なフィードバックの過程を共有しながら、読者のコミュニティを意識的につくっていこうという試みです。これまで6回のゼミを開催し、30歳以下の建築家や研究者によるそれぞれのレポートを公開しています。
原稿料・講演料をお支払いしているということも一応言っておきます。支払いがあることで、相手にもこちらにも緊張感が生まれると思います。
2021年から動画の制作も始めました。日本大学理工学部建築学科のWeb立ち上げをお手伝いしているなかで、YouTubeチャンネルを開設し、例えば、教員の佐藤光彦さんや古澤大輔さんの建築家としての仕事を紹介しています。建築の動画は、BGMが入っていたり演出の強いものが多いような気がしますが、ここでは日常性や偶然性、現場の音や声を尊重しています。「西所沢の住宅」(設計:佐藤光彦建築設計事務所、2001年)では、ご家族の所作、グレーチングの床を抜けて響く声、庭から聞こえる鳥や飼われているインコのさえずり、20年間過ごしてきたご夫婦の語り、佐藤さんの解説などを輻輳させています。「古澤邸」(設計:古澤大輔/リライト_D + 日本大学理工学部古澤研究室、2019年)では、お子さんの奔放さ、日常生活、風や電車の音などと古澤さんの解説を織り交ぜています。映像と環境の音、声、語りなども含めて時間の流れのなかで編集していく、そのことにとても可能性を感じています。
──実は『建築討論』でも、Webメディアの特性を今後もう少し活かしていきたいと思っています。スタティックに特集やテクストだけで構成するのではなく、ムービーコンテンツを取り入れたり、ウェブ会議なども。富井さんの多面的なメディウムの使い方は参考にしたいなと思っていました。
富井:なるほど、それは楽しみですね。ただ一方で反動的なことをいいますが、Webは意外とあっさりなくなります。また、かつて紙の本で読んだものをそうと気づかず電子書籍で最後まで読んでハッとした経験があります。記憶の定着の仕方が違うのかなと。紙の本だとどのあたりのページのどの位置に書いてあったかまで思い出せることもありますが、デジタルでは検索頼りになります。精神科医の中井久夫は、本は棚にあるだけで背表紙が内容を訴えかけてくると度々論じています。一度読んだ本を文庫や新版など別の版で読むとダメだとか、本を処分すると内容を一気に忘れるとか。これは僕も感覚的によくわかります。たとえ積ん読でも、その本からなにかしら情報を知覚してしまっている。電子書籍は便利ですが、いまのところ物としても記憶としても残るのは紙の本だと思います。
──たしかに、電子書籍は、ある時代の価値観にもとづいて糾弾された著者の書籍を、容易に閲覧不可にできたりするところに、危うさがあるように思います。アーカイヴの信頼性が足りない。ただ最近私は、研究書など何度も読み返すだろうものは紙、小説や新書など単線的に読んでしまうものはKindle、というように使い分けるようになりました。電子書籍にフィットした本、というものを作る計画などはありませんか。
富井:僕も漫画は結構電子書籍で読んでいますし、テキストベースでも電子書籍がふさわしいものもありますよね。物理的媒体への信頼は個人的・世代的なものの考え方なのかもしれませんし、情報技術とフィジカルなものは二者択一ではないです。先ほど挙げた『クリエイティブリユース』という本は完売間近なので、増補版を電子書籍として準備中です。2022年夏に刊行予定の連勇太朗さんの単著は、社会課題に関わる建築のあり方やその方法を扱うものですが、若い世代にこそ読んでほしいので、電子書籍版も同時に出す予定です。内容や条件に沿ってその都度組み合わせていけばいいと思います。
贈与としての出版とその基盤
──2010年に富井さんが出版社としてmillegraphを立ち上げられて以降、建築の言説や記録のための空間を独自にさまざまに展開させていることがよく理解できました。他方で、建築の出版業界全体としては長らく厳しい状況が続いています。建築メディアの現状、あるいは今後について、考えられていることはありますか。
富井:建築メディアの衰退がいわれて数十年経っていますが、ドライに見れば、かつての日本の建築ジャーナリズムや出版物の豊穣さは高度経済成長期の賜物だったのだと思います。建築の出版物や言説を支えてきたのは、実は大手ゼネコン、大手メーカーなどの文化事業やメセナ、広告事業でした。だからダメだというのではなく、ゆとりがあったということです。バブル崩壊から30年、貧すれば鈍するように、日本経済の停滞と建築メディアの廃刊・縮小は同期しています。議論の低調を憂うならば、それを支えている基盤にまで向き合わなければ、このグローバルな新自由主義のうねりのなかで有効な批評やメディアの展開はないはずです。
──大学や企業の経済的バックアップに依存しない、自律的な建築の批評空間のありかたを考えることが求められている。
富井:大学や企業のバックアップはあるに越したことはないと思います。ただ、このコンプライアンスやコスパが求められる時代に、例えばオリンピックのスポンサー企業がサポートするメディア上で本格的なオリンピック批評などは難しいでしょう。今後、建築の出版が盛り上がるなんてことは構造的にもありえないので、それぞれの方法で持続、サバイブしていくしかなく、そのためには社会的経済的基盤への思考が重要です。
とはいえ、そんなに大げさな話ではなく、まずは2,000〜3,000人の人が手に取ってくれればと思っています。建築や美術の出版はそもそもマイナーで、市場としても小さいです。もちろん日本の建設業の規模はかなり大きいですし、業に関わる人も多いので、そのなかでの売れ筋は明確にあって、実務に役立つ本、図面が沢山載っているような本などです。ただ、建築専門家が今日明日のために手に取る本、既存マーケットに対して内向きの本ではなく、その外にも伝わるものにしたいと常に思ってきました。本は今現在生きている人のためだけのものではないですから。かつて「出版は贈与(返礼)である」(『建築雑誌』2018年9月号、日本建築学会)と書いたことがありますが、本というメディアは古くて遅いけれど、寿命が長く、経済合理性だけでは測りきれないところがあります。人間社会に対する贈与(返礼)の連鎖ともいえるのが出版です。
多くの人が忙しすぎるのも大きな問題ですね。仕事や家事があって、無料の情報が溢れ、巨大なサブスクリプションサービスがいくつもあり時間を奪い合っていますから、本など読む暇はないという人がほとんどでしょう。本を読むにもつくるにも時間が大事ですね。僕は本を読む時間として、長風呂の時間を確保しています。行き交う情報を一時的に遮断し、お湯に浸かって本を読んでいると、この現代社会を相対化し、別の世界を考えることができます。風呂読書に限らず、今ここから離れる時間を持つことは豊かだと思いますし、自衛にもつながるはずです。■
2021年11月20日、富井雄太郎さんのオフィス兼自宅「ハウス/ミルグラフ」にて
写真(ポートレイト)・文=黒岩千尋
富井雄太郎| Yutaro Tomii
株式会社ミルグラフ代表取締役/1979年東京都生まれ。2002年早稲田大学理工学部建築学科卒業。新建築社を経て2010年株式会社ミルグラフ設立。2012~15年東京藝術大学美術学部建築科教育研究助手。
http://www.millegraph.com/