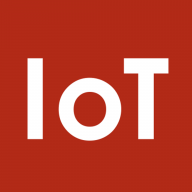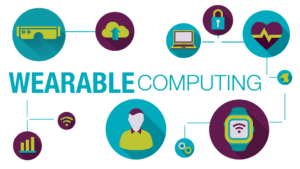こんにちは、小泉です。今回は、色んな意味で捉えられていて、わかりづらいとされている「DX」。この本質は何なのか?我々のビジネスや生活に与える影響はどういうところにあるのかを丁寧に解説します。
「DX」という言葉が流行り出してから数年たちます。私自身も様々なセミナーや勉強会等で、「DXとは何か」について話す機会が多いのですが、その前段階でお話を伺うと、「なんとなくわかるけど、それで結局何がいいの?」「うちの会社はどうなるの?」「生活は変わるの?」「どんな人材が求められるの?」といったところがピンとこないという話をよく聞きます。
そこで、この記事では、そういった疑問に丁寧に答えていきたいと思います。
目次
「DX」と「デジタル活用」の違い
DXが、「デジタルトランスフォーメーション」の略です。デジタルでトランスフォーム(変革)するわけですが、「何を」デジタルで変革するのかについては、この言葉自体に定義がありません。
私が思うに、そのことがもっとも理解しづらいところではないかと思うのです。
その一方で、「デジタル活用」「IT」「IoT」など、似たような意味になりそうな言葉が多いこともあり、これまでのいわゆる「IT活用」や「デジタル化」との違いが判りづらいと思う方が非常に多いです。
DX以前のデジタル化の歴史
これまでのデジタルを「活用する」取り組みにおいて、データを収集する目的は、集めたデータに基づき何らかの決断をヒトがするためのものでした。そして、ヒトが下した決断に対して、何かをやるのもまたヒトでした。
作業そのものはデジタルやロボットなどが代替してきましたが、その結果、自動化や効率化がすすんだとしても、その「ボタンを押す行為」自体はヒトがやっていました。
IoTが、考えられない量のデータを収集するように
最近になって、IoT(モノのインターネット)と呼ばれる技術が話題となり、現実世界にあるさまざまなモノの情報をネットワークを通して収集するという活動がおこなわれるようになりました。
収集可能な現実世界のデータ量が飛躍的に増加したのと同期してか、大量データをさばくコンピュータの処理速度も以前とは比べ物にならないくらいに向上した、そして、AIが業務で使えるレベルになってきた、などという背景もあり、ヒトが会議室に集まって、収集したデータに対する判断を行い、何を実行するのか選択するよりも、ある程度の判断はコンピュータに任せた方が良いと言う状態になってきたのです。
- IoTによる、現実世界の大量データが取得可能となった
- コンピュータ性能の飛躍的向上と、インターネットの世界的広がり
- AIが現実的に使えるようになってきた
さらに、2018年頃から、画像や音声といったこれまでは曖昧なデータとして利用されなかったものまで、利用可能とされることで、さらにデータの収集能力が向上し、現実世界で行う手段のバリエーションも、同時に可能な処理数も、飛躍的に増えました。
その結果、もはや「ヒトが判断し、実行する」ということが現実的ではなくなったのです。
そして、ある程度のことは、デジタルにコントロールさせた方が「経験に基づくカン」や、「感情」によるムラに左右されることなく、一番確度の高い選択を行うことができると言う事実が広がってきたのです。
DXのテクノロジー視点での本質
つまり、「デジタルトランスフォーメーション(DX)」は、技術面から見ると、これまで「ヒトが判断」してきた事柄を、ある程度は「デジタルに任せてしまおう」という取り組みといえます。
DXが実現された事業体では、データはこれまで以上に大量に収集することができるようになっていて、大量に集まってきたデータを、無限にあるともいえる選択肢の中から、もっとも有効な選択を、デジタルによって判断できるようになる。そして、判断結果を実行するのもデジタルやロボットが行うようになるのです。
つまり、 DXとデジタル活用の違いは何かと問われた場合の答えとしては、「デジタルを中心にして可能な限りのことはデジタルが行い、ヒトは人がやるべきことをやる」ということで、「ヒトが中心になって、人が理解できる範囲のことをデジタル技術の活用で効率化する」のがデジタル活用ということになるのです。
DXのビジネス視点での本質
では、ビジネス視点からみたら、DXはどうなるのでしょうか?
Uberなどはこの良い例といえます。
Uberは、利用者もドライバーも持っているスマートフォンを使ったビジネスです。
利用者は、Uberアプリを使って、自分の位置情報と目的地を設定。ドライバーは、近隣に利用者がクルマを探していた場合に、自分が迎えに行くことをドライバー用のUberアプリ上で意思表示すると、マッチングが完了し、ドライバーは利用者を迎えに行き、目的地まで運ぶというサービスです。
既存のタクシー業界では、クルマを所有して、配車も、クルマの管理も、ドライバーの教育も、全て人手でやっていました。しかし、Uberは、利用者もドライバーもスマートフォン一つあれば始めることができる。しかも、クルマは自家用車が空いている時間を使えるし、ドライバーの教育は相互評価という利用者とドライバーが相互に評価する仕組みを導入することで、自動的に実現できる工夫をこらしているのです。


こういう同じタクシー産業であるにもかかわらず、デジタルありきで、全く異なるビジネスを行う企業が登場すると、既存業界はどんどん駆逐されていきます。既存産業の対抗策としては、政治的に規制を行うくらいしか対抗手段がなくなっていくのです。
実際、日本では、タクシー業界の圧力によってUberを規制しているため、我々はその恩恵に預かることができないわけですが、これは実質的に「負けを認めている」に過ぎないともいえます。
DXの本質は、ビジネスデジタルトランスフォーメーション
テクノロジーとビジネスの視点からDXをみてきましたが、結論としては、デジタル環境の変化によって、ビジネスも大きく変わらざるを得なくなったということが重要なポイントで、デジタル活用ではないということがご理解いただけたのではないでしょうか。
事例から見るとわかる、DXとデジタル化の違い
皆さんが接している、わかりやすい例として、インターネット検索を考えます。
まだインターネット黎明期、Windows95が発売された頃の話ですが、当時のYahoo!のページは、カテゴリ別にホームページが分類されていました。
ヒトによる手作業で処理していた初期のYahoo!
今では信じられないかもしれないが、Yahoo!に掲載してほしいホームページのオーナーは、Yahoo!に申請フォームから申請を行い、申請が通ったらYahoo!に掲載されるのですが、どのカテゴリに掲載されるかについては、ヒトが登録していました。(もちろん審査もヒトが会議室で行っていた!)
ところが現在では、一人一台、スマートフォンを持つ時代となりました。
ホームページの数は星の数ほど多くなり、もはやヒトが分類できない量となりました。
こうなると、検索エンジンが、勝手に検索キーワードに対して適切なページを並べてくれないと、人手では、とてもじゃないけど追いつきません。
そして、インターネット上の広告配信なども、ある利用者の検索の履歴や、閲覧したホームページの内容を解析し、その人の趣味嗜好を統計的に割り出していかなければ、誰にどの広告をだせばよいかなんて、とてもじゃないけど決めることができません。
星の数ほどあるデータをコンピュータが処理するGoogle
これらのことを、ヒトが全て行うことはできませんが、Googleの検索エンジンは、こういった大量データから適切な検索結果や広告表示を実現する仕組みをAIを活用して実現したのです。

この例のように、元から検索エンジンなんて、デジタルだろう!と思われるかもしれませんが、みなさんの検索行為と広告配信を支える業務全体としては、かつては、かなりの割合でヒトの力が介在していました。
しかし、我々が知らない間に、検索エンジン企業の業務はDXされていて、ヒトが介在することなくても、サービスが提供されるようになったのです。
全ての既存ビジネスで、大量データが発生
こういう状況を見て、これまで既存産業のビジネスマンは、「インターネットの世界のことだ」とたかをくくっていたかもしれません。こんな大量のデータが日常的に生み出されるのは、ネットの世界のことだと。
しかし、IoTの登場で現実世界のさまざまなことをデータ収集可能とし、高速処理能力を備えたコンピュータの低価格化によって、ものすごい量のデータから判断するということを実現するようになったのです。
これにより、インターネット・ビジネスのような「デジタル技術の塊」とされる産業でなくても、全ての産業がDXを行うべきタイミングがきたのです。
- IoTによってネットのみならず、現実世界も大量データが取れるようになったことを知る
- AIなどデジタル技術に頼らなければ、ヒトでは処理しきれない状況に「全ての業界が」なったことを知る
- ネットの世界だけでなく、全ての産業でDXを行うタイミングがきていることを知るべき
既存産業にも必須となるDXの流れ
では、既存産業ではどんな変化が起きているか、ここで、コンシューマ向け商品を作る、メーカーの例をあげて考えます。
コンシューマ向け商品をつくるメーカーの例
これまでの企業では、自社製品の利用状況については、アンケートなどで定性的に取得するしかなく、改善点を新しい商品に盛り込むのにもかなりの時間が必要でした。
よく、「顧客ニーズを汲み取った商品を作らないといけない」と、上司からも言われますが、「汲み取る」ってどうやったら良いかわからないですよね。
そこで、「デジタル技術を駆使するDXにより解決しよう!」ということになったとします。
まず、製造業の主な業務は、設計業務、開発業務、製造業務、販売業務、保守業務に別れます。顧客のニーズが汲み取れれば、その情報は設計業務にフィードバックされるので、次の製品からは、顧客のニーズが反映された商品になります。
デジタルによって、顧客ニーズをどうつかむのか?というと、商品の中にさまざまなデータ収集を可能とするIoTの仕組みを搭載するのです。
例えば、電動アシスト自転車を作っている企業だとすると、電動アシスト自転車の利用状況を取得します。月に何回利用しているか、自転車の角度を取得して、どれくらいの坂道を普段利用しているのか、月間の走行距離はどれくらいなのか、利用に対する電池の減り具合はどうか、電池の劣化は進んでいるか、などさまざまな情報が取得可能です。

こういうさまざまな情報をIoTを使って集めると、利用者の利用状況をある程度類推することができます。
そうすると、「利用状況はそれほどでもないのに、電池の減り具合が著しい」とか、「坂道に差し掛かっているのに、電動アシスト機能を使っていないタイミングがある」とか、さまざまなことがわかります。
そして、前者の課題については、「電池を改良すべき」となり、後者については、「電動アシスト機能を使うべきタイミングを自動化するか、利用者に教えてあげる機能を搭載しよう」となるわけです。
- 機能やデバイスの実際の利用状況がわかる
- 利用者にアナウンスすべき内容がわかる
- 次世代の商品に取り込むべき機能がわかる
もし、インターネット経由でのソフトウエアのアップデートだけでこれらのことが実現できるような仕組みをあらかじめ持っていれば、購入済みの電動アシスト自転車であっても、アップグレードが可能となるわけです。
こうやって、改良された電動アシスト自転車は、顧客満足度が向上し、次も同じメーカーの商品を買おうと言う事になるわけです。
こういうと、すごいことをやっているように思うかもしれませんが、実はテスラという米国の自動車メーカーでは、すでにこういったことを実現しているのです。

IoTによる利用状況の把握が、顧客の声を代弁する
電動アシスト自転車の例でもわかるように、IoTによって、コンシューマの製品利用状況がつぶさにわかるので、どの機能が使われていないのか、想定通り使われているのか、といった状況が手にとるようにわかります。
その結果、設計上の問題や開発上の課題も早い段階でキャッチすることができるので。改善活動はスピードアップし、コンシューマも不満を抱えたまま日々を過ごすことなく、メーカーから改善製品のアナウンスを受けることで、ブランドへの帰属意識も増していくという効果が得られるわけです。
これでも十分にすごいのですが、このフェーズではまだ「DXとしては初歩」の域といえます。この範囲であれば、会議室でヒトがあつまって、デジタル技術で集めたデータを整理したグラフなんかを見ながら意思決定しているでしょう。(現状、ここまできている企業もほとんどありません)
しかし、本格的な「DX」では、取得したデータから、コンピュータが自分で判断し、現実世界の活動を変えていくことになります。
データはモノからだけでなく、ビジネス環境にも存在する
実は、上の電動アシスト自転車の例では、利用者に購入していただいた自転車からのデータは取得できますが、「ソーシャルネットワークで語られている話題」や、「社会の変化と消費者ニーズの変化」「生産技術の向上」「仕入れ材料の原価の変動」などは取得することができていません。
実は、この製品を取り巻く必要な情報はもっと沢山あるにもかかわらず、デジタルの力で利用状況のデータを取得できていることばかりに目を向けていると、ビジネスを取り巻く他の環境変化や、顧客の嗜好の変化をとらえることができなかったり、顧客の潜在的なニーズに気づくことができなかったりするのです。
つまり、本来取得すべき「顧客の声」などの、「ビジネス環境の変化」に関して、実際はもっと多くの要素から成り立っているのにもかかわらず、大雑把にとらえてしまい、「本当の最適化」を図ることなくビジネスを進めてしまう場合があるのです。
こういった多くの要素が取得できるようになってきたことを、ヒトが判断することが、ますます難しくなってきていて、セカンドオピニオンのような、ある程度のところまではデジタル技術で判定までしてくれないと、とても会議で決断できる状態ではなくなるのです。
これが、本格的なDX実現の必要性とも言えます。

ビジネス全体もデジタルありきで再構成がはじまっている
さらに、コストに関しても同じことがいえます。
製品一つ当たりのコストは、本来マーケティング、販売、在庫、設計、開発、製造、と横串で見ていかなければならないのですが、実際は、どんぶり勘定で評価している企業がほとんどです。
その結果、コストをゼロから組み立てられる、スタートアップが、自社と同様の製品を作った時、販売ルートの開拓など、長くビジネスを行ってきたからこそ対抗できる領域以外では、勝ち目がなくなってしまう。
実際、Uberのように、初めからビジネスをデジタル中心に組み立てて、極限まで工夫をこらしたスタートアップが登場していて、既存業界においては「ディスラプター」と呼ばれる、新しいプレーヤーが続々と参入してきています。
こちらの記事もよかったら参考にしてください。
DX時代に注目されるディスラプター50社

彼らの多くは、データを前提とすることで、ヒトの力で動かしている既存企業の盲点を見つけ出し、データありきでビジネスの組み立てを行うことで、産業構造全体の最適化を実現しているのです。
つまり、既存事業者は、これまでの競合関係やシェア争いとは全く関係のないところから、突如として、一切無駄がない、デジタルで武装した企業が現れていると言う状況にさらされているわけなのです。
もう、待ったなしで、自社もデジタル武装して、ビジネス全体を再構築したり、商品やサービスのあり方、部署などのあり方、仕事の仕方など、多くのことを見直さざるを得ない状況にあるというわけなのです。
DX時代に必要な人材とは
では、こんなDX時代にはどういう人材が必要になるのでしょうか。
ディスラプターに既存企業が負けないためには、まず、徹底的に自社が取得可能なデータを取得し、活用するための仕組みを整えることが重要になります。しかし、闇雲にデータを集めただけではヒトが判断したり、そのデータを利活用することができる限界に早晩たどり着いてしまうので、如何にデジタルによって自動的に判断させるか、そしていかに、判断結果を自動的に現実世界に戻していくか、こういった工夫を考え、実現することができる人材が必要になるのです。
これは、かなり難しい仕事です。
上位レイヤーのDX人材は、全体を俯瞰できる必要がある
なぜなら、前述した例のように、DX人材となる人が、ある業務だけを見ていれば良いのではなく、一つの会社のビジネスを横断的に知ることが必須となるからです。
「取得できるデータ」「できないデータ」を見極め、その会社のあるべき姿を実現するためのビジネスの仕組み(=ビジネスモデル)を再定義しなければなりません。
そして、ビジネスの仕組み(=ビジネスモデル)を実現するための、ビジネスの流れ(=ビジネスプロセス)を構築していかなければならないのです。
この仕事を、プロデューサー、ビジネスデザイナーと呼びます。
大きな会社であるほど、これは簡単ではありません。DX人材に求められる素養は以下の内容になります。
- その会社のことを横断的に知っている
- 社内のキーマンとのパイプがある
- 論理的に会社の置かれている状況を整理し、未来を予測してあるべき姿を見出すスキルがある
- あるべき姿を実現するために、組織のあり方を見直すスキルがある
- デジタル技術を導入して実現していくスキルがある
こんなことが全部できる人物がDX人材として必須であるとするのであれば、もはや多くの企業がお手上げとなるはずです。
確かに、これら全体を一度にやることは、手に負えないし、現実的ではないのですが、ある粒度で行うことは可能なはずです。重要なことは、上位レイヤーのDX人材には、求める粒度を縦割りに定義しないことなのです。
これまでは、製造業であれば、設計部門、製造部門、調達部門・・・と縦割りに組織を持ってきたと思うのですが、横串に、顧客に提供する価値単位でDXを実現していくことをイメージできる人材となるべきです。
製造業であれば、設計、開発、製造、調達、販売、保守とそれぞれの業務もある程度理解していて、ビジネスを横串にみて、「自社の顧客のためにやるべきデジタル変革を定義できる」ことが重要なのです。
そして、実施段階となると、DX人材は、組織横断で合意形成し、可能な段取りをスケジュールしていくことが求められます。スケジュールに対して必要な人材を現場から引き抜き、順次追加していく。そして、最終的には事業全体を変革していくことになります。
そういった、プロデューサー的立ち位置を求められるのです。
当然、既存事業を動かしながら変化していくことになるので、プロジェクトは簡単には進みません。マーケティングから製造、保守メンテまでを横串にとらえようとすると、そうもいかないことがわかるはずです。
仮に、しかるべき未来がイメージできたとしても、プロジェクトが長期化すれば、そこに向かう過程で、外部環境も、内部環境も、どんどん変化するので、動きながら意思決定し、やり方も変化させなければならない場合もあります。
上位レイヤーのDX人材には、粘り強さも要求されるのです。
具体的に業務を運営する仕組みに落とすDX人材も必要
やるべきことが、具体的になってきたら「アーキテクト」「UXデザイナー」「エンジニア」とより具体的な活動を行うDX人材が必要となります。
やりたいことを実現するための、業務プロセスを構築したり、情報システムの構造を考える。そして、実際に作り込む。できた情報システムが蓄積するデータをどのように読み解くか、また、どう次のビジネスに活用するか、そういった具体的な取り組みを行う人材です。
- 上位のDX人材が定義した、やるべきことを具体かできる
- 業務フローを可視化できる
- DX実現に必要なシステムアーキテクチャを構想することができる
- 業務で関わるヒトの体験をより良いものにすることができる
- 実際にデジタル技術を実装することができる
上位レイヤーのDX人材がある程度の方向性を打ち出してくれたとして、具体的に今の業務をどうしていくのか?新しいデジタルツールを導入するのか?といった具体的な判断をしていき、クラウド環境を使うのか、ネットワークのセキュリティはどう見るのか、など、具体的なシステムアーキテクチャを明確にすることが重要になります。
しかも、現場のヒトに負荷をなるべくかけないための取り組みも必要です。
例えば、作業中に両手が塞がっている業務があって、その状態で、マニュアルをみたいとなると、マニュアルをスマホで提供するのではなく、メガネ型のデバイスで表示した方が良い、となる、といったような、細かな検討が必要になるのです。
集めた大量データを解析、活用するDX人材
そして、作ったシステムが吐き出す大量のデータを集め、解析をしたり、次のビジネスに活かすために「データサイエンティスト」が必要となります。
データサイエンティストというと、AI技術のヒト、というイメージを持つ方もいると思いますが、大量データを扱う人は、データサイエンティストと呼んで差し支えありません。
- 大量のデータを扱うことができる
- AIについての知識と経験がある
- 実際の業務をイメージしたデータ活用の仮説が立てられる
DXはデジタル側から見れば、大量のデータをどう捌くのか、が重要なポイントとなるので、データサイエンティストには、業務知識の方向と、デジタル技術の方向の両軸の知識が求められます。
これが、データサイエンティストの給料が高い理由でもあります。
DX人材がいる企業は急速な社会変化にも負けない
こういった多くの荒波に負けず、DXを遂行する人材を得た企業は、DXを果たすことができ、今後ますます不確実性が増す社会においても柔軟なビジネスモデルと実行能力(=ケイパビリティ)を構築することができるようになるのです。
皆さんも、ぜひ、DX人材となって、急激な社会変化の中で大活躍して給料もドンドンあげていってください。
DX人材に関する、定義や仕事内容については、別の記事でも紹介しているのでこちらも見てみてください。
DX人材の6つの役割と必要なスキル
また、DX人材の育成を考えている方は、ぜひこちらもご一読ください!
非デジタル企業で、DX人材を育成する方法
さらに、DX転職を考えている方は、ぜひこちらもご一読ください!
DX転職で給料をアップする考え方
無料メルマガ会員に登録しませんか?

IoTNEWS代表
1973年生まれ。株式会社アールジーン代表取締役。
フジテレビ Live News α コメンテーター。J-WAVE TOKYO MORNING RADIO 記事解説。など。
大阪大学でニューロコンピューティングを学び、アクセンチュアなどのグローバルコンサルティングファームより現職。
著書に、「2時間でわかる図解IoTビジネス入門(あさ出版)」「顧客ともっとつながる(日経BP)」、YouTubeチャンネルに「小泉耕二の未来大学」がある。