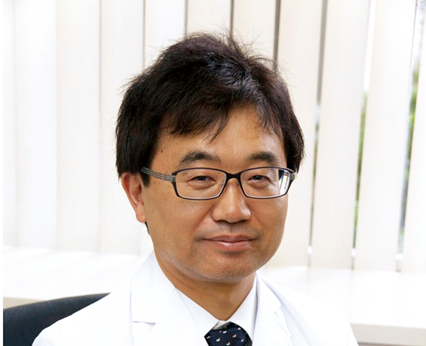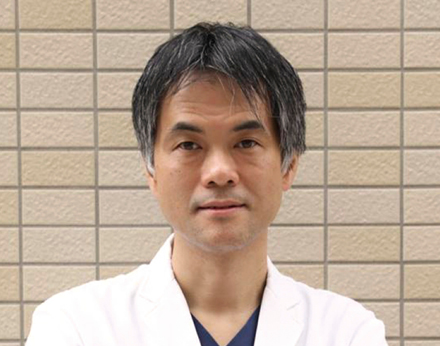今後ますます加速していく高齢化にともない、在宅医療の重要性は増していきます。在宅医療や地域医療に若手の医師が根付いていくためには何が必要なのでしょうか。20年近く、医学生や研修医の在宅医療研修を実施している長尾クリニック・長尾和宏先生が考える課題を、Web医事新報よりお届けします。
在宅研修に来るけれども
当院は20年近く、医学生や研修医の在宅医療の研修を引き受けている。ちなみに当院は朝夕の外来診療の合間に在宅医療を行うミックス型診療所(日本医師会が推進する“かかりつけ医”型の在宅医療を提供する診療所)である。医師だけでなく、看護学生や看護師、ケアマネジャー、介護職の在宅研修も引き受けている。教育を責務とする大学病院とは異なり、日常診療を行いながらの研修医指導はかなりの手間を要する。若者を指導することは診療のエネルギー以上の労力を要し診療効率もかなり悪くなる。しかし数少ない単独型・機能強化型在宅療養支援診療所として「教育機能」は責務だと考えて、これまで何百人の研修者を必死で指導してきた。
終日私が教えることになっている月曜日の研修が終わるのはおおよそ21時ないし22時になる。介護者の就労の関係上、19時頃までデイサービスがあり、夜間しか訪問できない在宅患者さんが少なからずおられ、夜診終了後も在宅を回るからだ。しかし最後までついてきた研修医はほとんどいない。9時・17時ではないが、中には17時が近くなるとソワソワし始める研修医がいる。「暇なので週に2回くらいはゴルフの練習に通っています」と聞き、大変驚いた。自分自身が研修時代は病院にずっと泊まり込み、家に帰ったのは2年間に数日しかない文字通りの奴隷生活であった。医局崩壊、そして働き方改革の結果だろう。研修医のほうが先に帰ってしまうという時代が来るとは夢にも思わなかった。
外科系医師が多い
前回に引き続いて今年も週刊朝日ムック「さいごまで自宅で診てくれるいいお医者さん」の監修を務めさせていただいた。この本では全国の在宅療養支援診療所と在宅療養支援病院の約2600施設が厚労省に届け出た実績をそのまま掲載している。一般市民や病院からみると在宅医療はまさにブラックボックスであろう。いや私たち在宅仲間同士でもお互いの診療所の実績や地域の在宅医療の実態はよく分からない。各診療所の実態を知るには本書が大いに役に立つ。市民に読んでいただきたいのはもちろん、病院の地域連携室に1冊は置いておきたい本だ。
この本を眺めていると実に飽きない。有名だけど実績はさほどではない医師、反対に無名だけどすごく頑張っている医師など、一目瞭然である。患者数と看取り数を眺めているだけでも、さまざまな想像ができる。患者数100人で看取り数100人という診療所は、主に病院から紹介される末期がんを診ているのだろう。一方、患者数2000人で看取り数が5人という診療所は集合住宅を中心に診ていて、終末期は病院送りなのだろう、と。
知人の医師も沢山載っているが、外科系出身者が多いことに気が付く。消化器外科、呼吸器外科、心臓外科、脳外科、整形外科、麻酔科、泌尿器科……。多くの修羅場を経て行きついた先が在宅だったのだろう。意外に少ないのが循環器科や糖尿病内分泌科などの内科系である。
アーリー・エクスポージャー
厚労省と医師臨床研修マッチング協議会が2019年度マッチングの結果を公表した。都会の病院の人気がある一方、地方の病院は定員割れが多く、研修医の偏在は明らかであった。職業選択の自由があるものの、10年後、そして多死社会のピークと推定される20年後の医療を考えた時、臨床研修の在り方は極めて重要だ。特に若手の先生が地域医療や在宅医療に入り、根付くためには何が必要なのだろうか。
そもそも大病院で臨床研修をしないといけないのだろうか。36年前、自分自身は医師が数人で、研修医は私1人しかいないという100床程度の救急病院で2年間の修業をした。平たく言えば野戦病院である。医師になったその日から手術場に入り、麻酔を習い、手術の前立ちをする一方、ひっきりなしに来る救急車の対応、当直業務、外来診療、病棟では白血病や心筋梗塞の重症入院患者の管理、そして末期がんの看取りなどに忙殺されていた。バイトで外来に来る医師の指導も相当受けた。
激しい修行の甲斐あって、2年間で数百人の看取りを経験し総合診療力が身についた。その後、大学病院に5年間勤務。博士号を授与されたあとは4年間市民病院に内科医長として勤務したところに阪神・淡路大震災が起こった。仮設住宅が建ち始めた頃、病院を飛び出して開業し、仮設住宅を巡回することになった。それが医師としての在宅医療の始まりである。しかし振り返れば、19歳の大学入学時に無医地区研究会に入り長野県下伊那郡の無医村で家庭訪問した頃が原点なのかもしれない。いずれにせよ10代で在宅医療に接したことがその後の医師生活に大きな影響を及ぼしている。
現在、私の診療所では新卒の看護師を採用して訪問看護師を養成している。2年で特定看護師に相当する実力を持つ看護師を育て、本人が希望するならば病院に移動してもいいと考えている。看護師の場合は、看護学校1年生が在宅研修に来る。まさにアーリー・エクスポージャー(早期体験学習)である。兵庫県が実施している中学2年生を対象とした職場体験「トライやる・ウィーク」の受け入れ先にもなっており、そこでの経験が看護師の道を選ぶきっかけになった人もいる。
救急や全身管理の経験は必須
では医師も看護師同様、いきなり在宅現場で研修したほうがいいのだろうか。私は、臨床実習や初期研修で半年~1年程度は来てほしいと考えている。その後、救急や麻酔科、あるいは外科系で修羅場を最低3~4年程度は経験し、「全身管理」や「治す医療」、「蘇生する医療」をしっかり学んでほしい。たくさんの修羅場を経験することで初めて、在宅患者さんの急変や終末期の緩和ケア、持続的鎮静に自信を持って対応できる。修羅場を経ずに在宅医療の道に進むのは問題があると思う。在宅医療にもリスクマネジメントという概念が入ってきており、危機管理の能力も問われる。厳しい修行を経てから再び、在宅医療を含む地域医療に戻ってきてほしい。簡単に言えば、真っ先に「支える医療」に少し接してから最低数年間は「治す医療」を学ぶべきだ。しかし現在は真逆である。その結果、在宅医療を始めるのが50代、60代と遅くなる。この年代では在宅医療の肝である夜間対応に弱くなるのは当然だ。そうではなく、体力が充実している30代、40代こそ在宅医療を含む地域医療で活躍できる医師の養成システムに組み替えることはできないのか。
この10月、私は北海道のオホーツク空港に近い広域紋別病院より在宅医療の講演に呼んでいただいた。設備の揃った綺麗な病院で、講演会にもたくさんの市民に来ていただいた。院長は50代前半、副院長は40代半ばと、若い!20人弱の医師はさらに若く、活気にあふれていた。数年前、長崎県の上五島病院を訪問した時も同じ光景を見た。最先端の手術を終えたばかりの医師がそのまま看取り往診に出かけていた。これこそが地域医療だ。治す医者が支える医療も普通に行う。「専門性と総合性の両立」が医師の研修や生涯教育の目標である、と確信している。
2020年から2040年の20年間で急速に多死社会を迎える。その死亡者の半数以上は85歳以上の超高齢者なのだ。超高齢者への急性期医療の需要は少ないことは当然だ。ちなみに2040年後も死亡者数は多少減るが、そもそも人口減少が加速し、それでも85歳以上の死亡者は増え続けることは国立社会保障・人口問題研究所の統計で明らかである。しかし現在の臨床研修では未来予想図に対応できない。病院再編を巡る議論が盛んであるが、ぜひ2040年を見据えた研修制度も検討してほしい。
出典:Web医事新報 連載「町医者で行こう!!」第103回:研修医と在宅医療
※本記事は株式会社日本医事新報社の提供により掲載しています。