私が今書いてる修士論文を書き始めたときに、指導教官がした話が面白かったので書いてみる。
ビジネススクールは、卒業時に論文を書くのは前提ではないので、自分で指導教官を選んで、概要を書いて持っていき、指導教官となることをお願いする。
私は、修士論文の内容を元に本を書きたい、と常々思っていたので、その本の構想を章立てにして、細かく概要を書いて持っていった。
分かっていた反応ではあったが、先生の反応は「これは多すぎる」というものだった。
「これが博士論文であれば、私はこれほど素晴らしい概要は無い、と言うだろう。
でも短期間で書き上げる修士論文としては、あまりに壮大すぎる。」
(そして、この内容なら素晴らしい博士論文が書けるから、と博士課程に進むことを強く勧められた)
私は、「多すぎるのは分かっている。実はこういう内容の本を近い将来書きたいと考えているのだ。
そう考えたとき、私は修士論文では何をすべきか。」
と先生に問うてみた。
そのときに先生がしてくれた話。
「何かを成し遂げようと思うときは、今自分がいる位置からどう積み上げるか、と考えてはダメだ。
出来上がった本なり、目指してるものをを自分が今手にしていることを想像して、今の自分がいる位置を振り返ってみるのが大切だ。
ゴールにたどり着くには、様々な道があり、どの道を通っていけばいいのか、全く分からない。
でも、ゴールにたどり着いた自分から見れば、道は自分が通ってきた一本だけだ。
ゴールにいる自分をよく想像する。
そこから今の自分を振り返ると、一本の通るべき道が見える。
その道をよく見ると、今の自分には大きく欠けている部分(Missing part)がいくつか見えるだろう。
そのMissing Partsこそが、最初に取り組むべきことだ。
このMissing Partは「今の自分に出来ること」をベースに積上げたのでは、絶対に見えない。
だから平凡な人は、いつまでもゴールにたどり着かないのだ。
まずはゴールを精細に思い描き、そこから振り返ってMissing partsを探しなさい。」
私の場合、ゴールである本の概要は明確に見えているわけで、それを書くに辺り、最も弱い仮説を深めて検証するのが、修士論文でやるべきことなのだ、というのはすぐに分かった。
ただ、この話は修士論文ではなく、人生の全ての取り組みにおいていえることであり、
学生に問われたときに、そういう示唆的な話がすぐに出来るのが、教育者の才能なのだ、と思った。
その後も、私のMBA卒業後の進路も含めて、色んな話を先生とした。
いい先生に出会えてよかった、と思った。











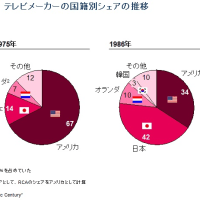
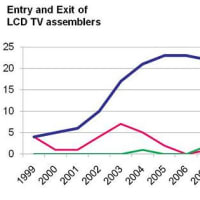
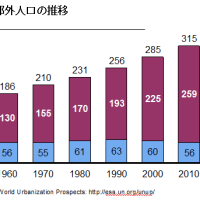
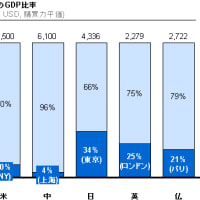

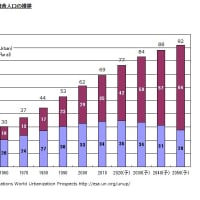
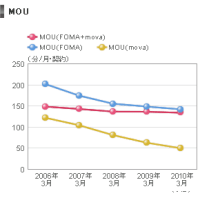
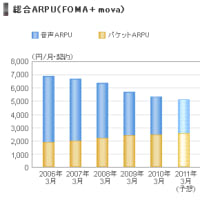
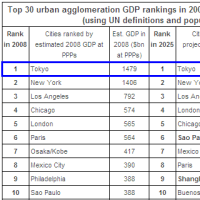
日本で、日本語の本を出すつもりなら、フリーの編集者でもいいし、とにかく経験がある人とコミットした方がいいよ。どんなに内容がよくても、売れないから。まぁ、戦略的に言うと、勝間さんのように、たくさん本を出して、実績を積むのが一番いいだろうね。それと、もし、電子書籍も考えているのなら、先頭を切らないとうまくいかないだろうね。ただ、電子書籍のパイオニアは、日本ではキツイだろうね。英語で書いて、海外で売れようと売れまいと実績をつくっておくのも一つだよね。結局、10冊ぐらい書けるネタをもっていないと、無理だろうな。あと、案外重要なのは、装丁してくれるデザイナーも自分で見つけたほうがいい。ラッピングが悪い商品は、なんでも売れないから。アメリカで全部勝負するなら、厚い一冊でも大丈夫だと思う。ついでに、ライティングスクールも有効だと思う。ま、本のビジネスは、どこの国も結構シビアだと思うね。どこかの会社で、例えば、新しい企業のビジネスで成功して、それを書けば売れるだろうけど。
ま、とにかく、イメージに、アメリカと日本が曖昧なのが一番難しくするかもね。
英語の原文で是非読みたいです。
最近、将来がよくわからない26歳のモラトリアム人間です。w
この記事のおかげで、将来のゴールをもう少し、正確に描写できるようにしようと思いました。
最終的にどんな終始論文になったのかも、よかったら報告を楽しみにしています。
がんばってください。
自分もこれから1 semesterオンリーで修士論文でして、どうしたもんかと思っていました。
私のほうは、本を書こうとかそんな壮大なプランはないわけですが、それでも、フツーに修士論文をイメージするだけで「なんだか、遠いなー!」と、気が遠くなりそうな日々がこのところ続いていたんですが、このエントリをヒントにちょっと整理してみます。ヒントいただきありがとうございます。
イメージできないと、到達できませんからね。
では。
教育者とはこういう人を言うのでしょう。
良い学校には良い先生がいるものですね。
これから大学生になる自分にとって、何となく描いていた目標を達成する為にひとつのヒントを頂いたようで参考になりました。
日記の主題とは少しズレますが質問です(時間が許す時に返事を頂けると嬉しいです)
自分は大学でこれから建築を学ぶ予定です。
最近は調べるほど、建築家として活躍するなら、構造・設計技術は当然、倫理・哲学・宗教・民俗など、多様な教養的知識が必要なのではないかと考えはじめました。
もしこれから、日本(アジア的な意味も含め)人が、世界で活躍する際に建築家として必要だと思うことがあったら教えて下さい。(質問が抽象的で答えにくいかもしれませんが、ラジカルな部分では関係性がある気がするので。)
また普段何気なく感じる、「ここは日本の教育にはないな」逆に「ここは日本の教育の良さだなぁ」など感じる事があったら教えて下さい。
当然教育環境で差はあると思いますが、理系最高学府であるMITと言うことで非常に興味があります。
長いので面倒でしたら何時でもよいのでお返事お待ちしてます!!
興味深いお話しだったので、読まさせていただきました。
ミッシングパートって良いですね!
素敵な本 楽しみにしてます☆
connecting the dots
の話をしていましたが、
点を打って行けば勝手につながっていくという話だったかと思います。
ゴールに向かっていくのか、
あるいは
いつのまにかゴールにいるのか。
将来の形を考えて今を考えるのか
あるいは
今を考えて行くと将来に形になっているのか。
そこらへんがまだよくわかりません。
その先生の話で、現在の自分にミッシングリンクが見えないのは同感。「詳細に想像」で見えるというのは疑問。明らかな見落としが少しは見えるけど、結局今の自分の経験からしか想像できないのでは?僕はそうだった。
ちょっと動いて壁があれば修正するとか業界の先輩と話すなど、これまでの想像と経験の外に出ないとミッシングリンクは見えませんでした。
jobsだって個別の事業に対してはゴールから逆算するアプローチを採ってると思いますよ。
connecting the dotsはもっと気が長い話。