イボタカイガラムシ(イボタロウムシ)の薬効 その2
イボタカイガラムシ(イボタロウムシ)の薬効 その2
第277回 2016.11
会津の名産 会津蝋(あいづろう) イボタの蝋(ロウ)は、疣取りの特効薬、
「最新薬用植物学」 刈米達夫、名越規朗 共著、1973年、広川書店 より
イボタノキ
イボタ蝋は、イボタ、オウイボタ、コバノトネリコ、ヒトツバタゴなどの枝幹にイボタロウカイガラムシの雄の幼虫が分泌する蝋を秋に成虫の羽化して飛去った後、乾燥したものである。本品は白色で大小不同の脆い粒状をなし、80~83℃で溶融し、特異の臭気がある。
虫白蝋は、イボタ蝋を溶融し、布漉しして夾雑物を除き型に注いで角板状にしたものである。
イボタロウカイガラムシは、東京付近では6月中旬、雌体の下にあった多数の卵から先ず雌の成虫が孵化し寄生植物の葉の裏面に移り、葉液を吸収して生育するが、7月中旬葉を去って枝に移り定着しはじめ笠状に、後に球状に変形する。
雄の幼虫は6月中旬~下旬に孵化し、雌幼虫と同じくはじめ葉面で葉液を吸って生活するが、7月上旬には2年~5・6か月の生の枝に移って群生し定着するが9月中旬まで生長を続け白蝋を盛んに分泌して体を覆い白蝋中の幼虫体は卵形に変じ、終に蛹化して白蝋の分泌を止める。
9月中下旬には多数の雄は羽化して出て、近距離を飛び拡がり、定着した雌体に達して交尾し、死滅するが、雌成虫は、肥大し生長をつづけ、翌年3月下旬には体は球状に膨大し、5月に老熟する。
雌は自分の体下に産卵後死し、卵は孵化し生活を繰り返す。
白蝋としての利用部分は枝に移って定着した雄の幼虫の分泌したものである。
薬用 民間:強壮薬として内用し、また止血薬として外用する。
用途・戸滑り、家具の艶出し料に用いる。
「民間薬用植物」梅村甚太郎先生、大正5年3月より、
いぼた Lygustrum Ibota Sieb.
漢名 水蝋樹。木犀科の落葉灌木であって、山野に広く自生する。茎の高さは、一丈余りに達する。
葉は楕円形、全邊にして対生している。五六月頃、小さな白い花を総状をなして開く。
果実は米粒大であって熟すれば黒色となる。樹皮に昆虫のために白色状の粉状物を、常に生ずる。これを蟲白蝋(いぼたろう)という。
蟲白蝋をとって、戸障子などの開閉が困難な時に敷居、鴨居などにぬれば滑らかになることにより、「戸すべり」と云う。
●疣のできたときは、その根を堅くしばり、この蝋を熱したのを一滴を落とせば、疣が抜け去るものである。
●この木の葉を食べる蜀候蛾(いぼたのむし)の幼虫は肺病、胃腸病に効があるとして、民間では炙ってたべる。あるいは、こうも云う。葉もまた焼いて食べれば肺病を治すと。
●弘前辺りにでは、イボタの実を、煎じて服用すれば、腹のカタマリを解き、葉を煎じて服用すれば、歯のゆるぎ痛むのに良いと云う。
「昆虫本草」梅村甚太郎先生、正文館書店、昭和18年11月
いぼたのらふむし Ericerus pela(Chavannes) イボタノカヒガラムシ
○虫白蝋は、他の脂肪に比べれば融解点が高く、摂氏85.5度から83度の間にあるので、特殊の用途がある。
中国では、四川、貴州、湖南、浙江、福建、安徽等の諸省にて、盛にこの虫を養殖している。
四川省に於ける年産額は、かって五百萬斤に達し、その多くは国内の需用に応じ、約五拾萬斤位は他国へ輸出されたが、現今は、その盛況は見られぬであらう。
虫白蝋の利用
○中国では、主として蝋燭の製造に用いる。又、丸薬の外皮に塗布したり、生絲織物の光沢をつけるのに用いた。
△民間にては打撲、切傷などに医用する膏薬に用いる事が多い。
△また、止血、鎮痛及び肉芽の発生を促す作用をもする。
○漢方医は、古来膏薬の原料として用いて来たが、我が国では、煎服して肺病、胃病に効ありとして、これらの疾病に使用してきた。又、疣取りに使用してきた。元来、いぽたの木と言う事は、疣とりの木と言う意味である。
○工業用としては、茶箪笥等のふきこみ、その他の木器具の表面に、これを塗布し琢磨して光輝を生ぜしめた。
又、朱に混じて模造珊瑚の製造の料に供し、書冊の表紙、靴の表面、磁器などの外用に塗布して光輝を附し、或いは、光沢布を作り、また一般家庭に於いては、敷居に塗って戸、障子の滑走を促すに用いる等、その用途は大変に多い。 `
「薬用植物図説」村越三千男、福村書店、1952年1月より
いぼたのき 水蝋樹
Ligus Ibota Sieb.var,augustifolium Blume.
(別名)イボタ・イボタラフ・イボノキ・イボトリ
産地・生態 北海道、本州、四国、九州、琉球、台湾などの林野に自生する落葉の灌木で、所によっては生け垣などの植栽している。幼條には短毛を生じ、幹の高さ1・5~1・9m位に達する。
葉は無柄で対生し、葉身は長楕円形、鈍頭である。
五月頃から梢の上方に白色の五弁花を総状に開き、花の後、小さな毬状をした黒色の果実を結ぶ。
薬用 この植物には一種の昆虫が白い巣を作りつけることがあるから秋冬の候に、その巣のある枝を取って天日に乾かしたものを「イボタ」蝋といって薬用に供する。
即ちこの「イボタ」蝋を煎じ服用すると水腫・利尿に効果がある。
また、手足等に出来た疣を細かい絹糸で固く結びつけてその上から「イボタ」蝋を熱して摘下すると、自然にこの疣を除き去ることが出来るのは不思議な位である。
「新編 中薬誌」 第四巻、肖培根主編、化学工業出版社、2002年12月
虫白蝋の項には、白蝋虫の寄生する植物として、白蝋樹と女貞があげられていますが、日本のとは、違うようです。1樹高が、全く違います。
白蝋樹は(学名が Fraxinus chinensis Roxb. 木犀科 Oleaceae)高さが16m、女貞は(学名 Ligstrum licidas Ait.f. 木犀科 Oleaceae)10mに達するとあります。
性味及び薬効 味は甘く、性質は温である。肌を生じ、瘡を斂する。血を止め、痛みを定める。
瘡瘍が久しく、潰れて斂しないのもの、金創出血等の症状に、用いる。
民間では、小量を内服すれば、強壮剤となり、外用で一は止血にもちいる。用量3~7g、外用は適量。
朝霞の漢方 昭和薬局 薬剤師 鈴木 覚
埼玉県朝霞市朝志ヶ丘1-2-6-106
TEL 048-473-7830 FAX 048-473-7332
このブログの中でひとつでもいいと思ったことがあれば
下のアイコンをクリックして応援していただけると嬉しいです。

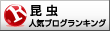

にほんブログ村
アクセスランキング参加中
☆☆☆実際に応用する場合は、自己責任で☆☆☆
そうだ!健康相談に行こう
【昭和薬局】薬剤師 鈴木 覚
〒351-0035 埼玉県朝霞市朝志ヶ丘1-2-6-106
【電話】048-473-7830
【FAX】 048-473-7332
【昭和薬局ホームページ】http://www.saitamakanpo.com 埼玉漢方ドットコム
【昭和薬局ブログ】http://showayakyk.exblog.jp/
第277回 2016.11
会津の名産 会津蝋(あいづろう) イボタの蝋(ロウ)は、疣取りの特効薬、
「最新薬用植物学」 刈米達夫、名越規朗 共著、1973年、広川書店 より
イボタノキ
イボタ蝋は、イボタ、オウイボタ、コバノトネリコ、ヒトツバタゴなどの枝幹にイボタロウカイガラムシの雄の幼虫が分泌する蝋を秋に成虫の羽化して飛去った後、乾燥したものである。本品は白色で大小不同の脆い粒状をなし、80~83℃で溶融し、特異の臭気がある。
虫白蝋は、イボタ蝋を溶融し、布漉しして夾雑物を除き型に注いで角板状にしたものである。
イボタロウカイガラムシは、東京付近では6月中旬、雌体の下にあった多数の卵から先ず雌の成虫が孵化し寄生植物の葉の裏面に移り、葉液を吸収して生育するが、7月中旬葉を去って枝に移り定着しはじめ笠状に、後に球状に変形する。
雄の幼虫は6月中旬~下旬に孵化し、雌幼虫と同じくはじめ葉面で葉液を吸って生活するが、7月上旬には2年~5・6か月の生の枝に移って群生し定着するが9月中旬まで生長を続け白蝋を盛んに分泌して体を覆い白蝋中の幼虫体は卵形に変じ、終に蛹化して白蝋の分泌を止める。
9月中下旬には多数の雄は羽化して出て、近距離を飛び拡がり、定着した雌体に達して交尾し、死滅するが、雌成虫は、肥大し生長をつづけ、翌年3月下旬には体は球状に膨大し、5月に老熟する。
雌は自分の体下に産卵後死し、卵は孵化し生活を繰り返す。
白蝋としての利用部分は枝に移って定着した雄の幼虫の分泌したものである。
薬用 民間:強壮薬として内用し、また止血薬として外用する。
用途・戸滑り、家具の艶出し料に用いる。
「民間薬用植物」梅村甚太郎先生、大正5年3月より、
いぼた Lygustrum Ibota Sieb.
漢名 水蝋樹。木犀科の落葉灌木であって、山野に広く自生する。茎の高さは、一丈余りに達する。
葉は楕円形、全邊にして対生している。五六月頃、小さな白い花を総状をなして開く。
果実は米粒大であって熟すれば黒色となる。樹皮に昆虫のために白色状の粉状物を、常に生ずる。これを蟲白蝋(いぼたろう)という。
蟲白蝋をとって、戸障子などの開閉が困難な時に敷居、鴨居などにぬれば滑らかになることにより、「戸すべり」と云う。
●疣のできたときは、その根を堅くしばり、この蝋を熱したのを一滴を落とせば、疣が抜け去るものである。
●この木の葉を食べる蜀候蛾(いぼたのむし)の幼虫は肺病、胃腸病に効があるとして、民間では炙ってたべる。あるいは、こうも云う。葉もまた焼いて食べれば肺病を治すと。
●弘前辺りにでは、イボタの実を、煎じて服用すれば、腹のカタマリを解き、葉を煎じて服用すれば、歯のゆるぎ痛むのに良いと云う。
「昆虫本草」梅村甚太郎先生、正文館書店、昭和18年11月
いぼたのらふむし Ericerus pela(Chavannes) イボタノカヒガラムシ
○虫白蝋は、他の脂肪に比べれば融解点が高く、摂氏85.5度から83度の間にあるので、特殊の用途がある。
中国では、四川、貴州、湖南、浙江、福建、安徽等の諸省にて、盛にこの虫を養殖している。
四川省に於ける年産額は、かって五百萬斤に達し、その多くは国内の需用に応じ、約五拾萬斤位は他国へ輸出されたが、現今は、その盛況は見られぬであらう。
虫白蝋の利用
○中国では、主として蝋燭の製造に用いる。又、丸薬の外皮に塗布したり、生絲織物の光沢をつけるのに用いた。
△民間にては打撲、切傷などに医用する膏薬に用いる事が多い。
△また、止血、鎮痛及び肉芽の発生を促す作用をもする。
○漢方医は、古来膏薬の原料として用いて来たが、我が国では、煎服して肺病、胃病に効ありとして、これらの疾病に使用してきた。又、疣取りに使用してきた。元来、いぽたの木と言う事は、疣とりの木と言う意味である。
○工業用としては、茶箪笥等のふきこみ、その他の木器具の表面に、これを塗布し琢磨して光輝を生ぜしめた。
又、朱に混じて模造珊瑚の製造の料に供し、書冊の表紙、靴の表面、磁器などの外用に塗布して光輝を附し、或いは、光沢布を作り、また一般家庭に於いては、敷居に塗って戸、障子の滑走を促すに用いる等、その用途は大変に多い。 `
「薬用植物図説」村越三千男、福村書店、1952年1月より
いぼたのき 水蝋樹
Ligus Ibota Sieb.var,augustifolium Blume.
(別名)イボタ・イボタラフ・イボノキ・イボトリ
産地・生態 北海道、本州、四国、九州、琉球、台湾などの林野に自生する落葉の灌木で、所によっては生け垣などの植栽している。幼條には短毛を生じ、幹の高さ1・5~1・9m位に達する。
葉は無柄で対生し、葉身は長楕円形、鈍頭である。
五月頃から梢の上方に白色の五弁花を総状に開き、花の後、小さな毬状をした黒色の果実を結ぶ。
薬用 この植物には一種の昆虫が白い巣を作りつけることがあるから秋冬の候に、その巣のある枝を取って天日に乾かしたものを「イボタ」蝋といって薬用に供する。
即ちこの「イボタ」蝋を煎じ服用すると水腫・利尿に効果がある。
また、手足等に出来た疣を細かい絹糸で固く結びつけてその上から「イボタ」蝋を熱して摘下すると、自然にこの疣を除き去ることが出来るのは不思議な位である。
「新編 中薬誌」 第四巻、肖培根主編、化学工業出版社、2002年12月
虫白蝋の項には、白蝋虫の寄生する植物として、白蝋樹と女貞があげられていますが、日本のとは、違うようです。1樹高が、全く違います。
白蝋樹は(学名が Fraxinus chinensis Roxb. 木犀科 Oleaceae)高さが16m、女貞は(学名 Ligstrum licidas Ait.f. 木犀科 Oleaceae)10mに達するとあります。
性味及び薬効 味は甘く、性質は温である。肌を生じ、瘡を斂する。血を止め、痛みを定める。
瘡瘍が久しく、潰れて斂しないのもの、金創出血等の症状に、用いる。
民間では、小量を内服すれば、強壮剤となり、外用で一は止血にもちいる。用量3~7g、外用は適量。
朝霞の漢方 昭和薬局 薬剤師 鈴木 覚
埼玉県朝霞市朝志ヶ丘1-2-6-106
TEL 048-473-7830 FAX 048-473-7332
このブログの中でひとつでもいいと思ったことがあれば
下のアイコンをクリックして応援していただけると嬉しいです。

にほんブログ村
アクセスランキング参加中
☆☆☆実際に応用する場合は、自己責任で☆☆☆
そうだ!健康相談に行こう
【昭和薬局】薬剤師 鈴木 覚
〒351-0035 埼玉県朝霞市朝志ヶ丘1-2-6-106
【電話】048-473-7830
【FAX】 048-473-7332
【昭和薬局ホームページ】http://www.saitamakanpo.com 埼玉漢方ドットコム
【昭和薬局ブログ】http://showayakyk.exblog.jp/


