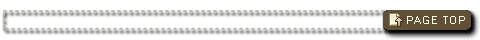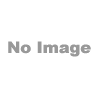ASCOが終わったところでした。
ASCO(43回アメリカ臨床腫瘍学会)の演題で急性期緩和ケアに関するものがあったようです。(日経メディカルオンライン)
この記事によると急性期緩和ケアとは、
『終末期に限定したケアと考えられがちな緩和ケアだが、最近は治癒を目指す治療をサポートする支持療法として早期から導入し、患者の病期、症状に応じたケアを選択していく。』
以前、緩和ケアはいつからという話をさせて頂きましたが同じような内容で今更って感じがしました。
特に、アメリカのAnderson癌センターからの発表でありましたので余計に。
また、癌専門医に、患者に悪い知らせを伝えるための正式なトレーニングをとの記事もありました。
がんの告知、再発、根治的治療の終了時などが悪い知らせ(breaking bad newsといいます。)でありそのときの患者さんとのコミュニケーションの技術をえるためのトレーニングのことです。
SPIKESとされており
S(setting、skill)プライバシーの守れる場所、アイコンタクトを取る、院内PHSなどで邪魔されないようにする、などです。
P(Perception)患者さんの理解、認識度を確かめて行う。
I(invitation)患者さんの心の準備を確認する。(詳しい話を聞きたいのか、手短に話して欲しいのか。)
K(knowledge)専門用語を使わず、理解、心の動揺を確かめながら行う。
E(empathy、exploration)気持ちを理解する。患者さんの感情に共感する。(『大変驚かれたでしょう。こんな、話をしないといけないのは残念です。』など)
S(strategy、summary)今後の方針と要約
以前、ある研究会(名前は忘れましたが、講師はアメリカの先生でした。)で勉強したことがあります。
この発表において、アメリカでは80%のがん専門医がこのトレーニングを受けていないとしています。
日本がどうだかわかりませんが、この2つの演題をみると日本の緩和医療も決して遅れているわけではないんだな。と思いました。
今後、どんどん緩和ケアを必要とする患者さんは増えるはずです。緩和ケアに精通した医療関係者が増えますように。
『人気ブログランキング』へ←ポチッとお願いします。
米国の方が圧倒的に緩和医療に関して進んでいると思っていたので、少し意外な感じがして記事にしました。