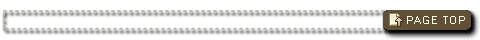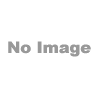薬には相互作用があります。
薬剤Aと薬剤Bを一緒に使うとAの薬の作用が増強される。
とか、
薬剤Aと薬剤Cを一緒に使うとAの薬の作用が減弱される。
とかです。
その中で超有名なのが『シトクロムP450 CYP3A4』です。
これは、薬物を分解する酵素の一種でこの酵素で分解される薬は多いのです。
また、この酵素を働きにくくする作用を持つ薬や、この酵素を誘導して普段以上に働くようにする作用を持つ薬があります。
薬でなくても例えば、セイヨウオトギリソウやセント・ジョーンズ・ワートなどと呼ばれる欧米でよく用いられる不眠などに使う健康食品もここに影響してこの酵素で代謝される薬の効果を減弱させます。
また、身近なところではグレープフルーツやそのジュースが有名です。
グレープフルーツもシトクロムP450 CYP3A4という酵素を分解しにくくします。
そうすることにより、薬の濃度をあげます。
ここで、薬の濃度をあげるということはどういう事か?
『より薬の効果が出る。』も正しいですし。
『より副作用が出やすくなる。』も正しいです。
一般的な薬は、効果と重篤な副作用の濃度の差が大きいのであまり問題になることはありませんが、抗がん剤では問題になります。
分子標的薬と呼ばれる抗がん剤の副作用には十分注意を払わなければなりません。
現在、日本でもいろいろな分子標的薬が認められています。
イレッサの話しも昔しましたが開発当時は予想もしなかった副作用(肺傷害など)が出ています。
最近は、イレッサよりも広い範囲で効果を出す薬(マルチターゲットドラッグ)まで認可されています。
例えば、スニチニブ(スーテント)がそうです。
腎癌やGIST(頻度の低い消化管腫瘍)で適応になっています。
この薬は、VEGFやPDGFやc-kitなどの作用して抗腫瘍効果を発揮します。
(イレッサやタルセバはEGFR一カ所だけへの効果でしたね。)
いろんなところに効くので効果もあるのですが、副作用も予期しないようなものが出ています。
例えば、皮膚毒性や下痢はイレッサやタルセバほかの分子標的薬でもよくみられたし、高血圧や出血などは、血管新生を抑えるアバスチンなどでみられました。
スニチニブは、甲状腺機能低下症や皮膚が黄色くなったりします。
また、好中球や血小板などが減少することがあります。
この副作用は、今までの殺細胞性の抗がん剤では一般に認められる副作用ですが分子標的薬ではほとんど報告がありませんでした。
(もちろん、他にも副作用ありますよ。)
ここで、話しを戻します。
このスニチニブは、例のシトクロムP450 CYP3A4で代謝されます。
つまり、グレープフルーツジュースなどで効果が増強しますし、副作用も増強するのです。
分子標的薬とはいえ抗がん剤は抗がん剤ですから、普通に使用していても致死的な副作用が出る可能性があります。
それが、グレープフルーツジュースと併用したら。。。。
恐いですね。
ちなみに、ある種の真菌薬と併用するとスニチニブの血中濃度が約1.5倍となるようです。
恐い。。。
もちろん、減弱させるものもあり、相互作用のために効果がなくなった。なんて可能性もあります。
しっかりと決められたことは守って、飲んでる薬や健康食品まで担当医や薬剤師に教えてくださいね。
そうしないと、恐いことがありますからね。
恐いと思った方『人気ブログランキング』へ←ポチッとお願いします。
よくわからなかった方は、『分子標的薬とは?』を先にお読みください。