リュウキュウツツジ | 関寺紫(セキデラムラサキ)
2024年11月10日

分類:琉球ツツジ(半落葉樹)
名前:関寺紫(セキデラムラサキ)
開花期🌸:4月中旬
4月の中旬から下旬にかけて開花する。
強健で日差しや乾燥に強い。
花以外の特徴は関寺とほぼ同じ。
暑さ🌞:強い。根付けば真夏の直射日光に耐える。
寒さ⛄:強い。東京では気にする必要がない。
乾湿💧:乾燥に少し弱く、若干の湿気を好む。
高温多湿💧:強い。
自生地:無し(日本の園芸品種)
品種登録:❎
商標登録:❎
在庫状況:✅
| 概要 |
関寺の枝変わり品種。
関寺は咲き分け品種で一つの株に白花、紫花を同時に咲かせるが、
関寺紫は咲き分けを一切せず紫花しか咲かなくなっている。
関寺のように花弁に別色の絞りが出ることもなく完全な一色咲きであり、
蜜標の色が濃く範囲が広いのは関寺と同一。
色も形もかなり類似した品種に同じリュウキュウツツジの紫琉球があり、
私も最初は本種を紫琉球と認識していたが後に関寺紫であると園芸家に教えて貰った。
私が管理する山に元から植栽してあった2本のツツジの内の1本で、
山に住む友人の祖父が昔に植えた関寺の古木からこの関寺紫が出ているので考えてみればそうだろう。

葉は関寺と同じくかなり粘り、触った後にベタベタとした感触が手に残る程の粘着力がある。
花期は花周りに虫の死骸などがくっ付く光景も変わらない。
要するに花色が紫色で固定されていること以外の要素は全て関寺そのままなので、
強健な性質も変わりなく関寺紫に受け継がれておりとても育てやすい。
ただし、古い品種故に苗木が全く流通しておらず、入手手段が極めて限られるのが難点。
元になった関寺と同じく江戸時代初期に生まれた品種であり、現代では関寺よりも更に観察の機会が限られる。
| 写真 |


咲き分けはしないが稀に色素の薄い花を咲かせる。
| 育て方 |

関寺の性質そのままで全体的に樹勢は強健。
根付いていれば真夏の直射日光にも耐え、乾燥にもそこそこ強い。
強健とはいえ基本的にはツツジらしく適度に湿った土壌と程々の日光を好む。
ある程度の耐陰性があり暗過ぎなければ半日陰でも一定数花を付けるが、
どちらかといえば陽樹で日光を好むので明るめの場所に植えると良い。
葉が粘り他のツツジと比べると害虫が若干付きにくいが、
付くときは付くので夏頃は一ヶ月に一度殺虫剤を散布すると万が一がなくなる。
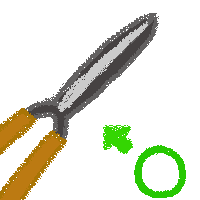
萌芽力があり刈り込みは可能。
花芽が形成されるのが初夏なのでその頃剪定をすると翌年の花芽を落としてしまうが、
関寺紫は樹勢が強く条件さえ良ければ意外と根性で花を再生成する。
ひこばえを根元から大量に出し、徒長枝も凄く新枝は非常に勢いがある。
樹形がかなり暴れやすいが剪定で単幹に仕立てることも可能。
その場合は最低でも1m以上背を出してやると樹勢が少し落ち着いて管理しやすくなる。
立性が強く放置すると縦に伸びていくが、
野生種に通ずるワイルドな伸び方をするので放置すると縦どころではない凄まじい姿になる。
| 雑記 |

関寺紫は関寺の枝変わり品種。
関寺は峰の松風の枝変わり品種なので、関寺紫は枝変わり品種の枝変わり品種ということになる。
私が山で管理している関寺紫は関寺の古木の枝から繋がって変化しており、
実際に枝変わりしたというのがとても分かりやすい。
この変化した枝は切断して挿し木しても性質をそのまま受け継ぎ、
以降挿し木苗が成長しても紫花しか咲かない株になる。

関寺は白花を機軸に紫花が咲き分け、もしくは絞りとして同じ株に少数発現するもので、
そのレア側である紫花が主軸になっている関寺紫は中々特別感がある。
色的には大紫ツツジ系の鮮烈な赤紫色ではなく、
モチツツジやキシツツジ系の淡いピンク色を少し濃くしたような色合い。
色が淡い故に濃いマゼンタ色の蜜標が殊更花弁に映える。
蜜標は虫がおしべに向かう時に迷わないよう存在する模様らしいが、
これだけはっきりと発色していれば虫も分かりやすいかもしれない。





