2009.09.12 「思い出の夏 その九 」 『別れ』 <<02:34
別れの朝がやってきた。
熱を出したおかげで 2日余分にはいられたが、それはあっという間の一週間だった。
出発の日の朝も、これまでの朝と同じように、かまどの煙のにおいと、
ご飯の炊きあがる甘い香りで目を覚ます。
まだ一週間やそこらでは、父の家の天井などの模様に慣れきってはいない。
いつも、どこで目が覚めたのかわからなくて少し戸惑った。
それでも、目覚めは、いつも、何か楽しい予感を伴ってこれまで毎朝
訪れてきた。病気で寝ていた時でさえそうであった。
しかしその日の朝は違った。
目覚めた瞬間に、悲しみの感情がさっと心に流れ込んできたのである。
今日は父と別れて母のもとに帰る日。
そういう自覚さえ、まだ頭に浮かばないぼんやりした目覚めの瞬間にも、
悲しみの感情というのはさっと忍び込むものなのである。
熱はもう下がっていた。
母には、私が熱を出したので、帰りが2,3日遅れるということを
電報で知らせてあった。そして今日帰る、ということも。
父と二人でとる最後の朝食。
またいつここに来られるか、わからなかった。
父の作ってくれた味噌汁の中に、涙が一粒。
別れの時が来るのは早い。
バスの時間が近づいていた。
叔母や従兄のお嫁さん、見習いの美容師さん、そしてコロまでが、
見送りに出てきた。バス停まで皆でぞろぞろと歩く。
T駅までは、従兄が送って行ってくれることになっていた。
用事があってちょうどTの街まで行く予定があったからである。
父も当然、私を送ってくるつもりだったのだが、
「。。兄ちゃんが送ってくれるからいい。」と私が断ったのである。
「そうか。それもいいかも知れんの。」父は私の気持がわかったようだった。
「それじゃあの。また帰って来いの。」
バスが来て、私が乗り込もうとするとき、父は言った。
そしてすぐに横を向いた。
「うん。」
ステップを上って中から振り返る。
父は私を見上げていた。黙ってうなづく。
その顔の前で、車掌がドアを閉じた。
「またおいでな。」
叔母達が口々に言って手を 振った。
バスが動き出す。
私はバスの最後尾まで行って、大きな窓から、遠ざかる人々の姿をじっと見つめていた。
みんなから少し離れて一人立つ父の姿が、涙で滲んで見えなくなった・・・・・・・・
それから25年後。
父は老いて、この故郷の地で、一人死にました。
覚悟の死でした。
私は小学校5年生になった一人娘を連れて、父の葬儀のために故郷に
帰りました。奇しくも、私がこの話の中でそうだった同じ5年生です。
しかも季節は同じ夏。
私たちは同じルートをたどって、T市に入りました。
しかし、時間は、あの輝かしかった夏の日と同じではなく、
もうすっかり暮れきった時間帯でした。
駅からタクシーに乗って、暗い高原を走って行きました。
青い、凄味のある月が出ていました。
父の亡くなった家は、この話に出てくる離れではありません。
離れはとうの昔に取り壊され、叔母の家には知らない人が住んでいました。
美容院も叔母亡きあとは無くなって、あの綺麗だった、私の憧れだったダリア畑や
叔母の野菜畑があったところには、幾棟かのアパートが建っていました。
父の死に顔は立派でした。
しっかりと口を引き結んで、しっかりと目を閉じて。
通夜の夜は、時折強い雨がさあーっと屋根に降りつけてまた止む、といったような
荒れ模様の天気でした。
それは親不幸だった娘の私に対する、父の抗議の声のような気が私はしていました。
その後の私は残酷な娘になって、ろくに父に会いにも帰らなかったのです。
ろうそくの火をたやさないようにすること。
それが今、父にわずかにしてやれることでした。
皆はさすがに疲れて眠りこんでいました。
私と父だけ・・・・・。
心の中を嵐は吹き荒れてやみません。
その私の心に呼応するように、時折吹きつける雨と風・・・・。
だんだん夜が明けてきました。
ちち!と、何かの鳥が寝言のような声をあげます。
そのうちに、ちち、ちち、という声が賑やかになっていきます。
聞いたこともない美しい鳥の声でした。
雨はいつのまにかやんでいました。
葬儀が始まる前のわずかな時間。
私は5年生の娘を連れて、家の裏の道を上って行きました。
その家は、少し行くともう草原につながるような位置にありました。
昔、私が喜々として父と摘んで歩いた花々。
あれを娘に見せたかったのです。
高原の間を続く道を、私は少し先まで歩いて行きました。
花はちっとも咲いていません。僅かに名も知らない地味な青い花が咲いているだけ。
あの夏、私に花の名を教えてくれた父はもう私の傍にいませんでした。
私を高原の奥へ奥へと誘って、美しい花を好きなだけ摘ませてくれた父は
もう私を案内してはくれません。
あまり先まで踏み込むと、私は娘ともども迷子になってしまいそうでした。
ああ、お父さん!
あなたの親不孝な娘は、ここで一人、行き暮れてしまいました!
あなたにこの、今私の傍にいる孫娘の顔を見せてやればよかった!
そうしたら、あなたはどんなに喜んで、どんなに張り切って、
山の仙人のようなあなたしか知らない、秘密の美しい美しいお花畑へと、
私たちをいざなって行ってくれたことでしょうか!
(終わり)

皆様、これで沈丁花の記事はすべて終わりです。
わずか8カ月余りでしたが、皆様とお会いできて幸せでした。
皆様のご健康とお幸せをお祈リしています。
ありがとうございました。
最後に、このブログのタイトルをとった唱歌、「故郷の廃家」を
よろしければお聴きください。
http://www.youtube.com/watch?v=m-b08yZSUVY
2009.09.11 「思い出の夏 その七」 『魚つり』 <<21:16
「さあ、今日は、川に行って魚を釣るからの。
美味い魚をお前に食わせてやリたくての。お前の竿も用意しといたで。」
翌々日、父は朝から張りきっていた。
父は釣りが大好き。それで母はいつも私に愚痴をこぼすのだった。
農繁期にも、釣りに出かけてしまう男だ、と。
「これから餌のミミズをちょっと用意するからの。おまえは雨戸を開けといてくれるか。」
父はそういって外へ出て行った。
私は言われたとおり、雨戸を開けに行く。
父の住む離れは、普段出入り口にしている勝手口からまっすぐに土間がのびていて、
そこが竹細工の作業場になっている。右手に茶の間、その奥に座敷が、縦に並んでいた。
道路に面したその座敷には短い廊下がついている。
座敷も廊下も真っ暗だ。
雨戸を繰ろうとして、ふと足元を見ると、雨戸に開いた小さな穴から
朝の太陽が幾筋か射し込んでいた。
その一筋の光線の中で、細かい細かい埃がもやもやと踊っている。
光線は暗い廊下の壁で途切れて、そこが丸い輪を描いていた。
しゃがみ込んでよく見ると、その輪の中に表の道路が逆さになって映っている。
ちょうど通りかかったバスや、向かいの菓子屋などが、くっきりと
幻燈のように映し出されていた。
面白くて、私はしばらくしゃがんだまま、その逆さになった小さな景色を眺めていた。
雨戸が開く様子がないので、父が表からこんこんと叩いて合図をしてきた。
はっと夢から覚めたように、私は立ち上がって雨戸を開けにかかる。
朝の陽が差し込むと、座敷も茶の間も一気に明るくなった。
座敷の床の間には、昨日私が摘んで帰って、しばらく冷たい小川の水に漬け、
それから活けた野の花たちが、どれもぐったりと首を垂れていた。
叔母に教えてもらって小川の綺麗で冷たい水の中で、水切りもしたのに、
花たちは元気のないまま、今朝はもう、萎れかかってしまっている。
私は悲しかった。
あんなに綺麗な花たちだったのに!
この腕いっぱいに摘んで帰って、母屋のおばさん達にも分けてあげ、
父の座敷に、大切に一所懸命活けた花たちだったのに。
「野の花は水揚げが悪い。」そうおばさんは言っていたが、やっぱり
綺麗な花たちは枯れてしまおうとしている・・・・。
私のせいだった。
あんなに野原では元気に美しく咲いていたのに・・…。
私はしおしおとして、父を探して外に出た。
父は離れの際に一本伸びている、大きな柿の木の辺りにいた。
しゃがみ込んで盛んに手を動かしている。
傍に行ってみると、柿の木の下のいつも少しじめじめした地面を掘って、
ミミズをとっているのだった。
私はちょっとぞっとして、少し離れたところから見ていた。
でも、釣りの支度をする父は、とても楽しげだった。
昨夜も、土間の、いつも作業をするござの上に坐って、翌日使おうとしている
釣針や、おもりや浮き、魚籠などを念入りに点検していた。
私用という、 少し短いつりざおも用意された。
「さあて、行こうか」
父が立ち上がると、土間に寝そべっていたコロものっそりと立ち上がった。
私達の後をついてくる。
今日は、表のバス通りからではなく、叔母の畑の、奥の木戸から父は出ていく。
杉木立でミンミンやつくつく法師が盛んに鳴き交わしていた。
コロはしばらくの間、私の横を歩いていたが、これから高原にはいる、という
道の前まで来たとき、父が
「コロ。もうおまえは帰れ。」と言うと、まるでその言葉がわかったかのように、
おとなしく家の方に引き返して行った。
私は少し残念。コロも一緒だとよかったのに。
渓流まで来るのにだいぶ歩いた。
ごろごろした石ばかりのところに一か所、私でも足場を確保できそうな、
狭いけれど小石ばかりを敷き詰めたような平らな一角があり、
父はそこで荷物を置いた。
叔母さんが用意してくれた、おむすびの弁当もある。
父は私のために釣りざおをセットしてくれた。
「こうして。」と言いながら、糸の投げ方を教えてくれる。
私はその通りにやってみる。
が、木々がうっそうと両岸に茂っている渓流で、私はすぐに糸を木に引っかけてしまった。
父が外しに行く。また引っ掛ける。
でも父は決していやな顔をしなかった。
すぐに餌を取られてしまっても、またつけてくれる。
私はただ糸を垂れるだけ。
私の世話で忙しく集中できないのか、父にもなかなか当たりは来ないようだった。
「お前、ここにおれるか。」と訊く。
「うん。」と私。
父は私を一人置いて、川をほんの少し下ったところの、川が淵になっているところのあたりへ
移動していった。
私はしばらく我慢して釣り糸をいじくってはいたものの、やはり退屈になって、
竿は岸辺に置き、崖の上の、父の姿がよく見える所に移動した。
父は静かに釣りざおを構えている。
水はその辺りでは深い淵になって、緑色を帯びている。
それでなくても涼しい高原の風が、ざああっと木々を揺らして吹き抜けて行った。
風が少し湿り気を帯びてきたようだ。
日陰の木立の中にいた私は少しぞくっとした。
その日の午前中の父の釣果はあまりはかばかしくなかったようだが、
それでも、このあたりで「えのは」と呼ばれている美しい魚が
3匹釣れていた。
父の、年期の入って飴色になった魚籠の中に、20数センチあるかなと思うくらいの
魚が、あっぷあっぷしている。
魚籠の中から、水の匂いが立ちあがった。
銀色の膚に黒っぽい斑点が並んでいる。ところどころに赤い小さな斑点も。
胸鰭などは黄色味を帯びている。
それは綺麗な魚だった。
「『えのは』というのは、外んところじゃ、普通はあまごとかヤマメ。
「ふうん。」
私はあまり食欲がない。
折角叔母さんが朝早く起きて作ってくれた美味しそうな弁当も、
あまりたくさん食べられなかった。でも、これもやはり叔母さんが朝早くから
準備して作ってくれた酒まんじゅうは美味しかった。
このあたりで、「かんから」と呼ばれている丸っこい葉っぱの上に乗せて
蒸しあげてあって、酒のほのかな香りと、その葉っぱの匂いが
白い皮にうつっている。
昼食後も、私は時々は釣竿を取りあげてはみたが、私の手にかかるような
エノハなど、いるはずもなかった。
私は、少し日も当たる草地を見つけて、そこで少しうとうとしたり、
また父の見える崖の上に行って、金平糖をなめていたりした。
父が時々場所を変えて、私から見えないところに行ってしまうと不安になった。
それでも、大きな声を上げて父を呼んだりはしない。
私は、自分で言うのも変だが、聞きわけのいい少女であった。
明日はもう父と別れる日であった。
5日はあっという間に過ぎてしまった。
今度いつ、また、父とこうやって会えるかわからなかった。
それが、私が心を弾ませられない、一つの理由であったかもしれない。
でも、今はこうして父といる。それだけで十分だった。
夕方、父はいそいそと夕餉の支度にとりかかった。
朝の茄子の味噌汁を温め、卵焼きを作り、大根おろしをする。
そうして、何より、今日の一番の料理は、エノハの焼いたのであった。
母屋からのさし入れの、煮物や冷奴、漬物などもある。
私が、小さな丸いちゃぶ台に箸などを並べて待っていると、
父が母屋から、焼きあがった魚を大事そうに捧げ持つようにしながら戻って来た。
「さあさあ、食べなあ。美味いぞー。」
魚が跳ねて踊っているように串にさして、こんがりと焼き上げられた魚は
本当においしそうだった。皮の焦げたいい匂いがする。
ぱくりと食いつく。香ばしい味が口いっぱいに広がった。
思わずにこりとすると、自分は食べるのを忘れて、私の反応をじっと見つめていた
父も、大きく笑った。
「お前にのー。これを食べさしてやりたかったんじゃ。」
しかし、私は多くを食べることができなかった。
その晩から熱を出してしまったのである。
夕飯の時はすでに熱があったのかもしれない。
父だけでなく、皆が大騒ぎであった。
薬を飲ませる。氷枕を作る。熱を測る。
私の熱が明日も下がらなければ、明日帰る、と思っている母に
どう連絡しよう、とか、。。さんは怒るじゃろうなあ、とか、
皆が色々なことを同時に心配してあたふたしていた。
2009.09.09 「思い出の夏 その八 」 『旅先の病い』 <<09:32
魚釣りをしたその日は、夜半を過ぎてからやはリ雨が降り出し、
座敷で寝ている私の耳にもその雨の音は届いた。
終始熱でうとうとはしていたが、時折目覚めると、自分がどこで寝ているか
わからない時があった。
田舎の夜は静かである。外ではもう、秋の虫が鳴き始めていた。
暗くした部屋で、慣れない天井を熱のある眼で見ていると、
母の看病が欲しくなった。母が心配するだろうと思った。
父は横に自分の布団を敷いて、静かに目をつむっていたが、
時折起き上がっては、私の額に手をやり、その手を自分の額において、
熱を比べたりする。頭の上にのせた手拭いは、すぐに熱で生温かくなり、
洗面器の水もぬるくなってしまう。
父は静かに音をたてないように勝手口の戸を引き開けて、
冷たい小川の水に汲み替えるために、暗い戸外に出て行った。
結局私は、それから2日間、熱で寝込むことになった。
父はつきっきりで看病してくれた。
小さい頃から病気がちで、肺浸潤などで二度も入院したことのある私。
父はまたそういう事態が起こりつつあるのではないかと、本当に心配していた。
でも、私自身は、熱で体が痛くてだるいのも、とろとろと眠いのも、
いっそ気持ちよく、病気を楽しんでいた節もある。
起きて何かをする、ということはなくても満足だった。
父が、土間で、竹細工をする気配を座敷にいても感じ、
時々父が、「どうかの。」とにこにこしながら様子を見にやってくると、
水が飲みたいだの、「あとで西瓜ね」などと言って甘えきっていた。
朝方少し下がった熱も、夕方になるとまた上がってくる。
ぼうっとした耳に、夕暮れ時、小川のほとりの杉林や、叔母の野菜畑の
ぐるりを取り巻く屋敷林で鳴くヒグラシの、悲しげな声が、届いてきた。
2009.09.08 「思い出の夏 その六 」 『高原へ』 <<10:33
父が朝の洗いものを済ませて戻って来るとすぐに,私たちは家を出た 。
叔母の家でも、既に美容院の仕事が動き始めているようだった。
一昨日バスで通った通りに出る。
父は、美容室の向かいの煙草屋兼お菓子屋に入って行く。
古びて薄暗い店内だが、もうずっとここで商売を続けてきた店らしく、
品物は豊富で、、ガラスのケースの中に、せんべいやビスケットなど、
いろいろな菓子が取り揃えてあった。
父はそこで、自分には刻み煙草を、そして私にはお菓子を買ってくれた。
私がいつも懐かしく思うふるさとの、黒砂糖味のお菓子。それに金平糖。
その黒砂糖の菓子は、私が好きだということで、夏の私の誕生日と、
クリスマスの頃に、必ず父が他の収穫物などと共に、荷物の中に
入れておいてくれるものだった。
日はもうすでにかなり高くなっていて道をかっと照らしつけてはいたが、
高原の空気は乾いていて暑さは感じなかった。
日陰に入ると、ひんやりと涼しい。
私たちは、ささやかに人家の続く道を、バスの一駅分ほど、昨日来た方向に
歩いて行った。
集落のはずれ近くにバス停があり、そこは雑貨屋になっていた。
麦わら帽子やざる、虫取り網など、店先に賑やかに吊るしかけてある。
父はそこで、私に麦わら帽子を買ってくれた。
ピンクの縁取りのを。
私の頭が意外に大きいので、いくつもサイズの違うのをかぶせなおしてみては笑っている。
店主の女の人は父と昔からの知り合いらしく、私が一緒にいるのを見ると、
「おや、こん子は誰じゃったかな」と聞いてきた。
「こりゃあ、わしの末子じゃ。」と父が答える。
「ありゃ、それじゃあ、こん子は、・・・ちゃんかな。」
「そうじゃあ。」
私の全く見知らぬ人が、私の名前をよく知っているらしいのが不思議だった。
その雑貨屋のちょうど前あたりが高原に入っていく道。
夏草が勢いよく茂る切り通しの道を、父は少し前のめりになりながら上って行った。
足がOの字だ。
私は父の少し後についていく。
道の両側の植物を珍しく見ながらついていくのでどうしても遅れてしまうのだ。
最初に見つけたのは、赤紫色のやわらかそうな花の咲くアザミ。
でも、葉は、ごつい針のような棘があって痛い。
なんでこんなに痛そうな葉や茎にこんな柔らかい花が咲くのかな。
私が手折ろうかどうしようか迷っていると、父が「欲しいんな」と聞いてきた。
黙っていると、黙って、持ってきた小ぶりの山刀のようなもので切り取ってくれた。
そして、「これはわしが持っていってやろう。」
父の手は、小柄な人にしては大きく、ごつごつしていた。
長年竹を扱って(母と私と皆で住んでいた温泉街の家でも)、
その手は、竹の鋭い切り口にも負けないような、分厚い手になっている。
アザミくらい平気なのかしら。
「あ、ナデシコ!」
次に私が見つけたのは、ピンクの5弁の可憐な花の撫子だった。
これは私でも折りとれる。2本3本と、土手の草むらに生えている。
だいぶ、高原の中に入りこんだところで、道は切れ、そこから先は
開けた草むらがずっと続いていた。

ナデシコもそうだが高原には、キキョウ、女郎花、などの秋の花が
もうここかしこに咲いていた。
キキョウは青紫色の5弁の花、女郎花は黄色い小花が扇状に広がっている。
フジバカマも秋の七草だ。これは少し地味な花だが、他をひきたてる。
萱草と彼岸花のどちらにも似ている、キツネノカミソリ、という、朱色の花。
綺麗なので私が摘み取ろうとすると、
「それは毒じゃ」と父。
私が手をひっこめると、父は笑って、平気でその花を摘み、私にくれた。
口に入れさえしなければ、摘んだくらいでは平気なのだという。
トラの尾、という白い房状の花もある。
リンドウの青も綺麗だった。
中でも私が一番気に行ったのは、途中で抜けて通った林の中に咲いていた、
大きな山百合の花だった。少しクリーム色を帯びた白の花弁には、
濃い赤の斑が入っていて、花弁に黄色い筋が入っているのと、
雄蕊が白百合のような黄色ではなく、暗い赤でしかも大きいので、
とにかく目立つ、華やかであでやかな花だった。
「高原の女王じゃの」と、父が言った。
百合といえば、他にも、可愛らしいピンクのササユリもあった。
それから、少し朱色がかった赤の、コオニユリの花も。
私は夢中になって花を摘んで歩く。
父はあとからゆっくりついてくる。
花の名前は皆、父が教えてくれた。
ふと気づいて私は訊いた。
「こんなに摘んでいいの?」
「ああ。かまやせん。山の花じゃ。好きなだけ摘めばいい」
もう私は自分の手にいっぱいなくらい、花を摘んでいた。
「どうかな。少しここらで休むかな。」
「うん」
父は草むらの間によっこらしょと腰を下ろした。
短いスカートをはいた私のためには持ってきた新聞紙を敷いてくれた。
父と並んで、草むらの中に低く坐って、あらためて辺りを見渡すと、
そこは広々とどこまでも草原の続く、まことに気持ちのいい眺めであった。
花摘みに夢中になっていた私は、それまであまり周囲を見渡してこなかったのである。
幾重にも重なりながら遠くまでのびていく草原の広がり。頭上に広がる青い空。
草原を吹きわたる、いい匂いの風。そして、明るく輝く夏の太陽。
そうして、かなたになだらかな稜線を見せてそびえる、私のふるさとの山…
父が水筒の水をくれた。
歩きまわって汗ばんだ体に、冷たい水は何にもまして美味しかった。
持ってきた袋をガサゴソ言わせて、父がさっき買ってきた黒砂糖の菓子や
金平糖を取り出す。
じっと、そうやって坐っているとなんだか眠くなってくる。
先に横になっていた父に倣って、私も草の上に体を横たえた。
ああ、いい気持ち・…
小さな小さな蜂が、耳元でう~ん、と羽音をさせる。
大きな体のクマンバチのようなのも、これはブ~ンと低く太い羽音をさせて
頭の上を飛行していく。
空が眩しい…
ふと、横の草むらに目をやると、これまで見たことのない変わった花が目に留まった。
「この花、なに?」
「ああ、それか。それはネジバナじゃ。」
なるほど、草竹20センチほどのその花は、すうっとのびた茎に、小さなピンクの花が
ねじれたようにくるっと上まで巻きついている。可愛い花だった。
あそこにも、ここにも。
でも私はもうそれらを摘まなかった。見ているだけで面白かった。
遠くで放牧されている牛の声がのどかに響いてくる。
大きな牛がこちらまで草を食べに気はしないか、と思ったが、
父と一緒ならだいじょうぶ。
何しろ父は山のことなら何でも知っているようだった。
私にはなだらかな草地がどこまでも続くとしか思えない高原を、
父は方向がわかって案内していってくれるし、花の名前、草の名前、
鳴き交わす鳥の種類なども、本当に詳しかった。
「この山と高原、どこでも知ってるの?」と訊ねると、
「ああ、そりゃあ、まあの。」とのんびり笑っている。
その上父は、釣りの名人、また、山に自生する山芋掘りの名人でも
あるという叔母の話だった。
こんな父と一緒なら、高原をどこまで行っても大丈夫なのだ。
帰りは、また、少し花を摘みながらゆっくりと帰ったが、
来た道と違うルートを取っているようで、案外早く高原を切りぬいて作った細い道に出た。
「あ!」。私は足をとめた。
「おお。それはホタルブクロじゃの。」父が言った。
「ほおう。まだ咲いとったか。お前にこの花を一番見せたかったんじゃ。」
それはリンドウのような釣鐘型の花が、下向きにさいている、少し紫がかった
薄いピンクの花だった。
「ほたるぶくろ?」
「ああ。その中にとらまえた、ホタルを入れてやると、花の中で
蛍がぼーっと光って、綺麗なんじゃ。しかしわしらはこれをカッポンというて」
父はそのうつむいた花を一輪折りとった。
「これをこうして口の中に入れて、ぷっと吹くと、花が割れて、カッポン!という音がする。
やってみようかの。」
「ううん!いい!」
私はあわてて父の手から、その花を取った。
そっと花の中をのぞく。
細かい毛が生えていて、中は柔らかく温かそうだった。
この花の中に入って、ぼんやりとした薄明かりに照らされ眠ったらさぞ気持ちがいいだろうな。
ほんとう。ホタルの寝床みたい…
「ほたるぶくろ」・・・・・、なんて可愛い花・・・・・・。
この花がいちばん好き・・・・・・。
早く家に帰ろう。
花たちがしおれかけている。帰って冷たい小川の水に浸けてやろう。
私は、父の先に立って道を元気よく下りて行った。
向こうに叔母の家の屋敷林が見えてきた・・・・・。

2009.09.06 「思い出の夏 その五 」 『街の子』 <<02:48
二人は、朝早くにやってきた。
私の姪。MとTの二人である。
姪とは言うが、長姉と私は18歳も年が離れているので、
Mは私と同い年の小学5年生。Tは3つ下の小学2年生であった。
3年前に私の温泉街の家に彼女たちが訪ねて来た時以来だったので、
私の方は最初なんとなくぎこちなく感じたが、
MとTはこの上もなく素直で何の隔てもなかった。
母親から、私が帰ってきているから遊びに行ってやれ、と言われて、
夏の高原の道を30分以上も歩いて、遊びに来てくれたのである。
二人とも、日焼けした顔の額や鼻の頭にまで、小さな汗の粒を浮かべていた。
二人とも、小柄だが胸板の厚い、しっかりした体つきをしている。
話し出しがいつも、「あんな」で始まるのがなんだかおかしかった。
「あんな、母ちゃんが、後で遊びに来いと。」(あのね、母ちゃんが後で遊びに来なさい、だって。)
「あんな、そこの小学校にあとで遊びに行こうな。」
という具合。
二人が来た、と聞いて、母屋の叔母が冷たいスイカを切って持ってきてくれた。
小川の水で十分に冷やされたそれは、甘くてみずみずしく、食べ応えがあった。
三人は母屋の台所を抜けて、小川を飛び越え、小学校の校庭に行った。
川のこちら側にも杉の木立。蝉の声が相変わらず賑やかである。
広い土の運動場には、遠くに、ちらほら子供の影が見えたが、夏休みのこととて、
がらんとしていた。
三人は小走りに校庭を横切って早速、鉄棒に取りついた。
と言っても、実は飛びついたのは2人だけ。
私は大の鉄棒嫌い。跳び箱も、マット運動も、雲梯も、皆苦手だった。
だから内心大変困りながら、少しまねごとをしただけ。
前方支持回り、という、いわゆる一番簡単な前回りをやってみるが、
着地の時、足がバタン!と聞き苦しい音を立てるので、
鉄棒が下手なことはすぐにわかってしまうのだった。
一方、M子とT子は鉄棒が上手かった。
とりわけ、無口な下のT子は、まだ2年生なのに、逆上がりや足かけ回りなど
平気でやる。
何気なく鉄棒に飛びつくと、その頑丈そうな体に反動をつけて、
後ろ回りなども平気で出来るのだった。
二人の同級生やその弟妹でまだ小学校にも上がっていないような子までが
いつしか集まってきて、私を注目する。
言葉や服装が違うと目立つのである。
私が一言、何か言うたびに皆がこちらを見るのには困った。
しかし、そこにいた子皆で、だるまさんが転んだ、などをして遊ぶうちに、
その垣根はやがて取り払われていった。
昼近くなって、私は二人と、二人の家、つまり私の長姉の家へと向かった。
高原の道を道草しながらダラダラと帰る。
叔母が畑から折り取ってきてくれた、ほおずきの赤い実を揉みながら
行くのでなおさらだった。
赤い袋の口を破り、橙色の丸いほおずきの実をゆっくりゆっくり時間をかけて
揉んでいると、やがて、付け根の方から、じくじくと汁が出てきはじめる。
少しづつその汁と中の種を付け根の隙から出していって最終的に
風船のように仕上げる。これを唇にあてて軽く噛むと、「グビッ」とか「ブビッ」とか
言うような音がして、子供たちはこれを飽きずに鳴らして遊ぶのである。
急ぐのは禁物。
袋を破らぬよう、それぞれが難しいところに差し掛かると、交代で途中で立ち止まって
しまうので、3人が姉の家に着いた時には、昼どきをだいぶ過ぎてしまっていて、
待ちくたびれた姉から少し怒られた。
姉の家の前庭はきれいに整えられている。
片隅には築山風の造作をしてあって、大きな生け簀には綺麗な色の鯉が、
泳いでいる。
ダリアのような花の形と葉の匂いの、黄色い花が池の周りに
大きな株となって無数の花をつけていたが、あれは何の花だったのだろう。
働き者の舅と、きつい姑。
姉は小さな女だった。
夜。
今日も母屋で夕食を食べ、父と二人、離れに戻ってきた。
母屋は蛍光灯の明かりがまぶしいほどだったが、父の離れの居間の電球は
100ワットでもなぜか薄暗く侘しい感じがした。
でも、私にはこの方が親しみやすかった。
夜になると、父が扱う竹細工の材料の、竹の匂いが強く感じられる。
何本も地面に置かれた長い青竹。
それを父は小刀で縦に長く何本にも割いてゆく。
2ミリほどの太さになった竹ひごは、やがて父の手によって、籠やざるに
編まれていくのである。
これが今の父の職業であった。
リズミカルな父の籠を編む手つきを見ていると、
もともと手を動かすのが好きな私。うらやましそうな顔をしていたのか、
「お前も小さいのを作ってみるか」、と父が言った。
父に倣って竹ひごを組んでいく。
静かな二人だけの夜が更けていく。
「明日はどうするか。魚釣りに行くかの。それとも、高原に遊びに行くか。」
「高原でお花摘み!」
私は即座に答えた。
2009.09.05 「思い出の夏 その四」 『最初の朝』 <<13:35
朝、いい煙の香りで眼を覚ました。
寝間の襖はしまっていたが、僅かな隙間からでも、父がかまどで燃やす焚き木の匂いが
漂い漏れてきていたのである。
針葉樹の燃えるいい匂い。
それに、ご飯の炊ける甘い香りも重なっている。
昨夜は母屋で、父や叔母。大きい従兄とそのお嫁さん、二人の間の赤ちゃん、
そして住みこみのインターン生の人などと一緒に、賑やかで、山の幸いっぱいの
食事をお腹いっぱい ごちそうになった。
それでも、ご飯を薪で炊く匂いは最高である。
「おお、起きたか。まずまあ、顔を洗っておいで。」
父がかまどから振り返って言った。
洗面は、母屋の横を流れる小川の水でする。
この小川の水は、山のどこかからか湧き出でて、高原の間を縫ってここまで流れて来る。
水は飽くまでも澄み切って、手を入れると飛び上がりそうになるくらい冷たかった。
小川の向こうは杉木立になっていて、そのさらに向こうは小学校の校庭。
杉木立の間から、朝日が差し込んで、川底の小石や砂をきらきら
輝かせている。
朝早いミンミンゼミやつくつく法師が、頭上の杉木立の中で
うるさいほどにもう鳴き交わしている。
それはもう、蝉の大合唱、と言ってもよかった。
叔母が母屋の台所から朝の食器を持って出てきて、冷たい小川の水に浸けた。
こうしておけば、川がいつの間にか、綺麗にしてくれるのである。
「よう眠れたな?」
「はい。」
「後で、高原の方に連れて行ってもらいなあ。美しい花が今頃はたくさん咲いとるから。」
叔母は笑顔でそう言ってまた母屋に入っていった。
どこからか、犬のコロがのっそりとまた現われて、私の横で水を飲んだ。
「コロ。おいで。」
そう言うと、私の後になり先になりしてついてくる。
コロは、本当は母屋の犬なのだが、農家であって美容院もやっている母屋の人々は
大抵忙しく、犬にかまってなどいられない。コロはよく、静かで優しい父の作業場で
一日を過ごすことが多いのだった。
私とは、昨夜のうちに仲良くなっていた。
父の家まで来ると、勝手知ったもののように、私の先に立って、
暗い土間の中に入って行く。
朝食の支度はほぼできていた。
父が釜の蓋を開けると、ご飯の白い湯気と甘い香りがたちのぼる。
お腹がくうーっと鳴った。
ふんわりと米粒が一粒一粒立ち上がった、釜で炊いたごはん。
そして、父が作ったみそ汁と卵焼き・・・。
ええっ!味噌汁にキュウリが入っている?
私は驚いたが、父は平気な顔で味噌汁を啜っている。
私は、ふと、母の顔を思い出し、涙が一粒、お椀の中にこぼれそうになった。
母は味噌汁にキュウリなど入れない。
柔らかく似たそれは、まずいものではなかったが、やはり私には奇妙だった。
いつも父は、こんな風に一人、かまどでご飯を炊いて、
キュウリなどの入ったみそ汁を作って食べているのだろうか。
そうして、母も今頃、私のことなど心配しながら、一人で食卓に向かっているだろうか。
どうして、父と母は一緒に暮せないのだろう・・・・・。
昨夜、生まれて初めて、父と二人で過ごす夜。
枕元の行燈形のスタンドの薄明かりの中、
私は母のことをどう思うか、父に聞いてみた。
常は優しい母は、いつも、父のこととなると、神経質になり、
父が、農作業より釣りをしたり本を読んだり、尺八の練習をしたり、ということなどの方が
好きで、家にいるより、この、妹の家にいることが多かったこと。
そこには気の強い姑までがやってきていて、母は一人家に残され、
幼い子供達と、若い頃、籾がらが目に入って失明してしまった舅と、
東京の士官学校に入ったが結核を得て、今は離れで養生する義弟と
それらすべてを抱え、広い田畑の農作業もほとんど一人で必死になってやったことなど、
生活力のない父のことは悪くいってばかりだったからである。
「そうじゃの。」父は私の質問に答えていった。
「若い頃は,そりゃあ、色が白くて綺麗だった。
髪の毛が真っ黒で、重いほどに豊かで多くての。」
父の口からは一言も母の悪口は出なかった。
それはその後もずっとそうであった。
それなのに……。
朝食後は、私の長姉の娘で、私にとっては姪にあたる子たちが2人で遊びに来るはずだった。
長姉は、父や叔母の家からさらに奥に、歩いてまるまる30分もかかるところに、
嫁に行って住んでいた。
そこから2人は私に会いにやってくる。
姪と言っても、私より、一ヶ月ほど先に生まれた子と、私より3つ年下の子たちである。
遊び相手としてこれほどいい相手はなかった。
さあ、父の家での最初の一日が始まる! 私の夏休みだ!
これからおよそ5日ほど。
父と思い切り二人で過ごせるのだ!
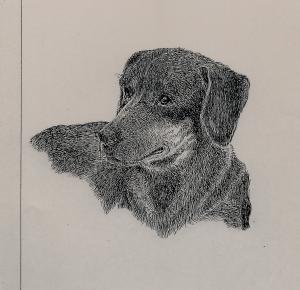
2009.09.04 「思い出の夏 その三」 『父の家』 <<10:39
バスは渓谷地帯を抜けた。
古びた農家が道の脇に点在する別の村を通る。
農家の前庭には、むしろを敷いた上に老婆が坐って、虫食いのマメか何かを
より分けているのが見える。庭先には大抵、百日草、千日紅、クレオメなど、
色も姿も優しい花々が咲いていた。
放し飼いの犬が、時折バスに沿って歩いていたりする。
「母屋の犬が遊びに来るで。」父が言った。
「本当?」
嬉しかった。私は犬を飼いたくて仕方がないのだけれど、アパート暮らしでは
望めなかったからだ。
やがて、目の前が広々と開けてきた。
いよいよ高原地帯に入ったのだ。
右にも左にも、なだらかな牧草地が広がっている。
牛の群れが呑気そうに草を食んでいるのが見えた。
時折、モーン!と頭をもたげて鳴く声ものどかさを増す。
バスの窓からは刈りたての草の匂いが甘く濃く漂い入ってくる。
いつもなら、20分もすると車酔いをして気分が悪くなる私が、
今日はちっとも酔わない。
高原を吹く風はバスの速度と合わさって、私の顔に吹き付けてくるが、
私は目を細めてその強い高原の風を楽しんでいた。
父はそんな私を黙って見ている。父とバスの揺れを共に感じているのが楽しかった。
「さあ、着いたで。」
父の声に目を覚ます。いつの間にか気持ちよく眠ってしまっていたらしい。
バスを降り、小学校らしいものを右に見て、少し道を引き返す。
そこが、父の妹、私にとっては叔母の家であった。
道路沿いに建つ割合大きな木造の家で、一部は美容室になっている。
細い側溝に澄んだ水がちょろちょろと流れていて、小さな木橋を渡ると、
前庭が店の前に広がっている。
夏の乾いた土に、赤、黄色、橙、白などの松葉ボタンの花が一面に
咲いていた。
父は店の方からではなく、横手の勝手口の方から妹の家に入って行った。
傍には幅1メートルくらいの小川があって、綺麗な澄んだ水が流れていた。
外の明るい日差しの中を歩いてきた者には、台所は最初真っ暗で、
反対側の出口がぽっかりと暗い中に口を開けているだけ。
「よーい!」父が声をかけると、奥の店の方から、小走りにかけてくる足音がした。
「あれまあ、あれまあ、よう来たなあ!」とにぎやかな声。
それが父の妹のH子叔母であった。
背の高い、浅黒の顔の、しかし、父に似て優しい大きな眼をした人である。
台所は広い土間の上に、大きなかまどや、ポンプでくみ上げる井戸、流しなどが
あるのが見て取れた。何か、豆腐のからのような甘い匂いが染みついている。
これが田舎の家の匂いである。忘れられない故郷の匂いの記憶。
奥からはさらに、いとこのお嫁さんも賑やかに出てきた。
さあさあ、まず上がって冷たいジュースでも飲みなさい、という叔母の言葉を
さえぎって、父が、「いや、まず先に離れで荷物を解かせよう」と言ってくれたので
私は内心ほっとした。
先ほど見えた反対側の戸口から外に出る。
そこは叔母の家の裏庭で、広い広い畑になっていた。
丈高く伸びたトウモロコシの畑は風にさやさや音をたててかすかに揺れている。
その隣にはナスの畑。つやつやした茄子が葉の陰から覗き、紫色の花も先の
収穫を約束するようにたくさん咲いている。
きゅうりの棚も大きく、そこには黄色い花。トマトは大きな赤い実。
インゲン豆の棚には、つるが勢いよく伸びて、赤い小さな豆の花が咲いている。
ああ、なんて広い畑なんだろう!
母がアパートの庭の一角を借りて細々と作っているキュウリやトマトとは大違いだ!
それでも、母は野菜作りが上手。毎年、手のひらにズシリと重い見事なトマトを収穫する。
ああ、母さん!
胸がズキン!とした。
今頃母は、一人アパートの部屋で、うつむいて縫い物をしながら、
私のことを想っているのではないだろうか。
列車の旅にして5時間。さらにバスで1時間近く。
私は母から遠く離れて、今父とともにいる。
寂しさが胸を打った。
そんな寂しさを吹っ飛ばせてくれたのが、叔母のダリア畑だった。
小屋脇の小川の縁に沿って、六畳間2部屋を縦に並べたくらいのひろさのダリア畑が
作ってあったのである!
赤、黄色、濃いピンク、薄いピンク、白。さらには赤と白の二色咲きのもの。
形も子供の頭くらいはありそうな大輪の花から、丸っこい形のぽんぽん咲きと言う
種類のもの、また小ぶりの花がたくさん付いたもの・・・・。
ありとあらゆる種類のダリアが咲き乱れていたのである。
なんて見事なんだろう!
私は、大きな、自分の背丈ほどもある、ピンクのダリアに顔を近づけてみた。
葉がこすれて、ダリア特有の青臭い、新鮮な香りがする!
私の好きな香りだった。
「見事じゃろう。私がただ自分の楽しみのために、毎年作っとるんじゃ。」
叔母が片方の脇の下に大きなザルを抱えて後からついてきて言った。
私は目を輝かせてうなづいた。
「後から、美味しい、甘い甘いトウモロコシを茹でて食べさせてやるけんな。
荷物を置いて、楽な服に着替えたら、また母屋の方に来なさい」
叔母はそうにこにこしながら言い置いおいて、トウモロコシ畑の中に入って行った。
父の住む離れはそのトウモロコシ畑の手前。
大きな柿の木の傍らにあった。
古い農家の離れである。暗い戸口を跨いで入ると、ここも土間。
昔、ここは私の祖父が病の身を横たえていた。そんなかすかな記憶があった。
薄暗くした部屋に、北向きの障子窓からの明かりが弱々しく入ってくる、
そこに寝ている人の姿・・・・・。
でも今は、薄暗いながら、風がさわやかに吹き抜け、綺麗好きの父らしく、
部屋は綺麗に掃き清められてあった。
土間には父の竹細工の材料や道具が所狭しと置いてある。
4、5メートルはありそうな、長い青竹が何本も積んであり、
出来かけの、籠も蓆の上に据えてある。
片隅には小さなかまど。
青い竹の匂いと、かすかなおからのような匂いがここでもする。
「さあ。まずは上がりなあ。」
父が言った。
入口の高い敷居を跨いで、大きな黒い犬がのっそりと入ってきた。
2009.09.03 「思い出の夏 その二」 『父との再会』 <<02:38
T駅に列車が停まると、拡声器からいきなり、美しいテノールの歌声が流れてきた。
このT市ゆかりの作曲家の歌である。
駅から少し行くと、この歌のモデルになった荒城が今もある。
ホームの端の花壇には、グラジオラスやカンナなどの、丈の高い夏の花が
爽やかな高地の太陽の光をいっぱいに浴びて、赤や黄色の鮮やかな花を咲かせている。
崖の上の木立からは、降るような蝉の声が聞こえてくる。
空気はひんやりとして冷たかった。
二つ三つホームを隔てた駅の改札口に、父の姿らしきものが見えたが、
私はわざとそちらは見ないようにして、姉とその恋人の後を歩いていた。
改札口の脇に、やはり父は身を乗り出すようにして待っていた。
にこにこしながら、私の荷物を受け取る。
「よく、帰ったの。」と一言。
私はこくりとしたが、なんだか恥ずかしくてまともに顔を上げられない。
姉だけが頼りのような気がして、姉にすがるような目を向けても、
こちらに背を向けて、これから登山という大きな装備を点検しているところで、
もう心はすでに山に向かっているらしかった。
姉は母と私の家を時々勝手に飛び出しては、この父のもとへ帰ってきていた。
勝気な母と勝気な姉はぶつかり合うことも多く、姉はどちらかというと、
昔から、父方についていたのである。
だから父と顔を合わせても、今さら特別何も言うことがあるわけではなく、
連れの大学生を軽く紹介しただけであった。
「じゃ、あたしたちはここで別れるからね。」
駅前のロータリーに出ると、姉はそう明るく言い置いて、
あとは振り返りもせず、恋人の大学生と共に去って行った。
大学生の友人たちとここで合流した後、私と父が向かう故郷の村の方からではなく、
別のルートで山に登るのだという。
私は父と二人。
まだ顔もろくに見合わせられない私だったが、胸の中は懐かしさでいっぱいだった。
ああ、この顔!
少し茶色味を帯びた、優しい目。鼻筋が通って頬骨がくっきりしている。
口元は引き締まっている。
父は整った顔の男だった。
しかし、私は父がもう50近くなってからの末っ子。
父の老いは隠せなかった。長年の農作業や山に分け入って魚を釣ったり山芋を掘ったり、
という暮らしに、脚がOの字に曲がってしまっているのが、子供心に悲しかった。
白い半袖の少しよれっとしたワイシャツを着て、頭には白っぽいパナマ帽。
3年前の夏に別れた時のままの父の姿であった。
私は懐かしさで何も言えない。父の後からただ歩き始める。
「お前、よく背が伸びたのう」
父は私が大きくなったことに驚いていた。
父は男にしては小柄な方であったから、私はもうほとんど父の身丈に
追いつきかけていたのである。
無口な父と無口な娘。
二人はこの町の一番賑やかな方へ歩いて行った。
私の生れた村。父の住む家は、このひなびた町の駅からバスに乗って、
さらに40分ほども、深い林や高原の間の道を通っていかねばならない。
次のバスがでるまでには時間があるので、買い物を少ししていくのだと父はいう。
小さな町の商店街は歩けばすぐに端まで来てしまうほどの大きさでしかないが、
父はそこで本屋に立ち寄ると、私にさらにもう一冊、少女雑誌を買ってくれた。
先日の誕生日の折に父が送ってくれたのとは別のを。
次に町の小さな洋品店に入っていって、私が遠慮するのにもかかわらず、
夏のワンピースを一着買ってくれた。
それは、私が母と住む賑やかな街のデパートにだって、あまりないのじゃないかと
思うような洒落たワンピースであった。
和裁は出来ても洋裁を習ったことはない母が作ってくれる、
シンプルで飾り気のない服をいつも着ていたから、
既製服の、しかも田舎の町にしては珍しく凝った作りの美しいワンピースを
買ってもらって、本当に嬉しかった。
色は紺。襟と、そで口とに、暗めの赤で細い縁取りがしてある。
そうして、スカートの裾はスカラップ(波型に飾り切りすること)されていて、
そこも、同じ赤の布で、綺麗な縁取りがなされていた。
私が大事そうに、本と服との2つの包みを抱え込むのを見ている父は嬉しそうだった。
バスはひた走りに走って、ふもとの町からだんだん高原の方へと入っていく。
暗い杉の林が両側に延々と続き、急にそれが明るくなったかと思うと、
道の片側が開けて、そこは深い崖を見下ろしている。
眼下には、流れが激しく岩にぶつかって白く泡をたてている急流や、
逆にとろとろと淀んだ深い淵もあって、そこは水も緑の色を湛え、
いかにも魚か何かが隠れていそうなのだった。
「うまい魚を釣って、焼いて食わせてやるからの。」
私はまた、こっくり頷く。
父は村でもちょっと有名な、渓流釣りの名人なのであった。


