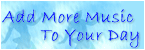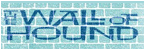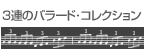前回は更新して半日もたってから、ひどいチョンボをしでかしたことに気づき、記事を修正しようかとも思ったのだが、すでに相当数の方がご覧になったあとのこと、やむをえず、つぎの記事で補足することにした。
◆ ウォルターL氏再び ◆◆
なにをやらかしたかというと、話はやや錯綜するので、周章てず騒がず、ゆっくりと行く。
若いころはすでにとりあげたDusterがバートン=コリエルのもっともいいアルバムと考えていたのだが、ボビー・モージーズのドラミングが好ましく感じられるようになってからは、Gary Burton Quartet in Concert Live at Carnegie Recital Hallが、この顔合わせのもっともいい瞬間を捉えた盤だと考えるようになった。
その理由は単一ではないのだけれど、最大の理由はWalter L.で、そのことを云い、もうすこし突っ込んで書く予定だったのに、オリジナルやカヴァーのことに気をとられて、それを失念してしまったという次第。面目ない。もう一度、くだんの曲をここに置く。
The Gary Burton Quartet - Walter L. (HQ Audio)
音楽のほとんどはそうだが、とくに4ビートでもっとも重要なのはプレイヤー間の対話、インタープレイがエクサイトメントを生む。その意味で、この4人がもっとも白熱した対話を交わしたのはこの日の、この曲の時だったと思う。
ロイ・ヘインズからボビー・モージーズに交代したことで、前作からリズムのニュアンスが変わったのだが(8ビート寄りのセンスになる)、このライヴでは、モージーズに交代したことが実を結んだと感じる。
それはとりわけコリエルとの「話」がストレートになったことにあらわれているのだが、なかでもWalter L.でのソロは、モージーズがカタパルトを提供したおかげでワイルドなほうへと向かった感じで、後半にすばらしいエクサイトメントが生まれている。

コリエルのトーンは、ソロに入った時から、当時の4ビートとしては常識外れの歪ませ方だが、2:35あたりから歪んだコードを多用して、いよいよ4ビートのニュアンスが消えていくと、モージーズも極端に強いスネアやシンバルのアクセントでコリエルを蹴り上げる。知るかぎりのコリエルのソロで、このあたりの展開がベストではないかと思う。
ボビー・モージーズはもののわかったドラマーらしく、ラリー・コリエルのソロが終わって、ゲーリー・バートンのソロに入ると、それまでよりビートを弱くする。ヴァイブラフォーンという楽器はワイルドにはプレイできないものなので、ギターのようには強いビートと拮抗することはできない。
ボビー・モージーズの盤はほかに十枚ほどしか聴いたことがないが、結局、この曲でのドラマティックなプレイがいちばん印象に残った。若いころのプレイを代表作とは云われたくないだろうけれど。
◆ 間違っていることが正しい ◆◆
LPで云うとここからB面に入って、再びラリー・コリエル作。
The Gary Burton Quartet - Wrong Is Right (HQ Audio)
タイトルが示唆するようなパラドキシーを感じさせる曲ではなく、このカルテットとしてはむしろオーソドクスなスタイルでプレイされているが、4ビートの厭ったらしいところがなく、すっきりとさわやかな音になるところがこのコンボの身上、好ましいトラックである。
オーソドクスな曲ではあるけれど、「間違っていることが正しい」というタイトルには、やはりいくぶんかの主張ないしは腹立ちが込められているのだろう。
べつに音楽にかぎったことではなく、さまざまな分野で云えることだが、それまでは「やってはいけない」とみなされたことをやってしまう人間が出現した時に、大きな変化が起きる。
ロックンロールでは当たり前のことなのに、たかがベンドをかけたぐらいでゴチャゴチャいうような小姑の多いジャンルでしばらくのあいだ暴れてみて、コリエルは、お前らが間違っていると云っていることが、じつは音楽にとっては正しいんだ、と思ったことだろう。エルヴィスやリトル・リチャードも同じようなことを思ったのにちがいないさ、気にするなラリー。
◆ ポップ・ミュージックへのアプローチ ◆◆
つづいてスティーヴ・スワロウのアップライト・ベースをリードにした、ディランのあの曲のカヴァー。
The Gary Burton Quartet - I Want You feat. Steve Swallow (HQ Audio)
1971年に日比谷公会堂で見た時、スワロウはエレクトリックへの移行過程にあり、アップライトとエレクトリックが半々ぐらい、何度も持ち替えていたが、この曲はベース・ソロだから、カーネギー・リサイタル・ホールのライヴと同じく、アップライトでやった。
プレイの質がどうこうという以前に、4ビートのシリアスなコンボが、ボブ・ディランの曲をカヴァーするということそれ自体に意味が生じる時代だったことに留意されたい。70年代の「フュージョン」ブーム(軽蔑を込めてカギ括弧に入れてやった)は未来の話なのだ。
前回の記事でご紹介した、ゲーリー・バートンの1966年の盤、Tennessee Firebirdはナッシュヴィル録音で、チャーリー・マコーイやケニー・バトリーもプレイした。
60年代のディランを聴く方ならよくご存知のように、I Want Youを含むダブル・アルバム、Blonde on Blondeのほとんどの曲が録音されたのはナッシュヴィルのコロンビア・スタジオ(クォンセット・ハットではない)、そのメンバーを集めたのはほかならぬチャーリー・マコーイで、Blonde on Blondeセッションを取り仕切ったのも、すでにNYでディランに会っていたマコーイだった。
そして、ゲーリー・バートンがTennessee Firebirdを録音した(66年9月19日からの三日間)のはディランのBlonde on Blonde(66年2月と3月に録音、遅くとも7月にリリース)のすぐあとのことで、この時はI Want Youだけでなく、Just Like a Womanも録音している。
Gary Burton - 07 I Want You (HQ)
前半のサックスはスティーヴ・マーカスだろう。後半、スティーヴ・スワロウのソロが出てきて、In Concertヴァージョンへとつながる。べつに悪くもないのだが、手つきに迷いがあるというか、まだ試行錯誤段階の音と感じる。
こういうところで、ゲーリー・バートンはラリー・コリエルを必要としたのではないか、と想像する。
バートンはこれ以前にもNorwegian Woodを録音していて、ビートルズと同世代のミュージシャンとして、ロックンロールの世界で起きていることはおおいに気にしていたにちがいない。
しかし、天才少年じみたプレイヤーが、若くして音楽学校で理論を学んだわけで、おそらく、ラリー・コリエルのように自分でロックンロール・バンドを組んだことなどなかったのだろう。そこが手つきにあらわれる。
ラリー・コリエルははじめから4ビートも8ビートも聴いていたのだろう。ビートルズもジミ・ヘンドリクスも「自分の音楽」と感じるから、そちらの曲をプレイするときに、まったく構えない。そのまますっと弾くことができた。
以上、全部憶測だが、66年のTennessee Firebird収録のI Want Youと、68年のIn Concert収録のI Want Youのあいだに横たわる差は、そういうことなのだと考える。ふつうの曲としてプレイできるようになった触媒はラリー・コリエルにちがいない。
次回、この項は完結できると期待している。
Click and follow Songs for 4 Seasons/metalside on Twitter

Gary Burton Quartet in Concert: Live at Carnegie Recital Hall

Gary Burton - Tennessee Firebird