1: ◆yHhcvqAd4.:2020/10/30(金) 18:09:19.62 :w3nnd9V30
スレが立ったら投下します。
【登場人物】
・木下ひなた
・ジュリア
【場面設定】
ミリシタのメインコミュでまだ上記二人のお話が終わっていないぐらいの時期
12,000字無いぐらいですー
スレが立ったら投下します。
【登場人物】
・木下ひなた
・ジュリア
【場面設定】
ミリシタのメインコミュでまだ上記二人のお話が終わっていないぐらいの時期
12,000字無いぐらいですー
2:飢餓感 1/8:2020/10/30(金) 18:10:30.72 :w3nnd9V30
失礼します、と一言かけて、木下ひなたは、今回は忘れずにノックをしてから事務室の扉を開いた。空調の効いた室内は暖かく、視線を合わせてくれたプロデューサーもジャケットを脱ぎ、椅子の背もたれに引っ掛けていた。彼の隣の席は空いており、ひなたはそこへ座るように促された。
一日につき一人十分ほどの短い時間ではあったが、39プロジェクトを契機に765プロダクションに所属することになった39人のアイドル達には、週に一度、面談の時間が設けられていた。ひなたのように実家を離れ、転校もして東京で暮らす者も複数いる。そういった地方出身者は特に優先的に面談を組まれ、親元を離れての生活の相談がしやすいよう、プロデューサーが面談のスケジュール管理を行っていた。
先程、同期の白石紬と廊下ですれ違った時にその優雅な歩き方を見て、ひなたは自分の足取りが重くなっていたのに気が付いたばかりだった。プロデューサーの席の隣に腰かけた時も、きっと不安が顔に出ているに違いない、と感じて、顔を上げ辛かった。
「何かあったか、ひなた」
プロデューサーはにっこりと笑った。自然な笑いとは少し違う、警戒心を解き、不安を和らげようとするための、努めて意識した笑顔。気を遣って彼がそうしているのだと、ひなたは理解していた。そして、自分達の知らない所で見えない苦労を重ねているはずのプロデューサーにそうさせてしまい、ひなたの胸中には苦い罪悪感が走った。
「あっ……ごめん、顔に出てたかい?」
「悩みがあって聞いて欲しい、って顔に書いてあるぞ?」
モニターに向いていた体を90度回転させて、プロデューサーはひなたの正面に向き合った。
「でも、話したら面談の時間、長引いちゃうかもしれないべさ」
「それはひなたが気にすることじゃないよ。話してごらん。それだけでも気分が上向きになる。大丈夫だ、ここには俺しかいないから」
大人の男性特有の低い声は、あくまでも落ち着いている。まだ湯気を立てているブラックコーヒーの香ばしい匂いが、ひなたの鼻腔にそっと手を差し伸べていた。
「ありがとう。じゃあ……話すねぇ。あのね、東京に引っ越してからもうだいぶ経って、ホームシックも克服できてきたって思うんだわ」
「そうだな。家族とも連絡取ってるんだろう?」
「うん。でも……家に帰って来た時とか、一人でご飯食べてる時とか、寝る前とか、朝起きた時とか、そういう時に声をかける相手がいないっていうのが、時々、無性に寂しくなっちゃって……」
ひなたが東京に来たばかりの頃、地方出身のメンバーを集めてオリエンテーションが行われたことがあった。互いの連絡先の交換、それぞれの住む場所から劇場までのアクセス、一人暮らしの注意点、東京で近づくべきでない危険な場所、生活に関して何か困ったら決して一人で抱え込まないことも資料と共に話された。その時に、ホームシックになった際の典型的な症状と、その対処法についてもひなたは知識としては知らされていた。
「時間が経てばホームシックも良くなるっていうのは、分かってるんだあ。ばあちゃんやじいちゃんと話したくて泣いちゃうようなことは、もう無くなったし……。でも、最近感じてる寂しさは、あんまり良くなってこなくって……」
体を揺すると、ひなたの体重を支えるオフィスチェアがギシッと静かに軋んだ。プロデューサーは前のめりの真剣な顔になって、ゆっくり話す担当アイドルの声に耳を傾けていた。
「そうか……俺も昔あったよ、そういうこと」
「えっ、プロデューサーが?」
彼がスイッチを切り、表計算ソフトを開いたままになっていたモニターが真っ暗になった。
「一人暮らしを続けてると、そういうストレスに苛まれることがあるんだ。家の中で誰とも会話しなかったり、何気ない挨拶が無い生活を送ってると、それがあった頃の生活と現状を比べてしまって、その落差に落ち込んでしまうんだよ」
「そっかぁ……そう言われると、家族と電話する時以外は、家の中じゃしゃべらんからねぇ……うーん……でも、どうしたらいいべさ?」
「俺は、大学生の頃に一人暮らしを始めたんだけど、無性に人恋しくなった時は、友達に頼んで、泊まりに行ったりしてたな。酒とか持ち込んでさ」
「へぇ、何だか楽しそうだねぇ」
落ち込んで平坦になっていた内心に僅かなザワつきの波が立った。俯き気味になっていた顔を上げて、ひなたはブラックコーヒーをすするプロデューサーの目を覗き込んだ。
失礼します、と一言かけて、木下ひなたは、今回は忘れずにノックをしてから事務室の扉を開いた。空調の効いた室内は暖かく、視線を合わせてくれたプロデューサーもジャケットを脱ぎ、椅子の背もたれに引っ掛けていた。彼の隣の席は空いており、ひなたはそこへ座るように促された。
一日につき一人十分ほどの短い時間ではあったが、39プロジェクトを契機に765プロダクションに所属することになった39人のアイドル達には、週に一度、面談の時間が設けられていた。ひなたのように実家を離れ、転校もして東京で暮らす者も複数いる。そういった地方出身者は特に優先的に面談を組まれ、親元を離れての生活の相談がしやすいよう、プロデューサーが面談のスケジュール管理を行っていた。
先程、同期の白石紬と廊下ですれ違った時にその優雅な歩き方を見て、ひなたは自分の足取りが重くなっていたのに気が付いたばかりだった。プロデューサーの席の隣に腰かけた時も、きっと不安が顔に出ているに違いない、と感じて、顔を上げ辛かった。
「何かあったか、ひなた」
プロデューサーはにっこりと笑った。自然な笑いとは少し違う、警戒心を解き、不安を和らげようとするための、努めて意識した笑顔。気を遣って彼がそうしているのだと、ひなたは理解していた。そして、自分達の知らない所で見えない苦労を重ねているはずのプロデューサーにそうさせてしまい、ひなたの胸中には苦い罪悪感が走った。
「あっ……ごめん、顔に出てたかい?」
「悩みがあって聞いて欲しい、って顔に書いてあるぞ?」
モニターに向いていた体を90度回転させて、プロデューサーはひなたの正面に向き合った。
「でも、話したら面談の時間、長引いちゃうかもしれないべさ」
「それはひなたが気にすることじゃないよ。話してごらん。それだけでも気分が上向きになる。大丈夫だ、ここには俺しかいないから」
大人の男性特有の低い声は、あくまでも落ち着いている。まだ湯気を立てているブラックコーヒーの香ばしい匂いが、ひなたの鼻腔にそっと手を差し伸べていた。
「ありがとう。じゃあ……話すねぇ。あのね、東京に引っ越してからもうだいぶ経って、ホームシックも克服できてきたって思うんだわ」
「そうだな。家族とも連絡取ってるんだろう?」
「うん。でも……家に帰って来た時とか、一人でご飯食べてる時とか、寝る前とか、朝起きた時とか、そういう時に声をかける相手がいないっていうのが、時々、無性に寂しくなっちゃって……」
ひなたが東京に来たばかりの頃、地方出身のメンバーを集めてオリエンテーションが行われたことがあった。互いの連絡先の交換、それぞれの住む場所から劇場までのアクセス、一人暮らしの注意点、東京で近づくべきでない危険な場所、生活に関して何か困ったら決して一人で抱え込まないことも資料と共に話された。その時に、ホームシックになった際の典型的な症状と、その対処法についてもひなたは知識としては知らされていた。
「時間が経てばホームシックも良くなるっていうのは、分かってるんだあ。ばあちゃんやじいちゃんと話したくて泣いちゃうようなことは、もう無くなったし……。でも、最近感じてる寂しさは、あんまり良くなってこなくって……」
体を揺すると、ひなたの体重を支えるオフィスチェアがギシッと静かに軋んだ。プロデューサーは前のめりの真剣な顔になって、ゆっくり話す担当アイドルの声に耳を傾けていた。
「そうか……俺も昔あったよ、そういうこと」
「えっ、プロデューサーが?」
彼がスイッチを切り、表計算ソフトを開いたままになっていたモニターが真っ暗になった。
「一人暮らしを続けてると、そういうストレスに苛まれることがあるんだ。家の中で誰とも会話しなかったり、何気ない挨拶が無い生活を送ってると、それがあった頃の生活と現状を比べてしまって、その落差に落ち込んでしまうんだよ」
「そっかぁ……そう言われると、家族と電話する時以外は、家の中じゃしゃべらんからねぇ……うーん……でも、どうしたらいいべさ?」
「俺は、大学生の頃に一人暮らしを始めたんだけど、無性に人恋しくなった時は、友達に頼んで、泊まりに行ったりしてたな。酒とか持ち込んでさ」
「へぇ、何だか楽しそうだねぇ」
落ち込んで平坦になっていた内心に僅かなザワつきの波が立った。俯き気味になっていた顔を上げて、ひなたはブラックコーヒーをすするプロデューサーの目を覗き込んだ。
3:飢餓感 2/8:2020/10/30(金) 18:11:45.87 :w3nnd9V30
「ひなたも、ここの誰かの家に泊まりに行ってみたらどうだ?」
「ええっ、だめだめ、そりゃ迷惑になっちゃうべさ」
「いや、そうとも言い切れないぞ。それこそ、一人暮らししてる子もいるんだし、似た立場の人と過ごしてみるのも、お互いリフレッシュにもなるはずだ」
泊まりに行く、という行為に心が躍るのを感じてはいたが、さしたる用事もないことを思うと、ひなたは遠慮せずにはいられなかった。でも、という前置きが口から滑り落ちた瞬間、ノックとほぼ同時に、視界の端にあったドアが開いた。
「……失礼しまーす。って、あ、まだ取り込み中か」
白いドアを背景に、かき上げてセットした赤い髪が殊更に目立っている。それに呼応するかのような、白い頬にあしらわれた青い星。
「ああ、もう次の人の時間だったか。そうだジュリア、ちょうどいい。頼みがあるんだ」
ノブを回して退出しようとするジュリアをプロデューサーが呼び止め、手近にあった椅子を引き寄せ、同席するよう促した。何が丁度いいんだ、と顔に疑問符を浮かべながらもジュリアはひなたのすぐ傍に腰かけた。
「地方組の同じ一人暮らしってことで、ひなたをジュリアの所に一晩泊めてもいいか?」
「ええっ、そんな、わる――」
「ああ、別にいいぜ」
プロデューサーの唐突な頼み事に慌てるひなたとは対照的に、何も聞かされていないにもかかわらず、ジュリアはひなたを一瞥すると即答した。まるで、質問される前から答えが決まっていたかのようだった。あまりにも堂々としたそのたたずまいに、ひなたは一瞬呼吸することを忘れてしまった。
「プロデューサー、今日でいいのか?」
「ああ、いけるか?」
「まあ、特段用事があるわけでもなければ、人を招けないほど散らかしてるわけでもないしな」
「ジュリアさん、いいのかい? まだなんも事情を話してないのに」
「話なら後でゆっくり聞くよ。じゃあヒナ、今日は一緒に帰ろうな」
ぽんぽん、とジュリアが、動揺からまだ立ち直れないひなたの肩を叩いた。
「う、うん。ありがとう……じゃあ」
ひなたは思案した。ただ泊めてもらうだけではダメだ。せめて食事の支度ぐらいはこちらで。実家の農園から送ってもらった野菜が真っ先に頭に浮かんだ。この事務室にも暖房がついている。夜になると肌寒い。北海道の冬ほどではないだろうけれど、きっと、今日だって少し寒いはず。それならやっぱり……。
「ジュリアさんのおうち、カセットコンロと、土鍋、あるかい?」
「……あ~、いや、無いな。フライパンと鍋なら一応……それも全然使ってないけどな」
二人のやり取りを聞いていたプロデューサーが、机の下の鞄から黒い長財布を取り出した。そこから紙幣を二枚取り出し、むき出しのままでひなたにそれらが差し出された。受け取ったひなたは軽い悲鳴をあげた。覗き込んだジュリアもギョッとしていた。
「今の時代だったら、カセットコンロよりクッキングヒーターの方が安全だし使いやすいぞ。対応する鍋を一緒に見繕っても、それで足りるだろう」
「あっ、でも、プロデューサー、もらいすぎだよぉ」
「残った分は戻してくれよ。ああ、領収書をもらっておいてくれ。名前は書いてもらわなくていいからな。もしかしたら、経費で落ちるかもしれないから」
差し入れのお菓子を分けあうような軽さで、プロデューサーは二万円もひなたに手渡していた。自分達のアイドル活動の裏で動いているお金の額が途方もないことを知ったひなたにとっても、自分が手にしたそれは大金であった。自分の財布に入れるときも、丁寧に二回も折り畳んだ。扱ったことの無い金額ではなかったものの、わざわざ自分のために差し出されたことを思うと、ひなたは掌が汗ばむのを感じた。
「ひなたも、ここの誰かの家に泊まりに行ってみたらどうだ?」
「ええっ、だめだめ、そりゃ迷惑になっちゃうべさ」
「いや、そうとも言い切れないぞ。それこそ、一人暮らししてる子もいるんだし、似た立場の人と過ごしてみるのも、お互いリフレッシュにもなるはずだ」
泊まりに行く、という行為に心が躍るのを感じてはいたが、さしたる用事もないことを思うと、ひなたは遠慮せずにはいられなかった。でも、という前置きが口から滑り落ちた瞬間、ノックとほぼ同時に、視界の端にあったドアが開いた。
「……失礼しまーす。って、あ、まだ取り込み中か」
白いドアを背景に、かき上げてセットした赤い髪が殊更に目立っている。それに呼応するかのような、白い頬にあしらわれた青い星。
「ああ、もう次の人の時間だったか。そうだジュリア、ちょうどいい。頼みがあるんだ」
ノブを回して退出しようとするジュリアをプロデューサーが呼び止め、手近にあった椅子を引き寄せ、同席するよう促した。何が丁度いいんだ、と顔に疑問符を浮かべながらもジュリアはひなたのすぐ傍に腰かけた。
「地方組の同じ一人暮らしってことで、ひなたをジュリアの所に一晩泊めてもいいか?」
「ええっ、そんな、わる――」
「ああ、別にいいぜ」
プロデューサーの唐突な頼み事に慌てるひなたとは対照的に、何も聞かされていないにもかかわらず、ジュリアはひなたを一瞥すると即答した。まるで、質問される前から答えが決まっていたかのようだった。あまりにも堂々としたそのたたずまいに、ひなたは一瞬呼吸することを忘れてしまった。
「プロデューサー、今日でいいのか?」
「ああ、いけるか?」
「まあ、特段用事があるわけでもなければ、人を招けないほど散らかしてるわけでもないしな」
「ジュリアさん、いいのかい? まだなんも事情を話してないのに」
「話なら後でゆっくり聞くよ。じゃあヒナ、今日は一緒に帰ろうな」
ぽんぽん、とジュリアが、動揺からまだ立ち直れないひなたの肩を叩いた。
「う、うん。ありがとう……じゃあ」
ひなたは思案した。ただ泊めてもらうだけではダメだ。せめて食事の支度ぐらいはこちらで。実家の農園から送ってもらった野菜が真っ先に頭に浮かんだ。この事務室にも暖房がついている。夜になると肌寒い。北海道の冬ほどではないだろうけれど、きっと、今日だって少し寒いはず。それならやっぱり……。
「ジュリアさんのおうち、カセットコンロと、土鍋、あるかい?」
「……あ~、いや、無いな。フライパンと鍋なら一応……それも全然使ってないけどな」
二人のやり取りを聞いていたプロデューサーが、机の下の鞄から黒い長財布を取り出した。そこから紙幣を二枚取り出し、むき出しのままでひなたにそれらが差し出された。受け取ったひなたは軽い悲鳴をあげた。覗き込んだジュリアもギョッとしていた。
「今の時代だったら、カセットコンロよりクッキングヒーターの方が安全だし使いやすいぞ。対応する鍋を一緒に見繕っても、それで足りるだろう」
「あっ、でも、プロデューサー、もらいすぎだよぉ」
「残った分は戻してくれよ。ああ、領収書をもらっておいてくれ。名前は書いてもらわなくていいからな。もしかしたら、経費で落ちるかもしれないから」
差し入れのお菓子を分けあうような軽さで、プロデューサーは二万円もひなたに手渡していた。自分達のアイドル活動の裏で動いているお金の額が途方もないことを知ったひなたにとっても、自分が手にしたそれは大金であった。自分の財布に入れるときも、丁寧に二回も折り畳んだ。扱ったことの無い金額ではなかったものの、わざわざ自分のために差し出されたことを思うと、ひなたは掌が汗ばむのを感じた。
4:飢餓感 3/8:2020/10/30(金) 18:12:41.88 :w3nnd9V30
「うん、領収書、もらってくるねぇ。ありがとう、こんなにしてくれて」
「お安い御用だ。それより、ジュリアに料理の基礎を教えてやってくれ。相当酷いらしいから」
「う、うるせーな。いいだろ別に……まぁ、酷いのは否定しねえけどな」
料理ができないことを指摘されたジュリアの顔は、開き直って得意気ですらあった。ひなたは、ある日の劇場の台所で見た「何か」のことを思い出していた。ひょっとして、あの得体の知れないのはジュリアさんが作ったんだろか、と言いたくなったが、それを口にするわけにはいかなかった。
ひとまず、今晩泊まることになるのなら荷物の準備をしておいで、とプロデューサーにすすめられ、ひなたはその場を後にして、オーバーしていた面談の時間をジュリアにパスした。後でな、とひなたに投げかけるその表情は、どこかにこやかだった。
数時間後、もう日が沈む頃になって、ひなたは野菜を詰め込んだエコバッグを手に、部屋着の入った鞄を背負って、劇場に戻ってきていた。翌日学校に行くから制服姿で行かなければ、と玄関で靴を履こうとした瞬間、今日が土曜日であることを思い出し、慌てて着替えて正解だった、と控室の椅子に腰を下ろしながら実感していた。控室には誰もいない。まだ何人かの鞄は置いたままになっていて、そういった荷物の中に黒いギターケースが立っていた。
あのギターケースが普段置かれている部屋――いつもカッコいいジュリアはどんな部屋で生活しているのか。普段家で何を食べているのか。部屋には何が置いてあるのか。控室の加湿器がもくもくと蒸気を吐き続けていた。スマートフォンで時刻を確かめようとした時、扉が開いた。
「よーヒナ。お疲れ」
「あっ、ジュリアさん。お疲れ様だべさ」
「いやー、今度の曲、ダンスが難しくてさ。ちょっと脚が痛いぜ」
ギターケースを担ぎ上げて、ジュリアがそれを背負った。普段から身に着けている服の一部みたいだった。
* * * * *
途中までは電車も一緒だったが、いつもと違う駅で降りて乗り換えると、もうひなたにとっては未知の世界だった。薄暗い空の下でピカピカ光る東京の街並みも、自分の家への最寄り駅へ向かう電車から眺めるそれと随分違っている。ジュリアの背中で周囲の視線から庇ってもらいながら、右手の出入り口から見える夜景と、目の前の派手な顔立ちと、ジュリアの腕の隙間から見える、男性が読んでいる新聞の一面の見出しに、ひなたは視線をぐるぐる巡らせていた。
自分の降りる駅よりもゴチャゴチャしていて会社帰りの人に埋もれそうになる中で、ジュリアはひなたの手を引いていてくれた。外での仕事に付き添う時にそうしてくれるプロデューサーみたいに、歩幅も合わせてくれた。違っていたのは、手の大きさと、指の細さと、しっとりしていて柔らかな肌の感触だった。
駅に隣接するビルの中に家具店があるから、とジュリアに案内されて、あちこち探しまわることも無く、早速クッキングヒーターとセットの鍋を購入することができた。野菜の入った袋を提げた腕に大きな袋も通そうとしたが、領収書を財布に収めた赤毛の同期にひょいとそれを持ちあげられた。荷物を分け合えて負担が減ったことにホッとした一方で、つなぐ手が塞がってしまったことにひなたはほんのりと心細さを覚えていた。
同じ駅ビルにあったスーパーで肉と少々の調味料を追加で購入する頃には、ひなたもジュリアも両手に袋をぶらさげるようになっていた。ちょっとしたパーティーみたいでワクワクするな、と、ジュリアはアパートの鍵を開きながら口角を上げて笑っていた。
「うん、領収書、もらってくるねぇ。ありがとう、こんなにしてくれて」
「お安い御用だ。それより、ジュリアに料理の基礎を教えてやってくれ。相当酷いらしいから」
「う、うるせーな。いいだろ別に……まぁ、酷いのは否定しねえけどな」
料理ができないことを指摘されたジュリアの顔は、開き直って得意気ですらあった。ひなたは、ある日の劇場の台所で見た「何か」のことを思い出していた。ひょっとして、あの得体の知れないのはジュリアさんが作ったんだろか、と言いたくなったが、それを口にするわけにはいかなかった。
ひとまず、今晩泊まることになるのなら荷物の準備をしておいで、とプロデューサーにすすめられ、ひなたはその場を後にして、オーバーしていた面談の時間をジュリアにパスした。後でな、とひなたに投げかけるその表情は、どこかにこやかだった。
数時間後、もう日が沈む頃になって、ひなたは野菜を詰め込んだエコバッグを手に、部屋着の入った鞄を背負って、劇場に戻ってきていた。翌日学校に行くから制服姿で行かなければ、と玄関で靴を履こうとした瞬間、今日が土曜日であることを思い出し、慌てて着替えて正解だった、と控室の椅子に腰を下ろしながら実感していた。控室には誰もいない。まだ何人かの鞄は置いたままになっていて、そういった荷物の中に黒いギターケースが立っていた。
あのギターケースが普段置かれている部屋――いつもカッコいいジュリアはどんな部屋で生活しているのか。普段家で何を食べているのか。部屋には何が置いてあるのか。控室の加湿器がもくもくと蒸気を吐き続けていた。スマートフォンで時刻を確かめようとした時、扉が開いた。
「よーヒナ。お疲れ」
「あっ、ジュリアさん。お疲れ様だべさ」
「いやー、今度の曲、ダンスが難しくてさ。ちょっと脚が痛いぜ」
ギターケースを担ぎ上げて、ジュリアがそれを背負った。普段から身に着けている服の一部みたいだった。
* * * * *
途中までは電車も一緒だったが、いつもと違う駅で降りて乗り換えると、もうひなたにとっては未知の世界だった。薄暗い空の下でピカピカ光る東京の街並みも、自分の家への最寄り駅へ向かう電車から眺めるそれと随分違っている。ジュリアの背中で周囲の視線から庇ってもらいながら、右手の出入り口から見える夜景と、目の前の派手な顔立ちと、ジュリアの腕の隙間から見える、男性が読んでいる新聞の一面の見出しに、ひなたは視線をぐるぐる巡らせていた。
自分の降りる駅よりもゴチャゴチャしていて会社帰りの人に埋もれそうになる中で、ジュリアはひなたの手を引いていてくれた。外での仕事に付き添う時にそうしてくれるプロデューサーみたいに、歩幅も合わせてくれた。違っていたのは、手の大きさと、指の細さと、しっとりしていて柔らかな肌の感触だった。
駅に隣接するビルの中に家具店があるから、とジュリアに案内されて、あちこち探しまわることも無く、早速クッキングヒーターとセットの鍋を購入することができた。野菜の入った袋を提げた腕に大きな袋も通そうとしたが、領収書を財布に収めた赤毛の同期にひょいとそれを持ちあげられた。荷物を分け合えて負担が減ったことにホッとした一方で、つなぐ手が塞がってしまったことにひなたはほんのりと心細さを覚えていた。
同じ駅ビルにあったスーパーで肉と少々の調味料を追加で購入する頃には、ひなたもジュリアも両手に袋をぶらさげるようになっていた。ちょっとしたパーティーみたいでワクワクするな、と、ジュリアはアパートの鍵を開きながら口角を上げて笑っていた。
5:飢餓感 4/8:2020/10/30(金) 18:13:33.15 :w3nnd9V30
「さ、上がりな。女の部屋にしちゃ、殺風景かもしれないけどな」
「うん……お、お邪魔します」
玄関を通ってまずしたことは、両手に提げた袋を下ろすことだった。平坦な1Kの廊下を通り抜けて案内されると、確かにジュリアの言う通り、デコレーションの少ないシンプルな部屋だった。テレビデッキの対面、部屋の中央に設置されたテーブルの上には、何かを書いては消した跡がいっぱい残った紙が、ボールペンと共に何枚か置いたままになっていて、楽譜らしき本がそのすぐ近くに数冊積みあがっていた。
「この紙か? 詞を書いてるんだ。メロディは先に出来上がってるんだけどさ」
時々控室でそうしているみたいにギターを手に、ステージで歌っているジュリアの姿が、ひなたの脳裏に浮かんだ。
「もしかして、劇場で歌う曲かい?」
「いや、まだまだそんな段階じゃないよ。とりあえず詞ができたらデモテープ録って、プロデューサーに提出してみる。それが採用されて、ちゃんとした編曲してもらえて、公演で出してOKって出来になってから、もしも、あたしのお披露目する機会が来れば……。ってな感じで、先は長いぜ」
「わあ~……ジュリアさん、すんごいねぇ。自分で歌が作れちゃうんだ」
ダンスはヘタクソだけどな、と返しながら、ジュリアはレザーのジャケットをハンガーに引っ掛けて、クッキングヒーターの説明書に目を通していた。火の出る所が無いのにこれで加熱ができるなんて不思議だ、と、ひなたも平べったい板を眺めながら感じていた。
「白菜、じゃがいも、ニンジン、タマネギ、白滝、あと豚肉と牛肉、か……なあヒナ、一体何を作るつもりなんだ?」
「肉じゃがだよぉ。白菜と豚バラは、ミルフィーユ鍋にするべさ」
「おいおいマジか……すげぇな。何か手伝えないか? あたしが余計なことしたら台無しになりそうだけど」
「それじゃあ、調味料、量ってもらってもいいかい? 醤油と、お酒と、みりんと、お砂糖。えっとね、量は……」
メモ帳に書き留めたレシピをひなたがジュリアに見せた。自分では覚えたつもりでいても、何をどのぐらい入れるのかを思い出そうとすると不安になってしまうから、必要かどうかは分からなかったが鞄に忍ばせてあったものだった。さっきまでは凛とした涼しげな表情をしていたのに、匙を握りしめたジュリアには緊張が走っていた。
「……ヒナ、助けてくれ。液体は分かる。ただ、砂糖の大さじ一杯ってどうすればいいんだ? 大さじってこのデカいのだろ?」
「えっとね、表面が平らになるようにとると、大さじ一杯になるよぉ」
「よ、よし……サンキュ、やってみるぜ」
すぐ隣でジュリアが恐る恐る砂糖を量っているのを横目に見ながら、ひなたは野菜の皮むきを終えていた。泊めてもらう話を何も言わず了承して、ここに案内してもらうまで大事に大事にエスコートしてくれたジュリアに何かしてあげられる実感が、ひなたの心を軽くしてくれた。じゃがいもとニンジンの処理を終えてタマネギの処理に入るときに、換気扇のスイッチを入れた。さっき買ったものとは別の鍋を温めて油を張り、肉を炒める頃には、ジュリアは調味料を量り終えて、一仕事終えたように額を手の甲で拭っていた。
「ヒナは、実家にいた頃も料理してたのか?」
「お手伝いしてることはあったけども、自分で作るようになったのは、東京に来てからだなぁ。ばあちゃんに作り方とか教えてもらったのをメモして、その通りにやってるだけだよぉ。まだ、ちょっこししか作れんし、美奈子さんみたいには上手くいかんべさ」
「それでも、自分で料理ができるだけで、すごいことだと思うぜ、あたしは」
「大げさだよぉ。分量と手順をちゃんと守るだけだべさ」
野菜にもそろそろ火が通る頃だった。ダシ汁、砂糖、酒、みりん、醤油と、水抜きを済ませた白滝。準備してあったものが順番に鍋の中へ飛び込み、一つに混ざり合っていく。しばらく大人しかった鍋が煮立つまで待つ間に、まだ自宅から持ってきたままの姿だった白菜をひなたが手に取った。外側から順に葉をはがして、薄切りの豚バラ肉を敷いてはまた一枚一枚重ねなおす。
「こっちの鍋に並べるのは、ジュリアさんにやってもらうべさ」
「ああ、それならできそうだ。出来上がりがイメージできる」
等間隔に切った白菜と豚バラの束が、ヒーターにかける方の鍋に敷き詰められていく。若干の余りが出てしまうぐらいで、一部分はジュリアが無理矢理押し込んでぎゅうぎゅう詰めになっていた。食材だったものが料理になっていく中で、炊飯器が蒸気を吹き出し始めていた。肉じゃがにもアルミホイルで落とし蓋が施され、後は煮汁が野菜に染み込んでいくのを待つだけとなった。出来上がりを楽しみにするひなたの隣で、ジュリアの腹の虫が悲鳴をあげた。
「さ、上がりな。女の部屋にしちゃ、殺風景かもしれないけどな」
「うん……お、お邪魔します」
玄関を通ってまずしたことは、両手に提げた袋を下ろすことだった。平坦な1Kの廊下を通り抜けて案内されると、確かにジュリアの言う通り、デコレーションの少ないシンプルな部屋だった。テレビデッキの対面、部屋の中央に設置されたテーブルの上には、何かを書いては消した跡がいっぱい残った紙が、ボールペンと共に何枚か置いたままになっていて、楽譜らしき本がそのすぐ近くに数冊積みあがっていた。
「この紙か? 詞を書いてるんだ。メロディは先に出来上がってるんだけどさ」
時々控室でそうしているみたいにギターを手に、ステージで歌っているジュリアの姿が、ひなたの脳裏に浮かんだ。
「もしかして、劇場で歌う曲かい?」
「いや、まだまだそんな段階じゃないよ。とりあえず詞ができたらデモテープ録って、プロデューサーに提出してみる。それが採用されて、ちゃんとした編曲してもらえて、公演で出してOKって出来になってから、もしも、あたしのお披露目する機会が来れば……。ってな感じで、先は長いぜ」
「わあ~……ジュリアさん、すんごいねぇ。自分で歌が作れちゃうんだ」
ダンスはヘタクソだけどな、と返しながら、ジュリアはレザーのジャケットをハンガーに引っ掛けて、クッキングヒーターの説明書に目を通していた。火の出る所が無いのにこれで加熱ができるなんて不思議だ、と、ひなたも平べったい板を眺めながら感じていた。
「白菜、じゃがいも、ニンジン、タマネギ、白滝、あと豚肉と牛肉、か……なあヒナ、一体何を作るつもりなんだ?」
「肉じゃがだよぉ。白菜と豚バラは、ミルフィーユ鍋にするべさ」
「おいおいマジか……すげぇな。何か手伝えないか? あたしが余計なことしたら台無しになりそうだけど」
「それじゃあ、調味料、量ってもらってもいいかい? 醤油と、お酒と、みりんと、お砂糖。えっとね、量は……」
メモ帳に書き留めたレシピをひなたがジュリアに見せた。自分では覚えたつもりでいても、何をどのぐらい入れるのかを思い出そうとすると不安になってしまうから、必要かどうかは分からなかったが鞄に忍ばせてあったものだった。さっきまでは凛とした涼しげな表情をしていたのに、匙を握りしめたジュリアには緊張が走っていた。
「……ヒナ、助けてくれ。液体は分かる。ただ、砂糖の大さじ一杯ってどうすればいいんだ? 大さじってこのデカいのだろ?」
「えっとね、表面が平らになるようにとると、大さじ一杯になるよぉ」
「よ、よし……サンキュ、やってみるぜ」
すぐ隣でジュリアが恐る恐る砂糖を量っているのを横目に見ながら、ひなたは野菜の皮むきを終えていた。泊めてもらう話を何も言わず了承して、ここに案内してもらうまで大事に大事にエスコートしてくれたジュリアに何かしてあげられる実感が、ひなたの心を軽くしてくれた。じゃがいもとニンジンの処理を終えてタマネギの処理に入るときに、換気扇のスイッチを入れた。さっき買ったものとは別の鍋を温めて油を張り、肉を炒める頃には、ジュリアは調味料を量り終えて、一仕事終えたように額を手の甲で拭っていた。
「ヒナは、実家にいた頃も料理してたのか?」
「お手伝いしてることはあったけども、自分で作るようになったのは、東京に来てからだなぁ。ばあちゃんに作り方とか教えてもらったのをメモして、その通りにやってるだけだよぉ。まだ、ちょっこししか作れんし、美奈子さんみたいには上手くいかんべさ」
「それでも、自分で料理ができるだけで、すごいことだと思うぜ、あたしは」
「大げさだよぉ。分量と手順をちゃんと守るだけだべさ」
野菜にもそろそろ火が通る頃だった。ダシ汁、砂糖、酒、みりん、醤油と、水抜きを済ませた白滝。準備してあったものが順番に鍋の中へ飛び込み、一つに混ざり合っていく。しばらく大人しかった鍋が煮立つまで待つ間に、まだ自宅から持ってきたままの姿だった白菜をひなたが手に取った。外側から順に葉をはがして、薄切りの豚バラ肉を敷いてはまた一枚一枚重ねなおす。
「こっちの鍋に並べるのは、ジュリアさんにやってもらうべさ」
「ああ、それならできそうだ。出来上がりがイメージできる」
等間隔に切った白菜と豚バラの束が、ヒーターにかける方の鍋に敷き詰められていく。若干の余りが出てしまうぐらいで、一部分はジュリアが無理矢理押し込んでぎゅうぎゅう詰めになっていた。食材だったものが料理になっていく中で、炊飯器が蒸気を吹き出し始めていた。肉じゃがにもアルミホイルで落とし蓋が施され、後は煮汁が野菜に染み込んでいくのを待つだけとなった。出来上がりを楽しみにするひなたの隣で、ジュリアの腹の虫が悲鳴をあげた。
6:飢餓感 5/8:2020/10/30(金) 18:14:10.57 :w3nnd9V30
さっきまでジュリアの作業机だったテーブルが、今はどこからどう見ても立派な食卓になっていた。クッションにお尻を預けた二人の目の前では、ミルフィーユ鍋がくつくつと煮えて食べ頃になっている。その脇には、湯気をほかほかと立てている肉じゃがが、小分けの器に盛られている。当然のものとしてご飯も並べられている。鍋が足りずに味噌汁を用意できなかったことだけが、ひなたの心残りだった。
「ああ……こんな、こんな美味そうなものが、あたしの家に……! 感激だぜ……!」
「お腹ぺこぺこだぁ。さ、食べよう食べよう」
示し合わせたわけでもないのに「いただきます」と手を合わせたのは二人で全く同時だった。取り分けた白菜は、出汁と豚肉の旨味をたっぷりと吸い込んでいて、空腹のままだった肉体と、家の中で誰かと囲む食事の場に餓えていたひなたの心に温かくじいんと染み渡った。「自宅で摂る食事がロクなもんじゃない」と語ったジュリアは、美味い、美味いと声を震わせながら何度もつぶやいていた。肉じゃがに入れた白滝のプチプチした食感が心地よく、肉の張り付いたニンジンも、一人で食べた時よりもずいぶん甘味が強いようにひなたには感じられた。
アパートの一室が、料理から立ち上る湯気と、出汁の香りで満たされていく。プライベートの生活空間の中に、言葉を交わし合える相手がいる状況は、自然とひなたに実家での生活を思い起こさせていた。しかしながら、その内心で膨らんでいたのは郷愁の想いではなく、家族と別れた時の寂しさでもなく、すぐ傍に人がいる安心感であった。
「ジュリアさん、出身は福岡だっけか? 福岡から遠く離れて暮らしてて、寂しくなったりはしないのかい?」
「いや、そう感じたことは無いな。地元の友達に会いたくなるときはあるけど、こっちに来てからはやりたいこととか刺激のあることだらけで、そういう気分になるヒマが無いっていうのかな」
「そっかぁ……家族に会えなくて寂しがってたあたしとは、大違いだねぇ」
鍋の具をよそった器のスープをぐるぐるかき混ぜるひなたを見て、ジュリアが一瞬、箸を止めた。
「あたしは大人に反抗的だったから……中学の頃は特に。ヒナみたいに家族と仲良くなかったからかもしれないな」
「ごめん、変なこと聞いちゃったべさ」
「おいおい、謝るなよ。あたしは追いかけたい夢があったからあのプロデューサーの誘いに乗ったんだ。実家が嫌で飛び出してきたわけじゃないよ」
鍋の中身が最後の一切れになり、どちらが引き取るか、視線でやりとりがなされ、ひなたの器にささやかな追加が入った。
「あっという間になくなっちまったな。いやー、美味かった」
「満足するのはまだ早いよぉ。残ったスープにご飯と卵入れて、雑炊にするべさ」
「雑炊! なんてこった、最高だな……!」
ヒーターのスイッチを入れ直し、白米と卵が投入される。落ち着きを取り戻していたスープの表面が、たちまち波立ち始めた。
「ヒナは……あったかい家庭で育ったんだろうな」
「うん、そうだねぇ。じいちゃんもばあちゃんも優しくてな、いつも甘えてたんだわ」
コクのあるスープを飲み込みながら、ひなたは実家の軒先を回想していた。穏やかな日差しの中でにっこりと微笑む祖母の姿を思い浮かべた瞬間、何かがこみあげそうになって、奥歯を強く噛み締めた。
「ちょっと、そういうの、羨ましいかもな」
「でも、あたしの所みたいなお家で育ってたら、今のカッコいいジュリアさんは、きっといないだろね」
「そうだな。あ、カッコいい云々じゃなくて、パンクロックにはハマってなかったってことだからな」
湯気の向こう側でジュリアが口元をほころばせた。
「ジュリアさん、目がキリッとしててカッコいいべさ」
「ははっ、そういう風に見せるメイクだからな。今度ヒナにもやってやるよ……っと、残り、もらってもいいか?」
どうぞ、とひなたが手で合図をすると、ジュリアが鍋の中身をきれいに片づけてくれた。二人で食べるにしても量が多いかもしれない、と考えていたひなたの予測はほぼ的中していた。ごちそう様でした、と二人で手を合わせた時に、お腹がいつもよりも重たかったが、不思議とそれが苦にはならなかった。
さっきまでジュリアの作業机だったテーブルが、今はどこからどう見ても立派な食卓になっていた。クッションにお尻を預けた二人の目の前では、ミルフィーユ鍋がくつくつと煮えて食べ頃になっている。その脇には、湯気をほかほかと立てている肉じゃがが、小分けの器に盛られている。当然のものとしてご飯も並べられている。鍋が足りずに味噌汁を用意できなかったことだけが、ひなたの心残りだった。
「ああ……こんな、こんな美味そうなものが、あたしの家に……! 感激だぜ……!」
「お腹ぺこぺこだぁ。さ、食べよう食べよう」
示し合わせたわけでもないのに「いただきます」と手を合わせたのは二人で全く同時だった。取り分けた白菜は、出汁と豚肉の旨味をたっぷりと吸い込んでいて、空腹のままだった肉体と、家の中で誰かと囲む食事の場に餓えていたひなたの心に温かくじいんと染み渡った。「自宅で摂る食事がロクなもんじゃない」と語ったジュリアは、美味い、美味いと声を震わせながら何度もつぶやいていた。肉じゃがに入れた白滝のプチプチした食感が心地よく、肉の張り付いたニンジンも、一人で食べた時よりもずいぶん甘味が強いようにひなたには感じられた。
アパートの一室が、料理から立ち上る湯気と、出汁の香りで満たされていく。プライベートの生活空間の中に、言葉を交わし合える相手がいる状況は、自然とひなたに実家での生活を思い起こさせていた。しかしながら、その内心で膨らんでいたのは郷愁の想いではなく、家族と別れた時の寂しさでもなく、すぐ傍に人がいる安心感であった。
「ジュリアさん、出身は福岡だっけか? 福岡から遠く離れて暮らしてて、寂しくなったりはしないのかい?」
「いや、そう感じたことは無いな。地元の友達に会いたくなるときはあるけど、こっちに来てからはやりたいこととか刺激のあることだらけで、そういう気分になるヒマが無いっていうのかな」
「そっかぁ……家族に会えなくて寂しがってたあたしとは、大違いだねぇ」
鍋の具をよそった器のスープをぐるぐるかき混ぜるひなたを見て、ジュリアが一瞬、箸を止めた。
「あたしは大人に反抗的だったから……中学の頃は特に。ヒナみたいに家族と仲良くなかったからかもしれないな」
「ごめん、変なこと聞いちゃったべさ」
「おいおい、謝るなよ。あたしは追いかけたい夢があったからあのプロデューサーの誘いに乗ったんだ。実家が嫌で飛び出してきたわけじゃないよ」
鍋の中身が最後の一切れになり、どちらが引き取るか、視線でやりとりがなされ、ひなたの器にささやかな追加が入った。
「あっという間になくなっちまったな。いやー、美味かった」
「満足するのはまだ早いよぉ。残ったスープにご飯と卵入れて、雑炊にするべさ」
「雑炊! なんてこった、最高だな……!」
ヒーターのスイッチを入れ直し、白米と卵が投入される。落ち着きを取り戻していたスープの表面が、たちまち波立ち始めた。
「ヒナは……あったかい家庭で育ったんだろうな」
「うん、そうだねぇ。じいちゃんもばあちゃんも優しくてな、いつも甘えてたんだわ」
コクのあるスープを飲み込みながら、ひなたは実家の軒先を回想していた。穏やかな日差しの中でにっこりと微笑む祖母の姿を思い浮かべた瞬間、何かがこみあげそうになって、奥歯を強く噛み締めた。
「ちょっと、そういうの、羨ましいかもな」
「でも、あたしの所みたいなお家で育ってたら、今のカッコいいジュリアさんは、きっといないだろね」
「そうだな。あ、カッコいい云々じゃなくて、パンクロックにはハマってなかったってことだからな」
湯気の向こう側でジュリアが口元をほころばせた。
「ジュリアさん、目がキリッとしててカッコいいべさ」
「ははっ、そういう風に見せるメイクだからな。今度ヒナにもやってやるよ……っと、残り、もらってもいいか?」
どうぞ、とひなたが手で合図をすると、ジュリアが鍋の中身をきれいに片づけてくれた。二人で食べるにしても量が多いかもしれない、と考えていたひなたの予測はほぼ的中していた。ごちそう様でした、と二人で手を合わせた時に、お腹がいつもよりも重たかったが、不思議とそれが苦にはならなかった。
7:飢餓感 6/8:2020/10/30(金) 18:14:50.77 :w3nnd9V30
しばらく腹を休めてから、食後の片付けをひなたは申し出たが、準備をやってもらったから、とジュリアが重ねた食器を台所へ運んでいった。ひなたが肉じゃがの面倒を見ている間にジュリアが風呂の支度を済ませてくれていたようで、先に浴室へ行くように勧められた。ふと壁にかけられた時計を見ると、いつもの就寝時間の30分前だった。すぐに平らげてしまった、と思っていたのに、ゆっくり時間をかけて食事を楽しんでいたことを、着替えを手にしながら実感していた。
自宅のものよりもほんのわずかに広い浴室、その片隅にあったシャンプーとコンディショナーが、ひなたの目に入った。見かけないデザインのボトルだった。トラベルセットの一式を持ち込んでいたが、ジュリアの使っているそれのポンプを押して、ひなたはシャンプーを手に取っていた。もしかしたら、こうすることで、自分もあんな風にクールな表情ができるようになるかもしれない。強い意思力を放つ目をできるようになるかもしれない。ひなたは髪を洗いながら、そんな期待をささやかに抱いていた。
食事を取って温まった体に加えて熱いお湯に浸かったことで、湯上りの肌には汗が浮いた。結局ボディソープも使わせてもらい、自分の体からいつもと違う香りが立ち上っているのが、ひなたは何だか嬉しかった。
「あー、ヒナ、悪い」
浴室から部屋に戻ると、ギターの弦をいじっていたジュリアが、少々気まずそうにベッドの方へ視線を流していた。
「すっかり忘れてた、予備の布団が無いんだった。一緒のベッドで寝ることになっちゃっても、平気か?」
「うん、大丈夫だよぉ」
一人暮らしの人の所へ泊まりに行くのだから、それはひなたの予想の範疇だった。実家でも祖父母や両親、あるいは弟と同じ布団で寝ることも多かったために、人肌の熱を感じながら眠ることにはさしたる抵抗も無かった。入れ替わりで浴室に向かっていくジュリアの背中を見送りながら、まだ整えられていないベッドが、ひなたには気になった。掛け布団の下敷きになるように毛布があって、毛布とマットレスの隙間に体を入れているらしいことが窺えた。毛布は、かけるよりも敷いた方が温かい。ちょうど、話し相手がしばらくいない所だったから、ひなたはそのままベッドメイキングを始めた。自分が使っているものよりもずいぶんと長いサイズの枕が気になった。二人で頭を載せるのにも苦労しなさそうだったが、もしかしたら抱き枕として使っているのかもしれない、ともひなたは思った。
「ふ~、さっぱりしたぜ」
「……あっ」
30分ぐらいは入っているのではないかとひなたは予想していたが、ジュリアは10分そこそこで入浴を終えた。スウェットの上下に身を包んだ風呂上りのジュリアは、髪を全て下ろし、メイクも落としていた。ステージに上がる時にはいつもジュリアは髪を下ろしていることをひなたは知っていたが、アイドル用のメイクもしていない素顔を見るのは初めてだった。
「ん? どうしたヒナ? あたしの顔に何かついてるか?」
「ジュリアさん、お化粧してないときのお顔、めんこいねぇ」
「……メンコイ?」
「可愛いって意味だよぉ。お目目くりくりしてて可愛いべさ」
「え、あ? い、いきなり何言ってんだよ」
肩にかけていたフェイスタオルでジュリアは目から下を覆ったが、耳がほんのり赤くなっていた。今日一日ずっとカッコいい姿を見せていたジュリアが照れているのを見ると、ひなたも何だかこそばゆかった。
「さっきまではオトナっぽかったけど、今は歳が近く感じるんだわぁ。あたしと二歳しか違わないもんねぇ」
「童顔だからな。もうちょっと年上に見えて欲しいもんだぜ」
ジュリアはそう言っていたが、学校の先輩みたいな距離感の、今の優しい顔の方が好きかもしれない、とひなたは内心で呟いた。
しばらく腹を休めてから、食後の片付けをひなたは申し出たが、準備をやってもらったから、とジュリアが重ねた食器を台所へ運んでいった。ひなたが肉じゃがの面倒を見ている間にジュリアが風呂の支度を済ませてくれていたようで、先に浴室へ行くように勧められた。ふと壁にかけられた時計を見ると、いつもの就寝時間の30分前だった。すぐに平らげてしまった、と思っていたのに、ゆっくり時間をかけて食事を楽しんでいたことを、着替えを手にしながら実感していた。
自宅のものよりもほんのわずかに広い浴室、その片隅にあったシャンプーとコンディショナーが、ひなたの目に入った。見かけないデザインのボトルだった。トラベルセットの一式を持ち込んでいたが、ジュリアの使っているそれのポンプを押して、ひなたはシャンプーを手に取っていた。もしかしたら、こうすることで、自分もあんな風にクールな表情ができるようになるかもしれない。強い意思力を放つ目をできるようになるかもしれない。ひなたは髪を洗いながら、そんな期待をささやかに抱いていた。
食事を取って温まった体に加えて熱いお湯に浸かったことで、湯上りの肌には汗が浮いた。結局ボディソープも使わせてもらい、自分の体からいつもと違う香りが立ち上っているのが、ひなたは何だか嬉しかった。
「あー、ヒナ、悪い」
浴室から部屋に戻ると、ギターの弦をいじっていたジュリアが、少々気まずそうにベッドの方へ視線を流していた。
「すっかり忘れてた、予備の布団が無いんだった。一緒のベッドで寝ることになっちゃっても、平気か?」
「うん、大丈夫だよぉ」
一人暮らしの人の所へ泊まりに行くのだから、それはひなたの予想の範疇だった。実家でも祖父母や両親、あるいは弟と同じ布団で寝ることも多かったために、人肌の熱を感じながら眠ることにはさしたる抵抗も無かった。入れ替わりで浴室に向かっていくジュリアの背中を見送りながら、まだ整えられていないベッドが、ひなたには気になった。掛け布団の下敷きになるように毛布があって、毛布とマットレスの隙間に体を入れているらしいことが窺えた。毛布は、かけるよりも敷いた方が温かい。ちょうど、話し相手がしばらくいない所だったから、ひなたはそのままベッドメイキングを始めた。自分が使っているものよりもずいぶんと長いサイズの枕が気になった。二人で頭を載せるのにも苦労しなさそうだったが、もしかしたら抱き枕として使っているのかもしれない、ともひなたは思った。
「ふ~、さっぱりしたぜ」
「……あっ」
30分ぐらいは入っているのではないかとひなたは予想していたが、ジュリアは10分そこそこで入浴を終えた。スウェットの上下に身を包んだ風呂上りのジュリアは、髪を全て下ろし、メイクも落としていた。ステージに上がる時にはいつもジュリアは髪を下ろしていることをひなたは知っていたが、アイドル用のメイクもしていない素顔を見るのは初めてだった。
「ん? どうしたヒナ? あたしの顔に何かついてるか?」
「ジュリアさん、お化粧してないときのお顔、めんこいねぇ」
「……メンコイ?」
「可愛いって意味だよぉ。お目目くりくりしてて可愛いべさ」
「え、あ? い、いきなり何言ってんだよ」
肩にかけていたフェイスタオルでジュリアは目から下を覆ったが、耳がほんのり赤くなっていた。今日一日ずっとカッコいい姿を見せていたジュリアが照れているのを見ると、ひなたも何だかこそばゆかった。
「さっきまではオトナっぽかったけど、今は歳が近く感じるんだわぁ。あたしと二歳しか違わないもんねぇ」
「童顔だからな。もうちょっと年上に見えて欲しいもんだぜ」
ジュリアはそう言っていたが、学校の先輩みたいな距離感の、今の優しい顔の方が好きかもしれない、とひなたは内心で呟いた。
8:飢餓感 7/8:2020/10/30(金) 18:15:26.80 :w3nnd9V30
「10時半か……ヒナ、いつも何時ぐらいに寝てるんだ?」
「いつもは9時半か、10時には寝てるよぉ」
非日常的な夜を過ごしてウキウキ気分のひなただったが、まぶたが重たくなってウトウトし始めていた。ベッドに寄りかかって座る今でも、このままじっとしていたら夢の国へ旅立てそうだった。まだ夜更かしして、お泊りの時間を楽しんでいたかったが、一日の三分の一近くを毎日奪い取る三大欲求の持つ引力には逆らうのは、困難を極めた。
「……眠たそうだな。あたしもダンスレッスンで体がクタクタだし、今日はもう寝るか」
「うん……あ、毛布の上に寝転がった方が、あったかくなるよぉ」
「え、そうなのか? そいつは知らなかった」
なんか変な感じがするな、と言いながら、ジュリアが先にベッドに入った。
* * * * *
カーテンで月明かりは遮られて、常夜灯の薄明かりは室内の輪郭もぼやけさせている。ほんの十数センチの距離にあるはずのジュリアの顔も、ひなたの目には映らない。充電器に接続したスマートフォンが待ち受け画面を表示してまた消灯するまで、その不自然に明るい光が天井向けて投げかけられていた。仰向けになって一人分の就寝スペースに何とか収まっているひなたは、一人で寝る時のように手足を投げ出したかったが、すぐ傍に感じる体温に直接触れてしまうのが気恥ずかしく思えて、腹の上で両手を組んでじっとしていた。ハロウィンイベント向けの資料にあった、棺に収まるヴァンパイアみたいな格好だと自分では思っていた。
「ヒナ」
「ん……何だい?」
「ああ、起きてたか。……少しは元気出たか?」
「あれ、プロデューサーから、聞いたのかい?」
「ちょっとだけだよ。ヒナの目がな……なんか、捨てられた犬みたいに見えて、ほっとけなかったんだ。上京組だと、ヒナが一番年下だしな」
「……そうかい。やっぱ、顔に出ちゃうんだなぁ」
「いいじゃねえか。何考えてるか分からねぇヤツより、ずっといい」
「うん……ありがとう」
「なあ、今度料理教えてくれよ。プロデューサーにも『食生活をマシにするため少しは自炊できないか』って、今日言われちゃってさぁ」
「いいよぉ。まだまだあたしも勉強中だけども」
そんな風に言葉を交わし合っている内に、段々と二人の間に交わされるやりとりのペースが落ちていき、ひなたの方が静かになった。投げかけられる音声に何かの返事をしてはいたが、何と答えているのか、ひなた自身にもよく分からなくなっていた。
「10時半か……ヒナ、いつも何時ぐらいに寝てるんだ?」
「いつもは9時半か、10時には寝てるよぉ」
非日常的な夜を過ごしてウキウキ気分のひなただったが、まぶたが重たくなってウトウトし始めていた。ベッドに寄りかかって座る今でも、このままじっとしていたら夢の国へ旅立てそうだった。まだ夜更かしして、お泊りの時間を楽しんでいたかったが、一日の三分の一近くを毎日奪い取る三大欲求の持つ引力には逆らうのは、困難を極めた。
「……眠たそうだな。あたしもダンスレッスンで体がクタクタだし、今日はもう寝るか」
「うん……あ、毛布の上に寝転がった方が、あったかくなるよぉ」
「え、そうなのか? そいつは知らなかった」
なんか変な感じがするな、と言いながら、ジュリアが先にベッドに入った。
* * * * *
カーテンで月明かりは遮られて、常夜灯の薄明かりは室内の輪郭もぼやけさせている。ほんの十数センチの距離にあるはずのジュリアの顔も、ひなたの目には映らない。充電器に接続したスマートフォンが待ち受け画面を表示してまた消灯するまで、その不自然に明るい光が天井向けて投げかけられていた。仰向けになって一人分の就寝スペースに何とか収まっているひなたは、一人で寝る時のように手足を投げ出したかったが、すぐ傍に感じる体温に直接触れてしまうのが気恥ずかしく思えて、腹の上で両手を組んでじっとしていた。ハロウィンイベント向けの資料にあった、棺に収まるヴァンパイアみたいな格好だと自分では思っていた。
「ヒナ」
「ん……何だい?」
「ああ、起きてたか。……少しは元気出たか?」
「あれ、プロデューサーから、聞いたのかい?」
「ちょっとだけだよ。ヒナの目がな……なんか、捨てられた犬みたいに見えて、ほっとけなかったんだ。上京組だと、ヒナが一番年下だしな」
「……そうかい。やっぱ、顔に出ちゃうんだなぁ」
「いいじゃねえか。何考えてるか分からねぇヤツより、ずっといい」
「うん……ありがとう」
「なあ、今度料理教えてくれよ。プロデューサーにも『食生活をマシにするため少しは自炊できないか』って、今日言われちゃってさぁ」
「いいよぉ。まだまだあたしも勉強中だけども」
そんな風に言葉を交わし合っている内に、段々と二人の間に交わされるやりとりのペースが落ちていき、ひなたの方が静かになった。投げかけられる音声に何かの返事をしてはいたが、何と答えているのか、ひなた自身にもよく分からなくなっていた。
9:飢餓感 8/8:2020/10/30(金) 18:16:13.81 :w3nnd9V30
そして、全身が眠気に包まれて、意識までもがふんわりと宙を漂い始めた頃、ベッドの外から話し声が聞こえてきた。すぐ隣にあった温かさは残されていたが、熱の発生源が感じられない。声を抑えて話しているようだったが、物音のしない部屋の中でそうしていても、ひなたには話し手の一方が丸聞こえだった。
――もしもし。あ、夜遅いけど、大丈夫だったか? いや、別に用があったわけじゃないけど……悪いかよ。用が無かったらあたしから電話しちゃいけねーなんてこと、無いだろ? ちょっと今日、事務所の友達と話してて。家族仲のいい子でさ……。うん。ウチの家族はどうしてんのかな、って。ん? 学校ならサボらず行ってるぜ? 仕事ある時は抜けてるけど。え……いや、実家にいつ帰れるかは、ちょっと分からねぇよ……いきなり仕事入ったりするし。年末年始は、無理じゃねえかなぁ……。まぁ、一応プロデューサーに話してみる。あ、あたしがテレビに出たら見て……あ~、やっぱ見ないでくれ。見ないでいいってば。
明日はいい朝が迎えられそうだ、とひなたは眠りかけの頭でぼんやりと考えていた。
終わり
そして、全身が眠気に包まれて、意識までもがふんわりと宙を漂い始めた頃、ベッドの外から話し声が聞こえてきた。すぐ隣にあった温かさは残されていたが、熱の発生源が感じられない。声を抑えて話しているようだったが、物音のしない部屋の中でそうしていても、ひなたには話し手の一方が丸聞こえだった。
――もしもし。あ、夜遅いけど、大丈夫だったか? いや、別に用があったわけじゃないけど……悪いかよ。用が無かったらあたしから電話しちゃいけねーなんてこと、無いだろ? ちょっと今日、事務所の友達と話してて。家族仲のいい子でさ……。うん。ウチの家族はどうしてんのかな、って。ん? 学校ならサボらず行ってるぜ? 仕事ある時は抜けてるけど。え……いや、実家にいつ帰れるかは、ちょっと分からねぇよ……いきなり仕事入ったりするし。年末年始は、無理じゃねえかなぁ……。まぁ、一応プロデューサーに話してみる。あ、あたしがテレビに出たら見て……あ~、やっぱ見ないでくれ。見ないでいいってば。
明日はいい朝が迎えられそうだ、とひなたは眠りかけの頭でぼんやりと考えていた。
終わり
10: ◆yHhcvqAd4.:2020/10/30(金) 18:21:08.49 :w3nnd9V30
以上になります。ここまで読んで頂きありがとうございます。
一応続きになるお話は考えてあるので、また書きあがったら投下しに来るかと思います。
書いてみた感想
・ひなた弁が難解
・解釈違い警察が怖い
読んでみた感想とかあったら頂けますと嬉しいです。
以上になります。ここまで読んで頂きありがとうございます。
一応続きになるお話は考えてあるので、また書きあがったら投下しに来るかと思います。
書いてみた感想
・ひなた弁が難解
・解釈違い警察が怖い
読んでみた感想とかあったら頂けますと嬉しいです。
12: ◆NdBxVzEDf6:2020/10/30(金) 20:06:00.89 :wQg+iatf0



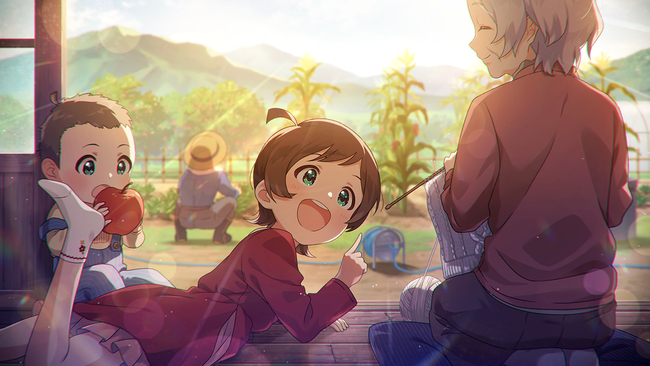






![鬼滅の刃 遊郭編 4 [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/919HAP1xhLL._SX300_CR0,100,300,400_.jpg)



![『ウマ箱2』第4コーナー アニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』トレーナーズBOX) [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61io03zeJaS._SX300_CR0,100,300,400_.jpg)
![プリンセスコネクト! Re:Dive Season 2 2[Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61-7nLuMgDL._SX300_CR0,100,300,400_.jpg)




コメント