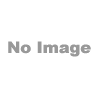「東方Project」二次創作 パチュリーのたまには動く大図書館Ⅳ #1
2011/01/18/Tue
寒風吹き荒ぶ丑三つ時、一筋の月明かりが、葉を落し、むき出しの身をあえなく露出させている木々の無骨な枝に複雑な影を作る、陰惨とした森の奥で、私はそれに出会った。それがただの偶然か、それとも星のめぐり合わせか、あるいは私の夜の眷属としての性がそれを嗅ぎつけたのか、私にはなんとも断言することができない。ただたしかなのは、冬のからっと乾燥した大気が星々をいつもより明らかに大きく輝かせていて、その様は不気味なほどであり、私の弱った視力でもその光線は見るものの脳髄を削り取ると思われんばかりに鋭かったことと、そんな魔性の夜の雰囲気が、魔法使いとしての私の感性を敏感にしていたということだけだった。
くちゃくちゃと手でなまものを扱うとき特有の煮え切らない音と、硬い骨を指でほじくり出し、がむしゃらに歯でそれを噛み砕く音、そして露骨な咀嚼の音とが、一歩一歩と現場に近づいていく私を出迎える。風が木々を擦っていくがさつな音と、私を過ぎる衣擦れの音がそれらに混じって、泥土の上にはすえた血のにおい、生臭い肉のにおいが、瘴気となって立ち込めているように私には思われた。その鼻をつく臭気は、無論、吸血鬼を友人に持つ私にとっては、ある程度、慣れ親しんだものにちがいなかったが、目の前の妖怪の行為の結果はあまりに泥臭く、手慣れてなく、つまり吸血鬼のように血だけ吸って終りというような優雅さの欠片もなく、ひどく素人じみたものであって、誰が見たところでその様子の見苦しさには目を逸らすほかなかったろう。……そんなことを思いつつも、だけど、私は自分の不愉快さを一切表情には出さなかった。そしてもう一歩私が近寄ったとき、自分の仕業にみずから陶酔していたろう幼い浅慮な妖怪は、ようやく私の存在に気づき、そろそろと顔を向ける。――シャツの上に水色の上着をまとった、空色の薄い髪、左右で赤、水色と異なる色をした目を私に回した、あどけなさを残した無垢な表情――ただ、それらすべては今は血にまみれ、口元はむやみに垂れた涎でもってべたべたに汚れている。その姿はまるで砂場で夢中になって遊んだ子どものようとも感じられた。――彼女の名前は……私は記憶を手繰り寄せた……多々良小傘といったろうか。……私はある冬の夜、陰惨な現場に遭遇した魔女にふさわしい微笑でもって、小傘に対面した。
「――驚かないの?」
「驚くって、なぜ?」
「これ、見て……」
「ああ。……ま、けっこう見慣れているのよ。ここまで無茶苦茶に散らかしちゃっているのは妹様を連想させるくらいかしら。」
「そっかぁ。」
そういって、この子はあっけらかんと笑った。私が驚きを示さなくても、そんなことは現在の彼女の満ち足りた心に一片の曇りももたらさないようだった。それは人を驚かすことをアイデンティティとしているこの妖怪にとっては、きわめて稀なことに思われた。
「――その人間は……」
私が身を乗り出し、小傘越しに見とめたのは、見るも無残な幼い妖怪に玩具のように食い散らかされた子どもの死体だった。……そう、子ども。ぱっと見た感じでは、まだ五、六歳を過ぎたばかりではないだろうか。しかしそれは顔の調子で予想されただけに過ぎず――意外なほど静かにその目は閉じられていた。おそらく眠っているところを食われたのだろう――激しく捕食された身体の残骸は私にこの人間の正確な情報を知ることを許してはくれなかった。
「――誰も驚いてくれないんだ。」
「え?」
「大人も、子どもも、里にいるみんなは誰も驚いてくれないんだ。逆に、みんな強いんだ。私、いじめられたんだ。石、投げられて、ほら、傘にも穴があいてる。ひどいんだ。」
小傘はそう朴訥にいった。
「――でも、見て、この子どもはさ、私を見て驚いてくれたんだ。私、よく里に降りてたからわかるんだ。この子はもう大きくなったのに、言葉を上手く話せなくて、身体も弱くて、みんなからいじめられてたんだ。除け者にされてたんだ。私みたいに。だから私は驚いてもらおうって、弱い子どもならなんとかなるだろうって思って、この子にお前をさらってやるぞっていったんだ。そしたら、この子は私より弱いくせに、お前みたいにみんなにバカにされてる妖怪にそんなことできるもんかっていったんだ。……私はその言い草が頭に来たんだけど、でも、この子、震えてた。ほんとうは、私が、こわかったんだ。」
「――で、さらったの?」
「うん。さらったら、この子、泣いてね。そしたら、なんかかわいくなってきちゃって、かわいくて、かわいくて、家に帰してってこの子は泣いて、たいへんで、それで――」
「食べちゃったの?」
「うん。」
ちっぽけな唐傘の妖怪に過ぎなかった弱い弱い怪異は、そういって笑った。目はどこまでも平坦で、ガラスのように美しい光を湛えていた。そして自分で食い殺した幼児の頭を手に取ると、親しい友に語りかけるような調子で、撫でながら、胴体から切り離された首に、ささやくのだった。――君は私に生きる意味を教えてくれた、と。
くちゃくちゃと手でなまものを扱うとき特有の煮え切らない音と、硬い骨を指でほじくり出し、がむしゃらに歯でそれを噛み砕く音、そして露骨な咀嚼の音とが、一歩一歩と現場に近づいていく私を出迎える。風が木々を擦っていくがさつな音と、私を過ぎる衣擦れの音がそれらに混じって、泥土の上にはすえた血のにおい、生臭い肉のにおいが、瘴気となって立ち込めているように私には思われた。その鼻をつく臭気は、無論、吸血鬼を友人に持つ私にとっては、ある程度、慣れ親しんだものにちがいなかったが、目の前の妖怪の行為の結果はあまりに泥臭く、手慣れてなく、つまり吸血鬼のように血だけ吸って終りというような優雅さの欠片もなく、ひどく素人じみたものであって、誰が見たところでその様子の見苦しさには目を逸らすほかなかったろう。……そんなことを思いつつも、だけど、私は自分の不愉快さを一切表情には出さなかった。そしてもう一歩私が近寄ったとき、自分の仕業にみずから陶酔していたろう幼い浅慮な妖怪は、ようやく私の存在に気づき、そろそろと顔を向ける。――シャツの上に水色の上着をまとった、空色の薄い髪、左右で赤、水色と異なる色をした目を私に回した、あどけなさを残した無垢な表情――ただ、それらすべては今は血にまみれ、口元はむやみに垂れた涎でもってべたべたに汚れている。その姿はまるで砂場で夢中になって遊んだ子どものようとも感じられた。――彼女の名前は……私は記憶を手繰り寄せた……多々良小傘といったろうか。……私はある冬の夜、陰惨な現場に遭遇した魔女にふさわしい微笑でもって、小傘に対面した。
「――驚かないの?」
「驚くって、なぜ?」
「これ、見て……」
「ああ。……ま、けっこう見慣れているのよ。ここまで無茶苦茶に散らかしちゃっているのは妹様を連想させるくらいかしら。」
「そっかぁ。」
そういって、この子はあっけらかんと笑った。私が驚きを示さなくても、そんなことは現在の彼女の満ち足りた心に一片の曇りももたらさないようだった。それは人を驚かすことをアイデンティティとしているこの妖怪にとっては、きわめて稀なことに思われた。
「――その人間は……」
私が身を乗り出し、小傘越しに見とめたのは、見るも無残な幼い妖怪に玩具のように食い散らかされた子どもの死体だった。……そう、子ども。ぱっと見た感じでは、まだ五、六歳を過ぎたばかりではないだろうか。しかしそれは顔の調子で予想されただけに過ぎず――意外なほど静かにその目は閉じられていた。おそらく眠っているところを食われたのだろう――激しく捕食された身体の残骸は私にこの人間の正確な情報を知ることを許してはくれなかった。
「――誰も驚いてくれないんだ。」
「え?」
「大人も、子どもも、里にいるみんなは誰も驚いてくれないんだ。逆に、みんな強いんだ。私、いじめられたんだ。石、投げられて、ほら、傘にも穴があいてる。ひどいんだ。」
小傘はそう朴訥にいった。
「――でも、見て、この子どもはさ、私を見て驚いてくれたんだ。私、よく里に降りてたからわかるんだ。この子はもう大きくなったのに、言葉を上手く話せなくて、身体も弱くて、みんなからいじめられてたんだ。除け者にされてたんだ。私みたいに。だから私は驚いてもらおうって、弱い子どもならなんとかなるだろうって思って、この子にお前をさらってやるぞっていったんだ。そしたら、この子は私より弱いくせに、お前みたいにみんなにバカにされてる妖怪にそんなことできるもんかっていったんだ。……私はその言い草が頭に来たんだけど、でも、この子、震えてた。ほんとうは、私が、こわかったんだ。」
「――で、さらったの?」
「うん。さらったら、この子、泣いてね。そしたら、なんかかわいくなってきちゃって、かわいくて、かわいくて、家に帰してってこの子は泣いて、たいへんで、それで――」
「食べちゃったの?」
「うん。」
ちっぽけな唐傘の妖怪に過ぎなかった弱い弱い怪異は、そういって笑った。目はどこまでも平坦で、ガラスのように美しい光を湛えていた。そして自分で食い殺した幼児の頭を手に取ると、親しい友に語りかけるような調子で、撫でながら、胴体から切り離された首に、ささやくのだった。――君は私に生きる意味を教えてくれた、と。