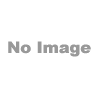「東方Project」二次創作 パチュリーのたまには動く大図書館Ⅲ #1
2011/01/05/Wed
目の前の僧侶は文字通り目にも捉えられない速度で空中に飛び上がると、困惑とも怒りとも取れない、しかしかすかな悲痛さを底に湛える深い瞳でもって私たちを見下ろした。彼女の存在は風の噂には効いていた。数百年間、妖怪の味方をしたという罪で魔界に封印されていたという、伝説に謳われる聖だった。彼女は元は人間だそうだが、長い年月と自身の選択した人生がもたらした苦難によって磨かれた魔法は、彼女をそこらの妖怪以上に計り知れない存在、ことによると、魔人と形容しても差し支えないほどの異形の怪と成していた。洋の東西のちがいはあれど、魔法という超自然の技法を操るという点では共通している私は、この女の力の底知れなさが嫌でも肌に感じられた。
「幻想郷に仏教僧なんて要りません。さあ、パチュリーさん、一緒にやっつけてやりましょう! 大丈夫、私は一度こいつに勝っていますから!」
「それはあなたの神社の二柱の力を借りてのことでしょう……」
沸々と滾る眼前の魔力を前にして、俄然、張り切る早苗を尻目に、私はどこまでもやる気がなかった。大体、今日の私は戦う準備なんて一切してきてないのだ。用意の不足した魔法使いは弱々だって、知ってる?
「いざ、覚悟――」
身がすくむほどの存在感を示す白蓮を前にして、この巫女の勇猛さは、若さからか無知ゆえか、早々に両手を上げて降参する私とは対照的に一目散に白蓮に飛び掛った早苗は、もしかしたら大物なのかもしれない。しかし、どれだけ意気盛んであろうと大火は小娘一人の手には負えるはずなく、案の定、瞬く間に青色の巫女はぼろぼろにされて地面に落ちてきた。死んだかと思って脈をとると、残念、息がある。私は情けなく目を回して気絶した早苗を肩に担ぐと、戦闘とも呼べないいざこざを終えた僧侶に会釈した。
「迷惑かけちゃったね。ごめんなさい。」
私の言葉に、白蓮は柔和に微笑んだ。その笑みの思いがけないやさしさとどことなく寂しさを思わせる風情に、私ははっと胸を打たれた気がして、思わず、この女性と二言、三言、言葉を交わしたい欲求に捕われた。だが、私のそんな思いは、冬の風が一吹き、枯れ枝を揺らした刹那に、舞った砂塵のなかに紛れて消えた白蓮の影のために、儚く絶たれてしまった。私はそれを惜しく思いながらも、背中に負った巫女の苦しげな呻き声を聞くと、もうこれ以上、あの聖には迷惑をかけられないかと考え直し、空へ飛んだ。
「――と、重い、この子……!」
私よりいくらか背が高いとはいえ、早苗一人抱えて飛ぶだけでも、もやしの私にはなんて重労働なことか! 私もさっきの僧のように身体を強くする魔法を覚えるべきかなと思案しつつ、冬空をふらふらと飛びながら、私はこの巫女と予想だにしないところで出会った日のことを思い出していた。それは人里のあの古道具屋でのことだった。
「――古い漫画みたいなのは置いてある。変なの。」
なんのために作られたものなのか、ぱっと見てはわからない奇妙なオブジェの数々が乱雑に並べられたこの古道具屋で、知った顔と鉢合わせる機会は稀というものだった。そもそも店主が人好きのする男ではないし、埃のたまった店内にいるのはただでさえぜん息持ちの私にとってはつらいものだったから、長居することはまずなかった。なので、この日たまたま山の神社の巫女である早苗と出会えたのは、単なる偶然以上の意味合いが私には感じられた。
「それは昭和の中ごろに流行した貸し本のひとつね。……ほら、多くの人に読まれたために、擦り切れて、時代を感じさせるでしょ。ほんの数十年前は日本でも本は高価だったから、多くの人はこうしてレンタルで読んでいたのよ。」
「あなたは、たしか……パチュリー、さん。」
「そう。美少女魔法使いのパチュリーさんよ。」
この巫女と顔を会わせた機会はそれほど多くなかった。話を聞くと、彼女は本が読みたくなってこの店に来たらしい。特になんの本が、というわけではない。現代世界から自分の意志と、そして半ば状況のために幻想郷に渡ったこの幼い少女にとって、活字の印刷物やさてはディスプレイの夥しい文字情報の海から、あまりに情報源の乏しい幻想郷に移ったということは、おそらく現代人が中世の世界へと生活を変えることと同じ程度のギャップがあるといっても過言ではないのだろう。何より、彼女くらいの年ごろは、さまざまな刺激を欲するのが自然というものだ。もちろん、幻想郷は十分にスリリングなところであるのはたしかだけれど、しかし好奇心というものは派手な弾幕のみで癒せるほど単純でないのもまた事実なのだ。好奇心にも、さまざまな種類があるのだから。
「なら、うちに来る? ちょっと毛色はちがうけど、あなたのいた現代世界でもそうは簡単にお目にかかることのできない本がたくさんあるのよ。」
「え、いいんですか?」
「もちろん。――あなたくらいの年ごろの子は、たくさん勉強したほうがきっといいと思うし。」
そういって私はにこっと笑った。当然、こういう私の言葉には裏がある。強大な力を持つ、山の神々の巫女である早苗に私の手で教育を与えることは、ひいては私の利益になるだろうという目論見があった。あの神さまたちの技術力は馬鹿にならないものがあったし、何より、博麗の巫女のように無軌道に勘でもって乱暴な力を振るわれるよりは、理知的な巫女がいたほうが都合がいいだろうし、いろいろとおもしろい。そう考えて、私は早苗の手をとった。
「いろいろ教えてあげましょう。中世フランス語とか。」
「えー、勉強はやだなぁ……」
早苗はそういいつつも私の誘いに乗ってきた。やはり、好奇心が先に立つ。――こうして、私と早苗の束の間の交流が始まった。……なぜ束の間という言葉を使ったのかというと、本当に、それは短い時間のことだったからだ。早苗の顔を思い出しながら、そうならざるをえなかった経緯を振り返ると、私は無駄と知りつつも、それを少し悲しく思う。
「幻想郷に仏教僧なんて要りません。さあ、パチュリーさん、一緒にやっつけてやりましょう! 大丈夫、私は一度こいつに勝っていますから!」
「それはあなたの神社の二柱の力を借りてのことでしょう……」
沸々と滾る眼前の魔力を前にして、俄然、張り切る早苗を尻目に、私はどこまでもやる気がなかった。大体、今日の私は戦う準備なんて一切してきてないのだ。用意の不足した魔法使いは弱々だって、知ってる?
「いざ、覚悟――」
身がすくむほどの存在感を示す白蓮を前にして、この巫女の勇猛さは、若さからか無知ゆえか、早々に両手を上げて降参する私とは対照的に一目散に白蓮に飛び掛った早苗は、もしかしたら大物なのかもしれない。しかし、どれだけ意気盛んであろうと大火は小娘一人の手には負えるはずなく、案の定、瞬く間に青色の巫女はぼろぼろにされて地面に落ちてきた。死んだかと思って脈をとると、残念、息がある。私は情けなく目を回して気絶した早苗を肩に担ぐと、戦闘とも呼べないいざこざを終えた僧侶に会釈した。
「迷惑かけちゃったね。ごめんなさい。」
私の言葉に、白蓮は柔和に微笑んだ。その笑みの思いがけないやさしさとどことなく寂しさを思わせる風情に、私ははっと胸を打たれた気がして、思わず、この女性と二言、三言、言葉を交わしたい欲求に捕われた。だが、私のそんな思いは、冬の風が一吹き、枯れ枝を揺らした刹那に、舞った砂塵のなかに紛れて消えた白蓮の影のために、儚く絶たれてしまった。私はそれを惜しく思いながらも、背中に負った巫女の苦しげな呻き声を聞くと、もうこれ以上、あの聖には迷惑をかけられないかと考え直し、空へ飛んだ。
「――と、重い、この子……!」
私よりいくらか背が高いとはいえ、早苗一人抱えて飛ぶだけでも、もやしの私にはなんて重労働なことか! 私もさっきの僧のように身体を強くする魔法を覚えるべきかなと思案しつつ、冬空をふらふらと飛びながら、私はこの巫女と予想だにしないところで出会った日のことを思い出していた。それは人里のあの古道具屋でのことだった。
「――古い漫画みたいなのは置いてある。変なの。」
なんのために作られたものなのか、ぱっと見てはわからない奇妙なオブジェの数々が乱雑に並べられたこの古道具屋で、知った顔と鉢合わせる機会は稀というものだった。そもそも店主が人好きのする男ではないし、埃のたまった店内にいるのはただでさえぜん息持ちの私にとってはつらいものだったから、長居することはまずなかった。なので、この日たまたま山の神社の巫女である早苗と出会えたのは、単なる偶然以上の意味合いが私には感じられた。
「それは昭和の中ごろに流行した貸し本のひとつね。……ほら、多くの人に読まれたために、擦り切れて、時代を感じさせるでしょ。ほんの数十年前は日本でも本は高価だったから、多くの人はこうしてレンタルで読んでいたのよ。」
「あなたは、たしか……パチュリー、さん。」
「そう。美少女魔法使いのパチュリーさんよ。」
この巫女と顔を会わせた機会はそれほど多くなかった。話を聞くと、彼女は本が読みたくなってこの店に来たらしい。特になんの本が、というわけではない。現代世界から自分の意志と、そして半ば状況のために幻想郷に渡ったこの幼い少女にとって、活字の印刷物やさてはディスプレイの夥しい文字情報の海から、あまりに情報源の乏しい幻想郷に移ったということは、おそらく現代人が中世の世界へと生活を変えることと同じ程度のギャップがあるといっても過言ではないのだろう。何より、彼女くらいの年ごろは、さまざまな刺激を欲するのが自然というものだ。もちろん、幻想郷は十分にスリリングなところであるのはたしかだけれど、しかし好奇心というものは派手な弾幕のみで癒せるほど単純でないのもまた事実なのだ。好奇心にも、さまざまな種類があるのだから。
「なら、うちに来る? ちょっと毛色はちがうけど、あなたのいた現代世界でもそうは簡単にお目にかかることのできない本がたくさんあるのよ。」
「え、いいんですか?」
「もちろん。――あなたくらいの年ごろの子は、たくさん勉強したほうがきっといいと思うし。」
そういって私はにこっと笑った。当然、こういう私の言葉には裏がある。強大な力を持つ、山の神々の巫女である早苗に私の手で教育を与えることは、ひいては私の利益になるだろうという目論見があった。あの神さまたちの技術力は馬鹿にならないものがあったし、何より、博麗の巫女のように無軌道に勘でもって乱暴な力を振るわれるよりは、理知的な巫女がいたほうが都合がいいだろうし、いろいろとおもしろい。そう考えて、私は早苗の手をとった。
「いろいろ教えてあげましょう。中世フランス語とか。」
「えー、勉強はやだなぁ……」
早苗はそういいつつも私の誘いに乗ってきた。やはり、好奇心が先に立つ。――こうして、私と早苗の束の間の交流が始まった。……なぜ束の間という言葉を使ったのかというと、本当に、それは短い時間のことだったからだ。早苗の顔を思い出しながら、そうならざるをえなかった経緯を振り返ると、私は無駄と知りつつも、それを少し悲しく思う。