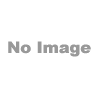「東方Project」二次創作 パチュリーのたまには動く大図書館Ⅱ #6
2010/12/02/Thu
――そは万象における完全なる父なり。その力は大地の上に限りなし。汝は、火と大地を、精と粗を、静かに巧みに分離すべし。そは大地より天に昇り、たちまち降りて、優と劣の力を取り集む。かくて汝は全世界の栄光を己がものとして、闇はすべて汝より離れ去らん。そは万物のうちの最強者なり。すべての精に勝ち、全物体に浸透するが故に。かく、世界は創造せられたり。かくの如きが、示されし驚異の変容の源なり。かくて我は世界霊魂の三部分を備うるがゆえに、ヘルメス・トリスメギストスと呼ばれたり。
『エメラルド・タブレット』の文言が私の周囲を取り巻き、やがて光り輝く文字は円環を取るよう配列していき、ついには宇宙蛇ウロボロスの模様を成した。アゾット石を吸収した私の身体は仄かに真紅に光り、かすかな熱を発し続ける。紫はそんな私を注意深く見つめ、一定の距離をとりながらも、しかし臆することなく、昨晩私を両断した空間を穿つ光の線を走らせた。その軌跡は通常なら私の肉体を無造作に横断し、精神を迷妄へと誘う力を秘めているのだろうが、今の私の前には無力だった。赤く輝く私の肌に触れるか否かといった手前まで接近したとき、跡形もなく境界の切れ目は煙のように霧散する。それと時を同じくして無数の目玉が私を取り巻くよう出現するが、しかしそれらは私を視界に収めた瞬間、太陽の激しい熱に直接焼かれたかのように、苦しみ悶えながら消滅していった。
「……錬金薬「エリキシル」。」
「そう。……もうあなたは私の境界を認識できない。あなたの攻撃は、私にたどり着く前に、焼け尽きる。」
私が手をかざすと、この場の物理法則を歪めていた紫の境界の能力はことごとく無力化され、もはや紫は武器を奪われたに等しかった。現と幻が奇妙に混在した迷いとイカサマの支配するカオスは消え去り、そこにはただ丸腰の妖怪がいるだけだった。
「あなたの境界の能力は決して無敵の能力ではない。もし本当にこの世界のありとあらゆる境界を意のままにできるのであれば、月の民でさえあなたの敵ではないはず。……あなたはあなたの認識できる境界しか、操作できないのよ。逆にいえば、あなたはあなたの想像を越えた存在を相手にしてはどうしようもできない。だから、私はあなたの想像を振り切った。なぜなら、あなたは誰かの想像と願いの上に成り立つ妖怪なんだから。」
「……錬金術は賢者の石により不純な物質を完全なる物質へと変成させることを目指した技術。当然、そのアナロジーは術者本人にも適用でき、賢者の石を服用した人間は、完全な身体を得ることが可能だという……」
「そのとおり。……ただだけど、まだまだ試験段階のアゾットだから、仮初の効果が得られるだけね。あなたの能力を無効化できるくらいで、蓬莱の薬には程遠い。」
「ふふふ。すばらしい。……でもそれだけでは私の刃を防いでいるに過ぎない。私の刃はあなたに届かないといえど、あなたの刃が私に届くわけではない。」
「それはそう。単なる魔法なら、インチキ極まりないあなたには通用しない。……だからこうやって工夫するのよ!」
そういって私は咲夜愛用の銀のナイフを所構わず周囲に投げつけ、そして同時に薄く灰色に濁った岩石の欠片の納められた小瓶を宙に掲げ、そこに能う限りの魔力を注ぎ込んだ。
「とっておきのサイレントセレナ!!」
小瓶に込められたのはこっそり持って帰っていた月の石の欠片であるイルミナイト。そこから放射される青白く凝縮された月の光は天に霞む月光と重なり、月の属性を示す銀のナイフを無数の槍と化し、紫目掛け、雨あられと降り注いだ。私の用意できるなかで月の性質を表現できる最高の媒介を二つ用いた魔法は、月の呪力の前に二度も膝をつくこととなった境界の妖怪を幾度も串刺しにしていく。穢れ深き地上の妖怪を代表するかのようなこの妖怪にとって、月精の加護を受けたこの魔法が通じぬ道理がなかったのだ。
「……お見事。……ですが、あなたも限界のようですね。」
全身を膾のように切り刻まれ、血の海に沈んだ紫が、しかしそんな傷などどうでもいいというかの如く、意識が朦朧とし、危うく地面に墜落しかけた私の身体を受けとめた。すでにアゾット石の効力は消え、鈍い痛みが全身に広がっている。赤い発光はもう収まり、ひどい頭痛がし、嫌な汗が全身を流れていた。
「不完全なアゾット石はすでにあなたの魔力をほとんど食らい尽したようですね。……ここから私があなたをくびり殺すのはたやすいでしょうが、しかし、パチュリー、私はあなたの知恵と決断と度胸に敬意を評し、今回の異変からは退きましょう。……アリスを救う方策はあるのですね?」
「……当然でしょう。私はパチュリー・ノーレッジ。幻想郷に並ぶもののない大魔道師よ。」
「わかりました。――では、パチュリー、私の力もあなたに預けます。今ここからアリスの心へと境界を開く。手を伸ばし、さあ、アリスを引っぱり出してあげなさい。」
――私にあなたの心はわからない。私は心理学者でも、まして覚でもないんだから。言葉で伝えてくれなきゃ、わからないのよ、アリス。
――私は私が欲しかった。別の私がいたら、もう一人の私が手に入れられたら、私は可能性を得られるから。
――可能性?
――妖怪じゃなく、人間として死ねた、私の可能性……
――その気持はなんとなくわかる。後悔って、いうのかな。
――…………
――でも、そうね、それより、たまにはお茶でもしにいらっしゃい。
――……え。
――あなたのクッキー、おいしかったから。愚痴くらいなら、いつでも聞くから。
――パチュリー……
――私はここにいる。そしてあなたはそこにいる。手を伸ばせば、届くから、さあ、ほら、手を伸ばして……――
私の指先が冷たくかすかに震えているアリスの手に触れた気がした。もう少し、もうちょっとだけ腕を伸ばせば、ほら、届く……私は彼女の手をつかむ……でも力が感じられない。彼女の手にはどこかためらいが感じられる。アリスの手のひらを、私はぎゅっと握り締める。力と、思いを込めて。そして……それから……おずおずと私の手を握り返す手ごたえが感じられる。私は思い切って、その手を引き上げた。
「……パチュリー!」
「さあ、クライマックスよ!!」
そこは魔法の森を抜け出た先にある湖の上空。煌々と照り輝く月を下に、もはやアリスの姿を留めていないグリル「足男」がその奇怪な容貌を顕わにし、邪悪な気を発していた。洋服や髪の毛といったアリスが人間らしくするために人形に施した工夫はすべて剥ぎとられ、骨格を成す木組みのみが残存している。ただ腕はない。なぜならあのグリルは頭と足のみで躍動する悪魔なのだから。そしてそんな足男を前にし、その呪いの拡散を防ぐべく、レミィと幽香が絶え間なく攻撃を仕掛けていた。しかし中世以来悪魔として扱われてきた歴史を背負う足男の呪力は桁違いであり、彼女たちの力でさえも阻まれてしまう。このままではいつかレミィたちも足男に取り込まれようかという状況のなかに、私とアリスは遥か上空から大地へと疾走した。
「レミィ! 幽香! 今から至高天の薔薇を描く!! あとは手はずどおりに!!」
そう叫び、私は最後の奥の手、アゾット石と純金からのみ合成されうる錬金術の奇蹟の到達点である「賢者の石」を湖の上に揺らいでいた足男へ向かって、なけなしの魔力を込め、投げつけた。わずかばかりの力であったが、賢者の石はそれでも弾丸のように飛び、七色に輝きながら、足男を中心にダンテの『神曲』天国篇に表現された、想像する限り最高の浄化の力を発揮する至高天の薔薇を、魔力を数百倍、数千倍に増幅させながら、展開した。降臨した聖なる力は足男の呪いを幾重にも封じ込め、周囲に撒き散らされていた邪悪な力をことごとく昇華させていく。
「幽香!!」
私の声に応じ、大地に深く腰を落とし、展開した傘をあたかも大砲のように構えた幽香が、渾身の光線を足男目掛け撃ち放った。そのあまりに巨体な熱と光の軌跡は夜を昼以上にまばゆく染めあげ、地面を抉りながら足男との距離を一瞬で詰め、その光の粒子のなかにグリルを押し流していった。
「レミィ!!」
重力の存在を感じさせないかのような猛スピードで彼方の天空に舞い上がったレミィの手には、どんな夜より黒く無骨にそびえる、レミィの体躯より倍も巨大な羿の弓が握られていた。そしてその弦にかけられるは、レミィの力により具現化される神槍「グングニル」。たなびく雲の上で翼をはためかせ、地上へと弓をつがえたレミィの気は一際大きく膨れあがり、吸血鬼の膂力によってのみ引き絞られるだろう強弓から、次の瞬間、極限にまで収斂された太陽さえ殺す一撃が、大地を穿っていた。
「……っ!!」
間髪入れず衝撃波が私たちを襲う。羿の弓の一射は大地にクレーターを作るほどで、その奈落のような穴からは煙が漂い、もはや足男は原型さえ残していなかった。残骸とも呼べないだろう粉々になったわずかな部分が、しかしそれでもなお、呪いの気をかすかに漂わせている。
「……精神体である悪魔を完全に殺すことはできない。それにアリス、あのグリルはあなたの感情を食ったため、あなたの心そのものと分ちがたく結びついている。あなたを殺さない限り、足男はこの世から消えない。」
「それじゃ……」
「ここから先はあなたの力で決着をつけるの。あなた自身の力で、あなたにしかできない技で、人形遣いのあなた以外には不可能な方法で。……あなたも魔法使いでしょう。なら、意地を見せなさい!」
私の言葉に、アリスは静かに眼を閉じると、それから意を決したかのようにこくんと頷いた。開かれた彼女の目には強い意志が宿っており、彼女は手を空にかざす。するとそこから黄金の滝ともいうべき魔力で編んだ糸の束が広げられていった。それは普段のアリスならここまで強い力は乗せないだろうという、人形遣いである彼女の真骨頂、人形を支配し操作する魔法の糸の集合であり、それらはまるでオーロラのように空にかかり、静謐に大地に溢れ、足男の存在そのものを縛っていく。金色に紡がれる糸の一本一本が、強靭な決意でもって、彼女の心を一時は食らい尽くそうとした闇の力を、今度は反対に支配しようとし、拘束していく。足男の命を、手中に納めていく。
――そう、アリス、悪魔になんて殺されるな。逆にあの悪魔の力を自分のものにしてしまえ。
光りたなびく黄金の糸が、そして次第にアリスの手もとに収束していった。……気づくと、もう、夜明けは近い。そしてすべては終っていた。昇り行く太陽を背にし、美しい、私でさえ見惚れてしまうような美しい、グリルを承伏した人形遣いの姿が、そこにはあるだけだった。彼女のまぶしいまでの笑顔が、黎明のなかに輝いていた。私もアリスに、とびきりの笑顔を向けていた。
おしまい
『エメラルド・タブレット』の文言が私の周囲を取り巻き、やがて光り輝く文字は円環を取るよう配列していき、ついには宇宙蛇ウロボロスの模様を成した。アゾット石を吸収した私の身体は仄かに真紅に光り、かすかな熱を発し続ける。紫はそんな私を注意深く見つめ、一定の距離をとりながらも、しかし臆することなく、昨晩私を両断した空間を穿つ光の線を走らせた。その軌跡は通常なら私の肉体を無造作に横断し、精神を迷妄へと誘う力を秘めているのだろうが、今の私の前には無力だった。赤く輝く私の肌に触れるか否かといった手前まで接近したとき、跡形もなく境界の切れ目は煙のように霧散する。それと時を同じくして無数の目玉が私を取り巻くよう出現するが、しかしそれらは私を視界に収めた瞬間、太陽の激しい熱に直接焼かれたかのように、苦しみ悶えながら消滅していった。
「……錬金薬「エリキシル」。」
「そう。……もうあなたは私の境界を認識できない。あなたの攻撃は、私にたどり着く前に、焼け尽きる。」
私が手をかざすと、この場の物理法則を歪めていた紫の境界の能力はことごとく無力化され、もはや紫は武器を奪われたに等しかった。現と幻が奇妙に混在した迷いとイカサマの支配するカオスは消え去り、そこにはただ丸腰の妖怪がいるだけだった。
「あなたの境界の能力は決して無敵の能力ではない。もし本当にこの世界のありとあらゆる境界を意のままにできるのであれば、月の民でさえあなたの敵ではないはず。……あなたはあなたの認識できる境界しか、操作できないのよ。逆にいえば、あなたはあなたの想像を越えた存在を相手にしてはどうしようもできない。だから、私はあなたの想像を振り切った。なぜなら、あなたは誰かの想像と願いの上に成り立つ妖怪なんだから。」
「……錬金術は賢者の石により不純な物質を完全なる物質へと変成させることを目指した技術。当然、そのアナロジーは術者本人にも適用でき、賢者の石を服用した人間は、完全な身体を得ることが可能だという……」
「そのとおり。……ただだけど、まだまだ試験段階のアゾットだから、仮初の効果が得られるだけね。あなたの能力を無効化できるくらいで、蓬莱の薬には程遠い。」
「ふふふ。すばらしい。……でもそれだけでは私の刃を防いでいるに過ぎない。私の刃はあなたに届かないといえど、あなたの刃が私に届くわけではない。」
「それはそう。単なる魔法なら、インチキ極まりないあなたには通用しない。……だからこうやって工夫するのよ!」
そういって私は咲夜愛用の銀のナイフを所構わず周囲に投げつけ、そして同時に薄く灰色に濁った岩石の欠片の納められた小瓶を宙に掲げ、そこに能う限りの魔力を注ぎ込んだ。
「とっておきのサイレントセレナ!!」
小瓶に込められたのはこっそり持って帰っていた月の石の欠片であるイルミナイト。そこから放射される青白く凝縮された月の光は天に霞む月光と重なり、月の属性を示す銀のナイフを無数の槍と化し、紫目掛け、雨あられと降り注いだ。私の用意できるなかで月の性質を表現できる最高の媒介を二つ用いた魔法は、月の呪力の前に二度も膝をつくこととなった境界の妖怪を幾度も串刺しにしていく。穢れ深き地上の妖怪を代表するかのようなこの妖怪にとって、月精の加護を受けたこの魔法が通じぬ道理がなかったのだ。
「……お見事。……ですが、あなたも限界のようですね。」
全身を膾のように切り刻まれ、血の海に沈んだ紫が、しかしそんな傷などどうでもいいというかの如く、意識が朦朧とし、危うく地面に墜落しかけた私の身体を受けとめた。すでにアゾット石の効力は消え、鈍い痛みが全身に広がっている。赤い発光はもう収まり、ひどい頭痛がし、嫌な汗が全身を流れていた。
「不完全なアゾット石はすでにあなたの魔力をほとんど食らい尽したようですね。……ここから私があなたをくびり殺すのはたやすいでしょうが、しかし、パチュリー、私はあなたの知恵と決断と度胸に敬意を評し、今回の異変からは退きましょう。……アリスを救う方策はあるのですね?」
「……当然でしょう。私はパチュリー・ノーレッジ。幻想郷に並ぶもののない大魔道師よ。」
「わかりました。――では、パチュリー、私の力もあなたに預けます。今ここからアリスの心へと境界を開く。手を伸ばし、さあ、アリスを引っぱり出してあげなさい。」
――私にあなたの心はわからない。私は心理学者でも、まして覚でもないんだから。言葉で伝えてくれなきゃ、わからないのよ、アリス。
――私は私が欲しかった。別の私がいたら、もう一人の私が手に入れられたら、私は可能性を得られるから。
――可能性?
――妖怪じゃなく、人間として死ねた、私の可能性……
――その気持はなんとなくわかる。後悔って、いうのかな。
――…………
――でも、そうね、それより、たまにはお茶でもしにいらっしゃい。
――……え。
――あなたのクッキー、おいしかったから。愚痴くらいなら、いつでも聞くから。
――パチュリー……
――私はここにいる。そしてあなたはそこにいる。手を伸ばせば、届くから、さあ、ほら、手を伸ばして……――
私の指先が冷たくかすかに震えているアリスの手に触れた気がした。もう少し、もうちょっとだけ腕を伸ばせば、ほら、届く……私は彼女の手をつかむ……でも力が感じられない。彼女の手にはどこかためらいが感じられる。アリスの手のひらを、私はぎゅっと握り締める。力と、思いを込めて。そして……それから……おずおずと私の手を握り返す手ごたえが感じられる。私は思い切って、その手を引き上げた。
「……パチュリー!」
「さあ、クライマックスよ!!」
そこは魔法の森を抜け出た先にある湖の上空。煌々と照り輝く月を下に、もはやアリスの姿を留めていないグリル「足男」がその奇怪な容貌を顕わにし、邪悪な気を発していた。洋服や髪の毛といったアリスが人間らしくするために人形に施した工夫はすべて剥ぎとられ、骨格を成す木組みのみが残存している。ただ腕はない。なぜならあのグリルは頭と足のみで躍動する悪魔なのだから。そしてそんな足男を前にし、その呪いの拡散を防ぐべく、レミィと幽香が絶え間なく攻撃を仕掛けていた。しかし中世以来悪魔として扱われてきた歴史を背負う足男の呪力は桁違いであり、彼女たちの力でさえも阻まれてしまう。このままではいつかレミィたちも足男に取り込まれようかという状況のなかに、私とアリスは遥か上空から大地へと疾走した。
「レミィ! 幽香! 今から至高天の薔薇を描く!! あとは手はずどおりに!!」
そう叫び、私は最後の奥の手、アゾット石と純金からのみ合成されうる錬金術の奇蹟の到達点である「賢者の石」を湖の上に揺らいでいた足男へ向かって、なけなしの魔力を込め、投げつけた。わずかばかりの力であったが、賢者の石はそれでも弾丸のように飛び、七色に輝きながら、足男を中心にダンテの『神曲』天国篇に表現された、想像する限り最高の浄化の力を発揮する至高天の薔薇を、魔力を数百倍、数千倍に増幅させながら、展開した。降臨した聖なる力は足男の呪いを幾重にも封じ込め、周囲に撒き散らされていた邪悪な力をことごとく昇華させていく。
「幽香!!」
私の声に応じ、大地に深く腰を落とし、展開した傘をあたかも大砲のように構えた幽香が、渾身の光線を足男目掛け撃ち放った。そのあまりに巨体な熱と光の軌跡は夜を昼以上にまばゆく染めあげ、地面を抉りながら足男との距離を一瞬で詰め、その光の粒子のなかにグリルを押し流していった。
「レミィ!!」
重力の存在を感じさせないかのような猛スピードで彼方の天空に舞い上がったレミィの手には、どんな夜より黒く無骨にそびえる、レミィの体躯より倍も巨大な羿の弓が握られていた。そしてその弦にかけられるは、レミィの力により具現化される神槍「グングニル」。たなびく雲の上で翼をはためかせ、地上へと弓をつがえたレミィの気は一際大きく膨れあがり、吸血鬼の膂力によってのみ引き絞られるだろう強弓から、次の瞬間、極限にまで収斂された太陽さえ殺す一撃が、大地を穿っていた。
「……っ!!」
間髪入れず衝撃波が私たちを襲う。羿の弓の一射は大地にクレーターを作るほどで、その奈落のような穴からは煙が漂い、もはや足男は原型さえ残していなかった。残骸とも呼べないだろう粉々になったわずかな部分が、しかしそれでもなお、呪いの気をかすかに漂わせている。
「……精神体である悪魔を完全に殺すことはできない。それにアリス、あのグリルはあなたの感情を食ったため、あなたの心そのものと分ちがたく結びついている。あなたを殺さない限り、足男はこの世から消えない。」
「それじゃ……」
「ここから先はあなたの力で決着をつけるの。あなた自身の力で、あなたにしかできない技で、人形遣いのあなた以外には不可能な方法で。……あなたも魔法使いでしょう。なら、意地を見せなさい!」
私の言葉に、アリスは静かに眼を閉じると、それから意を決したかのようにこくんと頷いた。開かれた彼女の目には強い意志が宿っており、彼女は手を空にかざす。するとそこから黄金の滝ともいうべき魔力で編んだ糸の束が広げられていった。それは普段のアリスならここまで強い力は乗せないだろうという、人形遣いである彼女の真骨頂、人形を支配し操作する魔法の糸の集合であり、それらはまるでオーロラのように空にかかり、静謐に大地に溢れ、足男の存在そのものを縛っていく。金色に紡がれる糸の一本一本が、強靭な決意でもって、彼女の心を一時は食らい尽くそうとした闇の力を、今度は反対に支配しようとし、拘束していく。足男の命を、手中に納めていく。
――そう、アリス、悪魔になんて殺されるな。逆にあの悪魔の力を自分のものにしてしまえ。
光りたなびく黄金の糸が、そして次第にアリスの手もとに収束していった。……気づくと、もう、夜明けは近い。そしてすべては終っていた。昇り行く太陽を背にし、美しい、私でさえ見惚れてしまうような美しい、グリルを承伏した人形遣いの姿が、そこにはあるだけだった。彼女のまぶしいまでの笑顔が、黎明のなかに輝いていた。私もアリスに、とびきりの笑顔を向けていた。
おしまい