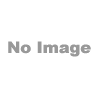「東方Project」二次創作 パチュリーのたまには動く大図書館Ⅱ #5
2010/11/30/Tue
「グリルはGryllosと書き、ラテン語で元来は豚というほどの意味に過ぎなかったんだけれど、時代を経るに従い、小人や巨人、あるいは上半身が獣であったり、あるいは下半身が鳥だったりする、いわゆる奇形的な、もしくは動物変態的な妖怪や化物を広く指す言葉として用いられるようになっていった。興味深いのはこの古代の異教的な想像力の産物だったグリルが、中世キリスト教社会において、魔術的な効力のある存在として認識され始めていくという事実ね。元々は単なる動物のパーツを奇妙に変形し組み合わせただけの、数多ある雑種的な神々でしかなかったわけだけれど、グリルはキリスト教の説教者たちの手によって、次第に悪の力を付与されるようになっていった。それはもちろん奇体なグリルの姿形がキリスト教が教えるところの悪魔の性質と同化しやすかったというのもあるのでしょうけど、人々の放埓な想像力は、キリスト教的倫理の示す禁忌の影響により、逆説的に拡大するかのように、グリルという悪魔の残虐なイメージの発明へと邁進した。……決定的だったのはダンテが『神曲』のなかで多数のグリルを地獄に登場させたことでしょうね。ダンテが表した地獄は純粋にキリスト教的世界観の産物ではなく、そこには古代世界と聖書との奇妙なイデオロギー的融合がある。グリルの秘める悪の力とは、だからその意味では、幻想郷に比すべき存在が見当らないほど、人々の情念が深く混交した複雑なものといえる。妖怪にとって楽園のようになってしまった今の幻想郷に、これほど似合わない幻想もまたないでしょうね。」
「でもなぜそんな存在がアリスの人形に宿ったわけ? そして、これは何に使われたというのかしら?」
そういい、幽香はテーブルの上に置かれたいくつかの白骨を指し示した。それは幽香がアリスの家の付近から回収したものであり、獣の死骸ではなく、まちがいなくかつて人間だったものの一部だった。
「……アリスは人形を自立させることを目論んでいた。自立のために何が必要かと考え、アリスがたどり着いた答えは、ずばり人形に魂を与えることだった。……その考えはおおむね正しい。魂が生命体を単なる物質の化合物以上の存在としているのだから。ただ、だけど、魂だけを創造することなんてまずできない。そこでアリスはある工夫を行なった。」
「工夫?」
「魂は生物に宿るという自然の事実を考えれば、アリスが実行したのは錬金術の秘儀の一つ、人造人間すなわちホムンクルスの創造にまちがいない。……その骨はおそらく幻想郷に迷い込んだ外の人間の成れの果てでしょうね。さすがに里の人間を襲えば巫女あたりが黙ってないでしょうし。あるいは墓から暴いた可能性も考えられるけれど、その骨はまださほど劣化してないから、その線は薄い。……骨はね、魂の受け皿として最も適当なのよ。「魂気天に帰し、形魄地に帰す」といってね、魂は気体のように浮きやすいものだから、フラスコとか骸骨とか、何かしら容れ物がないと上手く定着させることが叶わないのよ。」
「幻想郷は全てを受け入れる、か。……それで、このままそのグリルとかいう悪魔を放っておいたらどうなるのかしら? いつものように弾幕ごっこが通用する相手ではないのでしょう?」
幽香の質問に私はしばし目を瞑った。それから慎重に言葉を選びながら、泰然と構える幽香といつになく不安そうな目で私を見つめるレミィに対し、私はこう答える。
「……ホムンクルス製造も、そう簡単な技じゃないのよ。完全な生命体を構築するには、賢者の石か、あるいはそれに比する魔力を秘めたなんらかの神秘が必要になる。アリスがこの短期間で賢者の石を用意できるはずがないんだから、アリスには何か異なる魂を生む技の媒介が必要だった。そこで持ち出したのが、私が幻想郷に持ち込んだビザンチンの図像学とイスラムの宇宙誌的理論の集大成である、グリルのミニアチュール写本『ホルトゥス・デリキアルム』だったということなんでしょう。アリスがそれを見つけ出したのは偶然か……いえ、もともと魔界に縁の深いアリスは自然とあの本に引かれたのでしょうね。……しかし、だとしても、アリスの力だけでは私の封印は破れないし、あのグリル……グリルのなかで中世の逆説的雰囲気を最も体現するであろう、聖者をさえ説き伏せるグリル「足男」を、呼び寄せられるものじゃない。つまり、アリスにはあの悪魔と親和する何かがあった……」
「それはつまり?」
「負の感情。アリスの心にグリルを招き寄せるに足るなんらかの闇があったということにちがいない。……そして、召喚された悪魔は、本来ならアリスの人形へ魂を生み出す助力となるだけだったのでしょうけど、しかし逆にアリスの闇の感情につけ込み、アリスと人形ごと、我が物としてしまった。……そのうち、グリルはアリス本人を取り殺し、その呪いを幻想郷中に広めるべく動き出すでしょうね。」
「紫はどうするつもりだったの? そんなに強い悪魔もどうにかできる自信があったってことかな?」
レミィのその言葉に私は静かに首を振る。それから低い声でこう返答した。
「いつもの異変と同じように対処するつもりだから、慌てていないのよ。要するに、幻想郷の加護を受けた巫女が、巫女本来の力でもって、その使命を全うする。ただし、今回は、その命と引き換えに。……それが幻想郷のルールなんだから。」
そう言葉を切ると、私は立ち上がった。……私の状態は本調子とはいえない。むしろ気分は最悪だった。紫と真正面から向かい合った私のもともと丈夫じゃない身体はすでにぼろぼろだったし、何より精神的な損耗が激しかった。目を閉じれば、今も境界の妖怪と相対したときの不吉なヴィジョンが私の脳裏を埋め尽くすかのようで、思わず吐気に襲われる気がした。正直なところ、しばらくバカンスにでも行って、この心の傷を癒したかったのだが、そういうわけにも今回ばかりはいかない。というのも、悪魔を引き寄せるほど陰にこもった情念をアリスが抱えていることを見抜けなかったのは私の落ち度であったし、何よりここで何もせずこの異変の推移をただ傍観するのは、私のプライドがもう許さなかった。早ければ、紫は事態の解決に巫女を今夜にでも介入させるだろう。しかし、その前に、私がすべてを終らせる。
「アリスの心の闇がなんなのかは、わからない。……でも、方法はある。私には戦う術がある。……幽香とレミィは、手伝ってくれる?」
「月の花の件では、私が助けられました。今度は私がパチュリー、あなたに力を貸す番です。…ま、それに、アリスとはまったく知らない間柄というわけでもないし。」
「私はパチェの友だちじゃない! 大丈夫! そんじょそこらの古くさい悪魔なんて、吸血鬼っていう格調高い私の敵じゃないよ!」
怜悧な笑みを浮べる幽香と、胸を張って私を励ましてくれるレミィ。私はそんな二人にありがとうと聞こえないくらいに小さな声でそっと呟いた。案の定、二人には聞こえていないようだった。
――一度目は見逃しもし、許しもしましょう。しかし二度目はない。幸運はそうそう続かない。
コントラ・トリニタスが顕現した影響のためか、魔法の森はいつになく醜悪な雰囲気に包まれていた。獣が鳴き喚き、風は吹き荒れ、月にかかる雲は陰鬱な影を地面に落す。そして、そんな地上らしい穢れにまみれた大地の上を行く私たちの前に、地上の穢れのすべてを凝縮したかのように不吉で理解を絶した奇妙さを表現するかのような空間の断絶が生じ、そこから昨晩と同様、作り物めいた笑いを漂わした境界の妖怪が現れる。……が、こいつが姿を見せるのは予想どおりだ。私が頷くと、レミィと幽香はそれを合図に境界の妖怪には目もくれず、私一人を置いて、アリスのもとへと飛んでいった。その様子をさも意外そうに紫は眺め、それから手にした扇子で笑みを隠すように口元を覆い、私に細めた視線を差し向ける。
「おやおや。今度は三人がかりで私に立ち向かうものかと思っていましたが……。よろしいのかしら、あの二人といえど、グリルを相手にしたらそうは長く持ちません。……もっとも、私を前にしても、事情は変わるものではありませんけど。」
紫に対し、私は写本を開き、そして手もとから生まれたばかりの恒星のように赤く輝く球状の石を取り出した。それを見た瞬間、わずかに紫の顔色が歪むのを、私は見逃さなかった。
「あなたはたしかこんなことをいったっけね。覚悟の不十分な魔法使いほど殺しやすいものはない。……なら、逆にこうもいえるんじゃない? 覚悟を決めた魔法使いに、敵うものなどいはしない!!」
そう叫び、私は真紅に輝くその石を飲み込んだ。赤い石……万物の始原にして終焉の物質「アゾット」が、私の身体を染め上げていく。そして周囲に繰り広げられる『エメラルド・タブレット』の文言が、かつてないほどに私の魔力を練り上げていく。極限に高まった私の錬金術のすべてが、今、弾けようとしていた。
「でもなぜそんな存在がアリスの人形に宿ったわけ? そして、これは何に使われたというのかしら?」
そういい、幽香はテーブルの上に置かれたいくつかの白骨を指し示した。それは幽香がアリスの家の付近から回収したものであり、獣の死骸ではなく、まちがいなくかつて人間だったものの一部だった。
「……アリスは人形を自立させることを目論んでいた。自立のために何が必要かと考え、アリスがたどり着いた答えは、ずばり人形に魂を与えることだった。……その考えはおおむね正しい。魂が生命体を単なる物質の化合物以上の存在としているのだから。ただ、だけど、魂だけを創造することなんてまずできない。そこでアリスはある工夫を行なった。」
「工夫?」
「魂は生物に宿るという自然の事実を考えれば、アリスが実行したのは錬金術の秘儀の一つ、人造人間すなわちホムンクルスの創造にまちがいない。……その骨はおそらく幻想郷に迷い込んだ外の人間の成れの果てでしょうね。さすがに里の人間を襲えば巫女あたりが黙ってないでしょうし。あるいは墓から暴いた可能性も考えられるけれど、その骨はまださほど劣化してないから、その線は薄い。……骨はね、魂の受け皿として最も適当なのよ。「魂気天に帰し、形魄地に帰す」といってね、魂は気体のように浮きやすいものだから、フラスコとか骸骨とか、何かしら容れ物がないと上手く定着させることが叶わないのよ。」
「幻想郷は全てを受け入れる、か。……それで、このままそのグリルとかいう悪魔を放っておいたらどうなるのかしら? いつものように弾幕ごっこが通用する相手ではないのでしょう?」
幽香の質問に私はしばし目を瞑った。それから慎重に言葉を選びながら、泰然と構える幽香といつになく不安そうな目で私を見つめるレミィに対し、私はこう答える。
「……ホムンクルス製造も、そう簡単な技じゃないのよ。完全な生命体を構築するには、賢者の石か、あるいはそれに比する魔力を秘めたなんらかの神秘が必要になる。アリスがこの短期間で賢者の石を用意できるはずがないんだから、アリスには何か異なる魂を生む技の媒介が必要だった。そこで持ち出したのが、私が幻想郷に持ち込んだビザンチンの図像学とイスラムの宇宙誌的理論の集大成である、グリルのミニアチュール写本『ホルトゥス・デリキアルム』だったということなんでしょう。アリスがそれを見つけ出したのは偶然か……いえ、もともと魔界に縁の深いアリスは自然とあの本に引かれたのでしょうね。……しかし、だとしても、アリスの力だけでは私の封印は破れないし、あのグリル……グリルのなかで中世の逆説的雰囲気を最も体現するであろう、聖者をさえ説き伏せるグリル「足男」を、呼び寄せられるものじゃない。つまり、アリスにはあの悪魔と親和する何かがあった……」
「それはつまり?」
「負の感情。アリスの心にグリルを招き寄せるに足るなんらかの闇があったということにちがいない。……そして、召喚された悪魔は、本来ならアリスの人形へ魂を生み出す助力となるだけだったのでしょうけど、しかし逆にアリスの闇の感情につけ込み、アリスと人形ごと、我が物としてしまった。……そのうち、グリルはアリス本人を取り殺し、その呪いを幻想郷中に広めるべく動き出すでしょうね。」
「紫はどうするつもりだったの? そんなに強い悪魔もどうにかできる自信があったってことかな?」
レミィのその言葉に私は静かに首を振る。それから低い声でこう返答した。
「いつもの異変と同じように対処するつもりだから、慌てていないのよ。要するに、幻想郷の加護を受けた巫女が、巫女本来の力でもって、その使命を全うする。ただし、今回は、その命と引き換えに。……それが幻想郷のルールなんだから。」
そう言葉を切ると、私は立ち上がった。……私の状態は本調子とはいえない。むしろ気分は最悪だった。紫と真正面から向かい合った私のもともと丈夫じゃない身体はすでにぼろぼろだったし、何より精神的な損耗が激しかった。目を閉じれば、今も境界の妖怪と相対したときの不吉なヴィジョンが私の脳裏を埋め尽くすかのようで、思わず吐気に襲われる気がした。正直なところ、しばらくバカンスにでも行って、この心の傷を癒したかったのだが、そういうわけにも今回ばかりはいかない。というのも、悪魔を引き寄せるほど陰にこもった情念をアリスが抱えていることを見抜けなかったのは私の落ち度であったし、何よりここで何もせずこの異変の推移をただ傍観するのは、私のプライドがもう許さなかった。早ければ、紫は事態の解決に巫女を今夜にでも介入させるだろう。しかし、その前に、私がすべてを終らせる。
「アリスの心の闇がなんなのかは、わからない。……でも、方法はある。私には戦う術がある。……幽香とレミィは、手伝ってくれる?」
「月の花の件では、私が助けられました。今度は私がパチュリー、あなたに力を貸す番です。…ま、それに、アリスとはまったく知らない間柄というわけでもないし。」
「私はパチェの友だちじゃない! 大丈夫! そんじょそこらの古くさい悪魔なんて、吸血鬼っていう格調高い私の敵じゃないよ!」
怜悧な笑みを浮べる幽香と、胸を張って私を励ましてくれるレミィ。私はそんな二人にありがとうと聞こえないくらいに小さな声でそっと呟いた。案の定、二人には聞こえていないようだった。
――一度目は見逃しもし、許しもしましょう。しかし二度目はない。幸運はそうそう続かない。
コントラ・トリニタスが顕現した影響のためか、魔法の森はいつになく醜悪な雰囲気に包まれていた。獣が鳴き喚き、風は吹き荒れ、月にかかる雲は陰鬱な影を地面に落す。そして、そんな地上らしい穢れにまみれた大地の上を行く私たちの前に、地上の穢れのすべてを凝縮したかのように不吉で理解を絶した奇妙さを表現するかのような空間の断絶が生じ、そこから昨晩と同様、作り物めいた笑いを漂わした境界の妖怪が現れる。……が、こいつが姿を見せるのは予想どおりだ。私が頷くと、レミィと幽香はそれを合図に境界の妖怪には目もくれず、私一人を置いて、アリスのもとへと飛んでいった。その様子をさも意外そうに紫は眺め、それから手にした扇子で笑みを隠すように口元を覆い、私に細めた視線を差し向ける。
「おやおや。今度は三人がかりで私に立ち向かうものかと思っていましたが……。よろしいのかしら、あの二人といえど、グリルを相手にしたらそうは長く持ちません。……もっとも、私を前にしても、事情は変わるものではありませんけど。」
紫に対し、私は写本を開き、そして手もとから生まれたばかりの恒星のように赤く輝く球状の石を取り出した。それを見た瞬間、わずかに紫の顔色が歪むのを、私は見逃さなかった。
「あなたはたしかこんなことをいったっけね。覚悟の不十分な魔法使いほど殺しやすいものはない。……なら、逆にこうもいえるんじゃない? 覚悟を決めた魔法使いに、敵うものなどいはしない!!」
そう叫び、私は真紅に輝くその石を飲み込んだ。赤い石……万物の始原にして終焉の物質「アゾット」が、私の身体を染め上げていく。そして周囲に繰り広げられる『エメラルド・タブレット』の文言が、かつてないほどに私の魔力を練り上げていく。極限に高まった私の錬金術のすべてが、今、弾けようとしていた。