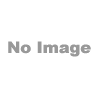「みつどもえ」二次創作 みつひとその3!
2010/08/13/Fri
「プライバシーがぜんぜんない……」
ざぶとんにあぐらをかいて座っている先生は、いつものように生気のない顔で、いつものごとく覇気の欠けた声で、宙のあらぬ方向を見つめて、そんなことを呟いた。
「私のことは気にしないでください。」
「気にするよ! というか、今日はなんでこんなに長くいるの!? いつもは朝ちょっといるか、チクビを取りに少し寄るくらいなのに!? ボク何もできないじゃないっ。」
「先生は私がいるの、迷惑なんですね…」
「そ、そうじゃないけど…。い、いや、ちがくて、もう夕方だよ。ひとはちゃんもそろそろ帰らないと、家の人、心配するんじゃないかな?」
「……そんなこと、別にないです。」
私はそっぽを向いてそういった。ベッドの端に腰かけた私の太ももの上にはハムスターのチクビが乗っかっていて、私は指先でかわいらしくちまちまと反応するチクビと戯れる。
「ボクごはん食べに行きたいんだけど……」
「勝手に行ってください。部屋の鍵はちゃんと持ってますから。」
「そういう問題じゃないんだけど! ってか、それも問題ではあるんだけど!」
先生はため息をついた。
「……ひとはちゃん、どうしちゃったの? ひとはちゃんがいなきゃ、みつばちゃんもふたばちゃんもお父さんも困るでしょ。それに……」
「……くしゅん。」
「…具合悪いよね? どこか熱っぽいというか、風邪なら家までボクが送っていこうか?」
「平気です……」
私は答えるのも億劫というように先生から顔を逸らした。先生はあきらめたのか、それとも呆れたのか、立ち上がると無言で部屋を出て行った。扉がばたんと閉まる。用心のためか、鍵もかけたようだ。私はそれら一連の音を聞き終えると、ベッドの上にだらりと横になった。チクビは私の手から逃れ、小走りに床を駆けていく。……夏の夕方の熱気にぼやかされた静かな乱雑な部屋。私は目をつむった。どうして私はこんなところにいるのだろう、と。……ゆるやかに上昇していく体温が、いつしか私の意識をさらっていった。
「――あ、ひとは起きた。」
「……ふたば?」
夢も見ない眠りから覚めた私は、微かに感じる振動と回った腕に伝わる温かみに、ふたばにおんぶされていることに気がついた。辺りはすでに薄暗く、外灯がまばらに舗装道の灰色を照らしている。その上をふたばは私を背負っていることなど意に介さない軽やかな足取りで進んでいく。
「……」
「ひとは、帰り遅いから探してたんス。休みの日は矢部っちのところにいるから、もしかしたらまだいるかなと思ったら、やっぱりいた。」
「……そっか。先生にも迷惑かけたね。」
「ひと、熱ある?」
「……少し。」
「無理しちゃだめっスよ。」
ふたばのぴょんぴょん揺れる頭の房を眺めて、私は深く息を吐いた。ふたばはそれ以上何も聞いてこない。今何時か、私はどれくらい眠っていたのか気にかかったけど、それより千々に乱れた心が、私に自然と無意識の心の裡を言葉として吐き出させようと働いた。
「……先生の部屋以外に思いつかなかったんだ。」
「何が?」
「私が誰のことも考えず、放っておかれる場所。……家にいたくなかったんだ。だからといって、ほかに、行くところもないし。」
「みんな心配してるスよ。」
「……嘘だよ。」
「嘘じゃないスよ。」
「……」
「みっちゃんもパパも小生も、ひとのこと、気にしてるよ。」
「……だから、」
「?」
「だから、だめなんだよ。」
私はそういって、ふたばに回した腕をきゅっと締めつけた。ふたばにすがりつき、熱にゆだった額を彼女の背に押しつける。ふたばは何もいわない。顔は見えないけど、きっとふたばは笑っているはず。いつものように、笑顔でいるはず。――私の存在は、気持は、それを壊しちゃうかもしれないんだよ? 私は何もいえなかった。
ざぶとんにあぐらをかいて座っている先生は、いつものように生気のない顔で、いつものごとく覇気の欠けた声で、宙のあらぬ方向を見つめて、そんなことを呟いた。
「私のことは気にしないでください。」
「気にするよ! というか、今日はなんでこんなに長くいるの!? いつもは朝ちょっといるか、チクビを取りに少し寄るくらいなのに!? ボク何もできないじゃないっ。」
「先生は私がいるの、迷惑なんですね…」
「そ、そうじゃないけど…。い、いや、ちがくて、もう夕方だよ。ひとはちゃんもそろそろ帰らないと、家の人、心配するんじゃないかな?」
「……そんなこと、別にないです。」
私はそっぽを向いてそういった。ベッドの端に腰かけた私の太ももの上にはハムスターのチクビが乗っかっていて、私は指先でかわいらしくちまちまと反応するチクビと戯れる。
「ボクごはん食べに行きたいんだけど……」
「勝手に行ってください。部屋の鍵はちゃんと持ってますから。」
「そういう問題じゃないんだけど! ってか、それも問題ではあるんだけど!」
先生はため息をついた。
「……ひとはちゃん、どうしちゃったの? ひとはちゃんがいなきゃ、みつばちゃんもふたばちゃんもお父さんも困るでしょ。それに……」
「……くしゅん。」
「…具合悪いよね? どこか熱っぽいというか、風邪なら家までボクが送っていこうか?」
「平気です……」
私は答えるのも億劫というように先生から顔を逸らした。先生はあきらめたのか、それとも呆れたのか、立ち上がると無言で部屋を出て行った。扉がばたんと閉まる。用心のためか、鍵もかけたようだ。私はそれら一連の音を聞き終えると、ベッドの上にだらりと横になった。チクビは私の手から逃れ、小走りに床を駆けていく。……夏の夕方の熱気にぼやかされた静かな乱雑な部屋。私は目をつむった。どうして私はこんなところにいるのだろう、と。……ゆるやかに上昇していく体温が、いつしか私の意識をさらっていった。
「――あ、ひとは起きた。」
「……ふたば?」
夢も見ない眠りから覚めた私は、微かに感じる振動と回った腕に伝わる温かみに、ふたばにおんぶされていることに気がついた。辺りはすでに薄暗く、外灯がまばらに舗装道の灰色を照らしている。その上をふたばは私を背負っていることなど意に介さない軽やかな足取りで進んでいく。
「……」
「ひとは、帰り遅いから探してたんス。休みの日は矢部っちのところにいるから、もしかしたらまだいるかなと思ったら、やっぱりいた。」
「……そっか。先生にも迷惑かけたね。」
「ひと、熱ある?」
「……少し。」
「無理しちゃだめっスよ。」
ふたばのぴょんぴょん揺れる頭の房を眺めて、私は深く息を吐いた。ふたばはそれ以上何も聞いてこない。今何時か、私はどれくらい眠っていたのか気にかかったけど、それより千々に乱れた心が、私に自然と無意識の心の裡を言葉として吐き出させようと働いた。
「……先生の部屋以外に思いつかなかったんだ。」
「何が?」
「私が誰のことも考えず、放っておかれる場所。……家にいたくなかったんだ。だからといって、ほかに、行くところもないし。」
「みんな心配してるスよ。」
「……嘘だよ。」
「嘘じゃないスよ。」
「……」
「みっちゃんもパパも小生も、ひとのこと、気にしてるよ。」
「……だから、」
「?」
「だから、だめなんだよ。」
私はそういって、ふたばに回した腕をきゅっと締めつけた。ふたばにすがりつき、熱にゆだった額を彼女の背に押しつける。ふたばは何もいわない。顔は見えないけど、きっとふたばは笑っているはず。いつものように、笑顔でいるはず。――私の存在は、気持は、それを壊しちゃうかもしれないんだよ? 私は何もいえなかった。