61式戦車 砲塔工作編
61式戦車製作記第2弾、砲塔工作編です!
報告は今になりましたが実際の加工は大分前に完了してたんですけどね。
なんせスケモは加工に関しては記事内容があまり無いので小出しでなんとか
乗り切ろうって事です。
キットは以前にプチリニューアルされた時にキャンバス付砲身が追加されて
まして、キャンバス無しのタイプと選択出来るようになってます。
イメージ的にも61式はキャンバス付きの方がしっくりくるのでこちらを選択。
(パーツが新しい分変形が少なかったって事もありますけど・・・・・・)

ほぼキットのままですけど、同軸機銃の銃口は開口して内部にプラパイプ
を入れてますが、実際にどうなってるかは知りません。
右側の照準眼鏡の部分も開口してあります。
下にあるのは砲塔上部に装備されるM2重機関銃で、本体はキットのままですけど
銃身は変形が酷かったので真鍮線と真鍮パイプで自作。
あと、コッキングレバーとグリップを追加してますが、グリップはこの後で形状を
変えてますので完成品は画像とは少し違ってます。

61式の砲塔は現在の戦車みたいな複合装甲ではなく、避弾経始を考慮した
円形の鋳造砲塔になってます。
なので鋳造表現を加えながら少しのディテアップで味付け。
砲塔後部の荷物積載用のフックは真鍮線に置き換え、キューポラのハッチ固定用の
チェーンも削り落として極細チェーンに置き換えてます。
アンテナは基部だけ残して真鍮線で自作、少し長めにしています。
砲身基部のキャンバス取り付け部にはキャンバス取り付け用の金具を追加。
ブラシートを張り付けて再現してますが固定ボルトの小さいのが手持ちで無かった
のでプリオンで代用しました。

砲塔の鋳造表現はこんな感じにしてます。
ラッカーパテを擦り付けたりする方法もありますが、私は接着剤を塗り付ける方法を
採用しています。
これは塗装面の荒れ具合の調整や細部の加工がしやすいって事もあります。
この鋳造表現ですけど、鋳造とは溶けた鉄を砂で作った鋳型に流し込んで形を作る
方法なので表面に砂面の荒れが出るので表面がブツブツや凸凹になります。
ですが、その後である程度は研磨されて表面は慣らされています。
戦時中のように少しでも早く戦線に投入する必要がある場合には省略されてました
のでかなり荒れた表面になってますが、大戦後の戦車ではその必要も無かった為か
結構綺麗な装甲面になってて陸自戦車でも同じようにツルツルとまではいかないけど
結構綺麗な面に仕上げられてます。
なので、使用する接着剤も流し込み用を使用して軽く溶けた状態で処理してます。
画像では結構荒れた状態になってますが、サフ吹き、塗装と進めていくと徐々に
荒れが消えていくのでその辺りを考慮しています。
(この段階であまり綺麗な面だとサフ吹きだけで消えてしまったりしちゃいますよ)

これはサフ吹きと下地塗装後の装甲面ですが、この程度まで落ち着きます。
これで大体実際の装甲面に近い荒れ具合になってると思います。
よく実車の拡大写真や実車を見て、かなり凸凹に処理されてる作例を見かけますが
拡大写真はその部分が強調されていますし、実車は物自体が大きいのでそういった
部分も良く目についてしまいます。
ですが、模型はスケールが1/35や1/74と小さくなっており、当然表面の荒れ具合の
見え方も細かくなってきますよね。
つまり同じ荒れ具合でもスケールによって見え方が変わるって事です。
スケールエフェクトなんて言葉がありますが、そういった事も考慮しながら模型を
製作すると、また違った作品が出来るんじゃないかなと思います。
な~んて、偉そうな事垂れてますが言ってる自分が出来てないんですけどね。
難しいですけど折角戦車を作るので色々とやってみたいと思ってます。

これもその一環として今回初めてやってみた車体表面の細かい傷表現。
画像では分かりにくいかもしれませんが通常の傷とは別に表面に細いすり傷が
入ってるの分かります?
車体に付いてる細いすり傷なんかは1/35サイズだと殆ど見えなくなります。
なのでサフ吹きの後で真鍮ブラシで表面をゴシゴシとやって、すり傷を再現。
ワイヤーブラシだと、きつく入り過ぎるので真鍮ブラシが丁度いい感じ。
サフ吹き前にキットに直接処理しても入れられますがサフを吹くと殆ど消えてしまい
ます。(それ程細い傷って事ですね)
その後塗装すると画像のような感じに仕上がります。
この傷、間近で凝視しないと分からない程度の傷でして、最終仕上げでツヤ消しに
すると拡大写真や見る角度を変えて間近で凝視しないと判別出来ないと思います。
自己満足かもしれませんが、こういった事も作品の仕上がりに影響してくるのでは
ないかなぁ?なんて思いますから。
という事で工作の方はこれで全て終了!
現在は塗装作業に入ってます。
塗装工程も幾らかは報告するつもりですけど、以前に作ったⅢ突とあまり大差ない
かもしれませんけどね。
まぁ、気が向いたら見て頂ければ幸いです。
では、今回はこの辺で!
| 固定リンク
| コメント (0)
| トラックバック (0)

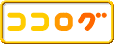





最近のコメント