常陸風土記の丘にいってみました
今日は土曜日で家にほとんどいたが、本当に暑かった。いつもクーラの中に昼間いると気がつかなかったのかもしれないが、体が秋を求めているのに「まだまだ~よ」と言われたような感じであった。
この暑い中に久しぶりに常陸風土記の丘公園に出かけてみた。この暑さで人もまばらではあったがこの空間は貴重であるので、益々の発展を願っている。

今は人気の花もなく、暑い日には人では少ない。小学生が自転車で5-6人遊んでいた。

公園も暑いが木陰に入るとホットする。風はあまりないがやはり涼しい。

古代ハスも8月半ばでほぼ花は終わり、今はハチの巣のような花弁が奇妙だ。

公園内はまだツクツクボウシが賑やかで、トンボはシオカラトンボとやっと赤トンボが結構飛んでいた。

花は今は見ごろのものはほとんどない。サルスベリの赤い花が美しかった。
公園の駐車場にはマイクロバスが1台。筑西市の俳句会様とか。俳句の会も近隣を中心に多くの人が訪れる。しかし、正岡子規の水戸紀行の時に泊まった「萬屋」旅館の跡地は知られていない。せめて看板でも設置してほしいものだ。市長さんからは「良い提案であるので「教育委員会」の方に検討するように指示した。」と4月に返事をもらったのだが・・・・。良いものを作ってもこれを皆さんに活用してもらうのは市民のみに目を向けていては活性化しない。PRもとてもへただな~。
この暑い中に久しぶりに常陸風土記の丘公園に出かけてみた。この暑さで人もまばらではあったがこの空間は貴重であるので、益々の発展を願っている。

今は人気の花もなく、暑い日には人では少ない。小学生が自転車で5-6人遊んでいた。

公園も暑いが木陰に入るとホットする。風はあまりないがやはり涼しい。

古代ハスも8月半ばでほぼ花は終わり、今はハチの巣のような花弁が奇妙だ。

公園内はまだツクツクボウシが賑やかで、トンボはシオカラトンボとやっと赤トンボが結構飛んでいた。

花は今は見ごろのものはほとんどない。サルスベリの赤い花が美しかった。
公園の駐車場にはマイクロバスが1台。筑西市の俳句会様とか。俳句の会も近隣を中心に多くの人が訪れる。しかし、正岡子規の水戸紀行の時に泊まった「萬屋」旅館の跡地は知られていない。せめて看板でも設置してほしいものだ。市長さんからは「良い提案であるので「教育委員会」の方に検討するように指示した。」と4月に返事をもらったのだが・・・・。良いものを作ってもこれを皆さんに活用してもらうのは市民のみに目を向けていては活性化しない。PRもとてもへただな~。
石岡の景観(恋瀬橋)
今日は幾分風があり、朝方は筑波山が比較的きれいに見えた。毎日のように山の方も何気なく眺めるようになっているが、夏場にはあまりはっきり見える日が少ない。以前石岡市で「残したい景観のアンケート」というのを依頼された。結果は市報か何かに載ったのを見たように思うが、その後の動きが見えない。少し景観について時々書いてみたいと思う。個人的な私感が伴うので、それ程のこともないが、とても気になっている。

この写真は6号国道の恋瀬川に架かる「恋瀬橋」からの眺めである。
この場所以外にも、常磐線の橋からの眺めや高浜の方からの眺めは同じように美しい。万葉の頃から歌に読まれ、風光明媚な場所であったことが想像される。山と川の組み合わせはとても素晴らしいものである。これは「恋瀬川」の名前の由来などの歴史を紐解いていくと尚一層素晴らしい景色に見えてくる。是非この景観をもう少し整備し(あまり人工的ではなく)余計なものは出来るだけ排除するように願いたい。
この写真を撮っているとき、私は2つのことを考えていた。一つは「太古の昔の人が電線や大きな橋などなく、もっと空気が澄んでいた時にどのように見えたのだろうか?」ということ、もちろん龍神山は元の雄姿でみることができたであろうから・・・。もう一つは「この景色はどこかで見た景色に少し似ているな。そう、尾瀬ヶ原と燧岳や至仏岳の雄姿の組み合わせだ。」ということだ。尾瀬は昔から何度も訪れているが、こんなに身近にも似た景色があったということであった。もちろん周りの環境などはまったく違っているので比べようもないが、昔はもっともっときれいだったに違いない。現在6号バイパスなる名前の道路が反対側で工事中で、青い橋が一部架けられているが、どの程度この景観が損なわれることになるのか・・・。
とても心配である。

この写真は6号国道の恋瀬川に架かる「恋瀬橋」からの眺めである。
この場所以外にも、常磐線の橋からの眺めや高浜の方からの眺めは同じように美しい。万葉の頃から歌に読まれ、風光明媚な場所であったことが想像される。山と川の組み合わせはとても素晴らしいものである。これは「恋瀬川」の名前の由来などの歴史を紐解いていくと尚一層素晴らしい景色に見えてくる。是非この景観をもう少し整備し(あまり人工的ではなく)余計なものは出来るだけ排除するように願いたい。
この写真を撮っているとき、私は2つのことを考えていた。一つは「太古の昔の人が電線や大きな橋などなく、もっと空気が澄んでいた時にどのように見えたのだろうか?」ということ、もちろん龍神山は元の雄姿でみることができたであろうから・・・。もう一つは「この景色はどこかで見た景色に少し似ているな。そう、尾瀬ヶ原と燧岳や至仏岳の雄姿の組み合わせだ。」ということだ。尾瀬は昔から何度も訪れているが、こんなに身近にも似た景色があったということであった。もちろん周りの環境などはまったく違っているので比べようもないが、昔はもっともっときれいだったに違いない。現在6号バイパスなる名前の道路が反対側で工事中で、青い橋が一部架けられているが、どの程度この景観が損なわれることになるのか・・・。
とても心配である。
石岡の景観(高浜の海)
台風のおかげで久しぶりの雨となった。一部激しく降ったりしているが、恵みの雨でもある。野菜などは助かっているだろう。さて、昨日に続いて石岡の景観について書いてみたい。今回は「高浜の海」である。江戸時代に利根川の東遷工事で銚子へ流れが変更されるまでは、今の霞ケ浦は海水で大きな内海であった。香取の海と呼ばれていた。高浜も「国府の浜」が「こうのはま」となり「たかはま」に名前が変わったと考えられている。昨日の恋瀬橋からの筑波山の眺めを紹介したが、ここ高浜から見た筑波山はまた違った美しさがある。

この写真は、今の6号国道のバイパス工事前の写真であり、この景色は大分変ってしまうかもしれない。
常陸風土記の書かれた頃(奈良時代初期)にはもっと水は豊かであったと思われ、交通も歩く以外は牛車や舟であるので今の鉄道や車の社会で想像するのは難しくなってきている。しかし、奈良時代を想像できる景観を残していかなければならないと思うのは私だけではないだろう。
高浜神社の看板に書かれた常陸風土記の口語訳を紹介しよう。
---------------------------------------------------------------
<高浜の海>
そもそもこの地は、花かおる春、また木の葉の色づき散りしく秋になると、あるいは駕(のりもの)を命じて出向き、また舟を漕ぎ出して遊ぶ。春の浦々には花が千々に咲き乱れ、秋には岸という岸の木の葉が色づく。春はさえずる鶯(うぐいす)の声を野のほとりで耳にし、秋は宙に舞う鶴の姿を海辺のなぎさで目にする。農夫の若者と海人(あま)の娘は、浜辺を逐(お)い走って群れつどい、商人と農夫は、小舟に棹(さお)さして行き交う。まして真夏の暑い朝、陽光でむっと暑い夕暮れになると。友を呼び僕(しもべ)を引き連れて、浜かげに並んで腰をおろし、海上はるかにながめやる。少し波立ち夕風がしずかに吹き出すと、暑さを避けて集まった者は、晴れやらぬ心の憂(う)さを風に払い、岡を照らしていた日影がしだいに動いて行くにつれ、涼を求める者は、喜びの心を動かすのである。
----------------------------------------------------------------
☆ 高浜に 来寄する浪の 沖つ浪 寄すとも寄らじ 子らにし寄らば
(高浜に寄せ来る波が、どんなに沖から寄せ来ても(他の女が寄って来ても)、私の心が動かないのは、あの娘に心を寄せてるからだ。)
☆ 高浜の 下風(したかぜ)さやぐ 妹を恋ひ 妻と言はばや しこと召しつも
(高浜の浜辺の下を騒がしく吹く風ではないが、恋するあの娘を妻と呼びたい気持ちがこみあげてくる。こんな私だのに。)

この写真は、今の6号国道のバイパス工事前の写真であり、この景色は大分変ってしまうかもしれない。
常陸風土記の書かれた頃(奈良時代初期)にはもっと水は豊かであったと思われ、交通も歩く以外は牛車や舟であるので今の鉄道や車の社会で想像するのは難しくなってきている。しかし、奈良時代を想像できる景観を残していかなければならないと思うのは私だけではないだろう。
高浜神社の看板に書かれた常陸風土記の口語訳を紹介しよう。
---------------------------------------------------------------
<高浜の海>
そもそもこの地は、花かおる春、また木の葉の色づき散りしく秋になると、あるいは駕(のりもの)を命じて出向き、また舟を漕ぎ出して遊ぶ。春の浦々には花が千々に咲き乱れ、秋には岸という岸の木の葉が色づく。春はさえずる鶯(うぐいす)の声を野のほとりで耳にし、秋は宙に舞う鶴の姿を海辺のなぎさで目にする。農夫の若者と海人(あま)の娘は、浜辺を逐(お)い走って群れつどい、商人と農夫は、小舟に棹(さお)さして行き交う。まして真夏の暑い朝、陽光でむっと暑い夕暮れになると。友を呼び僕(しもべ)を引き連れて、浜かげに並んで腰をおろし、海上はるかにながめやる。少し波立ち夕風がしずかに吹き出すと、暑さを避けて集まった者は、晴れやらぬ心の憂(う)さを風に払い、岡を照らしていた日影がしだいに動いて行くにつれ、涼を求める者は、喜びの心を動かすのである。
----------------------------------------------------------------
☆ 高浜に 来寄する浪の 沖つ浪 寄すとも寄らじ 子らにし寄らば
(高浜に寄せ来る波が、どんなに沖から寄せ来ても(他の女が寄って来ても)、私の心が動かないのは、あの娘に心を寄せてるからだ。)
☆ 高浜の 下風(したかぜ)さやぐ 妹を恋ひ 妻と言はばや しこと召しつも
(高浜の浜辺の下を騒がしく吹く風ではないが、恋するあの娘を妻と呼びたい気持ちがこみあげてくる。こんな私だのに。)
祭りが終わって明日は中秋の名月
石岡のお祭りも終わり、街はまた静けさを取り戻しました。
でも、賑やかだったはずなのにどこか虚しさが襲ってきます。
祭りの時以外に、この駅に降り立った人は、この人通りのなさをきっと「寂しい街だなあ」と思うに違いありません。
私などがいくら街をPRしてもほとんど効果はありませんが、それでも少しは活性化になるように思ってやってきたのですが・・・・。
良いものは沢山あるのに、それを見たり感じる感性がこの町には感じないのは何故でしょうか?
薬師古道を整備し、薬師堂の景色はすばらしい風情があった。
しかし、人寄せパンダではあるまいに人工的な石灯篭や看板を配し、意味のまったくつかめない姿に変わってしまった。奈良や大和の寺を歩いた人はこの保存会にいないのだろうか。
自慢できるものが一つ減ってしまった。残念に思えてならない。
こんな気持ちはきっと理解できないのだろう。
歴史の町と自認していても、その時代は戦国時代まで。平家の祖先がいた町であるのに、その後がない。
江戸時代などに見るものが何もない。260年もの間、何があったのでしょうか。
多くの火災があったと私はHPに書いた。そしてなくしたと・・・・。
しかし、なくしたのでは、隠しているか、敢えて見せないのだと思う。
舟塚山古墳に眠っていた宝物は何処に??
静かになった町の真上に名月がそっと優しい光を注いでいる。
昔ときっと変わらない光と思うが、「昔は活気があった。」などとこれからもズーッと言っていくのだろうか。
60歳以上のネットを使う人と使わない(使えない)人の差がラジオで議論になっていた。
使えるからどうってことはないが、何歳になっても物事に対する感性をなくしたくはない。
昭和36年に開かれた上野の国立美術館の「ルーブルを中心としたフランス美術展」に中学になったばかりだったが両親に連れられて見に行った。
上野公園の端から長蛇の列でやっと入場したが、人がいっぱい。
でもその時に見た絵画の印象が一生忘れられないものになった。
その後、西洋美術館にやってきた「ミロのビーナス」もすごい人だかりだった。
その当時は、文化的なものに飢えていたのかもしれない。
そして、東京駅のブリヂストン美術館や、倉敷の大原美術館、奈良の博物館、デパートで開催したマネ・モネ・ルノワール・セザンヌ・ビュフェ・ユトリロ・ダリなどの美術展に足を運んだりした。
しかし、大学に入ってゼミの人達と話をして、皆あまりにも知らないことに驚いたことがあった。
皆、私より裕福な家庭に育っているはずであったが・・・。
理科系の人は絵画や文学には興味がなかったのかもしれない。
石岡に立派でなくてもよいが、しっかりとした美術館、博物館、資料館などを建てていただけないだろうか。
図書館は利用者が多いが、美術館などは利用者が少ないのでダメ??
発想が貧弱なんだな~。これでは文化は育たない。
お月さんのウサギが笑ってら。
でも、賑やかだったはずなのにどこか虚しさが襲ってきます。
祭りの時以外に、この駅に降り立った人は、この人通りのなさをきっと「寂しい街だなあ」と思うに違いありません。
私などがいくら街をPRしてもほとんど効果はありませんが、それでも少しは活性化になるように思ってやってきたのですが・・・・。
良いものは沢山あるのに、それを見たり感じる感性がこの町には感じないのは何故でしょうか?
薬師古道を整備し、薬師堂の景色はすばらしい風情があった。
しかし、人寄せパンダではあるまいに人工的な石灯篭や看板を配し、意味のまったくつかめない姿に変わってしまった。奈良や大和の寺を歩いた人はこの保存会にいないのだろうか。
自慢できるものが一つ減ってしまった。残念に思えてならない。
こんな気持ちはきっと理解できないのだろう。
歴史の町と自認していても、その時代は戦国時代まで。平家の祖先がいた町であるのに、その後がない。
江戸時代などに見るものが何もない。260年もの間、何があったのでしょうか。
多くの火災があったと私はHPに書いた。そしてなくしたと・・・・。
しかし、なくしたのでは、隠しているか、敢えて見せないのだと思う。
舟塚山古墳に眠っていた宝物は何処に??
静かになった町の真上に名月がそっと優しい光を注いでいる。
昔ときっと変わらない光と思うが、「昔は活気があった。」などとこれからもズーッと言っていくのだろうか。
60歳以上のネットを使う人と使わない(使えない)人の差がラジオで議論になっていた。
使えるからどうってことはないが、何歳になっても物事に対する感性をなくしたくはない。
昭和36年に開かれた上野の国立美術館の「ルーブルを中心としたフランス美術展」に中学になったばかりだったが両親に連れられて見に行った。
上野公園の端から長蛇の列でやっと入場したが、人がいっぱい。
でもその時に見た絵画の印象が一生忘れられないものになった。
その後、西洋美術館にやってきた「ミロのビーナス」もすごい人だかりだった。
その当時は、文化的なものに飢えていたのかもしれない。
そして、東京駅のブリヂストン美術館や、倉敷の大原美術館、奈良の博物館、デパートで開催したマネ・モネ・ルノワール・セザンヌ・ビュフェ・ユトリロ・ダリなどの美術展に足を運んだりした。
しかし、大学に入ってゼミの人達と話をして、皆あまりにも知らないことに驚いたことがあった。
皆、私より裕福な家庭に育っているはずであったが・・・。
理科系の人は絵画や文学には興味がなかったのかもしれない。
石岡に立派でなくてもよいが、しっかりとした美術館、博物館、資料館などを建てていただけないだろうか。
図書館は利用者が多いが、美術館などは利用者が少ないのでダメ??
発想が貧弱なんだな~。これでは文化は育たない。
お月さんのウサギが笑ってら。
今日は冷え込んで筑波山がくっきり
今日はこの秋一番の冷え込みとのことでした。
しかし、朝は冷えていたが昼間は久しぶりの青空が広がり、とても気持ちの良い天気でした。
毎日のように恋瀬川から筑波山を眺めているが、今朝はくっきりと見ることができました。
やはり、恋瀬川から見る筑波山が一番美しい。
さて、昨日、諭吉通りの話を書いたが、この街道には「長豊街道」とある。
この辺りの地名かと思ったが、調べてみると茨城県旧長竿村(現河内町)と千葉県豊住村(現成田市)を結ぶ通りから名前がついたようだ。
茨城と千葉の境を流れる利根川に架かる長豊橋の名前が先についたと思われる。
この橋も地域住民の長年の運動が実ったといわれる。結構長い橋であり交通量も結構多い。
成田空港ができたためだろうか?
しかし、通りの沿線沿いはあまり開けていない。開発も難しいものだと考えさせられる。
羽田の国際線発着が始まり、成田の近辺ももっと開けることを期待していただろうに・このありさまです・・・。
東京の一極集中は本当にこのままでよいのだろうか?
地方は益々過疎、高齢化が進みます。
明日は、また雨で気温も上がらないとの予報。週末も天気は期待できないという。
なにか冷たい雨は気分も滅入りそうでいやになる。
金曜日には銚子にまたでかける。美味しいものでも食べることを考えよう。
しかし、朝は冷えていたが昼間は久しぶりの青空が広がり、とても気持ちの良い天気でした。
毎日のように恋瀬川から筑波山を眺めているが、今朝はくっきりと見ることができました。
やはり、恋瀬川から見る筑波山が一番美しい。
さて、昨日、諭吉通りの話を書いたが、この街道には「長豊街道」とある。
この辺りの地名かと思ったが、調べてみると茨城県旧長竿村(現河内町)と千葉県豊住村(現成田市)を結ぶ通りから名前がついたようだ。
茨城と千葉の境を流れる利根川に架かる長豊橋の名前が先についたと思われる。
この橋も地域住民の長年の運動が実ったといわれる。結構長い橋であり交通量も結構多い。
成田空港ができたためだろうか?
しかし、通りの沿線沿いはあまり開けていない。開発も難しいものだと考えさせられる。
羽田の国際線発着が始まり、成田の近辺ももっと開けることを期待していただろうに・このありさまです・・・。
東京の一極集中は本当にこのままでよいのだろうか?
地方は益々過疎、高齢化が進みます。
明日は、また雨で気温も上がらないとの予報。週末も天気は期待できないという。
なにか冷たい雨は気分も滅入りそうでいやになる。
金曜日には銚子にまたでかける。美味しいものでも食べることを考えよう。
寒さは緩んだが、今朝も筑波山はきれいだった。
最近あまり晴れの日が少ないので朝の筑波山もはっきり見える日が少なかったが、今日はきれいに見えた。
カメラを持っていなかったし、朝は急いでもいるので目に焼き付けておいた。
恋瀬川が昔の歌の名所である男女川(みなのがわ)であろうと鈴木健氏はいっている。
ここからの筑波山が一番きれいだし、石岡に国府があったことを考えればそれは本当に違いないと思う。
しかし、もう少しこの川もきれいにしてもらえないだろうか。
昔を偲ぶには「背い高泡立ち草」がいっぱいでは興ざめしてしまう。
少し整備して、そこに生息する動物や魚を観察し、皆に知らせてほしいものだ。
「地域おこし」はそこを訪れた人をリピータとして大事にすることが本当の底流になければならない。
どうすればリピータが増えるか、これは海外の事例も含めたくさんの方法が紹介されている。
図書館の建設は地元の利用者は喜ぶが、これは文化の向上にはなってもリピータの確保・増加の観点からは町おこしの対象にはならない。
それよりも受験生などが気軽に利用できる勉強スペース(ボックス)などを街中に確保して、学力の向上に役立ててほしい。
来年は電子書籍が世界中に広まる。何処の図書館にどんな図書があるかがすぐにわかる。
図書館に行かなくても世界中の本が見られるようになるかもしれない。
少し将来を見据えた斬新な図書館(七重の塔の形をした電子図書館など)なら話題性もあり、良いと思うが・・・・。
これから年より社会で、暇な老人はクーラや暖房の効いている無料で利用できる図書館は良いが、街の発展にはあまり寄与できない。
昨日今日と以前石岡の歴史のHPで知り合った方からブログにコメントをいただいた。
うれしいですね。またこのブログも止めずに続けていけそうだ。
カメラを持っていなかったし、朝は急いでもいるので目に焼き付けておいた。
恋瀬川が昔の歌の名所である男女川(みなのがわ)であろうと鈴木健氏はいっている。
ここからの筑波山が一番きれいだし、石岡に国府があったことを考えればそれは本当に違いないと思う。
しかし、もう少しこの川もきれいにしてもらえないだろうか。
昔を偲ぶには「背い高泡立ち草」がいっぱいでは興ざめしてしまう。
少し整備して、そこに生息する動物や魚を観察し、皆に知らせてほしいものだ。
「地域おこし」はそこを訪れた人をリピータとして大事にすることが本当の底流になければならない。
どうすればリピータが増えるか、これは海外の事例も含めたくさんの方法が紹介されている。
図書館の建設は地元の利用者は喜ぶが、これは文化の向上にはなってもリピータの確保・増加の観点からは町おこしの対象にはならない。
それよりも受験生などが気軽に利用できる勉強スペース(ボックス)などを街中に確保して、学力の向上に役立ててほしい。
来年は電子書籍が世界中に広まる。何処の図書館にどんな図書があるかがすぐにわかる。
図書館に行かなくても世界中の本が見られるようになるかもしれない。
少し将来を見据えた斬新な図書館(七重の塔の形をした電子図書館など)なら話題性もあり、良いと思うが・・・・。
これから年より社会で、暇な老人はクーラや暖房の効いている無料で利用できる図書館は良いが、街の発展にはあまり寄与できない。
昨日今日と以前石岡の歴史のHPで知り合った方からブログにコメントをいただいた。
うれしいですね。またこのブログも止めずに続けていけそうだ。
筑波山には尾花が似合う?
昨日の文化の日の私のブログはページアクセス数が130にもなった。
いつもはせいぜい20~30アクセス程度であるので一気に増えたことになる。
理由はある程度分かっているが、丁寧にナンページも見ていただいた方にはお礼を言いたい。
行徳在住者さんにはコメントもたくさんいただいた。
町おこしアドバイスも感謝!
まあ今日はいつものペースに戻ったようである。本ブログはブログ村やツイッターとも連動していない。
やり方はあるのだろうが、ノンビリマイペースでやることにしよう。
仕事を終えて外を見たら、まだ5時半だというのに真っ暗になっていた。
暗くなると寒さも増してくる。
今朝、恋瀬川の橋から筑波山をみたら、少し上の方にでていた雲の影響か、朝日がまだらに山に当たって、山の中腹は明るい緑色、少し上は濃い緑。山の二つの頂上も、手前の女体山は日が当らず、奥の男体山はキラキラと明るく輝いていた。
不思議な風景だあった。
昨日、恋瀬川の志筑寄りにある「粟田橋」付近で撮影したススキ(尾花)と筑波山の写真を載せておきます。

ここの橋は新しく架け直されて立派になり、常陸風土記の丘へとつながっている。
写真は昔の橋があった辺りの風景である。
筑波山には尾花が似合うのかもしれない。
もっとも万葉の頃の尾花は写真のようなススキ?ではないだろう。
このような細いススキでは茅葺の屋根は葺けない。
八郷地区には茅葺の家が何軒も残っている。
保存も大変なのだが、後世に残して行ってほしい。
「東京から最も近い田舎(里山)」をキャッチフレーズとしてPRしていこう!
いつもはせいぜい20~30アクセス程度であるので一気に増えたことになる。
理由はある程度分かっているが、丁寧にナンページも見ていただいた方にはお礼を言いたい。
行徳在住者さんにはコメントもたくさんいただいた。
町おこしアドバイスも感謝!
まあ今日はいつものペースに戻ったようである。本ブログはブログ村やツイッターとも連動していない。
やり方はあるのだろうが、ノンビリマイペースでやることにしよう。
仕事を終えて外を見たら、まだ5時半だというのに真っ暗になっていた。
暗くなると寒さも増してくる。
今朝、恋瀬川の橋から筑波山をみたら、少し上の方にでていた雲の影響か、朝日がまだらに山に当たって、山の中腹は明るい緑色、少し上は濃い緑。山の二つの頂上も、手前の女体山は日が当らず、奥の男体山はキラキラと明るく輝いていた。
不思議な風景だあった。
昨日、恋瀬川の志筑寄りにある「粟田橋」付近で撮影したススキ(尾花)と筑波山の写真を載せておきます。

ここの橋は新しく架け直されて立派になり、常陸風土記の丘へとつながっている。
写真は昔の橋があった辺りの風景である。
筑波山には尾花が似合うのかもしれない。
もっとも万葉の頃の尾花は写真のようなススキ?ではないだろう。
このような細いススキでは茅葺の屋根は葺けない。
八郷地区には茅葺の家が何軒も残っている。
保存も大変なのだが、後世に残して行ってほしい。
「東京から最も近い田舎(里山)」をキャッチフレーズとしてPRしていこう!
雨晴れてコスモス野に笑う
今日は久しぶりに天気も回復ししたが、スッキリした青空とはいかなかった。
しかし朝は久しぶりに筑波山が顔を見せ、朝日が二つの山にあたり輝いていた。
今週初めは朝冷え込み、車の窓ガラスが凍った。しかしその日の筑波山はとても美しく輝いていた。
また、その後朝は寒さが緩んでも、冷たい雨で一日気温が上がらず、気持ちも晴れない日が続いた。
今日は久しぶりの青空が広がった。コスモスも久しぶりに笑っているようだった。
もともと花が咲くことは笑うと同じだという。まあ山が笑うといえば春のことだが
コスモス畑も広がり筑波山も背景にはもってこいだった。
先日、テレビで東京に住んでいる人を対象にした県別人気度調査の話をしていた。
その結果は、茨城県は2年連続最下位となったという。
まったくおかしな話でもあり、またもっともとも思う。
東京に住んでいた頃の茨城のイメージは最悪であった。
言葉使いも何か親しみが持てず、正直をいって住みたいとは思わなかった。
しかし、住めば都というように今はすっかり茨城住民になった。
最下位はさすがにうれしくはない。
何が足りないのかについて、自分なりに考えはあるのだが・・・・。
温暖な気候、海に山に果物・野菜など実に豊富で、東京の台所となっているが、東京の人は認識がない。
これは、実に不思議なことである。
茨城といえば「納豆」と「水戸黄門」だという。
「県民性のせいだ」と片づけるのは簡単だが、私は違う見方をしている。
「PRしないことを佳し」とするのは本当に県民性のせいであろうか?
私は「努力が足りない」「努力をしなくても食べていけるから良いと今までずーと過ごしてきた。」
せいではないのかと思っている。まさに商売人ではないのです。
県のイメージを上げ、県を豊かにしていくことは将来の子供たちに対する義務でもあります。
例えば、ネットで発言したり、良さを発信するのも豊かな県では当たり前のように湧いてくるものです。
皆さん、おとなしすぎます。もっともっと自分を磨いて大いに発信しましょう。
しかし朝は久しぶりに筑波山が顔を見せ、朝日が二つの山にあたり輝いていた。
今週初めは朝冷え込み、車の窓ガラスが凍った。しかしその日の筑波山はとても美しく輝いていた。
また、その後朝は寒さが緩んでも、冷たい雨で一日気温が上がらず、気持ちも晴れない日が続いた。
今日は久しぶりの青空が広がった。コスモスも久しぶりに笑っているようだった。
もともと花が咲くことは笑うと同じだという。まあ山が笑うといえば春のことだが
コスモス畑も広がり筑波山も背景にはもってこいだった。
先日、テレビで東京に住んでいる人を対象にした県別人気度調査の話をしていた。
その結果は、茨城県は2年連続最下位となったという。
まったくおかしな話でもあり、またもっともとも思う。
東京に住んでいた頃の茨城のイメージは最悪であった。
言葉使いも何か親しみが持てず、正直をいって住みたいとは思わなかった。
しかし、住めば都というように今はすっかり茨城住民になった。
最下位はさすがにうれしくはない。
何が足りないのかについて、自分なりに考えはあるのだが・・・・。
温暖な気候、海に山に果物・野菜など実に豊富で、東京の台所となっているが、東京の人は認識がない。
これは、実に不思議なことである。
茨城といえば「納豆」と「水戸黄門」だという。
「県民性のせいだ」と片づけるのは簡単だが、私は違う見方をしている。
「PRしないことを佳し」とするのは本当に県民性のせいであろうか?
私は「努力が足りない」「努力をしなくても食べていけるから良いと今までずーと過ごしてきた。」
せいではないのかと思っている。まさに商売人ではないのです。
県のイメージを上げ、県を豊かにしていくことは将来の子供たちに対する義務でもあります。
例えば、ネットで発言したり、良さを発信するのも豊かな県では当たり前のように湧いてくるものです。
皆さん、おとなしすぎます。もっともっと自分を磨いて大いに発信しましょう。
かすみがうら水族館
今日は朝から雨。勤労感謝の日ではあるが仕事は休みでないので朝は出かけた。
午後から、東京から来ている母のために早く帰ってきた。
途中で黄色に色づいたイチョウの葉が雨で大分散ってしまっていた。
落ち葉も増え、やはり冬が来た感じがする。毎年時間のたつのは早い。
今は昭和ロマンの街並みに時々大きな丸い月が顔を出している。
先の日曜日に母を連れて、かすみがうら市の歩崎(あゆみざき)公園にある水族館に行ってきた。
ここは霞ケ浦の淡水生物の水族館として設立され、小さい子供などにも楽しめるように出来ている。
今は霞ケ浦だけでなく、世界の淡水魚や亀などがたくさんいて、一見の価値があるが、宣伝不足
のためか、あまり知られていない。

水族館の入口手前も昔に比べきれいに整備され、噴水や銅像などこれも天皇陛下のご来館が予定されたことがあったためでしょうか。
5年前に近くの「霞ケ浦環境科学センター」にこられ、その時に見学の話があったと聞いています。
しかし、あまりにもみすぼらしいのではないかとの話で・・・結果はどうなったのか??

しかし、銅像(あゆみ)に鯉のいる池と噴水はきれいに整備されています。

水族館の入口に大きなゾウガメ? その先に市民から愛称を募集した2匹のケヅメリクガメがいます。
子供のためか、世界のクワガタもこの時期にも生きて展示されています。

水族館の入口の霞ケ浦を一望できる場所に「帆引き船発祥の地」の石碑が建てられていました。
この日も日曜日だというのに、訪れていたのは、私たちと男の子を連れた親子3人の2組のみ。
賑やかなお祭りや遊具などがないので子供にも人気がないのだろうか。
ここには我が家の子供たちは小さい時に良き遊びに来た。
水辺の生物を触ることができるようになっていて結構楽しめたものだ。
しかし今は触れるようになっていたのはザリガニのみ。
しかしこのザリガニは日本ザリガニ? 日本ザリガニは貴重だが・・・
また外から見た建物よりも内部は結構広く、十分楽しめます。
石岡に戻るために数年前に無料となった霞ケ浦大橋をわたり、行方市の「道の駅たまつくり」や「水の科学館」側に渡ると、大勢の人があふれていました。
何があるというのでしょうか。
最近特に大型の店舗なども積極的に進出して人も集まるようになりました。
子供が楽しめる施設もあります。
数年前までは閑散としていたことを思えば雲泥の差です。
特別なものがなくても行ってみたいと思う何かがあるのでしょう。
でも行方市としては他の歴史的な史跡も多いのですが、あまり人が多いことはありません。
どこも閑散としています。霞ケ浦の自然が残され石岡とも古くから交流があった場所です。
鹿島鉄道があれば「玉造」-「石岡」はとても近いイメージだったのですが・・・。
午後から、東京から来ている母のために早く帰ってきた。
途中で黄色に色づいたイチョウの葉が雨で大分散ってしまっていた。
落ち葉も増え、やはり冬が来た感じがする。毎年時間のたつのは早い。
今は昭和ロマンの街並みに時々大きな丸い月が顔を出している。
先の日曜日に母を連れて、かすみがうら市の歩崎(あゆみざき)公園にある水族館に行ってきた。
ここは霞ケ浦の淡水生物の水族館として設立され、小さい子供などにも楽しめるように出来ている。
今は霞ケ浦だけでなく、世界の淡水魚や亀などがたくさんいて、一見の価値があるが、宣伝不足
のためか、あまり知られていない。

水族館の入口手前も昔に比べきれいに整備され、噴水や銅像などこれも天皇陛下のご来館が予定されたことがあったためでしょうか。
5年前に近くの「霞ケ浦環境科学センター」にこられ、その時に見学の話があったと聞いています。
しかし、あまりにもみすぼらしいのではないかとの話で・・・結果はどうなったのか??

しかし、銅像(あゆみ)に鯉のいる池と噴水はきれいに整備されています。

水族館の入口に大きなゾウガメ? その先に市民から愛称を募集した2匹のケヅメリクガメがいます。
子供のためか、世界のクワガタもこの時期にも生きて展示されています。

水族館の入口の霞ケ浦を一望できる場所に「帆引き船発祥の地」の石碑が建てられていました。
この日も日曜日だというのに、訪れていたのは、私たちと男の子を連れた親子3人の2組のみ。
賑やかなお祭りや遊具などがないので子供にも人気がないのだろうか。
ここには我が家の子供たちは小さい時に良き遊びに来た。
水辺の生物を触ることができるようになっていて結構楽しめたものだ。
しかし今は触れるようになっていたのはザリガニのみ。
しかしこのザリガニは日本ザリガニ? 日本ザリガニは貴重だが・・・
また外から見た建物よりも内部は結構広く、十分楽しめます。
石岡に戻るために数年前に無料となった霞ケ浦大橋をわたり、行方市の「道の駅たまつくり」や「水の科学館」側に渡ると、大勢の人があふれていました。
何があるというのでしょうか。
最近特に大型の店舗なども積極的に進出して人も集まるようになりました。
子供が楽しめる施設もあります。
数年前までは閑散としていたことを思えば雲泥の差です。
特別なものがなくても行ってみたいと思う何かがあるのでしょう。
でも行方市としては他の歴史的な史跡も多いのですが、あまり人が多いことはありません。
どこも閑散としています。霞ケ浦の自然が残され石岡とも古くから交流があった場所です。
鹿島鉄道があれば「玉造」-「石岡」はとても近いイメージだったのですが・・・。
筑波山が朝日に燃えていた。
今朝の筑波山は美しかった。
日が山や尾根に当たり、車の通りや橋などは少し日が陰って暗くなり、山の紅葉が朝日を浴びて輝きコントラストが見事であった。
毎日のように筑波山を見るが、同じ姿を見せることはほとんどない。
みな少しずつ違った姿を見せてくれるのはとてもありがたい。
石岡からみた筑波山は二つの頂上(男体山、女体山)が少し離れているだけで一番バランスが良いのである。
正岡子規の水戸紀行では次のように詠んでいる。
白雲の蒲團の中につゝまれてならんで寐たり女體男體
石岡から片倉へ向かう途中での歌ではあるが、ここから少し北(東)へ進むと、筑波山の2つの頂は一つになってくるのである。
また土浦やつくば市の方から見ると、2つの頂は大分離れて見える。
従って筑波山を見るには「高浜」や石岡の恋瀬川付近がもっとも美しく見える。
万葉の時代にはもっと美しく見えたのだろうと想像するだけで楽しくなる。
まだ先日引いた風邪が本調子ではない。
微熱で調子も悪いが、正岡子規が血を吐いても死ぬまで歌をうたうホトトギスの別名で自分の名前を
「子規」としたのは、この水戸紀行の途中で吐血し、旅行から戻って少したった頃と聞いている。
病気でも情熱があれば歌を詠むことができるのですね。
普通の人は気力も衰えてしまうものなのですが・・・。
人間何歳になっても情熱は捨ててはいけませんね。
私もまだまだ頑張りますわ。自分のできる範囲を精一杯やるだけですが・・・
論語にいわれる「七十にして矩を踰えず」ということは、70歳までは矩(のり)を踰(こ)えてもOK?
少しくらいまだ無理をしても良いともとれますね。
日が山や尾根に当たり、車の通りや橋などは少し日が陰って暗くなり、山の紅葉が朝日を浴びて輝きコントラストが見事であった。
毎日のように筑波山を見るが、同じ姿を見せることはほとんどない。
みな少しずつ違った姿を見せてくれるのはとてもありがたい。
石岡からみた筑波山は二つの頂上(男体山、女体山)が少し離れているだけで一番バランスが良いのである。
正岡子規の水戸紀行では次のように詠んでいる。
白雲の蒲團の中につゝまれてならんで寐たり女體男體
石岡から片倉へ向かう途中での歌ではあるが、ここから少し北(東)へ進むと、筑波山の2つの頂は一つになってくるのである。
また土浦やつくば市の方から見ると、2つの頂は大分離れて見える。
従って筑波山を見るには「高浜」や石岡の恋瀬川付近がもっとも美しく見える。
万葉の時代にはもっと美しく見えたのだろうと想像するだけで楽しくなる。
まだ先日引いた風邪が本調子ではない。
微熱で調子も悪いが、正岡子規が血を吐いても死ぬまで歌をうたうホトトギスの別名で自分の名前を
「子規」としたのは、この水戸紀行の途中で吐血し、旅行から戻って少したった頃と聞いている。
病気でも情熱があれば歌を詠むことができるのですね。
普通の人は気力も衰えてしまうものなのですが・・・。
人間何歳になっても情熱は捨ててはいけませんね。
私もまだまだ頑張りますわ。自分のできる範囲を精一杯やるだけですが・・・
論語にいわれる「七十にして矩を踰えず」ということは、70歳までは矩(のり)を踰(こ)えてもOK?
少しくらいまだ無理をしても良いともとれますね。
鬼越峠
最近ブログを毎日更新するということが結構大変だということに気がつき始めている。
まあ、きょうは何があったとか、単に写真を載せたりのものなら続きそうだが、テーマを探してそれをまた調べながら書くのにはどうしても時間がかかるのである。
今までにかなり多くのことを調べてはいるので、書きたいことはまだたくさんあるが、すべて中途半端な知識でしかない物が多い。
ブログを始めたのが8月11日であるから丁度4カ月になる。
止めようかと思うことも度々あったが、他人のブログを読んでみると更新がされていないとやはり寂しい思いがしてくるのでもう少し続けてみよう。
さて、NHKの「坂の上の雲」の題名であるが、これは当然司馬遼太郎の本のタイトルであり、明治維新を成し遂げた日本が次の新しい時代に向けて歩み始めた時に活躍した3人の若者の成長と活躍を描いた物語です。
ここでこの話は別にして、今回はこのタイトルを考えてみました。
坂の上の雲はすぐ手を伸ばせば届きそうに見えます。
この逆に下り坂の先の方に聳える山並みはとても高く、雄大に見えるのです。
この石岡の地に来た時に妻がここからの筑波山の姿が好きで、気分が落ち着くといった場所があります。
それは、石岡の城山中と言われた高台の横の道(石井の泉へ曲がる看板がある)から染谷地区を通り、栗田橋の方に続く道なのです。
確かに田圃と筑波山の組み合わせの景色が好いのですが、石岡市内側から355線バイパスの下をくぐるところが大きな下り坂です。
逆にここを自転車で中学生などが登るのは大変そうでかわいそうにもなります。
下り坂に入るとバイパス道の上に雄大な筑波山を見ることができ、その美しさにハットすることがあります。
しかし、この場所は電柱や、バイパスの通りに邪魔され、昔よりはかなり景観は損なわれているでしょう。
そうか、下り坂で見る筑波山は標高以上に高く見えることに気がついたのです。
これは当たり前なのですが、他にこのような場所はないのか・・・・。
今日、もう1か所見つけました。それが鬼越峠です。
石岡の昔話などを読んでいると、この鬼越峠の地名が良く出てきます。
しかし、私は今日までこの場所を良く知らなかったのです。
風土記の丘より八郷のフラワーパークの方に向かうきれいな舗装道路がその道だったとは・・・。
今回この道を通っていたら、次のような看板を見つけました。

ロータリークラブの方で作られた看板で、「鬼越峠の梅林」とあります。
確かに梅林らしき林が看板の少し手前にあるようです。これも始めて気がつきました。
ロータリークラブの方には感謝です。梅林も整備されれば観光名所になりますね。
鬼越峠の名前のいわれについてはいろいろな本に紹介されているので、ここでは詳しくは書きませんが、
茨城童子という大男(鬼)伝説があって、源頼光が鬼を退治に来ると知って逃げ出した時に越えた山で、その名前がついたとなっています。元々はこの峠を荷物を持って越えるのは大変であったことから「御荷越」から来ているとの解釈もあります。
さて、肝心の下り坂での筑波山ですが、この峠を下ると「茨城県畜産試験場」があります。
この試験場の手前から八郷片野地区と広がりとともに雄大に筑波山を見ることができます。
しかし、ここも木々に邪魔されなかなかベストアングルは撮れないですね。

写真は実際に見た感じとは大分違ってきますね。下り坂のイメージは写真で表せないことが判りました。
もう少し山がクッキリ見える朝方でもまた行ってみたいと思います。
まあ、きょうは何があったとか、単に写真を載せたりのものなら続きそうだが、テーマを探してそれをまた調べながら書くのにはどうしても時間がかかるのである。
今までにかなり多くのことを調べてはいるので、書きたいことはまだたくさんあるが、すべて中途半端な知識でしかない物が多い。
ブログを始めたのが8月11日であるから丁度4カ月になる。
止めようかと思うことも度々あったが、他人のブログを読んでみると更新がされていないとやはり寂しい思いがしてくるのでもう少し続けてみよう。
さて、NHKの「坂の上の雲」の題名であるが、これは当然司馬遼太郎の本のタイトルであり、明治維新を成し遂げた日本が次の新しい時代に向けて歩み始めた時に活躍した3人の若者の成長と活躍を描いた物語です。
ここでこの話は別にして、今回はこのタイトルを考えてみました。
坂の上の雲はすぐ手を伸ばせば届きそうに見えます。
この逆に下り坂の先の方に聳える山並みはとても高く、雄大に見えるのです。
この石岡の地に来た時に妻がここからの筑波山の姿が好きで、気分が落ち着くといった場所があります。
それは、石岡の城山中と言われた高台の横の道(石井の泉へ曲がる看板がある)から染谷地区を通り、栗田橋の方に続く道なのです。
確かに田圃と筑波山の組み合わせの景色が好いのですが、石岡市内側から355線バイパスの下をくぐるところが大きな下り坂です。
逆にここを自転車で中学生などが登るのは大変そうでかわいそうにもなります。
下り坂に入るとバイパス道の上に雄大な筑波山を見ることができ、その美しさにハットすることがあります。
しかし、この場所は電柱や、バイパスの通りに邪魔され、昔よりはかなり景観は損なわれているでしょう。
そうか、下り坂で見る筑波山は標高以上に高く見えることに気がついたのです。
これは当たり前なのですが、他にこのような場所はないのか・・・・。
今日、もう1か所見つけました。それが鬼越峠です。
石岡の昔話などを読んでいると、この鬼越峠の地名が良く出てきます。
しかし、私は今日までこの場所を良く知らなかったのです。
風土記の丘より八郷のフラワーパークの方に向かうきれいな舗装道路がその道だったとは・・・。
今回この道を通っていたら、次のような看板を見つけました。

ロータリークラブの方で作られた看板で、「鬼越峠の梅林」とあります。
確かに梅林らしき林が看板の少し手前にあるようです。これも始めて気がつきました。
ロータリークラブの方には感謝です。梅林も整備されれば観光名所になりますね。
鬼越峠の名前のいわれについてはいろいろな本に紹介されているので、ここでは詳しくは書きませんが、
茨城童子という大男(鬼)伝説があって、源頼光が鬼を退治に来ると知って逃げ出した時に越えた山で、その名前がついたとなっています。元々はこの峠を荷物を持って越えるのは大変であったことから「御荷越」から来ているとの解釈もあります。
さて、肝心の下り坂での筑波山ですが、この峠を下ると「茨城県畜産試験場」があります。
この試験場の手前から八郷片野地区と広がりとともに雄大に筑波山を見ることができます。
しかし、ここも木々に邪魔されなかなかベストアングルは撮れないですね。

写真は実際に見た感じとは大分違ってきますね。下り坂のイメージは写真で表せないことが判りました。
もう少し山がクッキリ見える朝方でもまた行ってみたいと思います。
雪の常陸国分寺
今日は一面の銀世界。
この地方では雪が積もるのは年に数回しかないが、古都の銀世界もいいものだ。
路地に雪が積もって、スノータイヤでない私の車ではあぶないので家にじっとしていた。
昨年も2月13日に同じような雪景色を経験したのも休日だったと思う。
当時はまだブログをやっていなかったので、この際だから1年前の写真を公開しておきます。
<国分寺>

<常陸国分寺中門跡:国分寺入口>

<都々一坊扇歌堂:国分寺境内>

<旧千手院山門:国分寺境内>

<国分尼寺跡>

写真を見ると昨年よりも今回の方が雪は積もっています。
この地方では雪が積もるのは年に数回しかないが、古都の銀世界もいいものだ。
路地に雪が積もって、スノータイヤでない私の車ではあぶないので家にじっとしていた。
昨年も2月13日に同じような雪景色を経験したのも休日だったと思う。
当時はまだブログをやっていなかったので、この際だから1年前の写真を公開しておきます。
<国分寺>

<常陸国分寺中門跡:国分寺入口>

<都々一坊扇歌堂:国分寺境内>

<旧千手院山門:国分寺境内>

<国分尼寺跡>

写真を見ると昨年よりも今回の方が雪は積もっています。
石岡ひな巡り
石岡の街中でも毎年この時期に「ひな巡り」を実施している。真壁はかなり知れ渡ってきたが、ここ「石岡のひな巡り」毎年実施している割にあまり知られていない。石岡の人は遠慮しがちなのか?
市内の商店会を中心に100店舗ほどが参加し、市民から寄付してもらった雛人形や工夫を凝らした雛も飾られている。期間は今日(2/13)から3月3日までだ。
毎週土日の甘酒サービスや、スタンプラリー・クイズラリーなども行われる。
是非一度見に来てください。

<2009年まちかど情報センターにて撮影>

<2010年まちかど情報センターにて撮影>

<2010年香丸町更生女性の会にて撮影>
ちびっこ広場、みんなの広場などの活動を行なっています。

ひな巡りの期間に野菜やおもちなどの直売も行なっています。

更生女性の会の中に飾られているこのひな人形は私のイギリスに嫁いだ娘の初節句の時に浅草橋の久月さんで買ったものです。飾って喜んでもらえたらと寄付させていただきました。

ちびっこ広場に置かれた童話などの本や本棚、テーブルなども寄付させていただきました。(写真のテーブルはちがいます。)
こうして、使ってもらえれば嬉しいですね。我が家の子供は皆成人しましたので、これからは地域で活躍してくれれば本当にうれしい事です。
ここで売られている野菜などの直売も私の女房がやっているので、皆さん買ってくださいね。
(売店には別のおばちゃんがいると思いますが・・・)
市内の商店会を中心に100店舗ほどが参加し、市民から寄付してもらった雛人形や工夫を凝らした雛も飾られている。期間は今日(2/13)から3月3日までだ。
毎週土日の甘酒サービスや、スタンプラリー・クイズラリーなども行われる。
是非一度見に来てください。

<2009年まちかど情報センターにて撮影>

<2010年まちかど情報センターにて撮影>

<2010年香丸町更生女性の会にて撮影>
ちびっこ広場、みんなの広場などの活動を行なっています。

ひな巡りの期間に野菜やおもちなどの直売も行なっています。

更生女性の会の中に飾られているこのひな人形は私のイギリスに嫁いだ娘の初節句の時に浅草橋の久月さんで買ったものです。飾って喜んでもらえたらと寄付させていただきました。

ちびっこ広場に置かれた童話などの本や本棚、テーブルなども寄付させていただきました。(写真のテーブルはちがいます。)
こうして、使ってもらえれば嬉しいですね。我が家の子供は皆成人しましたので、これからは地域で活躍してくれれば本当にうれしい事です。
ここで売られている野菜などの直売も私の女房がやっているので、皆さん買ってくださいね。
(売店には別のおばちゃんがいると思いますが・・・)
石岡ひな巡り(2)
今日は一日日が照らずに寒い日曜日になりましたが、石岡のひな巡りも3月3日までの週末には色々とイベントも用意して観光客も目立つようになってきました。
なかなか真壁のようにはまだいっていないのですが、確実に去年よりは盛り上がってきました。
今日は少し午前中に見て回りました。
各店で甘酒サービスなどをやっています。駅前の観光案内所でスタンプラリーなどの案内をもらってお出かけください。協賛店101店舗の地図が載っています。

香丸町では空き駐車場で「餅つき」に石岡ばやしの笛・太鼓で祭りを盛り上げていました。

今日は少し寒いですね。天気が良ければよかったのですが。
去年まではこちらの香丸町にはあまり人出がなかったように思います。

前回のブログで書いた「更生女性の会」(みんなの広場)の中の雛人形です。場所は上の太鼓などのテントの隣りです。

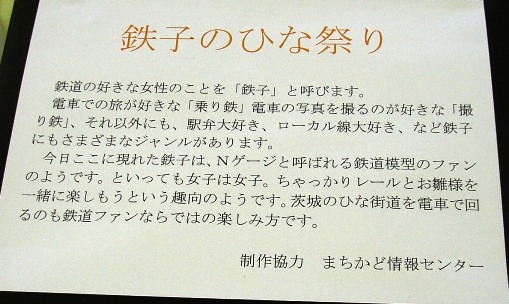
雛人形と鉄道模型を組み合わせていました。鉄道は実際に動かしていますので、子供たちは嬉しそうに見ていました。

まちかど情報センターの今年の雛人形のテーマは「かぐや姫月に還る」だったかな?
頑張って街を盛り上げましょう。
さて、今テレビで横浜国際マラソンを見ていたら「間門(まかど)折り返し」の案内で「昔ドイツ系の「間門ホテル」があった」と説明されていた。
ここ横浜市本牧の間門は私が小学校に最初に入った学校で1年の終わりに転向したが、懐かしい。
明治期のホテルのようだが、大変モダンな建物のようです。
石岡も昭和4年の大火の前は古くからの街並みが残り、また昭和の初期頃までは大変モダンな建物が建っていた。
現在の「まちかど情報センター」のところにあった「篠塚本店」などは大変シンボル的な建物で解体せずに、現在残していればと悔やまれます。
なかなか真壁のようにはまだいっていないのですが、確実に去年よりは盛り上がってきました。
今日は少し午前中に見て回りました。
各店で甘酒サービスなどをやっています。駅前の観光案内所でスタンプラリーなどの案内をもらってお出かけください。協賛店101店舗の地図が載っています。

香丸町では空き駐車場で「餅つき」に石岡ばやしの笛・太鼓で祭りを盛り上げていました。

今日は少し寒いですね。天気が良ければよかったのですが。
去年まではこちらの香丸町にはあまり人出がなかったように思います。

前回のブログで書いた「更生女性の会」(みんなの広場)の中の雛人形です。場所は上の太鼓などのテントの隣りです。

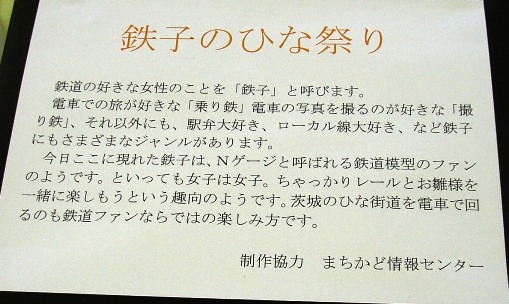
雛人形と鉄道模型を組み合わせていました。鉄道は実際に動かしていますので、子供たちは嬉しそうに見ていました。

まちかど情報センターの今年の雛人形のテーマは「かぐや姫月に還る」だったかな?
頑張って街を盛り上げましょう。
さて、今テレビで横浜国際マラソンを見ていたら「間門(まかど)折り返し」の案内で「昔ドイツ系の「間門ホテル」があった」と説明されていた。
ここ横浜市本牧の間門は私が小学校に最初に入った学校で1年の終わりに転向したが、懐かしい。
明治期のホテルのようだが、大変モダンな建物のようです。
石岡も昭和4年の大火の前は古くからの街並みが残り、また昭和の初期頃までは大変モダンな建物が建っていた。
現在の「まちかど情報センター」のところにあった「篠塚本店」などは大変シンボル的な建物で解体せずに、現在残していればと悔やまれます。
万葉の森
万葉集には筑波山について非常に多くの歌が載っている。これはこの山が、昔からの信仰の山であり、富士山と同じような形の良い山で、比較的登りやすかったせいもあるとも思いますが、恋歌も多く、多くの種類の木々・草花も豊富な場所でした。
全国に万葉植物園などと言われる施設ができており、何故この地には無いのだろうか?などと考えたこともありました。
しかし、旧八郷地区に「万葉の森」という公園ができていることを知りませんでした。
先日筑波山の風返峠から国民宿舎「つくばね」の方に下ったところに見つけました。

この公園は八郷ライオンズクラブが造ったもので、「ライオン広場」などと書かれています。
広場に色々な木々を植え、万葉集の歌の立札がそれぞれつけられています。

まだ先日降った雪が残っている時でしたので、多くの木には葉や花がない寂しい時でした。
このためか、一人も来ている人はいません。
今度は、花や木々が美しい時にまた来て見ようと思います。

石岡のこの場所は筑波山に車で登るには比較的緩やかで走りやすいのですが、あまり車は通りません。
そのため、なかなか知られないのかもしれませんね。
きれいに整備されていますので、近くを通られる時には寄ってみてください。「つくばね」の少し上です。
記念のコンサートなども開かれたようです。写真の石碑が置かれていました。

東京の国分寺の境内には「万葉植物園」という公園がひっそりとあります。
昔近くに住んでいたので何回か訪れたことがあります。
こちらの公園には水草や、シダ類なども多く、変わった草花が多いので、短歌をされる方などが良く訪れるようです。
ご住職が13年間かかって全国から集めたり、栽培して植物園としてを解放したといいます。
全国に万葉植物園などと言われる施設ができており、何故この地には無いのだろうか?などと考えたこともありました。
しかし、旧八郷地区に「万葉の森」という公園ができていることを知りませんでした。
先日筑波山の風返峠から国民宿舎「つくばね」の方に下ったところに見つけました。

この公園は八郷ライオンズクラブが造ったもので、「ライオン広場」などと書かれています。
広場に色々な木々を植え、万葉集の歌の立札がそれぞれつけられています。

まだ先日降った雪が残っている時でしたので、多くの木には葉や花がない寂しい時でした。
このためか、一人も来ている人はいません。
今度は、花や木々が美しい時にまた来て見ようと思います。

石岡のこの場所は筑波山に車で登るには比較的緩やかで走りやすいのですが、あまり車は通りません。
そのため、なかなか知られないのかもしれませんね。
きれいに整備されていますので、近くを通られる時には寄ってみてください。「つくばね」の少し上です。
記念のコンサートなども開かれたようです。写真の石碑が置かれていました。

東京の国分寺の境内には「万葉植物園」という公園がひっそりとあります。
昔近くに住んでいたので何回か訪れたことがあります。
こちらの公園には水草や、シダ類なども多く、変わった草花が多いので、短歌をされる方などが良く訪れるようです。
ご住職が13年間かかって全国から集めたり、栽培して植物園としてを解放したといいます。
茨城県産野菜
4月4日 3回目の投稿です。
このブログも石岡の情報発信を地震後しばらく続けていたが、少し落ち着いてきたので、この情報を見に来る人は少なくなったと思う。
市のホームページでも少し情報は載るようになった。
また、まちかど情報センターのHPでも情報を載せているので、別な情報を少しUPします。
・県のホームページに県内の野菜の放射線量の測定結果を載せています。
また、安全であった農産物の測定データはこちらに載っています。
これは参考になります。
今日の午後、「枝野幸男官房長官は、都道府県単位で実施してきた農産物の出荷制限について、市町村単位で設定、解除できるように改める方針を明らかにした」のニュースも飛び込んできました。
3回連続で規定値を下回れば解除可能とも言っています。
これからも数値をチェックしていきたいと思います。
このブログも石岡の情報発信を地震後しばらく続けていたが、少し落ち着いてきたので、この情報を見に来る人は少なくなったと思う。
市のホームページでも少し情報は載るようになった。
また、まちかど情報センターのHPでも情報を載せているので、別な情報を少しUPします。
・県のホームページに県内の野菜の放射線量の測定結果を載せています。
また、安全であった農産物の測定データはこちらに載っています。
これは参考になります。
今日の午後、「枝野幸男官房長官は、都道府県単位で実施してきた農産物の出荷制限について、市町村単位で設定、解除できるように改める方針を明らかにした」のニュースも飛び込んできました。
3回連続で規定値を下回れば解除可能とも言っています。
これからも数値をチェックしていきたいと思います。
いつもの春
今日も一日暖かでした。
震災後色々な情報などを発信してきましたが、気分はあまり明るくなりませんね。
今日は天気も良く、桜も一気に満開になりました。一部ではひらひら舞ってきています。
朝、車で出勤途中に、学校も始まり初々しい女子高校生の自転車の列が前を横切り、いつもの4月が始まっていました。
こちらの気分が晴れていなかったのであまり気がついていなかったのでしょう。
横断歩道の信号で、いつもの女生徒が携帯を見ながら何かしています。
信号が変わっても渡らないで携帯をじっと見て何かしています。これもいつもと同じ情景です。
ふと脇の原を見るとタンポポの花が一面を黄色く染めていました。
遅咲きの紅梅の古木にきれいな花が忘れてくれるなとまだささやいています。
空の高いところから鳥のさえずりが聞こえます。きっと雲雀ですね。
でも上を見上げたら黒いカラスが二羽、北から南へ飛んでいく姿が映りました。
やはり、いつもの春はいいですね。
原発も大変ですが、これからは何とかなると楽観主義で行きます。
ドリス・デイの歌ったケセラセラ"whatever will be, will be"を思い出しました。「きっとなるようになる」ですね。
でも、この「Will」には自分の意思を感じますので、他人任せではだめですね。
不安が無いわけではありませんが、不安に思って何かを発信しても伝わるのも更に不安な思いを増幅させるだけでしょうから・・・。
少しの心の準備をしたら、気分を変えて前に進むしかありません。
そういえば誕生日が過ぎてしまいました。何回目? それは言えません。
年を数えることはもうやめてしまいたいと最近は思うようになっています。
震災後色々な情報などを発信してきましたが、気分はあまり明るくなりませんね。
今日は天気も良く、桜も一気に満開になりました。一部ではひらひら舞ってきています。
朝、車で出勤途中に、学校も始まり初々しい女子高校生の自転車の列が前を横切り、いつもの4月が始まっていました。
こちらの気分が晴れていなかったのであまり気がついていなかったのでしょう。
横断歩道の信号で、いつもの女生徒が携帯を見ながら何かしています。
信号が変わっても渡らないで携帯をじっと見て何かしています。これもいつもと同じ情景です。
ふと脇の原を見るとタンポポの花が一面を黄色く染めていました。
遅咲きの紅梅の古木にきれいな花が忘れてくれるなとまだささやいています。
空の高いところから鳥のさえずりが聞こえます。きっと雲雀ですね。
でも上を見上げたら黒いカラスが二羽、北から南へ飛んでいく姿が映りました。
やはり、いつもの春はいいですね。
原発も大変ですが、これからは何とかなると楽観主義で行きます。
ドリス・デイの歌ったケセラセラ"whatever will be, will be"を思い出しました。「きっとなるようになる」ですね。
でも、この「Will」には自分の意思を感じますので、他人任せではだめですね。
不安が無いわけではありませんが、不安に思って何かを発信しても伝わるのも更に不安な思いを増幅させるだけでしょうから・・・。
少しの心の準備をしたら、気分を変えて前に進むしかありません。
そういえば誕生日が過ぎてしまいました。何回目? それは言えません。
年を数えることはもうやめてしまいたいと最近は思うようになっています。
霞ヶ浦総合公園
NHKテレビで土浦の霞ヶ浦総合公園のチューリップが紹介されていたので行ってみました。
ここは国民宿舎「水郷」があり、昔子供を連れて公園に遊びに来たり、野外バーベキューをやったりしましたが、最近きていなかったのです。
昔に比べ、公園はきれいに整備され、日帰り温泉施設「霞浦の湯(かほのゆ)」があります。しかし、「北海道二股温泉の石灰華原石を利用した人工温泉」となっていました。
国民宿舎はこの地震でまだ休業中。温泉施設だけが4月からオープンしていました。
また風車も土台部分が被害にあい、展望台などには入れないようです。
また、福島からの避難民を水郷体育館で受け入れておりましたが、4月10日に閉鎖となったようです。
避難者は親戚や市で準備したホテルなどに移られたようです。

シンボルである風車はオランダの風車をまねたもので、風車は動きません。内部に水を循環してきれいにする装置が取り付けられており、霞ケ浦の水質浄化が真の目的です。

チューリップはいつから始まったのでしょうか。発想はオランダの風車にはチューリップという単純なものですが、きれいに咲いていました。

子供たちも学校が始まっていると思いますが、宿題でしょうか「絵日記」のようなものを一生懸命書いていました。
先ほどいわき市の「スパリゾートハワイアンズ」(昔のハワイアンセンター)が被害にあい、再建も大変で、原発も近いので、ここでの営業をしばらくやめて、昔やった地方巡業をスタートさせると言っていました。頑張れ! フラガールズ。
ここは国民宿舎「水郷」があり、昔子供を連れて公園に遊びに来たり、野外バーベキューをやったりしましたが、最近きていなかったのです。
昔に比べ、公園はきれいに整備され、日帰り温泉施設「霞浦の湯(かほのゆ)」があります。しかし、「北海道二股温泉の石灰華原石を利用した人工温泉」となっていました。
国民宿舎はこの地震でまだ休業中。温泉施設だけが4月からオープンしていました。
また風車も土台部分が被害にあい、展望台などには入れないようです。
また、福島からの避難民を水郷体育館で受け入れておりましたが、4月10日に閉鎖となったようです。
避難者は親戚や市で準備したホテルなどに移られたようです。

シンボルである風車はオランダの風車をまねたもので、風車は動きません。内部に水を循環してきれいにする装置が取り付けられており、霞ケ浦の水質浄化が真の目的です。

チューリップはいつから始まったのでしょうか。発想はオランダの風車にはチューリップという単純なものですが、きれいに咲いていました。

子供たちも学校が始まっていると思いますが、宿題でしょうか「絵日記」のようなものを一生懸命書いていました。
先ほどいわき市の「スパリゾートハワイアンズ」(昔のハワイアンセンター)が被害にあい、再建も大変で、原発も近いので、ここでの営業をしばらくやめて、昔やった地方巡業をスタートさせると言っていました。頑張れ! フラガールズ。
日没と筑波山
4月29日です。ゴールデンウィークが始まったようですが、私は出勤です、
またこの連休は後半3日間も夏に電力を減らすために振替で出勤です。
それにしてもテレビ局は放送時間の短縮などは言い出さないですね。
昨日夕方6時過ぎに撮った写真をUPしておきます。
太陽がもっとも強いのは夏至の頃で、6月20日頃ですが、日が沈む方向が春分の日に真西であったものが徐々に北の方向にズレてきて、夏至の時にもっとも北になり23.4度地軸の傾き分だけズレるのです。
石岡から見ると、夏至には筑波山より少し北側の加波山寄りに沈みます。
筑波山に沈むのが丁度今頃から5月初めの頃になります。
今日は夕方に少し雲が出て太陽が少し隠れてしまったが、筑波山の陰影が何ともいえずきれいでした。

田圃にも水が張られ始めたので、山のシルエットもまた不思議です。

この写真は恋瀬川にかかる粟田橋の近くから撮影しましたが、山頂より少しまだ左側に太陽沈んでいました。
太陽の沈む地を昔の人は死んだ人の行く世界(黄泉国:よみのくに)と考えていたようです。
伊勢から日が昇ると熊野方面に沈みます。鹿島に日が昇ると筑波山に沈みます。
日光に徳川家康の御所をつくったのも、もしかしたら、日光が水戸から見て夏至の時に太陽が沈む方向になるのと関係があるのかもしれません。

(同じアングルで翌朝撮りました。比較のために追加します。)
レイラインなども考えてみるのも、今年は面白いかもしれません。
東京もネオンが減り、夜の明かりを少し落として月明かりがきれだといいますから・・・。
またこの連休は後半3日間も夏に電力を減らすために振替で出勤です。
それにしてもテレビ局は放送時間の短縮などは言い出さないですね。
昨日夕方6時過ぎに撮った写真をUPしておきます。
太陽がもっとも強いのは夏至の頃で、6月20日頃ですが、日が沈む方向が春分の日に真西であったものが徐々に北の方向にズレてきて、夏至の時にもっとも北になり23.4度地軸の傾き分だけズレるのです。
石岡から見ると、夏至には筑波山より少し北側の加波山寄りに沈みます。
筑波山に沈むのが丁度今頃から5月初めの頃になります。
今日は夕方に少し雲が出て太陽が少し隠れてしまったが、筑波山の陰影が何ともいえずきれいでした。

田圃にも水が張られ始めたので、山のシルエットもまた不思議です。

この写真は恋瀬川にかかる粟田橋の近くから撮影しましたが、山頂より少しまだ左側に太陽沈んでいました。
太陽の沈む地を昔の人は死んだ人の行く世界(黄泉国:よみのくに)と考えていたようです。
伊勢から日が昇ると熊野方面に沈みます。鹿島に日が昇ると筑波山に沈みます。
日光に徳川家康の御所をつくったのも、もしかしたら、日光が水戸から見て夏至の時に太陽が沈む方向になるのと関係があるのかもしれません。

(同じアングルで翌朝撮りました。比較のために追加します。)
レイラインなども考えてみるのも、今年は面白いかもしれません。
東京もネオンが減り、夜の明かりを少し落として月明かりがきれだといいますから・・・。
菜の花と栗畑
今は、何処へ行っても花が多いですね。
道の両側に菜の花が咲き乱れていると黄色の絨毯のように見えます。
茨城県は、栗の生産では日本一ですが、その中でも、ここかすみがうら市(旧千代田町)の栗は有名です。
この栗畑の中に一面の菜の花が植えられているところがあります。
少し目に付くところは多いのですが、ここは一面が菜の花です。
(A) かすみがうら市の四万騎(しまき)農園の菜の花です。菜の花ばかりで栗の木が目立ちません。
しかし、ここの栗は有名でジャムに加工して「マロンジャム」として銀座などに卸してもいます。
菜の花が良い肥料になるのですね。

四万騎農園さんの入口です。敷地の中に石蔵があり、時々コンサートなどが行なわれています。

通りからすぐ菜の花畑が広がります。

(B) 同じくかすみがうら市の笄崎(こうがいさき)のバス停近くの栗畑です。

通りからは生け垣があり菜の花が目立たないのですが、きれいな畑です。

こちらの栗の木はまだ若木のようです。
さて、有機栽培の栗に菜の花の堆肥がよいのでしょが、こちらのサイトは一応歴史のテーマを主に取り扱っていますので、この「四万騎(しまき)」と「笄崎(こうがいさき)」の地名について説明しましょう。
「四万騎」の名前の由来は、八幡太郎義家(源義家)が陸奥守に任じられて、後三年の役(1083年~)で奥州へ平定に行くのですが、後からの作りごとか、余程宣伝がうまかったのか、「義家参戦」とききつけて、一行の行進に続々とまわりから仲間が集まってきました。
このかすみがうら市の辺りでは兵は四万になり、この辺りは広い草原があるため、ここで馬術の稽古をしたといわれています。そのため「四万騎」と名がついたそうです。
また、石岡では更に増えて五万になったということで「五万堀」という地名が残り、食事をした池には「生板池」(生板はまないたのこと)などの地名も残っています。
さて、もう一方の笄崎(こうがいさき)ですが、どこにもまだ書いたものを見ていませんが、前にブログで書いたように笄(こうがい)が流れ着いた場所をさすと思われますので、ヤマトタケルが東京湾を渡る時に波を静めるために海に身を沈めた弟橘姫の髪を止めていた笄が霞ケ浦を流れて、この辺りまで川をさかのぼってきたなどという話が伝わっているのではないかなどと想像しています。
行方市羽生にある「橘郷造神社」はこの弟橘姫をまつった神社です。
また羽生の地名も弟橘姫の笄(こうがい)が霞ケ浦の岸に流されたものが、「羽を生やして飛んできた」とか、「鳥が群がって運んできた」などと言われているようです。
道の両側に菜の花が咲き乱れていると黄色の絨毯のように見えます。
茨城県は、栗の生産では日本一ですが、その中でも、ここかすみがうら市(旧千代田町)の栗は有名です。
この栗畑の中に一面の菜の花が植えられているところがあります。
少し目に付くところは多いのですが、ここは一面が菜の花です。
(A) かすみがうら市の四万騎(しまき)農園の菜の花です。菜の花ばかりで栗の木が目立ちません。
しかし、ここの栗は有名でジャムに加工して「マロンジャム」として銀座などに卸してもいます。
菜の花が良い肥料になるのですね。

四万騎農園さんの入口です。敷地の中に石蔵があり、時々コンサートなどが行なわれています。

通りからすぐ菜の花畑が広がります。

(B) 同じくかすみがうら市の笄崎(こうがいさき)のバス停近くの栗畑です。

通りからは生け垣があり菜の花が目立たないのですが、きれいな畑です。

こちらの栗の木はまだ若木のようです。
さて、有機栽培の栗に菜の花の堆肥がよいのでしょが、こちらのサイトは一応歴史のテーマを主に取り扱っていますので、この「四万騎(しまき)」と「笄崎(こうがいさき)」の地名について説明しましょう。
「四万騎」の名前の由来は、八幡太郎義家(源義家)が陸奥守に任じられて、後三年の役(1083年~)で奥州へ平定に行くのですが、後からの作りごとか、余程宣伝がうまかったのか、「義家参戦」とききつけて、一行の行進に続々とまわりから仲間が集まってきました。
このかすみがうら市の辺りでは兵は四万になり、この辺りは広い草原があるため、ここで馬術の稽古をしたといわれています。そのため「四万騎」と名がついたそうです。
また、石岡では更に増えて五万になったということで「五万堀」という地名が残り、食事をした池には「生板池」(生板はまないたのこと)などの地名も残っています。
さて、もう一方の笄崎(こうがいさき)ですが、どこにもまだ書いたものを見ていませんが、前にブログで書いたように笄(こうがい)が流れ着いた場所をさすと思われますので、ヤマトタケルが東京湾を渡る時に波を静めるために海に身を沈めた弟橘姫の髪を止めていた笄が霞ケ浦を流れて、この辺りまで川をさかのぼってきたなどという話が伝わっているのではないかなどと想像しています。
行方市羽生にある「橘郷造神社」はこの弟橘姫をまつった神社です。
また羽生の地名も弟橘姫の笄(こうがい)が霞ケ浦の岸に流されたものが、「羽を生やして飛んできた」とか、「鳥が群がって運んできた」などと言われているようです。


