言うまいと思え・・・こう暑くては、身体が持ちません・・・
せっかく作った梅干しを何かと使っています。
効用はいろいろとあるようですが、夏場に良い効用をネットで調べてみました。
梅干はアルカリ性の陽性の食品で、クエン酸の働きは、新陳代謝エネルギー代謝が活発になり、
疲労物質の乳酸を燃焼させ、身体の老廃物を身体から排除します。ゆえに疲労防止、疲労回復に効果があります。
梅に血液をサラサラにする成分「ムメフラール」が含まれていることが解っています。
ムメフラールは、熱を加えることにより、梅に含まれる糖分とクエン酸が結びつき、生まれます。
梅干に含まれる塩は、胃酸の働きを助け、食欲を増進して、血液に力を与えてくれます。
血液は、昔から血潮といって塩は不可欠なものです。
梅干は日本古来の食品で「メードインジャパン」で世界に誇れる食品であると思います。
(昨今、鰹節が世界に認められつつあるようですが。)
昔から『朝の梅干は一日の難のがれ』というように梅干には様々な効用がたくさんあります。 とありました。
特にこの夏は発汗とともに失われる塩分を補うのにも、熱中症予防にもよいとされているのは
周知のとおりです。
私は普通に梅干しは食事に取り入れていますが、夫は梅干しが苦手です。
大抵の食品は、特にそれが必要な人には敬遠される傾向があるような気もします。
高齢になると塩分を制限される人も多いかと思いますが、塩分量の少ないものや調理方法などうまく工夫して
やはりこの夏、梅干しは無くてはならないものと私は考えています。
青魚を煮るようなときは梅干しはよく使いますが(生臭さを和らげるため)、こう暑過ぎる夏にはもう、何にでも
使ってしまえとばかり、野菜の煮物やご飯を炊く時にも使います。
野菜の煮物にも ご飯を炊くときも


晩に炊いたご飯は、そのままお釜に残しておくと翌朝には、やや蒸れ匂いがしてしまう暑さですが
梅干しを入れて炊くと、まぁいいようですが。(炊いたご飯は残れば冷ましてその日のうちに冷蔵庫へが安全です。)
味付けを薄く料理するには、旨みの成分を感じられなければ美味しく感じられないと言われています。
調味料の中にはいいか悪いか分りませんが長年、だし昆布を漬けて使っています。

醤油 みりん、酒
梅干しを加えている分、料理の塩分味付けは気持ちやや薄口に。(大したことは無いと思います)
酒は調理酒は使っていません(塩分が入っているからです)合成清酒を使っています。
味醂もみりん風調味料は今は使っていません。本みりんを使っています。(糖の成分が違う)
薄口料理を作るためには旨みになるものを加えているという、私勝手の昔からの考えからですが
気休めと、微妙な違いでしかないかもしれませんが。
玉ねぎはただスライスしてさっと水にさらし(本当はさらさない方がよいらしいが)大きな密封容器に入れて
冷蔵庫に常備して、サラダのように朝晩に食しています。(これは夫の大好物。)
梅とえごま油のドレッシングを掛けています。
玉ねぎは血液をサラサラにするといわれて赤ワインや酢につけたものを作っていましたが、どちらも長続きせず
ただのスライスで落ち着きました。
シンプルでないと続かないのですね。
こう書いていくと健康オタクのようですが、そんな風でもありません。
先日の町内会のお祭りの役員の仕事時に、熱中症予防にと冷えたポカリスエットと梅干しを差し入れしましたが
どちらも「生き返る~~」と、言ってもらえました。
日本人は昨今の甘い梅干しよりやはり、梅干しは酸っぱくなくっちゃ。
そう言えばお酢も優れた食品で、使い方をもっと学びたいところですね。
ダラダラと書いて暑苦しい・・・

晩御飯
牛肉と野菜のソテー モロヘイヤのお浸し エリンギスープ

 (25センチ×35センチ)
(25センチ×35センチ)


 晩御飯
晩御飯
 (25センチ×35センチ)
(25センチ×35センチ)
 晩御飯
晩御飯  晩御飯
晩御飯




 晩御飯
晩御飯  晩御飯
晩御飯















 晩御飯
晩御飯  晩御飯
晩御飯



 晩御飯
晩御飯  晩御飯
晩御飯


 晩御飯
晩御飯








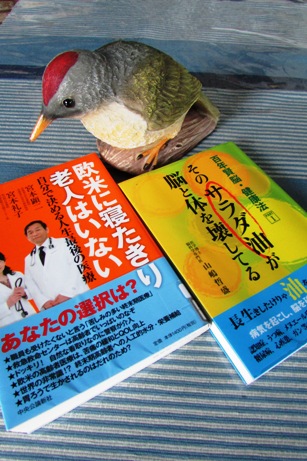



 醤油 みりん、酒
醤油 みりん、酒 晩御飯
晩御飯


 晩御飯
晩御飯
