Izalco Chrono Mod
経緯
以前ブログで書いた我が家のTTバイク、IzalcoChrono。
元々TTヘルメットから生えてきたものだったが、実際に自分で「TTバイクとして」晴れの舞台で登場したことは今まで無い。いわゆる盆栽バイクになってなりかけている。
たまに思い立って乗ってみるものの、尋常じゃない縦剛性からくる乗り心地の悪さと前傾のきつさに少し萎えてしまう、というのを繰り返している。
そもそも自分が「TT/トライアスロンって感じのカテゴリに載っていたものだから、トライアスロンの長距離バイクパートを楽に且つ速く走れるんだろうなぁ」と淡い期待をしていたのが間違っていた。TT/トライアスロンではなく実はTT専用であったからだ(過去記事参照)。
そんなこんなで、TTに出たいというJBCF戦士に貸し出している時を除き、乗るより眺める時間のほうが長いバイクではあった。しかし実はこのバイク、スタイルはお気に入りなんだがカラーリングは今ひとつストライクではなかった。なかったのだ。どうせ眺めることが多いバイクなら、見た目にこだわりたいじゃん?
じゃあどうするか。
オサイフが許す範囲でホイールを多少変えたくらいでは足りない。
かと言ってバイク
を買い換えるのはオサイフ的に不可。
を買い換えるのはオサイフ的に不可。
うーん、カラーリングが気に入らないなら、カラーリングだけ変えてしまえばいいじゃない!
ということでフレームを全塗装することに決めた。
これが今年の春頃の話。
デザイン
フレームの塗装をするということはフレームセット単体の状態にしないといけないわけだが、夏にある鈴鹿のTTで某高校生が駆る予定だったことから、鈴鹿が終わって手元に帰ってきてから全バラしようと計画。
貸し出している間に、デザインを考える。
現状のフレームのカラーはこの通り。
黒基調で赤と白でグラフィックが入った、カーボンフレームとしてはまぁ良くも悪くもベタなデザイン。
黒基調で赤と白でグラフィックが入った、カーボンフレームとしてはまぁ良くも悪くもベタなデザイン。
カラーのラインナップが少ないモデルに多いやつだ。
個人的にはところどころ入るグラデーションにデザインの古さを感じてしまうし、オリジナリティが少ないので今ひとつ好みではなかったのだ。
ということでオリジナリティを出そうとすると、一番最初に出てくるアイディアとしては「カラフルにする」だ。
しかし、フレームカラーを派手な多色でカラーリングするとバーテープその他小物の色柄がかなり絞られてしまう。
しかし、フレームカラーを派手な多色でカラーリングするとバーテープその他小物の色柄がかなり絞られてしまう。
また、フレームにマッチするバーテープを探そうにも、ハンドルに巻いて合わせてみないとわからず、バーテープが店頭に陳列された状態でフレームと比較しても色味がマッチするかどうかの判断が難しい。
さらに、乗るときのジャージもカラフルなものが多いので、フレームまで多色だとちんどん屋だ(表現が古い)。一応言っておくが、他の2台のロードバイクのバーテープは蛍光黄色と蛍光ピンクなことから察してもらえるが、ちんどん屋カラーは嫌いではない。しかし、そうでないバイクに乗りたいときもあるのだ。
なのでこのフレームは基本的にはモノトーン寄りのデザインにしたい。
なのでこのフレームは基本的にはモノトーン寄りのデザインにしたい。
ここで少し考えてみたが、カーボンフレームはソリッドカラーかカーボン地が多く特に黒が多い気がする。一
方でメタリック系や、カーキなどの地味なソリッドカラーはラインナップとして少ない。
方でメタリック系や、カーキなどの地味なソリッドカラーはラインナップとして少ない。
メタリックやパールが少ないのは軽量化競争で多層の塗膜が必要なカラーは淘汰されていっているのか。またあるいはロードバイク乗りからの人気を反映したものなのかどうなのかわからないが、逆にこのあたりだと人とかぶったりということを考えずに済む。
ベースとしては1-3色程度の塗り分けで、ディティールやワンポイントはカッティングシートで対応することにしよう。塗装より耐久性は劣るけど、飽きたら変えられるしね。
本当は近頃流行りのメッキ調カラーがいいと思っていたが、どうもこれを綺麗に塗ろうとするとわりと大掛かりな設備が必要らしく、そもそもスプレーではなくディッピング塗装になるらしいので残念ながら今回は見送り。メッキカラーは比較的塗膜が薄くても軽量に仕上がるのかな?
鈴鹿が終わり帰ってきたバイクを早速バラしにかかる。バラすのはネジを外すだけの簡単なお仕事だけど、再組付を自分でするつもりだったのでそこを考えて、部分部分を撮影しながら作業を進める。
工程
パーツ取り外し・塗装プラン
全バラ終了。といっても旧型のパイオニアパワーメータの角度検出ユニットは、取り外すと再組付の時に校正がめんどくさそうなので取り付けたまま塗装することにした。ワイヤーは抜いたら通すのめちゃめんどくさそう…と思っていたが杞憂だった。
足付け
サンドペーパーで研磨していく。既にある傷は本当はパテ埋めとかしたほうが綺麗に仕上がるんだろうけど、そこまでは求めないことにした。あと現状のカラーリングをすべて削るのにはまたかなりの労力が必要だし塗料の隠蔽性も高いのでそこまではしない。
プライマー塗布
塗料の密着性を向上させる工程。
1色目
シートチューブとフォークなどの内側はブラックアウト。色名は4T5-セーブルマイカメタリック。黒系メタリックでレクサスのLS600hとかの塗装色!(だからといって塗装単価が高いわけではない)
2色目
一番塗装面積の大きいトップチューブ、ダウンチューブはプラチナ系に近いシルバー、LX1Z-BAHIA BEIGE
Metallic。Audi Q7の塗装色!(だからといって略)
Metallic。Audi Q7の塗装色!(だからといって略)
塗ってみると思ったより黄みが強かった。もう少しシルバーよりにすればよかったかな…
3色目
シートステー、チェーンステーにはJW0-ミレニアムジェイドメタリック。やや緑がかったシルバーで、R34GTR
スペックM ニュル専用特別塗装色!(だか略)
スペックM ニュル専用特別塗装色!(だか略)
単色塗装ならこのカラーにしてたかも。なんてったってGTRだし!
クリアコート、研磨
写真で見るとピンとこないが実際に見たほうが色合いが良く見えるのは、良くも悪くもメタリックの特徴か。しかしやはり20mm角しかない色見本と実際に塗った印象ではかなり違い、調色の難しさを知った。再組付
当初懸念していたワイヤー内装は、過去に某高校生がライナーを通しておいてくれたお陰か、すんなりいった。
当初懸念していたワイヤー内装は、過去に某高校生がライナーを通しておいてくれたお陰か、すんなりいった。
よく考えるとBBとヘッド周り以外の組付を通してやったのは今回が初めてだった。
しかしコンポに驚くほど統一感がなく、調整が正攻法でいかないところもあったが、どうにかなった。(というかそもそも正攻法がちゃんと頭に入っているわけでもない)
シェイクダウン
しかしまぁ乗ってはみたものの相変わらずガチガチのフレームだし重い。もとからそこそこ重かったが、塗装で+100g程上乗せ。エアロバーとエアポンプを付けたRXRSよりさらに300g程重い。
さらにO'symetricでBCD130なのでインナーは42T。タダでさえ人間が登り向きでない上にこのバイクなので登坂は全力拒否だ。
ハンドルも以前外しっぱなしにしていた380mm幅はもがき難い。
落差はレース用にしているSempreよりもさらに2cmほど低い。これを乗りこなせるようになれば空力特性面で有利になるだろうけど、これは盆栽バイクというより試されるバイクに仕上がってしまった。
ハンドルがどうしても気に入らなければそのうち替えよう。
しかしまぁそれは身体を合わせればいいし、外観はかなり自分好みに近づいたので良しとする。
あとはカッティングステッカーを作ってメイクアップだ。
おわり
- [ edit ]
- ロードバイク
- / trackback:0
- / comment:0
高強度練のモチベーションを維持する6つの方法
ロードバイクにおいてレースで勝つ要素は、同じ運動でも例えば球技や武道のようなものと較べて、体力要素が大きく、テクニック、頭脳要素の比重は比較的小さい。つまりある程度のレベルまでは、ロードバイクレースで勝利するためにはフィジカルを強化することが最短ルートだろう。
さらにそのフィジカルを強化するための最短ルートは、高強度な練習を故障なくこなすことである。
楽に短期間でフィジカルが強化できる方法はドーピング以外にはない。
楽に短期間でフィジカルが強化できる方法はドーピング以外にはない。
逆にきついが自転車を速く走らせるためには効果が薄い精神論中心な練習も中にはあって、そういうのは避けて通ればいい。しかし、最短ルートにはもれなくきつい練習があり、避けて通れない。
このキツい練習の中でも最たるものの一つが、高強度インターバル練だ。
高強度インターバル練は、全力に近いレベルの運動強度を短時間維持、短いレストインターバルをはさみ、再び全力に近い運動を行うということを数回から十数回繰り返す。
例えばタバタ式インターバルと呼ばれるものは、全力で20秒ダッシュ、10秒レストを8セット行うトレーニングだ。これを自転車競技に適用する場合は、インターバルはVO2Max強度の1.7倍の出力を20秒維持、10秒レストというメニューとなる。
これは上記の通り8セットだとわずか4分。さらにこれだけのトレーニングで長時間持続可能な体力・短時間の高出力・回復力の増強が一度にできるとも言われ、時間比では超効率的であるため、オリンピック選手なども導入しているトレーニングだ。
タバタに関する詳しい言説は他の解説サイトに任せておこう。
このようなことから、某サイトではたった4分で痩せる!1時間運動したのと同じ効果!とか書いてある。ここまではまぁいい。どんな強度での1時間の運動かは知らないが。
しかしこの4分たるや、地獄の苦しさだ。
上記某サイトには、
「高強度とは、ややきついと感じる程度の運動で(略」
とあるが、「ややきつい」レベルは最初の20〜50秒だけだ。
インターバル開始から、どのような感じになるかというと…
ON 0-20sec お、まぁまぁきついな
off 20-30sec 息を整えて…
ON 30-50sec お、おおおきついぞ
off 50-60sec レスト短いな
ON 60-80sec これはきついぞぉぉぉ
off 80-90sec はぁはぁ
ON 90-110sec きついぞまだ半分かよくそったれぇぇぇ
off 110-120sec はぁはぁはぁはぁ
ON 120-140sec もう(ON)かぁぁぁ?!!あああああああああああああああああ
off 140-150sec ゼェゼェゼェゼェ
ON 150-170sec あ”あ”あ”あ”あぁぁぁぁぁ
off 170-180sec (レスト短すぎだろクソがぁぁぁぁ!!!!)
ON 180-200sec もう無理
off 200-210sec あ…と…いっ……かい
ON 210-230sec 「」
とまぁこんな感じで、崖島も日々タバタインターバルをやろうとしてはいるものの、その規定出力を完全に維持できた試しがない。
なので自分がトレーニングした時も、ログに「タバタ式」と書くには烏滸がましいと思っている。
なので自分がトレーニングした時も、ログに「タバタ式」と書くには烏滸がましいと思っている。
上記の通り、高強度インターバル練は本当に嫌だ。
そのために自転車にまたがることが億劫になる。
カウチに寝そべってアブトロニックを1時間とかとは比較にならないくらいにはモチベーションが必要である。(アブトロニックやったことないのでキツかったらごめんなさい)
とはいえそれでもそこは「最短ルート」。
これをやるのが一番効率がいいのがわかっているのを、みすみすしない訳にはいかない。
どうにかモチベーションを捻出したい。
そんなあなたのために、まずは自転車に跨がりさらにそこから高強度練習に対するモチベーションにつなげる方法を、バイラルメディアの意識高い系ライフハックみたいな主題で書いた。
頑張りたい方は試してみていただければと思う。
6つの方法
1. トレーニングログを取る。
2.仲間と練習の約束を取り付ける。
3.通勤に取り入れる。
4.とりあえずレーパンを履く。
5.まず10分漕いでみる。
6.内容は問わなくても、毎日乗る。
1. トレーニングログを取る。
これはシリアスレーサーなら当たり前のようにやってることなので、敢えて書くこともないかもしれない。ログを取ることによって達成感を得ることができ、次のトレーニングへのモチベーションに繋げることができる。パワーメーターのデータがあれば、そこからトレーニング強度から成長、疲労まで管理でき、トレーニング効率の向上やさらなるモチベーションの向上に繋げられる。
最近は自転車ならGarmin Connect、Strava、Cyclosphere、Golden Cheetahなど、無料で高機能なトレーニングログ管理アプリは選び放題だ。そしてこのログを取ることが、項目6にも実は繋がってくる。
最近は自転車ならGarmin Connect、Strava、Cyclosphere、Golden Cheetahなど、無料で高機能なトレーニングログ管理アプリは選び放題だ。そしてこのログを取ることが、項目6にも実は繋がってくる。
2.仲間と練習の約束を取り付ける。
人と一緒に練習する約束を取り付けることによって「めんどくさいから今日はいいや」を防ぐ。これは普通に練習に行くときは勿論のこと、そのために必要な早起きにも、人と練習する約束があればずるずる二度寝をかますことは少なくなり、かなり効果的である。
人と約束をしつつそれを平気でぶっちぎることができるやつはなかなか少ないし、あえて約束を変更することを連絡するにもそれなりにエネルギーが要るため有効なのだ。
しかし練習の約束を取り付けるモチベーションと、きつい練習に付き合ってくれる仲間が必要。
自分の場合はその辺りは、周りにJETからJPT選手を始めとした意識の高い面々に恵まれているため、助かっている。
人と約束をしつつそれを平気でぶっちぎることができるやつはなかなか少ないし、あえて約束を変更することを連絡するにもそれなりにエネルギーが要るため有効なのだ。
しかし練習の約束を取り付けるモチベーションと、きつい練習に付き合ってくれる仲間が必要。
自分の場合はその辺りは、周りにJETからJPT選手を始めとした意識の高い面々に恵まれているため、助かっている。
3.通勤に取り入れる。
自転車通勤できる環境に恵まれたら、その中で高強度インターバルをすることにする。モチベーションが上がらなくても自転車に乗る目的があるため、自転車に乗るための活性化障壁はかなり下がる。自分の場合は、幸いその環境があるので助かっている。しかし、往路に頑張ると仕事に支障を来たしてしまうので、高強度はできれば帰路にすることにしている。
4.とりあえずレーパンを履く。
やまれぬ事情があり、上記通勤で自転車に乗れなかったとする。その場合、帰宅後に自転車に乗ることになる。しかし人間、風呂に入ったり、夕飯を食ったりしていると、一気にモチベーションが下がる。飯を食ったら乗ろう、そう考えていても、仕事の疲れなどもあいまって、そのまま寝たくなったり、ごろ寝しながらツイッターをしたくなる。これが良くない。
なので帰宅直後の「練習しなきゃ」を持続するため、帰ったら即、レーパンを履く。これはそのまま練習に移行しなくても自分の場合は大丈夫。飯を食っている時もレーパンを履くことで緊張感が保たれ、食後にトレーニングに移ることができる。食後の場合はあまり食べ過ぎると、練習中に問題が起こるため控えめに。
なお、レーパンの緊張感に加え、レーパンはダイレクトに履くため、一度履いて脱ぐと洗濯しないといけない。家でゴロゴロするためにレーパンを履いて「そのまま洗濯するのがもったいないエネルギー」も練習モチベーションに利用するのだ。
なお、レーパンの緊張感に加え、レーパンはダイレクトに履くため、一度履いて脱ぐと洗濯しないといけない。家でゴロゴロするためにレーパンを履いて「そのまま洗濯するのがもったいないエネルギー」も練習モチベーションに利用するのだ。
5.まず10分漕いでみる。
第一の活性化障壁を超えて自転車に跨っても、そこから高強度トレーニングへ移行するには、第二の活性化障壁があり、エネルギーが必要である。前述だが高強度インターバルは辛いので、単純に嫌なのだ。モチベーションがあがらない。しかしまず軽くでもいいから10分漕いでみよう。特に頑張って漕がなくてもいい。するとどうだろうか。なぜかやる気が漲ってくる。ローラーに乗って漕ぎ出して「はぁー今日はレストにしてぇ」と思ってても、10分したら「よし、やったるか」に変わってる。もしかしたらウォーミングアップとはこのことか?とも思うけど、効能機序をネットで参照する限りそんなこともなさそう。10分漕いだら交感神経優位になり、アドレナリンが出て闘争モードになったりするのかな? 詳しい人だれか教えて。通勤帰路の高強度インターバルも走り出して10分くらいからスタートだ。しかしこれはどっちかといえば、いつもインターバルトレーニングをしている場所に突入する段階で否応無しにスイッチが入るという、条件反射も含むのかもしれない。
6.内容は問わなくても、毎日乗る。
とにかく毎日欠かさず乗る。5分でも10分でもいい。ただし、ほぼ毎日じゃ駄目。これを行うことで、1のトレーニングログのカレンダーのマスを埋めることができる。ある程度マスが埋まってくると、逆にそこで埋まっていないマスが出来るのを嫌うようになってしまうので、それを利用すればどうあれ毎日乗るというモチベーションになる。これは完璧主義者の嫌いがある方には特にオススメだ。乗ってしまえばそこから高強度インターバルへの活性化障壁は一段階低くなり、より高頻度でトレーニングできるようになるという仕組みだ。なお、連続して埋めてたマスが欠けても何ともないような性格の人間には効果がない。
以上が自分に練習のためのムチを入れる時、練習をルーティーンにする時のコツだ。
みんなもぜひやってみてくれ。
それと、これから痩せたいとか体力を付けたいとか運動を始めたい人が周りにいたら、是非オススメしてやってくれ!
「たった4分で超効率のいいトレーニングがある!」とね!
俺も自分だけでなく、最近ママさんバレーで向上心を持ちだした妻にタバタをやらせてみるとしよう。
なお、この記事を最後に更新が滞ってたら、察してください。
~終~
- [ edit ]
- ロードバイク
- / trackback:0
- / comment:0
Vittoria Corsa Evo CX レビュー
要旨
ラテックスライナーを使用したチューブラータイヤVittoria Corsa Evo CXの使用感と、空気漏れ速度について評価を実施した。
その結果概要は下記5点である。
・乗り心地、グリップはContinental Competitionと比較して、なんとなく良好であった。
・空気漏れの観点からは、24h以内のライドであれば使用可能。
・CO2ボンベで充填した圧力は最寄りの自転車店までしか持たないと考えるべき。
・レース等1/10bar単位での圧力管理をしたい場合は、ライド直前の空気充填が望ましい。
・短時間の平地基調のレースまたは1日以内に終了するライドであればおすすめである。
入手経緯
半年ほど前に友人K君から購入したVittoria Corsa Evo CXをZipp404に最近装着。
初めてのラテックスチューブ(正確にはラテックスインナーチューブ)ということで楽しみであった。
ラテックスチューブは、一般的なタイヤチューブがブチルゴム(以下、IIR)製であるのに対し、ラテックス* ≃ 天然ゴム(以下、NR)を使用したタイヤチューブであり、一般的には以下のメリット/デメリットがある。
*「ラテックス」は通常、ポリマーが水に分散したエマルジョンのことを言うが、自転車業界ではラテックスは天然ゴムのことを言う。
メリットとデメリットに関する考察
メリット
1. しなやかである。
物性面から言うとIIRと比べNRは引張強度は同等、破断伸びが高いので、引張モジュラスは低い。
また、ラテックスチューブの材料は自分の知っている中ではカーボン配合のものはなさそうであるが、
このカーボンレス配合も低モジュラスを実現している一因で、
これが乗り味のしなやかさに繋がっているのだろう。
2. 高圧充填可能である。
1同様、破断伸びが高いことから高圧充填しても破断=パンクしにくいといえる。
3. 耐パンク性が高い
やはり1同様に破断伸びが高いことによる。引裂き強さもIIRより高い。
例えば長めの異物がタイヤに刺さっても、ブチルチューブより伸びることによって
穴あきや破断まで達しにくいことになる。
4. 転がり抵抗が低い
NRは高温/高周波数の損失正接がIIRより小さいため、同じ弾性率のNRとIIRで比較をするとNRが粘性率が小さい。
粘性項が小さいと、タイヤの転がりによるチューブの変形の際のエネルギー損失が小さくなる。
つまり転がり抵抗が小さく、同じ出力でもより速さに繋がるといえる。
デメリット
5. エア抜けが速い。
気体透過性についてはIIRがゴムの中ではかなり小さい部類であるのに対し、NRは気体透過性が大きい部類。
これが結構なデメリットである。今回はここにスポットを当てた。
6. 熱に弱い。
IIRは構成する分子鎖の不飽和度が低いので比較的耐熱性がある。
これに対し、NRは基本的にポリマー化しても主鎖に二重結合が大量にあり、この部分が耐熱性を悪化させている。
7. 高価である。
大方ブチルチューブの倍くらいの値段である。インナーチューブだと1本2000円から。
充填量が少なくポリマー比率が高いから原料費が高いのか?理由は定かではない。
ちなみにブチルチューブはカーボン配合が殆どであるが、
これはIIRポリマーがNRと比較して高いこととIIRへのカーボン配合は物性の変化が小さいことから
カーボンで増量しているのが一因だろう。
また、IIRの加工性を改善のためにカーボンを配合しているとも思われる。
レビュー
乗り心地、グリップなど
上記のメリット・デメリットを踏まえ、Corsa Evo CXを装着して乗った感想をCompetitionとの比較で書こう。
と思っていたんだけど、実際は乗り心地、グリップはContinental Competitionと比較して、なんとなく良好であった。
くらいしか書けない。乗り心地はブラインドテストで比較したら判らない自信がある。
グリップも…そこまで攻めこまないから判らないけど、スリップダウンはしたことないから悪くないんじゃない?程度。
一言で言うと自分の鈍感さ故なんだけど、俺は官能的な評価は苦手なんだよね…
実は実際に乗って「お、これは違うぞ…!」と思ったパーツは案外少ない。
逆に俺が違いを感じられたものっていうのは相当な違いがあるもの、と思ってくれても構わないと思う。
エア漏れについて
使い始めて衝撃を受けたのがエア抜けの速さ。
いままでブチルチューブしか使ってきてない俺にとっては、スローパンクしてるんじゃなかろうかという速度。
なんせブチルの感じで空気入れて乗って、中一日空けてさわって圧確認したらタイヤぷよぷよですよ。ばよえーんですよ。
で、今度は10bar入れて28時間後に圧力確認したら、5bar。28時間で半分になってますね。
これは実用性に難が出てくるレベル。
ということで官能的な評価は苦手だけど、理論的・定量的な評価はどちらかというと得意な崖島、
エア漏れについてはNRとIIRの気体透過性について考察してみた。
以下の図表をご覧頂きたい。

気体透過性というものは基本的に透過する気体、透過される材質、雰囲気温度によって変わってくるが、これらを透過する材質の単位厚み、単位面積、単位圧力差あたりの漏れ量としたのが気体透過係数kである。
この気体透過係数は大きいほど気体透過が速く進むものである。
この表の上にある式は気体透過による圧力変化の式であるが、タイヤに入れた空気として説明すると、
「気体透過係数kのタイヤ(又はチューブ)に最初にポンプでP0の圧力まである気体を入れ、時間tが経過すると、タイヤの圧はP1になる」
ということであり、この式によりタイヤから気体の抜ける速さが計算できる。
この計算で必要なのは気体透過係数kであり、これらは実験により測定されたものがデータとしてWeb上の学術誌に載っていた。
それを自転車乗りに必要だと思われる部分のみ抜粋したのがTable.1である。
ゴム材NRとIIRによって、温度によって、気体によって、kの値が大きく異るのが見て取れる。
また、ヘリウムより二酸化炭素の方が気体透過係数が高いことから、一概に分子量が大きいほうが漏れやすいわけではないこともわかる。
数字がわかりにくいので、NRの空気による25℃における気体透過係数を1とした場合の表がTable.2である。
これはさらっと流して、この係数比と、NRの実際に空気圧が10から5に半減した時間28hを当てはめ、
他のゴム材、他の気体、他の温度条件で圧力半減期を求めた*ものをTable.3に示した。
自転車乗りに特に関係しそうな空気および二酸化炭素以外はグレーアウトしている。
*ここではチューブのゴム厚み、チューブサイズは考慮していない。
ここで注意。空気の圧力低下は直線的ではなく、最初に上げた数式の通り対数曲線的に起こる(Fig.1参照)。
つまり、タイヤの中の相対圧力が0barになるまで、一律に「一日あたり○○bar」とはならないのだ。
なので圧力の減少する速さは「時間あたり○bar」とはならず、「圧力が半減するのに○時間」という表現が正確だ*。
Fig.1を見ても分かる通り、10→5barに要する時間は、5→2.5barに要する時間に等しい。
このあたり勘違いしている人がたまにいるので念のため。
*ある程度の範囲内であれば近似は可能。
で、Table.3に話を戻すと…
NR25℃の行、Airの列を参照すると、28時間となっている。これが先の実験の結果だ。
これに対し、IIR25℃の行、Airの列を参照すると、639時間。26.6日=1ヶ月弱だ。
ブチルチューブに10bar入れて室温で放置だとひと月後には半分5bar弱ということだ。
まぁそんなもんだろう。
一方で、37.5℃条件だと386時間、16日少々だ。
夏場に暑い倉庫の中に保管していて、走行時も高い気温と路面温度だと入れた空気は半月もしないうちに圧力半減ということになる。
また、NRで37.5℃だと、25℃の時の1.5倍の速度である。
朝入れたら夜にはぷよぷよしだす、翌朝にはばよえーん(数十行振り2度目)、そんなレベルである。
こういうことから、ラテックス(インナー)チューブを使用するときは、基本毎朝空気を入れないといけないことがわかる。
さらに!NR37.5℃の行、CO2の列を参照して欲しい。
半減時間は1.7時間=102分である。
夏場の真っ昼間、パンクしちゃったぜ…!
パンク修理用にポンプは邪魔だからCO2ボンベしか持ってねぇ!

写真はちくわ
となった場合、ボンベで仮に6bar入ったとしても、1時間ですでに4barを切るレベルである。
なのでパンク修理してCO2充填した場合は、ライドを継続させようとせず、
速やかに最寄りの自転車屋で「一度すべての二酸化炭素を抜いた上で」空気を入れさせてもらうべきだ。
その前に、せめてCO2ボンベでなく携帯ポンプを装備していくのがマストだろう。
また、充填する気体が空気の場合でも、例えばレースなどでコンマ何barの精度でエア圧をコントロールしたい!
という細かい几帳面な方は、出走直前に希望するエア圧に設定すべきだろう。
おおまかに言えばこのCorsa Evo CXはレースで使用するだろう10-6barの領域では30分あたり0.1barの漏れが予想される。
1時間弱のレースなら、レースの招集が掛かる前に希望圧力+0.2bar位で充填すると丁度いいくらいか。
個人的には1barくらい違っても気にならないけど。
ということで漏れやすいことを書き立てたが、20時間以内の通常のライドならば使って問題ないんじゃなかろうか。
その他
とまぁ空気漏れに関して書いてきたわけだけど、実はこれと同じレベルで使用に際し気をつけなければいけない事象がひとつある。
ラテックスチューブは耐熱性が低いのである。
耐熱性が低いということは、呼んで字のごとく熱に弱い、つまり高温時には著しく強度が下がるということだ。
これがどういう時に問題になるかというと、過熱したリムの熱が逃げる前にチューブに伝わる場合である。
平坦地でのライドやロードレースくらいのアップダウンなら問題ないだろう。
しかし長く尚且つペースを抑えなければいけないダウンヒルがあるとき、つまりヒルクライムレースの下りやタイトコーナーが続く激坂のダウンヒルをする時が要注意だ。
というかできるだけ使用を控えたほうが良い。
知り合いのKさんが取ったデータによると、カーボンホイールにクリンチャータイヤの組み合わせで、富士ヒルクライムのレース後のダウンヒルでリムの温度上昇に気遣いながら下った時の、最高温度が前輪75℃、後輪65℃だったとのこと(サーモラベルによる測定)。
これくらいの温度領域であればぎりぎり大丈夫である。
が、海外のウェブサイトではHEDの評価でカーボンリム・クリンチャータイヤ・ダウンヒルで230℃以上になったという情報もある。
一方でラテックスチューブの耐久使用温度は100℃に満たない。瞬間使用可能温度もせいぜい150-200℃だろう。なので上記のようなDH時の温度で圧も高ければ、破裂待ったなしである。
カーボンリムが歪んだり割れたりするのが先になる可能性もあるがいずれにしても危険であることには変わりない。
なお、チューブラーであるCorsa Evo CXなら過熱したリムに直接ラテックスインナーチューブには触れていないので、クリンチャーでのラテックスチューブ使用よりは危険度はマシかもしれない。
まとめ
そんなこんなでCorsa Evo CXは乗り心地は良いけど使用するTPOには十分気をつける必要がある、そんなタイヤだということで結言とする。
違いのわかるオトコであれば、一度試してみてはいかがかな?
ただし鈍感な俺は、超安売りとかしてない限りCorsa Evo CXを買うことは今後ないかも。
おわり
参考:各種ゴムの特性データ
http://www.kayo-corp.co.jp/common/pdf/rub_propertylist.pdf
ラテックスライナーを使用したチューブラータイヤVittoria Corsa Evo CXの使用感と、空気漏れ速度について評価を実施した。
その結果概要は下記5点である。
・乗り心地、グリップはContinental Competitionと比較して、なんとなく良好であった。
・空気漏れの観点からは、24h以内のライドであれば使用可能。
・CO2ボンベで充填した圧力は最寄りの自転車店までしか持たないと考えるべき。
・レース等1/10bar単位での圧力管理をしたい場合は、ライド直前の空気充填が望ましい。
・短時間の平地基調のレースまたは1日以内に終了するライドであればおすすめである。
入手経緯
半年ほど前に友人K君から購入したVittoria Corsa Evo CXをZipp404に最近装着。
初めてのラテックスチューブ(正確にはラテックスインナーチューブ)ということで楽しみであった。
ラテックスチューブは、一般的なタイヤチューブがブチルゴム(以下、IIR)製であるのに対し、ラテックス* ≃ 天然ゴム(以下、NR)を使用したタイヤチューブであり、一般的には以下のメリット/デメリットがある。
*「ラテックス」は通常、ポリマーが水に分散したエマルジョンのことを言うが、自転車業界ではラテックスは天然ゴムのことを言う。
メリットとデメリットに関する考察
メリット
1. しなやかである。
物性面から言うとIIRと比べNRは引張強度は同等、破断伸びが高いので、引張モジュラスは低い。
また、ラテックスチューブの材料は自分の知っている中ではカーボン配合のものはなさそうであるが、
このカーボンレス配合も低モジュラスを実現している一因で、
これが乗り味のしなやかさに繋がっているのだろう。
2. 高圧充填可能である。
1同様、破断伸びが高いことから高圧充填しても破断=パンクしにくいといえる。
3. 耐パンク性が高い
やはり1同様に破断伸びが高いことによる。引裂き強さもIIRより高い。
例えば長めの異物がタイヤに刺さっても、ブチルチューブより伸びることによって
穴あきや破断まで達しにくいことになる。
4. 転がり抵抗が低い
NRは高温/高周波数の損失正接がIIRより小さいため、同じ弾性率のNRとIIRで比較をするとNRが粘性率が小さい。
粘性項が小さいと、タイヤの転がりによるチューブの変形の際のエネルギー損失が小さくなる。
つまり転がり抵抗が小さく、同じ出力でもより速さに繋がるといえる。
デメリット
5. エア抜けが速い。
気体透過性についてはIIRがゴムの中ではかなり小さい部類であるのに対し、NRは気体透過性が大きい部類。
これが結構なデメリットである。今回はここにスポットを当てた。
6. 熱に弱い。
IIRは構成する分子鎖の不飽和度が低いので比較的耐熱性がある。
これに対し、NRは基本的にポリマー化しても主鎖に二重結合が大量にあり、この部分が耐熱性を悪化させている。
7. 高価である。
大方ブチルチューブの倍くらいの値段である。インナーチューブだと1本2000円から。
充填量が少なくポリマー比率が高いから原料費が高いのか?理由は定かではない。
ちなみにブチルチューブはカーボン配合が殆どであるが、
これはIIRポリマーがNRと比較して高いこととIIRへのカーボン配合は物性の変化が小さいことから
カーボンで増量しているのが一因だろう。
また、IIRの加工性を改善のためにカーボンを配合しているとも思われる。
レビュー
乗り心地、グリップなど
上記のメリット・デメリットを踏まえ、Corsa Evo CXを装着して乗った感想をCompetitionとの比較で書こう。
と思っていたんだけど、実際は乗り心地、グリップはContinental Competitionと比較して、なんとなく良好であった。
くらいしか書けない。乗り心地はブラインドテストで比較したら判らない自信がある。
グリップも…そこまで攻めこまないから判らないけど、スリップダウンはしたことないから悪くないんじゃない?程度。
一言で言うと自分の鈍感さ故なんだけど、俺は官能的な評価は苦手なんだよね…
実は実際に乗って「お、これは違うぞ…!」と思ったパーツは案外少ない。
逆に俺が違いを感じられたものっていうのは相当な違いがあるもの、と思ってくれても構わないと思う。
エア漏れについて
使い始めて衝撃を受けたのがエア抜けの速さ。
いままでブチルチューブしか使ってきてない俺にとっては、スローパンクしてるんじゃなかろうかという速度。
なんせブチルの感じで空気入れて乗って、中一日空けてさわって圧確認したらタイヤぷよぷよですよ。ばよえーんですよ。
で、今度は10bar入れて28時間後に圧力確認したら、5bar。28時間で半分になってますね。
これは実用性に難が出てくるレベル。
ということで官能的な評価は苦手だけど、理論的・定量的な評価はどちらかというと得意な崖島、
エア漏れについてはNRとIIRの気体透過性について考察してみた。
以下の図表をご覧頂きたい。

気体透過性というものは基本的に透過する気体、透過される材質、雰囲気温度によって変わってくるが、これらを透過する材質の単位厚み、単位面積、単位圧力差あたりの漏れ量としたのが気体透過係数kである。
この気体透過係数は大きいほど気体透過が速く進むものである。
この表の上にある式は気体透過による圧力変化の式であるが、タイヤに入れた空気として説明すると、
「気体透過係数kのタイヤ(又はチューブ)に最初にポンプでP0の圧力まである気体を入れ、時間tが経過すると、タイヤの圧はP1になる」
ということであり、この式によりタイヤから気体の抜ける速さが計算できる。
この計算で必要なのは気体透過係数kであり、これらは実験により測定されたものがデータとしてWeb上の学術誌に載っていた。
それを自転車乗りに必要だと思われる部分のみ抜粋したのがTable.1である。
ゴム材NRとIIRによって、温度によって、気体によって、kの値が大きく異るのが見て取れる。
また、ヘリウムより二酸化炭素の方が気体透過係数が高いことから、一概に分子量が大きいほうが漏れやすいわけではないこともわかる。
数字がわかりにくいので、NRの空気による25℃における気体透過係数を1とした場合の表がTable.2である。
これはさらっと流して、この係数比と、NRの実際に空気圧が10から5に半減した時間28hを当てはめ、
他のゴム材、他の気体、他の温度条件で圧力半減期を求めた*ものをTable.3に示した。
自転車乗りに特に関係しそうな空気および二酸化炭素以外はグレーアウトしている。
*ここではチューブのゴム厚み、チューブサイズは考慮していない。
ここで注意。空気の圧力低下は直線的ではなく、最初に上げた数式の通り対数曲線的に起こる(Fig.1参照)。
つまり、タイヤの中の相対圧力が0barになるまで、一律に「一日あたり○○bar」とはならないのだ。
なので圧力の減少する速さは「時間あたり○bar」とはならず、「圧力が半減するのに○時間」という表現が正確だ*。
Fig.1を見ても分かる通り、10→5barに要する時間は、5→2.5barに要する時間に等しい。
このあたり勘違いしている人がたまにいるので念のため。
*ある程度の範囲内であれば近似は可能。
で、Table.3に話を戻すと…
NR25℃の行、Airの列を参照すると、28時間となっている。これが先の実験の結果だ。
これに対し、IIR25℃の行、Airの列を参照すると、639時間。26.6日=1ヶ月弱だ。
ブチルチューブに10bar入れて室温で放置だとひと月後には半分5bar弱ということだ。
まぁそんなもんだろう。
一方で、37.5℃条件だと386時間、16日少々だ。
夏場に暑い倉庫の中に保管していて、走行時も高い気温と路面温度だと入れた空気は半月もしないうちに圧力半減ということになる。
また、NRで37.5℃だと、25℃の時の1.5倍の速度である。
朝入れたら夜にはぷよぷよしだす、翌朝にはばよえーん(数十行振り2度目)、そんなレベルである。
こういうことから、ラテックス(インナー)チューブを使用するときは、基本毎朝空気を入れないといけないことがわかる。
さらに!NR37.5℃の行、CO2の列を参照して欲しい。
半減時間は1.7時間=102分である。
夏場の真っ昼間、パンクしちゃったぜ…!
パンク修理用にポンプは邪魔だからCO2ボンベしか持ってねぇ!

写真はちくわ
となった場合、ボンベで仮に6bar入ったとしても、1時間ですでに4barを切るレベルである。
なのでパンク修理してCO2充填した場合は、ライドを継続させようとせず、
速やかに最寄りの自転車屋で「一度すべての二酸化炭素を抜いた上で」空気を入れさせてもらうべきだ。
その前に、せめてCO2ボンベでなく携帯ポンプを装備していくのがマストだろう。
また、充填する気体が空気の場合でも、例えばレースなどでコンマ何barの精度でエア圧をコントロールしたい!
という
おおまかに言えばこのCorsa Evo CXはレースで使用するだろう10-6barの領域では30分あたり0.1barの漏れが予想される。
1時間弱のレースなら、レースの招集が掛かる前に希望圧力+0.2bar位で充填すると丁度いいくらいか。
個人的には1barくらい違っても気にならないけど。
ということで漏れやすいことを書き立てたが、20時間以内の通常のライドならば使って問題ないんじゃなかろうか。
その他
とまぁ空気漏れに関して書いてきたわけだけど、実はこれと同じレベルで使用に際し気をつけなければいけない事象がひとつある。
ラテックスチューブは耐熱性が低いのである。
耐熱性が低いということは、呼んで字のごとく熱に弱い、つまり高温時には著しく強度が下がるということだ。
これがどういう時に問題になるかというと、過熱したリムの熱が逃げる前にチューブに伝わる場合である。
平坦地でのライドやロードレースくらいのアップダウンなら問題ないだろう。
しかし長く尚且つペースを抑えなければいけないダウンヒルがあるとき、つまりヒルクライムレースの下りやタイトコーナーが続く激坂のダウンヒルをする時が要注意だ。
というかできるだけ使用を控えたほうが良い。
知り合いのKさんが取ったデータによると、カーボンホイールにクリンチャータイヤの組み合わせで、富士ヒルクライムのレース後のダウンヒルでリムの温度上昇に気遣いながら下った時の、最高温度が前輪75℃、後輪65℃だったとのこと(サーモラベルによる測定)。
これくらいの温度領域であればぎりぎり大丈夫である。
が、海外のウェブサイトではHEDの評価でカーボンリム・クリンチャータイヤ・ダウンヒルで230℃以上になったという情報もある。
一方でラテックスチューブの耐久使用温度は100℃に満たない。瞬間使用可能温度もせいぜい150-200℃だろう。なので上記のようなDH時の温度で圧も高ければ、破裂待ったなしである。
カーボンリムが歪んだり割れたりするのが先になる可能性もあるがいずれにしても危険であることには変わりない。
なお、チューブラーであるCorsa Evo CXなら過熱したリムに直接ラテックスインナーチューブには触れていないので、クリンチャーでのラテックスチューブ使用よりは危険度はマシかもしれない。
まとめ
そんなこんなでCorsa Evo CXは乗り心地は良いけど使用するTPOには十分気をつける必要がある、そんなタイヤだということで結言とする。
違いのわかるオトコであれば、一度試してみてはいかがかな?
ただし鈍感な俺は、超安売りとかしてない限りCorsa Evo CXを買うことは今後ないかも。
おわり
参考:各種ゴムの特性データ
http://www.kayo-corp.co.jp/common/pdf/rub_propertylist.pdf
- [ edit ]
- ロードバイク
- / trackback:0
- / comment:0
ちぎれてたまるか。
2016 カートコースクリテリウム レースレポート
目標
A決勝完走
結果
達成
(予選TT6位、A準決勝18位、A決勝12位完走)
経緯
実業団登録してから奈良クリテに続くJBCFのレースは、諸々の理由により9月の舞洲まで参加予定がない。ということでその合間にレース経験を積むためにも、地元岡山で開催のカートコースクリテに参加することにした。
概要
コースは中山サーキットの敷地にあるカートコース。
名前の通りレーシングカート向けに作ってあるため、アップダウンの激しい(というかアップダウンしかない)中山サーキット本コースと比較すると、ほぼ平坦。
さらに1周は800m程度と短い中にもコーナーが6程度とテクニカルなコース。
コーナリングの処理の良否が結果を左右する。
ただ噂によると「雨が降るとオイルが浮いてグリップゼロ」とのことだったので、そこはかなり心配だ。
レース方式は、今年春に行われた灘崎クリテと同じく、予選TTのベストラップタイムで準決勝A~Cクラスを決定、マスドスタートの準決勝での着順上位5名昇格・下位5名を降格して、決勝クラスを決定し、同じくマスドスタートの決勝を行う。決勝は7周回毎に周回賞(CCD)を設定。
事前準備
トレーニング
奈良クリテ前あたりから全然距離が乗れていなかった。
梅雨時と諸々の予定が重なったりしたことと、5月ごろから考えていた「1回1回の練習のパフォーマンスを上げるための完全休養」がいささか多過ぎたのか、FTPは15Wほど下がり、インターバルトレーニングが以前と同じ強度でこなせなくなってしまった。
反省。
ということで6月終わりごろから毎日漕ぐのを目標の一つに取り入れてトレーニングをした。
やはり個人的にはインターバル耐性をUPさせるため、個人練習でもインターバルメインのトレーニングだ。
しかし前々日晩から喉の具合があやしい。
ということで前日は万全を期すために完全休養。
機材
・レース前ほかの用事などで忙しかった
・スピードが乗らないコースレイアウト
・天候不順の可能性を考慮
以上の理由から、主な構成は奈良クリテの時と全く同じくSempreで前後クリンチャーホイール。
空気圧はフロント6.2kgf/cm2、リアは成り行き(6kgfくらい?)。
ただし当日かなり高温となることが予想されたので、ボトルは予備含め3つ。
内容は700ml氷満タン、700ml CCD満タン、500ml水道水だ。
当日
5:00 起床
喉その他身体の調子はどうやら無事なようだ。
6時に家を出発して7時に受付・試走開始する予定だった。
が、使い捨てコンタクトがパッケージの中で折りたたまれ張り付いて開けないトラブルが発生し、15分ほどロス。
これはクレームものだろ…結局さらに新しいパッケージを開封して装着。
試走時間が多少少なくなるが、このレース方式だと予選をそんなに重視しなくてもいいので、予選兼試走にしてしまってもいいかという思いでゆったり出発する。
7:30 現地到着
駐車場に車を何気なくとめたが、これまた壁ギリギリにとめることに成功。

これはレースもいいことあるんじゃないの?
(本当はぶつかったのかもしれないが、痕跡は見当たらず)
某ショップ練やレースでよくお会いするS田さんの区画へ止めさせていただく。
観覧席の下にあるので日陰になり涼しい。
これは、ということで車の駐車位置も日陰になる場所へ移動した。
7:40 試走
実はここは初めて走る。本コースは1度走ったことがあるが、上記のとおり傾斜・距離ともに全く性格が異なる。
路面状況に関しては本コースと近いものがある。コース自体がもう古くいたるところに補修がみられ、お世辞にもいいとは言えない。
が、そもそも走り回るようにできていないところを走らされた奈良クリテよりは全然マシだった。
さっさと計測チップを付けてコースに出る。
事前に情報を得ていた路面のギャップの大きさは、さほど気にならない。
Youtubeに挙がっていた車載動画でコーナーの具合は予習してきたつもりだった。
しかしその動画の、アクションカム特有の広角な画角を考慮していないかった。
予想していたよりかなりコーナーがきつい。
そりゃあカート向けのコースだからだろうけど、ジムカーナコースといってもいい。
が、悪くない。落車に巻き込まれなければ面白いレースにできるかもしれない。
コースでゆったり走りながら、岡山でよく会う顔なじみのレーサー、広島から来られたレーサーの方々とあいさつを交わす。
今回はロングライドの盟友H君が兵庫からくる予定だったが、姿が見えない。
後でツイッターをチェックすると…風邪でダウンとのこと。残念。
決着(?)はまたの機会だな。
10:10 予選開始
今回は予選3組目。速い選手は大方1分フラットくらいで回れるコースのようだったが、1組目でまさかの56秒というすごいタイムを出す選手が。
TRAPというチームのレーサーのようだ。要チェック。
なお、今回はA決勝を完走するのが目標のため、予選では手を抜かないことにしていた。
果たして全力で走ってどれくらいのタイムがでるんだろうか。
3組目に入って、コースイン。
できるだけクリアラップで走りたい気持ちから2周目でアタックすることにした。
が、すでに結構ハイペースで走っている選手がおり、クリアは取れそうにない。
まぁ仕方がないということで、1周目最終コーナーからペースを上げアタック。
立ち上がりは焦らずバイクを立ててから踏みだすことを意識する。
A準決勝に入る目標のためではあったので、きっちりしたパワーマネジメントはせず、体感で1分は持ちそうなペースで踏みしだく。
最終コーナーは残念ながら先行車がいるので仕方なくミドルインミドルのライン取りで抜け、コントロールラインまでしっかり踏んだ。
アタック完了後、メーター読みでは1:01を記録。これならA決勝だろう。
後は無駄な体力は使いたくないため、だらだらと左側を走行しクールダウン。
10:20 準決勝組み分け
暫くすると、予選のリザルト発表が。
メーターより若干速めの1分フラットを記録、総合6/84位だ。
やればできるじゃん、俺。
というわけで上位1/3に入ったのでA準決勝に進出。
しかしまぁこういうレース方式だし、TTを抜いてる選手なんかいくらでもいるだろうから、全く油断はできない。
12:00 A準決勝
エントリーリストを一通り眺めたあと、準決勝招集場所へ。
色々なレースで見かけたジャージや、いつもの練習メンバーがちらほら。
地元レースなだけに顔見知りが多い。かといって走力が分かってるのはほんの数名だが。
そんな雰囲気とJBCFでないことも併せて、緊張感はあまりない。
これ以上の昇格もないので、頑張って上位に食い込む必要はない。
スタート位置につきボトルの水を飲み干した。
なお、準決勝は20周、20分程度と予想していたので、途中の補給なくとも水分は足りるだろうと予測。
定刻になり、スタート。
灘崎と同じく、集団先頭周辺で位置取り、インターバルを避ける作戦で行く。
個人的には初めて見るチーム、ブルブルチキンの選手がスタート直後に飛び出した。
この選手は速いんだろうか?(後になってわかるがこの選手、プロであった)
まぁともかく上位を狙う必要がないことと序盤であることで、チェックはせず。
結局誰も追い掛けずに、ジワジワ下がってくる。
そして集団に吸収され、暫くするとまた同じくブルブルチキンM内選手がアタック。
が、皆割と無反応。やはり準決勝だからか。
とはいえ俺にとっては決して遅くないペースで展開する。
ジワジワキツくなってきて、決勝もあって脚を残さないと、と思いつついい感じに下がろうとしていた。
すると後ろに居た練習仲間のG選手に
「こりゃー!崖島ー!お前エリート選手じゃろーが!下がってんじゃねーぞ!」
「おぃこら中切れぞ!」
という罵倒激励の言葉を頂き、いくらか踏み直す。

喝を入れられるがなぜか笑っている様に見える Photo by Kohei T.
個人的にはE3って少なくともJBCFでは下っ端なので、E3って言われても何とも思わなかったろう。
しかしE3のEは「Elite」のEだ。「エリート選手」と言われると、良い意味で心に来るものがあった。
「エリート」と言われれば、無いプライドも湧いてくるもんだ。
と踏み直したのも束の間、いよいよ限界が近い。
どうにか後続に先に行ってもらい、こちらは後ろに下がる。
その周回の直後の15周目の南側の4番目の左コーナーで、前方10mくらいのあたりで落車!
そして直後に居たG選手も巻き込まれ落車!
コーナー出口でスピードが遅かったことと、後ろに下がってたことで距離があったことからどうにか躱す。
助かった。
助かったのはいいが、当然のようにそこから中切れが発生。
が、俺にはそれを埋める脚はもう残っていなかった。
じわじわ先頭集団と距離が開くなかF武さんがケツを軽くプッシュしてくれる。
その気持ちは大変嬉しかったが、残念ながら先立つものがないのできっちり追い縋ることもままならない。
と、続く周回でまたしても同じコーナーで落車が。
今度はそのF武さんが…!
何という因果。準決勝で俺に関わった2人とも落車ですよ…
そんなこんなで千切れながらも最終周回を迎えた。
多分大丈夫だと思うけど念のため前にいる選手1人くらいは捲ってゴールだ!
虚しさ溢れるスプリントをして無事ゴール!順位は18/28位で無事A決勝進出を決めた。
しかし後でリザルト見るとスプリントで抜かしたのは周回遅れの選手だったという何ともアレな無駄脚を使ってしまったらしい。
なおB決勝降格となった5人のうち4人は落車が決め手になった厳しい準決勝だった。
しかし上の2人とも、骨に異常が出るような大怪我でなかったようでよかった。
13:00 決勝前
さて、A決勝までは結構時間が余っていたので、カロリーメイトを一箱食って、車の日陰で30分程一寝入り。
この季節、駐車場に日陰があるのは本当に助かる。その後起き上がって水分をたっぷり補給。
恐らくレース中に飲む余裕は無いかもしれないので、準決勝と同じく事前にしっかり摂っておく。
しかし決勝は20周だったが、決勝は30周と比較的長丁場な上にこの暑さ。保険のために500ボトル半分程の水を入れておいた。かけることも考えて水だ。
14:50 決勝

ガケシマを探せ Photo by A. Harada
そしていよいよA決勝スタート前。
暑い。この中で30周も走りたくないな… と弱音を吐いても仕方ない。
しかし一応今回からはチームの看板背負って走るわけだし、良いとこ作りたい、との思いはあった。
なので決勝にはある7周回毎の周回賞は取りに行ってやる…。
なんならその後足切りになっても構わない。
去年の灘崎クリテでもそんな望みがあったがそれも虚しく、7周回目には既に息も絶え絶えだった思い出が過る。まぁ出方次第だ。
そんなこんなでスタート。
とりあえず準決勝と同じく前方で展開したいと思いながらも、思い通りの位置どりができず3周目ほどまで集団中盤で走る。
しかしやはり決勝、準決勝よりはハイペースには感じ、自分で下がらなくても後ろからどんどん被せられ位置が下がっていく。
これはあまり良くない展開だと感じながら7周回目を迎えた。
これは行っとくか?と思ったら周りが案外ペースが上がっていない。
これはチャンス! と思い位置を上げていき、最終抜けて渾身のスプリントで周回賞を取りに行く。
しかし集団前方のペース=周回賞へのモチベーションが異常に低い。
ストレート半分程走ったところで、遥か先の方に選手が。
周回遅れ…じゃないな!
逃げてる!
あっかーん…そりゃみんなポイント周回頑張らん筈だわ。
とうの昔に周回賞取られてたわけだ。
落胆しつつ、息切れしつつも、それが逆に功を奏し、先頭周辺に躍り出ることができた。
しかし自分の地脚の程度からしても良いペースで牽けるわけもなく、暫くしたら後ろに下がることになった。
後ろに下がったら当然最初と同じくインターバルがきつくなる。
中ほどやや後ろに位置していたN村さんに必死に食いつく。

Photo by A. Harada
奈良クリテでのインターバル死の反省から、今回はきっちり後ろにつく、コーナー前でギアを落とす、コーナーのラインは正確に、を意識したがまだまだ足りないようだ。
じわじわ置いていかれる。かといって立ち上がりで早めにペダリングを始めるのも気がひける。
今日のレースでは特にペダルヒットでの落車をよく見たからだ。
となると、どうすれば省エネできるかを考えた。
前走者と同じラインを走ってては立ち上がりでのインターバルは少なからずかかってしまう。
となれば、違うラインでいけばいいのか。
まずはインベタで回ってみる。
これはライン選択の優位はあるものの速度が殺され過ぎてしまい、余計インターバルが掛かってしまった。
次にアウトインアウト。
前走者とラインがほぼ被るのでだめ。
その次はクリップ奥目のスローインファストアウト。
これも前走者との距離がコーナー中に開いてしまうのでそんなに変わずインターバルがかかる気がする。
そしてアウトアウトアウト。
今回はこれだ。
ラインが被らないのでブレーキをかける必要も少なく、スピードをあまり殺さず曲がれた。
しかしあくまでこの序盤から中盤までの、勝負がかかっていない時に通用しやすいラインだろう。
終盤だとイン側からアウトにはらんだ選手に押し出されコースアウトしてしまう可能性があるので、場面を考えないと落車に繋がる。
後半になり集団が伸び気味になってくると、バックストレート半分あたりからコースティングで最終コーナーまで付いていける。
これは助かる。しかし多少はマシになったもののホーム/バックストレートの立ち上がりには依然としてかかってしまうインターバルでじわじわ消耗する。
逃げが吸収されたあとのポイント周回も、踏み込む元気はなくただひたすら集団から切れないように堪えるといった状況。
コーナーリングラインの試行錯誤と忍耐で周回数を重ねていき、ふと見ると残り3周。
「もういいだろ…ここから流しても脚切りにはならんよ、やめやめ」とかいう悪魔(?)の囁き。
「もう少しで集団維持でゴールできるんだ、最後まで踏めよ!」という天使(?)の励まし。
この葛藤が朦朧とした意識の中で行われていた。
が、どうやら体力と天使が打ち勝ったようで、最終周に突入。
最早着に絡む脚は残ってないにしても、安全に配慮しつつ可能な限り着順上げてやる!
最終コーナーを抜け最後の力を振り絞ってスプリントにならないスプリントを掛ける。
ここでB決勝とかなら経験上は何人か捲れるんだけど、流石のA決勝はそうはいかなかった。
順位維持でそのままゴール。前を走るE2のO森さんには追いつけず、12位での幕引きとなった。
なお優勝は準決勝でアタックを掛けまくっていたM内選手、最初に逃げていた選手は落車というドラマがあったようだ。
(M内選手は同じチームで3人居たけど、兄弟かな?)

無駄なあがき Photo by Gentatsu
分析
走行ログを見ての分析をしてみた。

準決勝チャート
準決勝でG選手に喝を入れられた13周目は1000Wくらい踏んでる。
その次の周に落車で中切れ、気持ちが切れて、W’balが上向いてきているのがわかる。

決勝チャート
一方決勝のW’balを見ると、7周目まででどんどん消耗しているのがわかる。
出力曲線に目を移すと、後半の周回と比べて踏んでいるときの出力が800Wを超える周も3回ある。
テーブルの方を見るとノンゼロの出力が300~400W。なるほどこれで消耗していたわけだ。
そして決勝一番特徴的だったのはやはり7周目からの先頭周辺での走行。
明らかにLap最大パワーが低く、そこから徐々にLap最大パワーが上がっている。
位置が後ろに下がりインターバルがきつくなっているのが如実にわかった。
データを掘ればもっといろいろなことがわかるだろうが今回はこの辺にしておこう。
総括
当初の目標であったA決勝完走は、一応ギリギリ集団ゴールという比較的良い形での達成となった。
しかし各レースともに入賞やポイント賞はなく、物的には得るものは全くなくそこが残念でなくはないが。
コーナリングのライン取りや脚の抜き方については学びがあったが、前回のシフトダウンやライン精度についてはまだまだだ。
この反省を再度次回に繋げて行こう。
ネクストガケシマ’s ヒント!
「舞洲」
終わり
目標
A決勝完走
結果
達成
(予選TT6位、A準決勝18位、A決勝12位完走)
経緯
実業団登録してから奈良クリテに続くJBCFのレースは、諸々の理由により9月の舞洲まで参加予定がない。ということでその合間にレース経験を積むためにも、地元岡山で開催のカートコースクリテに参加することにした。
概要
コースは中山サーキットの敷地にあるカートコース。
名前の通りレーシングカート向けに作ってあるため、アップダウンの激しい(というかアップダウンしかない)中山サーキット本コースと比較すると、ほぼ平坦。
さらに1周は800m程度と短い中にもコーナーが6程度とテクニカルなコース。
コーナリングの処理の良否が結果を左右する。
ただ噂によると「雨が降るとオイルが浮いてグリップゼロ」とのことだったので、そこはかなり心配だ。
レース方式は、今年春に行われた灘崎クリテと同じく、予選TTのベストラップタイムで準決勝A~Cクラスを決定、マスドスタートの準決勝での着順上位5名昇格・下位5名を降格して、決勝クラスを決定し、同じくマスドスタートの決勝を行う。決勝は7周回毎に周回賞(CCD)を設定。
事前準備
トレーニング
奈良クリテ前あたりから全然距離が乗れていなかった。
梅雨時と諸々の予定が重なったりしたことと、5月ごろから考えていた「1回1回の練習のパフォーマンスを上げるための完全休養」がいささか多過ぎたのか、FTPは15Wほど下がり、インターバルトレーニングが以前と同じ強度でこなせなくなってしまった。
反省。
ということで6月終わりごろから毎日漕ぐのを目標の一つに取り入れてトレーニングをした。
やはり個人的にはインターバル耐性をUPさせるため、個人練習でもインターバルメインのトレーニングだ。
しかし前々日晩から喉の具合があやしい。
ということで前日は万全を期すために完全休養。
機材
・レース前ほかの用事などで忙しかった
・スピードが乗らないコースレイアウト
・天候不順の可能性を考慮
以上の理由から、主な構成は奈良クリテの時と全く同じくSempreで前後クリンチャーホイール。
空気圧はフロント6.2kgf/cm2、リアは成り行き(6kgfくらい?)。
ただし当日かなり高温となることが予想されたので、ボトルは予備含め3つ。
内容は700ml氷満タン、700ml CCD満タン、500ml水道水だ。
当日
5:00 起床
喉その他身体の調子はどうやら無事なようだ。
6時に家を出発して7時に受付・試走開始する予定だった。
が、使い捨てコンタクトがパッケージの中で折りたたまれ張り付いて開けないトラブルが発生し、15分ほどロス。
これはクレームものだろ…結局さらに新しいパッケージを開封して装着。
試走時間が多少少なくなるが、このレース方式だと予選をそんなに重視しなくてもいいので、予選兼試走にしてしまってもいいかという思いでゆったり出発する。
7:30 現地到着
駐車場に車を何気なくとめたが、これまた壁ギリギリにとめることに成功。

これはレースもいいことあるんじゃないの?
(本当はぶつかったのかもしれないが、痕跡は見当たらず)
某ショップ練やレースでよくお会いするS田さんの区画へ止めさせていただく。
観覧席の下にあるので日陰になり涼しい。
これは、ということで車の駐車位置も日陰になる場所へ移動した。
7:40 試走
実はここは初めて走る。本コースは1度走ったことがあるが、上記のとおり傾斜・距離ともに全く性格が異なる。
路面状況に関しては本コースと近いものがある。コース自体がもう古くいたるところに補修がみられ、お世辞にもいいとは言えない。
が、そもそも走り回るようにできていないところを走らされた奈良クリテよりは全然マシだった。
さっさと計測チップを付けてコースに出る。
事前に情報を得ていた路面のギャップの大きさは、さほど気にならない。
Youtubeに挙がっていた車載動画でコーナーの具合は予習してきたつもりだった。
しかしその動画の、アクションカム特有の広角な画角を考慮していないかった。
予想していたよりかなりコーナーがきつい。
そりゃあカート向けのコースだからだろうけど、ジムカーナコースといってもいい。
が、悪くない。落車に巻き込まれなければ面白いレースにできるかもしれない。
コースでゆったり走りながら、岡山でよく会う顔なじみのレーサー、広島から来られたレーサーの方々とあいさつを交わす。
今回はロングライドの盟友H君が兵庫からくる予定だったが、姿が見えない。
後でツイッターをチェックすると…風邪でダウンとのこと。残念。
決着(?)はまたの機会だな。
10:10 予選開始
今回は予選3組目。速い選手は大方1分フラットくらいで回れるコースのようだったが、1組目でまさかの56秒というすごいタイムを出す選手が。
TRAPというチームのレーサーのようだ。要チェック。
なお、今回はA決勝を完走するのが目標のため、予選では手を抜かないことにしていた。
果たして全力で走ってどれくらいのタイムがでるんだろうか。
3組目に入って、コースイン。
できるだけクリアラップで走りたい気持ちから2周目でアタックすることにした。
が、すでに結構ハイペースで走っている選手がおり、クリアは取れそうにない。
まぁ仕方がないということで、1周目最終コーナーからペースを上げアタック。
立ち上がりは焦らずバイクを立ててから踏みだすことを意識する。
A準決勝に入る目標のためではあったので、きっちりしたパワーマネジメントはせず、体感で1分は持ちそうなペースで踏みしだく。
最終コーナーは残念ながら先行車がいるので仕方なくミドルインミドルのライン取りで抜け、コントロールラインまでしっかり踏んだ。
アタック完了後、メーター読みでは1:01を記録。これならA決勝だろう。
後は無駄な体力は使いたくないため、だらだらと左側を走行しクールダウン。
10:20 準決勝組み分け
暫くすると、予選のリザルト発表が。
メーターより若干速めの1分フラットを記録、総合6/84位だ。
やればできるじゃん、俺。
というわけで上位1/3に入ったのでA準決勝に進出。
しかしまぁこういうレース方式だし、TTを抜いてる選手なんかいくらでもいるだろうから、全く油断はできない。
12:00 A準決勝
エントリーリストを一通り眺めたあと、準決勝招集場所へ。
色々なレースで見かけたジャージや、いつもの練習メンバーがちらほら。
地元レースなだけに顔見知りが多い。かといって走力が分かってるのはほんの数名だが。
そんな雰囲気とJBCFでないことも併せて、緊張感はあまりない。
これ以上の昇格もないので、頑張って上位に食い込む必要はない。
スタート位置につきボトルの水を飲み干した。
なお、準決勝は20周、20分程度と予想していたので、途中の補給なくとも水分は足りるだろうと予測。
定刻になり、スタート。
灘崎と同じく、集団先頭周辺で位置取り、インターバルを避ける作戦で行く。
個人的には初めて見るチーム、ブルブルチキンの選手がスタート直後に飛び出した。
この選手は速いんだろうか?(後になってわかるがこの選手、プロであった)
まぁともかく上位を狙う必要がないことと序盤であることで、チェックはせず。
結局誰も追い掛けずに、ジワジワ下がってくる。
そして集団に吸収され、暫くするとまた同じくブルブルチキンM内選手がアタック。
が、皆割と無反応。やはり準決勝だからか。
とはいえ俺にとっては決して遅くないペースで展開する。
ジワジワキツくなってきて、決勝もあって脚を残さないと、と思いつついい感じに下がろうとしていた。
すると後ろに居た練習仲間のG選手に
「こりゃー!崖島ー!お前エリート選手じゃろーが!下がってんじゃねーぞ!」
「おぃこら中切れぞ!」
という

喝を入れられるがなぜか笑っている様に見える Photo by Kohei T.
個人的にはE3って少なくともJBCFでは下っ端なので、E3って言われても何とも思わなかったろう。
しかしE3のEは「Elite」のEだ。「エリート選手」と言われると、良い意味で心に来るものがあった。
「エリート」と言われれば、無いプライドも湧いてくるもんだ。
と踏み直したのも束の間、いよいよ限界が近い。
どうにか後続に先に行ってもらい、こちらは後ろに下がる。
その周回の直後の15周目の南側の4番目の左コーナーで、前方10mくらいのあたりで落車!
そして直後に居たG選手も巻き込まれ落車!
コーナー出口でスピードが遅かったことと、後ろに下がってたことで距離があったことからどうにか躱す。
助かった。
助かったのはいいが、当然のようにそこから中切れが発生。
が、俺にはそれを埋める脚はもう残っていなかった。
じわじわ先頭集団と距離が開くなかF武さんがケツを軽くプッシュしてくれる。
その気持ちは大変嬉しかったが、残念ながら先立つものがないのできっちり追い縋ることもままならない。
と、続く周回でまたしても同じコーナーで落車が。
今度はそのF武さんが…!
何という因果。準決勝で俺に関わった2人とも落車ですよ…
そんなこんなで千切れながらも最終周回を迎えた。
多分大丈夫だと思うけど念のため前にいる選手1人くらいは捲ってゴールだ!
虚しさ溢れるスプリントをして無事ゴール!順位は18/28位で無事A決勝進出を決めた。
しかし後でリザルト見るとスプリントで抜かしたのは周回遅れの選手だったという何ともアレな無駄脚を使ってしまったらしい。
なおB決勝降格となった5人のうち4人は落車が決め手になった厳しい準決勝だった。
しかし上の2人とも、骨に異常が出るような大怪我でなかったようでよかった。
13:00 決勝前
さて、A決勝までは結構時間が余っていたので、カロリーメイトを一箱食って、車の日陰で30分程一寝入り。
この季節、駐車場に日陰があるのは本当に助かる。その後起き上がって水分をたっぷり補給。
恐らくレース中に飲む余裕は無いかもしれないので、準決勝と同じく事前にしっかり摂っておく。
しかし決勝は20周だったが、決勝は30周と比較的長丁場な上にこの暑さ。保険のために500ボトル半分程の水を入れておいた。かけることも考えて水だ。
14:50 決勝

ガケシマを探せ Photo by A. Harada
そしていよいよA決勝スタート前。
暑い。この中で30周も走りたくないな… と弱音を吐いても仕方ない。
しかし一応今回からはチームの看板背負って走るわけだし、良いとこ作りたい、との思いはあった。
なので決勝にはある7周回毎の周回賞は取りに行ってやる…。
なんならその後足切りになっても構わない。
去年の灘崎クリテでもそんな望みがあったがそれも虚しく、7周回目には既に息も絶え絶えだった思い出が過る。まぁ出方次第だ。
そんなこんなでスタート。
とりあえず準決勝と同じく前方で展開したいと思いながらも、思い通りの位置どりができず3周目ほどまで集団中盤で走る。
しかしやはり決勝、準決勝よりはハイペースには感じ、自分で下がらなくても後ろからどんどん被せられ位置が下がっていく。
これはあまり良くない展開だと感じながら7周回目を迎えた。
これは行っとくか?と思ったら周りが案外ペースが上がっていない。
これはチャンス! と思い位置を上げていき、最終抜けて渾身のスプリントで周回賞を取りに行く。
しかし集団前方のペース=周回賞へのモチベーションが異常に低い。
ストレート半分程走ったところで、遥か先の方に選手が。
周回遅れ…じゃないな!
逃げてる!
あっかーん…そりゃみんなポイント周回頑張らん筈だわ。
とうの昔に周回賞取られてたわけだ。
落胆しつつ、息切れしつつも、それが逆に功を奏し、先頭周辺に躍り出ることができた。
しかし自分の地脚の程度からしても良いペースで牽けるわけもなく、暫くしたら後ろに下がることになった。
後ろに下がったら当然最初と同じくインターバルがきつくなる。
中ほどやや後ろに位置していたN村さんに必死に食いつく。

Photo by A. Harada
奈良クリテでのインターバル死の反省から、今回はきっちり後ろにつく、コーナー前でギアを落とす、コーナーのラインは正確に、を意識したがまだまだ足りないようだ。
じわじわ置いていかれる。かといって立ち上がりで早めにペダリングを始めるのも気がひける。
今日のレースでは特にペダルヒットでの落車をよく見たからだ。
となると、どうすれば省エネできるかを考えた。
前走者と同じラインを走ってては立ち上がりでのインターバルは少なからずかかってしまう。
となれば、違うラインでいけばいいのか。
まずはインベタで回ってみる。
これはライン選択の優位はあるものの速度が殺され過ぎてしまい、余計インターバルが掛かってしまった。
次にアウトインアウト。
前走者とラインがほぼ被るのでだめ。
その次はクリップ奥目のスローインファストアウト。
これも前走者との距離がコーナー中に開いてしまうのでそんなに変わずインターバルがかかる気がする。
そしてアウトアウトアウト。
今回はこれだ。
ラインが被らないのでブレーキをかける必要も少なく、スピードをあまり殺さず曲がれた。
しかしあくまでこの序盤から中盤までの、勝負がかかっていない時に通用しやすいラインだろう。
終盤だとイン側からアウトにはらんだ選手に押し出されコースアウトしてしまう可能性があるので、場面を考えないと落車に繋がる。
後半になり集団が伸び気味になってくると、バックストレート半分あたりからコースティングで最終コーナーまで付いていける。
これは助かる。しかし多少はマシになったもののホーム/バックストレートの立ち上がりには依然としてかかってしまうインターバルでじわじわ消耗する。
逃げが吸収されたあとのポイント周回も、踏み込む元気はなくただひたすら集団から切れないように堪えるといった状況。
コーナーリングラインの試行錯誤と忍耐で周回数を重ねていき、ふと見ると残り3周。
「もういいだろ…ここから流しても脚切りにはならんよ、やめやめ」とかいう悪魔(?)の囁き。
「もう少しで集団維持でゴールできるんだ、最後まで踏めよ!」という天使(?)の励まし。
この葛藤が朦朧とした意識の中で行われていた。
が、どうやら体力と天使が打ち勝ったようで、最終周に突入。
最早着に絡む脚は残ってないにしても、安全に配慮しつつ可能な限り着順上げてやる!
最終コーナーを抜け最後の力を振り絞ってスプリントにならないスプリントを掛ける。
ここでB決勝とかなら経験上は何人か捲れるんだけど、流石のA決勝はそうはいかなかった。
順位維持でそのままゴール。前を走るE2のO森さんには追いつけず、12位での幕引きとなった。
なお優勝は準決勝でアタックを掛けまくっていたM内選手、最初に逃げていた選手は落車というドラマがあったようだ。
(M内選手は同じチームで3人居たけど、兄弟かな?)

無駄なあがき Photo by Gentatsu
分析
走行ログを見ての分析をしてみた。

準決勝チャート
準決勝でG選手に喝を入れられた13周目は1000Wくらい踏んでる。
その次の周に落車で中切れ、気持ちが切れて、W’balが上向いてきているのがわかる。

決勝チャート
一方決勝のW’balを見ると、7周目まででどんどん消耗しているのがわかる。
出力曲線に目を移すと、後半の周回と比べて踏んでいるときの出力が800Wを超える周も3回ある。
テーブルの方を見るとノンゼロの出力が300~400W。なるほどこれで消耗していたわけだ。
そして決勝一番特徴的だったのはやはり7周目からの先頭周辺での走行。
明らかにLap最大パワーが低く、そこから徐々にLap最大パワーが上がっている。
位置が後ろに下がりインターバルがきつくなっているのが如実にわかった。
データを掘ればもっといろいろなことがわかるだろうが今回はこの辺にしておこう。
総括
当初の目標であったA決勝完走は、一応ギリギリ集団ゴールという比較的良い形での達成となった。
しかし各レースともに入賞やポイント賞はなく、物的には得るものは全くなくそこが残念でなくはないが。
コーナリングのライン取りや脚の抜き方については学びがあったが、前回のシフトダウンやライン精度についてはまだまだだ。
この反省を再度次回に繋げて行こう。
ネクストガケシマ’s ヒント!
「舞洲」
終わり
- [ edit ]
- ロードバイク
- / trackback:0
- / comment:0
JBCF奈良クリテリウム
奈良クリテリウム
目標
10位以内
結果
未達(31位/49人)
経緯
今シーズンに入って自転車関連レースでカテゴリ優勝を2回して、調子に乗って実業団(JBCF)選手登録しようと画策していた。そこへ、東京のサイクリストの友人がチームへ入らないかと誘ってくれたので、そこに入る決意をした。
チームの名前は
「パラティアム東京」、
2016年発足の新興チームだ。
文字通り東京を本拠地として活動しているチームではあるが、そこの練習に縁あって数回参加したこともきっかけだ。
パラティアム東京のチームメンバーは俺以外は東京近郊在住。なので西日本の首都とも呼ばれている[要出展]大都会岡山在住の俺はパラティアム東京・西日本支部を自称することにした。
ということで、先月晴れて実業団チーム入りした俺は、さっそく直近のJBCF主催レースの奈良クリテリウムに参加することにした。いわゆるデビュー戦だ。
ちなみに、なじみのない方々にごく簡単に説明すると、実業団連盟が取り決めているレーサーのカテゴリはP、E1、E2、E3、Fの5カテゴリで、男性はP(Pro)が一番速いカテゴリで、続いてE1,E2とありE3が実業団入門カテゴリである。Fは女性
(Feminine)レーサーのカテゴリだ。実業団登録すると、一部例外を除きE3からスタート、レースでの順位などによる実績でE3→E2→E1と昇格するしくみだ。
コース
奈良クリテは今年から開催される新しいコースでのレースだ。ロケーションは、奈良は大和郡山市の浄水場公園を周回する1周2.8キロのコース。そのコースをE3は5周する、はずだった。しかし各カテゴリとも全体的に参加者が多いことから開催の2週間ほど前に、4周に減った。さらに1km程度のローリングスタートとなったので実質10km程度で、クリテの中でもかなり距離が短いスプリントレースとなった。
ここからが本題。奈良クリテは基本的には浄水場の周囲の公園の中の道を通るコースだ。
ここは通常自転車が飛ばして走るような道ではないというのが予想はされていた。
まずレース開催概要にあるコースレイアウトからしてある程度ヤバさは出ていた。3日ほど前までの事前情報からはクランクコーナー3か所がヤバさのポイントだと思っていた。各クランクコーナーはかなりコース幅が絞られているので、落車のリスクが高くなおかつ立ち上がり加速のインターバルが強いことは目に見えていた。
しかし本当に怖いポイントは、前日位から現地で歩いた人や当日試走で続々と発覚してきた。
周回後半に連続する各直角コーナー。こいつらは、コースレイアウト図の線で見る限りでは特にこれといったヤバさは感じられない。しかし実際のコーナー路面は…
・舗装が古く荒れていて、タイヤとの接地面は少なくなる。
・グレーチングがある。実走時はフェルトのようなカバーがされるが、
アスファルトほどのグリップは期待できない。
・普段「門のレール」や「車止めポール」があるところがあり、ポールは取り外されるにしても、
支持元の金属部分は残っており、踏むとパンクやスリップの起点となる。
・マンホールがあり、その周囲が15cm程度盛り上がっている。
段差を超えることによるスリップ、逆バンクとなることによるグリップ低下が予想される。
と、かなり危険だ。
さらに悪いことに、当日は雨が予想されていた。
濡れると当然のことさらに状況は悪化する。
現状分析とトレーニング
前回の灘崎クリテと同じく、自分の特性を活かすには繰り返しの立ち上がりインターバルに耐えて最後まで脚を残しておかなければならない。
今までのレースからはレベルが更に上るので、よりインターバルの強度、巡航速度も高くなると予想される。
なので、今やるべきことは短時間高強度インターバルトレーニングだろう。
目標設定
調子に乗っているのでデビュー戦入賞を狙う。
が、まぁそううまくもいかないだろうなぁ。できて10位以内くらいか。
しかし集団の後ろのほうに行ってしまったらインターバルきつくてちぎれてしまうかも。
そうなった場合先頭から1分差でDNFルールが適用されるのでやばい。
落車に巻き込まれたり、落車の後ろにいたらアウトだ。
コースレイアウト的にも「落車なく」「完走する」ことが第一目標か。
往路
0315 起床
前日は決起集会的な夕食有りなんだかんだで寝たのは23時くらいか。前々日まではレース展開を思い浮かべるとアドレナリンが分泌されて心拍上がって眠れなくなってたんだけど、前日は就寝即入眠だった。この辺はよくコントロールできてるのか?しかし絶対的に睡眠時間少ないので眠い。
当日は同じ奈良クリテに出るSauceDevelopmentの面々と某TrailBlazerエースで乗り合って行く予定だったので、どうにか眠い身体を叩き起こし自転車その他を車に積み込み用意をして集合場所へ出発。
0420 集合・出発
集合した後は難なく積み込みも完了し、一路奈良へ。SauceのM君は奈良地元なのですんなり到着するだろう。
…ほんとに一路だった。No休憩で岡山→奈良。道は渋滞も全くなくすんなり。
しかし、高速を降り奈良の地に降り立った途端、前を走る軽自動車が十字路手前で左ウインカーを出し前走車を右に避け、右に曲がっていった。
何一つ合っていないぞ。
これが奈良か…!
そして前走してくれていたM君カーが左に入る。行く先は、
…パチ屋?
違う!
下っ端選手の駐車場となる奈良健康ランドだった。この建物…完全にパチ屋でしょ。
そしてそのパチ屋の駐車場で、フィットネスバイク風のものを漕ぐ全身タイツ男が1,2名(実際は3本ローラーでアップしていたものと思われる)。
場違い感半端ない。ここでアップはできないな…(個人的には本日もアップする気あんまりなし)
到着後、自転車を出しバックパックに荷物を詰め受付へ。
しかし下っ端とはいえ会場遠いんだよ畜生(2.8km、ビンディングで歩いて行く気にはならない距離)。
0730 会場に到着
パラティアム東京の仲間Sさん、Oさんと再開。受付を済ませる。
もう一人自走で来るらしいMさんと俺、今回奈良クリテ出場のパラティアム東京メンバーは全員E3だ。E3は14時以降からで、試走時間は8時からと昼過ぎの2回あるけど、コースがコースだけに2回見ておいた方が無難だ。さて、0800から試走時間だ。よくコース見とかないと…
と意気込んでいると、Sさん、Oさんに「朝飯行こうよ!」と誘われた。
(え、試走は…?)
確かに試走時間は昼過ぎにも設けられている。でも、先に試走しときたくない…?
しかしここは空気を読んで朝飯に一緒に行くことに!
0830 会場から車で約15分の「カフェ マイゲベック」
Sさん「(崖島)君、余裕だねー試走もしないなんて笑」
俺「いやいや、余裕なんて全くないんですが笑 Sさんは?」
Sさん「俺?俺はもう昨日終わったから。ツールド大仏」
俺「」
完全にやらかした。サンドウィッチカフェモーニングしてる場合じゃない。
とりあえずここでできることは…
レーサーリストを見て対策を立てることか!
まず知っている情報だけで
○某ETTの教祖、M君
○ヴィクトワールのN村さん(元プロクラス)
俺より確実に速いのが2人。俺が勝ち目ありそうな人は、知る限りはいない。
これ確率的には詰んでるよね。
Sさん「プロってったって「元」でしょ?だいじょぶだいじょぶ!」
俺 「いやいや元プロなら十分速いでしょ…」
Sさん「プロだった人でも1年練習してなかったら、ただの人だからねぇ。
しかもE3のレースでたぶんナメてるでしょ。勝てるって!」
(名前で戦績ググってみる)
俺 「全日本学生選手権クリテC1、4位ですね」
Sさん「昔の話でしょ」
俺 「2016/4/29」
Sさん 「」
やっぱりやらかしてたよね。
ま、試走1回だろうが2回だろうがVO2Maxが上がるわけじゃないし!
気を取り直して行こう!
カフェから会場への帰りに、奈良健康ランドでおろしてもらい、ホイールを雨対策でF6RからKsyrium/Rsysに換装。ブレーキパッドも変えないといけないのでめんどくさかった。
そんなこんなで、E3レース本番まではたくさんの自転車関連ツイッタフォロワーの面々とお会いすることができた。
レースはほぼオフ会といっても差支えないし、これもレースの楽しみの一つだ。
ちなみに昼食は摂らずに臨む。食うのはコリスのラムネとアンパン1個。
午前中にカロリー摂ったから、スプリントレースだし必要ないだろうと考えた。
ちなみにボトルは水を半分ほど。
待ち時間に飲む程度で、レース中に飲む気はほとんどなし。
てかそんな余裕なさそう。
機材
フレーム:Bianchi Sempre
ホイール:F Ksyrium SL/ R R-sys
チェーンリング:Powerring53T/O'symetric42T
スプロケット:CS6700 12-25T
タイヤ:F Ultremo ZX 23C / R Powerlink 23C
今回のコースはいつもに増して落車の確率が高くなりそうなのでフレームはSempre。(RXRSをクリテに出すときは来るのだろうか…)
そしてホイール、いつもの平地レースは空力とモチベーションのためにカーボンディープリムのF6Rを前後に履いているが、このホイールはウエットコンディションだとブレーキ性能が極端に悪い。
以前通勤で使っていて雨にふられた時には、本当にブレーキワイヤーが切れたかと思うぐらい初期タッチが悪かった。なお、チームメイトのSさんに「F6Rつけてたら検車でNGになるよ!」と言われるぐらいブレーキ性能はやばいらしいが、ドライなら決定的に悪いとは思ってないので晴天では使っている。
ということで、出発時にはF6Rを装着していたが、奈良に到着の時点でレース時間の降水確率が極めて高かったので雨天用スペアホイールとして予め準備しておいたアルミクリンチャーのKsyrium SL/Rsysに換装。なぜリアもKsyriumにしないかといえば、自分のKsyriumは11sかつカンパフリーなので10sのSempreには付かないからだ。平地レースなのでスポークの空力が悪そうなのは避けたかったが致し方なし。
スプロケットは12-23は1つしか持っていないので、あまりの12-25で。
戦略
1.コースレイアウトと天候から予想されることは「落車が多くなる」ということ。
まず落車しないように走らないと10位以内達成は難しい。
落車に巻き込まれないためにはできるだけ前のほうで走ればいい。
そしてまた体力的な面でも、コーナーが多く加減速が多くなる。
インターバルが少しでもましな上位数名の位置をキープするのがベターだろう。
2.コーナーが多いこと、裏ストレートの道幅が狭いことから抜き所が少ない。
また、単純にレース距離が短い。
この2つから導き出された戦略としては「最初から先頭周辺をキープする」というもの。
ローリングスタートの時点で最前列に位置取り、リアルスタートと同時にダッシュして先頭周辺をキープする。
あとはその位置をキープできていて余裕があれば2周目1位通過のポイント賞も狙う。
と書いてみたけど、昼前のE2でポイント賞副賞の内容が判明。
「奈良健康ランド賞」…奈良健康ランド利用3000円分
…うん、いらん。
ポイント周回ゲットのモチベーション下がった。
3周目以降のアタックには反応する。
しかし万が一自分がゴール前まで脚をためることができれば勝機がないわけではない、という程度で基本勝てる見込みはない、か…消極的だがしかたない。
実戦
1410 待機
出走サインをして、待機場所に自転車を置き余裕をこいて観戦していたら、いつのまにかE3-2組が待機場所に集合、俺の自転車置いてきぼり!な事態に。急いでストレート前の第2(?)待機場所に。ここの位置取りは2列目。まぁ悪くないか。ローリングで順位あげたろ…
雨がぱらついている。今は路面はドライだけど、スタートまでにどうなることやら…なんとか持ってほしい。
こういうの、俺は結構大事な時は雨降らずもってくれるんだけど、どうなんだろうなぁ。
まぁ雨神Kuego君はE3-2組だし大丈夫だろう。
そしてスタートラインへ誘導。ここでも微妙に位置取り争いが。しかし2列目をキープ。

Photo by 西村さん この頃はまだまだ元気である
1441 1st Lap ローリングスタート開始
路面はほぼドライ。なんとか持ってくれよと思いつつスタート。ほぼ2列目をキープしながら先導バイクと前走者を視界に入れ走る。ローリングスタートといっても35km/h出てる。
そして第1シケインを通過後、リアルスタート!一旦シケインでペースが落ちたが一気に43km/hくらいにまで上がる。ここは先頭から3,4番目をキープ。この位置ならまだインターバルがゆるい。大丈夫、これはいけるか?
この時はまだ元気。ログを見ると2個目シケイン立ち上がりで1000W近く踏んでる。なんと無駄脚な。
2nd Lap
と走っていたが、コーナー毎の減速が結構大きくインターバル加速で脚を削られる。
きつい、きついよ…これはヤバい展開だ。路面はまだドライ。幸いまだコーナーで危険な目にはあっていない。しかし辛い。頭がクラクラする。先頭集団の中でじわじわ順位が落ちていく。あとで反省するところではあるけど、自分の動きが雑過ぎて無駄に体力を削っている気がする。2周目後半でチームメイトMさんに抜かれる。役立たずで申し訳ない…
3rd Lap
ついに先頭集団から千切れた。時間の問題とは思っていたけど、最終周まで堪えたかったが、体力の限界だった。裏ストレート立ち上がり食い下がろうとするも自分の脚がタレるのが早い。集団が遠ざかっていくのを若干朦朧とした意識で感じながら直角コーナー区間に突入。ここからは完走目標に切り替えるしかない。2つ目の直角コーナーでは毎周回「明日は仕事~!」とのガヤが。やかましいわ!知っとるわ、それどころちゃうわこっちは!畜生!
Final Lap
ぽつりぽつりと後続に追い抜かれていくも追い縋る気力体力はほとんど残っておらず。さらに後ろから選手数名のグルペット(?)に「(ローテ)回して行こう!」と声を掛けてもらうも瀕死のこちらは声にならない「(むりぃぃぃぃ!)」しかしどうにかこの集団には付いていく。そして残り300m、最後の直角を抜け、ここからが勝負!…なわけない。もう先頭はゴールしてるだろうし何位だかわからんけどまぁケツに近いだろうな、完走できそうだし良しとするか…。もうさっきの集団もばらばら。最終シケインを抜け少し行ったところで、わずかに残った脚でへなちょこスプリント!出し殻になってやる!ペダルを踏みつけた!しかし何も起こらなかった。後でログを見ると600Wも出てない。なんてこった。

Photo by 西村さん 3,4周目の後方集団。雨粒が見える。
総括
出た順位は31位。残念だ…しかしこれが実力か。これが実業団か。自分の弱さを噛みしめた。
自分のパフォーマンスを見返す。
出力
Ave 233W
xPower 240W
NonZeroAve 274W
Max 991W
そこそこ低く抑えられてるのかな?しかし数値的にこの程度でちぎれるということは、インターバルに堪えられなかったってことだろう。やはりまだ弱点なようだ。しかし1周目で1000W近くだしてりゃそりゃちぎれもするわ。しかしW’balanceが+4%だったので、まだ追い込めたということか。
心拍数
Ave 201bpm
Max 208bpm
…きついわけだ。こんな心拍数でよく生きてるな俺。これに見合ったパワーが出てれば文句はないんだけど。
トップとの差:38秒差
ま、これくらい差はつくわな…あと1周あったらDNFだったかも。
今後の方針
今回はダメなところが目立った。というかいいとこひとつもなかったんじゃないか?強いて言えば落車しなかったことくらいか。
・インターバルがまだまだ弱い
・コーナー前できっちりシフトダウンしていないので立ち上がり重いギア踏みがち。
・コーナーのライン取りが雑。
・もっと前走者と距離を詰めてもいい。
・下がるな、余計キツイぞ。
以降はこれをキモに頑張っていくこととする。
おまけ
帰路、ナビに阪神高速を指定され渋滞にハマり車でもインターバル地獄に。辛かった。帰りはさすがに三木サービスエリアで夕食休憩。味噌ラーメンが結構うまかった。あと雨ひどすぎ。視界がめちゃ悪くて100km/hそこそこでも危険を感じた。
さーて、次回の崖島さんは?
・カートコースクリテリウム(中山)
・舞洲
・きらら浜
の3本、かな?予定は未定だけど基本平地だ。
ではまたレース会場でお会いしましょう。
おわり
目標
10位以内
結果
未達(31位/49人)
経緯
今シーズンに入って自転車関連レースでカテゴリ優勝を2回して、調子に乗って実業団(JBCF)選手登録しようと画策していた。そこへ、東京のサイクリストの友人がチームへ入らないかと誘ってくれたので、そこに入る決意をした。
チームの名前は
「パラティアム東京」、
2016年発足の新興チームだ。
文字通り東京を本拠地として活動しているチームではあるが、そこの練習に縁あって数回参加したこともきっかけだ。
パラティアム東京のチームメンバーは俺以外は東京近郊在住。なので西日本の首都とも呼ばれている[要出展]大都会岡山在住の俺はパラティアム東京・西日本支部を自称することにした。
ということで、先月晴れて実業団チーム入りした俺は、さっそく直近のJBCF主催レースの奈良クリテリウムに参加することにした。いわゆるデビュー戦だ。
ちなみに、なじみのない方々にごく簡単に説明すると、実業団連盟が取り決めているレーサーのカテゴリはP、E1、E2、E3、Fの5カテゴリで、男性はP(Pro)が一番速いカテゴリで、続いてE1,E2とありE3が実業団入門カテゴリである。Fは女性
(Feminine)レーサーのカテゴリだ。実業団登録すると、一部例外を除きE3からスタート、レースでの順位などによる実績でE3→E2→E1と昇格するしくみだ。
コース
奈良クリテは今年から開催される新しいコースでのレースだ。ロケーションは、奈良は大和郡山市の浄水場公園を周回する1周2.8キロのコース。そのコースをE3は5周する、はずだった。しかし各カテゴリとも全体的に参加者が多いことから開催の2週間ほど前に、4周に減った。さらに1km程度のローリングスタートとなったので実質10km程度で、クリテの中でもかなり距離が短いスプリントレースとなった。
ここからが本題。奈良クリテは基本的には浄水場の周囲の公園の中の道を通るコースだ。
ここは通常自転車が飛ばして走るような道ではないというのが予想はされていた。
まずレース開催概要にあるコースレイアウトからしてある程度ヤバさは出ていた。3日ほど前までの事前情報からはクランクコーナー3か所がヤバさのポイントだと思っていた。各クランクコーナーはかなりコース幅が絞られているので、落車のリスクが高くなおかつ立ち上がり加速のインターバルが強いことは目に見えていた。
しかし本当に怖いポイントは、前日位から現地で歩いた人や当日試走で続々と発覚してきた。
周回後半に連続する各直角コーナー。こいつらは、コースレイアウト図の線で見る限りでは特にこれといったヤバさは感じられない。しかし実際のコーナー路面は…
・舗装が古く荒れていて、タイヤとの接地面は少なくなる。
・グレーチングがある。実走時はフェルトのようなカバーがされるが、
アスファルトほどのグリップは期待できない。
・普段「門のレール」や「車止めポール」があるところがあり、ポールは取り外されるにしても、
支持元の金属部分は残っており、踏むとパンクやスリップの起点となる。
・マンホールがあり、その周囲が15cm程度盛り上がっている。
段差を超えることによるスリップ、逆バンクとなることによるグリップ低下が予想される。
と、かなり危険だ。
さらに悪いことに、当日は雨が予想されていた。
濡れると当然のことさらに状況は悪化する。
現状分析とトレーニング
前回の灘崎クリテと同じく、自分の特性を活かすには繰り返しの立ち上がりインターバルに耐えて最後まで脚を残しておかなければならない。
今までのレースからはレベルが更に上るので、よりインターバルの強度、巡航速度も高くなると予想される。
なので、今やるべきことは短時間高強度インターバルトレーニングだろう。
目標設定
調子に乗っているのでデビュー戦入賞を狙う。
が、まぁそううまくもいかないだろうなぁ。できて10位以内くらいか。
しかし集団の後ろのほうに行ってしまったらインターバルきつくてちぎれてしまうかも。
そうなった場合先頭から1分差でDNFルールが適用されるのでやばい。
落車に巻き込まれたり、落車の後ろにいたらアウトだ。
コースレイアウト的にも「落車なく」「完走する」ことが第一目標か。
往路
0315 起床
前日は決起集会的な夕食有りなんだかんだで寝たのは23時くらいか。前々日まではレース展開を思い浮かべるとアドレナリンが分泌されて心拍上がって眠れなくなってたんだけど、前日は就寝即入眠だった。この辺はよくコントロールできてるのか?しかし絶対的に睡眠時間少ないので眠い。
当日は同じ奈良クリテに出るSauceDevelopmentの面々と某TrailBlazerエースで乗り合って行く予定だったので、どうにか眠い身体を叩き起こし自転車その他を車に積み込み用意をして集合場所へ出発。
0420 集合・出発
集合した後は難なく積み込みも完了し、一路奈良へ。SauceのM君は奈良地元なのですんなり到着するだろう。
…ほんとに一路だった。No休憩で岡山→奈良。道は渋滞も全くなくすんなり。
しかし、高速を降り奈良の地に降り立った途端、前を走る軽自動車が十字路手前で左ウインカーを出し前走車を右に避け、右に曲がっていった。
何一つ合っていないぞ。
これが奈良か…!
そして前走してくれていたM君カーが左に入る。行く先は、
…パチ屋?
違う!
下っ端選手の駐車場となる奈良健康ランドだった。この建物…完全にパチ屋でしょ。
そしてそのパチ屋の駐車場で、フィットネスバイク風のものを漕ぐ全身タイツ男が1,2名(実際は3本ローラーでアップしていたものと思われる)。
場違い感半端ない。ここでアップはできないな…(個人的には本日もアップする気あんまりなし)
到着後、自転車を出しバックパックに荷物を詰め受付へ。
しかし下っ端とはいえ会場遠いんだよ畜生(2.8km、ビンディングで歩いて行く気にはならない距離)。
0730 会場に到着
パラティアム東京の仲間Sさん、Oさんと再開。受付を済ませる。
もう一人自走で来るらしいMさんと俺、今回奈良クリテ出場のパラティアム東京メンバーは全員E3だ。E3は14時以降からで、試走時間は8時からと昼過ぎの2回あるけど、コースがコースだけに2回見ておいた方が無難だ。さて、0800から試走時間だ。よくコース見とかないと…
と意気込んでいると、Sさん、Oさんに「朝飯行こうよ!」と誘われた。
(え、試走は…?)
確かに試走時間は昼過ぎにも設けられている。でも、先に試走しときたくない…?
しかしここは空気を読んで朝飯に一緒に行くことに!
0830 会場から車で約15分の「カフェ マイゲベック」
Sさん「(崖島)君、余裕だねー試走もしないなんて笑」
俺「いやいや、余裕なんて全くないんですが笑 Sさんは?」
Sさん「俺?俺はもう昨日終わったから。ツールド大仏」
俺「」
完全にやらかした。サンドウィッチカフェモーニングしてる場合じゃない。
とりあえずここでできることは…
レーサーリストを見て対策を立てることか!
まず知っている情報だけで
○某ETTの教祖、M君
○ヴィクトワールのN村さん(元プロクラス)
俺より確実に速いのが2人。俺が勝ち目ありそうな人は、知る限りはいない。
これ確率的には詰んでるよね。
Sさん「プロってったって「元」でしょ?だいじょぶだいじょぶ!」
俺 「いやいや元プロなら十分速いでしょ…」
Sさん「プロだった人でも1年練習してなかったら、ただの人だからねぇ。
しかもE3のレースでたぶんナメてるでしょ。勝てるって!」
(名前で戦績ググってみる)
俺 「全日本学生選手権クリテC1、4位ですね」
Sさん「昔の話でしょ」
俺 「2016/4/29」
Sさん 「」
やっぱりやらかしてたよね。
ま、試走1回だろうが2回だろうがVO2Maxが上がるわけじゃないし!
気を取り直して行こう!
カフェから会場への帰りに、奈良健康ランドでおろしてもらい、ホイールを雨対策でF6RからKsyrium/Rsysに換装。ブレーキパッドも変えないといけないのでめんどくさかった。
そんなこんなで、E3レース本番まではたくさんの自転車関連ツイッタフォロワーの面々とお会いすることができた。
レースはほぼオフ会といっても差支えないし、これもレースの楽しみの一つだ。
ちなみに昼食は摂らずに臨む。食うのはコリスのラムネとアンパン1個。
午前中にカロリー摂ったから、スプリントレースだし必要ないだろうと考えた。
ちなみにボトルは水を半分ほど。
待ち時間に飲む程度で、レース中に飲む気はほとんどなし。
てかそんな余裕なさそう。
機材
フレーム:Bianchi Sempre
ホイール:F Ksyrium SL/ R R-sys
チェーンリング:Powerring53T/O'symetric42T
スプロケット:CS6700 12-25T
タイヤ:F Ultremo ZX 23C / R Powerlink 23C
今回のコースはいつもに増して落車の確率が高くなりそうなのでフレームはSempre。(RXRSをクリテに出すときは来るのだろうか…)
そしてホイール、いつもの平地レースは空力とモチベーションのためにカーボンディープリムのF6Rを前後に履いているが、このホイールはウエットコンディションだとブレーキ性能が極端に悪い。
以前通勤で使っていて雨にふられた時には、本当にブレーキワイヤーが切れたかと思うぐらい初期タッチが悪かった。なお、チームメイトのSさんに「F6Rつけてたら検車でNGになるよ!」と言われるぐらいブレーキ性能はやばいらしいが、ドライなら決定的に悪いとは思ってないので晴天では使っている。
ということで、出発時にはF6Rを装着していたが、奈良に到着の時点でレース時間の降水確率が極めて高かったので雨天用スペアホイールとして予め準備しておいたアルミクリンチャーのKsyrium SL/Rsysに換装。なぜリアもKsyriumにしないかといえば、自分のKsyriumは11sかつカンパフリーなので10sのSempreには付かないからだ。平地レースなのでスポークの空力が悪そうなのは避けたかったが致し方なし。
スプロケットは12-23は1つしか持っていないので、あまりの12-25で。
戦略
1.コースレイアウトと天候から予想されることは「落車が多くなる」ということ。
まず落車しないように走らないと10位以内達成は難しい。
落車に巻き込まれないためにはできるだけ前のほうで走ればいい。
そしてまた体力的な面でも、コーナーが多く加減速が多くなる。
インターバルが少しでもましな上位数名の位置をキープするのがベターだろう。
2.コーナーが多いこと、裏ストレートの道幅が狭いことから抜き所が少ない。
また、単純にレース距離が短い。
この2つから導き出された戦略としては「最初から先頭周辺をキープする」というもの。
ローリングスタートの時点で最前列に位置取り、リアルスタートと同時にダッシュして先頭周辺をキープする。
あとはその位置をキープできていて余裕があれば2周目1位通過のポイント賞も狙う。
と書いてみたけど、昼前のE2でポイント賞副賞の内容が判明。
「奈良健康ランド賞」…奈良健康ランド利用3000円分
…うん、いらん。
ポイント周回ゲットのモチベーション下がった。
3周目以降のアタックには反応する。
しかし万が一自分がゴール前まで脚をためることができれば勝機がないわけではない、という程度で基本勝てる見込みはない、か…消極的だがしかたない。
実戦
1410 待機
出走サインをして、待機場所に自転車を置き余裕をこいて観戦していたら、いつのまにかE3-2組が待機場所に集合、俺の自転車置いてきぼり!な事態に。急いでストレート前の第2(?)待機場所に。ここの位置取りは2列目。まぁ悪くないか。ローリングで順位あげたろ…
雨がぱらついている。今は路面はドライだけど、スタートまでにどうなることやら…なんとか持ってほしい。
こういうの、俺は結構大事な時は雨降らずもってくれるんだけど、どうなんだろうなぁ。
まぁ雨神Kuego君はE3-2組だし大丈夫だろう。
そしてスタートラインへ誘導。ここでも微妙に位置取り争いが。しかし2列目をキープ。

Photo by 西村さん この頃はまだまだ元気である
1441 1st Lap ローリングスタート開始
路面はほぼドライ。なんとか持ってくれよと思いつつスタート。ほぼ2列目をキープしながら先導バイクと前走者を視界に入れ走る。ローリングスタートといっても35km/h出てる。
そして第1シケインを通過後、リアルスタート!一旦シケインでペースが落ちたが一気に43km/hくらいにまで上がる。ここは先頭から3,4番目をキープ。この位置ならまだインターバルがゆるい。大丈夫、これはいけるか?
この時はまだ元気。ログを見ると2個目シケイン立ち上がりで1000W近く踏んでる。なんと無駄脚な。
2nd Lap
と走っていたが、コーナー毎の減速が結構大きくインターバル加速で脚を削られる。
きつい、きついよ…これはヤバい展開だ。路面はまだドライ。幸いまだコーナーで危険な目にはあっていない。しかし辛い。頭がクラクラする。先頭集団の中でじわじわ順位が落ちていく。あとで反省するところではあるけど、自分の動きが雑過ぎて無駄に体力を削っている気がする。2周目後半でチームメイトMさんに抜かれる。役立たずで申し訳ない…
3rd Lap
ついに先頭集団から千切れた。時間の問題とは思っていたけど、最終周まで堪えたかったが、体力の限界だった。裏ストレート立ち上がり食い下がろうとするも自分の脚がタレるのが早い。集団が遠ざかっていくのを若干朦朧とした意識で感じながら直角コーナー区間に突入。ここからは完走目標に切り替えるしかない。2つ目の直角コーナーでは毎周回「明日は仕事~!」とのガヤが。やかましいわ!知っとるわ、それどころちゃうわこっちは!畜生!
Final Lap
ぽつりぽつりと後続に追い抜かれていくも追い縋る気力体力はほとんど残っておらず。さらに後ろから選手数名のグルペット(?)に「(ローテ)回して行こう!」と声を掛けてもらうも瀕死のこちらは声にならない「(むりぃぃぃぃ!)」しかしどうにかこの集団には付いていく。そして残り300m、最後の直角を抜け、ここからが勝負!…なわけない。もう先頭はゴールしてるだろうし何位だかわからんけどまぁケツに近いだろうな、完走できそうだし良しとするか…。もうさっきの集団もばらばら。最終シケインを抜け少し行ったところで、わずかに残った脚でへなちょこスプリント!出し殻になってやる!ペダルを踏みつけた!しかし何も起こらなかった。後でログを見ると600Wも出てない。なんてこった。

Photo by 西村さん 3,4周目の後方集団。雨粒が見える。
総括
出た順位は31位。残念だ…しかしこれが実力か。これが実業団か。自分の弱さを噛みしめた。
自分のパフォーマンスを見返す。
出力
Ave 233W
xPower 240W
NonZeroAve 274W
Max 991W
そこそこ低く抑えられてるのかな?しかし数値的にこの程度でちぎれるということは、インターバルに堪えられなかったってことだろう。やはりまだ弱点なようだ。しかし1周目で1000W近くだしてりゃそりゃちぎれもするわ。しかしW’balanceが+4%だったので、まだ追い込めたということか。
心拍数
Ave 201bpm
Max 208bpm
…きついわけだ。こんな心拍数でよく生きてるな俺。これに見合ったパワーが出てれば文句はないんだけど。
トップとの差:38秒差
ま、これくらい差はつくわな…あと1周あったらDNFだったかも。
今後の方針
今回はダメなところが目立った。というかいいとこひとつもなかったんじゃないか?強いて言えば落車しなかったことくらいか。
・インターバルがまだまだ弱い
・コーナー前できっちりシフトダウンしていないので立ち上がり重いギア踏みがち。
・コーナーのライン取りが雑。
・もっと前走者と距離を詰めてもいい。
・下がるな、余計キツイぞ。
以降はこれをキモに頑張っていくこととする。
おまけ
帰路、ナビに阪神高速を指定され渋滞にハマり車でもインターバル地獄に。辛かった。帰りはさすがに三木サービスエリアで夕食休憩。味噌ラーメンが結構うまかった。あと雨ひどすぎ。視界がめちゃ悪くて100km/hそこそこでも危険を感じた。
さーて、次回の崖島さんは?
・カートコースクリテリウム(中山)
・舞洲
・きらら浜
の3本、かな?予定は未定だけど基本平地だ。
ではまたレース会場でお会いしましょう。
おわり
- [ edit ]
- ロードバイク
- / trackback:0
- / comment:0
プロフィール
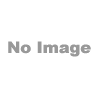
Author:Gakeshima
Twitter: @ang_orchestra
Instagram: gakestagram
Soundcloud: ANG Orchestra
Flickr: Gakeshima
最新記事
最新コメント
月別アーカイブ
- 2022/02 (1)
- 2021/10 (1)
- 2021/07 (1)
- 2021/02 (1)
- 2021/01 (1)
- 2020/12 (2)
- 2020/11 (1)
- 2020/05 (1)
- 2019/09 (2)
- 2019/05 (1)
- 2019/02 (1)
- 2019/01 (2)
- 2018/09 (1)
- 2018/07 (1)
- 2018/05 (2)
- 2018/01 (1)
- 2017/10 (2)
- 2017/09 (1)
- 2017/05 (3)
- 2017/04 (2)
- 2016/10 (1)
- 2016/09 (3)
- 2016/08 (1)
- 2016/07 (2)
- 2016/06 (1)
- 2016/04 (1)
- 2015/10 (2)
- 2015/08 (2)
- 2015/04 (3)
- 2015/03 (1)
- 2015/02 (2)
- 2015/01 (2)
- 2014/12 (2)
- 2014/11 (3)
- 2014/10 (4)
- 2014/09 (4)
- 2014/08 (1)
- 2014/07 (1)
- 2014/06 (4)
- 2014/05 (3)
カテゴリ
---
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム
QRコード











