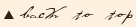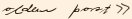『自衛隊のリアル』日本のリアルを知る一冊
集団的自衛権の行使を可能にする新安保法案が9月19日の参議院本会議の採決をへて成立した。憲法違反であるという裁判官や法学者たちの意見も蔑ろにされたまま、多くの国民は不安を抱えている。実際の現場に出ていくのは自衛隊である。しかし今まで、現場の自衛官たちの本音を聞く機会は少なかった。
本書は防衛大学校卒の新聞記者が、多くの自衛官やそのOB、家族にまで取材し、本心を探った一冊である。
彼らは法案と自分たちの立場の乖離に危機感を感じ始めている。「殺す/殺される」という戦場に向かうリアルな気持ちは、私たちが想像することのできないものだ。
2004年、イラク復興支援活動のため陸上自衛隊が派遣された。大きくは報道されなかったが、彼らは攻撃を受けていたのだ。死傷者がなかったのは僥倖に過ぎない。
本当の戦闘の際、自衛隊員は撃てるのか。創設から60年で撃たれた弾は一発だけで、それは遭難した登山者の遺体のザイルを狙ったものだ。陸自の一般部隊では実践的な教育も訓練もなされていないという。
1999年の「能登半島沖不審船事件」にはさらに戦慄させられる。北朝鮮の不審船を追跡中、海上自衛隊に「海上警備行動」が史上初めて発令された。不審船を停止させたが、「立ち入り検査」をするにも武器も防弾チョッキもない。腹の周りにマンガ雑誌を括り付け、彼らは命令を待つ。不審船は再度逃走したため大事にはならなかった。
本書では数々のこのようなエピソードが紹介される。報道されていない危機がこんなにあったのか。
先日の大洪水の際の活躍は記憶に新しい。今後はそこに「戦争の現場」が含まれる。自衛隊は国から派遣されるのだ。使う人間が間違えれば、彼らの活動は批判されてしまうだろう。今回の法案に賛成でも反対でも、自衛隊の直面してきたリアルはきちんと知っておくべきだと思う。