忘備録)Office 2019で急にen dash(エンダッシュ)がショートカットキーで入力できなくなったら
最近,Word 2019の起動が遅くなったので,標準テンプレート (Normal.dotm)を削除して作り直したところ,en dash(エンダッシュ)がショートカットキーで入力できなくなった.
以前も直した記憶があるのだが,どこを直したか覚えておらず,Google検索も日本語では出てこなかったので,忘備録として書いておきます.
通常Wrodでは,Ctrl + テンキーのマイナス記号で,en dash(エンダッシュ)が入力されます.
不具合発生時には,入力面が縮小される現象が起きました(Zoom out).
また,em dashは普通にCtrl + Alt + テンキーのマイナス記で正常に入力できました.
この件を英語で調べてみると,Microsoft Communityに解決方法が出ていました.
工程としては,ファイル => オプション => リボンのユーザー設定 => ショートカットキー =>
キーボードのユーザー設定 =>すべてのコマンドの中の ViewZoomOut =>現在のキー Ctrl+Num - を選択して削除する.
これで回復しました.
P.S. これで復活されない場合は,分類:記号/文字にあるコマンド:半角ダッシュにCtrl+Num -を割り当てる.
| コメント (0)







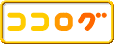
最近のコメント