Posted
on
ウォルター・モズリイ『流れは、いつか海へと』(ハヤカワミステリ)
ウォルター・モズリイの『流れは、いつか海へと』を読む。
昨年の暮れに出た本だが、最初に出版の情報を知ったときはちょっとした驚きがあった。デビュー当時はそこそこ評判になった作家だが、それはなんせ九十年代のことである。二十年以上経って再び、新刊を読む日が来ようとは予想だにしなかった。
その当時に出た小説は、『ブルー・ドレスの女』から『イエロードッグ・ブルース』までの六冊。当時、管理人はすべて買って読んだが、イージー・ローリンズを主人公にしたそれらの作品は、時代設定をあえて戦後にしたことで、黒人の主人公が抱える問題がより強調されたヘビーなハードボイルドだった。しかし、テーマに反してその語り口やストーリーは軽快で、悪くないシリーズだったと記憶する。
残念ながら我が国ではいまひとつ人気が伸びなかったのか、翻訳も六作で途絶えてしまったが(その後ノンフィクションが一冊だけ出ている)、本国ではすでに五十冊ほどの作品が書かれており、今回ご紹介する『流れは、いつか海へと』では、なんとMWAの最優秀長篇賞まで受賞したというから、ううむ、バリバリの現役ではないか。
こんな話。ジョー・オリヴァー・キングは優れた刑事ながら女に弱いのが玉に瑕。ハニートラップに引っかかって無実の罪を着せられ、職も家族も失ってしまった男だ。
今は私立探偵として働くジョーだが、そんな彼の元へ、警察官殺害の罪で死刑を宣告された黒人ジャーナリストを救ってほしいという依頼が飛び込んだ。時を同じくして、ジョーを陥れる原因となった女性から一通の手紙が届く。それはジョーを瞞した女性の謝罪と真相の告白の手紙であった。このタイミングで舞い込んだ二つの知らせに心を動かされたジョーは、二つの事件を同時に調べることにするが……。
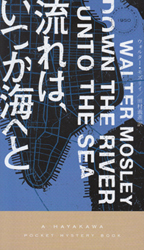
背景となるのはアメリカの警察機構と裏社会の両面。それは決して対比のためにあるのではなく、アメリカ全体が上から下まで完全に病んでしまっていることを端的に示しているに過ぎない。それと同様に、人種差別もいまだに大きく蔓延っている社会問題である。
そんな病んだ組織や社会の最前線で働いていたジョーはまんまと足を踏み外してしまい、どん底に落ちるのだが、目の前に現れた二つの事件によって、再び自身を試す機会が与えられる。果たして自分を貫けるのか、社会と折り合いをつけられるのか、本当に自分は再生したいのか。
よくある設定、よくある題材ではあるのだが、やはりアメリカの作家はこういうものを書くと実に巧い
(もちろん作家にもよるけれど)。
特に感心するのは、こうした社会の闇を徹底的に描きながらも、個としては常に「光」を感じさせる存在を登場させていることだ。刑事時代からの親友グラッドストーン、汚れなき娘エイジア、義理堅い元娼婦、何より頼りになる元凶悪犯の時計職人メルなどなど。全員が全員、まともな人物というわけではないのだが、ジョーにとっては代え難い「光」である。陳腐な表現にはなるが、やはり人は決して一人では生きられない。著者の信念が素直に感じられ、救われる気分になる。
ただ、気になった点もある。オーソドックスなハードボイルドでスタートした物語が、途中から犯罪小説のような雰囲気に変わっていくのである。それだけならまだ気にならないのだが、比例するかのように物語自体も派手な展開になり、誇張の幅がすいぶん大きくなってしまう。
どちらのテイストが良い悪いではなく、どちらかのトーンで統一した方がよかったということである。確かに爽快感は増すし、単純に面白さもアップはする。しかし、正直、後半の主人公の活躍は現実離れしており、その反動で当初の主人公の苦悩が薄まった感は否めない。
とまあ、最後に注文はつけたけれど、全体的に面白く読めるのは確かで、モズリイの作風の変化には驚かされた。これを機に早川さんはもう少し過去の作品も紹介してくれるとありがたい。
昨年の暮れに出た本だが、最初に出版の情報を知ったときはちょっとした驚きがあった。デビュー当時はそこそこ評判になった作家だが、それはなんせ九十年代のことである。二十年以上経って再び、新刊を読む日が来ようとは予想だにしなかった。
その当時に出た小説は、『ブルー・ドレスの女』から『イエロードッグ・ブルース』までの六冊。当時、管理人はすべて買って読んだが、イージー・ローリンズを主人公にしたそれらの作品は、時代設定をあえて戦後にしたことで、黒人の主人公が抱える問題がより強調されたヘビーなハードボイルドだった。しかし、テーマに反してその語り口やストーリーは軽快で、悪くないシリーズだったと記憶する。
残念ながら我が国ではいまひとつ人気が伸びなかったのか、翻訳も六作で途絶えてしまったが(その後ノンフィクションが一冊だけ出ている)、本国ではすでに五十冊ほどの作品が書かれており、今回ご紹介する『流れは、いつか海へと』では、なんとMWAの最優秀長篇賞まで受賞したというから、ううむ、バリバリの現役ではないか。
こんな話。ジョー・オリヴァー・キングは優れた刑事ながら女に弱いのが玉に瑕。ハニートラップに引っかかって無実の罪を着せられ、職も家族も失ってしまった男だ。
今は私立探偵として働くジョーだが、そんな彼の元へ、警察官殺害の罪で死刑を宣告された黒人ジャーナリストを救ってほしいという依頼が飛び込んだ。時を同じくして、ジョーを陥れる原因となった女性から一通の手紙が届く。それはジョーを瞞した女性の謝罪と真相の告白の手紙であった。このタイミングで舞い込んだ二つの知らせに心を動かされたジョーは、二つの事件を同時に調べることにするが……。
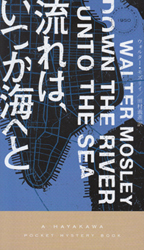
背景となるのはアメリカの警察機構と裏社会の両面。それは決して対比のためにあるのではなく、アメリカ全体が上から下まで完全に病んでしまっていることを端的に示しているに過ぎない。それと同様に、人種差別もいまだに大きく蔓延っている社会問題である。
そんな病んだ組織や社会の最前線で働いていたジョーはまんまと足を踏み外してしまい、どん底に落ちるのだが、目の前に現れた二つの事件によって、再び自身を試す機会が与えられる。果たして自分を貫けるのか、社会と折り合いをつけられるのか、本当に自分は再生したいのか。
よくある設定、よくある題材ではあるのだが、やはりアメリカの作家はこういうものを書くと実に巧い
(もちろん作家にもよるけれど)。
特に感心するのは、こうした社会の闇を徹底的に描きながらも、個としては常に「光」を感じさせる存在を登場させていることだ。刑事時代からの親友グラッドストーン、汚れなき娘エイジア、義理堅い元娼婦、何より頼りになる元凶悪犯の時計職人メルなどなど。全員が全員、まともな人物というわけではないのだが、ジョーにとっては代え難い「光」である。陳腐な表現にはなるが、やはり人は決して一人では生きられない。著者の信念が素直に感じられ、救われる気分になる。
ただ、気になった点もある。オーソドックスなハードボイルドでスタートした物語が、途中から犯罪小説のような雰囲気に変わっていくのである。それだけならまだ気にならないのだが、比例するかのように物語自体も派手な展開になり、誇張の幅がすいぶん大きくなってしまう。
どちらのテイストが良い悪いではなく、どちらかのトーンで統一した方がよかったということである。確かに爽快感は増すし、単純に面白さもアップはする。しかし、正直、後半の主人公の活躍は現実離れしており、その反動で当初の主人公の苦悩が薄まった感は否めない。
とまあ、最後に注文はつけたけれど、全体的に面白く読めるのは確かで、モズリイの作風の変化には驚かされた。これを機に早川さんはもう少し過去の作品も紹介してくれるとありがたい。


