Posted in 11 2022
Posted
on
笹沢左保『結婚って何さ』(講談社文庫)
もうすぐ「トクマの特選!」から笹沢左保の『結婚って何さ』が復刊されるというので、積ん読から掘り出してひと足早く読んでみた。
こんな話。上司の嫌がらせに怒って会社を辞めた遠井真弓と疋田三枝子。やけ酒とばかりにハシゴを続けるうち、行きずりの男と意気投合して最後は旅館に泊まって酔い潰れる。ところが翌朝、起きてみると男は絞殺死体となっていた。怖くなった二人は警察に届けず、そのまま逃げようとするのだが……。

なんせタイトルがひどいので(苦笑)、ちょっと後回しにしていたところはあるのだが、さすが『招かれざる客』、『霧に溶ける』、『人喰い』などと同じ1960年に発表されただけのことはあり、本作もまたなかなかの出来栄えだ。
基本的には巻き込まれ型のサスペンス。主人公の真弓がわずかな手がかりを頼りに自分で犯人を探そうとするが、あっという間に友人を失い、さらには第二、第三の事件に遭遇して……というスピーディーかつ予想外の展開が素晴らしい。とりわけそれらの事件が真弓自身の事件とは一見、関係ないと思われるところがミソ。
巻き込まれ型サスペンスといえば、古くはアイリッシュの作品などのように、主人公の打つ手打つ手が先回りするかのように新たな事件が起こったりするものだが、本作は複数の事件が同じタイミングで発生していたというのが面白い趣向である。もちろんそんな偶然はそうそうないだろうということなのだが、ではその関連やいかに?というのが謎の軸となる。読み進めるうち、これがただの巻き込まれ型のサスペンスではないことに気づく、その瞬間が最高である。
このほかにも密室殺人、アリバイ崩しなどもあるし、まあ、どれも大技とまではいかないし、しっかり前例もあるネタではあるが、プロットが非常によく考えられており、十分に佳作レベルといってよいだろう。ただ、短か目の長篇でスピード感優先ということもあってか、少々強引な処理が目立つのがもったいなく感じた。
本作の魅力としては、昭和三十年代の時代風俗やキャラクターが生き生きと描かれている点も忘れてはならないだろう。もともと笹沢作品にはそういう傾向が強いけれど、本作では主人公のOLが当時でいう「はすっぱ」、今でいうヤンキー系の女性であり、会話や行動力に独特のキレがあるというか、より効果的な印象である。
ただ、クセが強いだけに、人によっては拒否反応も出そうな気もするが(苦笑)。
ちなみに管理人が読んだのは古本で買ってあった講談社文庫版で、ほかには光文社文庫版もあるようだ。古書でも入手しやすい一冊ではあるが、せっかく近日、徳間文庫から復刻されるので、気になる方は応援の意味でもぜひそちらでどうぞ。
こんな話。上司の嫌がらせに怒って会社を辞めた遠井真弓と疋田三枝子。やけ酒とばかりにハシゴを続けるうち、行きずりの男と意気投合して最後は旅館に泊まって酔い潰れる。ところが翌朝、起きてみると男は絞殺死体となっていた。怖くなった二人は警察に届けず、そのまま逃げようとするのだが……。

なんせタイトルがひどいので(苦笑)、ちょっと後回しにしていたところはあるのだが、さすが『招かれざる客』、『霧に溶ける』、『人喰い』などと同じ1960年に発表されただけのことはあり、本作もまたなかなかの出来栄えだ。
基本的には巻き込まれ型のサスペンス。主人公の真弓がわずかな手がかりを頼りに自分で犯人を探そうとするが、あっという間に友人を失い、さらには第二、第三の事件に遭遇して……というスピーディーかつ予想外の展開が素晴らしい。とりわけそれらの事件が真弓自身の事件とは一見、関係ないと思われるところがミソ。
巻き込まれ型サスペンスといえば、古くはアイリッシュの作品などのように、主人公の打つ手打つ手が先回りするかのように新たな事件が起こったりするものだが、本作は複数の事件が同じタイミングで発生していたというのが面白い趣向である。もちろんそんな偶然はそうそうないだろうということなのだが、ではその関連やいかに?というのが謎の軸となる。読み進めるうち、これがただの巻き込まれ型のサスペンスではないことに気づく、その瞬間が最高である。
このほかにも密室殺人、アリバイ崩しなどもあるし、まあ、どれも大技とまではいかないし、しっかり前例もあるネタではあるが、プロットが非常によく考えられており、十分に佳作レベルといってよいだろう。ただ、短か目の長篇でスピード感優先ということもあってか、少々強引な処理が目立つのがもったいなく感じた。
本作の魅力としては、昭和三十年代の時代風俗やキャラクターが生き生きと描かれている点も忘れてはならないだろう。もともと笹沢作品にはそういう傾向が強いけれど、本作では主人公のOLが当時でいう「はすっぱ」、今でいうヤンキー系の女性であり、会話や行動力に独特のキレがあるというか、より効果的な印象である。
ただ、クセが強いだけに、人によっては拒否反応も出そうな気もするが(苦笑)。
ちなみに管理人が読んだのは古本で買ってあった講談社文庫版で、ほかには光文社文庫版もあるようだ。古書でも入手しやすい一冊ではあるが、せっかく近日、徳間文庫から復刻されるので、気になる方は応援の意味でもぜひそちらでどうぞ。
Posted
on
笹沢左保『アリバイ奪取 笹沢左保ミステリ短篇選』(中公文庫)
笹沢左保の短篇集『アリバイ奪取 笹沢左保ミステリ短篇選』を読む。笹沢左保は長編のみならず短編も数多く書いてきた作家で、短篇集だけでも百冊以上の著書があるという。本作はそんな短篇集から初期の傑作をセレクトしてまとめたもの。最近、マニアックなミステリ短編集を出している中公文庫、しかも編者は日下三蔵氏ということで、期待できる陣容である。
まずは収録作。
「伝言」
「殺してやりたい」
「十五年は長すぎる」
「お嫁にゆけない」
「第三の被害者」
「不安な証言」
「鏡のない部屋」
「アリバイ奪取」

主に六十年代初めに発表された作品が中心で、そのほとんどが労働者階級を主人公にしている。描かれているのは彼らの日常における金銭や愛欲に絡むトラブルだ。笹沢作品は長篇短篇かかわらず、この手の設定が多いけれども、これらは当時流行していた社会派の影響もあるだろうし、掲載された大衆誌などの要望もあるだろうが、そもそも著者がリアリティを重視した証というのが大きいだろう。
ただ、素材は似ていても、本格風からサスペンスまでアプローチはいろいろと工夫しているし、また短篇とはいえ長めのものが多く、物語は意外に濃い口。そういうところもミステリファンだけでなく広く読まれた理由ではないだろうか。個人的にはこの頃の男女の物語に火サス以上のドロドロ感が感じられ、これもまた昭和ミステリの味であろう。
初期傑作選だから当然ハズレもなく、どの作品も安心して読めるが、強いて好みを挙げると……文字どおり伝言の面白さがキモの「伝言」、クリスティの名作と日本の童話を連想させる怪作「お嫁にゆけない」、法定もののサスペンスが味わえる「不安な証言」、構成の妙が光る「アリバイ奪取」あたり。
解説によると、今後は違うテーマでの短篇集も予定されているということなので、ぜひ期待したい。
まずは収録作。
「伝言」
「殺してやりたい」
「十五年は長すぎる」
「お嫁にゆけない」
「第三の被害者」
「不安な証言」
「鏡のない部屋」
「アリバイ奪取」

主に六十年代初めに発表された作品が中心で、そのほとんどが労働者階級を主人公にしている。描かれているのは彼らの日常における金銭や愛欲に絡むトラブルだ。笹沢作品は長篇短篇かかわらず、この手の設定が多いけれども、これらは当時流行していた社会派の影響もあるだろうし、掲載された大衆誌などの要望もあるだろうが、そもそも著者がリアリティを重視した証というのが大きいだろう。
ただ、素材は似ていても、本格風からサスペンスまでアプローチはいろいろと工夫しているし、また短篇とはいえ長めのものが多く、物語は意外に濃い口。そういうところもミステリファンだけでなく広く読まれた理由ではないだろうか。個人的にはこの頃の男女の物語に火サス以上のドロドロ感が感じられ、これもまた昭和ミステリの味であろう。
初期傑作選だから当然ハズレもなく、どの作品も安心して読めるが、強いて好みを挙げると……文字どおり伝言の面白さがキモの「伝言」、クリスティの名作と日本の童話を連想させる怪作「お嫁にゆけない」、法定もののサスペンスが味わえる「不安な証言」、構成の妙が光る「アリバイ奪取」あたり。
解説によると、今後は違うテーマでの短篇集も予定されているということなので、ぜひ期待したい。
Posted
on
ドナルド・E・ウェストレイク『ギャンブラーが多すぎる』(新潮文庫)
ドナルド・E・ウェストレイクの『ギャンブラーが多すぎる』を読む。新潮文庫の「海外名作発掘 HIDDEN MASTERPIECES」の一作。
こんな話。ギャンブル好きのタクシードライバー、チェットは、あるとき客から競馬の裏情報を入手する。それが見事に的中し、配当金を受け取りにノミ屋のトニーを訪ねてゆく。ところがトニーの自宅で発見したのは、撃ち殺されたトニーの死体。警察に連絡し、いったんは解放されたものの、彼のもとへさまざまな人間が脅しをかけにくる。ギャングと思われる二人組、刑事、そしてトニーの妹。彼らは一様にトニーの妻がチェットと共謀していたのではと疑っていた。何とか自分は関係ないことを主張して、いったんはお引き取り願ったものの……。

ウェストレイクはハードボイルドや悪党パーカーなどのシリアス路線でスタートし、途中から泥棒ドートマンダーに代表されるようなクライムコメディに大きく舵をとった作家である。本作はちょうどその移行期ともいえる時期の作品で、ドートマンダー・シリーズもまだスタートしてはいない。
だからと言って、まだこなれていないかというと全然そんなことはない。すでにクライムコメディというスタイルを完全にものにしている感じで、主人公のとぼけた味や会話の面白さ、ドタバタなど、ツボもしっかり押さえている。それでいてミステリとしてもも案外しっかりしているのがウェストレイクの器用なところで、ラストなんて普通に「名探偵、みなを集めて〜」をやっていたりするのがまたいい。
とにかく疲れた頭にちょうどよいというか、本当に何も考えずに楽しめる一作である(褒めてます)。
正味、面白いだけで特に残るものもないし、刊行当時だってあくまで読み捨て系の面白本のはず。けれども今となってはこういうクラシカルで洗練されたクライムコメディは貴重であり、実は立派な職人技なのだ、ウェストレイクの翻訳は多いけれど、未訳はまだまだ残っているし、次はぜひ短篇集なども出してもらえれば。
こんな話。ギャンブル好きのタクシードライバー、チェットは、あるとき客から競馬の裏情報を入手する。それが見事に的中し、配当金を受け取りにノミ屋のトニーを訪ねてゆく。ところがトニーの自宅で発見したのは、撃ち殺されたトニーの死体。警察に連絡し、いったんは解放されたものの、彼のもとへさまざまな人間が脅しをかけにくる。ギャングと思われる二人組、刑事、そしてトニーの妹。彼らは一様にトニーの妻がチェットと共謀していたのではと疑っていた。何とか自分は関係ないことを主張して、いったんはお引き取り願ったものの……。

ウェストレイクはハードボイルドや悪党パーカーなどのシリアス路線でスタートし、途中から泥棒ドートマンダーに代表されるようなクライムコメディに大きく舵をとった作家である。本作はちょうどその移行期ともいえる時期の作品で、ドートマンダー・シリーズもまだスタートしてはいない。
だからと言って、まだこなれていないかというと全然そんなことはない。すでにクライムコメディというスタイルを完全にものにしている感じで、主人公のとぼけた味や会話の面白さ、ドタバタなど、ツボもしっかり押さえている。それでいてミステリとしてもも案外しっかりしているのがウェストレイクの器用なところで、ラストなんて普通に「名探偵、みなを集めて〜」をやっていたりするのがまたいい。
とにかく疲れた頭にちょうどよいというか、本当に何も考えずに楽しめる一作である(褒めてます)。
正味、面白いだけで特に残るものもないし、刊行当時だってあくまで読み捨て系の面白本のはず。けれども今となってはこういうクラシカルで洗練されたクライムコメディは貴重であり、実は立派な職人技なのだ、ウェストレイクの翻訳は多いけれど、未訳はまだまだ残っているし、次はぜひ短篇集なども出してもらえれば。
Posted
on
ジェローム・ルブリ『魔王の島』(文春文庫)
ジェローム・ルブリの『魔王の島』を読む。初めて読む作家さんだが、2017年にデビューしたフランス人作家で、すでに六冊ほどの著書があるようだ。本作は第三長篇となり、2019年度のコニャック・ミステリー大賞受賞作とのこと。
※ネタバレには注意しておりますが、今回の記事では伏字で処理している個所があります。それでも勘のいい人にはわかる可能性もありますので、閲覧にはご注意ください。
まずはストーリー。トゥール大学の教室で講義を始めたヴィルマン教授。その内容は、これまでどこにも記録されていない〈サンドリーヌの避難所事件〉についてであった。
……サンドリアーヌという若手の新聞記者がいた。ある日、彼女はこれまで会ったこともない祖母が亡くなったことを知らされ、その遺品整理などのために、祖母が住んでいた孤島へ出かけることになる。その島ではかつて子供のためのキャンプ施設があり、祖母はそこで働いていたのだ。だが忌まわしい事件が起こり、キャンプ施設は閉鎖。今では高齢者ばかりになった元従業員が数人で暮らしていた。しかし、サンドリアーヌが島を訪れるや否や、祖母の親友が死を遂げる……。
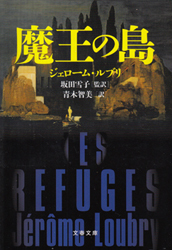
いやあ、これはなんというか。感想を書くにあたっては比較的あまい方だと思うのだが、これはダメだ。もう今年のワーストに挙げたい(笑)。
著者はどういうつもりで本作を書いたのだろう。たんに読者を驚かせたいから? ミステリにおける実験作として? ただ、どちらであってもこの作品はミステリとして成立しておらず、メインのネタには驚くどころか呆れるしかない。
いわゆる●●●●と変わりはない。これが成立するなら何でも可能であり、不可能犯罪とか論理的な解決とかサスペンスとか何の意味もない。必然性があるとか厳密な設定で裏打ちできるなら認めないこともないけれど(例えばアシモフの某短篇とか)、本作に関してはそれはない。しかも、それを二回も繰り返すか?
気になるところは他にもある。まずはルメートルの『その女アレックス』を意識したかのような構成。同じような効果を狙ってのことだろうが、そもそもの意味合いがまったく異なるので、ルメートルの着想には及ぶべくもない。
また、過剰な演出と語りもまずい。とにかく読者に対して「匂わせる」描写や展開が多すぎるのである。いや、匂わせるどころかミステリとしては完全にアンフェアな描写も多い。個人的には「第一の道しるべ 島」が終わった時点で、あまりの突拍子もないストーリーと描写に、「これ、もしかしたら●●●●か」と思ったのだが、まさかその悪い予感が的中するとは。
ともかく久々にひどいミステリを読んだので、これはこれで記憶に残る一冊にはなるだろう。それにしても、これでコニャック・ミステリー大賞受賞作とはなあ。信じられん。
※ネタバレには注意しておりますが、今回の記事では伏字で処理している個所があります。それでも勘のいい人にはわかる可能性もありますので、閲覧にはご注意ください。
まずはストーリー。トゥール大学の教室で講義を始めたヴィルマン教授。その内容は、これまでどこにも記録されていない〈サンドリーヌの避難所事件〉についてであった。
……サンドリアーヌという若手の新聞記者がいた。ある日、彼女はこれまで会ったこともない祖母が亡くなったことを知らされ、その遺品整理などのために、祖母が住んでいた孤島へ出かけることになる。その島ではかつて子供のためのキャンプ施設があり、祖母はそこで働いていたのだ。だが忌まわしい事件が起こり、キャンプ施設は閉鎖。今では高齢者ばかりになった元従業員が数人で暮らしていた。しかし、サンドリアーヌが島を訪れるや否や、祖母の親友が死を遂げる……。
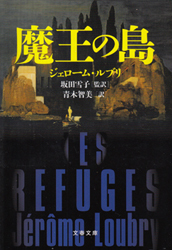
いやあ、これはなんというか。感想を書くにあたっては比較的あまい方だと思うのだが、これはダメだ。もう今年のワーストに挙げたい(笑)。
著者はどういうつもりで本作を書いたのだろう。たんに読者を驚かせたいから? ミステリにおける実験作として? ただ、どちらであってもこの作品はミステリとして成立しておらず、メインのネタには驚くどころか呆れるしかない。
いわゆる●●●●と変わりはない。これが成立するなら何でも可能であり、不可能犯罪とか論理的な解決とかサスペンスとか何の意味もない。必然性があるとか厳密な設定で裏打ちできるなら認めないこともないけれど(例えばアシモフの某短篇とか)、本作に関してはそれはない。しかも、それを二回も繰り返すか?
気になるところは他にもある。まずはルメートルの『その女アレックス』を意識したかのような構成。同じような効果を狙ってのことだろうが、そもそもの意味合いがまったく異なるので、ルメートルの着想には及ぶべくもない。
また、過剰な演出と語りもまずい。とにかく読者に対して「匂わせる」描写や展開が多すぎるのである。いや、匂わせるどころかミステリとしては完全にアンフェアな描写も多い。個人的には「第一の道しるべ 島」が終わった時点で、あまりの突拍子もないストーリーと描写に、「これ、もしかしたら●●●●か」と思ったのだが、まさかその悪い予感が的中するとは。
ともかく久々にひどいミステリを読んだので、これはこれで記憶に残る一冊にはなるだろう。それにしても、これでコニャック・ミステリー大賞受賞作とはなあ。信じられん。
Posted
on
年末ミステリベストテンを予想してみる
ワールドカップが始まったこともあって、あちらこちらで順位予想が盛んである。そういえば管理人もTwitterで年末のミステリベストテンの予想を立ててみたので、こちらでも残しておこう。「このミス」とか「文春」とか別々で予想しようとも思ったが、あまりに面倒なので以下の一本で。
1位 クリス・ウィタカー『われら闇より天を見る』
2位 スチュアート・タートン『名探偵と海の悪魔』
4位 タナ・フレンチ『捜索者』
4位 ジャニス・ハレット『ポピーのためにできること』
5位 ホリー・ジャクソン『優等生は探偵に向かない』
6位 M ・W・ クレイヴン『キュレーターの殺人』
7位 アンソニー・ホロヴィッツ『殺しへのライン』
8位 S・A・コスビー『黒き荒野の果て』
9位 アーナルデュル・インドリダソン『印』
10位 ドン ウィンズロウ『業火の市』
念の為に書いておくと、これはあくまで年末に各誌で行われるミステリベストテンの予想であって、自分の評価で選んだベストテンではない。過去作品の評価や人気、ネットでの評判から、この辺が選ばれるのだろうなという、ただの遊びで選んだ結果だ。自分の評価で選んだベストテンは、大晦日に「極私的ベストテン」として発表いたしまする。
さて少しだけ補足しておくと、ホロヴィッツはさすがに今回はベストテンクラスの作品とは思えないのだが、それでも絶体的ファンは投票するだろうし、このぐらいには滑り込みそうな気がする。ホリー・ジャクソンもインパクトは昨年より弱いが、質を考えるとこのぐらいはキープしそう。インドリダソンやクレイヴン、ウィンズロウもそうだが、常連作家やシリーズものは作品の出来以上に人気で投票する人も多そうで、安定して強いんだよね。
ただ、シリアス路線、感動系のノンシリーズはこのところ爆発力がある。そういう意味でウィタカーとタナ・フレンチは上位間違いなしと思うのだが、もしかするとこの二冊は票が割れそうで、となると後発のウィタカーの方が有利かもしれない。個人的には圧倒的に『捜索者』の方が好きなんだけれど。
そしてこれに迫る、あるいは凌駕しそうなのが『名探偵と海の悪魔』と『ポピーのためにできること』。エンタメかつ本格として今年の二大収穫だろう。ただ、『ポピー〜』はネットでの様子を見ているかぎり今ひとつ知られていない気がして、下手をするとまさかのランク外の可能性もありそう。こちらも個人的お気に入りなので杞憂に終わると良いのだけれど。
と、グダグダ書いてはみたが、実はこんなベストテンは当たり前すぎるので、番狂わせを起こしてくれそうな十作も挙げておこう(これもTwitterにアップしたもの)。正直、総合力では弱いかもしれないが、強力なウリを持った作品ばかりだ。なんなら裏ベストテンと言ってもいい。
エルヴェ・ル・テリエ『異常 アノマリー』
ライオネル・ホワイト『気狂いピエロ』
マリー・ルイーゼ・カシュニッツ『その昔、N市では』
エリー・グリフィス『窓辺の愛書家』
モーリス・ルヴェル『地獄の門』
リチャード・レヴィンソン&ウィリアム・リンク『レヴィンソン&リンク劇場 突然の奈落』
アレックス・ベール『狼たちの宴』
レオ・ブルース『レオ・ブルース短編全集』
エマ・ストーネクス『光を灯す男たち』
ジョン・ロード『デイヴィッドスン事件』
なかでも特に一位に推したいのが『異常 アノマリー』。純粋なミステリではないので、まったくランク外の可能性もあるけれど、こういう特殊な物語こそランクインしてほしいところ。
まあ先にも書いたが、こちらの十作は一芸に秀いでてはいるが総合力でどうしても不利なんである。とはいえ、その他の作品も何作かはランクインしそうな気もするし、とりあえず「このミス」や「文春」、「ミステリマガジン」をただ読むのではなく、答え合わせする楽しみが増えたのは喜ばしい(笑)。パーフェクトは難しいだろうが七割ぐらいは当たるんじゃないかな。
1位 クリス・ウィタカー『われら闇より天を見る』
2位 スチュアート・タートン『名探偵と海の悪魔』
4位 タナ・フレンチ『捜索者』
4位 ジャニス・ハレット『ポピーのためにできること』
5位 ホリー・ジャクソン『優等生は探偵に向かない』
6位 M ・W・ クレイヴン『キュレーターの殺人』
7位 アンソニー・ホロヴィッツ『殺しへのライン』
8位 S・A・コスビー『黒き荒野の果て』
9位 アーナルデュル・インドリダソン『印』
10位 ドン ウィンズロウ『業火の市』
念の為に書いておくと、これはあくまで年末に各誌で行われるミステリベストテンの予想であって、自分の評価で選んだベストテンではない。過去作品の評価や人気、ネットでの評判から、この辺が選ばれるのだろうなという、ただの遊びで選んだ結果だ。自分の評価で選んだベストテンは、大晦日に「極私的ベストテン」として発表いたしまする。
さて少しだけ補足しておくと、ホロヴィッツはさすがに今回はベストテンクラスの作品とは思えないのだが、それでも絶体的ファンは投票するだろうし、このぐらいには滑り込みそうな気がする。ホリー・ジャクソンもインパクトは昨年より弱いが、質を考えるとこのぐらいはキープしそう。インドリダソンやクレイヴン、ウィンズロウもそうだが、常連作家やシリーズものは作品の出来以上に人気で投票する人も多そうで、安定して強いんだよね。
ただ、シリアス路線、感動系のノンシリーズはこのところ爆発力がある。そういう意味でウィタカーとタナ・フレンチは上位間違いなしと思うのだが、もしかするとこの二冊は票が割れそうで、となると後発のウィタカーの方が有利かもしれない。個人的には圧倒的に『捜索者』の方が好きなんだけれど。
そしてこれに迫る、あるいは凌駕しそうなのが『名探偵と海の悪魔』と『ポピーのためにできること』。エンタメかつ本格として今年の二大収穫だろう。ただ、『ポピー〜』はネットでの様子を見ているかぎり今ひとつ知られていない気がして、下手をするとまさかのランク外の可能性もありそう。こちらも個人的お気に入りなので杞憂に終わると良いのだけれど。
と、グダグダ書いてはみたが、実はこんなベストテンは当たり前すぎるので、番狂わせを起こしてくれそうな十作も挙げておこう(これもTwitterにアップしたもの)。正直、総合力では弱いかもしれないが、強力なウリを持った作品ばかりだ。なんなら裏ベストテンと言ってもいい。
エルヴェ・ル・テリエ『異常 アノマリー』
ライオネル・ホワイト『気狂いピエロ』
マリー・ルイーゼ・カシュニッツ『その昔、N市では』
エリー・グリフィス『窓辺の愛書家』
モーリス・ルヴェル『地獄の門』
リチャード・レヴィンソン&ウィリアム・リンク『レヴィンソン&リンク劇場 突然の奈落』
アレックス・ベール『狼たちの宴』
レオ・ブルース『レオ・ブルース短編全集』
エマ・ストーネクス『光を灯す男たち』
ジョン・ロード『デイヴィッドスン事件』
なかでも特に一位に推したいのが『異常 アノマリー』。純粋なミステリではないので、まったくランク外の可能性もあるけれど、こういう特殊な物語こそランクインしてほしいところ。
まあ先にも書いたが、こちらの十作は一芸に秀いでてはいるが総合力でどうしても不利なんである。とはいえ、その他の作品も何作かはランクインしそうな気もするし、とりあえず「このミス」や「文春」、「ミステリマガジン」をただ読むのではなく、答え合わせする楽しみが増えたのは喜ばしい(笑)。パーフェクトは難しいだろうが七割ぐらいは当たるんじゃないかな。
Posted
on
タナ・フレンチ『捜索者』(ハヤカワ文庫)
タナ・フレンチの『捜索者』を読む。初めて読む作家さんだが、アイルランド系アメリカ人で、現在はアイルランド在住。そうしたバックボーンを生かした作品である。
シカゴ警察を退職し、アイルランドの片田舎に引っ越し、荒屋を買い取って修繕しながら暮らしているカル・ジョン・フーパー。村人たちとも徐々に親交を深め、静かな生活を送っていたが、ある時、何者かの視線を感じるようになる。ほどなくして正体は判明した。村人からは相手にされていない一家の子供、トレイだった。しかし、カルに近づいてはくるものの、打ち解ける様子は見せないトレイに、カルは家具の修繕を手伝わせ、徐々に距離を縮めてゆく。やがてトレイは、失踪した兄を探してほしいと依頼してくるのだが……。

退職した警官が、平穏を求めて田舎暮らしを始めるが、やがて村に潜む事件に直面し、捜査を開始する。こう書くと、よくある警察小説やハードボイルドのようにも思える。組織に馴染めない一匹狼の元警官が、怒りを内に込めつつトラブルの渦中に飛び込み、やがて田舎の村ならではの闇が浮かび上がるといった類の。
だが、本作は外観こそ似ているものの、そういうタイプのハードボイルドとはまったく異なる小説である。
主人公のカルはエキセントリックになることもなく、怒りをむやみに爆発させることもない。むしろ周囲と調和しようと考えて行動する男で、成熟した人間だ。別れた妻との関係、価値観の異なる村人との距離感、トレイとの接し方などに、そのバランス感覚が見て取れる。
そんなカルの日常が前半はじっくり描かれ、後半、トレイの兄の調査を始めても事件の描写ばかりにせず、そういう部分は大事に書いている。分量としてはかなりヘビーだが、こういう単なる味つけを超えた世界観、土台といったものの構築がとてつもなく丁寧で、しっかりと語られる。そこが良いのである。
とりわけトレイとのやりとりは読ませる。トレイは学も礼儀も身についていない、いわば獣のような子供だ。カルはそんなトレイに少しずつ興味のありそうな餌(大工仕事や銃、料理など)を与え、コミュニケーションを少しずつ図り、規範やマナーを教えてゆく。言葉は悪いが猛獣を調教しているようなものである。
その中でカルもまた「気づき」を得ていく。
成熟した大人の男であるカルだが、だからといって人生がうまくいくとは限らない。妻に逃げられ、ただ一人の娘とも離れて暮らすカルは、いってみれば家族作りに一度失敗した男だ。その反省はあるけれども、最善手は見つからず、今の自分がある。カルはトレイとのやり取りの中で、かつての自分ができなかった家族作りの手法をもう一度模索しているとも言える。思えばアイルランドに来たのもそこに要因があったわけで、そういった試行錯誤を通じ、カルは自分の最適な居場所を捜しているのだろう。「捜索者」というタイトルはトレイの兄を捜索するという以外に、そういう意味も含んでいるはずだ。
一方、ミステリとして見た場合。そこまで大きな事件ではない。「一見、静かな村に隠された邪悪な陰謀」というネタも、ミステリにはお馴染みのものではあるが、本作にそれを期待してはいけない。
だが、ゆったりしたペースで描かれるカルの調査、村人との駆け引きはなかなか興味深い。ありきたりの会話の裏に、はたまた一挙手一投足にはどのような意味あいがあるのか。警官としてカルが長年培ってきたそういう洞察力が発揮されるシーンは、地味ながらも本作の大きな魅力といえる。
700ページ弱はあろうかという分量に、最初はやや気圧されてしまうかもしれないが、いざ読み始めれば決して退屈することはない。最後には深い満足感を与えてくれるはずだ。ぜひお試しあれ。
シカゴ警察を退職し、アイルランドの片田舎に引っ越し、荒屋を買い取って修繕しながら暮らしているカル・ジョン・フーパー。村人たちとも徐々に親交を深め、静かな生活を送っていたが、ある時、何者かの視線を感じるようになる。ほどなくして正体は判明した。村人からは相手にされていない一家の子供、トレイだった。しかし、カルに近づいてはくるものの、打ち解ける様子は見せないトレイに、カルは家具の修繕を手伝わせ、徐々に距離を縮めてゆく。やがてトレイは、失踪した兄を探してほしいと依頼してくるのだが……。

退職した警官が、平穏を求めて田舎暮らしを始めるが、やがて村に潜む事件に直面し、捜査を開始する。こう書くと、よくある警察小説やハードボイルドのようにも思える。組織に馴染めない一匹狼の元警官が、怒りを内に込めつつトラブルの渦中に飛び込み、やがて田舎の村ならではの闇が浮かび上がるといった類の。
だが、本作は外観こそ似ているものの、そういうタイプのハードボイルドとはまったく異なる小説である。
主人公のカルはエキセントリックになることもなく、怒りをむやみに爆発させることもない。むしろ周囲と調和しようと考えて行動する男で、成熟した人間だ。別れた妻との関係、価値観の異なる村人との距離感、トレイとの接し方などに、そのバランス感覚が見て取れる。
そんなカルの日常が前半はじっくり描かれ、後半、トレイの兄の調査を始めても事件の描写ばかりにせず、そういう部分は大事に書いている。分量としてはかなりヘビーだが、こういう単なる味つけを超えた世界観、土台といったものの構築がとてつもなく丁寧で、しっかりと語られる。そこが良いのである。
とりわけトレイとのやりとりは読ませる。トレイは学も礼儀も身についていない、いわば獣のような子供だ。カルはそんなトレイに少しずつ興味のありそうな餌(大工仕事や銃、料理など)を与え、コミュニケーションを少しずつ図り、規範やマナーを教えてゆく。言葉は悪いが猛獣を調教しているようなものである。
その中でカルもまた「気づき」を得ていく。
成熟した大人の男であるカルだが、だからといって人生がうまくいくとは限らない。妻に逃げられ、ただ一人の娘とも離れて暮らすカルは、いってみれば家族作りに一度失敗した男だ。その反省はあるけれども、最善手は見つからず、今の自分がある。カルはトレイとのやり取りの中で、かつての自分ができなかった家族作りの手法をもう一度模索しているとも言える。思えばアイルランドに来たのもそこに要因があったわけで、そういった試行錯誤を通じ、カルは自分の最適な居場所を捜しているのだろう。「捜索者」というタイトルはトレイの兄を捜索するという以外に、そういう意味も含んでいるはずだ。
一方、ミステリとして見た場合。そこまで大きな事件ではない。「一見、静かな村に隠された邪悪な陰謀」というネタも、ミステリにはお馴染みのものではあるが、本作にそれを期待してはいけない。
だが、ゆったりしたペースで描かれるカルの調査、村人との駆け引きはなかなか興味深い。ありきたりの会話の裏に、はたまた一挙手一投足にはどのような意味あいがあるのか。警官としてカルが長年培ってきたそういう洞察力が発揮されるシーンは、地味ながらも本作の大きな魅力といえる。
700ページ弱はあろうかという分量に、最初はやや気圧されてしまうかもしれないが、いざ読み始めれば決して退屈することはない。最後には深い満足感を与えてくれるはずだ。ぜひお試しあれ。
Posted
on
ライオネル・ホワイト『気狂いピエロ』(新潮文庫)
新潮文庫が今年に入って海外名作の復刊を進めているようで、対象となる本の帯には「海外名作発掘 HIDDEN MASTERPIECES」というロゴまでついている。先日ブログにアップしたポール・ベンジャミンの『スクイズ・プレー』もそうだし、ウェストレイクの『ギャンブラーが多すぎる』というのもある。どういう経緯でスタートしたのか、新潮社のホームページにそれらしい紹介がないので詳しいところは不明だが、まあ歓迎したい企画ではある。新潮文庫には数年前から「スター・クラシックス 名作新訳コレクション」というシリーズもあるので、その関連かもしれない。
ともあれ本日の読了本は、その「海外名作発掘」の一冊からライオネル・ホワイトの『気狂いピエロ』。まずはストーリーから。
“おれ”はキッチンテーブルの椅子に座り、これまでのことをノートに綴ってっている。奴らが駆けつけるまでに二時間はかかるだろうから、それまでにすべての事実を記すつもりだ。
そもそもは六ヶ月前に始まったことだ。上手くいかない再就職、妻や子供たちとの不仲、魔性の魅力をもつ十七歳の娘・アリーとの出会い、そして見知らぬ男の死……。
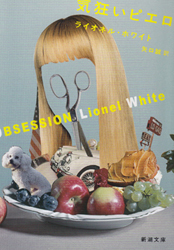
著者のライオネル・ホワイトは1950〜70年代にかけて活躍したノワール系の作家で、日本でもいくつか邦訳がある。犯罪者の視点で強盗や詐欺、誘拐事件などを描いた小説をケイパー小説などと言ったりもするが、著者はこのケイパー小説を多く書いた作家でもある。本作もまさしくそんな一冊だが、一般にはゴダールの名作映画『気狂いピエロ』の原作といった方が通りはいいだろう。
ただ、映画は原作の設定を借りた程度で、雰囲気などはかなり異なる。なんせフランス映画でもあるし、殺伐とはしているがどこかふわっとしたイメージがあり、思想的かつ芸術的な味わいが強い。ファムファタールの側面もあるが、いわゆる悪女とは違って小悪魔的イメージだ。その点、原作はストレートな犯罪小説の味わいである。どちらがいいというより、それぞれの持ち味があるという感じだろう。
原作に話を絞ると、本作はファムファタール、ケイパー小説として語られることも多いが、基本的にはもっとシンプルに、犯罪者に堕ちた主人公を描く広義のクライムノベル、ノワールという括りでいいのではないかと思う。
シナリオライターという華やかな業界人のはずが、失業したことで歯車が狂い始める主人公。そこそこの能力はあるのだが、物事を深く受けとめることをせず、常に受動的。いつも安直な方向を選択するため、打つ手のほとんどが裏目に出る。アリーに対しても、たぶらかされはするが愛情があるとか、その魅力に絡め取られるとかいうのではない。あくまでその場の肉欲でしかなく、根っこのところでの繋がりは極めて弱い。とにかく行動原理が軽く、刹那的な生き方しかできない主人公なのだ。
ある意味、そんなダメ男だからこそ主人公として魅力的であり、彼がどのように犯罪者へと堕ちていったのか、なぜそこまで堕ちていったのか、読まずにはいられないのである。ダメ男ではあるが、元は普通の勤め人。転落のきっかけは些細なことであり、その災厄が自分に降り掛かってこないと誰が言えるだろう。
ただ、正直いうと、本作でもっとも印象に残ったのは主人公でもなくアリーでもなく、主人公の妻、マータである。実は彼女が一番、怖い。
ともあれ本日の読了本は、その「海外名作発掘」の一冊からライオネル・ホワイトの『気狂いピエロ』。まずはストーリーから。
“おれ”はキッチンテーブルの椅子に座り、これまでのことをノートに綴ってっている。奴らが駆けつけるまでに二時間はかかるだろうから、それまでにすべての事実を記すつもりだ。
そもそもは六ヶ月前に始まったことだ。上手くいかない再就職、妻や子供たちとの不仲、魔性の魅力をもつ十七歳の娘・アリーとの出会い、そして見知らぬ男の死……。
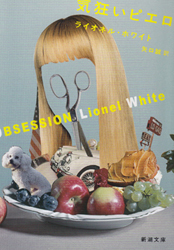
著者のライオネル・ホワイトは1950〜70年代にかけて活躍したノワール系の作家で、日本でもいくつか邦訳がある。犯罪者の視点で強盗や詐欺、誘拐事件などを描いた小説をケイパー小説などと言ったりもするが、著者はこのケイパー小説を多く書いた作家でもある。本作もまさしくそんな一冊だが、一般にはゴダールの名作映画『気狂いピエロ』の原作といった方が通りはいいだろう。
ただ、映画は原作の設定を借りた程度で、雰囲気などはかなり異なる。なんせフランス映画でもあるし、殺伐とはしているがどこかふわっとしたイメージがあり、思想的かつ芸術的な味わいが強い。ファムファタールの側面もあるが、いわゆる悪女とは違って小悪魔的イメージだ。その点、原作はストレートな犯罪小説の味わいである。どちらがいいというより、それぞれの持ち味があるという感じだろう。
原作に話を絞ると、本作はファムファタール、ケイパー小説として語られることも多いが、基本的にはもっとシンプルに、犯罪者に堕ちた主人公を描く広義のクライムノベル、ノワールという括りでいいのではないかと思う。
シナリオライターという華やかな業界人のはずが、失業したことで歯車が狂い始める主人公。そこそこの能力はあるのだが、物事を深く受けとめることをせず、常に受動的。いつも安直な方向を選択するため、打つ手のほとんどが裏目に出る。アリーに対しても、たぶらかされはするが愛情があるとか、その魅力に絡め取られるとかいうのではない。あくまでその場の肉欲でしかなく、根っこのところでの繋がりは極めて弱い。とにかく行動原理が軽く、刹那的な生き方しかできない主人公なのだ。
ある意味、そんなダメ男だからこそ主人公として魅力的であり、彼がどのように犯罪者へと堕ちていったのか、なぜそこまで堕ちていったのか、読まずにはいられないのである。ダメ男ではあるが、元は普通の勤め人。転落のきっかけは些細なことであり、その災厄が自分に降り掛かってこないと誰が言えるだろう。
ただ、正直いうと、本作でもっとも印象に残ったのは主人公でもなくアリーでもなく、主人公の妻、マータである。実は彼女が一番、怖い。
Posted
on
アリス・フィーニー『彼は彼女の顔が見えない』(創元推理文庫)
アリス・フィーニーの作品は今年の初めに『彼と彼女の衝撃の瞬間』を読んで以来。いわゆる叙述系のネタを中心にいろいろ仕込んだ作品で、やりすぎ&作りすぎが気になったものの、その甲斐あって面白い作品にはなっていた。それに続く邦訳が本日の読了本、『彼は彼女の顔が見えない』である。
こんな話。アダムとアメリアは結婚生活がうまくいかず、カウンセラーのアドバイスにしたがって旅行へ出かけることにした。タイミングよくアメリアの職場のクリスマスパーティーでくじが当たり、スコットランドの古いチャペルを利用できようになったのだ。
ところが当日は天候が崩れ、やっとの思いでチャペルに到着する二人。しかもチャペルでは不可解な出来事が発生し、二人の間には険悪なムードが漂い始める……。
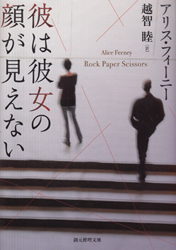
▲アリス・フィーニー『彼は彼女の顔が見えない』(創元推理文庫)【amazon】
ううむ、またも叙述系だったか。
本作の趣向もとにかく凝っている。まずアダムとアメリア、二人の視点がある。さらには第三の登場人物ロビンの視点が途中から加わり、これらはリアルタイムでの進行である。そして過去の回想として、妻がストレス解消のために書いているアダム宛の手紙(とはいえ決してアダムには見せないので、半分日記みたいなものだろう)が挿入され、都合四つのパートで交互に語られる物語となっているのだ。
まあ、叙述トリックそのもの否定するつもりはまったくないが、読みどころがこれしかないというのはミステリ作家としてどうなんだろう。基本的にはしっかりと書ける作家さんだとは思うのだが、山っけが強すぎるのか、ウケ狙いの気持ちが強すぎるのか、とにかく仕掛けたくて仕掛けたくてしょうがない感じ。もう「信頼できない語り手」どころのレベルではなく、作りすぎの結果、さまざまな齟齬や矛盾が出てしまう。
とにかくよくないのは、叙述トリックの存在が大前提みたいな作品なので、それを意識するとすぐに仕掛けが割れてしまうことだろう(登場人物が少ないことも損をしている)。個人的には手紙のパートの二回目あたりで全体の構造が見えてしまい、後は動機を探すぐらいの読書になってしまった。
物語自体が面白ければそれでもいいが、本作については視点の変わり目でいちいちエピソードが挿入されるのもうるさく、まるで昔のゴシック映画でもみている気分になる。たとえば、「アメリアがドアを開けるとアダムの姿が消えていた」という展開でアメリアのパートが終わる。サスペンスを高めるための手法であることはわかるが、次の章でアダムが階段を上がっていただけとか、どうでもいいサスペンスが多すぎるのだ。
また、各自のパートでも説明的な心理描写が多いのも気になったし、そのくせ肝心の自分の行動はうやむやにしてしまうのも気に入らない。アダムにしてもアメリアにしても、単なる一人称なのに、明らかに自分の胸中を正直に語ろうとせず、つまりは読者を意識して語る感じになってしまっているのだ。そういうのは手紙パートにもあって、手紙で会話を延々セリフとして書くというのはあまりに不自然で、ここでも読者のために読みやすくしているとしか思えない。
普通に三人称で書けば、それら欠点もかなり解消はできるはずだが、問題はそれを本作でやると平凡な話になってしまうことだろう。『彼と彼女の衝撃の瞬間』の場合は普通の三人称で書かれても面白く読めたと思うのだが。
あとはどんでん返しの多さもいただけない。ラスト二つのどんでん返しなど、ネタも後出しで、作者の思惑だけでどうとでもなる部分。それで喜ぶ読者もいるだろうが、個人的には余韻を壊すだけで不要としか思えなかった。
というわけで今回はかなり辛目の感想になってしまった。もう食傷気味ということもあるし、そもそも叙述トリックの弱点としてストーリー上の必然性に欠けるところがあり、そこが個人的には引っかかる。その点が上手く解消できれば、また見方も変わるのだろうけれど。
ともあれ著者については技術のある作家だとは思うので、叙述トリック以外の、異なる傾向の作品を読ませてほしいものだ。
こんな話。アダムとアメリアは結婚生活がうまくいかず、カウンセラーのアドバイスにしたがって旅行へ出かけることにした。タイミングよくアメリアの職場のクリスマスパーティーでくじが当たり、スコットランドの古いチャペルを利用できようになったのだ。
ところが当日は天候が崩れ、やっとの思いでチャペルに到着する二人。しかもチャペルでは不可解な出来事が発生し、二人の間には険悪なムードが漂い始める……。
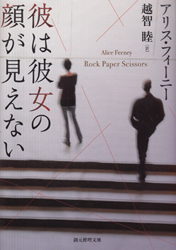
▲アリス・フィーニー『彼は彼女の顔が見えない』(創元推理文庫)【amazon】
ううむ、またも叙述系だったか。
本作の趣向もとにかく凝っている。まずアダムとアメリア、二人の視点がある。さらには第三の登場人物ロビンの視点が途中から加わり、これらはリアルタイムでの進行である。そして過去の回想として、妻がストレス解消のために書いているアダム宛の手紙(とはいえ決してアダムには見せないので、半分日記みたいなものだろう)が挿入され、都合四つのパートで交互に語られる物語となっているのだ。
まあ、叙述トリックそのもの否定するつもりはまったくないが、読みどころがこれしかないというのはミステリ作家としてどうなんだろう。基本的にはしっかりと書ける作家さんだとは思うのだが、山っけが強すぎるのか、ウケ狙いの気持ちが強すぎるのか、とにかく仕掛けたくて仕掛けたくてしょうがない感じ。もう「信頼できない語り手」どころのレベルではなく、作りすぎの結果、さまざまな齟齬や矛盾が出てしまう。
とにかくよくないのは、叙述トリックの存在が大前提みたいな作品なので、それを意識するとすぐに仕掛けが割れてしまうことだろう(登場人物が少ないことも損をしている)。個人的には手紙のパートの二回目あたりで全体の構造が見えてしまい、後は動機を探すぐらいの読書になってしまった。
物語自体が面白ければそれでもいいが、本作については視点の変わり目でいちいちエピソードが挿入されるのもうるさく、まるで昔のゴシック映画でもみている気分になる。たとえば、「アメリアがドアを開けるとアダムの姿が消えていた」という展開でアメリアのパートが終わる。サスペンスを高めるための手法であることはわかるが、次の章でアダムが階段を上がっていただけとか、どうでもいいサスペンスが多すぎるのだ。
また、各自のパートでも説明的な心理描写が多いのも気になったし、そのくせ肝心の自分の行動はうやむやにしてしまうのも気に入らない。アダムにしてもアメリアにしても、単なる一人称なのに、明らかに自分の胸中を正直に語ろうとせず、つまりは読者を意識して語る感じになってしまっているのだ。そういうのは手紙パートにもあって、手紙で会話を延々セリフとして書くというのはあまりに不自然で、ここでも読者のために読みやすくしているとしか思えない。
普通に三人称で書けば、それら欠点もかなり解消はできるはずだが、問題はそれを本作でやると平凡な話になってしまうことだろう。『彼と彼女の衝撃の瞬間』の場合は普通の三人称で書かれても面白く読めたと思うのだが。
あとはどんでん返しの多さもいただけない。ラスト二つのどんでん返しなど、ネタも後出しで、作者の思惑だけでどうとでもなる部分。それで喜ぶ読者もいるだろうが、個人的には余韻を壊すだけで不要としか思えなかった。
というわけで今回はかなり辛目の感想になってしまった。もう食傷気味ということもあるし、そもそも叙述トリックの弱点としてストーリー上の必然性に欠けるところがあり、そこが個人的には引っかかる。その点が上手く解消できれば、また見方も変わるのだろうけれど。
ともあれ著者については技術のある作家だとは思うので、叙述トリック以外の、異なる傾向の作品を読ませてほしいものだ。
Posted
on
ジョン・ロード『デイヴィッドスン事件』(論創海外ミステリ)
かつて退屈派と揶揄されたジョン・ロード。実際、我が国で訳された作品にもそのようなものがあったことから、遅々として紹介が進まなかったが、近年になってようやく状況が改善されつつあるようで喜ばしい。
私見だが、ロードの作品のキモは論理性にある。情報を集め、それらをもとに推論を重ね、事件を論理的に解明する過程こそが読みどころなのだ。ストーリーやトリック、雰囲気作りなどにはそこまで興味がなかったようで、残念ながらその結果としてとにかく地味な作風になってしまった。それが退屈派と呼ばれた一番の原因だとは思うのだが、我が国においてはこれに加え、単純に初期の傑作と思われる作品がなかなか翻訳されなかったこともあるのだろう。
本日の読了本は、そんな不運な(?)ロードの初期傑作のひとつ『デイヴィッドスン事件』。ようやく真打ち登場といったところだろう。
こんな話。化学装置の設計・製造を手掛けるデイヴィッド社の社長ヘクターは、利益のみを追求し、設計技師として貢献してきたローリーをクビにすることにした。ヒット商品の報酬を彼に支払うのが惜しくなったのである。それを聞いたヘクターの従兄弟で取締役を務めるガイは憤慨する。これまで多大な貢献をしてくれた社員への仕打ちとして酷なだけでなく、会社の将来にとっても大きなマイナスである。また、ローリーの恋人でヘクターの秘書を務めるオルガも激しい怒りを覚えていた。彼女もまた会社を愛するがゆえにヘクターのセクハラに我慢してきた過去があったのだ。
そんなある日、ヘクターは大きな籐製のケースを抱え、列車で郊外の屋敷へ出かけていく。そして駅まで迎えにきたトラックにケースを積み、自らも荷台へ乗車した。ところが屋敷へ到着したとき、ヘクターはすでに息絶えていた。死因は鋭利なものによる刺殺と思われる。警察は秘書のオルガに容疑を絞るが、プリーストリー博士には別の考えがあった……。

なるほど確かにこれはいろいろと見どころがあり、面白い作品だ。なんならジョン・ロード・ファン必読と言ってもよい。
ミステリとしての大きな仕掛けは二つあるのだが、ひとつは割と見抜きやすい。事件が起こる過程がフェアというか丁寧に描写しているので、ミステリに慣れている読者ならある程度は気づいてしまうのではないだろうか。
もうひとつの仕掛けはそちらに比べるとかなり効果的だ。ネタバレになるから詳しくは書かないけれど、要は二重解決のスタイルをとっている。ストーリー三分の二のあたりで早々に犯人を明かしながら、法廷でそれをひっくり返し、ラストで真相を明かすというもの。このひっくり返す仕掛けが巧妙で、その結果がストーリー展開にも寄与していて面白い部分だ。
そして仕掛けとは少し異なるのだけれど、本作にはラストである趣向が施されていることに驚かされる。この点だけでもロード作品としては異色の部類に入るだろうが、ストーリーや読後感にも影響するため、かなり好き嫌いが分かれるところだろう。
ただ、個人的にはぶっちゃけ微妙だなという感じ(苦笑)。終盤に入ってからの犯人のキャラクターには、正直、薄気味悪さしか感じなかったが、大いに共感する人がいても別におかしくはない。言ってみれば、そういうさまざまな受けとり方がある作品だからこそ、本作はロード・ファン必読の一冊なのだ。
私見だが、ロードの作品のキモは論理性にある。情報を集め、それらをもとに推論を重ね、事件を論理的に解明する過程こそが読みどころなのだ。ストーリーやトリック、雰囲気作りなどにはそこまで興味がなかったようで、残念ながらその結果としてとにかく地味な作風になってしまった。それが退屈派と呼ばれた一番の原因だとは思うのだが、我が国においてはこれに加え、単純に初期の傑作と思われる作品がなかなか翻訳されなかったこともあるのだろう。
本日の読了本は、そんな不運な(?)ロードの初期傑作のひとつ『デイヴィッドスン事件』。ようやく真打ち登場といったところだろう。
こんな話。化学装置の設計・製造を手掛けるデイヴィッド社の社長ヘクターは、利益のみを追求し、設計技師として貢献してきたローリーをクビにすることにした。ヒット商品の報酬を彼に支払うのが惜しくなったのである。それを聞いたヘクターの従兄弟で取締役を務めるガイは憤慨する。これまで多大な貢献をしてくれた社員への仕打ちとして酷なだけでなく、会社の将来にとっても大きなマイナスである。また、ローリーの恋人でヘクターの秘書を務めるオルガも激しい怒りを覚えていた。彼女もまた会社を愛するがゆえにヘクターのセクハラに我慢してきた過去があったのだ。
そんなある日、ヘクターは大きな籐製のケースを抱え、列車で郊外の屋敷へ出かけていく。そして駅まで迎えにきたトラックにケースを積み、自らも荷台へ乗車した。ところが屋敷へ到着したとき、ヘクターはすでに息絶えていた。死因は鋭利なものによる刺殺と思われる。警察は秘書のオルガに容疑を絞るが、プリーストリー博士には別の考えがあった……。

なるほど確かにこれはいろいろと見どころがあり、面白い作品だ。なんならジョン・ロード・ファン必読と言ってもよい。
ミステリとしての大きな仕掛けは二つあるのだが、ひとつは割と見抜きやすい。事件が起こる過程がフェアというか丁寧に描写しているので、ミステリに慣れている読者ならある程度は気づいてしまうのではないだろうか。
もうひとつの仕掛けはそちらに比べるとかなり効果的だ。ネタバレになるから詳しくは書かないけれど、要は二重解決のスタイルをとっている。ストーリー三分の二のあたりで早々に犯人を明かしながら、法廷でそれをひっくり返し、ラストで真相を明かすというもの。このひっくり返す仕掛けが巧妙で、その結果がストーリー展開にも寄与していて面白い部分だ。
そして仕掛けとは少し異なるのだけれど、本作にはラストである趣向が施されていることに驚かされる。この点だけでもロード作品としては異色の部類に入るだろうが、ストーリーや読後感にも影響するため、かなり好き嫌いが分かれるところだろう。
ただ、個人的にはぶっちゃけ微妙だなという感じ(苦笑)。終盤に入ってからの犯人のキャラクターには、正直、薄気味悪さしか感じなかったが、大いに共感する人がいても別におかしくはない。言ってみれば、そういうさまざまな受けとり方がある作品だからこそ、本作はロード・ファン必読の一冊なのだ。
Posted
on
アーナルデュル・インドリダソン『印』(東京創元社)
アーナルデュル・インドリダソンの『印』を読む(ちなみに「印」と書いて「サイン」と読ませます)。エーレンデュル捜査官シリーズの第六作である。
こんな話。湖のほとりにあるサマーハウスで首を吊っている女性マリアが発見された。発見者はマリアからそのサマーハウスを借りた友人のカレン。マリアは二年前に母を失ってから不安定な状態がずっと続いており、それが原因の自殺だと思われた。しかし、事件を担当したエーレンデュルの元にカレンが現れ、マリアは自殺したのではないと訴える……。

▲アーナルデュル・インドリダソン『印』(東京創元社)【amazon】
北欧ミステリはとにかく暗い話が多い印象があるけれど、インドリダソンの作品などはその最たるものかもしれない。事件の性質はもちろんだが、その事件が起こった社会の背景、さらには主人公のエーレンデュル自身の問題も相まって、常に暗く冷え冷えとした印象ばかりだ。
なかでも本作は、父と母を失ったマリアがずっとその影を引きずったまま暮らし、夫とようやく安定した暮らしを手に入れたというのに、結局は自殺するという事件である。捜査を続けるエーレンデュルは、そんな彼女が母の死後に霊媒師と会っており、死後の世界を信じるようになっていたこと、また、父親との事件でトラウマを抱えていたことを知る。マリアの自殺した原因は果たしてどこにあったのか。
ただ、マリアの精神状態を突き止めたからといって、それが何の手がかりになるのか、それがマリアにとって救いになるのか。そもそも事件性もない。エーレンデュルも特に現状を変えられるとは思っておらず、そこには自身の置かれた現状にも似た諦めの境地すら感じさせる。だが、それでもエーレンデュルは真実を知りたいと願う。
最後まで正式な事件ではなく、半分オカルト世界に足を突っ込んだような事件で、エーレンデュルは粛々と関係者に会い、話を聞く。およそ普通のミステリで得られるようなカタルシスはほぼない。内容も地味だし、正直、読んでいて楽しいと思うことはほとんどないのだが、読者に訴えかける力は強く、とにかく読まずにはいられない。
そして最後に突きつけられる意外な真相と、更なる哀しみ。だがその哀しみには、なぜか静謐さも感じられ、そこにこそ本作最大の魅力があるのだ。
シリーズ中でも異色の作品だろうが、個人的にはかなり好み。次作は同僚の刑事が主人公らしくいわばスピンオフ的作品のようだが、こちらも期待したい。
こんな話。湖のほとりにあるサマーハウスで首を吊っている女性マリアが発見された。発見者はマリアからそのサマーハウスを借りた友人のカレン。マリアは二年前に母を失ってから不安定な状態がずっと続いており、それが原因の自殺だと思われた。しかし、事件を担当したエーレンデュルの元にカレンが現れ、マリアは自殺したのではないと訴える……。

▲アーナルデュル・インドリダソン『印』(東京創元社)【amazon】
北欧ミステリはとにかく暗い話が多い印象があるけれど、インドリダソンの作品などはその最たるものかもしれない。事件の性質はもちろんだが、その事件が起こった社会の背景、さらには主人公のエーレンデュル自身の問題も相まって、常に暗く冷え冷えとした印象ばかりだ。
なかでも本作は、父と母を失ったマリアがずっとその影を引きずったまま暮らし、夫とようやく安定した暮らしを手に入れたというのに、結局は自殺するという事件である。捜査を続けるエーレンデュルは、そんな彼女が母の死後に霊媒師と会っており、死後の世界を信じるようになっていたこと、また、父親との事件でトラウマを抱えていたことを知る。マリアの自殺した原因は果たしてどこにあったのか。
ただ、マリアの精神状態を突き止めたからといって、それが何の手がかりになるのか、それがマリアにとって救いになるのか。そもそも事件性もない。エーレンデュルも特に現状を変えられるとは思っておらず、そこには自身の置かれた現状にも似た諦めの境地すら感じさせる。だが、それでもエーレンデュルは真実を知りたいと願う。
最後まで正式な事件ではなく、半分オカルト世界に足を突っ込んだような事件で、エーレンデュルは粛々と関係者に会い、話を聞く。およそ普通のミステリで得られるようなカタルシスはほぼない。内容も地味だし、正直、読んでいて楽しいと思うことはほとんどないのだが、読者に訴えかける力は強く、とにかく読まずにはいられない。
そして最後に突きつけられる意外な真相と、更なる哀しみ。だがその哀しみには、なぜか静謐さも感じられ、そこにこそ本作最大の魅力があるのだ。
シリーズ中でも異色の作品だろうが、個人的にはかなり好み。次作は同僚の刑事が主人公らしくいわばスピンオフ的作品のようだが、こちらも期待したい。
Posted
on
マイクル・Z・リューイン『父親たちにまつわる疑問』(ハヤカワ文庫)
リューイン生誕80周年記念の掉尾を飾る作品『父親たちにまつわる疑問』を読む。なんと私立探偵アルバート・サムスン・シリーズの最新刊でもあり、邦訳では十六年ぶり。しかもシリーズ初の連作中篇集で、いろいろと気になる一冊である。
まずは収録作。
Who I Am「それが僕ですから」
Good Intentions「善意」
Extra Fries「おまけのポテトフライ」
A Question of Fathers「父親たちにまつわる疑問」

独特の味わいを持つ中篇集だ。もともとは当時流行し始めたネオ・ハードボイルドの私立探偵として登場したアルバート・サムスン。だがハードボイルドには珍しく、タフガイの対極にあるような探偵だった。暴力を嫌い、女性を口説かず、人間味のある、ユーモア精神を持った探偵である。その特徴だけで普通のハードボイルドとはかなり味わいが異なるのだけれど、シリーズを積み重ねてより磨きを増し、本書などは非常にユーモラスでハートウォーミングな物語ばかりである。ハードボイルドとかミステリとか関係なく、もうオリジナリティに溢れすぎた結果、リューイン自体が一つのジャンルのようになってしまったのかもしれない。
最初の「それが僕ですから」からして、いきなり引き込まれる。宇宙人と地球人のハーフと名乗る男・レブロンから、父の手形がついた石が自宅から盗まれたので見つけてほしいと頼まれるのだ。サムスンは近所で聞き込みを開始し、見事に事件を解決するが、極論すると本作のポイントはそこではない。事件後、犯人や事件に関与する人間の悩みや問題に寄り添い、救済しようとするところにあるのだ。
そしてその役割を担うのは、サムスンではなく、宇宙人と地球人のハーフを自称するレブロンである。レブロンは四作すべてに登場する。「善意」では血だらけの状態でサムスンに助けを求め、「おまけのポテトフライ」では妻に殺されるという疑いを抱えた依頼者を伴い、「父親たちにまつわる疑問」では異父兄の捜索を依頼してくる。
ただ、レブロンは宇宙人と地球人のハーフを名乗るだけでなく、現れるたびに有名人の名前を借用するし、独特の価値観を持っているため、サムスンはいつもコミュニケーションに苦労する。しかし、その面倒なやり取りの中でサムスンは根っからの善人、自己犠牲の塊でもあるレブロンの人柄を好ましく思い、いつしか自らの父親についても思いを巡らすようになる。その最終的な結論らしきものが描かれる表題作「父親たちにまつわる疑問」は絶品だろう。
などと書いていてふと思ったのだが、レブロンがエイリアンだと自称するから目先を逸らされるが、彼は良心の具現化のような存在でもあり、言ってみれば神のような存在なのではないだろうか。自らは直接アクションを起こさず、そのきっかけを人間に与えることで、よき結果を導こうとする。そう考えると各事件の寓話性みたいなものも感じられ、これはもしかするとリューイン流の現代のお伽噺、神話のようなものかもしれないと考えた次第。
まずは収録作。
Who I Am「それが僕ですから」
Good Intentions「善意」
Extra Fries「おまけのポテトフライ」
A Question of Fathers「父親たちにまつわる疑問」

独特の味わいを持つ中篇集だ。もともとは当時流行し始めたネオ・ハードボイルドの私立探偵として登場したアルバート・サムスン。だがハードボイルドには珍しく、タフガイの対極にあるような探偵だった。暴力を嫌い、女性を口説かず、人間味のある、ユーモア精神を持った探偵である。その特徴だけで普通のハードボイルドとはかなり味わいが異なるのだけれど、シリーズを積み重ねてより磨きを増し、本書などは非常にユーモラスでハートウォーミングな物語ばかりである。ハードボイルドとかミステリとか関係なく、もうオリジナリティに溢れすぎた結果、リューイン自体が一つのジャンルのようになってしまったのかもしれない。
最初の「それが僕ですから」からして、いきなり引き込まれる。宇宙人と地球人のハーフと名乗る男・レブロンから、父の手形がついた石が自宅から盗まれたので見つけてほしいと頼まれるのだ。サムスンは近所で聞き込みを開始し、見事に事件を解決するが、極論すると本作のポイントはそこではない。事件後、犯人や事件に関与する人間の悩みや問題に寄り添い、救済しようとするところにあるのだ。
そしてその役割を担うのは、サムスンではなく、宇宙人と地球人のハーフを自称するレブロンである。レブロンは四作すべてに登場する。「善意」では血だらけの状態でサムスンに助けを求め、「おまけのポテトフライ」では妻に殺されるという疑いを抱えた依頼者を伴い、「父親たちにまつわる疑問」では異父兄の捜索を依頼してくる。
ただ、レブロンは宇宙人と地球人のハーフを名乗るだけでなく、現れるたびに有名人の名前を借用するし、独特の価値観を持っているため、サムスンはいつもコミュニケーションに苦労する。しかし、その面倒なやり取りの中でサムスンは根っからの善人、自己犠牲の塊でもあるレブロンの人柄を好ましく思い、いつしか自らの父親についても思いを巡らすようになる。その最終的な結論らしきものが描かれる表題作「父親たちにまつわる疑問」は絶品だろう。
などと書いていてふと思ったのだが、レブロンがエイリアンだと自称するから目先を逸らされるが、彼は良心の具現化のような存在でもあり、言ってみれば神のような存在なのではないだろうか。自らは直接アクションを起こさず、そのきっかけを人間に与えることで、よき結果を導こうとする。そう考えると各事件の寓話性みたいなものも感じられ、これはもしかするとリューイン流の現代のお伽噺、神話のようなものかもしれないと考えた次第。
Posted
on
ポール・ベンジャミン『スクイズ・プレー』(新潮文庫)
純文学系の作家がミステリを書く例は枚挙にいとまがないが、これは国内外を問わない。本日の読了本、ポール・ベンジャミンの『スクイズ・プレー』もそんな一冊。
といってもポール・ベンジャミンという名前にはあまり馴染みがないところで、これはあのポール・オースターの別名である。本作はオースターが『シティ・オブ・グラス』をはじめとするニューヨーク三部作でブレイクする前、最初に書かれたデビュー長編、しかもハードボイルド作品なのだ。
こんな話。市立探偵マックス・クラインに、元大リーガーのジョージ・チャップマンから依頼が飛び込んできた。チャップマンはかつて素晴らしい成績を残した大選手だが、その絶頂時に交通事故を起こし、片脚を失って、その後は福祉や政治活動に重きを置くようになっていた。そんな彼の元に殺意を匂わす脅迫状が送られてきたのだという。
かつての交通事故にきな臭いものを感じたクラインは、事故の関係者らに聞き込みを開始するが、調査を止めるよう圧力が脅迫を受ける……。

ニューヨーク三部作にしてもハードボイルド風味が濃い作品なので、ポール・オースターがハードボイルドを書いていたとはいえ、そこまで意外性はないのだが、それでも、それらの作品はあくまでハードボイルドテイストを備えた純文学系の作品であった。その点『スクイズ・プレー』はストレートど真ん中のハードボイルドになっていることに驚く。
もうベッタベタのハードボイルド。主人公のマックスは正義のためには職をも投げ打ち、理不尽なことがあっても自分の主義を貫き通す、暴力にも屈せず劣勢でも減らず口を叩き続ける。時に女性に対して甘さを見せるところも含め、クラシックという但書はつくけれども、典型的なハードボイルドの私立探偵だ。彼が巻き込まれる事件にしても、隠しごとをするする依頼人、悲劇の美女、敵対する警官にマフィアのボス、汚れた上流階級などなど、お膳立てもバッチリである。
書かれた当時はハードボイルドが流行していたこともあるだろうが、それにしてもハードボイルドというスタイルをここまで完璧にマスターしていたことに感心するほかない。
表面的スタイルだけでなく、内容も悪くない。
野暮ではあるが、最近は野球に詳しくない人も多いらしいので一応書いておくと、タイトルの「スクイズ・プレー」はバントによって三塁上のランナーを返して得点を狙うプレイのこと。自らははアウトになるのが前提で、「犠打」の一つである。要するに自己犠牲のプレイであり、これが終盤に大きな意味を持ってくる。単に野球ネタだから、と思っているとそれが見事にテーマに直結する流れは、これまたさすがとしか言いようがない。
個人的な好みでいうと、主人公のキャラクターが先行しすぎている嫌いもあり、もう少し主人公の動機づけを掘り下げてくれればとも思ったが、まあ、オースターがこれをやるとハードボイルドでは無くなってしまう可能性もあるので仕方ないか。
ともかくクラシックなハードボイルドを読みたい人であれば、オースター云々抜きで普通にオススメしたい一作である。
といってもポール・ベンジャミンという名前にはあまり馴染みがないところで、これはあのポール・オースターの別名である。本作はオースターが『シティ・オブ・グラス』をはじめとするニューヨーク三部作でブレイクする前、最初に書かれたデビュー長編、しかもハードボイルド作品なのだ。
こんな話。市立探偵マックス・クラインに、元大リーガーのジョージ・チャップマンから依頼が飛び込んできた。チャップマンはかつて素晴らしい成績を残した大選手だが、その絶頂時に交通事故を起こし、片脚を失って、その後は福祉や政治活動に重きを置くようになっていた。そんな彼の元に殺意を匂わす脅迫状が送られてきたのだという。
かつての交通事故にきな臭いものを感じたクラインは、事故の関係者らに聞き込みを開始するが、調査を止めるよう圧力が脅迫を受ける……。

ニューヨーク三部作にしてもハードボイルド風味が濃い作品なので、ポール・オースターがハードボイルドを書いていたとはいえ、そこまで意外性はないのだが、それでも、それらの作品はあくまでハードボイルドテイストを備えた純文学系の作品であった。その点『スクイズ・プレー』はストレートど真ん中のハードボイルドになっていることに驚く。
もうベッタベタのハードボイルド。主人公のマックスは正義のためには職をも投げ打ち、理不尽なことがあっても自分の主義を貫き通す、暴力にも屈せず劣勢でも減らず口を叩き続ける。時に女性に対して甘さを見せるところも含め、クラシックという但書はつくけれども、典型的なハードボイルドの私立探偵だ。彼が巻き込まれる事件にしても、隠しごとをするする依頼人、悲劇の美女、敵対する警官にマフィアのボス、汚れた上流階級などなど、お膳立てもバッチリである。
書かれた当時はハードボイルドが流行していたこともあるだろうが、それにしてもハードボイルドというスタイルをここまで完璧にマスターしていたことに感心するほかない。
表面的スタイルだけでなく、内容も悪くない。
野暮ではあるが、最近は野球に詳しくない人も多いらしいので一応書いておくと、タイトルの「スクイズ・プレー」はバントによって三塁上のランナーを返して得点を狙うプレイのこと。自らははアウトになるのが前提で、「犠打」の一つである。要するに自己犠牲のプレイであり、これが終盤に大きな意味を持ってくる。単に野球ネタだから、と思っているとそれが見事にテーマに直結する流れは、これまたさすがとしか言いようがない。
個人的な好みでいうと、主人公のキャラクターが先行しすぎている嫌いもあり、もう少し主人公の動機づけを掘り下げてくれればとも思ったが、まあ、オースターがこれをやるとハードボイルドでは無くなってしまう可能性もあるので仕方ないか。
ともかくクラシックなハードボイルドを読みたい人であれば、オースター云々抜きで普通にオススメしたい一作である。


