Posted in 01 2018
Posted
on
ロバート・クレイス『約束』(創元推理文庫)
ロバート・クレイスの『約束』を読む。警察犬マギーと警察官スコットの活躍と友情を描いた前作『容疑者』の続編。だが、本作はスコット&マギーのシリーズというだけでなく、同時に著者もうひとつのシリーズキャラクター、私立探偵エルヴィス・コール&ジョー・パイクが登場するダブル主演作でもある。
こんな話。
スコットと警察犬のマギーは逃亡中の殺人犯を追跡していた。しかし、ある住宅地で容疑者と思われる死体と大量の爆発物を発見してしまう。
時を同じくして、私立探偵コールもまたその住宅地を訪れていた。失踪した会社の同僚を探してほしいという依頼の調査のためだったが、スコットッたちの捜査する現場から逃げ出した男を追いかけようとしたことで、警察からいらぬ疑惑の目を向けられてしまう。しかし、失踪事件の陰に大きな犯罪があることを感じていたコールは、あくまで独自に調査を続けようとする。
一方、現場から逃げ出した男を直前に目撃していたことから、スコットの身には危険が迫っていた……。

ずいぶん上からの言い方になってしまうが(苦笑)、ロバート・クレイスもいつの間にかすっかり巧い作家になったものだ。著者が複数のシリーズを融合させるという手法も、最近ではそれほど珍しいものではなくなってしまったが、それでもやはり難しい作業であることにに変わりはないだろう。
特にクレイスの場合、シリーズの主人公がそれぞれパイクとマギーという相棒を連れていることから、よけいやりにくいはずで、それを案外さらりとやってのけているのが見事。
単に事件解決までを描くだけではなく、描写の配分という問題もあるだろうし、クレイスは比較的強いメッセージ性を込める作家だから、そういう部分の盛り上げも考えると、これは相当にレベルの高い作品なのである。
『容疑者』に比べると本作は事件そのものも魅力的だ。
ストーリーはエイミーという女性化学技術者の失踪事件が軸になるのだが、関係者の多くが隠し立てをする状況。そのなかでコールはパイクやジョン・ストーン、そしてスコット&マギーらの協力を得て、ひとつずつ新たな事実を確かなものにしていく。そのなかでエイミーという女性の本当の姿も明らかになっていくのは、常套手段といえば常套手段だが、そこからさらに捻って、この失踪事件の様相そのものが揺らぐような展開にもっていく。
簡単に物事が進みすぎるきらいもないではないが、こういうストーリーの出し入れというか緩急というか、適度な焦燥感と爽快感の混じり具合もクレイスの巧いところだ。
ただ、『容疑者』のような犬と人の感動友情ストーリーは今回さすがに抑え気味だ。毎度毎度あんな感動的な出来事が同じ当事者に起こるわけがないので、まあ、そこは致し方あるまい。
とはいえマギーの見せ場や犬好きには堪えられないシーンもちゃんと用意されているし、場面ごとのクオリティはいささかの劣化もない。前作が気に入った人なら本作も必読である。
今後はシリーズキャラクターをいろいろ取り混ぜた展開もあるようで、ますます楽しみになってきたクレイスの作品。積ん読も少し消化していくべきかな。
こんな話。
スコットと警察犬のマギーは逃亡中の殺人犯を追跡していた。しかし、ある住宅地で容疑者と思われる死体と大量の爆発物を発見してしまう。
時を同じくして、私立探偵コールもまたその住宅地を訪れていた。失踪した会社の同僚を探してほしいという依頼の調査のためだったが、スコットッたちの捜査する現場から逃げ出した男を追いかけようとしたことで、警察からいらぬ疑惑の目を向けられてしまう。しかし、失踪事件の陰に大きな犯罪があることを感じていたコールは、あくまで独自に調査を続けようとする。
一方、現場から逃げ出した男を直前に目撃していたことから、スコットの身には危険が迫っていた……。

ずいぶん上からの言い方になってしまうが(苦笑)、ロバート・クレイスもいつの間にかすっかり巧い作家になったものだ。著者が複数のシリーズを融合させるという手法も、最近ではそれほど珍しいものではなくなってしまったが、それでもやはり難しい作業であることにに変わりはないだろう。
特にクレイスの場合、シリーズの主人公がそれぞれパイクとマギーという相棒を連れていることから、よけいやりにくいはずで、それを案外さらりとやってのけているのが見事。
単に事件解決までを描くだけではなく、描写の配分という問題もあるだろうし、クレイスは比較的強いメッセージ性を込める作家だから、そういう部分の盛り上げも考えると、これは相当にレベルの高い作品なのである。
『容疑者』に比べると本作は事件そのものも魅力的だ。
ストーリーはエイミーという女性化学技術者の失踪事件が軸になるのだが、関係者の多くが隠し立てをする状況。そのなかでコールはパイクやジョン・ストーン、そしてスコット&マギーらの協力を得て、ひとつずつ新たな事実を確かなものにしていく。そのなかでエイミーという女性の本当の姿も明らかになっていくのは、常套手段といえば常套手段だが、そこからさらに捻って、この失踪事件の様相そのものが揺らぐような展開にもっていく。
簡単に物事が進みすぎるきらいもないではないが、こういうストーリーの出し入れというか緩急というか、適度な焦燥感と爽快感の混じり具合もクレイスの巧いところだ。
ただ、『容疑者』のような犬と人の感動友情ストーリーは今回さすがに抑え気味だ。毎度毎度あんな感動的な出来事が同じ当事者に起こるわけがないので、まあ、そこは致し方あるまい。
とはいえマギーの見せ場や犬好きには堪えられないシーンもちゃんと用意されているし、場面ごとのクオリティはいささかの劣化もない。前作が気に入った人なら本作も必読である。
今後はシリーズキャラクターをいろいろ取り混ぜた展開もあるようで、ますます楽しみになってきたクレイスの作品。積ん読も少し消化していくべきかな。
Posted
on
エドガー・ウォーレス『真紅の輪』(論創海外ミステリ)
エドガー・ウォーレスの『真紅の輪』を読む。
著者のウォーレスは二十世紀初頭にスリラーで絶大なる人気を誇った作家で、あの『キングコング』の生みの親でもある。多作家としても知られ、その著作は長篇だけでも百五十作以上に及び、その他にも短編やシナリオ、エッセイなど多数にのぼる。
日本でも昭和初期にはけっこう訳されていたようだが、内容が通俗的で時代がかっているせいか戦後は紹介が途絶え、二十一世紀になってようやく長崎出版や論創社で新訳が出るようになったのは、まだ記憶に新しいところだ。
さて『真紅の輪』だが、まずはストーリー。
連続殺人でロンドンを恐怖に陥れている“クリムゾン・サークル”。大金持ちに脅迫状を送っては、多額の金銭を要求してくる謎の犯罪集団である。さもなくば命はない、と。
それに立ち向かうのが警視庁のパー警部、そして超能力で調査を行う私立探偵イエール。二人は協力して富豪ジェイムズ・ビアードモアを警護しようとするが、クリムゾン・サークルの手によって遂にジェイムズは殺害される。
そして事件の影で暗躍する謎の女タリア。ジェイムズの息子ジャックは周囲の反対も聞かずタリアに惹かれていくが……。

まあ、何ともぶっとんだ設定である。とりわけ探偵イエールがすごくて、彼は現場に残された物から心象風景を読みとるという、いわゆるサイコメトリーの持ち主。
一方のパー警部は一見、鈍重そうながら、実は粘り強さが身上の切れ者。この相反するやり方の二人が協力して捜査を進めるのがなかなか見ものである。ここまでタイプが違うとハードボイルドあたりでは絶対に敵対関係になるはずだが、それをやらないところが時代ゆえか著者の上手いところなのか。悪党側が混沌としているだけに、捜査側が一枚岩になっているのはストレスがなくてよろしい。
また、探偵だけでなく“クリムゾン・サークル”の設定も捨てがたい。
けっこうな規模の犯罪組織なのだが、そのボスは誰も見たことがなく、また、組織のメンバーもすべては秘密に包まれている。
時代がかった部分ではあるが、もちろんサスペンスを高める効果は高く、特にボスの正体はわかりそうでわかりにくく、伏線やミスリードも適度に散りばめられていてミステリとしてもきちんと機能している。
ミステリ的な興味でいうと密室殺人も危ういトリックではあるが着想としては面白い。
これらに加えて、謎の女泥棒タリアの存在も忘れてはならない。峰不二子的な存在として(苦笑)パー警部や探偵イエールとも対立し、他の犯罪者とも丁々発止。“クリムゾン・サークル”ともどうやら関係をもちそうな、この魅力的な悪女。
さらには、タニアに恋い焦がれ、何度も断られながらも「あなたはそんな悪人じゃない」と言い続ける純情青年のジャック。この二人のロマンスの行方も要注目。決して味付けで終わらせない著者の腕前が見事だ。
とにかく予想以上の面白さである。ぶっ飛んだ設定なのだが、テイストはあくまで通俗スリラー。思わず先を読みたくなる興味のつなげ方、テンポのよさ、そして読みやすさが合わさって、とても1922年の作品とは思えない。
これまで訳された『正義の四人/ロンドン大包囲網』や『淑女怪盗ジェーンの冒険』も予想以上だったが、やはり書かれた時代というところがあった。しかし、本作はそういった但し書き抜きにしても十分楽しめる。
サイト「翻訳ミステリー大賞シンジケート」の記事で、「乱歩の通俗物長編によく似ている。」という評があったのだが、そう、まさにそのとおり。乱歩の通俗長編がもついかがわしい魅力が本作にも満載なのだ。発表当時は評論家に酷評されたウォーレスだが、一般大衆の好みはバカにはできないのである。
著者のウォーレスは二十世紀初頭にスリラーで絶大なる人気を誇った作家で、あの『キングコング』の生みの親でもある。多作家としても知られ、その著作は長篇だけでも百五十作以上に及び、その他にも短編やシナリオ、エッセイなど多数にのぼる。
日本でも昭和初期にはけっこう訳されていたようだが、内容が通俗的で時代がかっているせいか戦後は紹介が途絶え、二十一世紀になってようやく長崎出版や論創社で新訳が出るようになったのは、まだ記憶に新しいところだ。
さて『真紅の輪』だが、まずはストーリー。
連続殺人でロンドンを恐怖に陥れている“クリムゾン・サークル”。大金持ちに脅迫状を送っては、多額の金銭を要求してくる謎の犯罪集団である。さもなくば命はない、と。
それに立ち向かうのが警視庁のパー警部、そして超能力で調査を行う私立探偵イエール。二人は協力して富豪ジェイムズ・ビアードモアを警護しようとするが、クリムゾン・サークルの手によって遂にジェイムズは殺害される。
そして事件の影で暗躍する謎の女タリア。ジェイムズの息子ジャックは周囲の反対も聞かずタリアに惹かれていくが……。

まあ、何ともぶっとんだ設定である。とりわけ探偵イエールがすごくて、彼は現場に残された物から心象風景を読みとるという、いわゆるサイコメトリーの持ち主。
一方のパー警部は一見、鈍重そうながら、実は粘り強さが身上の切れ者。この相反するやり方の二人が協力して捜査を進めるのがなかなか見ものである。ここまでタイプが違うとハードボイルドあたりでは絶対に敵対関係になるはずだが、それをやらないところが時代ゆえか著者の上手いところなのか。悪党側が混沌としているだけに、捜査側が一枚岩になっているのはストレスがなくてよろしい。
また、探偵だけでなく“クリムゾン・サークル”の設定も捨てがたい。
けっこうな規模の犯罪組織なのだが、そのボスは誰も見たことがなく、また、組織のメンバーもすべては秘密に包まれている。
時代がかった部分ではあるが、もちろんサスペンスを高める効果は高く、特にボスの正体はわかりそうでわかりにくく、伏線やミスリードも適度に散りばめられていてミステリとしてもきちんと機能している。
ミステリ的な興味でいうと密室殺人も危ういトリックではあるが着想としては面白い。
これらに加えて、謎の女泥棒タリアの存在も忘れてはならない。峰不二子的な存在として(苦笑)パー警部や探偵イエールとも対立し、他の犯罪者とも丁々発止。“クリムゾン・サークル”ともどうやら関係をもちそうな、この魅力的な悪女。
さらには、タニアに恋い焦がれ、何度も断られながらも「あなたはそんな悪人じゃない」と言い続ける純情青年のジャック。この二人のロマンスの行方も要注目。決して味付けで終わらせない著者の腕前が見事だ。
とにかく予想以上の面白さである。ぶっ飛んだ設定なのだが、テイストはあくまで通俗スリラー。思わず先を読みたくなる興味のつなげ方、テンポのよさ、そして読みやすさが合わさって、とても1922年の作品とは思えない。
これまで訳された『正義の四人/ロンドン大包囲網』や『淑女怪盗ジェーンの冒険』も予想以上だったが、やはり書かれた時代というところがあった。しかし、本作はそういった但し書き抜きにしても十分楽しめる。
サイト「翻訳ミステリー大賞シンジケート」の記事で、「乱歩の通俗物長編によく似ている。」という評があったのだが、そう、まさにそのとおり。乱歩の通俗長編がもついかがわしい魅力が本作にも満載なのだ。発表当時は評論家に酷評されたウォーレスだが、一般大衆の好みはバカにはできないのである。
Posted
on
ジョルジュ・シムノン『メグレ夫人の恋人』(角川文庫)
大雪なのでいつもよりは早めに帰宅。風呂上がりに雪かきをするはめになるとは夢にも思わなんだが(苦笑)。
本日の読了本はシムノンの短編集『メグレ夫人の恋人』。まずは収録作から。
L'Amoureux de Madame Maigret「メグレ夫人の恋人」
Peine de mort「死刑」
La Fenetre ouverte「開いた窓」
La Peniche aux deux pendus「首吊り船」
Les Larmes bougie「蝋のしずく」
Une erreur de Maigret「メグレの失敗」
L'Affaire du boulevard Beaumarchais「ボーマルシェ大通りの事件 」
Jeumont, cinquante et une minutes「停車─五十一分間」
Stan le tueur「殺し屋スタン」

本書は1944年に刊行された『Les Nouvelles Enquetes de Maigret』(メグレ、最新の事件簿)から九作をセレクトした一冊。メグレものの短編集は五冊あって、長篇に比べると実に少ないのだが、その出来は長篇に勝るとも劣らない。
全般に長篇ほどには人間ドラマを押し出しておらず、意外な結末を用意するなど、かなり通常のミステリに寄せているような印象である。
短篇をもとに長篇化するケースは海外の作家にありがちだけれど、シムノンもその例に漏れず、おそらくは長篇化する際にいろいろとドラマの肉付けをすると思われる。したがってミステリとしては、むしろ短篇の方がすっきり読めるものが多いのかもしれない。まあ、あくまで想像だけど。
ともあれシムノンの作品でどんでん返しがこれだけ楽しめるというのは非常に楽しい。
「メグレ夫人の恋人」はタイトルだけ見れば不倫もの?と勘違いしそうだが、まったくそんなことはない。メグレ夫妻が暮らすアパルトメンから見渡せる広場で、いつもベンチに長時間座っている男がおり、それをメグレ夫人が気にしていることから、メグレが夫人をからかって“恋人”と称したことによるもの。
ところがあるとき男がベンチに座ったまま殺害されてしまという事件が起こり、男の奇妙な行動の裏に何があったのかメグレが捜査する。
メグレ夫人が夫顔負けの推理や捜査の真似ごとをするのが微笑ましいが、真相やそれに到達する流れも面白く巻頭を飾るにふさわしい一作。
「死刑」も面白い。尻尾を掴ませない容疑者に対し、メグレは徹底的な尾行でプレッシャーをかけるのだが、そこにはメグレの意外な狙いがあったというもの。
実業家の爆殺事件を扱うのが「開いた窓」。メグレは実業家に長年虐げられていた部下に目をつけるものの、その男にはアリバイがあった……。
「首吊り船」はセーヌ川に浮かぶ船から発見された男女の首吊り死体の謎を追う。男はちょっとした資産家の老人、女はその資産目当てに結婚した若い妻であった……。
田舎町の老姉妹宅で起こった殺人事件を捜査する「蝋のしずく」。町の描写や事件の真相が陰々滅々としており、メグレもの本来の味わいが濃厚な一品。
タイトルどおり「メグレの失敗」談。特殊書店に勤める若い女性が殺害され、メグレは店主を犯人とにらむが、その真相はほろ苦いものだった……。メグレが行き場のない感情を爆発させるのが見もの。
「ボーマルシェ大通りの事件」は夫と妻、その妹の三角関係から起こった事件。妻が毒殺され、メグレは夫と妹を交互に調べていくが……。現代でこそ起こりそうな事件。
国際列車のなかで起きた殺人事件を捜査するのが 「停車─五十一分間」。『オリエント急行殺人事件』ばりのシチュエーションは楽しいが、ラストが妙に駆け足なことが物足りず、ミステリとしての仕掛けもいまひとつ。
「殺し屋スタン」は早川書房の世界ミステリ全集のアンソロジー『37の短編』、それを再編集したポケミス版『天外消失』にも「殺し屋」のタイトルで収録されている傑作。
殺し屋スタンを含むポーランド難民の強盗団を追うメグレたち。そこへ自殺を考えているポーランド人の男が、せめて最後にこの命をポーランド強盗団逮捕に役立てたいと、執拗にメグレを追い回す。メグレは渋々引き受けることになるが……。
再読ゆえ真相は知っていたが、シムノンの語り口がある意味カモフラージュになっていることがよくわかり、再読でも十分楽しめる。未読の人ならもちろんこのラストに驚くはず。
本日の読了本はシムノンの短編集『メグレ夫人の恋人』。まずは収録作から。
L'Amoureux de Madame Maigret「メグレ夫人の恋人」
Peine de mort「死刑」
La Fenetre ouverte「開いた窓」
La Peniche aux deux pendus「首吊り船」
Les Larmes bougie「蝋のしずく」
Une erreur de Maigret「メグレの失敗」
L'Affaire du boulevard Beaumarchais「ボーマルシェ大通りの事件 」
Jeumont, cinquante et une minutes「停車─五十一分間」
Stan le tueur「殺し屋スタン」

本書は1944年に刊行された『Les Nouvelles Enquetes de Maigret』(メグレ、最新の事件簿)から九作をセレクトした一冊。メグレものの短編集は五冊あって、長篇に比べると実に少ないのだが、その出来は長篇に勝るとも劣らない。
全般に長篇ほどには人間ドラマを押し出しておらず、意外な結末を用意するなど、かなり通常のミステリに寄せているような印象である。
短篇をもとに長篇化するケースは海外の作家にありがちだけれど、シムノンもその例に漏れず、おそらくは長篇化する際にいろいろとドラマの肉付けをすると思われる。したがってミステリとしては、むしろ短篇の方がすっきり読めるものが多いのかもしれない。まあ、あくまで想像だけど。
ともあれシムノンの作品でどんでん返しがこれだけ楽しめるというのは非常に楽しい。
「メグレ夫人の恋人」はタイトルだけ見れば不倫もの?と勘違いしそうだが、まったくそんなことはない。メグレ夫妻が暮らすアパルトメンから見渡せる広場で、いつもベンチに長時間座っている男がおり、それをメグレ夫人が気にしていることから、メグレが夫人をからかって“恋人”と称したことによるもの。
ところがあるとき男がベンチに座ったまま殺害されてしまという事件が起こり、男の奇妙な行動の裏に何があったのかメグレが捜査する。
メグレ夫人が夫顔負けの推理や捜査の真似ごとをするのが微笑ましいが、真相やそれに到達する流れも面白く巻頭を飾るにふさわしい一作。
「死刑」も面白い。尻尾を掴ませない容疑者に対し、メグレは徹底的な尾行でプレッシャーをかけるのだが、そこにはメグレの意外な狙いがあったというもの。
実業家の爆殺事件を扱うのが「開いた窓」。メグレは実業家に長年虐げられていた部下に目をつけるものの、その男にはアリバイがあった……。
「首吊り船」はセーヌ川に浮かぶ船から発見された男女の首吊り死体の謎を追う。男はちょっとした資産家の老人、女はその資産目当てに結婚した若い妻であった……。
田舎町の老姉妹宅で起こった殺人事件を捜査する「蝋のしずく」。町の描写や事件の真相が陰々滅々としており、メグレもの本来の味わいが濃厚な一品。
タイトルどおり「メグレの失敗」談。特殊書店に勤める若い女性が殺害され、メグレは店主を犯人とにらむが、その真相はほろ苦いものだった……。メグレが行き場のない感情を爆発させるのが見もの。
「ボーマルシェ大通りの事件」は夫と妻、その妹の三角関係から起こった事件。妻が毒殺され、メグレは夫と妹を交互に調べていくが……。現代でこそ起こりそうな事件。
国際列車のなかで起きた殺人事件を捜査するのが 「停車─五十一分間」。『オリエント急行殺人事件』ばりのシチュエーションは楽しいが、ラストが妙に駆け足なことが物足りず、ミステリとしての仕掛けもいまひとつ。
「殺し屋スタン」は早川書房の世界ミステリ全集のアンソロジー『37の短編』、それを再編集したポケミス版『天外消失』にも「殺し屋」のタイトルで収録されている傑作。
殺し屋スタンを含むポーランド難民の強盗団を追うメグレたち。そこへ自殺を考えているポーランド人の男が、せめて最後にこの命をポーランド強盗団逮捕に役立てたいと、執拗にメグレを追い回す。メグレは渋々引き受けることになるが……。
再読ゆえ真相は知っていたが、シムノンの語り口がある意味カモフラージュになっていることがよくわかり、再読でも十分楽しめる。未読の人ならもちろんこのラストに驚くはず。
Posted
on
吉野賛十『吉野賛十探偵小説選』(論創ミステリ叢書)
論創ミステリ叢書から『吉野賛十探偵小説選』を読む。
吉野賛十については名前だけはけっこう記憶に残っていて、それは無論、鮎川哲也の『幻の探偵作家を求めて』に取り上げられていたからなのだが、実際のところ、これまで読んでいるのはおそらく短編「鼻」一作しかない。
それもそのはず。吉野賛十の探偵小説がまとめられたのは本書が初。しかも「鼻」以外はアンソロジーに収録されたこともないようで、つまり本書に採られている作品は「鼻」以外すべて単行本初収録なのである。
論創ミステリ叢書ではそれほど珍しくもないことだが、これ一冊で「吉野賛十探偵小説全集」というわけで、毎度のことながら感謝感激である。
さて、吉野賛十は商業デビューこそ探偵小説の「ロオランサンの女の事件」だったが、その後は純文学中心に同人活動などを行なっていた。上で「吉野賛十の探偵小説がまとめられたのは本書が初」などと書いたが、純文学の著書としてはすでにこの時期にいくつかあり、作家としては比較的、順調な歩みだったようだ。
だが戦争の影響で執筆から離れてしまい、戦後は商業高校や盲学校の教師として働く。そして1950年代の前半ごろ、木々高太郎と知り合ったことをきっかけに、探偵小説で作家としての再スタートをきるのである。

「ロオランサンの女の事件」
「鼻」
「顔」
「耳」
「指」
「声」
「二又道」
「不整形」
「落胤の恐怖」
「悪の系譜」
「北を向いている顔」
「五万円の小切手」
「それを見ていた女」
「レンズの蔭の殺人」
「犯人は声を残した」
「魔の大烏賊」
「宝石」
「三人は逃亡した」
「盲目夫婦の死」
「蛇」
「死体ゆずります」
「走狗」
収録作は以上。
吉野賛十の作品の特徴は、なんといっても盲人を扱った作品が多いことで、これはもちろん盲学校での教職経験が大きく活きているといっていいだろう。
探偵役に盲目の花輪正一を起用したシリーズもあるが、盲目の探偵というと思い出すのが、まずアーネスト・ブラマの生んだマックス・カラドス。そのほかではベイナード・ケンドリックのダンカン・マクレーン、デイヴィッド・ローンのハーレックあたり。
ただ、これらの探偵は目が見えないことから超人的な聴覚や勘のよさを身につけて、常人顔負けの活躍をするのに対し、本シリーズに登場する花輪正一は名探偵にはほど遠い。多少は勘のよさも見せるが基本は一般人であり、探偵役というよりは狂言回しに近いかもしれない。
ただ、そういう主人公の位置付けが、むしろ効果的で面白いところでもある。
たとえばマックス・カラドスあたりになると、作中では目が見えないことなどほとんど本筋に関係ないのだけれど、花輪正一ものでは目が見えないことがストレートに物語の中心に据えられ、そこから派生する謎や推理が生まれてくるといった按配。狙いの面白さや興味深さでは、花輪正一ものに軍配を上げたいところだ。
盲人の心理や行動もさすがに詳しいし、作品にうユーモアとペーソスが入り混じった感じ、なんともいえないトホホな雰囲気がまた絶妙で、これが意外とクセになる(苦笑)。
惜しむらくはミステリとしての出来がそれほどでもないところだが、当時だからこそ書けた、日本の探偵小説史上でも稀有なシリーズということで、やはり探偵小説マニアとしては押さえておきたい一冊だろう。
吉野賛十については名前だけはけっこう記憶に残っていて、それは無論、鮎川哲也の『幻の探偵作家を求めて』に取り上げられていたからなのだが、実際のところ、これまで読んでいるのはおそらく短編「鼻」一作しかない。
それもそのはず。吉野賛十の探偵小説がまとめられたのは本書が初。しかも「鼻」以外はアンソロジーに収録されたこともないようで、つまり本書に採られている作品は「鼻」以外すべて単行本初収録なのである。
論創ミステリ叢書ではそれほど珍しくもないことだが、これ一冊で「吉野賛十探偵小説全集」というわけで、毎度のことながら感謝感激である。
さて、吉野賛十は商業デビューこそ探偵小説の「ロオランサンの女の事件」だったが、その後は純文学中心に同人活動などを行なっていた。上で「吉野賛十の探偵小説がまとめられたのは本書が初」などと書いたが、純文学の著書としてはすでにこの時期にいくつかあり、作家としては比較的、順調な歩みだったようだ。
だが戦争の影響で執筆から離れてしまい、戦後は商業高校や盲学校の教師として働く。そして1950年代の前半ごろ、木々高太郎と知り合ったことをきっかけに、探偵小説で作家としての再スタートをきるのである。

「ロオランサンの女の事件」
「鼻」
「顔」
「耳」
「指」
「声」
「二又道」
「不整形」
「落胤の恐怖」
「悪の系譜」
「北を向いている顔」
「五万円の小切手」
「それを見ていた女」
「レンズの蔭の殺人」
「犯人は声を残した」
「魔の大烏賊」
「宝石」
「三人は逃亡した」
「盲目夫婦の死」
「蛇」
「死体ゆずります」
「走狗」
収録作は以上。
吉野賛十の作品の特徴は、なんといっても盲人を扱った作品が多いことで、これはもちろん盲学校での教職経験が大きく活きているといっていいだろう。
探偵役に盲目の花輪正一を起用したシリーズもあるが、盲目の探偵というと思い出すのが、まずアーネスト・ブラマの生んだマックス・カラドス。そのほかではベイナード・ケンドリックのダンカン・マクレーン、デイヴィッド・ローンのハーレックあたり。
ただ、これらの探偵は目が見えないことから超人的な聴覚や勘のよさを身につけて、常人顔負けの活躍をするのに対し、本シリーズに登場する花輪正一は名探偵にはほど遠い。多少は勘のよさも見せるが基本は一般人であり、探偵役というよりは狂言回しに近いかもしれない。
ただ、そういう主人公の位置付けが、むしろ効果的で面白いところでもある。
たとえばマックス・カラドスあたりになると、作中では目が見えないことなどほとんど本筋に関係ないのだけれど、花輪正一ものでは目が見えないことがストレートに物語の中心に据えられ、そこから派生する謎や推理が生まれてくるといった按配。狙いの面白さや興味深さでは、花輪正一ものに軍配を上げたいところだ。
盲人の心理や行動もさすがに詳しいし、作品にうユーモアとペーソスが入り混じった感じ、なんともいえないトホホな雰囲気がまた絶妙で、これが意外とクセになる(苦笑)。
惜しむらくはミステリとしての出来がそれほどでもないところだが、当時だからこそ書けた、日本の探偵小説史上でも稀有なシリーズということで、やはり探偵小説マニアとしては押さえておきたい一冊だろう。
Posted
on
小酒井不木『疑問の黒枠』(河出文庫)
小酒井不木の『疑問の黒枠』を読む。河出文庫から「KAWADEノスタルジック 探偵・怪奇・幻想シリーズ」の一冊として刊行された戦前の探偵小説。このシリーズも順調に刊行が続いているようで何よりだが、論創社が短編中心なので、こちらはぜひこういう長篇で攻めてもらいたいところである。
さて『疑問の黒枠』だが、こんな話。
名古屋で会社を営む村井喜七郎の死亡広告が新聞に掲載された。しかし、本人は死んでおらず、実はこれが何物かによって出された虚偽の広告であった。ところが村井はこれを面白がり、親しい住職と相談して、広告どおりに模擬葬式を出そうとする。
そして葬儀当日。村井は死装束をつけて棺の中へ入り、その後、姿を現す段取りだったが、一向に出てくる気配がない。心配した周囲の者が棺の蓋を開けると、なんと村井は本当に死体となって発見されたのだ。
さらには村井の娘・富子がその場から失踪し、医師の丸薬も紛失。富子の恋人・中沢保は村井に取り入っていた押毛が怪しいと騒ぐが、今度はその押毛もいなくなる始末。
一方、村井の遺体は検死にかけられるべく、小窪教授のもとに届けられていた。小窪は木乃伊の研究を続けながら、犯罪にも一家言をもつ医学者である。だが、解剖のために小窪たちが安置所を訪れると、今度はその遺体、までもが消え失せていた。
警察に協力して中沢保や小窪の助手・肥後も加わり、捜査は進められるが……。

日本の探偵小説黎明期に多大な貢献を果たした不木の、これが長編第一作にあたる。そのせいか力の入り方は相当なもので、大丈夫かと思うぐらい次から次へと謎を提示し、サスペンス仕立てで物語を引っ張っていく。
不木といえば医学知識を生かした怪奇風味の変格短編というイメージが強いのだけれど、本作に関してはきちんと本格としての興味も先行しており(ただし決してフェアではない)、短編の諸作品に比べるとスマートな印象である。
ただ、そんな印象とは裏腹に、実はプロットは相当に複雑であり、真相もこてこて。登場人物も無駄な人は一切いませんというぐらい重要な役割を振られ、全員が犯人とは言わないけれど(苦笑)、まあ関係者の多いこと。
その結果として辻褄を合わせるための御都合主義も少なくはなく、とにかくプロットがストーリーに上手く落としこまれていないのが痛い。読んでいてちぐはぐな印象はどうしても否めず、そこが本作の大きな弱点といえるだろう。
とはいえ、そういった粗に目をつぶってあげるなら、本作の探偵小説としての熱量は素晴らしいものがあり、個人的にはまずまず楽しむことができた。
特に本作の探偵役(これ自体も一つの興味なので、誰とは書かないが)の事件における役割や立ち位置がなかなか面白く、この時代の日本でこういうアイディアを形にしたというだけでも、読む価値はあるといっておこう。
さて『疑問の黒枠』だが、こんな話。
名古屋で会社を営む村井喜七郎の死亡広告が新聞に掲載された。しかし、本人は死んでおらず、実はこれが何物かによって出された虚偽の広告であった。ところが村井はこれを面白がり、親しい住職と相談して、広告どおりに模擬葬式を出そうとする。
そして葬儀当日。村井は死装束をつけて棺の中へ入り、その後、姿を現す段取りだったが、一向に出てくる気配がない。心配した周囲の者が棺の蓋を開けると、なんと村井は本当に死体となって発見されたのだ。
さらには村井の娘・富子がその場から失踪し、医師の丸薬も紛失。富子の恋人・中沢保は村井に取り入っていた押毛が怪しいと騒ぐが、今度はその押毛もいなくなる始末。
一方、村井の遺体は検死にかけられるべく、小窪教授のもとに届けられていた。小窪は木乃伊の研究を続けながら、犯罪にも一家言をもつ医学者である。だが、解剖のために小窪たちが安置所を訪れると、今度はその遺体、までもが消え失せていた。
警察に協力して中沢保や小窪の助手・肥後も加わり、捜査は進められるが……。

日本の探偵小説黎明期に多大な貢献を果たした不木の、これが長編第一作にあたる。そのせいか力の入り方は相当なもので、大丈夫かと思うぐらい次から次へと謎を提示し、サスペンス仕立てで物語を引っ張っていく。
不木といえば医学知識を生かした怪奇風味の変格短編というイメージが強いのだけれど、本作に関してはきちんと本格としての興味も先行しており(ただし決してフェアではない)、短編の諸作品に比べるとスマートな印象である。
ただ、そんな印象とは裏腹に、実はプロットは相当に複雑であり、真相もこてこて。登場人物も無駄な人は一切いませんというぐらい重要な役割を振られ、全員が犯人とは言わないけれど(苦笑)、まあ関係者の多いこと。
その結果として辻褄を合わせるための御都合主義も少なくはなく、とにかくプロットがストーリーに上手く落としこまれていないのが痛い。読んでいてちぐはぐな印象はどうしても否めず、そこが本作の大きな弱点といえるだろう。
とはいえ、そういった粗に目をつぶってあげるなら、本作の探偵小説としての熱量は素晴らしいものがあり、個人的にはまずまず楽しむことができた。
特に本作の探偵役(これ自体も一つの興味なので、誰とは書かないが)の事件における役割や立ち位置がなかなか面白く、この時代の日本でこういうアイディアを形にしたというだけでも、読む価値はあるといっておこう。
Posted
on
ジョルジュ・シムノン『片道切符』(集英社文庫)
ジョルジュ・シムノンの『片道切符』を読む。1942年に刊行されたノンシリーズ作品で、いわゆる心理小説と呼ばれるもの。
シムノンはメグレ警視ものだけではなく、数多くの心理小説も残したが、そもそも心理小説とはフランス文学のお家芸みたいなもので、人間の心の微妙な綾を簡潔な文体で表現し、克明に分析しようとするのが特徴。この説明がそのままシムノンの小説の説明にも当てはまる。
こんな話。
殺人罪で逮捕され、仮釈放の身となったジャン。たいした目的もないままバスに乗り込んだが、そこで
同じバスに乗り合わせた中年の未亡人タチの荷物(孵卵器)運びを手伝ったことがきっかけで、そのままタチの家に下男として住み込むことになる。ジャンはタチの情夫となるが、そこにタチの姪フェリシーが現れて……。

流れ者が女と知り合い、痴情のもつれから再び人を殺してしまう、ただ、それだけの物語。だが、殺す側にどういう理由があったのか、それが直接的に語られることはなく、シムノンはあくまで登場人物たちの行動からそれをイメージさせる。
とりわけ主人公のジャンが無口なキャラクターであるため、彼が前科者であることや実は街の有力者の息子であることも最初は隠されており、そういった事実が少しずつ明らかになるたびに読む側としては軽くショックを受け、ジャンがどのような人間なのか想いを巡らせてしまうわけである。
ただ、一見なんの希望もなく虚無的に見えるジャンだが、タチ&フェリシーとのやりとりやたまに差し込まれる過去の回想によって、実は重度のストレスを抱えていることも窺える。それが近い将来のカタストロフィを予想させ、良質の心理的サスペンスを生んでいくのだろう。
シンプルだが、シムノンの上手さを再認識できる佳作である。
シムノンはメグレ警視ものだけではなく、数多くの心理小説も残したが、そもそも心理小説とはフランス文学のお家芸みたいなもので、人間の心の微妙な綾を簡潔な文体で表現し、克明に分析しようとするのが特徴。この説明がそのままシムノンの小説の説明にも当てはまる。
こんな話。
殺人罪で逮捕され、仮釈放の身となったジャン。たいした目的もないままバスに乗り込んだが、そこで
同じバスに乗り合わせた中年の未亡人タチの荷物(孵卵器)運びを手伝ったことがきっかけで、そのままタチの家に下男として住み込むことになる。ジャンはタチの情夫となるが、そこにタチの姪フェリシーが現れて……。

流れ者が女と知り合い、痴情のもつれから再び人を殺してしまう、ただ、それだけの物語。だが、殺す側にどういう理由があったのか、それが直接的に語られることはなく、シムノンはあくまで登場人物たちの行動からそれをイメージさせる。
とりわけ主人公のジャンが無口なキャラクターであるため、彼が前科者であることや実は街の有力者の息子であることも最初は隠されており、そういった事実が少しずつ明らかになるたびに読む側としては軽くショックを受け、ジャンがどのような人間なのか想いを巡らせてしまうわけである。
ただ、一見なんの希望もなく虚無的に見えるジャンだが、タチ&フェリシーとのやりとりやたまに差し込まれる過去の回想によって、実は重度のストレスを抱えていることも窺える。それが近い将来のカタストロフィを予想させ、良質の心理的サスペンスを生んでいくのだろう。
シンプルだが、シムノンの上手さを再認識できる佳作である。
Posted
on
ライアン・ジョンソン『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』
『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』をようやく視聴。全九部作の八作目にあたる本作は、監督がJ・J・エイブラムスからライアン・ジョンソンにバトンタッチされ、普通に楽しめる作品にはなっているけれど、やはり不満はないではない。

本作は前作『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』からダイレクトにつながる物語で、大きくは二つの軸で流れていく。
ひとつはファースト・オーダーによって追い詰められていくレジスタンスのストーリー。もうひとつは覚醒したレイがルークと会うストーリーである。
もちろんそのふたつの流れが最後には一つにまとまるわけだが、レジスタンスのほうには、さらにサイドストーリー的にレジスタンスの若きリーダー・ポーや元ファースト・オーダの脱走兵・フィンの流れもあったりで、三時間弱という尺を飽きさせない工夫はさすが。
ドラマとしてはかなり微妙な出来か。善と悪の戦いというよりは、銀河の覇者の候補たちの世代交代劇のように見えてしまった。敵も味方もぽんぽん死にすぎであり、これが感動にいまひとつ結びつかないところに本作最大の弱点があるように思う。
サイドストーリーの詰め込みすぎも影響しているのだろうが、やはりこういう映画なのだから、テーマとストーリーはきちっと見せておくべきだろう。
他にもけっこうな不満や疑問はあるのだが、 まあ、そもそもが本作はミドル・ストーリーなので野暮はやめときましょう。普通にアクションSF映画としてみればそれなりによくできた作品であることは確かだし。
ただ、このまま次で本当に完結するのかどうか、かなり不安だなぁ(苦笑)。

本作は前作『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』からダイレクトにつながる物語で、大きくは二つの軸で流れていく。
ひとつはファースト・オーダーによって追い詰められていくレジスタンスのストーリー。もうひとつは覚醒したレイがルークと会うストーリーである。
もちろんそのふたつの流れが最後には一つにまとまるわけだが、レジスタンスのほうには、さらにサイドストーリー的にレジスタンスの若きリーダー・ポーや元ファースト・オーダの脱走兵・フィンの流れもあったりで、三時間弱という尺を飽きさせない工夫はさすが。
ドラマとしてはかなり微妙な出来か。善と悪の戦いというよりは、銀河の覇者の候補たちの世代交代劇のように見えてしまった。敵も味方もぽんぽん死にすぎであり、これが感動にいまひとつ結びつかないところに本作最大の弱点があるように思う。
サイドストーリーの詰め込みすぎも影響しているのだろうが、やはりこういう映画なのだから、テーマとストーリーはきちっと見せておくべきだろう。
他にもけっこうな不満や疑問はあるのだが、 まあ、そもそもが本作はミドル・ストーリーなので野暮はやめときましょう。普通にアクションSF映画としてみればそれなりによくできた作品であることは確かだし。
ただ、このまま次で本当に完結するのかどうか、かなり不安だなぁ(苦笑)。
Posted
on
江戸川乱歩『明智小五郎事件簿XI「妖怪博士」「暗黒星」』(集英社文庫)
日本のミステリ史に燦然と輝く名探偵といえば、なんといっても乱歩が創り出した明智小五郎を忘れてはならない。集英社文庫の〈明智小五郎事件簿〉は、そんな明智の活躍を事件発生順にまとめたシリーズであり、本日の読了本『明智小五郎事件簿XI「妖怪博士」「暗黒星」』は、その十一巻目にあたる。

まずは「妖怪博士」から。
少年探偵団の一員、相川泰二君が帰宅途中のこと。曲がり角に差し掛かるたび、何やら道路にマークを記している奇妙な老人と遭遇する。その怪しげな様子が気にかかり、泰二君はこっそり後をつけ、ある洋館に忍びこんだ。だが、そこで待ち受けていた蛭田博士と名乗る男に捕まってしまい……。
乱歩が書いた子供向け作品、いわゆる少年探偵団ものとしては「怪人二十面相」、「少年探偵団」に続く三作目にあたる。
内容としても前二作を踏まえたもので、明智たちにしてやられた二十面相が明智や少年探偵団に対する復讐を行うというもの。 とにかくこれでもかというぐらい徹底的な二十面相の復讐譚が見もので、明智はともかく、なぜ子供相手にそこまで執着するのか理解不能である。
ただ、二十面相が子供相手に真剣にやってくれるところが当時の子供の心に響いたことは間違いなく、ストーリーやトリックなどは前二作より劣るが、エネルギーとしては相当なものだ。
とりあえずこの時点で乱歩も二十面相ものに一区切りつけるような意図はあったのだろう、ラストでは二十面相が完敗を認めており、二十面相の再登場はなんとほぼ十年後になってしまう(まあ、実際は戦時という事情も大きいのだけれど)。
お次の「暗黒星」は大人向けの一作。
関東大震災の大火を免れた東京の一角にとある洋館があった。そこには奇人資産家として知られる伊志田鉄造氏の一家が住んでいた。
ある日、一家が揃って十六ミリフィルムの映像を眺めていると、なぜか家族の大写しの場面で映写が止まり、フィルムが焼けてしまうというアクシデントが続発する。その不吉な出来事に、長男の一郎が最近身の回りで起こっている怪しい出来事を告白するが……。
地球に衝突しようとしているのに誰にもまったく気づかれない光のない星、それが暗黒星だ。明智は事件の真犯人をその暗黒星になぞらえているが、このタイトルこそ格好いいものの、実はそれほど評価の高い作品ではない。
舞台がほぼ屋敷で起こっているというのに、それに対応できない明智と警察があまりに非力というか間抜けというか。使い回しやミステリとしていかがなものかというネタもありで、この時期に書かれた作品の中でもかなり落ちるほうだろう。
ただ、家族で十六ミリを観る導入からけっこう雰囲気はいいし、全体的にこじんまりした感じが意外に好ましく、個人的にはそれほど嫌いな作品ではない。
ともかく、これでようやく〈明智小五郎事件簿〉読破にリーチ。残すはいよいよ最終巻の『~XII「悪魔の紋章」「地獄の道化師」 』である。

まずは「妖怪博士」から。
少年探偵団の一員、相川泰二君が帰宅途中のこと。曲がり角に差し掛かるたび、何やら道路にマークを記している奇妙な老人と遭遇する。その怪しげな様子が気にかかり、泰二君はこっそり後をつけ、ある洋館に忍びこんだ。だが、そこで待ち受けていた蛭田博士と名乗る男に捕まってしまい……。
乱歩が書いた子供向け作品、いわゆる少年探偵団ものとしては「怪人二十面相」、「少年探偵団」に続く三作目にあたる。
内容としても前二作を踏まえたもので、明智たちにしてやられた二十面相が明智や少年探偵団に対する復讐を行うというもの。 とにかくこれでもかというぐらい徹底的な二十面相の復讐譚が見もので、明智はともかく、なぜ子供相手にそこまで執着するのか理解不能である。
ただ、二十面相が子供相手に真剣にやってくれるところが当時の子供の心に響いたことは間違いなく、ストーリーやトリックなどは前二作より劣るが、エネルギーとしては相当なものだ。
とりあえずこの時点で乱歩も二十面相ものに一区切りつけるような意図はあったのだろう、ラストでは二十面相が完敗を認めており、二十面相の再登場はなんとほぼ十年後になってしまう(まあ、実際は戦時という事情も大きいのだけれど)。
お次の「暗黒星」は大人向けの一作。
関東大震災の大火を免れた東京の一角にとある洋館があった。そこには奇人資産家として知られる伊志田鉄造氏の一家が住んでいた。
ある日、一家が揃って十六ミリフィルムの映像を眺めていると、なぜか家族の大写しの場面で映写が止まり、フィルムが焼けてしまうというアクシデントが続発する。その不吉な出来事に、長男の一郎が最近身の回りで起こっている怪しい出来事を告白するが……。
地球に衝突しようとしているのに誰にもまったく気づかれない光のない星、それが暗黒星だ。明智は事件の真犯人をその暗黒星になぞらえているが、このタイトルこそ格好いいものの、実はそれほど評価の高い作品ではない。
舞台がほぼ屋敷で起こっているというのに、それに対応できない明智と警察があまりに非力というか間抜けというか。使い回しやミステリとしていかがなものかというネタもありで、この時期に書かれた作品の中でもかなり落ちるほうだろう。
ただ、家族で十六ミリを観る導入からけっこう雰囲気はいいし、全体的にこじんまりした感じが意外に好ましく、個人的にはそれほど嫌いな作品ではない。
ともかく、これでようやく〈明智小五郎事件簿〉読破にリーチ。残すはいよいよ最終巻の『~XII「悪魔の紋章」「地獄の道化師」 』である。
Posted
on
ティモシー・フラー『ハーバード同窓会殺人事件』(論創海外ミステリ))
ティモシー・フラーの『ハーバード同窓会殺人事件』を読む。
著者についてはほぼ予備知識ゼロ。なんでもハーバード大学在学中に『ハーバード大学殺人事件』でデビューし、生涯で五冊のミステリを残した。その全作に登場するシリーズ探偵ジュピター・ジョーンズは、ハーバード大学で美術を教える講師であり、犯罪に興味をもつアマチュア探偵である。
本作は1941年に発表された本格ものの一冊。
ハーバード大学の同窓会が催され、全米各地から会場のホテルへ集まってくる卒業生たち。ところが隣接するゴルフ場で、卒業生の一人ノースが射殺死体となって発見される。
そのころノースと相部屋になっていたライスが部屋で目を覚ましていた。彼は自分の右手についていた傷や衣服に血がついていることに気づくが、いかんせん飲み過ぎたせいで昨晩の記憶も定かでない。やがてノースの事件を知らされ、昨晩はどうやらその格好でホテル内をうろつき回っていたことを思い出す。
このままでは自分が疑われる可能性は高い。不安になったライスは素人探偵として名高い親友ジュピターに連絡したが、なんとジュピターは結婚式を明日に控える身。ジュピターは結婚式までにライスを助けるべく、新郎ベティとともにホテルへ向かったが……。
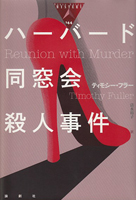
全体のテイストだけみると典型的なユーモアミステリのようにも思えるが、本作の魅力はそれだけではない。
まず注目すべきは、某有名作品と同じトリックが本作で使われていること。かなり特殊なネタなので、他の作家が流用するにはかえって度胸がいると思うが(著者が某有名作品を知らなかった可能性もないではないが)、まったく異なるシチュエーションで組み立てているのでそれほどパクリというような印象はない。
まあ本家ほどの鮮やかさはないし、本家が抱えていた主題を少々おざなりにしている欠点はあるのだけれど、しっかり独自の作品にまとめているといっていいだろう。
本作の前半では、ジュピターたちが卒業生の寄稿したクラスレポート(近況報告)を読みながら、それぞれの卒業生に聴き取りを行うシーンがあるのだけれど、結末を知ってからクラスレポートを読み直すのも一興である。
もうひとつ注目したいのは、本作の裏テーマともいうべき側面。
被害者をはじめとして登場人物はみなハーバードの卒業生である。そんな彼らが十年という時を経てそれぞれの人生を歩んでいるわけだが、ちょうど戦時ということも相まって、必ずしもエリートとしての道ばかりではない。
同窓会という舞台はそんな人生の岐路を考えさせる装置であり、明快な答えはないけれども著者のメッセージはじわっと染みてくるところがあり、なかなか捨てたものではない。
ちなみに『ハーバードからの贈り物』という本があるのだが、同書にはハーバード・ビジネススクールの教授の「同窓会には出るな」という内容の話が載っている。
五年目や十年目の同窓会に出ると、どうしても同期の年収や出世が気になって、短絡的な道に進みがちである。自分が本来めざしていた目標を見失いがちになるので、きちんと長期的な展望を持ちなさいという話だ。
そういう話を頭に入れて本作を読むと、より深く楽しめるのではないだろうか。
ということで、これはけっこう拾いものであった。他の作品の出来はわからないが、このレベルなら紹介を続けてもよいのでは。
著者についてはほぼ予備知識ゼロ。なんでもハーバード大学在学中に『ハーバード大学殺人事件』でデビューし、生涯で五冊のミステリを残した。その全作に登場するシリーズ探偵ジュピター・ジョーンズは、ハーバード大学で美術を教える講師であり、犯罪に興味をもつアマチュア探偵である。
本作は1941年に発表された本格ものの一冊。
ハーバード大学の同窓会が催され、全米各地から会場のホテルへ集まってくる卒業生たち。ところが隣接するゴルフ場で、卒業生の一人ノースが射殺死体となって発見される。
そのころノースと相部屋になっていたライスが部屋で目を覚ましていた。彼は自分の右手についていた傷や衣服に血がついていることに気づくが、いかんせん飲み過ぎたせいで昨晩の記憶も定かでない。やがてノースの事件を知らされ、昨晩はどうやらその格好でホテル内をうろつき回っていたことを思い出す。
このままでは自分が疑われる可能性は高い。不安になったライスは素人探偵として名高い親友ジュピターに連絡したが、なんとジュピターは結婚式を明日に控える身。ジュピターは結婚式までにライスを助けるべく、新郎ベティとともにホテルへ向かったが……。
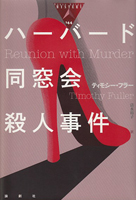
全体のテイストだけみると典型的なユーモアミステリのようにも思えるが、本作の魅力はそれだけではない。
まず注目すべきは、某有名作品と同じトリックが本作で使われていること。かなり特殊なネタなので、他の作家が流用するにはかえって度胸がいると思うが(著者が某有名作品を知らなかった可能性もないではないが)、まったく異なるシチュエーションで組み立てているのでそれほどパクリというような印象はない。
まあ本家ほどの鮮やかさはないし、本家が抱えていた主題を少々おざなりにしている欠点はあるのだけれど、しっかり独自の作品にまとめているといっていいだろう。
本作の前半では、ジュピターたちが卒業生の寄稿したクラスレポート(近況報告)を読みながら、それぞれの卒業生に聴き取りを行うシーンがあるのだけれど、結末を知ってからクラスレポートを読み直すのも一興である。
もうひとつ注目したいのは、本作の裏テーマともいうべき側面。
被害者をはじめとして登場人物はみなハーバードの卒業生である。そんな彼らが十年という時を経てそれぞれの人生を歩んでいるわけだが、ちょうど戦時ということも相まって、必ずしもエリートとしての道ばかりではない。
同窓会という舞台はそんな人生の岐路を考えさせる装置であり、明快な答えはないけれども著者のメッセージはじわっと染みてくるところがあり、なかなか捨てたものではない。
ちなみに『ハーバードからの贈り物』という本があるのだが、同書にはハーバード・ビジネススクールの教授の「同窓会には出るな」という内容の話が載っている。
五年目や十年目の同窓会に出ると、どうしても同期の年収や出世が気になって、短絡的な道に進みがちである。自分が本来めざしていた目標を見失いがちになるので、きちんと長期的な展望を持ちなさいという話だ。
そういう話を頭に入れて本作を読むと、より深く楽しめるのではないだろうか。
ということで、これはけっこう拾いものであった。他の作品の出来はわからないが、このレベルなら紹介を続けてもよいのでは。
Posted
on
平井憲太郎、他『怪人 江戸川乱歩のコレクション』(新潮社)
このところ江戸川乱歩関連の出版が相次いでいるようで。2015年が乱歩没後50年ということでいろいろな企画が行われたが、その後も勢いは衰えず、ずっと乱歩ブームが続いているような印象である。
最近の出版で目につくところでは、ビジュアル本の『怪人 江戸川乱歩のコレクション』をはじめ、岩波文庫の短編集、集英社から出た評論『江戸川乱歩と横溝正史』、変わったところでは集英社文庫の「明智小五郎事件簿」の編者としても知られる平山雄一氏が書いた『明智小五郎回顧談』なんていうのもある。それらもすべて買っているので、これからぼちぼち消化していこうとは思っているのだが、とりあえず本日は新潮社〈とんぼの本〉『怪人 江戸川乱歩のコレクション』を読んでみた。

さて、その内容だが、〈とんぼの本〉という性質もあって、基本はビジュアルメインであり入門書的な一冊。乱歩が残した数々の“モノ”を写真で紹介しつつ、そこから乱歩のもつ特殊な嗜好や人物像を感じとってもらって、さらには著書に興味をもってもらえればという乱歩入門ガイドである。
アプローチとしては面白いのだが、正直、乱歩入門者向けというよりは、これはマニア向けだろう。乱歩の作品にのめりこんだあまり、乱歩の愛した“モノ”にまで興味をもってしまった人、あるいは市井の乱歩研究者、そのぐらいの人でなければ、普通はこんな本は楽しめない(苦笑)。
ただ、マニア向けとするなら、今度はテキスト面(掲載写真の解説)での不満が残る。乱歩の生涯とかも掲載されているが、ほんと申し訳程度のレベルである。また、巻末の近藤ようこ氏による漫画「お勢登場」も作品としては別に悪くないのだが、ページ数の調整で入れた感が無きにしも非ず。
結局、初心者向けなのかマニア向けなのか、編集方針がはっきり打ち出されておらず、それが本づくりにも悪影響を与えたような一冊であった。
最近の出版で目につくところでは、ビジュアル本の『怪人 江戸川乱歩のコレクション』をはじめ、岩波文庫の短編集、集英社から出た評論『江戸川乱歩と横溝正史』、変わったところでは集英社文庫の「明智小五郎事件簿」の編者としても知られる平山雄一氏が書いた『明智小五郎回顧談』なんていうのもある。それらもすべて買っているので、これからぼちぼち消化していこうとは思っているのだが、とりあえず本日は新潮社〈とんぼの本〉『怪人 江戸川乱歩のコレクション』を読んでみた。

さて、その内容だが、〈とんぼの本〉という性質もあって、基本はビジュアルメインであり入門書的な一冊。乱歩が残した数々の“モノ”を写真で紹介しつつ、そこから乱歩のもつ特殊な嗜好や人物像を感じとってもらって、さらには著書に興味をもってもらえればという乱歩入門ガイドである。
アプローチとしては面白いのだが、正直、乱歩入門者向けというよりは、これはマニア向けだろう。乱歩の作品にのめりこんだあまり、乱歩の愛した“モノ”にまで興味をもってしまった人、あるいは市井の乱歩研究者、そのぐらいの人でなければ、普通はこんな本は楽しめない(苦笑)。
ただ、マニア向けとするなら、今度はテキスト面(掲載写真の解説)での不満が残る。乱歩の生涯とかも掲載されているが、ほんと申し訳程度のレベルである。また、巻末の近藤ようこ氏による漫画「お勢登場」も作品としては別に悪くないのだが、ページ数の調整で入れた感が無きにしも非ず。
結局、初心者向けなのかマニア向けなのか、編集方針がはっきり打ち出されておらず、それが本づくりにも悪影響を与えたような一冊であった。
Posted
on
蘭郁二郎『蘭郁二郎探偵小説選II』(論創ミステリ叢書)
新年明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
年末年始はいつものごとく寝正月。元日は遅めに起きてお雑煮の下拵えをしてから初詣。この数年は仕事がめまぐるしいのと、年のせいか体調がいまひとつなのもあって、今年はなんとか平穏な一年を送らせてくだされと諸々お願いする。
さて、今年最初の一冊は論創ミステリ叢書から『蘭郁二郎探偵小説選II』。
前期の変格探偵小説から後期はSFに移行した蘭郁二郎だが、その後期にも探偵小説はけっこう書いていたそうで、それをまとめたものが論創ミステリ叢書版『蘭郁二郎探偵小説選』。昨年に読んだ『~I』ではシリーズものが収録されていたが、本書はノンシリーズものというラインナップだ。

「息を止める男」
「足の裏」
「蝱(あぶ)の囁き――肺病の唄―― 」
「鱗粉」
「雷」
「腐った蜉蝣(かげろう)」
「ニュース劇場の女」
「黄色いスヰトピー」
「寝言レコード」
「死後の眼(まなこ)」
「黒い東京地図」
「設計室の殺人」
「匂ひの事件」
「睡魔」
「楕円の応接間」
「電子の中の男」
「古井戸」
「刑事の手」
収録作は以上。前期の変態ちっくな探偵小説ではなく、後期作品らしくSF的なアイディアが盛り込まれたスマートな本格ものという印象。まあ、トリックなどは推して知るべしといったところだが、本格の香りは意外に濃く、それなりに楽しめる。
個人的な好みは乱歩の影響も感じられる「息を止める男」、「足の裏」、「蝱(あぶ)の囁き――肺病の唄―― 」あたり。ただ、実はこれらは前期変格系の作品で、ちくま文庫の『怪奇探偵小説名作選〈7〉蘭郁二郎集 魔像』にも採られている。意図はよくわからないが、このあたりの作品もあえて収録しているところに編集方針のぶれがうかがえ、少々気になってしまった。
本年もよろしくお願いいたします。
年末年始はいつものごとく寝正月。元日は遅めに起きてお雑煮の下拵えをしてから初詣。この数年は仕事がめまぐるしいのと、年のせいか体調がいまひとつなのもあって、今年はなんとか平穏な一年を送らせてくだされと諸々お願いする。
さて、今年最初の一冊は論創ミステリ叢書から『蘭郁二郎探偵小説選II』。
前期の変格探偵小説から後期はSFに移行した蘭郁二郎だが、その後期にも探偵小説はけっこう書いていたそうで、それをまとめたものが論創ミステリ叢書版『蘭郁二郎探偵小説選』。昨年に読んだ『~I』ではシリーズものが収録されていたが、本書はノンシリーズものというラインナップだ。

「息を止める男」
「足の裏」
「蝱(あぶ)の囁き――肺病の唄―― 」
「鱗粉」
「雷」
「腐った蜉蝣(かげろう)」
「ニュース劇場の女」
「黄色いスヰトピー」
「寝言レコード」
「死後の眼(まなこ)」
「黒い東京地図」
「設計室の殺人」
「匂ひの事件」
「睡魔」
「楕円の応接間」
「電子の中の男」
「古井戸」
「刑事の手」
収録作は以上。前期の変態ちっくな探偵小説ではなく、後期作品らしくSF的なアイディアが盛り込まれたスマートな本格ものという印象。まあ、トリックなどは推して知るべしといったところだが、本格の香りは意外に濃く、それなりに楽しめる。
個人的な好みは乱歩の影響も感じられる「息を止める男」、「足の裏」、「蝱(あぶ)の囁き――肺病の唄―― 」あたり。ただ、実はこれらは前期変格系の作品で、ちくま文庫の『怪奇探偵小説名作選〈7〉蘭郁二郎集 魔像』にも採られている。意図はよくわからないが、このあたりの作品もあえて収録しているところに編集方針のぶれがうかがえ、少々気になってしまった。


