Posted in 10 2013
Posted
on
エルモア・レナード『ママ、大変、うちにコヨーテがいるよ!』(角川書店)
エルモア・レナードが日本で広く知られるようになったのは『グリッツ』からだ。当時は新しいタイプの犯罪小説の書き手として紹介されることが多かったと記憶するが、けっこう下積みは長かったようで、レナードが作家として大成功するのは、結局デビューから二十年以上が過ぎてからのことである。しかし、その実力が認められてからは順風満帆、八十年代には『グリッツ』や『プロント』をはじめとする傑作を次々とものにし、最後は巨匠とまで呼ばれるようになったのだから大したものだ。
今月号のミステリマガジンでは、そんなレナードの追悼特集が組まれていた。そう、レナードはこの八月に亡くなったばかりなのだ。
ご多分に漏れず、管理人がレナードを初めて読んだの、『グリッツ』からである。一時期はけっこうはまった作家だったが、最近はすっかりご無沙汰。未読の作品もずいぶん多くなってしまって、こんな機会でもないと読まないというのはちょっとアレな感じだが、まあ読まないよりはましだろうと、『ママ、大変、うちにコヨーテがいるよ!』に手を出してみた。
こんな話。主人公はハリウッドの丘に住む若きコヨーテ、アントワン。自由な生活をこよなく 愛し、群れのボスも期待されているリーダー格のコヨーテだが、あるときひょんなことから人間に飼われているシェパードのバディと知り合いになる。するとバディがアントワンに、互いの立場を入れ替えてみないかと相談を持ちかけてきて……。
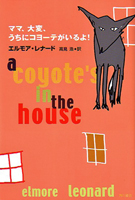
エルモア・レナードが孫のために書いたという動物小説である。形としてはYA(ヤングアダルト)向けということになろうが、さすがレナードが書いただけのことはあって、むしろ大人のためのファンタジーという雰囲気を醸し出している。
まあ、ミステリ作家が動物を主人公にして書いた小説というのは今どき珍しくもないわけだが、これがことハードボイルドや犯罪小説の作家に限ると、さすがにレアではなかろうか。いま管理人が思い出せるのはマイケル・Z・リューインの『のら犬ローヴァー町を行く』ぐらいだ。
たまたまだろうが『のら犬ローヴァー町を行く』と『ママ、大変、うちにコヨーテがいるよ!』の二作は、けっこう表面的なテーマが似ている。
主人公はともに野生の犬orコヨーテである。彼らは安定した日々を送れているわけではないが、自然を謳歌し、自由を愛する。人間に依存する生活などプライドが許さないし、考えたこともない。それが単なる自然礼賛といったテーマではなく、人間の社会を投影させたものであることは簡単に想像できるだろう。
面白いのはこの両者、テーマが似ているとはいえ、そのアプローチはけっこう異なる。例えばリューインは義侠心溢れる主人公を設定し、あくまでシリアスに語ってゆく。正にハードボイルドそのままの味で、主人公ローヴァーはあくまで卑しい町をゆく騎士なのである。
一方のレナードの描いた物語は、彼が普段から描いていた犯罪小説の世界を、そのままコヨーテと犬の世界に置き換えたようなイメージ。主人公は騎士などではなく、あくまで小悪党。才覚と好奇心の働くままに行動し、なめた口をきいては周囲を苛立たせる。その騒動をコミカル&シニカルに描いていく。もちろんYA向けなので多少はソフトに抑えられてはいるが、レナードの語りは健在である。
ここで最初の話に戻るのだけれど、おそらく本書の本当のテーマは自然礼賛でも、実は格差社会の批判でもないと思っている。
コヨーテと飼い犬たちは互いを敵視しているところからスタートし、やがて相手を理解し、敬うこともできるようになる。だが、最終的に彼らの間には越えられない最後の一線があり、やがて各々は元の生活に戻ってゆく。どちらがいいとか悪いとかではなく、それぞれの生き方を尊重し合うことの大切さである。
ややもすると人は互いの生き方や考え、趣味、文化、宗教を否定するところから関係をスタートしたりもするのだが、その馬鹿らしさや愚かさをレナードは笑っているのである。
とりわけクライマックスを過ぎてから後のエピソードが絶品で、アントワンとバディがある場所で語り合うシーンは深い余韻を残す。
とまあ固っくるしく書いてはみたけれど、実はそんなことを考えながら読む必要はまったくない。そもそもが楽しいお話なのであり、読んでいれば自然に笑えるし、自然に心に染みてくる一冊なのである。素直に読んで全然OK。おすすめ。
今月号のミステリマガジンでは、そんなレナードの追悼特集が組まれていた。そう、レナードはこの八月に亡くなったばかりなのだ。
ご多分に漏れず、管理人がレナードを初めて読んだの、『グリッツ』からである。一時期はけっこうはまった作家だったが、最近はすっかりご無沙汰。未読の作品もずいぶん多くなってしまって、こんな機会でもないと読まないというのはちょっとアレな感じだが、まあ読まないよりはましだろうと、『ママ、大変、うちにコヨーテがいるよ!』に手を出してみた。
こんな話。主人公はハリウッドの丘に住む若きコヨーテ、アントワン。自由な生活をこよなく 愛し、群れのボスも期待されているリーダー格のコヨーテだが、あるときひょんなことから人間に飼われているシェパードのバディと知り合いになる。するとバディがアントワンに、互いの立場を入れ替えてみないかと相談を持ちかけてきて……。
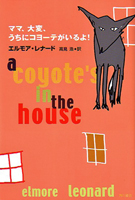
エルモア・レナードが孫のために書いたという動物小説である。形としてはYA(ヤングアダルト)向けということになろうが、さすがレナードが書いただけのことはあって、むしろ大人のためのファンタジーという雰囲気を醸し出している。
まあ、ミステリ作家が動物を主人公にして書いた小説というのは今どき珍しくもないわけだが、これがことハードボイルドや犯罪小説の作家に限ると、さすがにレアではなかろうか。いま管理人が思い出せるのはマイケル・Z・リューインの『のら犬ローヴァー町を行く』ぐらいだ。
たまたまだろうが『のら犬ローヴァー町を行く』と『ママ、大変、うちにコヨーテがいるよ!』の二作は、けっこう表面的なテーマが似ている。
主人公はともに野生の犬orコヨーテである。彼らは安定した日々を送れているわけではないが、自然を謳歌し、自由を愛する。人間に依存する生活などプライドが許さないし、考えたこともない。それが単なる自然礼賛といったテーマではなく、人間の社会を投影させたものであることは簡単に想像できるだろう。
面白いのはこの両者、テーマが似ているとはいえ、そのアプローチはけっこう異なる。例えばリューインは義侠心溢れる主人公を設定し、あくまでシリアスに語ってゆく。正にハードボイルドそのままの味で、主人公ローヴァーはあくまで卑しい町をゆく騎士なのである。
一方のレナードの描いた物語は、彼が普段から描いていた犯罪小説の世界を、そのままコヨーテと犬の世界に置き換えたようなイメージ。主人公は騎士などではなく、あくまで小悪党。才覚と好奇心の働くままに行動し、なめた口をきいては周囲を苛立たせる。その騒動をコミカル&シニカルに描いていく。もちろんYA向けなので多少はソフトに抑えられてはいるが、レナードの語りは健在である。
ここで最初の話に戻るのだけれど、おそらく本書の本当のテーマは自然礼賛でも、実は格差社会の批判でもないと思っている。
コヨーテと飼い犬たちは互いを敵視しているところからスタートし、やがて相手を理解し、敬うこともできるようになる。だが、最終的に彼らの間には越えられない最後の一線があり、やがて各々は元の生活に戻ってゆく。どちらがいいとか悪いとかではなく、それぞれの生き方を尊重し合うことの大切さである。
ややもすると人は互いの生き方や考え、趣味、文化、宗教を否定するところから関係をスタートしたりもするのだが、その馬鹿らしさや愚かさをレナードは笑っているのである。
とりわけクライマックスを過ぎてから後のエピソードが絶品で、アントワンとバディがある場所で語り合うシーンは深い余韻を残す。
とまあ固っくるしく書いてはみたけれど、実はそんなことを考えながら読む必要はまったくない。そもそもが楽しいお話なのであり、読んでいれば自然に笑えるし、自然に心に染みてくる一冊なのである。素直に読んで全然OK。おすすめ。
Posted
on
山本禾太郎『山本禾太郎探偵小説選II』(論創ミステリ叢書)
論創ミステリ叢書から『山本禾太郎探偵小説選II』を読む。まずは収録作から。
「貞操料」
「重大なる過失」
「仙人掌の花」
「二階から降りきた者」
「一時五十二分」
「黒子」
「おとしもの」
「黄色の寝衣」
「幽霊写真」
「セルを着た人形」
「八月十一日の夜」
「小さな事件」
「抱茗荷の説」
「少年と一万円」

ちょうど一ヶ月ほど前にI巻を読んだのだが、あちらはデビューから執筆中断するまでの前半期の作品を集めたもの。II巻にあたる本書は一年の休筆を経て執筆再開したあとの作品を集めたもので、両方合わせてほぼ全集という形となるようだ。
残念ながらI巻では二、三の作品をのぞき、全般的には低調な出来であった。一年間という休筆の期間がどの程度の意味を持つのか正直わからないが、本書を読む限り、少なくとも後期の作品のほうがよりバラエティに富んでいるとは感じた。
I巻の記事でも書いたとおり、山本禾太郎の作風は犯罪実話、ドキュメンタリー文学、記録文学といったところにある。本書に収められた後期の作品には、そういったドキュメンタリズムを突き詰めた感のある「貞操料」はあるのだが、シナリオの形で描いた「八月十一日の夜」、幻想文学寄りの「抱茗荷の説」などなかなか幅広い。休筆云々は抜きにしても、やはり作家としての成熟は感じられる。
ただ、探偵小説としての面白さはまた別で、いくつかの作品を除くとアベレージは決して高くない。
例外的に面白く読めたのは、まず「貞操料」。ドキュメンタリー、記録文学を極めようとしたとき、重要なのはその方法論であって極論すればテーマは何であってもよいのではないか。それを具体的に示したのが本作で、基本的にはすべてが裁判記録だけで構成されているという代物。
ただし、そこで争われているのは、結婚したのに夫がHしてくれませんという妻、いやいやそんなことはないでしょという夫の家庭内トラブル。手法と内容のギャップが凄まじく、ただただ苦笑するしかないのだが、禾太郎がこの馬鹿馬鹿しさを狙ってやったのかどうかが非常に気になるところである(一応、解説では意図していた旨があるけれど)。
「抱茗荷の説」はドキュメンタリーとはかなり遠いところに位置する幻想的作品で、幼いときに失った両親の死の秘密をさぐる少女の物語。朧にしか残らない当時の記憶、そしてじわりと浮かび上がる真実。語りもイメージも叙情性も素晴らしく、I巻も合わせて間違いなく作者のベストである。
山下武氏によると禾太郎が犯罪実話、ドキュメンタリー型の小説の限界を悟った末の作品という位置づけらしいが、こういう優れた作品を読むと、持てる才能をすべて発揮する前に亡くなってしまった感は強い。チャレンジ精神にあふれる印象があるだけに、もっともっと生きて書いてもらいたかった作家である。
「貞操料」
「重大なる過失」
「仙人掌の花」
「二階から降りきた者」
「一時五十二分」
「黒子」
「おとしもの」
「黄色の寝衣」
「幽霊写真」
「セルを着た人形」
「八月十一日の夜」
「小さな事件」
「抱茗荷の説」
「少年と一万円」

ちょうど一ヶ月ほど前にI巻を読んだのだが、あちらはデビューから執筆中断するまでの前半期の作品を集めたもの。II巻にあたる本書は一年の休筆を経て執筆再開したあとの作品を集めたもので、両方合わせてほぼ全集という形となるようだ。
残念ながらI巻では二、三の作品をのぞき、全般的には低調な出来であった。一年間という休筆の期間がどの程度の意味を持つのか正直わからないが、本書を読む限り、少なくとも後期の作品のほうがよりバラエティに富んでいるとは感じた。
I巻の記事でも書いたとおり、山本禾太郎の作風は犯罪実話、ドキュメンタリー文学、記録文学といったところにある。本書に収められた後期の作品には、そういったドキュメンタリズムを突き詰めた感のある「貞操料」はあるのだが、シナリオの形で描いた「八月十一日の夜」、幻想文学寄りの「抱茗荷の説」などなかなか幅広い。休筆云々は抜きにしても、やはり作家としての成熟は感じられる。
ただ、探偵小説としての面白さはまた別で、いくつかの作品を除くとアベレージは決して高くない。
例外的に面白く読めたのは、まず「貞操料」。ドキュメンタリー、記録文学を極めようとしたとき、重要なのはその方法論であって極論すればテーマは何であってもよいのではないか。それを具体的に示したのが本作で、基本的にはすべてが裁判記録だけで構成されているという代物。
ただし、そこで争われているのは、結婚したのに夫がHしてくれませんという妻、いやいやそんなことはないでしょという夫の家庭内トラブル。手法と内容のギャップが凄まじく、ただただ苦笑するしかないのだが、禾太郎がこの馬鹿馬鹿しさを狙ってやったのかどうかが非常に気になるところである(一応、解説では意図していた旨があるけれど)。
「抱茗荷の説」はドキュメンタリーとはかなり遠いところに位置する幻想的作品で、幼いときに失った両親の死の秘密をさぐる少女の物語。朧にしか残らない当時の記憶、そしてじわりと浮かび上がる真実。語りもイメージも叙情性も素晴らしく、I巻も合わせて間違いなく作者のベストである。
山下武氏によると禾太郎が犯罪実話、ドキュメンタリー型の小説の限界を悟った末の作品という位置づけらしいが、こういう優れた作品を読むと、持てる才能をすべて発揮する前に亡くなってしまった感は強い。チャレンジ精神にあふれる印象があるだけに、もっともっと生きて書いてもらいたかった作家である。
Posted
on
サックス・ローマー『骨董屋探偵の事件簿』(創元推理文庫)
サックス・ローマーの『骨董屋探偵の事件簿』を読む。
著者は1920~1940年あたりに活躍した英国の作家である。代表作は、世界征服を企む謎の中国人フー・マンチュー博士を悪役に据えたシリーズだが、他にも多数のシリーズを手がけていたことは、我が国ではあまり知られていない。そもそも日本ではフー・マンチュー博士すらそんなに知られていないだろうから、それも無理はない話である。
ただ、先に書いたように、欧米では絶大な人気を博していたサックス・ローマー。フー・マンチュー博士以外のシリーズも好評だったようで、とりわけ評判が高かったのが、本書『骨董屋探偵の事件簿』の主人公、モリス・ クロウのシリーズである。
まずは収録作。
Case of the Tragedies in the Greek Room「ギリシャの間の悲劇」
Case of the Potsherd of Anubis「アヌビスの陶片」
Case of the Crusader's Axe「十字軍の斧」
Case of the Ivory Statue「象牙の彫像」
Case of the Blue Rajah「ブルー・ラジャ」
Case of the Chrod in G「ト短調の和音」
Case of the Headless Mummies「頭のないミイラ」
Case of the Haunting of Grange「グレンジ館の呪い」
Case of the Veil of Isis「イシスのヴェール」

題名に「骨董屋探偵」とあるように、モリス・クロウは骨董商を営んでいる。当然ながら歴史的遺産や美術品に造詣が深く、博物館などで事件が起こった際にはその知識を買われ、警察や友人のサールズから探偵出馬を依頼されるという結構。
だが、これだけではクロウの特徴の半分も説明したことにはならない。彼の最大の持ち味は、その捜査法にあるのだ。
クロウは事件現場に特殊なクッションを持ち込み、現場で眠ることによって、決定的な場面を夢として再現する。つまり人の思念とは実体なのであり、いまわの際の心象風景は写真のように周囲の空気に刻印されている。その写真を頭の中で再現できるよう訓練したというのである。
まあ独創的な捜査法であることは間違いないが、夢で犯行現場見ましたとか言ったところで、誰が信じるかという話である(苦笑)。そういった、一歩まちがうとただのバカミスに陥りそうなところを食い止めているのが(食い止めていないかも知れないけれど)、全体的なオカルト趣味とプロット。
文体はあくまで古色蒼然。大仰な語り口でもって読者を煽り、しかも歴史的美術品に隠された伝説や因縁を絡めることで、怪奇ムードを盛り上げる。
ただし、真相はあくまで合理的なものがほとんど。一見オカルトチックな事件ばかりだが、そのすべては科学的に説明がつけられ、ミステリの定石はきちんと踏まえられている。このオカルト趣味とミステリのバランスが悪くないのである。
これでトリックに相当の工夫がされていれば言うことはないのだが、残念ながらそのレベルには達していない。
そういう意味ではあまり本格としての期待はせず、素直に物語やキャラクターを楽しむ方がいいだろう。例えば「頭のないミイラ」や「イシスのヴェール」といったオカルト重視の作品もあり、ミステリとしては消化不良だけれど、むしろそちらの系統の方が楽しく読めた。
それ以外では、このトリックだったら最低だなと思って読んでいたら案の定そのトリックが使われていた「象牙の彫像」もある意味おすすめ(笑)。
ただ、本格ミステリとして過大な期待をかけると肩すかしを食うのでご注意を。
著者は1920~1940年あたりに活躍した英国の作家である。代表作は、世界征服を企む謎の中国人フー・マンチュー博士を悪役に据えたシリーズだが、他にも多数のシリーズを手がけていたことは、我が国ではあまり知られていない。そもそも日本ではフー・マンチュー博士すらそんなに知られていないだろうから、それも無理はない話である。
ただ、先に書いたように、欧米では絶大な人気を博していたサックス・ローマー。フー・マンチュー博士以外のシリーズも好評だったようで、とりわけ評判が高かったのが、本書『骨董屋探偵の事件簿』の主人公、モリス・ クロウのシリーズである。
まずは収録作。
Case of the Tragedies in the Greek Room「ギリシャの間の悲劇」
Case of the Potsherd of Anubis「アヌビスの陶片」
Case of the Crusader's Axe「十字軍の斧」
Case of the Ivory Statue「象牙の彫像」
Case of the Blue Rajah「ブルー・ラジャ」
Case of the Chrod in G「ト短調の和音」
Case of the Headless Mummies「頭のないミイラ」
Case of the Haunting of Grange「グレンジ館の呪い」
Case of the Veil of Isis「イシスのヴェール」

題名に「骨董屋探偵」とあるように、モリス・クロウは骨董商を営んでいる。当然ながら歴史的遺産や美術品に造詣が深く、博物館などで事件が起こった際にはその知識を買われ、警察や友人のサールズから探偵出馬を依頼されるという結構。
だが、これだけではクロウの特徴の半分も説明したことにはならない。彼の最大の持ち味は、その捜査法にあるのだ。
クロウは事件現場に特殊なクッションを持ち込み、現場で眠ることによって、決定的な場面を夢として再現する。つまり人の思念とは実体なのであり、いまわの際の心象風景は写真のように周囲の空気に刻印されている。その写真を頭の中で再現できるよう訓練したというのである。
まあ独創的な捜査法であることは間違いないが、夢で犯行現場見ましたとか言ったところで、誰が信じるかという話である(苦笑)。そういった、一歩まちがうとただのバカミスに陥りそうなところを食い止めているのが(食い止めていないかも知れないけれど)、全体的なオカルト趣味とプロット。
文体はあくまで古色蒼然。大仰な語り口でもって読者を煽り、しかも歴史的美術品に隠された伝説や因縁を絡めることで、怪奇ムードを盛り上げる。
ただし、真相はあくまで合理的なものがほとんど。一見オカルトチックな事件ばかりだが、そのすべては科学的に説明がつけられ、ミステリの定石はきちんと踏まえられている。このオカルト趣味とミステリのバランスが悪くないのである。
これでトリックに相当の工夫がされていれば言うことはないのだが、残念ながらそのレベルには達していない。
そういう意味ではあまり本格としての期待はせず、素直に物語やキャラクターを楽しむ方がいいだろう。例えば「頭のないミイラ」や「イシスのヴェール」といったオカルト重視の作品もあり、ミステリとしては消化不良だけれど、むしろそちらの系統の方が楽しく読めた。
それ以外では、このトリックだったら最低だなと思って読んでいたら案の定そのトリックが使われていた「象牙の彫像」もある意味おすすめ(笑)。
ただ、本格ミステリとして過大な期待をかけると肩すかしを食うのでご注意を。
Posted
on
ダリル・デューク『新・刑事コロンボ/犯罪警報』
今週末も家事に明け暮れつつ、合間をぬってお持ち帰りの仕事も進める。ううむ、まったく気持ちが安まらんな。
というわけで気分転換に本の整理。自宅の本が飽和状態で先週やむなくレンタルBOXを追加したが、そちらに移すだけでなく、少しは処分もしておこうと、とりあえず段ボール一箱分を古書店に持っていく。約800円也。予想よりは多かったか。
夜はDVDで『新・刑事コロンボ/犯罪警報』を視聴。通算五十七作目。監督はダリル・デューク。
凶悪事件のドキュメンタリー番組「犯罪警報」で人気沸騰のホスト役ウェイド・アンダース。そこへ、かつて司会者の座を争ったバド・クラークが現れ、ウェイドが無名時代に出演したポルノ映画をもっていると告げる。バドは「犯罪警報」のホスト役を譲らなければ、自分のニュース番組でその事実を公表するという。
ウェイドはオフィスのカメラでアリバイ工作をすると、バドを訪ね、毒薬入りの煙草をすり替えてバドを毒殺した。証拠となるビデオを回収し、暴露記事のデータもすり替え、ウェイドの未来は安泰かに思えたが……。

ううむ、これはきつい。スタイル自体は旧シリーズを踏まえたオーソドックスな倒叙もので、セレブな犯人をコロンボが少しずつ追い詰めるという展開は安心して見られるレベル。冗長なところは多いがまあ演出は悪くない。
ただ、肝心の犯行が粗すぎて、これはコロンボが捜査しなくともいずれ犯人は簡単に捕まったに違いない。なんせウェイドの仕掛けたトリックのほとんどすべてにミスがあるのである。煙草の吸い殻のフィルター、大文字と小文字の違い、プリント用紙の指紋、カメラに映った背景の矛盾などなど。犯人が犯罪番組のホスト、しかも元警備のプロだというのに、これはいただけません。
犯人の体たらくに引きずられるかのように、コロンボも精彩を欠く。ラストで示す決め手も単なる状況証拠だし、決定的な証拠はなかったように思えるのだが……。
ちなみに犯人役のジョージ・ハミルトンは『5時30分の目撃者』以来の再登場。お年は召したが相変わらずダンディーで、セレブな犯人役としては理想的なタイプである。実際、本作での存在感もなかなかのものだが、いかんせん肝心の中身が悪かった。
まあ『5時30分の目撃者』も傑作とはいえるほどの内容ではないのだが、どうもジョージ・ハミルトンはことコロンボものに関しては、あまりいい作品に恵まれていないようだ。
というわけで気分転換に本の整理。自宅の本が飽和状態で先週やむなくレンタルBOXを追加したが、そちらに移すだけでなく、少しは処分もしておこうと、とりあえず段ボール一箱分を古書店に持っていく。約800円也。予想よりは多かったか。
夜はDVDで『新・刑事コロンボ/犯罪警報』を視聴。通算五十七作目。監督はダリル・デューク。
凶悪事件のドキュメンタリー番組「犯罪警報」で人気沸騰のホスト役ウェイド・アンダース。そこへ、かつて司会者の座を争ったバド・クラークが現れ、ウェイドが無名時代に出演したポルノ映画をもっていると告げる。バドは「犯罪警報」のホスト役を譲らなければ、自分のニュース番組でその事実を公表するという。
ウェイドはオフィスのカメラでアリバイ工作をすると、バドを訪ね、毒薬入りの煙草をすり替えてバドを毒殺した。証拠となるビデオを回収し、暴露記事のデータもすり替え、ウェイドの未来は安泰かに思えたが……。

ううむ、これはきつい。スタイル自体は旧シリーズを踏まえたオーソドックスな倒叙もので、セレブな犯人をコロンボが少しずつ追い詰めるという展開は安心して見られるレベル。冗長なところは多いがまあ演出は悪くない。
ただ、肝心の犯行が粗すぎて、これはコロンボが捜査しなくともいずれ犯人は簡単に捕まったに違いない。なんせウェイドの仕掛けたトリックのほとんどすべてにミスがあるのである。煙草の吸い殻のフィルター、大文字と小文字の違い、プリント用紙の指紋、カメラに映った背景の矛盾などなど。犯人が犯罪番組のホスト、しかも元警備のプロだというのに、これはいただけません。
犯人の体たらくに引きずられるかのように、コロンボも精彩を欠く。ラストで示す決め手も単なる状況証拠だし、決定的な証拠はなかったように思えるのだが……。
ちなみに犯人役のジョージ・ハミルトンは『5時30分の目撃者』以来の再登場。お年は召したが相変わらずダンディーで、セレブな犯人役としては理想的なタイプである。実際、本作での存在感もなかなかのものだが、いかんせん肝心の中身が悪かった。
まあ『5時30分の目撃者』も傑作とはいえるほどの内容ではないのだが、どうもジョージ・ハミルトンはことコロンボものに関しては、あまりいい作品に恵まれていないようだ。
Posted
on
松本清張『点と線』(新潮文庫)
光文社文庫の『松本清張短編全集』をすべて読み終えたのが昨年の五月。しばらく時間が空いたけれど、そろそろ長篇も手を出すことにした。
ミステリの読書ブログと謳っておきながら、正直、管理人はこれまで清張の長篇は数作しか読んでいない。理由は明白。若いときから社会派ミステリというジャンルに浪漫を感じられず、ほぼ読まず嫌いで来ただけである。確かに数作は読んだけれど、これまた若いときはそれほど面白みを感じられなかったこともある。
ところが人間変わるもので、『松本清張短編全集』が文庫化されたのを機に試してみたところ、これがまあ面白いのなんの。結局足かけ三年ほどかけて読み終え、ようやく長篇の順番がきたというわけである。
で、最初の一冊はもちろん長篇第一作の『点と線』。ン十年ぶりの再読である。
今さら感はすごいものがあるけれど(笑)、一応ストーリーから。
機械工具商を営む安田辰郎は、行きつけの料亭「小雪」の仲居2人に見送られ、東京駅の13番線ホームに立っていた。そのとき三人は向かいの15番線ホームに、同じく「小雪」で働くお時が男性と特急列車「あさかぜ」に乗り込むところを目にする。
それから数日後。お時と男性が福岡県香椎の海岸で死体となって発見される。男性の名は佐山。世間を賑わす汚職事件の関係者であったことから、それを苦にした心中事件に思われた。
しかし、ベテラン刑事の鳥飼はどこか納得がいかなかった。列車食堂の受取証が気にかかり、一人で捜査を開始する。一方、汚職事件を追っていた東京の刑事、三原は心中事件を追って九州へ向かった……。

若い頃に読んだときはあまり面白みを感じられなかったと書いたばかりだが、これだけは当時も別格。十分に楽しく読めた記憶があり、今回あらためて読んでみて、さらにその意を強くした。
本作は松本清張の長篇第一作というばかりでなく、社会派ミステリの幕開けを告げる記念すべき作品でもあるわけだが、そんな冠をつけるまでもなく、まずミステリとして十分に面白いのである。
ポイントはいくつかあろうが、何といってもクロフツばりのアリバイ崩しがあげられるだろう。さすがにメイントリックは今となっては驚きも少ないが、警察の地道な捜査によって少しずつ真相が紐解かれていく様は実にスリリング。しかも読者の少しだけ先をゆく展開が非常に巧みで、ぐいぐい引き込まれてゆく。冒頭の東京駅のホームのシーンが、四分間の空白として、後半に生きてくるプロットもさすがだ。
完璧に思われた犯罪が、その完璧さによって逆に作為的だと鳥飼刑事が着目するという流れも楽しい。このあたりはコロンボとも共通する部分で、どちらかというと鵜飼は脇役ではあるのだが、キャラクター的には主役の三原刑事を上回る存在感を見せつけるのもなかなか。
褒めついでにもうひとつ挙げると、動機や犯人像もなかなかよいのだ。動機については社会派ミステリと呼ばれる所以でもあるので今さら述べるまでもないが、犯人像は軽く衝撃を受けるぐらいの仕掛けが施されている。
そういった数々のポイントがカチッとまとまった本作、つまらないわけがないのである。ちょっとした傷もないわけではないし、ラストはできれば書簡というスタイルにしてほしくなかったと思うのだが、それはこの際、目をつぶる。
社会派なんて、と食わず嫌いの方にもぜひおすすめしたい傑作。
ミステリの読書ブログと謳っておきながら、正直、管理人はこれまで清張の長篇は数作しか読んでいない。理由は明白。若いときから社会派ミステリというジャンルに浪漫を感じられず、ほぼ読まず嫌いで来ただけである。確かに数作は読んだけれど、これまた若いときはそれほど面白みを感じられなかったこともある。
ところが人間変わるもので、『松本清張短編全集』が文庫化されたのを機に試してみたところ、これがまあ面白いのなんの。結局足かけ三年ほどかけて読み終え、ようやく長篇の順番がきたというわけである。
で、最初の一冊はもちろん長篇第一作の『点と線』。ン十年ぶりの再読である。
今さら感はすごいものがあるけれど(笑)、一応ストーリーから。
機械工具商を営む安田辰郎は、行きつけの料亭「小雪」の仲居2人に見送られ、東京駅の13番線ホームに立っていた。そのとき三人は向かいの15番線ホームに、同じく「小雪」で働くお時が男性と特急列車「あさかぜ」に乗り込むところを目にする。
それから数日後。お時と男性が福岡県香椎の海岸で死体となって発見される。男性の名は佐山。世間を賑わす汚職事件の関係者であったことから、それを苦にした心中事件に思われた。
しかし、ベテラン刑事の鳥飼はどこか納得がいかなかった。列車食堂の受取証が気にかかり、一人で捜査を開始する。一方、汚職事件を追っていた東京の刑事、三原は心中事件を追って九州へ向かった……。

若い頃に読んだときはあまり面白みを感じられなかったと書いたばかりだが、これだけは当時も別格。十分に楽しく読めた記憶があり、今回あらためて読んでみて、さらにその意を強くした。
本作は松本清張の長篇第一作というばかりでなく、社会派ミステリの幕開けを告げる記念すべき作品でもあるわけだが、そんな冠をつけるまでもなく、まずミステリとして十分に面白いのである。
ポイントはいくつかあろうが、何といってもクロフツばりのアリバイ崩しがあげられるだろう。さすがにメイントリックは今となっては驚きも少ないが、警察の地道な捜査によって少しずつ真相が紐解かれていく様は実にスリリング。しかも読者の少しだけ先をゆく展開が非常に巧みで、ぐいぐい引き込まれてゆく。冒頭の東京駅のホームのシーンが、四分間の空白として、後半に生きてくるプロットもさすがだ。
完璧に思われた犯罪が、その完璧さによって逆に作為的だと鳥飼刑事が着目するという流れも楽しい。このあたりはコロンボとも共通する部分で、どちらかというと鵜飼は脇役ではあるのだが、キャラクター的には主役の三原刑事を上回る存在感を見せつけるのもなかなか。
褒めついでにもうひとつ挙げると、動機や犯人像もなかなかよいのだ。動機については社会派ミステリと呼ばれる所以でもあるので今さら述べるまでもないが、犯人像は軽く衝撃を受けるぐらいの仕掛けが施されている。
そういった数々のポイントがカチッとまとまった本作、つまらないわけがないのである。ちょっとした傷もないわけではないし、ラストはできれば書簡というスタイルにしてほしくなかったと思うのだが、それはこの際、目をつぶる。
社会派なんて、と食わず嫌いの方にもぜひおすすめしたい傑作。
Posted
on
ジェームズ・オコノリー『恐竜グワンジ』
家事に追われる一日。とはいえ、それだけで三連休が終わるのもあれなので、少しだけ「八王子古本まつり」に出かける。考えると古本市に出かけるのも久しぶりで、一時間ほどかけてゆっくりと棚を見て回る。ただ、本日で四日目なので大したものが残っているはずもなく、大谷羊太郎の『虹色の陥穽』のみ購入。
夜はDVDで『恐竜グワンジ』を視聴。ごぞんじレイ・ハリーハウゼンが特撮を手掛けた1969年の作品。監督はジェームズ・オコノリー。
こんな話。メキシコのロデオ・サーカス団へ不思議な動物が持ち込まれた。古生物学の教授はそれを中生代にいたウマの祖先であると断言するが、これで一儲けを企むサーカス団は聞く耳をもたない。やがて呪いを恐れるジプシーたちがそれを"禁断の谷"と呼ばれる渓谷へ返すため、奪い返してしまう。ジプシーの後を追うサーカス団と教授は、やがて"禁断の谷"へ足を踏み入れ、そこで驚愕の生物に遭遇する……。

ハリーハウゼン絡みの作品では比較的、地味な方だろうが、これがなかなかよくできている。コマ撮りによる恐竜の動き、俳優との合成の完成度もさることながら、意外にキャラクターがたっており、ドラマとして普通に面白いのがいい。ぶっちゃけキングコングとロストワールドを足して二で割ったような話ではあるし、安易な部分も多いのだけれど(笑)、それらを差し引いても十分楽しめる。
主人公、ヒロイン、教授、ジプシー、サーカス団それぞれの思惑が、きちんと描き分けられているのがポイントだろう。前半はそれらの利害が複雑に絡み合い、きちんと物語の興味で引っ張っていく。これが後半になると見事に収斂され、クライマックスにきれいにつながる。いやお見事。
小粒ながら見せ場も多く、個人的にはハリーハウゼン作品の上位に推したい一作である。
夜はDVDで『恐竜グワンジ』を視聴。ごぞんじレイ・ハリーハウゼンが特撮を手掛けた1969年の作品。監督はジェームズ・オコノリー。
こんな話。メキシコのロデオ・サーカス団へ不思議な動物が持ち込まれた。古生物学の教授はそれを中生代にいたウマの祖先であると断言するが、これで一儲けを企むサーカス団は聞く耳をもたない。やがて呪いを恐れるジプシーたちがそれを"禁断の谷"と呼ばれる渓谷へ返すため、奪い返してしまう。ジプシーの後を追うサーカス団と教授は、やがて"禁断の谷"へ足を踏み入れ、そこで驚愕の生物に遭遇する……。

ハリーハウゼン絡みの作品では比較的、地味な方だろうが、これがなかなかよくできている。コマ撮りによる恐竜の動き、俳優との合成の完成度もさることながら、意外にキャラクターがたっており、ドラマとして普通に面白いのがいい。ぶっちゃけキングコングとロストワールドを足して二で割ったような話ではあるし、安易な部分も多いのだけれど(笑)、それらを差し引いても十分楽しめる。
主人公、ヒロイン、教授、ジプシー、サーカス団それぞれの思惑が、きちんと描き分けられているのがポイントだろう。前半はそれらの利害が複雑に絡み合い、きちんと物語の興味で引っ張っていく。これが後半になると見事に収斂され、クライマックスにきれいにつながる。いやお見事。
小粒ながら見せ場も多く、個人的にはハリーハウゼン作品の上位に推したい一作である。
Posted
on
谷口基『変格探偵小説入門 奇想の遺産』(岩波現代全書)
本好きの人が抱えている悩みはいろいろあろうけれど、その代表的なところといえば、これはもう本の置き場所である。なかには図書館派の方もおられるだろうが、事情さえ許せば自分の好きな本に囲まれて暮らしたいというのが本音ではないだろうか。
かくいう管理人も学生の頃から、常にこの悩みとは隣り合わせ。その頃は六畳一間のアパートとかだったから、そもそもスペースが全然ないのだけれど、まあ働き出してからは引っ越しを繰り返し、その度に本を置くスペースを拡充させてきた。そして十五年ほど前に家を買って、ようやくこういう悩みとはサヨナラかと思ったのだが。
本とはいうのはなぜこうも増えるのでありましょうか。
結局、十年ほどで家にすべて置くことを断念。なんとレンタル倉庫を借りて、そこに蔵書の一部を突っこむことにした。まあ、レンタル倉庫といっても一坪もないレンタルBOXというタイプなのだが、それでも段ボールにして八十箱ぐらいは楽に入るからとりあえずは重宝する。そして数年。
本とはいうのはなぜこうも増えるのでありましょうか。
歴史は繰り返す。レンタル倉庫の収容能力がついに限界に達し、この週末に同じタイプのレンタル倉庫をもうひとつ借りてしまったのであった。本の収納に特化した家に建て替えたいと、真剣に思う今日この頃である。
さて近況報告はこのぐらいにして(笑)。
本日の読了本は『変格探偵小説入門 奇想の遺産』。「入門」とは謳っているが、日本の変格探偵小説を俯瞰的に論じた評論であり、少なくともミステリ初心者が手軽に読めるような入門書ではない。もう少しタイトルは考えてもよかったのではないかな。

それはともかく。
内容は十分に面白い。そもそも変格とは何か、という話になるわけだが、謎解きを主とした本格探偵小説に対し、謎解き以外の要素を重要視した探偵小説という認識でよいだろう。それは怪奇や幻想、SF、冒険などの要素を含んだ多様な小説群である。「本格」に対する「変格」、語感としては本格より一段低いランクというイメージをもった変格ではあるが、日本の探偵小説の歴史は変格に始まり、戦後まではむしろ圧倒的に主流であった。江戸川乱歩に横溝正史、小酒井不木、小栗虫太郎、夢野久作、海野十三、城昌幸、橘外男、渡辺温、久生十蘭などなど。なんと豪華な面子っていうか、戦前のメジャーな探偵作家はほとんど変格なのである。
探偵小説を探偵小説として認知させた要素は、謎解きでありロジックの面白さである。これらの要素が主であったから、それまでの小説とは異なるジャンルを形成し、市民権を得た。その「謎解き」を主としないミステリは、どうやってミステリとして成立できるのか。
「本格」と「変格」という語を作りだした甲賀三郎は、この疑問があるが故に、本格と変格を区別したかった。その小説的価値は認めつつも、根本的なところで探偵小説としては認めたくなかったのである。
ただ、変格の中にも論理はあった。それが非合理の合理主義=非論理の論理とでもいうべきもので、既成文学の枠を超えようとする乱歩の傑作は正にそれを体現したものであった。
本書はそんな矛盾した存在である変格探偵小説の姿を、あらためて認識するための一冊である。そのものの歴史だけではなく、いくつかの作品を例に挙げつつ、時代の証言を掘り起こし、ときには時代背景や一般文壇も絡め、その文学的意義を掘り下げていく。非常に陳腐な表現だが、面白くてためになるとはこういう本のことか。
戦前探偵小説のファンならぜひ。
かくいう管理人も学生の頃から、常にこの悩みとは隣り合わせ。その頃は六畳一間のアパートとかだったから、そもそもスペースが全然ないのだけれど、まあ働き出してからは引っ越しを繰り返し、その度に本を置くスペースを拡充させてきた。そして十五年ほど前に家を買って、ようやくこういう悩みとはサヨナラかと思ったのだが。
本とはいうのはなぜこうも増えるのでありましょうか。
結局、十年ほどで家にすべて置くことを断念。なんとレンタル倉庫を借りて、そこに蔵書の一部を突っこむことにした。まあ、レンタル倉庫といっても一坪もないレンタルBOXというタイプなのだが、それでも段ボールにして八十箱ぐらいは楽に入るからとりあえずは重宝する。そして数年。
本とはいうのはなぜこうも増えるのでありましょうか。
歴史は繰り返す。レンタル倉庫の収容能力がついに限界に達し、この週末に同じタイプのレンタル倉庫をもうひとつ借りてしまったのであった。本の収納に特化した家に建て替えたいと、真剣に思う今日この頃である。
さて近況報告はこのぐらいにして(笑)。
本日の読了本は『変格探偵小説入門 奇想の遺産』。「入門」とは謳っているが、日本の変格探偵小説を俯瞰的に論じた評論であり、少なくともミステリ初心者が手軽に読めるような入門書ではない。もう少しタイトルは考えてもよかったのではないかな。

それはともかく。
内容は十分に面白い。そもそも変格とは何か、という話になるわけだが、謎解きを主とした本格探偵小説に対し、謎解き以外の要素を重要視した探偵小説という認識でよいだろう。それは怪奇や幻想、SF、冒険などの要素を含んだ多様な小説群である。「本格」に対する「変格」、語感としては本格より一段低いランクというイメージをもった変格ではあるが、日本の探偵小説の歴史は変格に始まり、戦後まではむしろ圧倒的に主流であった。江戸川乱歩に横溝正史、小酒井不木、小栗虫太郎、夢野久作、海野十三、城昌幸、橘外男、渡辺温、久生十蘭などなど。なんと豪華な面子っていうか、戦前のメジャーな探偵作家はほとんど変格なのである。
探偵小説を探偵小説として認知させた要素は、謎解きでありロジックの面白さである。これらの要素が主であったから、それまでの小説とは異なるジャンルを形成し、市民権を得た。その「謎解き」を主としないミステリは、どうやってミステリとして成立できるのか。
「本格」と「変格」という語を作りだした甲賀三郎は、この疑問があるが故に、本格と変格を区別したかった。その小説的価値は認めつつも、根本的なところで探偵小説としては認めたくなかったのである。
ただ、変格の中にも論理はあった。それが非合理の合理主義=非論理の論理とでもいうべきもので、既成文学の枠を超えようとする乱歩の傑作は正にそれを体現したものであった。
本書はそんな矛盾した存在である変格探偵小説の姿を、あらためて認識するための一冊である。そのものの歴史だけではなく、いくつかの作品を例に挙げつつ、時代の証言を掘り起こし、ときには時代背景や一般文壇も絡め、その文学的意義を掘り下げていく。非常に陳腐な表現だが、面白くてためになるとはこういう本のことか。
戦前探偵小説のファンならぜひ。
Posted
on
E・W・スワックハマー『新・刑事コロンボ/殺人講義』
DVDで『新・刑事コロンボ/殺人講義』を観る。通算五十六作目、監督はE・W・スワックハマー。
大学生のジャスティンとクーパーは家柄もよく、頭脳も明晰。しかし、そんな恵まれた環境に感謝することもなく、数々のトラブルを起こしては、親に尻ぬぐいをしてもらっていた。そしてとうとうクーパーは、父親に今度問題を起こしたら勘当だと最終通告を突きつけられる。
その直後、試験用紙を盗んだことが発覚した二人は、ラスク教授に呼び出しを受け、処分を待てと言い渡された。親に相談することもできず、彼らは事が公になる前にラスク教授を殺害賞と計画する。そんなある日、ラスク教授の授業に、特別講師としてコロンボが派遣されてきた……。

基本的な構成は割合にオーソドックス、というかシリーズ中でもかなりシンプルな構成である。殺害トリックをラストまで明らかにしないというポイントはあるのだが、逆にいうとそのトリックがほぼすべて。ただし、秀才君が考えたトリックとしては機械的に過ぎて、ミステリとしての面白みは少ない。
しかもコロンボまでもがツキに恵まれたと作中で語るように、推理の部分も物足りない。
ただ、新シリーズの中で印象に残るエピソードであることもまた確か。その理由は異色の犯人像にある。
シリーズ中でもおそらくはもっとも若い犯人。加えてもっとも無礼な犯人でもある。コロンボに登場する犯人は多くがその道の成功者であったり、野心家であったりするが、彼らは一流であるがゆえ次第にコロンボの秘められた実力に気づき、ときには敬意すら抱くこともしばしばである。
ところが本作の犯人は最後の最後までコロンボの力に気づくこともなく、あろうことか陰ではコロンボの悪口を言いまくる。若さゆえの愚かさというのは誰にでもあることだが、それをここまで押し出す脚本は果たしてどういう狙いがあったのか。まあ、普通に考えると、かなりお年を召してきたコロンボと、孫ほどの犯人との対比であり、人間的な成熟にスポットを当てたというところだろう。しかしながら、それが非常に画一的すぎて見る者に響いてこない。
そういう意味では、どうにもカタルシスを得られず、なんだか最後まで楽しめないままに終わってしまった。残念。
大学生のジャスティンとクーパーは家柄もよく、頭脳も明晰。しかし、そんな恵まれた環境に感謝することもなく、数々のトラブルを起こしては、親に尻ぬぐいをしてもらっていた。そしてとうとうクーパーは、父親に今度問題を起こしたら勘当だと最終通告を突きつけられる。
その直後、試験用紙を盗んだことが発覚した二人は、ラスク教授に呼び出しを受け、処分を待てと言い渡された。親に相談することもできず、彼らは事が公になる前にラスク教授を殺害賞と計画する。そんなある日、ラスク教授の授業に、特別講師としてコロンボが派遣されてきた……。

基本的な構成は割合にオーソドックス、というかシリーズ中でもかなりシンプルな構成である。殺害トリックをラストまで明らかにしないというポイントはあるのだが、逆にいうとそのトリックがほぼすべて。ただし、秀才君が考えたトリックとしては機械的に過ぎて、ミステリとしての面白みは少ない。
しかもコロンボまでもがツキに恵まれたと作中で語るように、推理の部分も物足りない。
ただ、新シリーズの中で印象に残るエピソードであることもまた確か。その理由は異色の犯人像にある。
シリーズ中でもおそらくはもっとも若い犯人。加えてもっとも無礼な犯人でもある。コロンボに登場する犯人は多くがその道の成功者であったり、野心家であったりするが、彼らは一流であるがゆえ次第にコロンボの秘められた実力に気づき、ときには敬意すら抱くこともしばしばである。
ところが本作の犯人は最後の最後までコロンボの力に気づくこともなく、あろうことか陰ではコロンボの悪口を言いまくる。若さゆえの愚かさというのは誰にでもあることだが、それをここまで押し出す脚本は果たしてどういう狙いがあったのか。まあ、普通に考えると、かなりお年を召してきたコロンボと、孫ほどの犯人との対比であり、人間的な成熟にスポットを当てたというところだろう。しかしながら、それが非常に画一的すぎて見る者に響いてこない。
そういう意味では、どうにもカタルシスを得られず、なんだか最後まで楽しめないままに終わってしまった。残念。
Posted
on
梶龍雄『龍神池の小さな死体』(ケイブンシャ文庫)
トム・クランシーが10月1日に亡くなった。『レッド・オクトーバーを追え』で華々しくデビューし、あっという間に世界的ベストセラー作家に登りつめたことはまだ記憶に新しいが、その最大の功績はハイテク軍事小説とでもいうべきジャンルを確立させたことにある。
もちろん彼の登場以前にも軍事小説は多く書かれていたが、それらはあくまで冒険小説としての側面が強かった。トム・クランシーはそこに情報小説というエッセンスをぶちこんだ。近代の戦術やハイテク兵器など、軍事マニアが喜びそうなネタを徹底的に詰め込み、新しい時代の軍事小説を展開してみせたのである。キャラクターがステロタイプ、アメリカ礼賛が鼻につくなどの批判もあったが、初期のいくつかの作品は間違いなく傑作であり、このジャンルの先駆者として忘れるわけにはいかないだろう。
まだ六十六歳という若さであり、死因が公表されていないこともあって何やらきな臭い感じもあるが、何はともあれご冥福をお祈りしたい。
気分を変えて読了本の感想を。梶龍雄の長篇第五作目にあたる『龍神池の小さな死体』。
おまえの弟は殺されたんだよ——母親が臨終の間際に残した言葉に、建築工学の教授、仲城智一はショックを受けた。弟の秀二は小学生の頃、学童疎開先の千葉は鶴舞で水死したはずだったのだ。智一は大学の休みをとり、真相を探るべく秀二のかつての同級生らを訪ね、そして鶴舞にある龍神池へと向かったが……。

梶龍雄の代表作として語られることが多い本書だが、それも納得。
序盤はどちらかといえば退屈なぐらいなのだが、主人公が鶴舞を訪れるあたりから物語が少しずつ動き始め、中盤を過ぎると一気にたたみかける。これがまったく思いがけない方向からやってくるので、こちらが態勢を立て直す間もあらばこそ、二転三転する事実が常に読者の先をいく。
成功の要因はとにかく緻密なプロットと巧妙な伏線だろう。ラストの真相はかなり意外なもので、それだけにややプロットが強引かとも感じたが、ここまでやってくれれば固いことは言いますまい。あれもこれもすべてに意味があったのかと、その徹底的な伏線の作り込みには心底脱帽である。
なお、ところどころで顔を見せる社会派ミステリ的なメッセージや主人公の生き様を云々するような描写はけっこう気になった。
ストーリー上は確かにあってもおかしくないのだけれど、本書はあくまで本格寄りに力点を置いたミステリである。『海を見ないで陸を見よう』のような叙情性そのものが意味を持つミステリではないのだから、こういった部分を強調させるような描写は、全体のバランスを悪くしているように感じてしまった。決着のつけ方も同じ意味で気になった次第。
ともあれそれらを差し引いても、本書は間違いなくおすすめ。これを絶版にしてはだめでしょ。
もちろん彼の登場以前にも軍事小説は多く書かれていたが、それらはあくまで冒険小説としての側面が強かった。トム・クランシーはそこに情報小説というエッセンスをぶちこんだ。近代の戦術やハイテク兵器など、軍事マニアが喜びそうなネタを徹底的に詰め込み、新しい時代の軍事小説を展開してみせたのである。キャラクターがステロタイプ、アメリカ礼賛が鼻につくなどの批判もあったが、初期のいくつかの作品は間違いなく傑作であり、このジャンルの先駆者として忘れるわけにはいかないだろう。
まだ六十六歳という若さであり、死因が公表されていないこともあって何やらきな臭い感じもあるが、何はともあれご冥福をお祈りしたい。
気分を変えて読了本の感想を。梶龍雄の長篇第五作目にあたる『龍神池の小さな死体』。
おまえの弟は殺されたんだよ——母親が臨終の間際に残した言葉に、建築工学の教授、仲城智一はショックを受けた。弟の秀二は小学生の頃、学童疎開先の千葉は鶴舞で水死したはずだったのだ。智一は大学の休みをとり、真相を探るべく秀二のかつての同級生らを訪ね、そして鶴舞にある龍神池へと向かったが……。

梶龍雄の代表作として語られることが多い本書だが、それも納得。
序盤はどちらかといえば退屈なぐらいなのだが、主人公が鶴舞を訪れるあたりから物語が少しずつ動き始め、中盤を過ぎると一気にたたみかける。これがまったく思いがけない方向からやってくるので、こちらが態勢を立て直す間もあらばこそ、二転三転する事実が常に読者の先をいく。
成功の要因はとにかく緻密なプロットと巧妙な伏線だろう。ラストの真相はかなり意外なもので、それだけにややプロットが強引かとも感じたが、ここまでやってくれれば固いことは言いますまい。あれもこれもすべてに意味があったのかと、その徹底的な伏線の作り込みには心底脱帽である。
なお、ところどころで顔を見せる社会派ミステリ的なメッセージや主人公の生き様を云々するような描写はけっこう気になった。
ストーリー上は確かにあってもおかしくないのだけれど、本書はあくまで本格寄りに力点を置いたミステリである。『海を見ないで陸を見よう』のような叙情性そのものが意味を持つミステリではないのだから、こういった部分を強調させるような描写は、全体のバランスを悪くしているように感じてしまった。決着のつけ方も同じ意味で気になった次第。
ともあれそれらを差し引いても、本書は間違いなくおすすめ。これを絶版にしてはだめでしょ。


