Posted in 06 2012
Posted
on
スティーグ・ラーソン『ミレニアム2火と戯れる女(上)』(ハヤカワ文庫)
スティーグ・ラーソンの『ミレニアム2火と戯れる女』を、とりあえず上巻まで読了。
天才的ハッカーでもある警備会社の女性調査員リスベット。彼女の後見人に指名された弁護士ビュルマンは、かつてその地位を利用してリスベットを暴行したが、逆に徹底的な報復を受け、生きる気力をなくしていた。だが、ある出来事をきっかけに再びリスベットへの憎悪が燃え上がり、復讐の計画を練り始める。
そんな頃、月刊誌『ミレニアム』の発行責任者ミカエルたちは、スウェーデンにはびこる人身売買問題を大々的に取りあげる決定を下していた。その企画の中心として活躍するジャーナリストのダグと恋人ミアは、調査の中で「ザラ」という謎の人物の存在を知り、さらなる調査も進めていた。
一方、長期の旅行に出ていたリスベットは、偶然ダグの調査を知り、独自に「ザラ」の調査に乗り出していく。だが、そんな彼らを狙う者たちの姿があった……。

ほほう。前作『ミレニアム1ドラゴン・タトゥーの女』は、登場人物や設定は現代的なれど、意外なほど謎解きやクラシック要素の強いオーソドックスな作品だったが、本作はガラリと趣向を変えてきている。謎解き要素は影を潜め、徹底的にストーリーの面白さとサスペンスで押す現代的な作風である。
前作では第三者的に事件に絡んだリスベットが、本作では完全に渦中の一人となり、彼女を中心に動くのも大きな変更点。キャラクターの特徴を考えれば、確かにこういうタイプの作品の方が、その魅力は最大限に活かせるだろう。
ただ、これは前作と同様の不満点だが、事件が動き出すまでの助走が長すぎである。事件そのものは上巻の終盤でようやく動き始めるのだが、そこからの展開がいいだけに、なんともバランスが悪い。書き込みが悪いわけではないのだけれど、ラーソンの場合、出てくる人出てくる組織すべてを説明しないではいられないところがある。通行人Aを通行人Aとすることに対し、我慢ができないのかも。とにかくいろいろな意味で饒舌なのである。
とはいえ、上で書いたように上巻終盤からの展開が一気に盛り上がるので、それはこの際、目をつぶろう。下巻に期待。
天才的ハッカーでもある警備会社の女性調査員リスベット。彼女の後見人に指名された弁護士ビュルマンは、かつてその地位を利用してリスベットを暴行したが、逆に徹底的な報復を受け、生きる気力をなくしていた。だが、ある出来事をきっかけに再びリスベットへの憎悪が燃え上がり、復讐の計画を練り始める。
そんな頃、月刊誌『ミレニアム』の発行責任者ミカエルたちは、スウェーデンにはびこる人身売買問題を大々的に取りあげる決定を下していた。その企画の中心として活躍するジャーナリストのダグと恋人ミアは、調査の中で「ザラ」という謎の人物の存在を知り、さらなる調査も進めていた。
一方、長期の旅行に出ていたリスベットは、偶然ダグの調査を知り、独自に「ザラ」の調査に乗り出していく。だが、そんな彼らを狙う者たちの姿があった……。

ほほう。前作『ミレニアム1ドラゴン・タトゥーの女』は、登場人物や設定は現代的なれど、意外なほど謎解きやクラシック要素の強いオーソドックスな作品だったが、本作はガラリと趣向を変えてきている。謎解き要素は影を潜め、徹底的にストーリーの面白さとサスペンスで押す現代的な作風である。
前作では第三者的に事件に絡んだリスベットが、本作では完全に渦中の一人となり、彼女を中心に動くのも大きな変更点。キャラクターの特徴を考えれば、確かにこういうタイプの作品の方が、その魅力は最大限に活かせるだろう。
ただ、これは前作と同様の不満点だが、事件が動き出すまでの助走が長すぎである。事件そのものは上巻の終盤でようやく動き始めるのだが、そこからの展開がいいだけに、なんともバランスが悪い。書き込みが悪いわけではないのだけれど、ラーソンの場合、出てくる人出てくる組織すべてを説明しないではいられないところがある。通行人Aを通行人Aとすることに対し、我慢ができないのかも。とにかくいろいろな意味で饒舌なのである。
とはいえ、上で書いたように上巻終盤からの展開が一気に盛り上がるので、それはこの際、目をつぶろう。下巻に期待。
Posted
on
原口智生『ミカドロイド』
ROM138号が届いたので、ぱらぱらと目を通す。小林晋氏の「『死の扉』前後のこと」とか森英俊氏の「Book Sleuth」とか真田啓介氏の「江戸川乱歩の「探偵小説の定義」をめぐって」とか、相変わらず濃い話や興味深い考察が目白押しで圧倒される。S・A・ドゥーセの短編掲載も嬉しいですのぅ。
東宝特撮映画DVDコレクションから『ミカドロイド』を観る。映画ではなく、もとは「東宝シネパック」というブランドで発売されたビデオである。1991年の作品で監督は原口智生。名前程度は知っていたが、これが初見。長年気にはなっていたのだが、期待半分地雷半分という雰囲気だったので、こういう機会でもなければおそらく観なかったはずの一本である。こういう機会がどういう機会なのかは自分でもよくわからんが(笑)。

太平洋戦争末期のこと。旧日本軍は本土決戦に向け、「百二十四式特殊装甲兵ジンラ號」という秘密兵器を開発していた。それは不死身の肉体をもつ人造人間を造り、さらにそれを特殊装甲と各種武装で包んだ、いわば人間戦車とでもいうべき究極の殺人兵器だった。だが敗戦濃厚な日本は計画を中止、兵器は開発者や研究所もろとも処分される。
ときは流れて1990年代。かつての研究所の真上に建設されたディスコの地下で漏電事故が発生する。そして、それが深い眠りについていたジンラ號に再び生を与えた。そんな頃、ジンラ號の目覚めに気づいた者たちがいた……。
設定は以上のとおり、なかなか凝った設定だが、実際の物語はほとんどが追いつ追われつのサスペンス。見せ方もホラー仕立てで極めてシンプルな造りである。物語の舞台もほとんどがビルの地下にある駐車場と研究所だし、登場人物もその中に偶然に閉じ込められた二人の若者、ジンラ號、そしてジンラ號を倒そうとする二人の男という具合。
そういった諸々の基本設計は嫌いではない。戦争の亡霊というジンラ號の意義、バブル末期という世相を反映した登場人物のバックボーンも悪くはない。個人的にはジンラ號のデザインも旧日本軍の兵器という味は十分出せていると思う。
ただ、それでもオススメというには厳しい映画である。今あげた長所を帳消しにする短所がいろいろとあるわけで、最たるものは演出のまずさか。
ホラー映画的盛り上げを重ねる割にはぬるい殺戮シーン、なぜかアップでしか描写してくれないメイン武器「100式短機関銃」、ラストのカギ爪の設定など、気になる点は数多い。プロローグがけっこう頑張っているだけに、本編に入ってからがいやはやなんとも。
また、戦争兵器としての改造された男たちの悲哀、それぞれの友情のドラマが、いまひとつ伝わりにくいのも惜しい。要は説明不足なだけなのだが、クライマックスにも通ずるところだし、最も重要な部分なだけに実に残念。
ビデオゆえ予算の問題などもあったのだろうが、素材がけっこう面白いだけにもったいないという印象ばかりが残る。それこそ映画にでもリメイクして、今の特撮技術で撮ればかなり良くなる気もするのだが。ううむ。
東宝特撮映画DVDコレクションから『ミカドロイド』を観る。映画ではなく、もとは「東宝シネパック」というブランドで発売されたビデオである。1991年の作品で監督は原口智生。名前程度は知っていたが、これが初見。長年気にはなっていたのだが、期待半分地雷半分という雰囲気だったので、こういう機会でもなければおそらく観なかったはずの一本である。こういう機会がどういう機会なのかは自分でもよくわからんが(笑)。

太平洋戦争末期のこと。旧日本軍は本土決戦に向け、「百二十四式特殊装甲兵ジンラ號」という秘密兵器を開発していた。それは不死身の肉体をもつ人造人間を造り、さらにそれを特殊装甲と各種武装で包んだ、いわば人間戦車とでもいうべき究極の殺人兵器だった。だが敗戦濃厚な日本は計画を中止、兵器は開発者や研究所もろとも処分される。
ときは流れて1990年代。かつての研究所の真上に建設されたディスコの地下で漏電事故が発生する。そして、それが深い眠りについていたジンラ號に再び生を与えた。そんな頃、ジンラ號の目覚めに気づいた者たちがいた……。
設定は以上のとおり、なかなか凝った設定だが、実際の物語はほとんどが追いつ追われつのサスペンス。見せ方もホラー仕立てで極めてシンプルな造りである。物語の舞台もほとんどがビルの地下にある駐車場と研究所だし、登場人物もその中に偶然に閉じ込められた二人の若者、ジンラ號、そしてジンラ號を倒そうとする二人の男という具合。
そういった諸々の基本設計は嫌いではない。戦争の亡霊というジンラ號の意義、バブル末期という世相を反映した登場人物のバックボーンも悪くはない。個人的にはジンラ號のデザインも旧日本軍の兵器という味は十分出せていると思う。
ただ、それでもオススメというには厳しい映画である。今あげた長所を帳消しにする短所がいろいろとあるわけで、最たるものは演出のまずさか。
ホラー映画的盛り上げを重ねる割にはぬるい殺戮シーン、なぜかアップでしか描写してくれないメイン武器「100式短機関銃」、ラストのカギ爪の設定など、気になる点は数多い。プロローグがけっこう頑張っているだけに、本編に入ってからがいやはやなんとも。
また、戦争兵器としての改造された男たちの悲哀、それぞれの友情のドラマが、いまひとつ伝わりにくいのも惜しい。要は説明不足なだけなのだが、クライマックスにも通ずるところだし、最も重要な部分なだけに実に残念。
ビデオゆえ予算の問題などもあったのだろうが、素材がけっこう面白いだけにもったいないという印象ばかりが残る。それこそ映画にでもリメイクして、今の特撮技術で撮ればかなり良くなる気もするのだが。ううむ。
論創ミステリ叢書から『戦前探偵小説四人集』を読む。五十巻目の本書を機に、論叢ミステリ叢書はひとまずのピリオドを打ったのは、まだ記憶に新しいところ。
しかしながら、まだまだ紹介していない作家はいるし、ここまできたのなら乱歩の巻だって出してほしい。ぜひ、いつの日か復活を願いつつ……などと書くまでもなく、つい先日に判型を変えて論創ミステリ叢書が再スタートを切ったのは皆様ご存じのとおりである。既に『守友恒探偵小説選』『大下宇陀児探偵小説選I』と順調すぎるペースで刊行中。やれ嬉しや。
とまあ、そんなわけで一度は最終巻を迎えた論創ミステリ叢書。その区切りの五十巻目は『戦前探偵小説四人集』という思い切ったラインナップであった。
収録されている作家は、羽志主水・星田三平・水上呂理・米田三星の四名。戦前ミステリのアンソロジーではちょくちょくお目にかかる名前ばかり、そのくせ一人では一冊にまとまらない程度しか作品が残っていないというマニア泣かせの方々で、当然これまで独立した著書はない。それならってんで四人の著作をまとめた形にしたのが本書。なんと四人分の全集なのである。
もう戦前探偵小説好きには堪らない一冊。出ただけで十分ありがたいわけで、ここで本日はお終いにしてもいいのだが、それではこのブログのはかない意義もますますはかなくなってしまうゆえ、以下、収録作と感想などを記す。
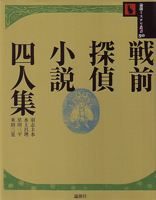
■羽志主水
「蠅の足」
「監獄部屋」
「越後獅子」
「天佑」
「処女作について」(随筆)
「雁釣り」(随筆)
「唯灸」(随筆)
「涙香の思出」(随筆)
「マイクロフォン」(随筆)
■水上呂理
「精神分析」
「蹠の衝動」
「犬の芸当」
「麻痺性痴呆患者の犯罪工作」
「驚き盤」
「石は語らず」
「処女作の思ひ出」(随筆)
「お問合せ」(随筆)
「燃えない焔」(随筆)
■星田三平
「せんとらる地球市建設記録」
「探偵殺害事件」
「落下傘嬢殺害事件」
「ヱル・ベチヨオ」
「米国の戦慄」
「もだん・しんごう」
「偽視界」
■米田三星
「生きてゐる皮膚」
「蜘蛛」
「告げ口心臓」
「血劇」
「児を産む死人」(随筆)
「森下雨村さんと私」(随筆)
頭からざっくりいくと、羽志主水は「監獄部屋」と「越後獅子」のみアンソロジーで既読。とにかく探偵小説としては実に珍しい、プロレタリアート的内容の「監獄部屋」の印象が強くて、ほぼそれだけのイメージしかなかったのだが、再読してもやはり「監獄部屋」強しである。探偵小説的なのはオチの部分ぐらいだが、思想を探偵小説にはめたかなり早い例だと思うし、それだけでも評価してしかるべきだろう。
水上呂理は昔からペンネームのインパクトだけで憶えていた作家。本名をもじったものらしいのだが、今では非常に誤解を招きやすい名前である(笑)。
まあ、それはさておき。実はこの四人の中では、これまで一番作品の印象が弱かったのだが、改めて読むとこんなに心理学や精神分析などを用いた作家だったのかと驚く。そっち系のネタだと木々高太郎とかぶる部分は多いわけだが、なんとデビューは木々より八年ほど早いと知り、二度ビックリ。ただ、どうしても内容的な今更感があるのは辛いところだ。
今回、もっとも気に入ったのが星田三平。SF的でもあり冒険小説的でもありハードボイルドチックな雰囲気も漂わせた「せんとらる地球市建設記録」はもともと好きだったのだが、他の作品を読むと、けっこういろいろなタイプにチャレンジしているのが素晴らしい。
なかには「米国の戦慄」なんていうトンデモ小説まであって、これはヴァン・ダインの生んだ名探偵ファイロ・ヴァンスとアメリカ裏社会を牛耳っていたアル・カポネを対決させた物語。これらの設定やニューヨークテロというテーマは派手だが、双方が持っている魅力や特徴をまったく用いず、内容もグダグダという超企画倒れの一篇である。ただ、話のタネだけのために読んでおいても損はない(笑)。
ちなみに書き溜めしてあった原稿が、戦災でほとんど焼失したらしく、まったく残念このうえない。
ラストは米田三星。意外なことに、まとめて読むと明らかに本書中の他の作家とはレベルが違う。戦前探偵小説というフィルター抜きで、普通に小説が巧いと感じられる作家なのである。文章もしっかりしているし雰囲気も十分。米田三星ならたとえ誘われたとしても、間違ってもファイロ・ヴァンスのパスティーシュなどは書かないだろう(笑)。いや、ファイロ・ヴァンスのパスティーシュも、それはそれで戦前探偵小説的ではあるのだが。
さてさて、こうやって褒めてはみたけれど、むろん今の探偵小説と比較するべきではない。同時代とはいえ、乱歩や正史はものが違うのだ。その他の作家など、決して期待するべきではないのである。
それでも「実はこんなミステリがあるんだけどね」とオススメしたい衝動にかられてしまう、そんな魅力がこの時代の作家にはあるんだよなぁ。当時の探偵小説に免疫がない人にぜひ読んでもらって、感想を聞いてみたいものだ。
しかしながら、まだまだ紹介していない作家はいるし、ここまできたのなら乱歩の巻だって出してほしい。ぜひ、いつの日か復活を願いつつ……などと書くまでもなく、つい先日に判型を変えて論創ミステリ叢書が再スタートを切ったのは皆様ご存じのとおりである。既に『守友恒探偵小説選』『大下宇陀児探偵小説選I』と順調すぎるペースで刊行中。やれ嬉しや。
とまあ、そんなわけで一度は最終巻を迎えた論創ミステリ叢書。その区切りの五十巻目は『戦前探偵小説四人集』という思い切ったラインナップであった。
収録されている作家は、羽志主水・星田三平・水上呂理・米田三星の四名。戦前ミステリのアンソロジーではちょくちょくお目にかかる名前ばかり、そのくせ一人では一冊にまとまらない程度しか作品が残っていないというマニア泣かせの方々で、当然これまで独立した著書はない。それならってんで四人の著作をまとめた形にしたのが本書。なんと四人分の全集なのである。
もう戦前探偵小説好きには堪らない一冊。出ただけで十分ありがたいわけで、ここで本日はお終いにしてもいいのだが、それではこのブログのはかない意義もますますはかなくなってしまうゆえ、以下、収録作と感想などを記す。
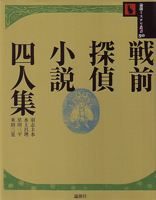
■羽志主水
「蠅の足」
「監獄部屋」
「越後獅子」
「天佑」
「処女作について」(随筆)
「雁釣り」(随筆)
「唯灸」(随筆)
「涙香の思出」(随筆)
「マイクロフォン」(随筆)
■水上呂理
「精神分析」
「蹠の衝動」
「犬の芸当」
「麻痺性痴呆患者の犯罪工作」
「驚き盤」
「石は語らず」
「処女作の思ひ出」(随筆)
「お問合せ」(随筆)
「燃えない焔」(随筆)
■星田三平
「せんとらる地球市建設記録」
「探偵殺害事件」
「落下傘嬢殺害事件」
「ヱル・ベチヨオ」
「米国の戦慄」
「もだん・しんごう」
「偽視界」
■米田三星
「生きてゐる皮膚」
「蜘蛛」
「告げ口心臓」
「血劇」
「児を産む死人」(随筆)
「森下雨村さんと私」(随筆)
頭からざっくりいくと、羽志主水は「監獄部屋」と「越後獅子」のみアンソロジーで既読。とにかく探偵小説としては実に珍しい、プロレタリアート的内容の「監獄部屋」の印象が強くて、ほぼそれだけのイメージしかなかったのだが、再読してもやはり「監獄部屋」強しである。探偵小説的なのはオチの部分ぐらいだが、思想を探偵小説にはめたかなり早い例だと思うし、それだけでも評価してしかるべきだろう。
水上呂理は昔からペンネームのインパクトだけで憶えていた作家。本名をもじったものらしいのだが、今では非常に誤解を招きやすい名前である(笑)。
まあ、それはさておき。実はこの四人の中では、これまで一番作品の印象が弱かったのだが、改めて読むとこんなに心理学や精神分析などを用いた作家だったのかと驚く。そっち系のネタだと木々高太郎とかぶる部分は多いわけだが、なんとデビューは木々より八年ほど早いと知り、二度ビックリ。ただ、どうしても内容的な今更感があるのは辛いところだ。
今回、もっとも気に入ったのが星田三平。SF的でもあり冒険小説的でもありハードボイルドチックな雰囲気も漂わせた「せんとらる地球市建設記録」はもともと好きだったのだが、他の作品を読むと、けっこういろいろなタイプにチャレンジしているのが素晴らしい。
なかには「米国の戦慄」なんていうトンデモ小説まであって、これはヴァン・ダインの生んだ名探偵ファイロ・ヴァンスとアメリカ裏社会を牛耳っていたアル・カポネを対決させた物語。これらの設定やニューヨークテロというテーマは派手だが、双方が持っている魅力や特徴をまったく用いず、内容もグダグダという超企画倒れの一篇である。ただ、話のタネだけのために読んでおいても損はない(笑)。
ちなみに書き溜めしてあった原稿が、戦災でほとんど焼失したらしく、まったく残念このうえない。
ラストは米田三星。意外なことに、まとめて読むと明らかに本書中の他の作家とはレベルが違う。戦前探偵小説というフィルター抜きで、普通に小説が巧いと感じられる作家なのである。文章もしっかりしているし雰囲気も十分。米田三星ならたとえ誘われたとしても、間違ってもファイロ・ヴァンスのパスティーシュなどは書かないだろう(笑)。いや、ファイロ・ヴァンスのパスティーシュも、それはそれで戦前探偵小説的ではあるのだが。
さてさて、こうやって褒めてはみたけれど、むろん今の探偵小説と比較するべきではない。同時代とはいえ、乱歩や正史はものが違うのだ。その他の作家など、決して期待するべきではないのである。
それでも「実はこんなミステリがあるんだけどね」とオススメしたい衝動にかられてしまう、そんな魅力がこの時代の作家にはあるんだよなぁ。当時の探偵小説に免疫がない人にぜひ読んでもらって、感想を聞いてみたいものだ。
昨晩の帰宅時の話。台風四号が絶好調で、通勤に使っている中央線は案の定ストップしている。仕方なく災害には滅法強いといわれる都営新宿線>京王線というルートを利用するが、これがまさかの強風ストップ。ううむ、震災のときですらイチ早く動いた京王線なのに。だが止まった駅が幸いにも明大前、そこからなぜか元気に動いている井の頭線で吉祥寺へ向かう。その頃には総武線のみちらほら動いているような状況だったが、三鷹までなら遅い電車を待つ必要もなし。ここからはちょいと高いがタクシーか、と思ったものの考えることはみな同じ。駅前のタクシーは長蛇の列である。そこで暴風のなかを駅から少し離れると、あっさりタクシーをゲット、ようやく帰宅できたのであった。まるでクエストをひとつクリアした気分である。
話は変わるが、今月は偉大な二人の幻想作家が立て続けに逝去した。言うまでもなくレイ・ブラッドベリと赤江爆のお二方である。まるで何かの符合のようでもあり、二人が仕掛けた悪い冗談のようでもある。特にブラッドベリは新刊が五月、六月と二冊も出たばかりなので、ちょっとにわかには信じがたかった。ともかく心より追悼の意を表したい。
故人を偲び、本日の読了本はブラッドベリ。ちくま文庫で出たばかりの『お菓子の髑髏 ブラッドベリ初期ミステリ短編集』である。副題にあるとおり、若き日のブラッドベリが書いた、ミステリ系の作品をまとめた短編集。時代的には40年代後半の作品が中心である。

The Small Assassin「幼い刺客」
A Careful Men Dies「用心深い男の死」
It Burns Me Up !「わが怒りの炎」
Half-Pint Homicide「悪党の処理引き受けます」
Four-Way Funeral「悪党どもは地獄へ行け」
The Long Night「長い夜」
Corpse Carnival「屍体カーニバル」
Hell's Half Hour「地獄の三十分」
The Long Way Home「はるかな家路」
Wake for the Living「生ける葬儀」
I'm Not So Dumb ! 「ぼくはそれほどばかじゃない ! 」
The Trunk Lady「トランク・レディ」
Yesterday I Lived !「銀幕の女王の死」
Dead Men Rise Up Never「死者は甦らず」
The Candy Skull「お菓子の髑髏」
収録作は以上。本書はもともと徳間文庫『悪夢のカーニバル』として出たものの改題版で、収録作はそれとまったく同じ。
まあ、出してくれるだけでも偉いとは思うが、できれば改題版なんかではなく新しく編纂したりはできなかったのだろうか。せめてボーナストラックを入れるとか。そうすれば新しいファンだけでなく従来からのファンも楽しめるのに。ちょっともったいないなぁ。
のっけからケチをつけたが、中身はブラッドベリの味が存分に発揮されたミステリ短編集である。とはいってもブラッドベリのことだから、普通のミステリなどほとんどない。幻想的なものから叙情的なもの、あるいはブラックな笑いに包まれたものまで、ブラッドベリの奇想がてんこ盛りである。
若干、そのアイディアがうまく文章に昇華されていないというか、表現や言い回しがもたついているものもあるのは惜しい。それは若書きのゆえか、あるいは翻訳のせいなのかは不明だが、全体に訳文は硬くブラッドベリにはちょっと合わないイメージもある。特に子供や若者などが主人公の「長い夜」「屍体カーニバル」「ぼくはそれほどばかじゃない ! 」などはもう少し柔らかく湿気のある文体がいいのではないかと思う次第。
個人的な好みはまず「幼い刺客」。これは昔から好きな作品で何度読んでも怖い。
他には「用心深い男の死」「屍体カーニバル」「地獄の三十分」「ぼくはそれほどばかじゃない ! 」「お菓子の髑髏」あたり。不謹慎かもしれないが、ここまで「死」を茶化し、同時に薄ら寒い何かを感じさせるセンスはブラッドベリならでは。
個人的には、この紙一重を楽しむことこそ、ブラッドベリを読む醍醐味なのである。
話は変わるが、今月は偉大な二人の幻想作家が立て続けに逝去した。言うまでもなくレイ・ブラッドベリと赤江爆のお二方である。まるで何かの符合のようでもあり、二人が仕掛けた悪い冗談のようでもある。特にブラッドベリは新刊が五月、六月と二冊も出たばかりなので、ちょっとにわかには信じがたかった。ともかく心より追悼の意を表したい。
故人を偲び、本日の読了本はブラッドベリ。ちくま文庫で出たばかりの『お菓子の髑髏 ブラッドベリ初期ミステリ短編集』である。副題にあるとおり、若き日のブラッドベリが書いた、ミステリ系の作品をまとめた短編集。時代的には40年代後半の作品が中心である。

The Small Assassin「幼い刺客」
A Careful Men Dies「用心深い男の死」
It Burns Me Up !「わが怒りの炎」
Half-Pint Homicide「悪党の処理引き受けます」
Four-Way Funeral「悪党どもは地獄へ行け」
The Long Night「長い夜」
Corpse Carnival「屍体カーニバル」
Hell's Half Hour「地獄の三十分」
The Long Way Home「はるかな家路」
Wake for the Living「生ける葬儀」
I'm Not So Dumb ! 「ぼくはそれほどばかじゃない ! 」
The Trunk Lady「トランク・レディ」
Yesterday I Lived !「銀幕の女王の死」
Dead Men Rise Up Never「死者は甦らず」
The Candy Skull「お菓子の髑髏」
収録作は以上。本書はもともと徳間文庫『悪夢のカーニバル』として出たものの改題版で、収録作はそれとまったく同じ。
まあ、出してくれるだけでも偉いとは思うが、できれば改題版なんかではなく新しく編纂したりはできなかったのだろうか。せめてボーナストラックを入れるとか。そうすれば新しいファンだけでなく従来からのファンも楽しめるのに。ちょっともったいないなぁ。
のっけからケチをつけたが、中身はブラッドベリの味が存分に発揮されたミステリ短編集である。とはいってもブラッドベリのことだから、普通のミステリなどほとんどない。幻想的なものから叙情的なもの、あるいはブラックな笑いに包まれたものまで、ブラッドベリの奇想がてんこ盛りである。
若干、そのアイディアがうまく文章に昇華されていないというか、表現や言い回しがもたついているものもあるのは惜しい。それは若書きのゆえか、あるいは翻訳のせいなのかは不明だが、全体に訳文は硬くブラッドベリにはちょっと合わないイメージもある。特に子供や若者などが主人公の「長い夜」「屍体カーニバル」「ぼくはそれほどばかじゃない ! 」などはもう少し柔らかく湿気のある文体がいいのではないかと思う次第。
個人的な好みはまず「幼い刺客」。これは昔から好きな作品で何度読んでも怖い。
他には「用心深い男の死」「屍体カーニバル」「地獄の三十分」「ぼくはそれほどばかじゃない ! 」「お菓子の髑髏」あたり。不謹慎かもしれないが、ここまで「死」を茶化し、同時に薄ら寒い何かを感じさせるセンスはブラッドベリならでは。
個人的には、この紙一重を楽しむことこそ、ブラッドベリを読む醍醐味なのである。
ううむ、ほんとに最近は夜に弱くなってしまった。寝る前の読書もそうだが、午前様まで飲んでいると、いっそうそれを痛感する。それほど飲んだわけではないのに、結局、本日の午前はつぶれて使いものにならず。昼に武蔵野うどんを食いにでかけ、ようやく復活する。
ようやくといえばスティーグ・ラーソン『ミレニアム1ドラゴン・タトゥーの女(下)』もやっと読了。
上巻では少々まどろこしかった展開も後半に入って徐々に動き出す。事件の糸口が掴め、少しずつ見えてくる事件の様相。そしてその過程において、二人の主人公、ミカエルとリスベットがついに出会うことになる。そこから先はまさに怒濤の急展開。驚愕の真相が明らかになり、さらにはミカエルとリスベットがそれぞれ抱える問題にも、ひとつの決着がつけられようとする。

うむ、面白い。エンターテインメントとして十分に魅力的だ。当時の年末ベストテンを賑わせたのも当然と思わせる作品である。
ただ、同じベストテンにランクインするような他の作品と比べ、圧倒的に差があるわけではない。むしろ気になる部分もいろいろと感じられ、世界的ベストセラーとなった理由までは正直わからん(苦笑)。
まあ思いつくままにポイントを挙げてみよう。
まずミステリとしての趣向をいろいろ盛り込んでいるところは、やはり評価されていい。
嵐の山荘パターン、見立て殺人、暗号など、ミステリ好きを惹きつける手として効果的なのはもちろんだが、これは事件を様々な角度から考えさせることになるし、ストーリー的な伏線としても巧いやり方をとっている。ただ、ひとつひとつがそれほど凝ったネタとはいえず、アッと驚くほどのトリックがないのは残念。
ミステリという部分では、むしろ一枚の写真をベースにしてそこから想像と推理を広げ、次々と手がかりを連鎖させてゆく展開に感心した。この辺りはさすがジャーナリストの面目躍如といったところか、手がかりをひとつひとつ検証しつつ駒を進めるといった趣で、知的スリルもあり、非常にワクワクさせてくれる。
そのくせハッキングでストーリーに関わる重要なネタを入手したりというのは、あまりに都合主義的でいただけない。これはミステリ要素だけでなく、小説の要素としてもかなり痛い部分だ。これがジェフリー・ディーヴァー辺りであればハッキングで得た情報をさらにひねったりするところだが、残念ながらそれはない。
リスベットというスーパーウーマンのキャラクターは非常に魅力的なのだが、あまりに特殊能力を与えすぎたのは著者の失敗だろう。これによってストーリーが安易に流れすぎている個所は意外に多い。
ミステリから離れたところでは、やはりスウェーデンが抱える社会問題を告発している部分は見逃せない。巧いなと思ったのは、経済や報道の在り方といったソーシャルな問題はミカエル、差別や薬物問題といった個人の抱える問題はリスベット、メインの事件ではまた別のテーマというように切り分け、主要な登場人物とリンクさせてテーマを掘り下げていく部分。
ただし、狙いはいいが、それほどこなれていないのが惜しい。それぞれのテーマにまつわる展開が独立しすぎており、非常にちぐはぐな印象を与えるのである。テーマ自体は上巻でけっこうしっかりと書き込まれている。それがストーリーが進むにつれ融合していくのが理想なのだが、結局のところミカエルはミカエル、リスベットはリスベットでそれぞれの問題を追求するにとどまり、互いに干渉することはない。この平行線は最後まで続くのだが、もともとそういう狙いなのか、それとも盛り込んだはいいが、まとめきれなかっただけなのか。
それが最もストーリーに悪影響を与えているのが、いわゆる後日談的ストーリー。事件が一応の解決をみたあとが長すぎるのである。余韻を味わう暇もあらばこそ、ミカエルとリスベットそれぞれのテーマに通じる内容がけっこうな分量で入ってしまい、本来の事件の意味合いが薄れてしまうのである。しかもストーリーをメールのやりとりで見せるなど、あまり意味のない演出がわずらわしい。
ううむ、なんだかケチの方が多くなってしまったが、最初に書いたようにトータルでは十分面白いので念のため。真相は驚くべきものだし、基本的なストーリー展開も面白い。キャラクター設定もテーマも悪くない。スウェーデンという馴染みの少ない国についての実情も知ることができるなど、情報小説としての価値もある。読み物としては十分な出来なのである。
ただ、それらの評価も、ミステリというよりは、やはりエンターテインメントとしてのものだという気はする。
近いうちに2も読み始める予定だが、こちらは1以上に評価が高いそうなので一応は期待しておこう。
ようやくといえばスティーグ・ラーソン『ミレニアム1ドラゴン・タトゥーの女(下)』もやっと読了。
上巻では少々まどろこしかった展開も後半に入って徐々に動き出す。事件の糸口が掴め、少しずつ見えてくる事件の様相。そしてその過程において、二人の主人公、ミカエルとリスベットがついに出会うことになる。そこから先はまさに怒濤の急展開。驚愕の真相が明らかになり、さらにはミカエルとリスベットがそれぞれ抱える問題にも、ひとつの決着がつけられようとする。

うむ、面白い。エンターテインメントとして十分に魅力的だ。当時の年末ベストテンを賑わせたのも当然と思わせる作品である。
ただ、同じベストテンにランクインするような他の作品と比べ、圧倒的に差があるわけではない。むしろ気になる部分もいろいろと感じられ、世界的ベストセラーとなった理由までは正直わからん(苦笑)。
まあ思いつくままにポイントを挙げてみよう。
まずミステリとしての趣向をいろいろ盛り込んでいるところは、やはり評価されていい。
嵐の山荘パターン、見立て殺人、暗号など、ミステリ好きを惹きつける手として効果的なのはもちろんだが、これは事件を様々な角度から考えさせることになるし、ストーリー的な伏線としても巧いやり方をとっている。ただ、ひとつひとつがそれほど凝ったネタとはいえず、アッと驚くほどのトリックがないのは残念。
ミステリという部分では、むしろ一枚の写真をベースにしてそこから想像と推理を広げ、次々と手がかりを連鎖させてゆく展開に感心した。この辺りはさすがジャーナリストの面目躍如といったところか、手がかりをひとつひとつ検証しつつ駒を進めるといった趣で、知的スリルもあり、非常にワクワクさせてくれる。
そのくせハッキングでストーリーに関わる重要なネタを入手したりというのは、あまりに都合主義的でいただけない。これはミステリ要素だけでなく、小説の要素としてもかなり痛い部分だ。これがジェフリー・ディーヴァー辺りであればハッキングで得た情報をさらにひねったりするところだが、残念ながらそれはない。
リスベットというスーパーウーマンのキャラクターは非常に魅力的なのだが、あまりに特殊能力を与えすぎたのは著者の失敗だろう。これによってストーリーが安易に流れすぎている個所は意外に多い。
ミステリから離れたところでは、やはりスウェーデンが抱える社会問題を告発している部分は見逃せない。巧いなと思ったのは、経済や報道の在り方といったソーシャルな問題はミカエル、差別や薬物問題といった個人の抱える問題はリスベット、メインの事件ではまた別のテーマというように切り分け、主要な登場人物とリンクさせてテーマを掘り下げていく部分。
ただし、狙いはいいが、それほどこなれていないのが惜しい。それぞれのテーマにまつわる展開が独立しすぎており、非常にちぐはぐな印象を与えるのである。テーマ自体は上巻でけっこうしっかりと書き込まれている。それがストーリーが進むにつれ融合していくのが理想なのだが、結局のところミカエルはミカエル、リスベットはリスベットでそれぞれの問題を追求するにとどまり、互いに干渉することはない。この平行線は最後まで続くのだが、もともとそういう狙いなのか、それとも盛り込んだはいいが、まとめきれなかっただけなのか。
それが最もストーリーに悪影響を与えているのが、いわゆる後日談的ストーリー。事件が一応の解決をみたあとが長すぎるのである。余韻を味わう暇もあらばこそ、ミカエルとリスベットそれぞれのテーマに通じる内容がけっこうな分量で入ってしまい、本来の事件の意味合いが薄れてしまうのである。しかもストーリーをメールのやりとりで見せるなど、あまり意味のない演出がわずらわしい。
ううむ、なんだかケチの方が多くなってしまったが、最初に書いたようにトータルでは十分面白いので念のため。真相は驚くべきものだし、基本的なストーリー展開も面白い。キャラクター設定もテーマも悪くない。スウェーデンという馴染みの少ない国についての実情も知ることができるなど、情報小説としての価値もある。読み物としては十分な出来なのである。
ただ、それらの評価も、ミステリというよりは、やはりエンターテインメントとしてのものだという気はする。
近いうちに2も読み始める予定だが、こちらは1以上に評価が高いそうなので一応は期待しておこう。
ラーソンの続きは置いといて、この週末に観たDVDの感想をば。ものは東宝特撮映画DVDコレクションの最終巻にあたる『大冒険』。
まずは先入観抜きで、下のストーリーを読んでもらいたい。
世界の主要都市で次々と発生する偽札事件。このままでは経済的な大混乱は必至。国際的組織の暗躍が囁かれるなか、警視庁は極秘裏に捜査を開始した。
ところかわって都内の安アパート。元体操選手という華々しい経歴をもちつつも、今ではしがない雑誌記者の植松という男がいた。彼は隣のアパートに住むアマチュア発明家とともに、複写機の特許で一稼ぎする計画を練っていた。ところがそのテスト中に偽札を発見し、植松はそれを記事にしてたちまちトップ賞を手に入れる。
だが、そんな植松を警察は偽札犯と断定し、植松の逮捕に向かう。一方、偽札組織も植松が重大な秘密を知っているとばかり、その命を狙いだす。果たしてこの三つ巴のチェイスの行方は……?

古澤憲吾監督による1965年公開のこの『大冒険』。上のストーリーではまるでサスペンスものであり、確かに特撮もふんだんに使われてはいるのだが、実はこのシリーズに入れていいのかどうか微妙なところではある。
なんせ本作はクレージーキャッツ結成10周年記念映画。主役に植木等を据えたコメディ作品だからだ。
とはいえ中身の方が、当時人気のあった007をパロったスパイコメディとあれば、特撮の必然性もそれなりにあるのかもしれない(笑)。植木等らクレイジーキャッツの面々が体を張ってアクションに挑むというのも、それはそれで魅力的。しかも、お笑い要素をとりのぞくと、意外にちゃんとした巻き込まれ型スリラーになっているのはさすがである。かてて加えて、実は●●ものだなんてオチまでつき、これはなかなかツボを突いているんじゃなかろうか。
ところどころ間の繋ぎが悪くて、テンポを削ぐところがあるのは残念だが、「え?」というようなアクションシーンも多くて、意外にスケールの大きい作品である。今でもひまつぶしには十分耐えられる面白さで、特撮云々はこのさい忘れて観るのが吉かと。
まずは先入観抜きで、下のストーリーを読んでもらいたい。
世界の主要都市で次々と発生する偽札事件。このままでは経済的な大混乱は必至。国際的組織の暗躍が囁かれるなか、警視庁は極秘裏に捜査を開始した。
ところかわって都内の安アパート。元体操選手という華々しい経歴をもちつつも、今ではしがない雑誌記者の植松という男がいた。彼は隣のアパートに住むアマチュア発明家とともに、複写機の特許で一稼ぎする計画を練っていた。ところがそのテスト中に偽札を発見し、植松はそれを記事にしてたちまちトップ賞を手に入れる。
だが、そんな植松を警察は偽札犯と断定し、植松の逮捕に向かう。一方、偽札組織も植松が重大な秘密を知っているとばかり、その命を狙いだす。果たしてこの三つ巴のチェイスの行方は……?

古澤憲吾監督による1965年公開のこの『大冒険』。上のストーリーではまるでサスペンスものであり、確かに特撮もふんだんに使われてはいるのだが、実はこのシリーズに入れていいのかどうか微妙なところではある。
なんせ本作はクレージーキャッツ結成10周年記念映画。主役に植木等を据えたコメディ作品だからだ。
とはいえ中身の方が、当時人気のあった007をパロったスパイコメディとあれば、特撮の必然性もそれなりにあるのかもしれない(笑)。植木等らクレイジーキャッツの面々が体を張ってアクションに挑むというのも、それはそれで魅力的。しかも、お笑い要素をとりのぞくと、意外にちゃんとした巻き込まれ型スリラーになっているのはさすがである。かてて加えて、実は●●ものだなんてオチまでつき、これはなかなかツボを突いているんじゃなかろうか。
ところどころ間の繋ぎが悪くて、テンポを削ぐところがあるのは残念だが、「え?」というようなアクションシーンも多くて、意外にスケールの大きい作品である。今でもひまつぶしには十分耐えられる面白さで、特撮云々はこのさい忘れて観るのが吉かと。
遅まきながらスティーグ・ラーソンの『ミレニアム1ドラゴンタトゥーの女』にとりかかる。
いうまでもなく、最近はやりの北欧ミステリの火付け役。古いところではペール・ヴァール&マイ・シューヴァル、最近ではヘニング・マンケルとか、これまでも大きく評価された北欧のミステリ作家はそれなりにいたのだが、スティーグ・ラーソンがここまでブレイクし、他の北欧作家の紹介にまで大きく影響するとは誰も予想できなかったのではないだろうか。
もともと版元の仕掛けはけっこう強気だったけれど、映画化、文庫化、映画のリメイク、DVD化と話題が途切れなかったのも大きい。なわけで、ここにきて、ようやく管理人も読んでおこうかという気になった次第である。
雑誌「ミレニアム」の発行責任者であり有名ジャーナリストでもあるミカエル。彼は大物実業家ヴェンネルストレムの不正行為を暴露する記事を発表したが、名誉毀損で訴えられ、有罪判決を宣告される。
「ミレニアム」を離れる決意をしたミカエルだが、そんな彼を密かに調査する者たちがいた。大企業グループの前会長ヘンリック・ヴァンゲルである。ヘンリックは弁護士フルーデを通じ、ある警備会社にミカエルの身辺調査を依頼し、リスベットという女性調査員がその任にあたった。
ミカエルが信頼に足る人物だと確信したヘンリックは、さっそくミカエルを呼び出し、ある仕事を依頼した。内容は二つ。表向きの依頼は自伝の執筆協力、そして真の依頼は、四十年前に姿を消した孫娘ハリエットの失踪事件の調査であった……。

上巻まで読んだところでは、ほとんど動きらしい動きはなし。ミカエルがハリエット失踪事件の謎にとりかかってはいるが、まだ大きな糸口は掴めず。エピソードを重ねつつ、主要な登場人物の人となりを紹介するといった趣きである。やや詳細に過ぎるのではというまどろっこしさも感じないではないが、語り口は悪くなく、基本的に人物造形などはうまい。
特に気になる人物としては、まずミカエル。著者自身がジャーナリストだったこともあって、ミカエルを著者の分身というふうにとらえるのは容易いが、むしろ著者の考えるジャーナリストの理想像と見てもいいかもしれない。
もちろんリスベットは言うに及ばず。北欧社会の抱える問題を一心に受けもつ存在であり、彼女がどういうふうに事件に関わり活躍するのか興味津々である。その他ではセシリアというヘンリックの姪が面白い存在か。
とりあえず本日はここまで。続きは下巻読了時に。
いうまでもなく、最近はやりの北欧ミステリの火付け役。古いところではペール・ヴァール&マイ・シューヴァル、最近ではヘニング・マンケルとか、これまでも大きく評価された北欧のミステリ作家はそれなりにいたのだが、スティーグ・ラーソンがここまでブレイクし、他の北欧作家の紹介にまで大きく影響するとは誰も予想できなかったのではないだろうか。
もともと版元の仕掛けはけっこう強気だったけれど、映画化、文庫化、映画のリメイク、DVD化と話題が途切れなかったのも大きい。なわけで、ここにきて、ようやく管理人も読んでおこうかという気になった次第である。
雑誌「ミレニアム」の発行責任者であり有名ジャーナリストでもあるミカエル。彼は大物実業家ヴェンネルストレムの不正行為を暴露する記事を発表したが、名誉毀損で訴えられ、有罪判決を宣告される。
「ミレニアム」を離れる決意をしたミカエルだが、そんな彼を密かに調査する者たちがいた。大企業グループの前会長ヘンリック・ヴァンゲルである。ヘンリックは弁護士フルーデを通じ、ある警備会社にミカエルの身辺調査を依頼し、リスベットという女性調査員がその任にあたった。
ミカエルが信頼に足る人物だと確信したヘンリックは、さっそくミカエルを呼び出し、ある仕事を依頼した。内容は二つ。表向きの依頼は自伝の執筆協力、そして真の依頼は、四十年前に姿を消した孫娘ハリエットの失踪事件の調査であった……。

上巻まで読んだところでは、ほとんど動きらしい動きはなし。ミカエルがハリエット失踪事件の謎にとりかかってはいるが、まだ大きな糸口は掴めず。エピソードを重ねつつ、主要な登場人物の人となりを紹介するといった趣きである。やや詳細に過ぎるのではというまどろっこしさも感じないではないが、語り口は悪くなく、基本的に人物造形などはうまい。
特に気になる人物としては、まずミカエル。著者自身がジャーナリストだったこともあって、ミカエルを著者の分身というふうにとらえるのは容易いが、むしろ著者の考えるジャーナリストの理想像と見てもいいかもしれない。
もちろんリスベットは言うに及ばず。北欧社会の抱える問題を一心に受けもつ存在であり、彼女がどういうふうに事件に関わり活躍するのか興味津々である。その他ではセシリアというヘンリックの姪が面白い存在か。
とりあえず本日はここまで。続きは下巻読了時に。
今週は仕事がハードでろくに本も読めず、っていうか平均睡眠時間がちょっとやばい。
せめて心に少しでも潤いを、と思って今週は久々に本をたくさん買った。
ただ、購入書のラインナップをよく見ると、岡本綺堂、橫溝正史、大下宇陀児、久生十蘭、中町信といったあたりで、これらが全部新刊で買えたところが驚異。こういう古いものばかりで自分大丈夫かとも思ったが、なあに、新しいものはディーヴァー『追撃の森』、マーク・アレン・スミス『尋問請負人』といった海外勢も押さえているから、それなりにバランスはとれているのだ。って誰に説明しているのか俺は。
まあ買うばかりではあれなので、水曜日だったかに昼休みを利用して、〈杉本一文原画展〉をのぞいてきた(会社が神保町にある幸せ!)。もうネットのあちらこちらで記事があがっているので今更感満載なのだが、自分用の記録として記しておく。
ところで杉本一文といえば、もちろん角川橫溝のカバー絵でおなじみの、あの杉本一文氏である。今では文字を大きく載せただけのつまんない角川横溝のカバーだが、一昔前までは角川書店の橫溝正史といえば、すべて杉本一文の絵で統一されていた。
おどろおどろしく、それでいて妖しい美しさも備える杉本一文氏の絵にはファンも多いときく。もちろん管理人もその一人である。橫溝正史ブームに角川映画の貢献があったことは異論もないだろうが、当時、このカバー絵に魅了されて本を手にとった人も多かったのではないだろうか。
さて、〈杉本一文原画展〉である。今年は〈橫溝正史生誕百十周年記念〉ということで、角川書店が復刻カバーフェアを実施したのがそもそものようだ(フェアのページはこちら)。それと先頃リニューアルなった東京堂書店のオープニング企画という意味合いもあるみたいで、どちらサイドが持ちかけたかは知らぬが、まあ、こういう素敵なコラボ企画ならどんどんやってもらいたい。この辺、詳しいことはまったくわからないのだけれど、近隣の三省堂や書泉といった大書店でも復刻カバーがまったく見当たらなかったので、東京堂書店がいろいろと仕掛けているのかなぁと邪推中。いや、褒めてるんですよ、これは。
▼ちなみに下は東京堂書店でただで配っている記念ポストカード。

会場はホールといってもこじんまりしたもので、平日の昼間と言うこともあって、一人で貸し切り状態。ゆっくりできるはずが、いかんせん仕事中の昼休みゆえ結局は駆け足で見て回る。原画はほとんどがA4ぐらいで思ったより小さかったが、『犬神家に一族』など、一部の作品だけはかなりのサイズで描かれていたものもあった。これはおそらく映画化された作品のポスター制作のために描き直したものだろう。
しかし、当たり前のことだが原画はいい。文庫ではサイズも小さくなるし、印刷によって見えなくなる部分もあるんだよね。原画ではそういったスケール変更や印刷技術による誤差がないので、実はすごく立体的なことがわかるのである。ぺたっとした印象がなくなるというか。そういうのを原画で確認できたのがすごい収穫である。
ちなみに角川横溝は、管理人も十何年ほど前に一念発起してコンプリートし、すべて読了している。あの頃にブログやってりゃ感想をきちんと残せたのになぁとちょっと悔やまれるところである。
あ、それと今回の復刻カバーだが、復刻といいながら実はオリジナルも二点混じっている。『首』と『人面瘡』の二作がそれ。といっても中身そのものは改題や短編の再編集なので新しいものはないはず(?)だし、過去に小さいサイズでカバーに使われたことはあったからコンプリート済みであればまったく買う必要はない。まったくない。ないのだけれど、今回はフルサイズで過去作品とデザインを踏襲しており、よりコンプリート熱を煽る仕組みとなっている(笑)。まあ、しょうがないから買ったけどな。
なお、会期は6月1日(金)から6月10日(日)、要するに明日までである。最後のチャンスですぜ、だんな。
せめて心に少しでも潤いを、と思って今週は久々に本をたくさん買った。
ただ、購入書のラインナップをよく見ると、岡本綺堂、橫溝正史、大下宇陀児、久生十蘭、中町信といったあたりで、これらが全部新刊で買えたところが驚異。こういう古いものばかりで自分大丈夫かとも思ったが、なあに、新しいものはディーヴァー『追撃の森』、マーク・アレン・スミス『尋問請負人』といった海外勢も押さえているから、それなりにバランスはとれているのだ。って誰に説明しているのか俺は。
まあ買うばかりではあれなので、水曜日だったかに昼休みを利用して、〈杉本一文原画展〉をのぞいてきた(会社が神保町にある幸せ!)。もうネットのあちらこちらで記事があがっているので今更感満載なのだが、自分用の記録として記しておく。
ところで杉本一文といえば、もちろん角川橫溝のカバー絵でおなじみの、あの杉本一文氏である。今では文字を大きく載せただけのつまんない角川横溝のカバーだが、一昔前までは角川書店の橫溝正史といえば、すべて杉本一文の絵で統一されていた。
おどろおどろしく、それでいて妖しい美しさも備える杉本一文氏の絵にはファンも多いときく。もちろん管理人もその一人である。橫溝正史ブームに角川映画の貢献があったことは異論もないだろうが、当時、このカバー絵に魅了されて本を手にとった人も多かったのではないだろうか。
さて、〈杉本一文原画展〉である。今年は〈橫溝正史生誕百十周年記念〉ということで、角川書店が復刻カバーフェアを実施したのがそもそものようだ(フェアのページはこちら)。それと先頃リニューアルなった東京堂書店のオープニング企画という意味合いもあるみたいで、どちらサイドが持ちかけたかは知らぬが、まあ、こういう素敵なコラボ企画ならどんどんやってもらいたい。この辺、詳しいことはまったくわからないのだけれど、近隣の三省堂や書泉といった大書店でも復刻カバーがまったく見当たらなかったので、東京堂書店がいろいろと仕掛けているのかなぁと邪推中。いや、褒めてるんですよ、これは。
▼ちなみに下は東京堂書店でただで配っている記念ポストカード。

会場はホールといってもこじんまりしたもので、平日の昼間と言うこともあって、一人で貸し切り状態。ゆっくりできるはずが、いかんせん仕事中の昼休みゆえ結局は駆け足で見て回る。原画はほとんどがA4ぐらいで思ったより小さかったが、『犬神家に一族』など、一部の作品だけはかなりのサイズで描かれていたものもあった。これはおそらく映画化された作品のポスター制作のために描き直したものだろう。
しかし、当たり前のことだが原画はいい。文庫ではサイズも小さくなるし、印刷によって見えなくなる部分もあるんだよね。原画ではそういったスケール変更や印刷技術による誤差がないので、実はすごく立体的なことがわかるのである。ぺたっとした印象がなくなるというか。そういうのを原画で確認できたのがすごい収穫である。
ちなみに角川横溝は、管理人も十何年ほど前に一念発起してコンプリートし、すべて読了している。あの頃にブログやってりゃ感想をきちんと残せたのになぁとちょっと悔やまれるところである。
あ、それと今回の復刻カバーだが、復刻といいながら実はオリジナルも二点混じっている。『首』と『人面瘡』の二作がそれ。といっても中身そのものは改題や短編の再編集なので新しいものはないはず(?)だし、過去に小さいサイズでカバーに使われたことはあったからコンプリート済みであればまったく買う必要はない。まったくない。ないのだけれど、今回はフルサイズで過去作品とデザインを踏襲しており、よりコンプリート熱を煽る仕組みとなっている(笑)。まあ、しょうがないから買ったけどな。
なお、会期は6月1日(金)から6月10日(日)、要するに明日までである。最後のチャンスですぜ、だんな。
Posted
on
米田興弘『モスラ3 キングギドラ来襲』
仕事がけっこう慌ただしく、読書が進まないうえに体力も下降気味。本日は久々にゆっくり完全休養することにして、午後からビールを飲みつつダラダラDVDを観たり、パラパラ本を読んだり。読書は二冊同時進行中で、どちらもボリュームがあるので遅々として進まず。決してつまんないわけではなく、どちらも楽しんでおりますゆえ、感想は後日。
さて、本日はDVDの感想など。ものは平成モスラ・シリーズの掉尾を飾る第三弾『モスラ3 キングギドラ来襲』。監督は米田興弘、公開は1998年。
キングギドラの来襲を、あの有名な「ノストラダムスの大予言」の“空から大王が降ってくる”というフレーズになぞらえる導入部は、1998年という時代ならでは。まあ、それが本編に活かされているわけではなくて、あくまで導入部だけの話だが(笑)。

まあ、そんな導入で地球に現れたキングギドラだが、これまでの設定とはずいぶん様相が異なっている。なんと地球で生態系の上位にくる生物を捕食し、地球を滅ぼそうとするのである。一億二千年前の恐竜絶滅もキングギドラの仕業というからいやはやなんとも。
で、現代の地球では当然ターゲットが人間であり、キングギドラは子供を掠っては、富士の樹海に作り出したドームに閉じ込めてしまう。子供たちを一気に食らうことでより自らのエネルギーを高められるのだという。そんな危機的状況にインファント島のフェアリー、エリアス姉妹はモスラを呼び出して戦わせる。しかし、いかんせん相手が悪い。相手は宇宙最強の呼び声高いキングギドラだ。モスラは戦いに敗れるばかりか、エリアス姉妹の一人、ロラもキングギドラにマインドコントロールされる事態となる。キングギドラどんだけスキル高いのか(笑)。
ところ変わって主人公の少年がいる。この少年が登校拒否児童という、これまた時代を反映した設定だが、彼は登校拒否をしていたおかげでキングギドラに掠われずにすむ。そしてエリアス姉妹のかたわれモル、そしてキングギドラに敗れたモスラと出会うわけである。
ここから物語は急展開。このままでは強大なキングギドラに勝てないため、モスラは恐竜を滅ぼした時代、一億二千年前へ飛び、幼体のキングギドラと戦うというのだ。しかし、過去へ飛べば現代へ戻る手段はない。それでもモスラはゆく。しかもモルはモスラを過去へ送ることでエネルギーを使い果たし命を落とす。いまわの際、モルはロラのマインドコントロールを解くよう少年に依頼する。「僕は学校にも行くことができないのに……」尻込みする少年。だがモルは、登校拒否が少年のもつ美しく繊細な心ゆえのことであると諭し、息を引き取る。少年は子供たちが閉じ込められたドームへ向かい、モスラは過去で幼体キングギドラと激突する。その結末やいかに。
実はここから、さらに物語は二転三転。個人的にはストーリーは(破綻が大きいけれど)決して嫌いではない。しかし、何というかなぁ。制作者たちのやりたいことはヒシヒシと伝わってくるのだが、なんでそれがちゃんと映像になって表れてこないのか。
例えば本作のテーマは、平成モスラシリーズならではの家族愛、絆である。これについては人間ドラマもさることながら、平成モスラシリーズのカギを握る存在として描かれてきたエリアス三姉妹によってより強調されている。前作でエリアス姉妹が二人ではなく、悪役ベルバラもまた姉妹であることが明らかになったわけだが、本作ではそれぞれ個性の異なる彼女たちが心をひとつにすることで、より大きな力を得ることになる。
それはいいのだけれど、主人公の少年のドラマがそれなりに重くなければならないのに、これが実にアッサリとしか描かれない。小学生の登校拒否ですよ登校拒否。それなりの事情が当然あるはずなのに、一切を説明抜きで家族もそんなに心配してないし、子供も苦悩を抱えているようにはまったく見えない。もちろんわざわざ生臭い話にする必要はないけれど、蓋をしすぎるのも考えものだ。子供向けに作っておきながら、結局は子供をなめている。子供の側に踏み込んでいく姿勢が皆無で、歯がゆくて仕方がない。
特撮も中途半端。最もひどいのは恐竜の時代である。本作の五年前にあの『ジュラシックパーク』があるというのに、このちゃちさは何なんだ。誇張でも何でもなくソフビの人形レベルで、ちょっとこれは噴飯もの。キングギドラやモスラで予算を使い果たして恐竜まではフォローできなかったというのか。こんなものしか出来ないなら、最初から恐竜時代などやってくれるなと言いたい。
あと、これは平成モスラ全般にいえるのだが、飛行シーンの不自然さが一向に改善される気配がないのもなんだかなぁ。制作側も自然に見えないのはわかっていると思うのだが、こういうところをきちんと見せるだけでも、ずいぶん印象は変わってくるのにねぇ。
日本の特撮映画というのは本当に不思議な存在である。制作者たちの志、技術、お家の事情などが時代によってアンバランスに入り混じり、その結果、摩訶不思議なものが出来上がる。東宝に限っていえば『ゴジラ』の呪縛といってもいいかもしれない。
これからもファンを歓喜させ悶絶させていく作品ができあがるのだろうが、まあ、こちらもそれを承知で見続けるしかないんだろうなぁ。
さて、本日はDVDの感想など。ものは平成モスラ・シリーズの掉尾を飾る第三弾『モスラ3 キングギドラ来襲』。監督は米田興弘、公開は1998年。
キングギドラの来襲を、あの有名な「ノストラダムスの大予言」の“空から大王が降ってくる”というフレーズになぞらえる導入部は、1998年という時代ならでは。まあ、それが本編に活かされているわけではなくて、あくまで導入部だけの話だが(笑)。

まあ、そんな導入で地球に現れたキングギドラだが、これまでの設定とはずいぶん様相が異なっている。なんと地球で生態系の上位にくる生物を捕食し、地球を滅ぼそうとするのである。一億二千年前の恐竜絶滅もキングギドラの仕業というからいやはやなんとも。
で、現代の地球では当然ターゲットが人間であり、キングギドラは子供を掠っては、富士の樹海に作り出したドームに閉じ込めてしまう。子供たちを一気に食らうことでより自らのエネルギーを高められるのだという。そんな危機的状況にインファント島のフェアリー、エリアス姉妹はモスラを呼び出して戦わせる。しかし、いかんせん相手が悪い。相手は宇宙最強の呼び声高いキングギドラだ。モスラは戦いに敗れるばかりか、エリアス姉妹の一人、ロラもキングギドラにマインドコントロールされる事態となる。キングギドラどんだけスキル高いのか(笑)。
ところ変わって主人公の少年がいる。この少年が登校拒否児童という、これまた時代を反映した設定だが、彼は登校拒否をしていたおかげでキングギドラに掠われずにすむ。そしてエリアス姉妹のかたわれモル、そしてキングギドラに敗れたモスラと出会うわけである。
ここから物語は急展開。このままでは強大なキングギドラに勝てないため、モスラは恐竜を滅ぼした時代、一億二千年前へ飛び、幼体のキングギドラと戦うというのだ。しかし、過去へ飛べば現代へ戻る手段はない。それでもモスラはゆく。しかもモルはモスラを過去へ送ることでエネルギーを使い果たし命を落とす。いまわの際、モルはロラのマインドコントロールを解くよう少年に依頼する。「僕は学校にも行くことができないのに……」尻込みする少年。だがモルは、登校拒否が少年のもつ美しく繊細な心ゆえのことであると諭し、息を引き取る。少年は子供たちが閉じ込められたドームへ向かい、モスラは過去で幼体キングギドラと激突する。その結末やいかに。
実はここから、さらに物語は二転三転。個人的にはストーリーは(破綻が大きいけれど)決して嫌いではない。しかし、何というかなぁ。制作者たちのやりたいことはヒシヒシと伝わってくるのだが、なんでそれがちゃんと映像になって表れてこないのか。
例えば本作のテーマは、平成モスラシリーズならではの家族愛、絆である。これについては人間ドラマもさることながら、平成モスラシリーズのカギを握る存在として描かれてきたエリアス三姉妹によってより強調されている。前作でエリアス姉妹が二人ではなく、悪役ベルバラもまた姉妹であることが明らかになったわけだが、本作ではそれぞれ個性の異なる彼女たちが心をひとつにすることで、より大きな力を得ることになる。
それはいいのだけれど、主人公の少年のドラマがそれなりに重くなければならないのに、これが実にアッサリとしか描かれない。小学生の登校拒否ですよ登校拒否。それなりの事情が当然あるはずなのに、一切を説明抜きで家族もそんなに心配してないし、子供も苦悩を抱えているようにはまったく見えない。もちろんわざわざ生臭い話にする必要はないけれど、蓋をしすぎるのも考えものだ。子供向けに作っておきながら、結局は子供をなめている。子供の側に踏み込んでいく姿勢が皆無で、歯がゆくて仕方がない。
特撮も中途半端。最もひどいのは恐竜の時代である。本作の五年前にあの『ジュラシックパーク』があるというのに、このちゃちさは何なんだ。誇張でも何でもなくソフビの人形レベルで、ちょっとこれは噴飯もの。キングギドラやモスラで予算を使い果たして恐竜まではフォローできなかったというのか。こんなものしか出来ないなら、最初から恐竜時代などやってくれるなと言いたい。
あと、これは平成モスラ全般にいえるのだが、飛行シーンの不自然さが一向に改善される気配がないのもなんだかなぁ。制作側も自然に見えないのはわかっていると思うのだが、こういうところをきちんと見せるだけでも、ずいぶん印象は変わってくるのにねぇ。
日本の特撮映画というのは本当に不思議な存在である。制作者たちの志、技術、お家の事情などが時代によってアンバランスに入り混じり、その結果、摩訶不思議なものが出来上がる。東宝に限っていえば『ゴジラ』の呪縛といってもいいかもしれない。
これからもファンを歓喜させ悶絶させていく作品ができあがるのだろうが、まあ、こちらもそれを承知で見続けるしかないんだろうなぁ。


