Posted in 01 2008
Posted
on
『刑事コロンボ/アリバイのダイヤル』
『刑事コロンボ/アリバイのダイヤル』を見る。タイトルにもあるように電話を使ったアリバイものである(といっても原題は『The Most Crucial Game』だが)。
電話が盗聴されていることを知った犯人は、アリバイ作りのため、逆にそれを利用することを思いつく。電話中にラジオの中継を鳴らし、競技場の一室にいるかのように装うのだ。コロンボはそれが擬装であると考えたが、どう耳を凝らして聞いても録音には他の場所を示すような音は入っていない。コロンボが最後に行きついたのは……というお話。
デヴィッド・ローンの書いた『音のてがかり』の主人公ハーレックなら、あっという間に解決したかもしれない(笑)。まあそれは冗談としても、カギとなるトリックはともかく、全体に説明が粗っぽく、ちょっとストーリーを追いかけるのにしんどい。最後の証拠もそれほど強いものではなく、あれで諦める犯人もちょっとなぁ。
シリーズ中ではかなり落ちる方か。
電話が盗聴されていることを知った犯人は、アリバイ作りのため、逆にそれを利用することを思いつく。電話中にラジオの中継を鳴らし、競技場の一室にいるかのように装うのだ。コロンボはそれが擬装であると考えたが、どう耳を凝らして聞いても録音には他の場所を示すような音は入っていない。コロンボが最後に行きついたのは……というお話。
デヴィッド・ローンの書いた『音のてがかり』の主人公ハーレックなら、あっという間に解決したかもしれない(笑)。まあそれは冗談としても、カギとなるトリックはともかく、全体に説明が粗っぽく、ちょっとストーリーを追いかけるのにしんどい。最後の証拠もそれほど強いものではなく、あれで諦める犯人もちょっとなぁ。
シリーズ中ではかなり落ちる方か。
日曜にやや復調したと思ったのだが、月曜にぶり返しがきたようで、っていうかむしろ月曜からが本番だったのか。ついに吐き気と下痢でダウン。病院へ行くとウイルス性の腸炎とのこと(ノロウイルスではなさそう)。昨日今日と会社を休んで自宅静養。トイレがお友達なのでほぼ引きこもってはいるものの、ときどきメールをチェックして会社の用事をいくつか片付けたり、DVDをぼちぼち観たり。
で、簡単に観たDVDの感想など。ものは『間宮兄弟』。
江國香織の原作は読んでないのであくまで映画の感想になるが、まあ面白いところに目をつけたとは思う。
人はよくて家族も大切にするいい兄弟なのだが、オタクでつきあいベタでダサイ二人。でもそんな彼らだって当然女性とは楽しくつきあいたい。ただ、ここが重要なところだが、彼らはこれまでの趣味に浸った生活も壊したくないわけである。ここがミソ。
人が大人になるために時間軸としての成長と社会的な成長がともに成熟する必要がある。また、成長とは自分を少し犠牲にして、少し相手を理解することでもある。そして人は新しい自分の価値観を創造していく。間宮兄弟はそのハードルを越えようとしているところだ。数々の悪戦苦闘もするが、だからこそ彼らの魅力にぼんやりと気づき始める女性も出てくるわけである。間宮兄弟の本当の成長は、兄弟が別れて暮らすことだというのは自明だろうが、それを敢えて封印しているのは、作者の思いやりなのだろうか。
で、簡単に観たDVDの感想など。ものは『間宮兄弟』。
江國香織の原作は読んでないのであくまで映画の感想になるが、まあ面白いところに目をつけたとは思う。
人はよくて家族も大切にするいい兄弟なのだが、オタクでつきあいベタでダサイ二人。でもそんな彼らだって当然女性とは楽しくつきあいたい。ただ、ここが重要なところだが、彼らはこれまでの趣味に浸った生活も壊したくないわけである。ここがミソ。
人が大人になるために時間軸としての成長と社会的な成長がともに成熟する必要がある。また、成長とは自分を少し犠牲にして、少し相手を理解することでもある。そして人は新しい自分の価値観を創造していく。間宮兄弟はそのハードルを越えようとしているところだ。数々の悪戦苦闘もするが、だからこそ彼らの魅力にぼんやりと気づき始める女性も出てくるわけである。間宮兄弟の本当の成長は、兄弟が別れて暮らすことだというのは自明だろうが、それを敢えて封印しているのは、作者の思いやりなのだろうか。
Posted
on
『ラヂオの時間』&『かもめ食堂』
土日はカレンダーどおり休み。ところが土曜の昼に外出した辺りから急に体調が崩れてきて、帰宅するなり床についてしまう。たぶん風邪だったとは思うのだが、熱の他に吐き気なども催してかなりフラフラ。大人しく夕方から翌朝までほとんど寝て過ごす。
日曜はまずまず復調。最近気になっていたデジカメを物色しにいく。近所の家電量販店を三軒ほどまわり、NikonのP5100を購入。このクラスでは画質の良さと機能性の高さがウリ。デザインもちょっと無骨なところがかえってカッコイイ。帰宅後はマニュアルと首っ引きで操作のマスター。しばらくしたらそれで撮った画像をお目にかけることができるかも。
というわけであまりミステリとは関係ない週末。体調の悪さで読書も進まなかったが、DVDで『ラヂオの時間』を観る。何を今さらという感じだが。
『ラヂオの時間』は三谷幸喜の映画監督デビュー作で、生ラジオ・ドラマの収録中にスタジオで起こるドタバタを描いたシチュエーションドラマ。もともと東京サンシャインボーイズの脚本ではあるが、この豪華キャストによる映画版も実にいい。三谷幸喜の描く笑いは個人的にもツボであり、正直つまらないと思ったためしがない。世代もほぼ同じであり、これからも彼の芝居や映画は観つづけていくに違いない。
ついでに先日観たDVD『かもめ食堂』の感想も少し。こちらは三谷幸喜の奥さんである小林聡美が主演のドラマ。フィンランドのヘルシンキで食堂を経営する日本人女性を描く物語だが、これがほとんど事件といった事件も起こらない、実にまったりとした話である。空気で観るといえばよいか、劇中の何気ない会話や仕草、それらの絵などを楽しむのが吉。こんな生き方ができればいいが、現実の自分は日々せわしないばかりで、まず無理だなぁ。せめて老後ぐらいははこうありたいものである。
日曜はまずまず復調。最近気になっていたデジカメを物色しにいく。近所の家電量販店を三軒ほどまわり、NikonのP5100を購入。このクラスでは画質の良さと機能性の高さがウリ。デザインもちょっと無骨なところがかえってカッコイイ。帰宅後はマニュアルと首っ引きで操作のマスター。しばらくしたらそれで撮った画像をお目にかけることができるかも。
というわけであまりミステリとは関係ない週末。体調の悪さで読書も進まなかったが、DVDで『ラヂオの時間』を観る。何を今さらという感じだが。
『ラヂオの時間』は三谷幸喜の映画監督デビュー作で、生ラジオ・ドラマの収録中にスタジオで起こるドタバタを描いたシチュエーションドラマ。もともと東京サンシャインボーイズの脚本ではあるが、この豪華キャストによる映画版も実にいい。三谷幸喜の描く笑いは個人的にもツボであり、正直つまらないと思ったためしがない。世代もほぼ同じであり、これからも彼の芝居や映画は観つづけていくに違いない。
ついでに先日観たDVD『かもめ食堂』の感想も少し。こちらは三谷幸喜の奥さんである小林聡美が主演のドラマ。フィンランドのヘルシンキで食堂を経営する日本人女性を描く物語だが、これがほとんど事件といった事件も起こらない、実にまったりとした話である。空気で観るといえばよいか、劇中の何気ない会話や仕草、それらの絵などを楽しむのが吉。こんな生き方ができればいいが、現実の自分は日々せわしないばかりで、まず無理だなぁ。せめて老後ぐらいははこうありたいものである。
Posted
on
大下宇陀児『子供は悪魔だ』(講談社ロマンブックス)
まったく個人的なことだが、本日、ようやく、ようやくにして、あの探偵小説誌『幻影城』をコンプリートすることができた。やっほーい。
リーチがかかっていたのはNo.18、すなわち増刊号の『横溝正史の世界』。これがまたエッセイや評論、作品事典など、内容盛り沢山のいい本であり、古書店やネットでも比較的見かける本だから〆の一冊としては最適、と思ったのがもう二年ほど前のこと。そこからが実に長かった……。まあ、あまり高く買うのも嫌だったのでずっと我慢はしてきたのだが、今日たまたま入った古書店で、ラーメン+ギョウザ3人前ぐらいの値段で見つけ、思わず購入。ああ、今日は酒がうまいぜい。

本日の読了本は大下宇陀児の『子供は悪魔だ』。題名に「子供」とついてはいるが、さすがにこれはジュヴナイルに非ず。少々長めの短編、「子供は悪魔だ」「売春巷談」「山は殺さず」「百舌鳥」、以上の四作を収めた短編集である。
政治家の汚職から若者の乱れた風潮まで、当時の社会問題などを取り上げつつもその筆はかなり通俗的で、読み物としてはなかなか面白い。ただし探偵小説としての結構は備えているけれども、トリック等は例によって腰くだけなので、あくまで当時の風俗や人物描写などを中心に古い探偵小説の雰囲気を楽しむのが吉であろう。出来そのものは先日読んだ『おれは不服だ』よりは上。
「子供は悪魔だ」は、莫大な財産を手にしたがため、ろくでもない子供たちばかりを抱えることになった男の悲運を描く。五人兄妹それぞれのごくつぶし振りが多様で、時代は変われどありそうな話ではある。結末は肩すかしといえば肩すかし、皮肉といえば皮肉。
「売春巷談」は売春婦が主人公の物語。前半は彼女たちのエピソードばかりがつづられ、そんな話なのかと思ったら、後半はちゃんとした本格探偵小説的に展開し、このギャップがまず面白い。一応密室的トリックを用いているところもオオッと思わせるが、残念ながらこちらはいまひとつ……というか作中の説明はまったく説明になっていない気がする(笑)。でも宇陀児だから許す(爆)。
「山は殺さず」は雪山で死んだ若者の事件が発端となり、過去に起こった誘拐事件にまで連なるという物語。書く人が書けば相当に壮大な話になるはずだが、これを非常にサラッとまとめているのが大下宇陀児ならでは。だが誘拐事件にも一種の密室のような状態を設定するなど、アイデアは悪くない。これはしっかり書き込んで長編にしてもよかったのではないかなぁ。
「百舌鳥」は三角関係にある男女が挑む犯罪とその心理を描く。主人公の小鳥好きという設定をうまく活かしており、ラストはそれなりにグッと来る。本書の中では最も謎解きから遠い位置にある作品だが、読み応えは一番。
リーチがかかっていたのはNo.18、すなわち増刊号の『横溝正史の世界』。これがまたエッセイや評論、作品事典など、内容盛り沢山のいい本であり、古書店やネットでも比較的見かける本だから〆の一冊としては最適、と思ったのがもう二年ほど前のこと。そこからが実に長かった……。まあ、あまり高く買うのも嫌だったのでずっと我慢はしてきたのだが、今日たまたま入った古書店で、ラーメン+ギョウザ3人前ぐらいの値段で見つけ、思わず購入。ああ、今日は酒がうまいぜい。

本日の読了本は大下宇陀児の『子供は悪魔だ』。題名に「子供」とついてはいるが、さすがにこれはジュヴナイルに非ず。少々長めの短編、「子供は悪魔だ」「売春巷談」「山は殺さず」「百舌鳥」、以上の四作を収めた短編集である。
政治家の汚職から若者の乱れた風潮まで、当時の社会問題などを取り上げつつもその筆はかなり通俗的で、読み物としてはなかなか面白い。ただし探偵小説としての結構は備えているけれども、トリック等は例によって腰くだけなので、あくまで当時の風俗や人物描写などを中心に古い探偵小説の雰囲気を楽しむのが吉であろう。出来そのものは先日読んだ『おれは不服だ』よりは上。
「子供は悪魔だ」は、莫大な財産を手にしたがため、ろくでもない子供たちばかりを抱えることになった男の悲運を描く。五人兄妹それぞれのごくつぶし振りが多様で、時代は変われどありそうな話ではある。結末は肩すかしといえば肩すかし、皮肉といえば皮肉。
「売春巷談」は売春婦が主人公の物語。前半は彼女たちのエピソードばかりがつづられ、そんな話なのかと思ったら、後半はちゃんとした本格探偵小説的に展開し、このギャップがまず面白い。一応密室的トリックを用いているところもオオッと思わせるが、残念ながらこちらはいまひとつ……というか作中の説明はまったく説明になっていない気がする(笑)。でも宇陀児だから許す(爆)。
「山は殺さず」は雪山で死んだ若者の事件が発端となり、過去に起こった誘拐事件にまで連なるという物語。書く人が書けば相当に壮大な話になるはずだが、これを非常にサラッとまとめているのが大下宇陀児ならでは。だが誘拐事件にも一種の密室のような状態を設定するなど、アイデアは悪くない。これはしっかり書き込んで長編にしてもよかったのではないかなぁ。
「百舌鳥」は三角関係にある男女が挑む犯罪とその心理を描く。主人公の小鳥好きという設定をうまく活かしており、ラストはそれなりにグッと来る。本書の中では最も謎解きから遠い位置にある作品だが、読み応えは一番。
Posted
on
キャロリン・キーン『古時計の秘密』(創元推理文庫)

すっかりジュヴナイルモードに入ってしまった感のある今日この頃。本日は海外での定番でもある「ナンシー・ドルー・シリーズ」、その第一作『古時計の秘密』を読む。翻訳ものの児童書ではアレンジや抄訳など当たり前だが(超訳などとは異なり、これは理解できるし仕方ないこと)、創元版ではあえて原作に忠実に訳することで、既刊との差別化を図ったという。こんな話。
ナンシ・ドルーは弁護士の父親をもつ才気煥発な18歳。あるとき橋から落ちた女の子を助けたことがきっかけで、その子を育てる貧しい老姉妹と知り合いになり、彼女たちの身の上を知ることになる。話によると姉妹はこれまで援助してくれていた親切な紳士が亡くなったため、経済的に苦しんでいるらしい。しかも紳士は姉妹に遺産を残す予定だったが、強欲な一家に遺産を独り占めされてしまったというではないか。さらには、紳士が他にも困っている多くの人々に援助をしていたことが判明。ナンシーは皆を助けるべく、残されているはずの遺言書を見つけ出そうとするが……。
驚くなかれ本書が書かれたのは1930年。あの乱歩の少年探偵団とほぼ同時期に生まれ、脈々と書かれ続け、読まれ続けてきた人気シリーズである。今回、その作品をおよそ三十五年振りぐらいに再読して、あらためてその人気の理由を再認識できた。
勧善懲悪の爽快感、スピーディーでテンポのよい展開、適度なスリル等々、子供を飽きさせない工夫が非常に盛り込まれており、今こうしてオッサンになった自分が読んでも普通に楽しめる。同じ児童向けの少年探偵団やホームズ、ルパンものに比べるとアッという驚きや謎解きの要素はないのだが、この爽やかさは「ナンシー・ドルー・シリーズ」ならではのものであり、家族で楽しめるということも人気の大きなアドバンテージになっているといえるだろう。
唯一、引っかかるのは18歳というナンシー・ドルーの年齢か。その言動はどうみても中学生程度であり、この幼さに違和感を感じるとやや辛くなるかもしれない。まあ、脳内で15歳ぐらいに置き換えて読めば、あまり気にはならないけれども(笑)。
本国ではハウスネーム的に複数の作者によって書き継がれ、今では200作を越える作品があるというが、どうせ着手したのだから創元はせめてオリジナルの56作までは刊行してほしいものである。
Posted
on
仁木悦子『子供たちの探偵簿1朝の巻』(出版芸術社)
少年探偵・春田龍介のせいで、もう少しこの手のものを読みたくなり、仁木悦子の『子供たちの探偵簿1朝の巻』に手を出す。
すべて小学五、六年生が主人公だが、春田龍介シリーズと大きく異なるのは、彼らがごくごく普通の子供たちであるということ(ま、当たり前ですが)。偶然に巻き込まれた事件のなか、彼や彼女はほんの少しの勇気と知恵を振り絞って、事件を解決に導いてゆく。収録作は以下の十編。
「かあちゃんは犯人じゃない」
「誘拐犯はサクラ印」
「鬼子母の手」
「恋人とその弟」
「光った眼」
「銅の魚」
「夏雲の下で」
「石段の家」
「うす紫の午後」
「穴」
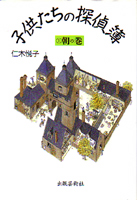
何より特徴的なのは、いずれの作品も子供たちの一人称で語られること。そしていずれの作品も完全な大人向けの作品であるということだ。著者が意識的に始めたこのスタイルは、数々の童話の創作もこなしてきた著者ならではの技法であり、真相をうまくカモフラージュする効果と、独特の作品世界を確立させる二重の効果を上げている。
各作品の出来のムラが少ない点もポイントが高いところだが、読んでいるうちにある種のパターンみたいなものも感じられる。これは決してマイナス要素ではなく、そのパターンに慣れてきたところでドカンと来る「うす紫の午後」みたいな作品があるから、ほんとに油断できないのである。本書は万人におすすめできる良質の短編集。いいぞ。
すべて小学五、六年生が主人公だが、春田龍介シリーズと大きく異なるのは、彼らがごくごく普通の子供たちであるということ(ま、当たり前ですが)。偶然に巻き込まれた事件のなか、彼や彼女はほんの少しの勇気と知恵を振り絞って、事件を解決に導いてゆく。収録作は以下の十編。
「かあちゃんは犯人じゃない」
「誘拐犯はサクラ印」
「鬼子母の手」
「恋人とその弟」
「光った眼」
「銅の魚」
「夏雲の下で」
「石段の家」
「うす紫の午後」
「穴」
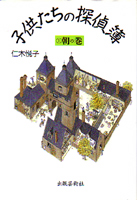
何より特徴的なのは、いずれの作品も子供たちの一人称で語られること。そしていずれの作品も完全な大人向けの作品であるということだ。著者が意識的に始めたこのスタイルは、数々の童話の創作もこなしてきた著者ならではの技法であり、真相をうまくカモフラージュする効果と、独特の作品世界を確立させる二重の効果を上げている。
各作品の出来のムラが少ない点もポイントが高いところだが、読んでいるうちにある種のパターンみたいなものも感じられる。これは決してマイナス要素ではなく、そのパターンに慣れてきたところでドカンと来る「うす紫の午後」みたいな作品があるから、ほんとに油断できないのである。本書は万人におすすめできる良質の短編集。いいぞ。
Posted
on
山本周五郎『山本周五郎探偵小説全集1少年探偵・春田龍介』(作品社)
昨年秋頃から作品社の「山本周五郎探偵小説全集」が刊行され始めたことはご存じの方も多いだろう。だが山本周五郎の書いた探偵小説といえば、せいぜい『寝ぼけ署長』が知られている程度で、逆に言うとそれぐらいしか作品がないと思っていた人もまた多いのではないか。
かくいう管理人も今はなき探偵小説誌『幻影城』で特集を読んだことがあるので、多少は他の探偵小説の存在を知ってはいたものの、全集の全貌が明らかになるにつれ、こりゃとんでもない勘違いだったことを痛感している次第である。
本日の読了本はその「山本周五郎探偵小説全集」の第一巻『少年探偵・春田龍介』。あの文豪がこれだけのジュヴナイルを書いていたことにも驚くが、問題はその量より質である。
そもそも戦前に書かれた少年向け探偵小説といえば、基本的には正義感溢れる少年が、知恵と勇気と腕力にものをいわせ、数々の事件を解決してゆくというパターンである。ただし当時の世相を反映して、様々な条件を満たすことを要求された。例えばその国威高揚愛国精神爆発的な思想の上に成り立っていることは必要不可欠。そのため事件も単なる犯罪よりは防諜ものスパイものが多くなり、加えてそれらの物語を彩る様々なギミックも必要となる。テンションもあくまで高くなければならない。それらが当時の少年たちの心を掴むために欠かせなかったのだ。
考えてみれば、これは生半可なテクニックだけで書けるものではない。少年向けだからこそある意味大人向けの普通小説よりも過大な努力と技量が試されるのである。そして驚くべきことに、山本周五郎はこのハードルを若い時代に、易々とクリアしていたのだ。

「危し!! 潜水艦の秘密」
「黒襟飾(ネクタイ)組の魔手」
「幽霊屋敷の殺人」
「骸骨島の大冒険」
「謎の顎飾り事件」
「ウラルの東」
「殺生谷の鬼火」
「亡霊ホテル」
「天狗岩の殺人魔」
「劇団「笑う妖魔」」
収録作は以上十作。上から六作は春田龍介を主人公とするシリーズで、下の四作はノン・シリーズ、「ウラルの東」のみ長篇という構成である。
ノン・シリーズ作品はオカルトチックな謎を科学的に解いてゆくという意外にまっとうな作りであり、カーばりの展開にちょっと嬉しくなったりもするのだが、本書の魅力はやはり春田少年のシリーズであろう。
もちろん魅力といっても、今の水準で考えるととんでもない要素ばかりである(笑)。春田少年は中学生ながら、車は運転する、ピストルは撃つ、あげくに大砲まで扱い、大の大人にも当然ため口。自信も相当なもので、単身満州に乗り込んで、アジアを震撼させているギャング団を一人でたたきつぶそうというのだから、嫌なガキである(笑)。御都合主義も凄まじく、悪者の落とした暗号がたまたま春田少年の学校で見つかったり、まったく痕跡が残らないという未知の毒薬が登場したり。
また、物語とは直接関係ないところでもけっこう無茶がある。例えば短編のいくつかはストーリーに関連があったりするのだが、登場人物の名前がころころ変わっていたりするのが困る。春田少年の伯父さんなどは登場する度に「若林」>「林田」>「牧野」と変化していき、もしかするとこれは別人なのだろうか、自分が読み間違っているのだろうかと思ったりもするのだが、でもたぶん周五郎の間違いである。そういう点には大らかな時代だったのであろう。
さらに、力が入りすぎの章タイトルも読みどころであろう。まあ、作品のタイトルですら「危し!! 潜水艦の秘密」とかなり危し感は出ているのだが、章のタイトルともなると「危機! 危機!!」とか「殴れ!! 壮太!!」とか「こん畜生、毛唐め!!」とか「アレアレ墜落する天狗岩」とか。なんなんだ「アレアレ」って。ただ、これらの章タイトルは笑ってみていればよいが、中にはネタバレしている章タイトルまであって、それにはマジに閉口した。見出しでオチを書いてどうする?(笑)
まあ、いろいろと笑いどころを並べてみたものの、本書の胆はそんなところにあるのではないーーいや、確かに相当に楽しいんだけれどねーーそうではなく、むしろ少年小説とはかくあるべし、みたいな熱がヒシヒシと感じられるところにあるのだ。
文豪の作品とはいえ名声を得るのはまだまだ後の話、習作時代といってもよい頃の作品で、しかも生活費稼ぎのために書いたとされている子供向けの作品群ということだが、そんなことは微塵も感じさせない。当時の少年小説で必要とされたエッセンスをとことんまで煮込み、濃縮に濃縮を重ねたかのような味わいである。この手の作品に免疫のない人はともかく、少年探偵団が死ぬほど好きだった人にはぜひともお勧めしたい。中毒性、高し。
かくいう管理人も今はなき探偵小説誌『幻影城』で特集を読んだことがあるので、多少は他の探偵小説の存在を知ってはいたものの、全集の全貌が明らかになるにつれ、こりゃとんでもない勘違いだったことを痛感している次第である。
本日の読了本はその「山本周五郎探偵小説全集」の第一巻『少年探偵・春田龍介』。あの文豪がこれだけのジュヴナイルを書いていたことにも驚くが、問題はその量より質である。
そもそも戦前に書かれた少年向け探偵小説といえば、基本的には正義感溢れる少年が、知恵と勇気と腕力にものをいわせ、数々の事件を解決してゆくというパターンである。ただし当時の世相を反映して、様々な条件を満たすことを要求された。例えばその国威高揚愛国精神爆発的な思想の上に成り立っていることは必要不可欠。そのため事件も単なる犯罪よりは防諜ものスパイものが多くなり、加えてそれらの物語を彩る様々なギミックも必要となる。テンションもあくまで高くなければならない。それらが当時の少年たちの心を掴むために欠かせなかったのだ。
考えてみれば、これは生半可なテクニックだけで書けるものではない。少年向けだからこそある意味大人向けの普通小説よりも過大な努力と技量が試されるのである。そして驚くべきことに、山本周五郎はこのハードルを若い時代に、易々とクリアしていたのだ。

「危し!! 潜水艦の秘密」
「黒襟飾(ネクタイ)組の魔手」
「幽霊屋敷の殺人」
「骸骨島の大冒険」
「謎の顎飾り事件」
「ウラルの東」
「殺生谷の鬼火」
「亡霊ホテル」
「天狗岩の殺人魔」
「劇団「笑う妖魔」」
収録作は以上十作。上から六作は春田龍介を主人公とするシリーズで、下の四作はノン・シリーズ、「ウラルの東」のみ長篇という構成である。
ノン・シリーズ作品はオカルトチックな謎を科学的に解いてゆくという意外にまっとうな作りであり、カーばりの展開にちょっと嬉しくなったりもするのだが、本書の魅力はやはり春田少年のシリーズであろう。
もちろん魅力といっても、今の水準で考えるととんでもない要素ばかりである(笑)。春田少年は中学生ながら、車は運転する、ピストルは撃つ、あげくに大砲まで扱い、大の大人にも当然ため口。自信も相当なもので、単身満州に乗り込んで、アジアを震撼させているギャング団を一人でたたきつぶそうというのだから、嫌なガキである(笑)。御都合主義も凄まじく、悪者の落とした暗号がたまたま春田少年の学校で見つかったり、まったく痕跡が残らないという未知の毒薬が登場したり。
また、物語とは直接関係ないところでもけっこう無茶がある。例えば短編のいくつかはストーリーに関連があったりするのだが、登場人物の名前がころころ変わっていたりするのが困る。春田少年の伯父さんなどは登場する度に「若林」>「林田」>「牧野」と変化していき、もしかするとこれは別人なのだろうか、自分が読み間違っているのだろうかと思ったりもするのだが、でもたぶん周五郎の間違いである。そういう点には大らかな時代だったのであろう。
さらに、力が入りすぎの章タイトルも読みどころであろう。まあ、作品のタイトルですら「危し!! 潜水艦の秘密」とかなり危し感は出ているのだが、章のタイトルともなると「危機! 危機!!」とか「殴れ!! 壮太!!」とか「こん畜生、毛唐め!!」とか「アレアレ墜落する天狗岩」とか。なんなんだ「アレアレ」って。ただ、これらの章タイトルは笑ってみていればよいが、中にはネタバレしている章タイトルまであって、それにはマジに閉口した。見出しでオチを書いてどうする?(笑)
まあ、いろいろと笑いどころを並べてみたものの、本書の胆はそんなところにあるのではないーーいや、確かに相当に楽しいんだけれどねーーそうではなく、むしろ少年小説とはかくあるべし、みたいな熱がヒシヒシと感じられるところにあるのだ。
文豪の作品とはいえ名声を得るのはまだまだ後の話、習作時代といってもよい頃の作品で、しかも生活費稼ぎのために書いたとされている子供向けの作品群ということだが、そんなことは微塵も感じさせない。当時の少年小説で必要とされたエッセンスをとことんまで煮込み、濃縮に濃縮を重ねたかのような味わいである。この手の作品に免疫のない人はともかく、少年探偵団が死ぬほど好きだった人にはぜひともお勧めしたい。中毒性、高し。
Posted
on
ジム・トンプスン『鬼警部アイアンサイド』(ハヤカワミステリ)
ここ最近の文芸関係のビッグニュースというとやはり芥川賞・直木賞の発表だが、個人的にはエドワード・D・ホックの訃報である。七十七歳ということだが、急死らしく詳しいことはまだわかってないようだ。不可能犯罪を追い求め、膨大な作品を作り続けてきた作家だっただけに、ミステリ界には実に大きな損失である。合掌。
もうひとつニュース。東京創元社からのメールマガジンによると、フィリップ・マクドナルドの『ライノクス殺人事件』が文庫化されるとのこと。もちろんあの六興キャンドルミステリーズの一冊である。これ自体は評価したいが、長らくストップしたままになっている企画や自社の絶版物も頼んまっせ、ほんと。

読了本はジム・トンプスンの『鬼警部アイアンサイド』。あのノワールの巨匠がTVドラマ『鬼警部アイアンサイド』の設定を借りて書き下ろした、オリジナルのストーリーである。
個人的にはリアルタイムでのTV放映を観てはいたが、初放映時か再放送かは定かでない。また、車椅子の警官という設定のせいか、当時の記憶ではかなり硬派な印象があり、コロンボなどのように熱中した覚えもない。
したがって実は「アイアンサイド」に対してそれほど思い入れがあるわけではないのだが、気になるのはジム・トンプスンがその設定をどう料理したかである。トンプスンはもともと構成やプロットに優れた作家というわけではなく、文章やセンスが先行するタイプだ。オリジナルとはいえTVのイメージが確立しているからにはそこから大きく逸脱するわけにもいかず、ジム・トンプスンの長所が打ち消されるのではないかと危惧したのである。
だが、それはまったくの杞憂であった。逆に多少の縛りがいい方向に流れたのではないかと思えるほど、物語としてきっちりまとまっている。よくよく考えれば小説では奔放な作品をものにしてきたトンプスンだが、同時に映画やテレビの脚本もこなしているわけであり、やはり一級の職人だったのである。
作中で直接的に、あるいは比喩的に言及される正義と悪の概念。そしてTV版ではおそらくなかったろう激しい暴力シーン。ジム・トンプスンらしさも残しつつ、こうしてTVのノヴェライゼーションとして形になった作品だが、そこらのノヴェライゼーションとは明らかに一線を画す出来であり、トンプスンのファンならずとも読んで損はない一冊である。
もうひとつニュース。東京創元社からのメールマガジンによると、フィリップ・マクドナルドの『ライノクス殺人事件』が文庫化されるとのこと。もちろんあの六興キャンドルミステリーズの一冊である。これ自体は評価したいが、長らくストップしたままになっている企画や自社の絶版物も頼んまっせ、ほんと。

読了本はジム・トンプスンの『鬼警部アイアンサイド』。あのノワールの巨匠がTVドラマ『鬼警部アイアンサイド』の設定を借りて書き下ろした、オリジナルのストーリーである。
個人的にはリアルタイムでのTV放映を観てはいたが、初放映時か再放送かは定かでない。また、車椅子の警官という設定のせいか、当時の記憶ではかなり硬派な印象があり、コロンボなどのように熱中した覚えもない。
したがって実は「アイアンサイド」に対してそれほど思い入れがあるわけではないのだが、気になるのはジム・トンプスンがその設定をどう料理したかである。トンプスンはもともと構成やプロットに優れた作家というわけではなく、文章やセンスが先行するタイプだ。オリジナルとはいえTVのイメージが確立しているからにはそこから大きく逸脱するわけにもいかず、ジム・トンプスンの長所が打ち消されるのではないかと危惧したのである。
だが、それはまったくの杞憂であった。逆に多少の縛りがいい方向に流れたのではないかと思えるほど、物語としてきっちりまとまっている。よくよく考えれば小説では奔放な作品をものにしてきたトンプスンだが、同時に映画やテレビの脚本もこなしているわけであり、やはり一級の職人だったのである。
作中で直接的に、あるいは比喩的に言及される正義と悪の概念。そしてTV版ではおそらくなかったろう激しい暴力シーン。ジム・トンプスンらしさも残しつつ、こうしてTVのノヴェライゼーションとして形になった作品だが、そこらのノヴェライゼーションとは明らかに一線を画す出来であり、トンプスンのファンならずとも読んで損はない一冊である。
Posted
on
佐藤祐市『キサラギ』
映画公開のときから気になっていた『キサラギ』を、ようやくDVDで観ることができた。
自殺したグラビアアイドル「如月ミキ」の一周忌にファンサイトを通じて集まった5人の男を描いた作品。全編のほとんどが一つの部屋の中で進行する密室劇、しかもそのアイドルの死に絡む謎が徐々に明らかになってゆくという、実にミステリ的風味満載の物語である。
で、これがなかなか良くできていて、ネタそのものはちょっとしたミステリファンならお馴染みのものばかりであるが、そのつなぎ方というか盛り込み方が巧い。会話や設定のひとつひとつがほぼ伏線だらけといってもよく、名作『十二人の怒れる男』を彷彿とさせるといったら言い過ぎだろうか。
導入部分、そしてラストのプラネタリウムのシーン以降の演出が過剰すぎて、そこが実に不満なのだが、そこにさえ目をつぶれば、これはもう十分傑作である。邦画でこれだけミステリマインド溢れた映画を観たのはいったい何時以来だろう。オススメ。
自殺したグラビアアイドル「如月ミキ」の一周忌にファンサイトを通じて集まった5人の男を描いた作品。全編のほとんどが一つの部屋の中で進行する密室劇、しかもそのアイドルの死に絡む謎が徐々に明らかになってゆくという、実にミステリ的風味満載の物語である。
で、これがなかなか良くできていて、ネタそのものはちょっとしたミステリファンならお馴染みのものばかりであるが、そのつなぎ方というか盛り込み方が巧い。会話や設定のひとつひとつがほぼ伏線だらけといってもよく、名作『十二人の怒れる男』を彷彿とさせるといったら言い過ぎだろうか。
導入部分、そしてラストのプラネタリウムのシーン以降の演出が過剰すぎて、そこが実に不満なのだが、そこにさえ目をつぶれば、これはもう十分傑作である。邦画でこれだけミステリマインド溢れた映画を観たのはいったい何時以来だろう。オススメ。
Posted
on
筒井康隆『巨船ベラス・レトラス』(文藝春秋)

本日の読了本は筒井康隆の『巨船ベラス・レトラス』。
本作は現代の文壇を舞台にした実験的小説であり、こう書くと察しのいい筒井ファンならすぐに『大いなる助走』が頭に浮かぶところだろうが、確かに縦軸としては作家を主人公にして現代の文壇や出版業界を徹底的に揶揄してはいるものの、そこにお得意のメタ・フィクショナルな構造をもちだしきて様々な文学論を幾重にも重ねてゆくのは『文学部唯野教授』や『虚構船団』あたりがかえって近いのかもしれないと思わせ、さらにはその矛先が書店や読者にまで向けられるにいたっては読者たるこちらまでが内心ヒヤヒヤとしながらも、齢七十を越えて意気軒昂たる筒井の姿勢に驚嘆するばかりとなり、最後には作者本人までが登場して無断出版事件を暴露してしまうところなどは実に拍手喝采。
とはいうものの三十年以上も筒井作品を読んできた身にはこれぐらいの描写はすでに馴染みのものであることもまた確かであり、むしろ80~90年代にかけてはこれ以上の過激さと驚きがあったものだと振り返ることもしばしとなるわけで、齢七十を越えてこれだけの作品を書けることには感嘆しつつも、意外なほどの読みやすさは昨今の若い読者を意識してのことか、もしかすると作中でいみじくも村雨澄子が語っているように、一般読者の啓蒙を口実に過去の実験や冒険をより楽な作業で繰り返しているのではないかとげすの勘ぐりも生じないわけではない。ただ、これすら筒井の思うつぼであり企てであるとする可能性も高く、誤読は読者の自由であると胸を張りきれない気持ちもあるのである。
Posted
on
ポール・ドハティー『赤き死の訪れ』(創元推理文庫)
ポール・ドハティーの『赤き死の訪れ』を読む。
大の酒好きで、捜査中に飲み過ぎて居眠りまでしてしまうという体たらくのクランストン検死官。過去に重い罪と深い心の傷を負い、その贖罪の日々を送るべく托鉢修道士として暮らしながら、ひとたび事件が起こればクランストンを支えて活躍するアセルスタン。
本作はそんな二人の名コンビによる中世歴史ミステリ第二弾である。

ロンドン塔の城守、ラルフ・ホイットン卿が塔内の一室で惨殺された。話によると卿は数日前に謎の手紙を受け取っており、それ以来ひどく様子がおかしかったという。だが惨劇はこれで終わりではなかった。謎の手紙はホイットン卿の周囲の人間にも届いており、一人、また一人と命を奪われてゆく……。
本作がちょっと面白いのは、クランストンとアセルスタンの二人にもそれぞれ個人的な問題がおこり、その謎がメインの事件と平行して語られること。この三つの事件がそれぞれどのように関係し、どのように決着をつけてくれるのか、ここが読みどころと言ってよいだろう。
正直、メインの謎はそれほど大したことがないのだが、相変わらず歴史ものとしての興味やキャラクター造りの巧さは見事で、これプラス先に挙げた立体的な謎の構成などが加わるから、トータルではまず申し分ない出来映え。
ただ、贅沢な注文だとは思うが、やはりキャラクターに頼りすぎているのが気になるところ。できれば謎解きにもう少しだけ寄ってほしいとは思う。あっと驚く仕掛けがもうひとつぐらいあると完璧なのだが。
大の酒好きで、捜査中に飲み過ぎて居眠りまでしてしまうという体たらくのクランストン検死官。過去に重い罪と深い心の傷を負い、その贖罪の日々を送るべく托鉢修道士として暮らしながら、ひとたび事件が起こればクランストンを支えて活躍するアセルスタン。
本作はそんな二人の名コンビによる中世歴史ミステリ第二弾である。

ロンドン塔の城守、ラルフ・ホイットン卿が塔内の一室で惨殺された。話によると卿は数日前に謎の手紙を受け取っており、それ以来ひどく様子がおかしかったという。だが惨劇はこれで終わりではなかった。謎の手紙はホイットン卿の周囲の人間にも届いており、一人、また一人と命を奪われてゆく……。
本作がちょっと面白いのは、クランストンとアセルスタンの二人にもそれぞれ個人的な問題がおこり、その謎がメインの事件と平行して語られること。この三つの事件がそれぞれどのように関係し、どのように決着をつけてくれるのか、ここが読みどころと言ってよいだろう。
正直、メインの謎はそれほど大したことがないのだが、相変わらず歴史ものとしての興味やキャラクター造りの巧さは見事で、これプラス先に挙げた立体的な謎の構成などが加わるから、トータルではまず申し分ない出来映え。
ただ、贅沢な注文だとは思うが、やはりキャラクターに頼りすぎているのが気になるところ。できれば謎解きにもう少しだけ寄ってほしいとは思う。あっと驚く仕掛けがもうひとつぐらいあると完璧なのだが。
一応、三連休。おまけに相方が里帰りということで、のんびり過ごすつもりだったが、けっこうなんだかんだで仕事をひきずる。
それでも相方がいるとなかなか一緒には観られないDVDや映画などをぽつぽつと消化。いや、一緒に観られないといっても、別にあっち方面ではなく(笑)。
ひとつはDVDで『仮面ライダー THE FIRST』。もちろんあの『仮面ライダー』である。うちの会社は仕事柄そういうのに詳しいやつが山ほどいるのだが、その中の一人に、「ぜひ観てください」と渡されたもの(笑)。
本作はTVシリーズの第一作『仮面ライダー』を大人向けに映画化したもので、2005年公開。原作である石ノ森章太郎の漫画の設定を、あるていど忠実に再現しているのが売りらしい。なるほど、確かにリアルタイムで漫画、TVを観ていた者にはそそるストーリーだ。ただ、今風にワイヤーアクションなどを取り入れているものの、やっぱりアクションがしょぼい。それ以上に若手俳優たちの演技がしょぼい(ただしウエンツ瑛士が意外に好演)。けっこうシナリオは頑張っていて、ほろりとさせるサイドストーリーなどもあるので、ちょっともったいないかも。やっぱりこういう特撮ものはもっとお金をかけないとダメだ。
そのお金をふんだんに使いましたという一作が、『AVP2 エイリアンズ VS. プレデター』。といっても有名な俳優さんはほぼ皆無で、お金はすべて特撮につぎこんでいるようだ(笑)。
前作の『エイリアン VS. プレデター』が中途半端にコミカルになってしまっていたが、本作はかなり真面目に作っているのが好印象。プレデターがエイリアン狩りに乗り出し、人間たちはその争いに巻き込まれ、右往左往しながら逃げるだけという、実にまっとうなパニック映画になっている。
ただ、観ていてハッとするような、新鮮な驚きが(映像的にもストーリー的にも)ほとんどなかったのが残念。ラストにちょっとした設定上のオチがあるけれど、あれは予想どおりだし。総合的な出来は前作より全然いいのだが、衝撃度では前作の方が勝れている。
なお、映画公開前にあえてシークレットにしていた「プレデリアン」の造形については、隠すほどのもんか?という感じ。
読書はドハティーの『赤き死の訪れ』。もう少しで読了なので、感想は明日にでも。
それでも相方がいるとなかなか一緒には観られないDVDや映画などをぽつぽつと消化。いや、一緒に観られないといっても、別にあっち方面ではなく(笑)。
ひとつはDVDで『仮面ライダー THE FIRST』。もちろんあの『仮面ライダー』である。うちの会社は仕事柄そういうのに詳しいやつが山ほどいるのだが、その中の一人に、「ぜひ観てください」と渡されたもの(笑)。
本作はTVシリーズの第一作『仮面ライダー』を大人向けに映画化したもので、2005年公開。原作である石ノ森章太郎の漫画の設定を、あるていど忠実に再現しているのが売りらしい。なるほど、確かにリアルタイムで漫画、TVを観ていた者にはそそるストーリーだ。ただ、今風にワイヤーアクションなどを取り入れているものの、やっぱりアクションがしょぼい。それ以上に若手俳優たちの演技がしょぼい(ただしウエンツ瑛士が意外に好演)。けっこうシナリオは頑張っていて、ほろりとさせるサイドストーリーなどもあるので、ちょっともったいないかも。やっぱりこういう特撮ものはもっとお金をかけないとダメだ。
そのお金をふんだんに使いましたという一作が、『AVP2 エイリアンズ VS. プレデター』。といっても有名な俳優さんはほぼ皆無で、お金はすべて特撮につぎこんでいるようだ(笑)。
前作の『エイリアン VS. プレデター』が中途半端にコミカルになってしまっていたが、本作はかなり真面目に作っているのが好印象。プレデターがエイリアン狩りに乗り出し、人間たちはその争いに巻き込まれ、右往左往しながら逃げるだけという、実にまっとうなパニック映画になっている。
ただ、観ていてハッとするような、新鮮な驚きが(映像的にもストーリー的にも)ほとんどなかったのが残念。ラストにちょっとした設定上のオチがあるけれど、あれは予想どおりだし。総合的な出来は前作より全然いいのだが、衝撃度では前作の方が勝れている。
なお、映画公開前にあえてシークレットにしていた「プレデリアン」の造形については、隠すほどのもんか?という感じ。
読書はドハティーの『赤き死の訪れ』。もう少しで読了なので、感想は明日にでも。
Posted
on
大下宇陀児『おれは不服だ』(講談社ロマン・ブックス)
大下宇陀児の『おれは不服だ』を読む。表題作を含む短編集で、昭和32年に講談社ロマン・ブックスとして刊行された一冊。まずは収録作から。
「獺」
「娘たちは怖い」
「風が吹くと」
「痣を見せるな」
「おれは不服だ」
「十四人目の乗客」

なかなかバラエティに富んだ作品集。大下宇陀児の通俗的な部分と幅の広さが存分に発揮されてはいるが、いやあ、純粋に質を問われると、これは厳しい(笑)。もちろん端から傑作などを期待しているわけではないのだが、逆に『宙に浮く首』ぐらいハチャメチャなものが読めるのでは、などと思っていたので、この中途半端さがなかなか。以下、各感想。
「獺」はいわゆる悪女ものだが、それに絡む犯罪の真相をうっちゃったまま終わるのに唖然。リドル・ストーリーとかじゃなくて、本当に無視しちゃうのである(笑)。
「娘たちは怖い」はあるアパートで起きた殺人事件の物語。通報したくせになぜか肝心の部分で黙秘を続ける女子学生たち。彼女たちがなぜ黙秘するのか、というのが本作の肝だが、あまりにそのまんまのオチでのけぞること確実。
「風が吹くと」は悪女ものでありつつ、それに溺れて破滅する中年男の話だが、雰囲気なら「獺」の方が上。こちらは変にクライムノベルっぽくしているせいか、かえってテーマがぼけている感じだ。
「痣を見せるな」は本書のなかでは一番まともな作品。「痣のある子供」ばかりを狙う猟奇殺人という設定からして、実に探偵小説っぽい。今では手垢のついた真相ながら、当時であればけっこういい線をいったはずである。事件解決に至る手段がちょっとアレだが、これぐらいのレベルの作品が半分ほどあれば、本書もオススメできたと思うのだが(苦笑)。
表題作の「おれは不服だ」は典型的なクライムノベル。ある男に偶然殺しを依頼された主人公だが、実は……という作品。オチはミエミエだが、タイトルや語り口などがコミカルで、それなりに読ませる。
「十四人目の乗客」は珍しく奇妙な味に含まれそうな作品だが、やはり無理があるなぁ。
古書としては入手しやすい部類だが、いまネットで調べてみるとけっこう高価で驚く。作品の質や希少性を考えても、あまり無理に読む本ではないので念のため。
「獺」
「娘たちは怖い」
「風が吹くと」
「痣を見せるな」
「おれは不服だ」
「十四人目の乗客」

なかなかバラエティに富んだ作品集。大下宇陀児の通俗的な部分と幅の広さが存分に発揮されてはいるが、いやあ、純粋に質を問われると、これは厳しい(笑)。もちろん端から傑作などを期待しているわけではないのだが、逆に『宙に浮く首』ぐらいハチャメチャなものが読めるのでは、などと思っていたので、この中途半端さがなかなか。以下、各感想。
「獺」はいわゆる悪女ものだが、それに絡む犯罪の真相をうっちゃったまま終わるのに唖然。リドル・ストーリーとかじゃなくて、本当に無視しちゃうのである(笑)。
「娘たちは怖い」はあるアパートで起きた殺人事件の物語。通報したくせになぜか肝心の部分で黙秘を続ける女子学生たち。彼女たちがなぜ黙秘するのか、というのが本作の肝だが、あまりにそのまんまのオチでのけぞること確実。
「風が吹くと」は悪女ものでありつつ、それに溺れて破滅する中年男の話だが、雰囲気なら「獺」の方が上。こちらは変にクライムノベルっぽくしているせいか、かえってテーマがぼけている感じだ。
「痣を見せるな」は本書のなかでは一番まともな作品。「痣のある子供」ばかりを狙う猟奇殺人という設定からして、実に探偵小説っぽい。今では手垢のついた真相ながら、当時であればけっこういい線をいったはずである。事件解決に至る手段がちょっとアレだが、これぐらいのレベルの作品が半分ほどあれば、本書もオススメできたと思うのだが(苦笑)。
表題作の「おれは不服だ」は典型的なクライムノベル。ある男に偶然殺しを依頼された主人公だが、実は……という作品。オチはミエミエだが、タイトルや語り口などがコミカルで、それなりに読ませる。
「十四人目の乗客」は珍しく奇妙な味に含まれそうな作品だが、やはり無理があるなぁ。
古書としては入手しやすい部類だが、いまネットで調べてみるとけっこう高価で驚く。作品の質や希少性を考えても、あまり無理に読む本ではないので念のため。
Posted
on
リチャード・ニーリィ『愛する者に死を』(ハヤカワミステリ)
リチャード・ニーリィの『愛する者に死を』を読む。『心ひき裂かれて』や『殺人症候群』『オイディプスの報酬』といったトリッキーな作品でその名も高いニーリィだが、本書はそんな彼が1969年に書いたデビュー作である。こんな話。
業績不振に悩む出版社の社長、マイクルの元に、奇妙な手紙が届けられた。P・Sと名乗るその手紙の送り主は、殺人の実行を宣言しており、その顛末を出版しないかというのだ。マイクルはその話にとびついたものの、彼を待っていたのは死体と、周到に計画された罠であった……。

いやいや、三つ子の魂百までというが、ニーリィはデビュー作からこういうことを考えていた人なのだ。本書で初めてニーリィに接した人は、このサービス精神にちょっと驚くかもしれない。サプライズに次ぐサプライズ、やや過剰なお色気シーン、変にダラダラせずピシッと簡潔にまとめる構成。何より1969年の作品であるにもかかわらず、すでに昨今のサイコ・スリラーの原型ともいえる結構を備えているところはさすがである。
ただし、後の『心ひき裂かれて』などに比べると、完成度という点では残念ながら一枚も二枚も落ちる。特にいただけないのは、サプライズありきゆえの強引な犯人像とそのトリック。上で褒めておいたくせにこういうのも何だが、やっぱり無理がありすぎる(笑)。本格至上主義の人はこういうの許せないんじゃないか(笑)。
また、あまりハッキリと主人公を設定していないのは、ラストの盛り上がりとサプライズのためには必要だったと思うのだが、全体のサスペンスという点では逆にかなりマイナスになっているのが残念だった。
とりあえずニーリィを読むなら、まずは角川文庫の諸作品であり(特に『心ひき裂かれて』は必読)、本書はそれからでも十分だろう。
業績不振に悩む出版社の社長、マイクルの元に、奇妙な手紙が届けられた。P・Sと名乗るその手紙の送り主は、殺人の実行を宣言しており、その顛末を出版しないかというのだ。マイクルはその話にとびついたものの、彼を待っていたのは死体と、周到に計画された罠であった……。

いやいや、三つ子の魂百までというが、ニーリィはデビュー作からこういうことを考えていた人なのだ。本書で初めてニーリィに接した人は、このサービス精神にちょっと驚くかもしれない。サプライズに次ぐサプライズ、やや過剰なお色気シーン、変にダラダラせずピシッと簡潔にまとめる構成。何より1969年の作品であるにもかかわらず、すでに昨今のサイコ・スリラーの原型ともいえる結構を備えているところはさすがである。
ただし、後の『心ひき裂かれて』などに比べると、完成度という点では残念ながら一枚も二枚も落ちる。特にいただけないのは、サプライズありきゆえの強引な犯人像とそのトリック。上で褒めておいたくせにこういうのも何だが、やっぱり無理がありすぎる(笑)。本格至上主義の人はこういうの許せないんじゃないか(笑)。
また、あまりハッキリと主人公を設定していないのは、ラストの盛り上がりとサプライズのためには必要だったと思うのだが、全体のサスペンスという点では逆にかなりマイナスになっているのが残念だった。
とりあえずニーリィを読むなら、まずは角川文庫の諸作品であり(特に『心ひき裂かれて』は必読)、本書はそれからでも十分だろう。
Posted
on
クリフォード・ナイト『ミステリ講座の殺人』(原書房)
ちょっと遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。
本年も皆様が素晴らしい探偵小説三昧の日々を送れますようお祈り申し上げます。
正月は初詣に出かけたぐらいで、あとは典型的な寝正月。こういう緊張感のない時間を過ごすことが最近少なかったので、精神的にはずいぶん疲れがとれた気がする。何をしていたのか自分でもよく思い出せないが、酒だけはけっこう飲んでいたなぁ(苦笑)。
今年一発目の読了本は、原書房のヴィンテージ・ミステリから『ミステリ講座の殺人』。
作者は我が国ではほぼ無名のクリフォード・ナイト。日本はもちろん本国でもほとんど忘れられた作家だが、当時はミステリ・コンテストで華々しくデビューした後、アメリカの黄金時代を支えたバイプレイヤー的存在だったらしい。本書は著者の長篇第二作目にあたる。

著名なミステリ作家イーディス・メアリー・マーカー。彼女は自分の屋敷に人々を集め、「ミステリ講座」を催していた。しかし、ある夜のこと。「天の声」と名付けられた鐘の音でたたき起こされた人々が見たものは、短剣によって殺害された老女の姿。彼女はイーディスの秘書であると同時に、イーディスのよき相談役でもあった。残された人々は頼りない保安官の言動に業を煮やし、自ら真相を探ろうとするが……。
設定がミステリ・マニアの興味をいやがうえにもそそり、おまけにタイトルがメタミステリっぽいものを連想させる。しかも巻末には「手がかり索引」まで付けられているので、これは著者が相当なマニアであることを想像させるのだが、そういう場合は逆に要注意。変なこだわりばかりが先に立って、小説としてはダメダメなことが多いのはよくある話。
本書の場合、結果からいうと、やはり出来はいまひとつ。
ただ、問題なのは、マニアがこだわりすぎて自滅したというより、試みが中途半端で物足りないということだ。登場人物たちの大半がミステリ作家や志望者であることを考えると、もっともっとミステリ論などが戦わされてもいいはずだし、技法上の話があってもいいはずだが、基本的には少ないし、あってもそれほどくすぐられるレベルのものではない。加えて設定に比べると事件もおとなしく、意識的なのかどうか知らないが妙にさらっと流している感じが気になった。
これはあくまで個人的な考えだが、少なくともミステリ作家がミステリ作家をネタにしてミステリを書こうというのなら、相応の覚悟や自身をもって大見得をきってほしいものだ。本書は決してつまらないというほどの作品ではないのだが、やはり企画倒れという言葉がぴったりの一冊といえるだろう。
本年も皆様が素晴らしい探偵小説三昧の日々を送れますようお祈り申し上げます。
正月は初詣に出かけたぐらいで、あとは典型的な寝正月。こういう緊張感のない時間を過ごすことが最近少なかったので、精神的にはずいぶん疲れがとれた気がする。何をしていたのか自分でもよく思い出せないが、酒だけはけっこう飲んでいたなぁ(苦笑)。
今年一発目の読了本は、原書房のヴィンテージ・ミステリから『ミステリ講座の殺人』。
作者は我が国ではほぼ無名のクリフォード・ナイト。日本はもちろん本国でもほとんど忘れられた作家だが、当時はミステリ・コンテストで華々しくデビューした後、アメリカの黄金時代を支えたバイプレイヤー的存在だったらしい。本書は著者の長篇第二作目にあたる。

著名なミステリ作家イーディス・メアリー・マーカー。彼女は自分の屋敷に人々を集め、「ミステリ講座」を催していた。しかし、ある夜のこと。「天の声」と名付けられた鐘の音でたたき起こされた人々が見たものは、短剣によって殺害された老女の姿。彼女はイーディスの秘書であると同時に、イーディスのよき相談役でもあった。残された人々は頼りない保安官の言動に業を煮やし、自ら真相を探ろうとするが……。
設定がミステリ・マニアの興味をいやがうえにもそそり、おまけにタイトルがメタミステリっぽいものを連想させる。しかも巻末には「手がかり索引」まで付けられているので、これは著者が相当なマニアであることを想像させるのだが、そういう場合は逆に要注意。変なこだわりばかりが先に立って、小説としてはダメダメなことが多いのはよくある話。
本書の場合、結果からいうと、やはり出来はいまひとつ。
ただ、問題なのは、マニアがこだわりすぎて自滅したというより、試みが中途半端で物足りないということだ。登場人物たちの大半がミステリ作家や志望者であることを考えると、もっともっとミステリ論などが戦わされてもいいはずだし、技法上の話があってもいいはずだが、基本的には少ないし、あってもそれほどくすぐられるレベルのものではない。加えて設定に比べると事件もおとなしく、意識的なのかどうか知らないが妙にさらっと流している感じが気になった。
これはあくまで個人的な考えだが、少なくともミステリ作家がミステリ作家をネタにしてミステリを書こうというのなら、相応の覚悟や自身をもって大見得をきってほしいものだ。本書は決してつまらないというほどの作品ではないのだが、やはり企画倒れという言葉がぴったりの一冊といえるだろう。


