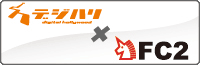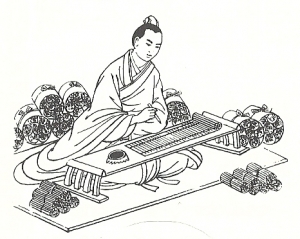古事記・日本書紀のなかの史実Ⅱ (40) 産婦焼き
先週、前号(41号)を先に投稿してましたが、こちらを先に投稿するはずでした・・(汗)
ニニギはオオヤマツミの二人の娘のうちの妹コノハナサクヤヒメと結ばれました。その続きです。
【のちに、コノハナサクヤヒメはニニギの所に参り赴いて、「私は妊娠して、今出産の時になりました。この天津神(ニニギ)を父とする御子は、こっそりと産んではいけないので、事情を申し上げます。」と申し上げた。そこでニニギは、「サクヤヒメよ、ただ一夜の交わりで妊娠したのか。これは私の子のはずがない。きっと国津神の子であろう。」と仰せになった。
答えていうには、「私が産んだ子がもし国津神の子ならば、産むことは無事ではないでしょう。もし天津神の子であるなら、無事にうめるでしょう。」と申し上げて、すぐに出入り口に無い大きな家を作ってその中に入って、土を塗って塞いで、産む時に火を建物に付けて出産した。た。こうしたことから、その火の盛んに燃えている時に産んだ子の名は、火照(ホデリ)命(これは隼人阿多君の祖)、次に産んだ子の名は火須勢理(ホスセリ)命、次に産んだ子の名は火遠理(ホオリ)命、亦の名は天津日高日子穂穂手見(アマツヒコヒコホホテミ)命。】
たった一夜の契りで子が生まれたので、ニニギは自分の子ではないのではないか、と疑いました。つまりニニギは、コノハナサクヤヒメがもともと国津神の誰かと関係をもっており、その国津神との子ではないか、と疑ったわけです。コノハナサクヤヒメはその疑いを晴らすために、家に火をつけ、家中で出産します。
この神話について、吉田敦彦氏は、
ニニギはオオヤマツミの二人の娘のうちの妹コノハナサクヤヒメと結ばれました。その続きです。
【のちに、コノハナサクヤヒメはニニギの所に参り赴いて、「私は妊娠して、今出産の時になりました。この天津神(ニニギ)を父とする御子は、こっそりと産んではいけないので、事情を申し上げます。」と申し上げた。そこでニニギは、「サクヤヒメよ、ただ一夜の交わりで妊娠したのか。これは私の子のはずがない。きっと国津神の子であろう。」と仰せになった。
答えていうには、「私が産んだ子がもし国津神の子ならば、産むことは無事ではないでしょう。もし天津神の子であるなら、無事にうめるでしょう。」と申し上げて、すぐに出入り口に無い大きな家を作ってその中に入って、土を塗って塞いで、産む時に火を建物に付けて出産した。た。こうしたことから、その火の盛んに燃えている時に産んだ子の名は、火照(ホデリ)命(これは隼人阿多君の祖)、次に産んだ子の名は火須勢理(ホスセリ)命、次に産んだ子の名は火遠理(ホオリ)命、亦の名は天津日高日子穂穂手見(アマツヒコヒコホホテミ)命。】
たった一夜の契りで子が生まれたので、ニニギは自分の子ではないのではないか、と疑いました。つまりニニギは、コノハナサクヤヒメがもともと国津神の誰かと関係をもっており、その国津神との子ではないか、と疑ったわけです。コノハナサクヤヒメはその疑いを晴らすために、家に火をつけ、家中で出産します。
この神話について、吉田敦彦氏は、
”インドネシアからインドシナ半島にみられる、産婦の近くで火を燃やす「産婦焼き」の習慣を思わせる。また日本書記の引く第三の一書の伝承によれば、この火中における出産の際に、児のへその緒を切るために竹刀が用いられたとされているのは、インドネシアの各地に例が見られる風習と一致する。”
このように、ニニギノミコト以下皇室三代の祖先たちにまつわる話は、多くの点で南洋、特にインドネシアの神話や風習と、何らかの、親縁関係を考えざるをえないほどの類似性がある。”と述べてます。
”このことを、最近まで多くの研究者たちは、南九州地方の原住民であった隼人(はやと)がインドネシア系の種族であったとみなし、日向神話を、全体的にこの隼人の伝承を取り入れたものと考えることによって説明してきた。”
と述べてます。(吉田敦彦『日本神話の源流』P46-47)。
このように、家に火を付け、その中で出産するという神話は、インドネシアなど東南アジアに源流があるように思われます。これに対して吉田氏は、このあと中国江南地方との説を提唱しています。
私は次に続く海幸彦・山幸彦の神話とともに、かつてマレー半島からインドネシアにかけてあった大陸棚(スンダランド)が源流ではないかと考えてます。では次回、海幸彦・山幸彦の話をみていきましょう。

このように、家に火を付け、その中で出産するという神話は、インドネシアなど東南アジアに源流があるように思われます。これに対して吉田氏は、このあと中国江南地方との説を提唱しています。
私は次に続く海幸彦・山幸彦の神話とともに、かつてマレー半島からインドネシアにかけてあった大陸棚(スンダランド)が源流ではないかと考えてます。では次回、海幸彦・山幸彦の話をみていきましょう。